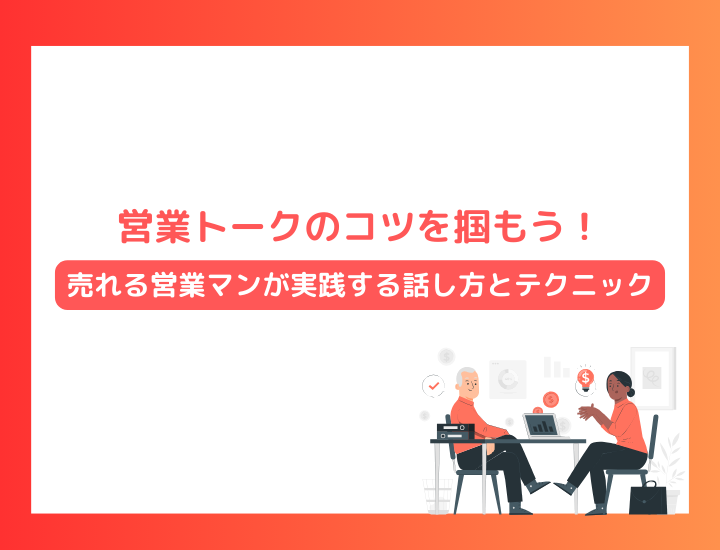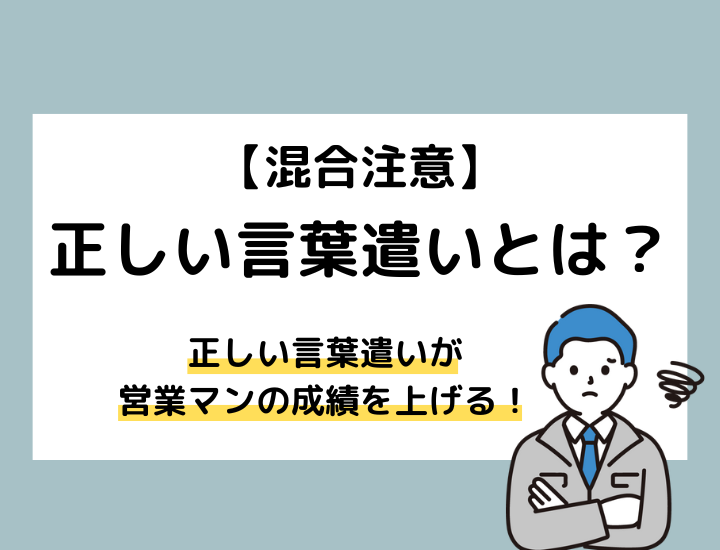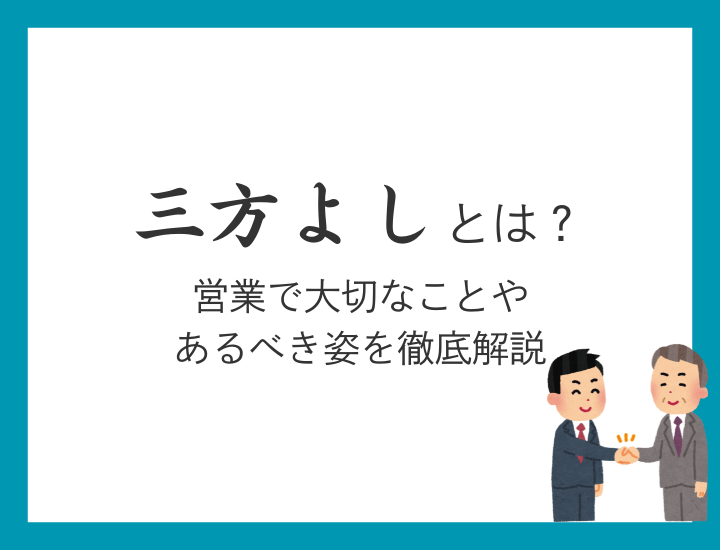
三方よしとは?営業としてあるべき立ち位置と上質な関係構築の方法
ビジネスの現場では、「売上を伸ばす」「契約を取る」といった成果ばかりに意識が向きがちですが、本当に信頼され、長く活躍できる営業は、もっと本質的な価値を大切にしています。
その考え方の一つが「三方よし」です。
これは、近江商人に由来する「売り手よし・買い手よし・世間よし」という経営哲学で、ビジネスにおける理想的な立ち位置や人間関係の築き方にも通じます。
「三方よし」は、単純に会社間の良質な関係性を表すだけでなく、営業としてのあり方を考える際にも役立ちます。
本記事では、「三方よし」の考え方をもとに、顧客との信頼関係を築きながら、社会にも貢献できる営業スタイルを解説します。
誠実さや問題解決力といった営業に必要な資質に加え、トップ営業マンになるための具体的な行動指針も紹介。
これから営業として成長したい方にとって、実践的で本質的なヒントが詰まった内容です。
三方よしとは
皆さんは、そもそも「三方よし」という言葉をご存知でしょうか。
これは単なる商売のスローガンではなく、営業職にとっても重要な指針となる考え方です。
売り手・買い手・世間の三者すべてにとって良い結果をもたらすことを目指すこの理念は、信頼関係の構築や社会的価値の創出にもつながります。
ここでは、営業としてどのように「三方よし」の姿勢を実践すべきかを、売り手(=営業)、買い手(=顧客)、そして世間という3つの視点から詳しく解説していきます。
売り手(=営業)
「三方よし」の理念において、売り手である営業は単なる商品やサービスの提供者にとどまりません。
顧客に価値を届ける最前線に立ち、企業と顧客をつなぐ重要な橋渡し役です。
営業が果たすべき役割は、単なる売上確保ではなく、顧客の課題に真摯に向き合い、最適な解決策を提案すること。
その姿勢が、顧客からの信頼を生み、結果的に企業のブランド価値や社会的評価にもつながっていきます。
また、売り手として重要なのは、自社の利益だけを追求しないバランス感覚です。
顧客にとって本当に必要なものを見極め、無理な売り込みをせず、長期的な関係を築くことが、「三方よし」の精神を体現する営業の姿勢といえるでしょう。
信頼と誠実さを土台に、顧客と社会の双方に価値を提供することで、持続可能なビジネスが実現します。
営業はまさに、「売ってよし」「買ってよし」「世間よし」を結ぶキーパーソンなのです。
買手(=顧客)
買手、つまり顧客の満足は「三方よし」の関係性の中心的な要素です。
前述の通り、売り手となる営業が買い手(=顧客)の本当のニーズを理解し、最適な解決策を提供します。
そして最終的には顧客が価値を実感し、納得して購入してはじめて「良し」と言える関係が築かれます。
また、顧客との信頼関係は一朝一夕には生まれません。
継続的なコミュニケーションと誠実な対応を通じて、「この営業担当から買いたい」と思ってもらえることが理想です。
顧客満足の追求は、単なる契約の獲得ではなく、その後の継続的な関係や紹介といった新たなビジネスチャンスにもつながります。
つまり、顧客にとって「買って良かった」と感じてもらうことが、営業としての成功であり、三方よしの実現に直結します。
買手の立場を深く理解し、価値提供を最優先に考える姿勢が、上質な関係構築への第一歩となるのです。
世間
「三方よし」における”世間”とは、売り手と買い手の関係だけでなく、地域社会や業界、ひいては日本全体の社会全体を含む第三の視点です。
単なる商取引の枠を超え、企業活動が社会にどのような影響を与えるかを意識することが重要です。
現代においては、環境保護や地域貢献、雇用の創出、倫理的なビジネス姿勢などが「世間よし」としての具体的な要素にあたります。
たとえば、地元企業との協業や地域イベントへの協賛、持続可能な製品開発などが挙げられます。
これらは単なるイメージアップにとどまらず、企業の信用力やブランド価値の向上につながります。
営業という立場でも、目の前の利益にとらわれず、地域や社会全体の利益を意識した行動が求められます。
「世間よし」を意識した営業活動は、長期的な信頼を得るための土台となり、結果的に企業の持続的成長へとつながるのです。
三方よしを定義した近江商人の考え方
「三方よし」という理念は、江戸時代に活躍した近江商人の行動哲学に由来します。
「売り手よし・買い手よし・世間よし」の三者すべてが満足する取引を追求するという考え方であり、当時から持続可能な商いの在り方として重視されてきました。
単なる利益追求ではなく、相手に誠意を持って接し、地域や社会への貢献も忘れない姿勢が、近江商人の商売の根底にありました。
この考え方は、現代のビジネスにおいても強く共鳴します。
例えば、顧客満足(買い手よし)だけでなく、従業員の働きがいや企業の社会的責任(CSR)など、ステークホルダー全体に価値を届ける姿勢が企業に求められています。
営業活動においても、目先の売上だけでなく、長期的な信頼関係の構築や社会貢献を意識することで、より持続可能で強固なビジネスが実現できるのです。
「三方よし」は、時代を超えて活用できる普遍的なビジネス哲学と言えるでしょう。
三方よしの経営理念
「三方よし」という、三者が満足する取引を重んじた考え方は、多くの企業の理念としても採用されています。
特に伊藤忠商事はその代表例です。
同社は経営理念として「三方よし」を明確に掲げ、ビジネスのあらゆる判断基準において、企業の利益だけでなく、顧客や社会全体への貢献を重視しています。
また、ヤマト運輸や西武グループなど、顧客満足と社会的責任の両立を目指す企業が「三方よし」の精神を採用しています。
この考え方は単なる理念にとどまらず、企業の信頼構築、持続可能な成長、そして企業価値の向上にもつながる重要な経営指針といえるでしょう。
営業活動においても「三方よし」の精神を取り入れることで、顧客との信頼関係を強化し、社会から選ばれる存在となることが可能です。
「三方よし」の営業活動で大切なこと
営業活動において「三方よし」の精神を実践することは、短期的な成果にとどまらず、長期的な信頼関係の構築や持続可能な成長につながります。
ただ売るだけではなく、相手の立場に立ち、誠実に向き合う姿勢が求められるのです。
売り手・買い手・社会それぞれが満足できる関係性を築くには、何より信頼を土台に、互いに利害を超えた真のパートナーシップを目指すことが重要です。
また、企業や個人として社会にどのような価値を提供できるかを意識することで、より大きな成果が生まれます。
ここでは、営業活動において「三方よし」を実現するために大切な視点を紹介します。
信頼第一の関係構築
営業活動において、顧客との信頼関係を築くことは最も重要な要素の一つです。
単に商品やサービスを売るだけでは、長期的な成果にはつながりません。
むしろ、顧客が営業担当者に対して「この人から買いたい」「この人になら相談できる」と感じる関係性こそが、継続的な取引や紹介、信頼の連鎖を生み出します。
そのためには、まず誠実な姿勢が欠かせません。
誤魔化しやご都合主義ではなく、顧客にとって本当に必要なものを見極め、時には売らないという判断が求められることもあります。
また、約束を守る、迅速な対応を心がける、小さな要望にも丁寧に応じるといった行動が信頼を積み重ねる基盤となります。
さらに、営業担当者は「売り手」と「買い手」という立場を超えた、人間対人間のつながりを意識することが大切です。
一つひとつのコミュニケーションに誠意を込め、相手の期待を上回る対応をすることで、「この人と付き合ってよかった」と思ってもらえる関係が築かれていきます。
信頼第一の姿勢は、三方よしの営業活動の出発点です。
利害関係ゼロの関係構築
営業活動において重要なのは、自社の利益や取引先の都合だけでなく、両者にとって不利益がない“利害関係ゼロ”の関係性を築くことです。
これは、どちらか一方だけが得をするのではなく、双方が納得し、価値を感じられる取引を意味します。
無理な営業トークや過剰な価格交渉は一時的な成果を生むかもしれませんが、信頼関係の構築にはつながりません。
むしろ、長期的なビジネスの継続性を損なうリスクが高いと言えるでしょう。
理想的なのは、営業担当者自身が中立的な立場に立ち、相手のニーズをしっかりと汲み取った上で、最適な提案を行うこと。
その結果、取引先も自社も満足できる「Win-Win」の関係が成立し、さらに第三者である社会にとっても価値のある成果を生み出せるのです。
こうした関係性は、まさに「三方よし」の精神を体現した営業活動のあり方と言えるでしょう。
社会貢献度も高める
「三方よし」の精神に基づいた営業活動では、前述した信頼関係構築や利害関係の排除に加え、社会貢献を意識する姿勢も非常に重要です。
売り手と買い手の満足だけでなく、「世間」=社会全体への価値提供を考えることが、より上質な関係性の構築につながります。
たとえば、環境に配慮した製品の提案や、地域社会への支援、持続可能なサービスの提供などは、社会貢献度を高める代表的な取り組みです。
こうした姿勢は顧客からの信頼を深めると同時に、企業としてのブランド価値向上にもつながります。
営業担当者としては、自社の商品やサービスがどのように社会の役に立つのかを意識しながら提案することで、相手との関係性が一過性のものではなく、長期的で誠実なつながりへと進化します。
「三方よし」を体現するためには、目先の利益だけでなく、社会全体へのプラスの影響を常に意識することが求められます。
営業としてあるべき姿
営業職は単なる「売る人」ではありません。
顧客や社会と信頼関係を築きながら、継続的な価値提供を行う役割が求められます。
その中で、「営業としてどうあるべきか」という姿勢や心構えは、結果として顧客満足や企業成長に大きく影響します。
ここからは、営業が目指すべき理想像を「誠実さ」「寄り添い」「問題解決力」という3つの視点から紐解きます。
これらの要素を深く理解し実践することで、単なる成果主義ではない、長期的に信頼される営業へと近づくことができるでしょう。
誠実な姿
営業として最も基本でありながら、最も信頼を築く上で欠かせない要素が「誠実さ」です。
誠実とは、ただ嘘をつかないということにとどまりません。
相手の立場に立って物事を考え、言葉や行動に一貫性を持ち、自分の利益だけでなく相手の利益も真剣に考える姿勢が問われます。
顧客との信頼関係は、一朝一夕で築けるものではなく、日々の積み重ねによって生まれます。
たとえば、都合の悪い情報であっても正直に伝える、無理に商品を勧めないといった行動が、誠実な営業の代表例です。
また、約束や納期を守るといった基本的なビジネスマナーも誠実さの表れです。
誠実な営業は、顧客から「また相談したい」「この人になら任せられる」と思われる存在になり、長期的な信頼と関係構築につながります。
目先の成果を追うのではなく、誠実な姿勢を貫くことが、営業としての真の価値を高める鍵となります。
寄り添う姿
営業として、常に顧客側の立場に立って寄り添う姿勢でいることも、非常に大切なことです。
営業職は、単に商品やサービスを売ることが仕事ではありません。
顧客が本当に必要としているものを理解し、その課題や悩みに共感しながら、最適な解決策をともに考える姿勢が求められます。
この「寄り添い」は、顧客との信頼関係を築くための第一歩であり、長期的な関係構築にもつながる重要な要素です。
また、顧客の立場になって物事を考えることは、提案の質を高め、相手にとって本当に価値のある提案を行うことにつながります。
「売る」ことが目的になってしまうと、営業の言動は一方的になりがちです。
しかし「寄り添う」意識がある営業は、顧客の声に耳を傾け、丁寧に対話を重ねながら、共にゴールを目指す伴走者としての役割を果たします。
こうした姿勢は、三方よしの「買手よし」につながり、顧客満足を超えた信頼の獲得へと導いてくれます。
営業とは、商品ではなく信頼を売る仕事であると言えるでしょう。
問題解決力
営業の本質的な役割は、相手の課題を解決することですから、問題解決力を持ち合わせていることも重要です。
顧客の要望にただ応えるだけでなく、顧客自身が気づいていない潜在的な課題を見抜き、最適な解決策を提案する力こそが、信頼される営業に求められます。
問題解決力を高めるためには、まずヒアリング力の向上が不可欠です。
相手の話を深く聞き、背景や本質を読み取る力が重要です。
また、自社の商品・サービスの知識を深めるだけでなく、業界全体の動向にもアンテナを張ることで、幅広い視点から提案ができるようになります。
さらに、論理的思考や仮説検証力も大切です。
問題の原因を特定し、段階的にアプローチする姿勢が信頼へとつながります。
営業は単なる商品提供者ではなく、「課題を解決するパートナー」であるという意識を持つことで、顧客との関係性もより深まり、三方よしの営業活動が実現できます。
営業の目的とは
営業職において成果を上げ続けるためには、「なぜ営業をするのか」という明確な目的意識が欠かせません。
ただ目の前の業務をこなすだけでは、やがて意欲が薄れ、成果にも悪影響を及ぼします。
営業の目的は業種や業界によって異なるものの、すべての営業職に共通する基本的な目的があります。
それは、顧客の課題を解決すること、会社の売上を確保すること、そして企業イメージを高めることです。
これらの目的をしっかりと認識し、日々の営業活動に落とし込むことが、信頼される営業パーソンへの第一歩です。
顧客の課題に対しての解決
営業活動において、顧客の課題を正確に把握し、最適な解決策を提案することは非常に重要です。
顧客は一人ひとり背景や価値観、重視するポイントが異なり、すべての要望に応えるのは難しい場合もあります。
しかし、まずは顧客の声に真摯に耳を傾け、「何に困っているのか」「何を求めているのか」を丁寧に理解する姿勢が求められます。
中には、コストの制約や社内事情など、すぐには対応できない問題もあるでしょう。
だからこそ、営業は自社の商品・サービスがどのように顧客の課題解決に貢献できるかを分かりやすく伝える必要があります。
ただ売るのではなく、「信頼できる相談相手」として認識されることが、営業としての価値を高めます。
さらに、顧客の課題を知ることは、将来的な商品開発やサービス改善のヒントにもなります。
日々の対話を通じて得られる顧客のリアルな声は、企業にとって大きな財産です。
継続的なコミュニケーションを通じて、顧客との関係性を深め、長期的な信頼を築いていくことが営業の目的の一つです。
会社に対しての売上の確保
営業の大きな目的の一つは、会社にとっての利益を確実に生み出すことです。
営業活動はあくまでもビジネスであり、ボランティアではありません。
したがって、自社の売上を維持し、さらには成長させる視点を常に持つことが求められます。
ただし、単に商品やサービスを売り込むのではなく、顧客の課題やニーズに的確に応える提案を行うことで、信頼関係を構築することが大切です。
信頼が生まれると、顧客は自社の商品やサービスを「必要なもの」として受け入れ、より価値の高い提案にも耳を傾けるようになります。
結果として、単価の高い商品や付加価値のあるサービスの受注にもつながり、売上拡大が可能になります。
また、営業が顧客の満足を第一に考えながらも、しっかりと自社の利益確保も視野に入れて行動することで、持続的にモチベーションを保ちやすくなります。
顧客と会社の双方にとって「価値ある営業」を実現することこそが、売上の確保と営業としての本来の役割を果たすことにつながるのです。
会社の窓口としてのイメージ力アップ
営業職は、単に商品やサービスを販売するだけでなく、企業の「顔」としての役割を担っています。
顧客が企業と最初に接点を持つのは、たいてい営業担当者です。
そのため、営業の印象がそのまま会社全体のイメージに直結すると言っても過言ではありません。
たとえば、丁寧なあいさつや誠実な対応、相手の話にしっかり耳を傾ける姿勢などは、顧客に安心感と信頼を与えます。
その結果、「この人のいる会社なら信頼できそうだ」と企業全体への評価が高まるのです。
一方で、無愛想な態度やマナーの欠如は、「社員教育が行き届いていない会社」というネガティブな印象を与えかねません。
現在では、同じような商品・サービスを提供する企業が多数存在しています。
だからこそ、営業担当者の人柄や立ち居振る舞いが差別化の要因となり、顧客の選択を左右します。
営業は、自身が企業の第一印象を決定づける「会社の窓口」であることを常に意識し、信頼される存在として行動することが求められます。
トップ営業マンになるためのコツ5つ
営業職として配属されたからには、「いつかトップ営業マンとして活躍したい」と考える方も多いでしょう。
業界や商材を問わず、優れた営業パーソンにはある種の「型」があります。
ここでは、トップ営業マンが実践している5つのポイントをご紹介します。
どれも基本的なことですが、深く理解し継続することで、確かな成果へとつながっていきます。
それでは一つずつ見ていきましょう。
1.セルフイメージを常に持つ
トップ営業マンに共通する特徴のひとつに、「セルフイメージの高さ」があります。
セルフイメージとは、自己認識や自己評価のことで、自分に対してどのようなイメージを抱いているかを意味します。
営業においてこのセルフイメージは非常に重要です。
高いセルフイメージを持つ営業マンは、たとえ困難な状況に直面しても、前向きな思考を保ちやすくなります。
たとえば、顧客から厳しい意見やクレームを受けたとしても、それを「サービス改善のための貴重なフィードバック」と捉えることができます。
また、営業活動のなかで壁にぶつかった際も、それを「自分が成長できる機会」だと受け止めることができるのです。
そのようなセルフイメージを持ち続けるためには、まず営業としての目標やミッションを明確にし、その達成後の姿を具体的に思い描くことが効果的です。
日々の業務の中で、自分自身がどんな営業マンでありたいのか、どのように周囲から見られたいのかを意識することが、自信とポジティブな行動につながっていきます。
セルフイメージの向上は、営業成績だけでなく、顧客との信頼関係や社内での存在感にも直結します。
まずは「理想の自分」をしっかり描くことから始めましょう。
2.目標を逆算して立てている
どの分野でも目標を立てることは進歩につながります。大まかな目標を立てる人もいれば、小さな目標をいくつも立てる人もおり、目標に対する見方は人それぞれです。
加えて、多くのトップ営業マンは、現段階で自分の能力をきちんと把握しており、立てた目標達成するまでの道筋を逆算して立てています。そのために必要なのは、立てた目標を数値で示すことです。
例えば、売上目標や成約率の向上を目標にする場合、まず目標を数値化します。その後、今月の達成率を算出し、算出値から逆算して来月の目標値を立てる流れです。目標を数値化し、逆算して具体的な営業活動をどれくらい行えばよいかを考慮します。
この流れを繰り返すことにより、顧客のニーズや課題に敏感に対応し、安定した営業成績の維持が可能です。
3.第一印象に気を配る
よく「会って3秒で印象が決まる」と言われますが、営業職において第一印象は、想像以上に大きな影響を与えます。
どれだけ話が上手で商品知識に長けていたとしても、第一印象が悪ければ、の後の商談に悪影響を及ぼす可能性があります。
特に、清潔感のない服装や乱れた身だしなみは、相手に不快感を与えかねません。
実際に、多くのトップ営業マンは、業界や職種を問わず、身だしなみに細心の注意を払っています。
顧客と信頼関係を築くためには、まず相手に「この人なら信頼できそうだ」と思ってもらうことが大切です。
そのためには、見た目にも誠実さや清潔感が表れるよう心掛ける必要があります。
また、身だしなみだけでなく、表情や立ち振る舞いにも気を配りましょう。
明るく爽やかな笑顔や丁寧な態度は、相手に好印象を与え、会話のスタートをスムーズにしてくれます。
第一印象は一度きり。
その短い時間で信頼の種をまく意識を持つことが、トップ営業マンとしての第一歩です。
身だしなみや態度を整えることは、営業における基本であり、商談を円滑に進めるための重要なポイントなのです。
4.常にお客様目線で物事を考える
営業活動において、自社の売上向上や利益確保は重要な目標です。
しかし、こればかりを優先していると、顧客の信頼を得ることは難しくなります。
トップ営業マンが共通して持っている視点は、「常にお客様目線で考える」姿勢です。
これは、顧客の立場に立って課題やニーズを的確に把握し、最適な提案をするという基本姿勢にほかなりません。
特に意識したいのは、提案時だけでなく、日常的にこまめに連絡を取り、顧客の状況に寄り添うこと。
こうした丁寧なアプローチは、顧客からの信頼を築く土台となります。
この「お客様目線」は、売り手・買い手・社会の三者すべてが満足する「三方よし」の精神にも通じるものです。
営業として成果を出すには、売上だけでなく顧客の成功、さらには社会全体への貢献まで視野に入れることが重要です。
日頃から相手を思いやる習慣を育み、名前で呼ぶ、気軽に連絡するなどの小さな行動から積み重ねていきましょう。
5.柔軟に行動をする
柔軟性も営業職に必要です。人はそれぞれ考え方や性格が異なるため、営業する際に自分のやり方にいつも固執していてはうまくいかないケースが多くあります。
相手の性格や状況に合わせて、営業スタイルを変える柔軟性があれば、顧客層の拡大につながるため重要です。
営業スタイルには、いくつか種類があります。一般的な分類は、説明型・提案型・共創型・能動型です。具体的な説明を中心に行ったほうがよいのか、顧客と一緒にアイデアを出し合う方法がよいのか、その場の雰囲気や顧客の性格に合わせてスタイルを変えます。
少し高度な技術が必要ですが、相手に合わせた柔軟な対応は三方よしにも関連する方法です。常に周りに気を配る姿勢を心がけましょう。
三方よしを活用して営業で活躍しよう
営業職で成果を上げるためには、売上だけを追い求めるのではなく、顧客や社会全体への貢献を意識することが重要です。
その考え方を体現しているのが「三方よし」です。
近江商人が提唱したこの哲学は、「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」という三者の満足を追求するものであり、現代の営業活動においても通用する普遍的な価値観です。
三方よしの精神を営業に取り入れることで、お客様の立場に立った提案や課題解決が可能となり、信頼関係を築きやすくなります。
また、自己の成長に向けた努力、たとえば自己分析や柔軟な対応力の習得も欠かせません。
トップ営業を目指すうえでは、こうした姿勢が長期的な成果と評価につながります。
今後も「自分」「相手」「社会」の三方にとっての最善を意識しながら、一歩ずつ前進していきましょう。
それこそが、営業として本当の意味で活躍するための道なのです。
SHARE この記事を友達におしえる!