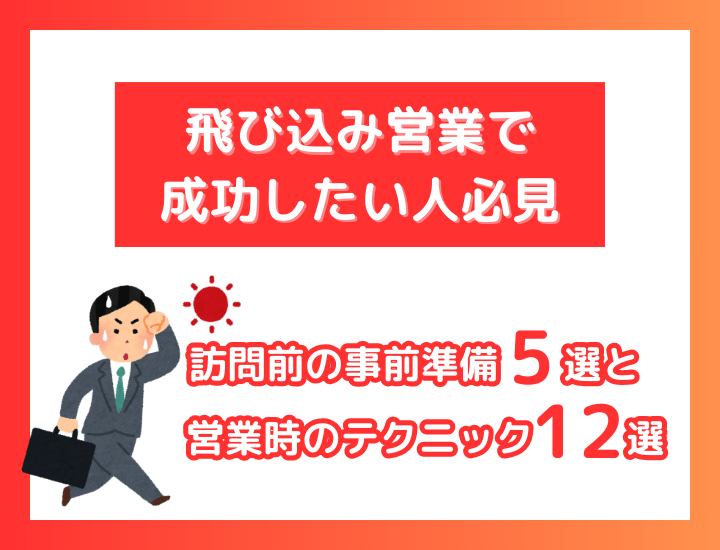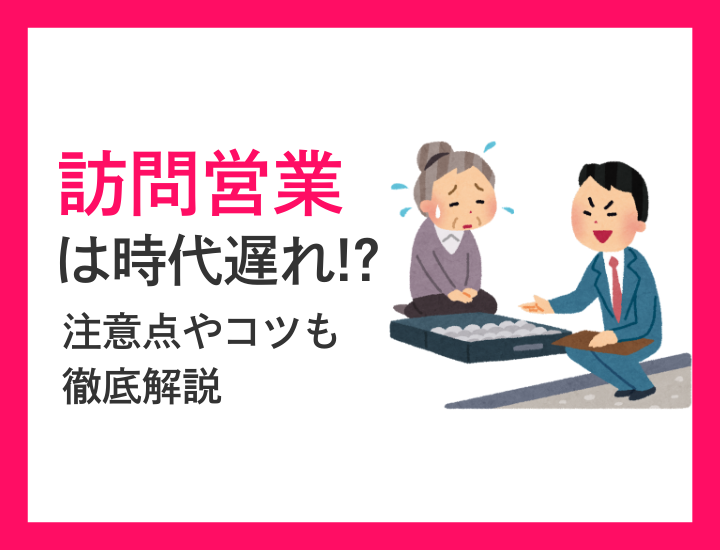
【訪問営業とは】手法が時代遅れ?目的やメリット・コツまで徹底解説!
はじめに
訪問営業は、顧客に直接会って商品やサービスを提案する営業手法です。
オンライン営業が広がる現在でも、対面ならではの信頼関係の構築力から多くの企業で採用されています。
一方で、移動や時間調整の負担が大きく、効率面では課題もあります。
この記事では、訪問営業の目的やメリット、成果を上げるための方法を解説します。
【訪問営業とは】訪問営業の目的
訪問営業の目的は、顧客との信頼関係を直接築き、商品やサービスの魅力を正しく伝えることにあります。
電話やメールなどの非対面手法では得られない情報や反応をその場で確認でき、顧客の課題やニーズを把握しやすくなります。
特に初めての商談や高額商材の場合、対面での説明は安心感を与え、購買意欲を高める効果があるでしょう。
また、定期的な訪問は顧客との関係性を強化し、継続的な取引や紹介につながる点も大きな目的のひとつです。
【訪問営業とは】訪問営業の仕事内容
訪問営業は、顧客と直接顔を合わせて商品やサービスを提案する営業手法です。
営業担当者は顧客先を訪れ、ニーズを把握しながら最適な解決策を提案します。
顧客の反応をその場で確認できるため、信頼関係を築きやすいのが特徴です。
また、資料を使ったプレゼンや実際のデモンストレーションを行うことで、商品の魅力をより具体的に伝えられるでしょう。
訪問のスタイルには、大きく分けて「事前にアポイントを取ってから訪問する方法」と「飛び込みで直接訪問する方法」があります。
アポイントありの場合は効率的に商談を進められますが、アポなしの飛び込み営業は、数多くの顧客と接点を作るきっかけになります。
ここからは、それぞれの訪問スタイルの特徴とポイントを解説します。
アポを取ったあとに訪問する営業
アポを取った後に訪問する営業では、アポ取りは基本的に電話で行います。
突然直接会いに行く飛び込み営業と違い、まずは電話でその商品やサービスに興味があるかを確認できるため効率的です。
わざわざ足を運んだ営業が無駄になる確率は格段に減ります。
しかし、会ったこともない人から突然電話がきて商品やサービスを紹介されて「じゃあ直接話を聞いてみようかな」と思わせるためには、相当のコツや技術が必要です。
飛び込み営業
飛び込み営業はその名のとおり、企業や個人宅に直接訪問して営業活動を行う手法です。
事前に約束をせずに、どんな人が住んでいるのかもわからないまま訪ねます。
そのため、インターホンのモニター越しに門前払いされてしまうケースのほうが多いのも事実です。
企業でも担当者に会うまで至らない場合も少なくありません。
とにかく足を使って話を聞いてくれる人を探すことになるため、効率の悪い営業手法といわれています。
断られ続けているうちに、精神的につらくなってくる営業職も多い傾向です。
【訪問営業とは】訪問営業のメリット
訪問営業には、非対面営業では得られない多くのメリットがあります。
特に、顧客と直接会うことで信頼関係を築きやすく、細かな表情や反応をその場で確認できる点は大きな強みです。
商品やサービスの魅力を実際に体験してもらうことで、顧客の理解や納得度を高めやすくなります。
また、商談中に顧客の課題やニーズを深く掘り下げることができ、受注につながる確率も高まるでしょう。
ここからは、訪問営業ならではのメリットを4つの観点から見ていきましょう。
信頼関係が築きやすい
訪問営業の最も大きなメリットは、顧客との信頼関係が築きやすいことです。
非対面で行う営業よりも相手の顔を見ながら商談ができるため、より親近感を持ってもらいやすくなります。
ウェブ会議ツールなどで行う非対面の営業の場合、相手の顔を見られても目の前にはいないため、相手の姿勢などの十分な把握は難しいのが現状です。
対面での営業は、身振り手振りを交えて行うため、相手の印象に残りやすくなります。
さらに、人間には「単純接触効果」があります。
単純接触効果とは「同じものや人に何度も触れているうちに、その物や人に対して好印象を抱きやすい」心理状態です。
何度も訪問営業を繰り返せば相手にも認知され、関心を持ってもらっているとうれしく感じてもらえる可能性が高まります。
こうした信頼関係の構築は、訪問営業のメリットです。
コミュニケーションが取りやすい
コミュニケーションが取りやすいのも、訪問営業の大きな魅力です。
相手の表情やリアクションが分かり、会話をしてる際の温度感もリアルでつかめます。
営業は台本があって進めるわけではありません。
時には、その場の雰囲気に合わせて臨機応変な対応を取ることも必要です。
また訪問営業を行うことで、顧客のオフィスの雰囲気や所在地の雰囲気なども分かります。
これらはオンライン営業では分からない現地の情報です。
対面で有益な情報を提供し続ければ、相手からの信頼も得られ、コミュニケーションはより容易に行えるようになります。
実際に対面してコミュニケーションが促進されることは多いため、訪問営業は効果的な活用が大切です。
リスクを回避しやすい
訪問営業では、顧客と直接会話しながら商談を進めるため、トラブルやキャンセルのリスクを事前に察知しやすいメリットがあります。
対面であれば顧客の表情や言葉のニュアンスから不安や懸念点を早期に把握でき、その場で疑問を解消できます。
特に高額商材や契約内容が複雑なサービスでは、メールや電話だけでは説明不足になり、契約後のトラブルやキャンセルにつながるケースも。
訪問営業なら、実際の資料やサンプルを用いて誤解を防ぎ、顧客の理解度を確認しながら進められるため、契約後のリスクを減らせます。
また、訪問時に顧客の状況を直接確認することで、潜在的な問題点や課題を見つけやすくなり、柔軟な提案や代替案を提示できる点も大きな強みです。
商品やサービスの魅力を伝えやすい
実際にカタログを渡す・デモ画面を見てもらう・商品の紹介をして実感を持ってもらうなどができるのは、訪問営業の大きなメリットです。
オンライン営業では、リアルな商品サンプルを触ってもらうなどは難しく、雰囲気を伝えることが困難ではないでしょうか。
サービスを紹介する際、実機を用いてその場で紹介した方が、現場の雰囲気や自分自身の業務内容に照らし合わせやすくなります。
さらに、自分で操作してもらうなどもできるため、商品やサービスに関する理解を深めてもらえることもメリットです。
実際に商品を見てみたい、サービスを簡単に触ってみたいなどのニーズは多いため、営業活動の進捗に合わせて訪問営業を活用できます。
【訪問営業とは】訪問営業はなぜ時代遅れと言われるのか
訪問営業は、かつて営業活動の中心的な手法として多くの企業で採用されてきました。
しかし、オンライン営業やインサイドセールスといった非対面型の手法が主流になる中で、「訪問営業は時代遅れ」という声もあります。
その背景には、移動時間やコストの増大、効率性の低下、顧客側の働き方の変化があります。
ここからは、訪問営業が時代遅れといわれる理由を解説します。
働き方が変化した
近年のテレワークやフレックスタイム制度の普及により、顧客が常にオフィスにいるとは限らなくなりました。
特にコロナ禍以降はオンライン会議やチャットツールの活用が一般化し、訪問営業よりも非対面の営業スタイルが好まれる傾向があります。
顧客にとっても訪問のために時間を割く負担が増え、アポイントの調整が難しくなっているのが現状です。
こうした背景から、訪問営業は効率が悪く、相手のスケジュールを妨げる可能性があると見なされることがあります。
現代の営業活動では、顧客の働き方やライフスタイルに配慮し、オンライン商談や事前の情報提供を組み合わせるなど、柔軟な対応が必要かもしれません。
業務効率が悪い
訪問営業は顧客先までの移動が必須であり、1日の商談件数が限られてしまう点が大きな課題です。
例えば、片道1時間以上かかる訪問先を複数回る場合、移動時間だけで半日が潰れてしまうこともあります。
さらに、顧客の都合によっては短時間の面談で終わることも多く、コストパフォーマンスが悪いと感じる営業担当者も少なくありません。
また、天候や交通事情に左右されやすく、予定通りに訪問できないリスクもあります。
これに対し、オンライン営業や電話営業は移動時間を必要とせず、短時間で複数の顧客と接点を持つことが可能です。
そのため、訪問営業は効率性の面で見劣りし、特に都市部や広範囲に営業先を抱える企業では負担が大きくなりがちです。
【訪問営業とは】訪問営業で成果を出すためのコツ
訪問営業で成果を上げるには、ただ訪問件数を増やすだけでは不十分です。
顧客の課題を的確に把握し、信頼を得ながら最適な提案を行うための戦略と工夫が求められます。
特に、ヒアリングの質を高めることや、相手の状況に合わせた柔軟な対応は欠かせません。
ここからは、訪問営業で成果を出すために意識すべきポイントを紹介します。
顧客からのヒアリング
訪問営業で成果を上げるには、顧客の課題やニーズを正確に把握することが重要です。
商談の初期段階では、顧客が抱える不満や要望を丁寧に聞き出すことから始めます。
この際に有効なのが「オープンクエスチョン」です。
オープンクエスチョンとは、はい・いいえで答えられない質問のことで、「どのような課題がありますか?」や「現在の状況で不便を感じている点は?」といった形で、顧客が具体的に話しやすくなるのが特徴です。
また、課題を数値や事例で具体化できれば、後の提案がより説得力を持ちます。
さらに、顧客の予算感を把握することも大切です。
価格面での認識がずれたまま提案を進めると、商談が成立しにくくなることも。
個人顧客であれば直接予算を尋ねることも可能ですが、法人の場合は会話や公開情報から予算規模を推測する必要があります。
こうしたヒアリングを丁寧に行うことで、提案内容を無理なく顧客の状況に合わせることができ、成約につながりやすくなります。
落ち着いてゆっくりと話す
訪問営業する際は、なるべく落ち着いたテンションを心がけましょう。
前提として、聞き取りやすい会話の速度を意識する必要があります。
実際に話始めると焦って早口になってしまい、同時に動作も慌ただしくなってしまった経験がある営業職は多いのではないでしょうか。
それでは無意識のうちに顧客へ悪い印象を与えてしまいます。
営業に明確な時間制限はありません。
はじめのうちは世間話をして、お互いの緊張をほぐすための時間を設けましょう。
いわゆるアイスブレイクです。
いきなりあらわれた営業職を最初から信頼する人のほうが珍しいことを念頭に置き、焦らずにじっくりと交渉を進めていきましょう。
お互いに落ち着いてゆっくりと話せる状況を作れたら、あらためて商品を紹介します。
まずは、少しでも信頼してもらうことが大切です。
やりとりの連絡は即レスで
営業職として意識しておくべきなのは、連絡を取り合う際の「即レス」です。
相手からの連絡に対してすぐに返事をしないと「自分は後回しにされている気がする」「だらしない性格なのか」などの誤解を与えてしまうおそれがあります。
結果的に「この人と一緒に仕事をするのは不安」と思わせてしまう結果になりかねません。
たとえ急いでいなくても、すぐに連絡をくれる営業職は信用に値します。
即レスができる人に対しては「スピード感をもって仕事ができる人」「自分のことをいつも気にかけてくれている人」との印象を抱くのが一般的です。
直接会っていなくても、電話やメールでのやりとりは相手との接触回数に含まれます。
こまめな接触は、信頼度を上げることにもつながることを覚えておきましょう。
目的を整理する
訪問営業に苦手意識を感じたり、成果を出せなくて悩んだりしたときは、自分がやろうとしていることや目的を一度整理してみましょう。
とにかく成果につなげて会社での評価を上げることだけを考えていると、なかなかうまくいきません。
なぜなら、そのような目的で営業をしても相手のことを一切考えていないため、誠意が伝わらないからです。
もちろん最終的な目標は成果を上げることです。
しかし、お客様に良いサービスを提供し、喜んでもらうことが前提とされていることを忘れてはいけません。
それでこそ、自分自身が得られる達成感も大きなものになるはずです。
そのためには、各お客様への丁寧な接し方が何よりも大切なポイントになります。
決裁権を持つ人物の特定
個人が相手の訪問営業の場合は問題にならないものの、法人営業の場合は誰が最終的な決裁権を持っているかをできるだけ早い段階で把握しておくことは重要なポイントです。
訪問営業の際、対応してくれた相手が良い反応を示してくれても、最終決裁権を持つ人でなければ契約には至りません。
決裁権を持つ人の意向やニーズに見合った提案ではないケースがあるためです。
可能であれば、最初の段階で最終決裁権を持っているのは誰なのかを聞くようにしましょう。
決裁者のスケジュールをヒアリングし、直接会話できる機会を設けられるよう努力します。
直接会うのが無理な場合は、担当者から決裁者の意向やニーズを聞き出すことが必要です。
担当者が上手に決裁者に説明できるような提案を心掛けましょう。
導入予定の打ち合わせを行う
こちら側の提案に対して良い手応えを感じた場合、具体的な導入予定日を聞き出すことも重要です。
担当者または決裁者が、自社サービスを導入しているイメージを描けるようにする必要があります。
もし、具体的な導入時期に関する話し合いがされていなければ、何らかの事情により後回しにされかねません。
今すぐに検討しなくてもよい事案として扱われ、忘れられてしまう可能性もあります。
営業職は、契約の締結が最終的な目的だとの認識を忘れないようにしましょう。
相手の反応があいまいの場合は、こちらから具体的なスケジュールを提案するのも効果的な方法です。
なぜその時期が良いのかを説明できれば、説得力が増します。
関係構築などの種まきを行う
営業職の最終的な目標は契約とはいえ、1回の訪問で全て決まることはほぼありません。
昨今のニュースを見ても分かるとおり、人々の警戒心が強いのが現状です。
初めて会う人に対して心を許す人はさほど多くありません。
そのため、訪問営業を行う際は、信頼関係を構築するための種まきをする必要があることを覚えておきましょう。
電話営業も含め、何度か接点を持つうちに信頼関係が構築されます。
相手のニーズを確かめられるような簡単なヒアリングをしたり、分かりやすい資料を準備したりして、信頼を勝ち得るための工夫が必要です。
相手の抱く疑問や不安を想定し、納得してもらえるような回答を準備しておくことも助けになります。
売り込みすぎない
訪問営業で注意したい点は、何が何でも契約に結び付けたいとの意識を全面に出さないことです。
売り込みたいとの強い意気込みを持って相手に接してしまうと、相手は警戒心を強めてしまいます。
警戒心を抱いた相手に対しては、信頼関係は構築されにくいのが現状です。
信頼できない相手からある程度費用がかさむ商材・サービスを購入したいと思う人はいないのではないでしょうか。
同じような商材・サービスを提供している同業他社との競合に勝つためには、顧客との信頼関係は欠かせません。
初回から売り込み過ぎないようにし、お互いに関する理解を深めることを目標に訪問を重ねていきましょう。
訪問回数を増やして信頼関係を構築する
訪問営業では、初回の訪問で契約を決めるのは難しいのが現実です。
多くの場合、顧客は初対面の営業担当者に警戒心を抱き、商品やサービスの話をすぐに受け入れてくれるとは限りません。
そこで重要になるのが、複数回の訪問による関係構築です。
心理学で「ザイオンス効果」と呼ばれるように、人は繰り返し接触する相手に対して自然と好感度や信頼感を抱きやすくなります。
たとえ最初は興味がなくても、何度か顔を合わせることで警戒心や不安感は次第に薄れ、相手に安心感を持つようになります。
また、訪問を重ねる中で顧客の状況や課題が明確になり、適切な提案を行いやすくなります。
初回から契約を迫るのではなく、情報提供や簡単なヒアリングを通じて信頼を積み重ねることが重要です。
多くの顧客は購入を決定する前に十分な情報収集や比較検討を行うため、1回の訪問で成果が出なくても焦る必要はありません。
諦めずに継続的な接触を続けることで、契約に至る可能性は着実に高まるでしょう。
営業活動の内容を振り返る
訪問営業をした後は、できるだけ早い段階で営業活動の内容を振り返ることは大切です。
うまく契約締結に至った場合だけでなく、断られた場合もどのような会話がなされたのかを振り返るようにしましょう。
相手がどのような人だったのか、どのような話の流れで契約できたのかなどを思い返します。
断られた場合は、相手のニーズが本当は何だったのかを考えるようにすれば、次回につながる教訓を得ることが可能です。
いずれにしても、成功や失敗の原因と改善策を常に振り返り、今後の段階的な目標を設定します。
日々の努力により営業スキルを伸ばしていきましょう。
【訪問営業とは】訪問営業の注意点
訪問営業は、顧客と直接対面して信頼を築ける反面、進め方を誤ると逆効果になることもあります。
訪問のタイミングや頻度、約束の取り扱い方など、基本的なマナーや配慮を欠くと相手に不快感を与え、関係が悪化する原因になります。
また、状況に応じた臨機応変な対応も欠かせません。
ここからは、訪問営業を行う際に押さえておきたい注意点を紹介します。
相手の対応しやすい時間に訪問する
訪問営業は顧客ファーストで行うことが基本です。
最も意識するべきなのは時間帯といっても過言ではありません。
自分の営業活動が行える時間が限られていても、相手に強要しないようにしましょう。
朝イチの訪問やお昼休み時間帯の訪問、就業時間間際の時間帯に訪問するのは避けた方が無難です。
アポイントを取る際には、ピンポイントで時間の指定を行うのではなく、いくつかの候補を挙げて選択肢を持たせましょう。
また、お昼休みの時間帯での電話は避けるなど、相手の対応しやすい時間帯を意識して動くことが必要です。
訪問頻度を意識する
訪問頻度にも注意しましょう。
なぜなら訪問頻度は、案件の大きさや進捗状況、相手との信頼関係などによって変わってくるからです。
まったく案件がなく、情報提供するものもないにもかかわらず、何度も訪問してしまうと逆に信頼を損ねてしまいます。
また、大きなプロジェクトを進行しているにもかかわらず、訪問頻度が少ないと相手からの信用を得ることは難しいことを覚えておきましょう。
臨機応変に対応する営業スキルが求められます。
訪問頻度に決まった回数はありません。
顧客との信頼関係や必要性に応じて、何度も訪問した方が良いか、たまに顔を出す程度で良いのかを考えていきましょう。
手土産の持参を検討する
訪問営業では、商談や挨拶の際に小さな手土産を持参することで、相手に良い印象を与えることがあります。
手土産は必須ではありませんが、「わざわざ時間を割いてもらったことへの感謝」を形にできるため、信頼関係の構築に役立ちます。
高価なものや大げさな贈り物はかえって気を遣わせる可能性があるため、菓子折りや簡単なお茶菓子など、日常的に消費できる品が好ましいでしょう。
また、手土産は会話のきっかけにもなり、商談前の雰囲気を和ませる効果があります。
ただし、業種や取引内容によっては受け取れない場合もあるため、相手の状況を事前に確認しておくことが大切です。
適切なタイミングと品選びを意識すれば、営業の成果に間接的なプラス効果をもたらすはずです。
相手と約束したことは守る
顧客との約束は必ず守るようにしましょう。
例えば商談の中で、顧客からたくさんの質問が出るケースがあります。
その場で明確な回答ができなくても、後からメールで回答できる場合は少なくありません。
その際に、いつまでにどのような形で回答するかを決め、きちんと守ることが信頼につながっていきます。
営業として結果が出ないのは、顧客との約束を守れない・質問に対しての回答が遅い・納品日を守れないなどが主な理由です。
少しの遅れでも大きな信用損失につながってしまうため、人と人との関係を意識しながら、相手と約束したことは必ず守るようにしましょう。
臨機応変に対応する
訪問営業は突然の予定変更も多くあります。
例えば、顧客の担当者が体調不良になってしまったので日程を変えてほしいなどです。
他にも、資料をカタログではなくPDFファイルで送ってほしいなど、顧客からの要望にできる範囲で臨機応変に対応しましょう。
また、訪問営業で行なった商談の内容が芳しくないと感じた場合は、提案内容を変えてみるなども臨機応変な対応です。
対面だからこそ分かる空気感もあるため、五感を活かしながら営業活動を行ない、どんな状況にも慌てないように対応しましょう。
【訪問営業とは】訪問営業で成果を出すための心構え
訪問営業で成果を上げるためには、単に訪問回数を増やすだけでは不十分です。
顧客との関係構築や商談の質を高めるために、営業担当者自身の心構えが重要となります。
訪問の目的を明確にし、断られることを前提に冷静に行動するようにしましょう。
ここからは、訪問営業で成果を出すために意識すべき心構えを解説します。
質と量の両立
相手と接触する回数を増やすことは、好感度を高める効果が期待できます。
大抵の新人営業職は、まだ営業のスキルが十分ではありません。
まずは訪問回数を増やして、経験を積むことが大切です。
しかし、ただやみくもに何度も会えばよいわけではありません。
ある程度訪問回数を増やして相手の警戒心を解いた後は、商談の質を上げることに尽力しましょう。
例えば、商品やサービスに興味を持ってくれた相手に絞って訪問したり、過去の顧客受注データを分析してターゲットを決めたりするのがおすすめです。
もし、訪問営業で成果を出せないと悩んでいるなら、それは営業の質と量が両立できていないことに原因がある可能性も考えられます。
訪問する目的を常に明確にする
訪問営業は断られるケースが多く、最初からうまくいくことはほとんどありません。
何度も足を運び、質の高い商談ができたときにはじめて成功の可能性が見えてきます。
だからこそ、訪問する際の目的をその都度明確にする過程が重要です。
営業で企業や個人宅を訪問する目的は、主に以下の4つがあります。
・商品の提案やお客様の要望に関するヒアリング
・問題が起きてしまったときの謝罪
・契約書の回収、情報の提供
・担当者が変更になったときや季節のあいさつなど
目的によって、事前のアポが必要になることもあるので注意してください。
相手の時間を有意義なものにするためにも「今回はこのような目的で来ました」と明確に伝えてから本題に入りましょう。
断られるのが当たり前と考える
基本的に、訪問営業は断られるのが当たり前と考えておきましょう。
どんなトップ営業職でも、百発百中で契約を取ることは不可能です。
むしろ「契約が取れたらラッキー」くらいの思考を心がけましょう。
特に、こちら側から営業をかける訪問販売では、断られることが当たり前です。
たまたま都合がつかないタイミングだったなど、さまざまな要因が考えられます。
必ずしも営業の仕方に落ち度があったわけではないことを覚えておきましょう。
もし仮にそうであっても、後悔したところで結果は変わりません。
しっかりと反省して、次に活かしたほうが身のためです。
あまり思い詰めすぎないように注意しましょう。
特に対応が難しい訪問先だった場合は、気にしすぎないことが大切です。
選り好みせずにすべて訪問する
営業では、ある程度ターゲットを決めて顧客を選ぶことも、ときには必要です。
周辺の情報を集めることも大切な業務です。
しかし、情報収集は外回りの時間外に行ってください。
外回り中は、なるべく訪問そのものに集中しましょう。
訪問営業自体が新規層開拓につながり、訪問数を増やせば制約率を高められる可能性があります。
一見するとかなり地道な業務に感じるかもしれません。
しかし、地道な活動が自分の業績に必ず反映されます。
営業で大切なのは顧客との信頼関係です。
そして、その信頼は簡単に築けるものではありません。
ただ単に商品を紹介するスキルがあっても、人の心を動かすことは困難です。
信頼を得るために、まずは自分からきちんと行動を起こすことが大切です。
【訪問営業とは】訪問営業に向いている人
訪問営業は、顧客と直接対面し、コミュニケーションを取りながら提案を進める仕事です。
そのため、向いている人にはいくつか共通する特徴があります。
主なポイントは以下です。
1. コミュニケーション能力が高い人
訪問営業は、相手の表情や反応を読み取り、臨機応変に対応する力が求められます。
会話のキャッチボールが得意で、相手に安心感を与えられる人は訪問営業に向いています。
2. 粘り強く行動できる人
一度の訪問で成果が出ることは少なく、複数回の訪問が必要です。
断られても前向きに挑戦し続ける粘り強さが重要です。
3. 相手の立場を考えられる人
顧客の課題や要望を理解し、適切なタイミングで提案するには、相手目線で考える姿勢が不可欠です。
押し売りではなく、相手の利益を意識できる人が信頼を得やすい傾向があります。
4. 自己管理ができる人
訪問営業は移動や時間管理が必要なため、計画性や自己管理能力が求められます。
訪問先や商談の準備を丁寧に行える人は成果を出しやすいです。
5. フィードバックを活かせる人
商談後に自分の営業活動を振り返り、改善点を見つけて次に活かせる柔軟さも大切です。
試行錯誤を重ねながらスキルを伸ばす意欲がある人は、訪問営業に向いています。
【訪問営業とは】訪問営業に向いていない人
訪問営業は顧客と直接向き合うため、人によっては負担やストレスを感じやすい仕事です。
訪問営業に向いていない人の特徴は以下です。
1. コミュニケーションが苦手な人
訪問営業では初対面の相手に話しかけ、短時間で信頼を得る必要があります。
人と会話するのが苦手、または緊張しやすい人はスムーズな商談が難しくなりがちです。
2. 断られることに過度にストレスを感じる人
訪問営業では断られることが日常です。
「断られた=失敗」と感じてしまう人は精神的に消耗しやすく、長続きしにくい傾向があります。
3. 自己管理ができない人
訪問営業は移動や訪問件数の計画、資料準備などやるべきことが多くあります。
スケジュール管理が苦手だと効率的に行動できず、成果につながりにくくなります。
4. 環境の変化に対応できない人
訪問営業は相手の都合に合わせて柔軟に対応することが求められます。
臨機応変な判断が苦手な人や、計画が少しでも崩れると焦ってしまう人には不向きです。
5. 行動力が不足している人
訪問営業は自ら行動しなければ始まりません。
受け身の姿勢で待つタイプの人や、外回りが面倒と感じる人はモチベーションを維持しにくいです。
【訪問営業とは】訪問営業以外の営業手法を解説
営業活動には訪問営業以外にもさまざまな手法が存在し、業種や顧客の状況に合わせて使い分けることが求められます。
近年では、オンライン商談やインバウンド営業など、移動を伴わず効率的に顧客と接点を持てる方法が注目されています。
ここからは、代表的な営業手法であるインバウンド営業、オンライン営業、インサイドセールス、電話営業、アウトバウンド営業の特徴について解説します。
インバウンド営業
企業側から商材・サービスの購入に関して積極的に営業するのではなく、見込み顧客側からの問い合わせを待つ受け身型スタイルをインバウンド営業(プル型営業)と呼びます。
営業職の仕事内容は、ウェビナーや自社ホームページなどを活用し、商材・サービスに関する有益な情報を発信し続けることです。
ある程度興味や関心を示した人が問い合わせてくるため、顧客となり得る見込みが高く、契約まで発展しやすいメリットがあります。
インバウンド営業では、いかに人々のニーズを察知し、必要としている情報を提供できるかが重要なポイントです。
加えて、問い合わせてきた相手の不安点や疑問点に的確に答える必要もあります。
オンライン営業
インターネット回線を利用して行う営業活動全般をオンライン営業と呼びます。
例えば、メール・チャットツール・ウェブ会議システムなどを利用した営業手法です。
近年、数多くの企業で導入が促進されているDX化に伴い、顧客データの蓄積や分析が容易になりました。
顧客ニーズに合わせてより効果的に営業できるメリットがあります。
加えて、訪問営業とは異なり、相手の自宅や会社へ出向く時間を省けるため、効率的な業務遂行が可能です。
コロナ禍で働き方が変化したことにより、幅広い業種で取り入れられるようになりました。
商談から成約までの期間を短くできれば、費用対効果が見込める営業手法です。
インサイドセールス
インバウンド営業やオンライン営業と似ており、訪問するのではなく内勤で行う営業手法をインサイドセールスと呼びます。
メール・ウェブ会議システム・電話などを用いた、非対面の営業スタイルです。
見込み顧客とのコミュニケーションを通じて、ニーズや課題をヒアリングします。
次いで、自社商材・サービスの利用によりどのように課題解決やニーズへの対応につながるかをイメージできるように助ける、見込み顧客の育成が重要な段階です。
顧客に関するデータ管理を行ったり、問い合わせに対してスピーディーに対応したりします。
業務内容は、各企業や個々の状況によって異なることが一般的です。
電話営業
訪問営業同様、従来より用いられている営業手法は電話営業(テレアポ)です。
一般的に、取引履歴がない企業や個人に直接電話をかけ、新規顧客を開拓します。
良い手応えが感じられれば、商材・サービスに関する資料を送付したり、訪問営業のアポイントを取り付けたりするのが主な目的です。
外回りをする訪問営業とは、営業活動する場所やアプローチ数が大きな違いとなっています。
内勤で次々とアプローチできる電話営業は、低コストで時間効率が良い営業手法です。
ただし、対面ではないため、電話を切られたりクレームをいわれたりする確率も高いことを覚えておきましょう。
アウトバウンド営業
アウトバウンド営業とは、企業側が積極的に顧客獲得に向けて行う営業活動全般を指します。
企業や業界により若干意味が異なる場合があるため注意しましょう。
訪問営業や電話営業なども含まれるケースが一般的です。
ダイレクトメールやテレビCMなども含まれます。
アウトバウンド営業は、営業する相手を企業側が選べるメリットがあるため、より高額な商材・サービスを購入してくれそうな相手に絞って営業するケースも珍しくありません。
反対に、可能な限り手あたり次第、幅広い層にアプローチすれば知名度アップにつながります。
自社の目的にしたがって、手法やターゲット層を決めることが可能です。
【訪問営業とは】訪問営業で成果を出すための事前準備
訪問営業では、事前の準備が成果を大きく左右します。
顧客の情報を把握せずに訪問すると、的外れな提案となり信頼を得にくくなります。
訪問前には、相手の課題やニーズを把握するためのリサーチや、分かりやすい営業資料の用意が欠かせません。
また、当日の商談をスムーズに進めるためには、話の流れや想定される質問への回答を準備しておくことも重要です。
ここからは、訪問営業に必要な準備項目を解説します。
事前リサーチ
「なぜ、この商品やサービスをあなたにおすすめしたいのか」としっかり伝えることで、説得力が生まれます。
誰にでも同じ内容の商談をするのではなく、商談する相手に合わせた内容は誠意が伝わりやすくなるため効果的です。
そのため、相手のことを事前にしっかり調査してから訪問するようにしましょう。
「自分たちのことをこんなに調べてくれている」「その上で勧めてくれている」のは、相手にとって大きな魅力です。
ヒアリングの質は、事前の仮説立てが大きく影響します。
ヒアリング目的で訪問する際にも、事前リサーチは欠かさないようにしましょう。
事前にしっかりとリサーチをしておけば、お客様によりよい提案ができるようなヒアリングができます。
営業資料作成
商談の際には営業資料も必要ですが、何が書かれているのかはっきり理解できない資料を用意しても逆効果になります。
難しい専門用語ばかりが並んでいたり、文字が小さ過ぎたりする資料は、誰が見ても分かりやすい資料とはいえません。
実例や実績などもきちんと記載し、整ったデザインにするなど、視覚的に分かりやすいプレゼン資料を作成しましょう。
また、営業する相手が誰なのかを明確にした上で、その人が商品やサービスの利用で得られるメリットや、利益にはどのようなものがあるかを伝えられるようにしてください。
営業資料は、営業職が説明する内容の意味が分からなかったときや後から考え直すとき、上司に伝えるときなどに使用する重要な書類です。
その点を念頭に置いて再度確認しておきましょう。
話す流れの確認
スムーズに商談を進めるためには、相手に「自分はできる営業職だ」と印象づけることが大切です。
もし、話す順番がバラバラで、何を話しているのかが分からなければ最後まで聞いてもらえません。
相手と打ち解けるための「起」・相手の要望を聞き出すための「承」・提案して商談を始める「転」・最終確認「結」のように、起承転結がしっかりした話し方をします。
ただし長々と話すと、結局何を伝えたかったのかが分かりにくくなってしまうため、重要なポイントが何か分かるように短くまとめましょう。
特に印象づけたい言葉を何度か繰り返し使うと、要点が伝わりやすくなります。
注意点として、商談を成功させたくて焦り過ぎると、相手に警戒心を与えてしまうことになりかねません。
落ち着いた姿勢を見せることも大切です。
想定できる反論があれば、それに対する準備までしておくとよりスムーズに商談が進みます。
相手を飽きさせないよう、話が盛り上がる努力をしてください。
身だしなみを完璧にする
特に、初めて訪問営業にいくときは身だしなみを完璧にしましょう。
初対面の人に好印象を抱くかそうでないかは、見た目が大きく影響します。
「きちんとスーツを着ていない」「ワイシャツがヨレヨレ」「寝ぐせが付いている」「口臭が気になる」など、身だしなみが乱れていると相手に不快感を与えるのは当然です。
極端な場合、話を聞きたい気持ちにならないどころか「近寄らないでほしい」「もう会いたくない」と思われてしまう可能性もあります。
身だしなみは社会人としての最低限のマナーです。
商談に行くときだけでなく、普段から意識しておきましょう。
【訪問営業とは】訪問営業に関する法規制
どの業界・業種でも、業務を遂行するにあたって関係する法律をきちんと把握しておかなければなりません。
訪問営業の場合は、自社のブランドイメージのみならず、顧客との信頼関係にも大きく影響するため十分注意を払いましょう。
関係する法律に関する知識は、必須であり、重要問題との認識を持つ必要があります。
主な3つの法規制を確認しておきましょう。
クーリングオフ
訪問営業の際に、顧客に説明する必要がある法規制のひとつはクーリングオフ制度です。
クーリングオフ制度とは、契約締結後8日以内であれば、顧客は無条件で契約解除または申し込み撤回を請求できる制度を指します。
訪問営業の顧客が個人の場合に適用される制度で、事業者・企業が顧客の場合は適用されません。
また、契約または申し込みした商材・サービスが消耗品だったり、現金3,000円未満だったりする場合も適用外です。
営業職は、販売する商材・サービスがクーリングオフの対象かどうかを明確に説明する責任があります。
クーリングオフ制度の起点となる日も、誤解のないよう確認しましょう。
特定商取引法
訪問営業は、個人を対象として行う場合は特定商取引法の規制対象です。
飛び込み営業かアポイントメントセールスかは関係ありません。
特定商取引法で定められているルールには、氏名の明示・再勧誘の禁止・書面交付・禁止事項がはっきりと定められています。
企業名や自分の名前だけでなく、営業目的・商材の内容などを誤解されないよう正確かつ明確に伝えることが重要です。
相手が営業を受ける意思がないことが明らかでも強引に説明を始める場合は、特定商取引法に抵触するため相手の声にきちんと耳を傾けましょう。
クーリングオフ制度の適用対象にもかかわらず、解約できないかのような印象を与えることも禁止事項に含まれています。
表現や口調に十分注意しましょう。
不退去罪
相手の自宅や企業を訪ねる訪問営業をする際は、不退去罪に関する予備知識も蓄えておきましょう。
不退去罪とは、帰るよう要求されたにもかかわらず退去しなかった場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が課される犯罪です。
営業を断られ帰るよう求められた場合、たとえ熱意を込めて仕事を全うしていると主張しても、他人の住居・建造物に居座っていると見られかねません。
場合によっては、不退去罪として通報される結果になります。
企業の信用は失墜してしまうだけでなく、今後の営業活動にも大きな影響を及ぼす可能性があることを忘れないようにしましょう。
営業の成果を求めるあまり、強引な印象を与えることがないよう注意が必要です。
まとめ
訪問営業は、顧客と直接対面することで信頼関係を築きやすく、商品の魅力を伝えやすい営業手法です。
しかし、効率面や働き方の変化から、オンライン営業やインサイドセールスなど他の手法と組み合わせる必要があります。
成果を出すためには、事前準備や心構え、継続的な訪問による関係構築が欠かせません。
もし訪問営業に不安を感じたり、営業スキルを活かした転職を考えているなら、アゲルキャリアの転職支援を利用するのもおすすめです。
経験豊富なエージェントが、あなたに合ったキャリアプランを一緒に考えます。
この機会にぜひチェックしてみてください。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!