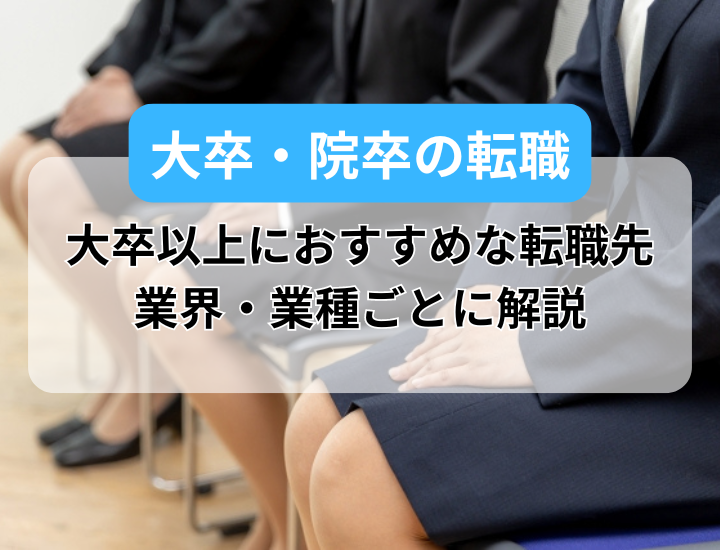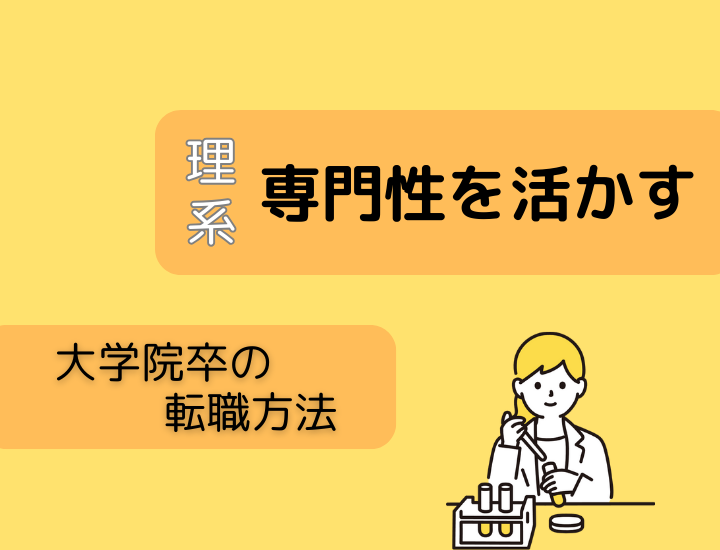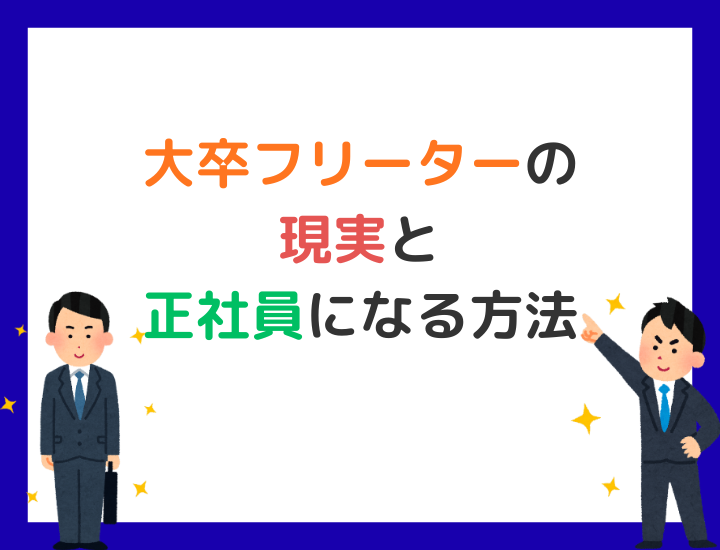
大卒フリーターの現実と正社員になる方法|割合・理由・就活のコツまで徹底解説
はじめに
大学を卒業したものの何らかの理由で就職に至らず、フリーターになる人も少なくありません。
大卒でフリーターとなった場合でも、正社員としての就職は十分に可能です。
ただし、現状を正しく把握し、自分に合った就職方法を知ることが重要です。
大卒フリーターがどのくらいの割合で存在し、社会的にどのように見られているのかを理解することで、今後の選択肢が明確になるでしょう。
この記事では、大卒フリーターの実態と就職活動における効果的なステップを整理し、確実に正社員への道を歩むための情報を提供します。
大卒フリーターの割合について
大卒フリーターがどの程度いるのかを知ることで、自分が少数派なのかどうかが明確になります。
ここでは、大卒でフリーターになる人の割合や背景を詳しく見ていきましょう。
大卒フリーターは全体の約2割
大学を卒業した若者のうち、一定数が正社員ではなくフリーターとしての道を選んでいます。
労働政策研究・研修機構の調査によれば、首都圏・中京圏・近畿圏の三大都市圏において、卒業後しばらくフリーターを経験した大卒者は、調査対象者全体の約2割に達していました。
学歴別に見ても決して少数ではなく、卒業から就職までの猶予期間や初期の就職活動がうまくいかなかったケースなどで、非正規の仕事を選ぶ事例が一定数見られます。
また、就業構造の変化や個人の価値観の多様化も背景にあり、フリーターという選択が必ずしも例外的とは言えない状況になりつつあります。
今後のキャリア形成を考えるうえで、2割という数字は決して無視できるものではありません。
出典:労働政策研究・研修機構|大都市の若者の就業行動と意識の変容
年齢が上がるとさらに減少していく傾向がある
大卒後にフリーターとして働く人の割合は、年齢の上昇とともに次第に減少する傾向があります。
フリーターの割合は20代前半に高く見られますが、30代に入ると著しく減少していきます。
背景に挙げられるのは、長期間にわたって非正規雇用を続けることへのリスク意識の高まりや、安定収入の必要性、周囲との比較意識です。
とくに30歳を超えると、転職市場では「第二新卒」としての扱いが難しくなり、正社員就職へのハードルが一段と高くなるため、20代のうちに就職活動を本格化させる人が増えていきます。
年齢と就業形態の関係を把握することで、適切なタイミングでのキャリア選択が可能になります。
社会全体からのイメージや立ち位置を理解する
社会的に見たフリーターの立ち位置は、正社員と比べると不安定とみなされる傾向があります。
とくに大卒であるにもかかわらず非正規で働いている場合、「なぜ就職しなかったのか」という目で見られる場面も少なくありません。
企業の人事担当者は、フリーター期間が長いほど採用時に懸念を抱くことがあります。
キャリア形成の空白期間が、スキル不足や職務遂行能力への不安と結びつくためです。
ただし、フリーターであること自体が即マイナスになるわけではなく、明確な理由や前向きな姿勢があれば十分に評価されます。
高学歴でも珍しくないケースが増えている
一部の高学歴層でも、卒業後にフリーターになるケースがあります。
たとえば、旧帝大や難関私立大学を卒業しても、自分の希望に合う仕事を見つけられなかった結果、アルバイトを選ぶ人もいます。
背景に挙げられるのは「やりたい仕事に出会えない」「理想の条件でなければ働きたくない」といった意識の高さです。
また、近年ではSNSやメディアでも、大卒フリーターという立場を公表する若者が増えており、情報としても身近な存在となっています。
高学歴であってもフリーターになること自体は、決して例外的な状況ではなくなりつつあります。
今後のキャリア設計に重要な基礎データとなる
現在の立ち位置を明確にするには、客観的な統計や社会的な見方を基にした自己評価が不可欠です。
大卒でフリーターとなった場合、自分がどの層に属しているのか、今後どのようなリスクやチャンスがあるのかを把握しておくことは、キャリアの方向性を定めるうえで大きな指針になります。
たとえば、長くアルバイトを続けたリスクに挙げられるのは、スキルの獲得や収入の伸び悩みに直面することです。
一方で、早期に就職活動を始めれば、新卒同様の扱いを受けられる可能性も残されています。
大卒でフリーターになる5つの理由
大学を卒業してから正社員にならず、フリーターとして働く理由は一つではありません。
就職活動に関する事情や個人の価値観、心理的な背景が影響している場合もあります。
以下では、大卒フリーターに多く見られる5つの理由を具体的に見ていきましょう。
- 就職活動をしなかった・避けた
- 内定をもらえなかった・辞退した
- 早期退職してフリーターになった
- 夢や目標のために選んだ
- 就活が心理的に負担で行動できなかった
就職活動をしなかった・避けた
大学生活の中で就職活動を意識せず過ごした場合、卒業後に明確な進路が定まらず、結果的にアルバイトを選ぶことがあります。
とくにコロナ禍以降は、インターンや説明会の中止も重なり、企業情報を得られないまま卒業を迎える人も増加傾向にありました。
また「就職は後回しでも良い」という考えや、「何となく」でアルバイトを続けてしまうケースもあります。
大都市圏を中心に一定の割合で見受けられる傾向であり、就活を避けたことが必ずしも珍しい行動ではないといえます。
内定をもらえなかった・辞退した
努力を重ねても内定が得られなかった場合、やむを得ずフリーターとなる人がいます。
また、一度は内定を得たものの「希望する職種と違った」「企業風土が合わなかった」といった理由から辞退を選ぶことも少なくありません。
とくに近年は「就職先のミスマッチ」を避けたいという意識が強く、自分に合わないと感じた場合に決断を先送りする傾向も見られます。
結果、アルバイトなど非正規の働き方でつなぐことになり、結果的にフリーター状態が長引いてしまうケースが発生するのです。
早期退職してフリーターになった
一度正社員として就職したものの早期に退職してしまい、再就職せずにアルバイトへと移行する例もあります。
大都市の若者の就業行動に関する調査では、職場環境によるミスマッチや過重労働、メンタル面の不調により、入社後1年以内に退職する割合が一定数を保っています。
結果、正社員で働くことへの不信感や不安を抱くようになり、比較的自由度の高いフリーターを選択肢とする人が増えているのです。
再就職に踏み切るまでの猶予期間として捉えているケースもあり、個人のペースで今後のキャリアを見直す傾向も見られます。
夢や目標のために選んだ
特定の目標や夢を追いかける過程で、フリーターを選ぶ人も少なくありません。
たとえば、音楽活動や芸術・クリエイティブ分野での挑戦を続けるため、時間や柔軟性を確保できるアルバイトという働き方を意図的に選んでいるケースがあります。
また、起業準備や留学資金の確保といった目的意識が明確な場合、就職を一時的に後回しにする判断も合理的といえます。
一見リスクに見える選択かもしれませんが、本人の中では計画的なキャリア戦略の一部となっていることも多いでしょう。
就活が心理的に負担で行動できなかった
就職活動そのものが精神的に重荷となり、行動に踏み切れなかったケースもあります。
コミュニケーションに苦手意識がある人や自己肯定感が低い人にとって、エントリーや面接への不安が大きな障壁になります。
自己肯定感が低い若者ほど就活の進行が遅れる傾向もあり、結果としてアルバイトを選ぶことで安心感を得ようとする行動が見られるのです。
心理的な背景を抱える場合、自力での就職活動が困難になりやすいため、外部のサポートや専門家の介入が重要になります。
大卒フリーターの5つのメリット
正社員ではなくフリーターとして働くことには、一定のメリットも存在します。
ここでは、大卒フリーターという立場で得られる以下のメリットについて深掘りしましょう。
- 自由な時間が多く確保できる
- 正社員より精神的に気楽に働ける
- 責任が軽くプレッシャーが少ない
- やりたいことに挑戦しやすい
- 生活スタイルを自分でコントロールできる
自由な時間が多く確保できる
非正規で働くことで勤務時間をある程度コントロールできるため、自己投資や趣味の時間を確保しやすくなります。
大学卒業後の若年層にとって、柔軟なスケジュールは自分探しや新しい分野への挑戦にもつながります。
正社員と異なり、残業や休日出勤が少ない環境を選びやすいため、ライフスタイル重視の働き方としてメリットを感じる人もいるでしょう。
また、時間に余裕があることで、資格取得や就職活動の準備にも取り組みやすくなるというメリットがあります。
正社員より精神的に気楽に働ける
フリーターとして働くことにより、職場での過度なストレスや上下関係の煩わしさから解放されると感じる人もいます。
職場での責任や成果への圧力が少ないため、メンタルヘルスの安定を重視する人にとっては魅力的です。
とくに若年層では、正社員の働き方に対する不安や拒否感を持つケースもあり、自由度の高さや環境への適応のしやすさが心理的な安定につながると考えられています。
就労そのものが苦にならないという感覚を維持できる点が、働き続けるうえでの安心材料となることもあります。
責任が軽くプレッシャーが少ない
正社員とは異なり、長期的なプロジェクトの責任を担う機会が少なく、日々の業務に集中できるのがフリーターの特徴です。
短時間勤務や限定された業務内容により、仕事への精神的負荷を軽減できるという点も挙げられます。
とくに初めて社会に出る人や人間関係に不安を感じている人にとって、責任の範囲が明確な働き方は安心感を得る要因になります。
社会経験を積むうえで、ワンクッションとして機能する働き方でもあります。
やりたいことに挑戦しやすい
勤務時間や収入の調整が可能なフリーターは、自分の時間を活かして新たな分野へ挑戦しやすい立場です。
とくに以下のような目的を持った人にとって、フリーターという働き方は柔軟な選択肢となり得ます。
- 起業準備や副業の立ち上げ
- 専門学校やスクールへの通学
- アーティスト・クリエイター活動
- 資格取得や国家試験への勉強
- 海外留学や語学学習の資金準備
やりたいことを実現するための「土台」として、あえてフリーターを選ぶ人も存在します。
生活スタイルを自分でコントロールできる
フリーターは勤務日数や時間帯を選択できるため、生活リズムを自分で設計する自由があります。
朝型・夜型などのライフサイクルに合わせた働き方を実現できる点も、正社員にはないメリットです。
また、通勤時間や職場の距離を優先して仕事を選べるため、生活全体の満足度にもつながりやすくなります。
生活と仕事のバランスを重視する人にとって、柔軟なシフト制や短期勤務などの制度は強い味方です。
自己管理ができる人にとっては、ストレスを最小限に抑えた働き方として機能することがあります。
大卒フリーターの5つのデメリット
フリーターには自由な面もありますが、長期的に見たときには不利な点も多く存在します。
以下では、大卒フリーターとして働き続けた場合に直面しやすいデメリットを整理していきます。
- 正社員と収入格差が広がりやすい
- キャリア形成やスキル習得が遅れる
- 社会的信用が得にくい
- 年齢が上がると就職が難しくなる
- 将来のライフプランが立てづらい
正社員と収入格差が広がりやすい
大卒フリーターと正社員の間では、賃金面での格差が年々拡大しています。
初任給では大きな差が見られない場合でも、昇給やボーナス、福利厚生といった継続的な収入の差が積み重なることで、長期的な年収の差は顕著になるでしょう。
労働政策研究・研修機構の調査でも、非正規雇用者は年収300万円未満の層が多数を占めており、年齢とともにギャップはさらに拡大する傾向があります。
とくに30代以降では、年収面での大きな差が資産形成や生活レベルに直結するため、収入面での将来不安は避けられません。
出典:労働政策研究・研修機構|大都市の若者の就業行動と意識の変容
キャリア形成やスキル習得が遅れる
フリーターとして働く環境では業務内容が限定的であることが多く、キャリアアップにつながるスキルや経験を積みにくいという課題があります。
正社員のように長期的な目標や人材育成制度が整っていないため、自己成長の機会が限られがちです。
たとえば、リーダーシップやマネジメント経験など、転職市場で評価されやすい能力を獲得するには不利な立場にあります。
フリーターの期間が長くなると「何ができるのか」が明確に示せないまま就職活動を迎えることになり、職種選択の幅も狭まってしまいます。
社会的信用が得にくい
雇用形態による社会的評価の違いから、フリーターは正社員と比べて信用面でのハンディを背負いやすくなります。
とくに、ローンの審査や住宅契約などで不利になるケースが多く、安定した収入がないことが主な要因とされています。
以下は、雇用形態による社会的信用の差を比較した一覧です。
| 項目 | 正社員 | フリーター |
|---|---|---|
| クレジットカード審査 | 通りやすい | 審査に通らないことが多い |
| 住宅ローンの借入 | 審査対象として扱われる | ほとんどが対象外 |
| 賃貸契約時の信頼度 | 保証人なしでも契約可能な例あり | 保証人が必要な場合が多い |
| 社会的印象 | 安定していると見なされる | 生活に不安があると思われやすい |
年齢が上がると就職が難しくなる
若年層のうちはポテンシャル重視で採用される可能性がありますが、年齢が上がるにつれてその傾向は薄れていきます。
とくにフリーター歴が長期化すると、「なぜ正社員にならなかったのか」といった採用側の懸念が強まるため、就職活動が一層厳しくなります。
企業側も年齢に応じたスキルや経験を期待する傾向にあるため、30歳を超えると未経験採用枠の対象外とされるケースも増えるでしょう。
将来のライフプランが立てづらい
不安定な収入や将来的な雇用継続の見通しが立たないため、結婚や子育て、住宅購入といったライフイベントの実現が難しくなります。
収入の変動が大きいことで生活設計が立てにくく、日々の支出を抑えることに意識が向いてしまいがちです。
また、年金や社会保険の加入状況にも差が生じるため、老後の備えにも不安が残ります。
安定した人生設計を望むのであれば、早期に正社員としての基盤を整えることが大きな意味を持ちます。
大卒フリーターの悲惨な末路を避けるためにすべきこと
フリーターとして働く状態を長期間続けることで、将来の就職や生活に影響を及ぼすリスクが高まります。
ここからは、大卒フリーターが悲惨な末路を回避するために意識すべき行動をまとめます。
- できるだけ早く就活を始める
- 年齢が若いうちに正社員を目指す
- 長期フリーターのリスクを理解する
- 就職先の選択肢を広げて考える
- 一人で悩まず専門家に相談する
できるだけ早く就活を始める
卒業後の空白期間が長くなるほど、就職活動は不利になります。
就職支援の現場でも、卒業後3年以内を「新卒扱い」できるラストチャンスと捉えるケースが多く、時間的な猶予には限りがあります。
採用側も若年層にはポテンシャルを求める傾向があるため、早期の就職活動開始は大きな武器になるでしょう。
準備不足で自信がない場合でも、まずは動き出すことが次の選択肢を広げるポイントです。
年齢が若いうちに正社員を目指す
年齢が若いほど、未経験でも正社員採用される可能性が高まります。
大卒後すぐであれば職歴がなくても教育前提での採用が期待できますが、時間が経過するにつれて「経験者優遇」へとシフトしていきます。
とくに20代前半は、ポテンシャル採用や育成枠の対象として最も評価されやすいため、就活スタートのタイミングとしては非常に有利です。
先延ばしをすればするほど、チャンスは狭まっていきます。
長期フリーターのリスクを理解する
非正規雇用の期間が長引くほど、正社員就職の難易度は上昇していきます。
以下は、長期間フリーターを続けた場合に直面しやすい課題の一例です。
- 応募時に空白期間の説明が求められる
- 正社員求人の応募条件を満たしにくくなる
- 同年代との収入格差が顕著になる
- 職務経験のなさからスキル不足と判断される
- 社会的信用が低く、生活面で不利になる
上記のリスクを把握することで、現状維持のままでは危険であるという実感が持てるようになります。
就職先の選択肢を広げて考える
「やりたい仕事」や「理想の職場」だけに絞って就職活動を進めると、選択肢が狭まり、内定を得にくくなります。
とくに初めての正社員就職では、業界や職種にこだわりすぎず、自分に合う可能性のある仕事の幅を広げて考えることが有効です。
職場での経験を通じて、自身の適性を見極めていく方法もあります。
まずは「社会人として働き始める」ことを最優先にした柔軟な視点が重要です。
一人で悩まず専門家に相談する
就職活動において「何から始めればいいかわからない」「自信が持てない」と感じる場面は少なくありません。
フリーターや既卒の支援実績がある、就職支援サービスの活用が効果的です。
なかでも「アゲルキャリア」は20代のフリーターや既卒者を対象に、個別面談を通じて内定獲得までを一貫して支援してくれるサービスです。
専任エージェントが利用者の状況に合わせて求人を提案してくれるため、自己分析から企業選び、面接対策まで一人で抱え込まずに進められます。
また、最短1週間での内定獲得を目指せる体制が整っている点も、大卒フリーターにとっては大きな魅力です。
時間的猶予が限られる状況でも、安心して頼れるサポートを受けられるため、不安の多い就職活動の強い味方となるはずです。
大卒フリーターがまずやるべき5つの行動
就職を目指すにあたって、「とにかく動かなければ」と焦る一方で、何から始めれば良いのかわからないという声も少なくありません。
ここでは、大卒フリーターが正社員を目指すうえで着手すべき5つの基本的な行動を紹介します。
- 自己分析で自分の強みを把握する
- 企業研究で応募先の候補を見つける
- 履歴書や職務経歴書を準備する
- 未経験歓迎の職種をリストアップする
- 就職エージェントに相談して任せる
自己分析で自分の強みを把握する
自己分析は、どの業種・職種に向いているのかを判断するための基礎となります。
自分では気づいていない強みや価値観を可視化することで、職種選びや自己PRの軸が明確になります。
アルバイト経験や、大学生活の中で得た経験を振り返ることから始めましょう。
とくに「どんな環境で力を発揮できるか」「どんな課題にやりがいを感じたか」を掘り下げて考えることが重要です。
企業研究で応募先の候補を見つける
企業研究は「なんとなくの応募」から抜け出し、自分に合った会社を見つけるために欠かせない工程です。
とくに未経験者の場合、社風や教育体制、入社後のキャリアパスなどを事前に把握しておくことでミスマッチを避けやすくなります。
企業のホームページや口コミサイト、採用ページなどから情報を収集し、比較・検討を進めましょう。
また、気になる企業が複数ある場合は、一覧化して比較するのも効果的です。
履歴書や職務経歴書を準備する
履歴書や職務経歴書などの書類は、面接以前に自身をアピールする最初の「顔」となります。
書類選考の通過率を高めるためには、内容だけでなく見やすさや構成にも配慮が必要です。
履歴書では志望動機と自己PRを明確に伝えることが重要であり、職務経歴書ではアルバイト経験やインターンで培ったスキルを具体的に記載しましょう。
正社員経験がない場合でも、工夫次第で十分に評価される書類を作成できます。
未経験歓迎の職種をリストアップする
最初の就職では経験を問われない職種を中心に検討することが現実的です。
とくに以下のような職種は、未経験からでもチャレンジしやすく、正社員としてのキャリアを築きやすい傾向があります。
- 営業職
- 販売・接客職
- 事務職(一般・営業事務など)
- ITエンジニア(研修制度あり)
- 介護・福祉職(資格取得支援あり)
上記の職種は入社後の教育体制が整っている場合が多く、異業種からの転職者も多く存在しています。
就職エージェントに相談して任せる
自力での情報収集や企業選びに限界を感じたら、就職エージェントのサポートを受けるのも一つの選択肢です。
とくにフリーターや既卒に特化したエージェントであれば、応募書類の添削や面接対策、求人紹介まで包括的に支援してくれます。
| サポート内容 | 説明 |
|---|---|
| キャリアカウンセリング | 強みや希望を明確にし、就活の方向性を定める |
| 求人の提案 | 利用者の希望と適性に合う企業を紹介してもらえる |
| 書類添削・面接対策 | プロの目線で書類の完成度を高め、模擬面接も実施可能 |
| 内定後のフォロー | 条件交渉や入社準備などを一貫してサポート |
とくに「何をすればよいか分からない」「書類が苦手」「面接に不安がある」という場合は、フリーターや既卒者の就職支援に特化した「アゲルキャリア」の利用が効果的です。
専任のエージェントがマンツーマンでサポートしてくれるため、初めての就職活動でも安心して取り組めます。
大卒フリーターの履歴書と面接で押さえるポイント
就職活動では、書類と面接を通じて自分をどのように伝えるかが合否を大きく左右します。
ここでは、履歴書作成と面接対応で押さえておきたい実践的なポイントを紹介します。
フリーター期間を前向きに表現する
履歴書や面接でフリーター期間について問われた場合は「なぜその期間が生まれたのか」「何を得たのか」を前向きに伝えることが大切です。
たとえば、アルバイトでの接客経験から得た対人スキルや、資格取得のために使った時間など、目的を持って過ごしたことがアピールになります。
空白期間がある場合も、「就職に向けて準備していた」「方向性を定めるために自己分析を行っていた」といった姿勢を明確にすることで、採用担当者の印象は大きく変わります。
志望動機を明確に伝える
志望動機は、応募企業ごとに具体的に言語化しましょう。
汎用的な内容ではなく、「なぜその企業か」「なぜその職種か」といった軸を丁寧に掘り下げることが求められます。
企業の事業内容や理念に共感した理由、自分の経験との接点を盛り込むことで説得力が増します。
とくにフリーター歴がある場合、「今後は安定して働きたい」だけでは不十分です。
過去の経験を踏まえて「どのように貢献したいか」を伝える姿勢が重要です。
経験を活かし、御社の営業職として、お客様の課題に寄り添う提案を行いたいと考えています。
上記の例では、過去の経験と企業の職種を結び付けることで志望の根拠が明確になっています。
また「貢献したい」という未来志向の言葉が入っており、採用後のイメージを持ってもらいやすくなる構成になっています。
自己PRに具体的なエピソードを入れる
自己PRでは、単なる長所の羅列ではなく、行動の背景や成果を具体的に語る必要があります。
アルバイトや大学生活での経験から、課題を乗り越えたエピソードをピックアップすると、印象に残りやすくなります。
以下に、効果的な自己PRを構成する要素を整理しました。
- 長所や強み(例:粘り強さ、対人スキルなど)
- 長所や強みが発揮された具体的な場面
- 課題や困難に対して取った行動
- 結果どのような成果を得たか
- 入社後にどのように活かしたいか
一貫性と具体性を意識することで、採用側に「一緒に働く姿」がイメージされやすくなります。
質問の意図を理解して回答する
面接での質問は、回答そのもの以上に「どのように考えて答えているか」が見られています。
とくに「なぜ正社員ではなかったのか」「なぜ今から就職したいのか」といった質問では、防御的な態度を取るのではなく、前向きな姿勢で意欲を伝えることが大切です。
質問の裏にある意図をくみ取り、「採用してもすぐ辞めないか」「意欲は本物か」といった不安を払拭する回答が求められます。
緊張しやすい人は、事前によくある質問を整理しておくと安心です。
プロの模擬面接で練習しておく
実際の面接では、想定外の質問や緊張から言葉が詰まってしまうことがあります。
就職支援サービスなどが提供している、模擬面接を利用して対策をとりましょう。
第三者のフィードバックを受けることで、自分の話し方や表情のクセ、伝え方の改善点を客観的に把握できます。
とくにフリーター期間に関する質問や、志望動機の伝え方は練習しておくことで安心感が生まれ、本番で落ち着いて話せるようになります。
大卒フリーターにおすすめの仕事・就活方法
正社員を目指すうえで、「どの仕事を選べばいいのか」「自分に合った就活の進め方がわからない」と感じる人も多くいます。
ここでは、未経験からでも目指しやすく、将来的にキャリアアップにもつながりやすい職種と就職ルートを紹介します。
未経験OKの営業職や販売職を狙う
営業職や販売職は、業界を問わず未経験者の受け入れが比較的柔軟であるため、大卒フリーターにとって非常に現実的な選択肢です。
とくにコミュニケーション能力や柔軟な対応力が求められるため、アルバイト経験で培った接客スキルなども強みとして評価されやすくなります。
また、実績次第で昇給・昇格が見込める環境も整っているため、成長意欲のある人には魅力的なキャリアパスが用意されています。
介護・福祉など人材不足業界を検討する
高齢化が進行する日本社会では、介護・福祉業界の人手不足が深刻な課題となっています。
そのため、未経験からの正社員登用が積極的に行われており、働きながら資格取得を支援してくれる企業も多数存在します。
人と接する仕事が好きな人、やりがいを重視する人にとっては適性がある分野といえるでしょう。
また、実務経験と資格を積み重ねることで、施設長やケアマネジャーなどの専門職にもステップアップできる可能性があります。
工場や製造業の正社員登用制度を活用する
製造業や工場勤務も、大卒フリーターにとって現実的な選択肢のひとつです。
とくに派遣社員や契約社員からスタートして、一定期間の勤務後に正社員登用される制度を導入している企業も多く見られます。
専門的な資格がなくても始めやすい点、体を動かす作業を好む人に向いている点など、特性に応じた職場選びが可能です。
以下に、製造業で活用されている主な正社員登用制度をまとめました。
| 登用制度の種類 | 内容 |
|---|---|
| 紹介予定派遣 | 派遣期間終了後に正社員登用を前提とした就業スタイル |
| 登用前提の契約社員制度 | 最初は契約社員だが、一定の評価を経て正社員への道が開かれる |
| トライアル雇用制度 | 試用期間を経て、企業と本人双方の合意により正社員化される |
上記の制度を活用すれば、未経験でも職場に馴染みながら正社員への道を目指すことが可能です。
紹介予定派遣や契約社員から正社員を目指す
直接正社員での採用を狙うだけでなく「紹介予定派遣」や「契約社員スタート」というルートを経ることで、就職成功率を高める方法もあります。
実際の業務に携わりながら企業との相性や職務内容を確認できるため、ミスマッチを防ぐ効果があります。
また、一定期間働いた実績が評価材料になるため、正社員登用後も円滑な人間関係を築きやすい点がメリットです。
まずは働く環境に慣れ、徐々にステップアップしたい人に向いた就活戦略です。
専門性を磨ける資格取得も視野に入れる
就職活動と並行して、将来的に役立つ資格の取得を目指すのも有効な手段です。
とくに、以下のような分野は未経験者でも挑戦しやすく、正社員採用においても評価されやすくなっています。
- ITパスポート(IT業界)
- 宅地建物取引士(不動産業界)
- 介護職員初任者研修(介護業界)
- 日商簿記3級(事務・経理職)
- MOS(Microsoft Office Specialist)
上記の資格は独学や通信講座でも学習可能なものが多く、自己成長の証として履歴書でもアピールしやすいでしょう。
大卒フリーターに関するよくある質問
最後に、大卒フリーターによく寄せられる代表的な質問とその考え方を紹介します。
自分自身の状況と照らし合わせながら、就活の方向性を整理する手助けにしてください。
何歳までならフリーターでも問題ない?
一般的には、20代のうちであれば未経験採用の対象として受け入れられるケースが多く見られます。
とくに25歳以下であれば、新卒扱いに準じた採用枠で評価されやすい傾向があります。
一方で、30歳を超えると「即戦力」や「業務経験」が重視されやすくなり、未経験からの就職が難しくなるかもしれません。
したがって、年齢が若いうちに行動を起こすことが重要です。
就職市場における評価基準が年齢とともに変化するという事実は、早期決断の大きな根拠になります。
フリーターから正社員になれない人もいる?
正社員になれない人がいる一方で、多くのフリーターが未経験からでも就職を実現しています。
重要なのは「なぜ今まで正社員を選ばなかったのか」を自分なりに説明できることです。
また、就職活動においては、希望条件を厳しく設定しすぎると内定獲得が難しくなる傾向があります。
視野を広げ、未経験歓迎の職種や育成前提の企業を選択肢に加えることで、採用の可能性は大きく高まります。
就活のタイミングはいつ始めるべき?
「今すぐ」がもっとも適切なタイミングです。
空白期間が長くなるほど書類選考や面接で理由を求められる機会が増えるため、不利に働くかもしれません。
とくに卒業から3年以内は「既卒枠」での新卒採用に応募できる場合が多く、行動の早さが結果を左右します。
完璧な準備が整っていなくても、まずは求人情報を調べたり、相談窓口にアクセスするところから始めることが推奨されます。
フリーター歴が長いとどれくらい不利?
フリーターとしての期間が長引くと、企業側から「なぜ正社員を目指さなかったのか」「継続して働けるのか」といった点が懸念されやすくなります。
ただし、明確な理由や努力の跡を説明できる場合は、その印象を和らげることが可能です。
以下に、フリーター歴が長い人が面接で問われやすい懸念点をまとめました。
- 仕事に対する継続力があるか
- 企業風土に適応できるか
- チームで働く意識があるか
- 成長意欲を持っているか
上記の視点を自己PRや志望動機で事前にカバーしておくことが、就職成功のポイントになります。
就職エージェントは本当に無料?
就職エージェントのサービスは、基本的に利用者側の費用負担は発生しません。
企業からの紹介手数料で運営されているため、履歴書添削や面接練習、求人紹介などのサポートをすべて無料で受けられます。
安心して利用できるサービスかどうかを見極めるためには、実績や対応業種、担当者の対応などを比較することがポイントです。
複数登録して、相性の良いエージェントを見つける方法も効果的です。
まとめ
大卒フリーターという状況に、不安を感じている人は少なくありません。
しかし、現状を正しく理解し、就職活動に向けて一歩を踏み出すことで、正社員として働く未来は十分に実現可能です。
年齢や空白期間の影響はあるものの、若いうちの行動や情報収集が就職を成功に導くポイントになります。
自己分析や職種選び、書類準備といった基礎を着実に進め、必要に応じて就職エージェントの支援を受けることも有効です。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!