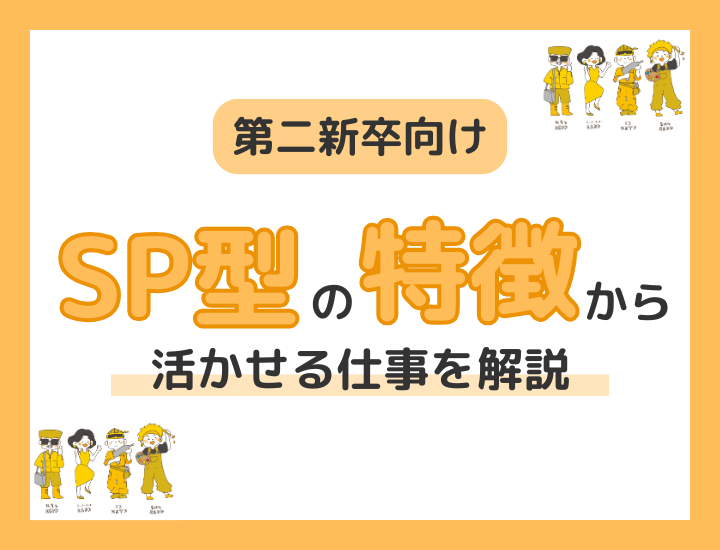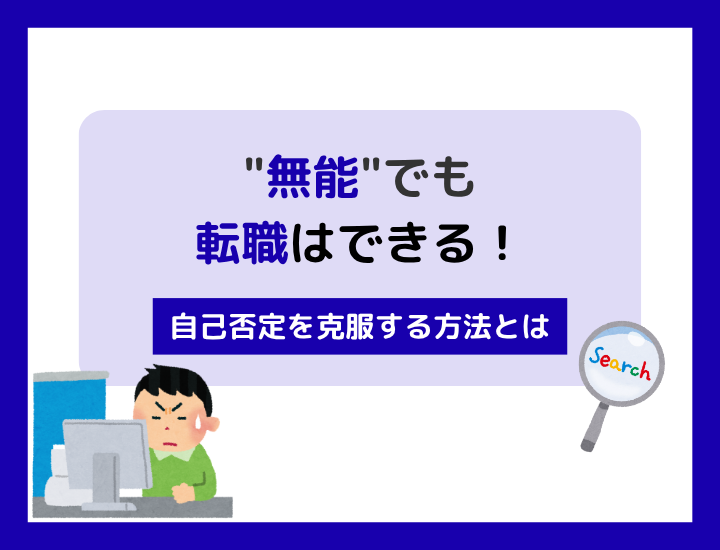
【転職】無能でも転職はできる!自己否定を克服する方法とは
はじめに
転職を考えるとき、「自分は無能だからうまくいかないのでは」と不安を抱える人は少なくありません。
特に、現職で評価が低かったり、上司や同僚から否定的な扱いを受けたりすると、自信を失い転職を諦めたくなることもあります。
しかし実際には、無能だと感じていることと転職の成否は必ずしも一致しません。
企業が求めるのは「過去の評価」ではなく「今後の可能性」であり、自分に合った環境や方法を選べば状況を大きく変えることができます。
この記事では、無能と感じてしまう背景や克服の方法、転職するためのポイントを解説します。
【転職】無能だから転職できないのか
「無能だから転職できない」と思い込んでしまう人は少なくありません。
しかし、採用の可否は個人の評価だけでなく、企業や市場のニーズによって大きく左右されます。
不採用になったからといって無能と決めつけるのは早計です。
ここからは、採用がどのように決まるのか、不採用が意味することは何かを整理していきます。
採用は転職市場のニーズで決まる
転職活動をしていると「自分の能力が低いから採用されない」と考えてしまいがちです。
しかし実際には、採用の可否は個人の優劣だけでなく、その時点での転職市場のニーズに大きく左右されます。
企業は常に同じ基準で採用しているわけではなく、人手不足の職種や新規事業の立ち上げなど、状況によって求める人材像は変化します。
たとえば、営業職を多く募集している時期であれば、経験が浅くても「人と関わることが好き」「話を聞くのが得意」といった強みを持つ人は採用されやすくなります。
逆に同じ人が事務職を希望した場合、企業側が「即戦力で高度なスキルを持つ人」を必要としていれば、不採用になることもあります。
これはその人が無能だからではなく、あくまで企業が求めている条件と合わなかっただけです。
つまり、不採用という結果は応募者の価値を否定するものではありません。
採用の判断は「能力があるか・ないか」ではなく、「その時点の企業ニーズと合致しているかどうか」で決まります。
だからこそ、自分の強みや経験を知り、それが評価されやすい業界や職種を見極めることが重要です。
不採用=無能ではない
転職活動を続けていると、不採用の通知が届くたびに「やはり自分は無能だからだ」と思い込んでしまうかもしれません。
しかし、不採用の理由は多岐にわたり、その多くは応募者の能力不足とは関係がありません。
まず、面接は限られた時間の中で判断されるため、緊張や焦りから本来の力を十分に出せないことがあります。
また、企業の事情によっても結果は変わります。
例えば、採用枠がわずかしかなく、応募者が多い場合には、優秀な人材であっても単純に人数の関係で落とされるかもしれません。
さらに重要なのは、企業が重視するポイントがそれぞれ異なるということです。
ある会社は即戦力を求めるため経験豊富な人を優先しますが、別の会社ではポテンシャルや人柄を重視して未経験者を歓迎する場合もあります。
不採用は「能力がないから」ではなく、「その会社の条件に合わなかっただけ」というケースが大半です。
不採用が続いたとしても「自分は無能だ」と断定する必要はありません。
むしろ、自分の強みが活かせる環境や企業を見極めるためのきっかけとして捉えることが大切です。
転職活動は企業との相性探しであり、一度の結果に過剰に落ち込むのではなく、自分に合った職場を探し続けることが、次のチャンスにつながります。
【転職】無能だと感じている人によくある特徴
自分を「無能だ」と感じてしまう人には、いくつか共通する傾向があります。
たとえば、仕事がうまく進められない、周囲と比べて劣っていると感じやすいなどです。
ただし、これらはあくまで特徴であり「無能」と決めつけられるものではありません。
大切なのは原因を正しく理解し、自分に合った改善策や働き方を見つけることです。
ここでは、よくある特徴を整理して紹介します。
コミュニケーションが苦手
職場で「無能」と感じてしまう人の中には、コミュニケーションの難しさを抱えているケースが多くあります。
上司や同僚に相談したいのにうまく言葉が出てこないこともあれば、報告や連絡が遅れて誤解を招いてしまうこともあります。
また、雑談が苦手でチームに溶け込みにくいと感じることもあり、その積み重ねが「自分は仕事ができないのでは」という不安につながります。
ただし、コミュニケーションが苦手だからといって無能と決めつける必要はありません。
話すことが得意でなくても、文章やメールで丁寧に伝える力を持っている人もいますし、相手の話をしっかり聞ける人は信頼を得やすい場面もあります。
重要なのは「口下手=仕事ができない」と短絡的に考えず、自分に合った伝え方や関わり方を探すことです。
たとえば、話す前に要点をメモにまとめる、口頭でのやり取りが苦手ならチャットやメールを積極的に活用するなど、工夫によって改善できる余地は十分にあります。
苦手意識を持つこと自体が悪いのではなく、その対処法を身につけることが大切なのです。
時間の管理ができない
仕事で「無能だ」と感じてしまう理由のひとつに、時間の管理が苦手であることが挙げられます。
たとえば、作業にかかる時間を見積もれず、いつも締め切りぎりぎりになってしまう人もいます。
また、優先順位をつけられずにあれこれ同時に手をつけてしまい、結果としてどのタスクも中途半端になってしまうケースもあります。
こうした状況が続くと、周囲から「だらしない」「仕事が遅い」と評価され、自分自身も「自分は無能なのでは」と思い込んでしまいがちです。
しかし、時間管理が苦手だからといって能力がないわけではありません。
実際には、スケジュールを細かく区切って作業する、タスク管理アプリを利用するなど、仕組みを整えることで改善できる問題です。
時間の感覚は訓練次第で身につけられるものであり、努力すれば着実に変えられる部分でもあります。
大切なのは、自分を「時間にルーズだから無能だ」と決めつけず、できる工夫を一つずつ試していくことです。
小さな改善を積み重ねることで、仕事への取り組み方は大きく変わり、自信を取り戻すきっかけにもつながるでしょう。
集団行動が苦手
「無能だ」と感じる人の中には、集団で行動することに苦手意識を持つケースがあります。
会議やグループワークで自分の意見を言えずに黙ってしまったり、周囲のペースに合わせることが難しく孤立感を抱いたりすることがあります。
さらに、雑談や飲み会といった職場の付き合いにうまくなじめないと「チームワークが取れない人」と見られてしまい、自信をなくしてしまうことも少なくありません。
しかし、大勢の場では発言が少なくても、一対一でのやり取りなら丁寧に対応できる人もいます。
また、グループ全体を引っ張るのは得意でなくても、陰で支える役割を果たすことで信頼を得ることもできます。
集団行動の苦手さは「能力の欠如」ではなく「向き不向きの違い」にすぎません。
もし集団でのやり取りに苦手意識を持つなら、自分が得意な関わり方を意識して選ぶことが大切です。
大きな会議で無理に発言するより、事前に資料を作って準備する、一対一のコミュニケーションを重視するなど、自分の強みを活かす方法があります。
集団行動が苦手でも工夫次第で十分に活躍できるのです。
こだわりが強い
「無能ではないか」と悩む人の中には、こだわりの強さが原因で周囲から誤解されてしまうケースがあります。
自分のやり方に固執して柔軟に対応できなかったり、細部に時間をかけすぎて全体の進行が遅れてしまったりすると、「協調性がない」「仕事が遅い」と評価されることもあります。
その結果、自分自身を責めてしまいがちです。
ただし、こだわりの強さは見方を変えれば集中力や探究心の表れでもあります。
たとえば、品質に妥協しない姿勢は製造業やデザイン業務などで大きな武器になりますし、細かいチェックが得意な人はチームの信頼を得やすい場面もあります。
重要なのは「すべての場面で同じこだわりを発揮する」のではなく、「どこで活かし、どこで引くか」を見極めることです。
こだわりを活かすためには、あらかじめ優先順位をつけて「ここだけは譲らない部分」と「妥協してもよい部分」を区別しておくと効果的です。
また、自分一人の判断ではなく周囲と話し合いながら調整することで、無駄な摩擦を防げます。
こだわりが強いことは欠点ではなく、適切な場で使えば大きな強みになるのです。
劣等感を感じやすい
仕事で「無能だ」と感じる人の多くは、他人と自分を比べることで強い劣等感を抱きやすい傾向があります。
同期が成果を上げているのを見ると「自分だけ取り残されている」と感じたり、上司に褒められている同僚と比べて「自分には価値がない」と思い込んでしまったりするのです。
この思考が積み重なると、実際の能力以上に自分を過小評価し、自信を失いやすくなります。
しかし、劣等感を持つことは必ずしも悪いことではありません。
適度な劣等感は努力の原動力となり、成長への意欲につながる場合もあります。
問題なのは、劣等感を「自分は無能だから仕方がない」と結論づけてしまうことです。
実際には、誰にでも得意・不得意はあり、周囲と比較しても意味がない場面が多いのです。
劣等感を軽減するためには、他人ではなく「昨日の自分」と比べる意識を持つことが効果的です。
また、小さな成功体験を積み重ねることで、自信を取り戻すことができます。
自分にとっての強みを見つけ出し、それを活かせる仕事や環境を選ぶことも大切です。
劣等感をきっかけに自分を深く理解できれば、それは長所に変わるでしょう。
継続する力がない
資格の勉強を始めても三日坊主で終わってしまうことがあったり、仕事でも新しい取り組みを続けられず途中で投げ出してしまったりする人もいます。
そうした経験が積み重なると、「自分は根気がない」「努力ができない」と思い込みやすくなり、自己評価を必要以上に下げてしまうのです。
多くの場合、続かない原因は本人の性格や能力ではなく、環境や方法が合っていないことにあります。
たとえば、目標が漠然としていると途中で意欲を失いやすくなりますし、習慣化の工夫がなければ行動が長続きしません。
逆に、小さな目標を設定して達成感を積み重ねたり、仲間と一緒に取り組んだりすれば、継続はずっと簡単になります。
継続力を高めるためには、意志の強さだけに頼らず、仕組みや環境を工夫することが大切です。
スケジュールを細かく区切る、日々の進捗を記録するなど、日々のやるべきことを詳細にすることで「自分は継続できない」という思い込みから脱却できるかもしれません。
ミスが多い
書類の誤字脱字や数字の入力間違い、確認不足による手戻りなどが続くと、周囲からの信頼を失ったように感じ、自信をなくしてしまいます。
また、自分でも「またやってしまった」と落ち込み、失敗を重ねるごとにさらにミスを招くという悪循環に陥ることもあります。
ミスが多い原因を振り返ると、単純な不注意や業務量の多さ、作業環境の問題が関係している場合があります。
改善策としては、チェックリストを用意して確認を徹底する、作業を小分けにして一つずつ確実にこなす、集中力が続く時間帯に重要なタスクを行うなどが効果的です。
ミスをなくすことだけに意識を向けるのではなく、「どうすれば防げるか」という仕組みを整えることが重要です。
工夫を重ねることで失敗は減り、同じ経験を通じて注意深さや改善力が身につけば、それはむしろ強みにもなります。
アドバイスや指摘が苦手
職場で「無能なのでは」と感じやすい人の中には、上司や同僚からのアドバイスや指摘を受け止めるのが苦手なタイプがいます。
注意されると必要以上に落ち込んでしまったり、指摘を防御的に受け止めて素直に聞けなかったりすることがあります。
その結果、成長の機会を逃し、「自分は仕事ができない」と感じる悪循環に陥ることも少なくありません。
しかし、多くの場合、失敗を恐れる気持ちが強かったり、過去の経験から「怒られる」と感じてしまう心理的な要因が背景にあります。
このような場合、指摘を「攻撃」ではなく「改善のための情報」と捉える視点を持つことが大切です。
改善のためには、指摘を受けたときにすぐ反論するのではなく、一度受け止めてから自分に必要な部分を改善する方法が有効です。
また、どう改善すべきか分からないときは率直に質問することで、学びのきっかけにもなります。
アドバイスを受け入れる姿勢を持てれば、周囲からの信頼も高まるはずです。
責任感がない
任された業務を途中で投げ出してしまったり、トラブルが起きた際に自分の責任を避けてしまったりすると、周囲から「頼りにならない」と見られてしまいます。
その結果、本人も「自分は役に立たない」と感じ、自己否定につながりやすいのです。
ただし、責任感がないとされる人の多くは、本当に無責任なのではなく「失敗が怖い」「自分に自信がない」ことが背景にあります。
自分がやってもうまくいかないのではと不安に思うため、積極的に行動できず、結果として責任を取らない態度に見えてしまいます。
改善のためには、いきなり大きな責任を負うのではなく、小さなタスクを着実にこなして成功体験を積み重ねることが有効です。
また、困ったときに一人で抱え込まず、上司や同僚に相談することで「責任を共有する」感覚を持つことも役立ちます。
責任感は性格ではなく経験の中で育まれます。
少しずつ行動を重ねていけば、「責任感がない」という評価を変えることは十分に可能です。
【転職】自分が無能だと感じる理由
「自分は無能かもしれない」と思ってしまう背景には、いくつかの共通するパターンがあります。
まず多いのが、必要以上に自分を責めてしまうことです。
小さな失敗でも「自分はやっぱりダメだ」と大きく捉えてしまい、実際の実力以上に自信を失ってしまうのです。
また、周囲と自分を比べることも原因になりやすいでしょう。
同期や同僚が成果を出していると、「自分だけ遅れている」と感じ、評価を過小に見積もってしまうことがあります。
さらに、職場環境の影響も大きく、上司の厳しい言葉や同僚との人間関係がうまくいかないことで、自分の価値を見失ってしまうこともあります。
実際には「無能」と感じる理由の多くは能力不足ではなく、考え方や環境によるものです。
なぜそう思ってしまうのかを整理するだけでも、気持ちが軽くなり、改善のきっかけにつながるかもしれません。
【転職】無能感を克服する方法
自分を無能だと感じる気持ちは、多くの場合「思い込み」によって強くなります。
その思いが積み重なると転職活動への自信を失い、挑戦する前から諦めてしまうことにつながります。
しかし、克服の方法を知り、少しずつ実践していくことで状況は変えられます。
ここからは、前向きに行動するための方法を紹介します。
計画を立てる
自分を無能だと感じやすいときほど、行動が思うように進まず悪循環に陥りがちです。
そんなときに役立つのが、あらかじめ計画を立てて取り組む方法です。
漠然と「頑張ろう」と思うだけでは成果が見えにくく、達成感を得られないまま終わってしまいます。
計画を立てる際には、大きな目標を小さなステップに分けることがポイントです。
たとえば「転職活動を進める」という大きな目標も、求人を探す、履歴書を更新する、1日1社応募する、といった小さな行動に分解すれば実行しやすくなります。
また、計画は完璧である必要はありません。
余裕を持たせてスケジュールを組むことで、予定通りに進まなかった場合でも気持ちが大きく揺らがなくなります。
計画は自分を縛るものではなく、行動を整理し前に進むための作業です。
小さな達成を積み重ねていくことで、自信を少しずつ取り戻すことができるでしょう。
自己分析をする
転職を考えるとき、多くの人が「自分には何もない」と感じて不安を抱えます。
しかし実際には、誰しもこれまでの経験や得意分野の中に強みを持っています。
それを明確にする方法が自己分析です。
自己分析では、過去の仕事や学びの中で「うまくいったこと」「人に褒められたこと」「楽しく取り組めたこと」を書き出していきましょう。
そうすることで、自分が成果を出しやすい状況や得意な行動パターンが見えてきます。
逆に苦手な分野を整理すれば、転職先で避けるべき職種や工夫すべき課題もはっきりします。
また、自分一人で考えるのが難しい場合は、転職エージェントを活用すると効果的です。
第三者の客観的な意見は、自分では気づけなかった強みに気づくきっかけになります。
自己分析は、無能感に振り回されず、自分に合った仕事を選ぶために必要です。
優先順位を決める
タスクを一度に抱え込むと、結局どれも中途半端になり、成果が見えにくくなります。
その結果、「自分は仕事ができない」と思い込みやすくなるのです。
この状況を避けるためには、優先順位をつけて行動することが大切です。
まず、緊急性と重要性を軸にタスクを整理しましょう。
すぐに対応すべきものは先に取り組み、重要だけれど期限が先のものは計画的に進める、といった区分けを行えば効率は改善します。
また、すべてを完璧にこなそうとせず、必要に応じて「やらないこと」を決めるのも有効です。
優先順位を明確にすれば、時間や労力を本当に必要な仕事に集中でき、無駄な消耗を防げます。
行動が整理されることで達成感も得やすくなり、無能感にとらわれにくくなります。
時間の管理をする
仕事に追われていると「いつも時間が足りない」「予定通りに終わらない」と感じやすく、それが無能感につながることがあります。
しかし、多くの場合は能力の問題ではなく、時間の使い方に工夫が足りないだけです。
時間を管理するためには、自分がどの作業にどれだけ時間を使っているかを把握することが大切です。
一日のスケジュールを細かく記録してみると、想像以上に無駄な時間があることに気づけます。
その上で、集中が必要な作業は午前中にまとめる、メール確認は時間を決めて行うなど、効率的な使い方を意識すると成果が出やすくなります。
また、ツールやアプリを活用してタスクを可視化するのも有効です。
やるべきことを一目で確認できるようにすれば、優先順位を誤ることが減り、気持ちにも余裕が生まれます。
時間を意識して動く習慣を身につけることで、「いつも遅れてしまう」という悪循環を断ち切り、無能感を軽くすることができるでしょう。
周りに相談する
一人で抱え込みすぎることも、無能と感じてしまう大きな要因です。
自分だけで解決しようとすると時間がかかり、思うように進まず「やっぱり自分はできない」と感じやすくなります。
その悪循環を断ち切るためには、早めに周りへ相談することが大切です。
相談することで、客観的な視点や解決策を得られるだけでなく、「一人ではない」という安心感も得られます。
上司や同僚への報告・連絡・相談、いわゆる「報連相」を意識するだけでも、業務の進めやすさは大きく変わります。
また、転職活動においても転職エージェントやキャリアアドバイザーに相談すれば、自分では気づけなかった強みや改善点を知ることができます。
大切なのは、「相談=迷惑をかける」ではないという考え方です。
むしろ適切に相談できる人は信頼されやすく、仕事を円滑に進める力として評価されます。
周りに助けを求めることは弱さではなく、前に進むための行動だと考えていきましょう。
【転職】無能だと感じやすい人におすすめの仕事
「自分にはできる仕事がない」と思い込んでしまっても、実際には数多くの仕事があります。
ここでは、比較的挑戦しやすく、特別な実績や高度なスキルがなくても始められる仕事を紹介します。
自分の特性や環境に合いそうなものを確認してみてください。
同じ作業を繰り返すことが中心で、集中力があれば黙々と働けます。
派遣や契約社員の募集も多く、挑戦しやすい仕事です。
2. タクシー運転手
乗客を目的地に届けるシンプルな仕事内容。
基本的に一人で完結するため、人間関係のストレスを避けやすい職種です。
3. トラック運転手
荷物の運搬が主な業務で、運転中は一人で過ごせます。
規則正しいルート配送など、ルーチンを好む人に向いています。
4. フードデリバリー配達員
仕事内容が単純で、働く場所や時間を自分で選べる自由度の高さが魅力です。
副業として始める人も多い仕事です。
5. 介護職
ルーチンワークが中心で、常に人材不足のため就職しやすい分野です。
人の役に立ちたい人に向いています。
6. 清掃員
一人で作業できる場合が多く、人間関係の煩わしさが少ない職種です。
頭を使うより体を動かすことが好きな人におすすめです。
7. 警備員
特別なスキルが不要で、未経験者やシニア層も活躍しています。
決まった手順を守る仕事なので安心して取り組めるでしょう。
8. 接客業
業務の流れが決まっており、慣れてしまえばルーチンで働けます。
人との会話が苦にならない人には適しています。
9. 自販機補充・ルート配送
ルーチンワーク中心で、一人で進める時間も多い職種です。
学歴や経験が問われにくい点も特徴です。
10. 建設・土木作業員
体力があれば始めやすい職種です。
人手不足のため採用されやすく、未経験者でも挑戦できます。
11. 塗装職人
現場ごとに内容は変わりますが、需要が高く安定している職種です。
体で覚えるタイプの仕事なので、経験がなくても始めやすいです。
12. Webライター
パソコンがあれば始められる仕事で、フリーランスなら自由度が高い働き方が可能です。
文章を書くことが好きな人に向いています。
13. プログラマー
専門的なスキルは必要ですが、独学やスクールで学びながら未経験から挑戦できる仕事です。
フリーランスとして自由に働く道もあります。
「無能だからできる仕事はない」と思い込む必要はありません。
自分に合った環境を選べば、安心して働ける職場は必ず見つかります。
【転職】無能だと感じているからこそ気を付けたい転職の落とし穴
無能だと感じながら転職を進めると、不安や焦りから冷静な判断を見失いやすくなります。
その結果、合わない職場を選んで再び苦しむことも。
ここでは、特に注意すべき転職の落とし穴と、避けるためのポイントを解説します。
焦って企業選びをしない
「今の職場から早く抜け出したい」という気持ちが強すぎると、十分に調べないまま次の仕事を決めてしまうことがあります。
しかし、このような焦りは転職の大きな失敗につながるかもしれません。
仕事内容や待遇、人間関係を確認せずに入社すると、ブラック企業や自分に合わない職場を選んでしまい、短期間で再び転職を考えることも。
焦りを抑えるためには、まず転職の目的を明確にしましょう。
「年収を上げたい」「人間関係のストレスを減らしたい」など、優先順位を決めてから企業を探すと判断がぶれにくくなります。
また、求人票の条件だけでなく、口コミサイトやOB訪問などで社内の雰囲気を調べるのも効果的です。
焦って決めてしまうより、少し時間をかけて慎重に選ぶことで、入社後の後悔を防ぐことができます。
転職理由はポジティブに変換する
面接で必ず聞かれる質問の一つが「転職理由」です。
ここで「前の職場で評価されなかった」「上司と合わなかった」といったネガティブな答え方をしてしまうと、面接官に「また同じ理由で辞めるのでは」と不安を与えてしまいます。
その結果、採用に不利になることも少なくありません。
重要なのは、ネガティブな理由をそのまま伝えるのではなく、前向きな表現に変えることです。
たとえば「上司と合わなかった」という場合も、「自分の意見を活かせる環境で挑戦したい」と言い換えることで印象が大きく変わります。
また、「仕事についていけなかった」という理由も、「より自分の強みを活かせる分野に挑戦したい」とすれば、前向きな姿勢をアピールできるでしょう。
転職理由はただの説明ではなく、自分の意欲や方向性を伝える大事な場面です。
否定的な表現を避け、成長や挑戦をアピールすることで、面接官に納得感を与えられるはずです。
ビジネスマナーに気を配る
転職活動では、スキルや経験だけでなく、基本的なマナーも見られています。
特に面接では最初の印象が大きく影響し、服装や態度が整っていないだけで評価が下がることがあります。
大切なのは難しいマナーではなく、社会人として当たり前とされる行動を丁寧に行うことです。
清潔感のある服装、時間を守る、礼儀正しい言葉づかいを心がけるなど、基本を徹底するだけで信頼を得やすくなるでしょう。
さらに、面接以外の場面でも気配りは必要です。
メールでは誤字脱字を避け、迅速に返信すること。
電話では明るくはっきりとした声を意識すること。
これらの積み重ねが「安心して任せられる人」という印象につながります。
転職エージェントを利用して第三者からのアドバイスを受けよう
転職活動をスムーズに行うには第三者の視点が欠かせません。
そのために役立つのが転職エージェントです。
転職エージェントは、求人情報の紹介だけでなく、履歴書や職務経歴書の添削、面接対策、キャリア相談など幅広くサポートします。
自分では短所だと思っていた部分を「企業にとっての強み」として言い換えてくれることもあり、無能感にとらわれていた気持ちが前向きに変わるきっかけになるでしょう。
さらに、非公開求人を紹介してもらえることもあります。
一人で悩みながら進めるより、専門のサポートを受けることで効率的に活動でき、納得のいく転職につながりやすくなります。
この機会に転職エージェントを活用してみましょう。
まとめ
自分を「無能だ」と感じてしまうと、転職活動に踏み出すことすら難しくなります。
しかし、不採用や評価の低さは必ずしも能力のなさを意味するものではなく、多くの場合は環境や企業のニーズとの相性によるものです。
大切なのは、自分の強みを正しく理解し、活かせる場所を見つけることです。
転職は環境を変える大きなチャンスです。
自己否定にとらわれるのではなく、一歩を踏み出し、自分に合った転職先を見つけていきましょう。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!