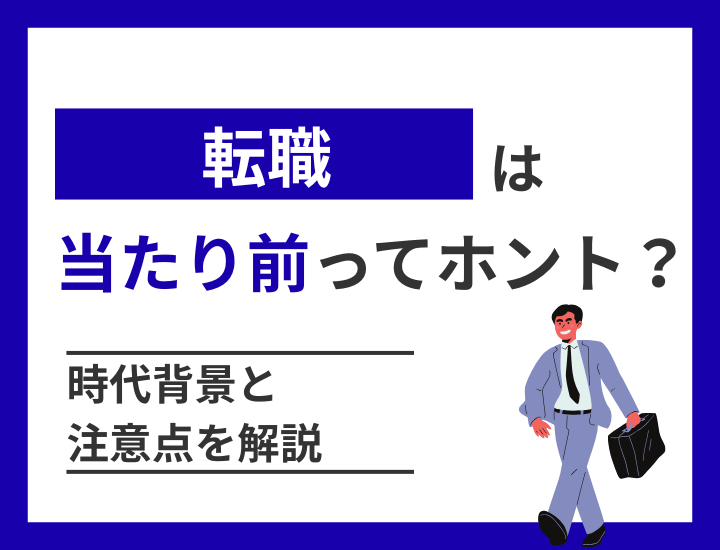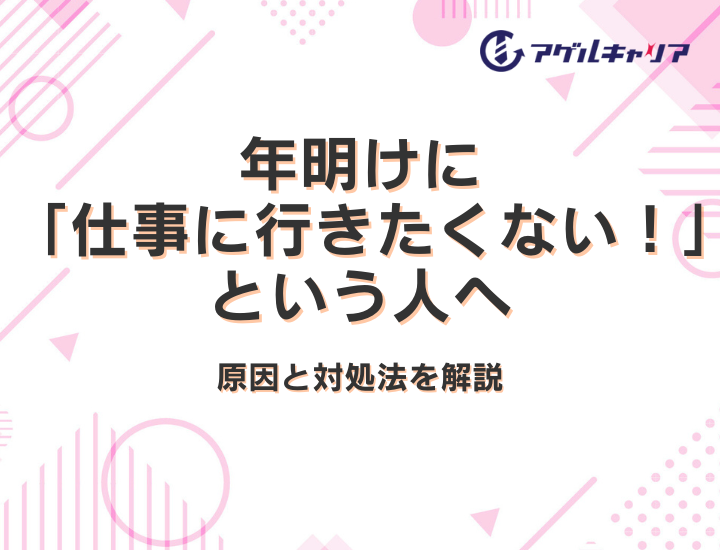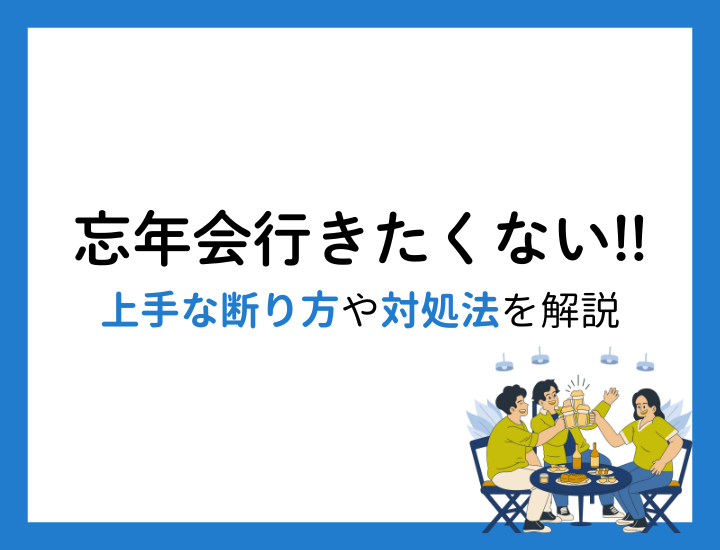
忘年会に行きたくない!断り方と仕事に響かない対処法を徹底解説
はじめに
コロナ禍を経て、多くの企業で飲み会や忘年会の開催は減少しました。
リモートワークが普及したこともあり、「会社の飲み会はもう当たり前ではない」という流れが生まれています。
とはいえ、すべての会社がその風潮に乗っているわけではなく、今でも毎年の恒例行事として忘年会を実施する企業も少なくありません。
そんな状況のなかで、「正直、忘年会に行きたくない」と感じる人は増えています。
仕事自体には真剣に向き合っていても、プライベートの時間や金銭的な負担を考えると、素直に参加を楽しめないという人は多いでしょう。
「行かない」と伝えることが仕事に響かないか、人間関係に影響しないかと不安になるのも自然なことです。
本記事では、「忘年会に行きたくない」と感じたときにどう対応すべきかを解説します。
実際に参加を断る方法や、最低限の配慮をしながら欠席するコツ、無理なく関係性を保つための工夫についても紹介します。
自分に合ったスタンスを見つけ、無理のない形で年末を過ごせるようにしていきましょう。
忘年会に「行きたくない」は失礼なのか?
「忘年会に行きたくない」と感じるのは珍しいことではありません。
ですが、「断ったら周囲からどう思われるだろう」「評価に影響するのではないか」と不安に思う人も多いはずです。
忘年会は会社によって位置づけが異なり、参加が半ば当然とされる雰囲気の職場もあれば、自由参加を尊重する職場もあります。
本章では、忘年会がどのような意味を持ち、なぜ参加へのプレッシャーが生まれるのかについて整理していきます。
忘年会の位置づけ
忘年会は、日本の企業文化に深く根付いた恒例行事のひとつです。
語源は「一年の苦労を忘れる会」とされ、単なる飲み会ではなく、1年間の労をねぎらい、社員同士が感謝を伝え合う場としての意味合いがあります。
多くの会社では、部署や役職を越えた交流の場となり、普段は接点の少ない上司や他部門の同僚と関係を築ける貴重な機会とされています。
また、上司が部下へ直接ねぎらいの言葉をかけたり、部下が日頃の感謝を表現できたりする場でもあります。
そのため、忘年会は「仕事の延長」というより「職場の人間関係を良くするための機会」としての役割を担うことが多いのです。
特に大企業や歴史ある会社では、この位置づけが強く、参加が当然とされる雰囲気があります。
こうした文化的背景から、参加を断ることが難しいと感じる人が多いのです。
会社による暗黙のルールや雰囲気
忘年会に関しては、企業ごとに暗黙のルールや雰囲気が存在します。
たとえば、伝統的な企業や上下関係が色濃い職場では「全員参加」が当然とされ、欠席すると「協調性がない」「上司を立てられない」といった印象を持たれることもあります。
ただし、近年では働き方改革や価値観の多様化が進み、若手社員やベンチャー企業を中心に「自由参加」が浸透しつつあります。
リモートワークの普及やプライベート重視の傾向から、「行きたい人だけが行けばいい」というスタンスを取る会社も増えているのです。
それでも、従来型の組織文化を持つ会社では「出席しない=消極的」という評価につながることも少なくありません。
つまり、忘年会への参加をどう受け止めるかは、職場の雰囲気や慣習によって大きく左右されます。
このような暗黙のルールが、社員に「断りづらい」という心理的圧力を与えているのです。
「参加しなければならない」と感じる背景
多くの人が「忘年会に参加しなければならない」という義務感を持ってしまう背景には、日本企業特有の評価基準や人間関係の影響があります。
日本の職場では、成果だけでなく「協調性」や「チームへの姿勢」が重視されやすいため、忘年会を断ることで「協力的ではない」と見られるのではないかという不安が生まれるのです。
さらに、新入社員や若手のころに「新人は必ず参加」「部署全員がそろうのが当たり前」といった文化を経験した人ほど、参加を義務のように感じやすくなります。
また、忘年会は取引先や上司と直接交流できる機会でもあるため、欠席すると「信頼関係を築くチャンスを逃すのでは」と考えてしまうケースも少なくありません。
日本社会では「和を乱さないこと」が美徳とされるため、自分だけ欠席することで周囲から浮いてしまうのではないかという心理的プレッシャーが強く働きます。
これらの要因が重なり、「本当は行きたくないのに参加せざるを得ない」という状況が生まれているのです。
忘年会に行きたくない人は多い?
「忘年会は会社の恒例行事だから参加するもの」と考える人がいる一方で、近年では忘年会に行きたくないと感じる人も増えています。
特にコロナ禍を経てオンライン飲み会や直接の交流機会が減ったことで、「仕事は仕事、プライベートはプライベート」と切り分けたいという考え方が強まってきました。
実際、参加を望まない人は世代を問わず存在しますが、若手を中心にその傾向が顕著です。
ここでは、忘年会に参加したくない人の割合と、若手世代を中心に「不要派」が増えている背景を詳しく見ていきます。
忘年会に参加したくない人の割合
忘年会に参加したくないと考える人は、決して少数派ではありません。
近年の調査によると、忘年会の参加を「気が進まない」と答える人は全体の約4割程度にのぼり、特に20代・30代の若手社員においてはその割合がさらに高くなる傾向があります。
かつては「上司や同僚との交流の場」として積極的に参加する人が多かったものの、働き方や価値観の多様化に伴い、「お金がかかる」「拘束時間が長い」「気を遣って疲れる」といった理由から避けたいと考える人が増えています。
さらに、コロナ禍で強制的に飲み会文化が縮小した経験も大きく影響しています。
リモートワークやオンラインのコミュニケーションに慣れた世代にとっては、「わざわざ集まってお酒を飲む必要はない」と感じやすいのです。
そのため、若い世代ほど忘年会を義務的に参加する意義を見いだせず、結果として「行きたくない」と思う人の割合が高まっています。
若手世代を中心に「不要派」が増えている
特に20代の若手世代を中心に「忘年会は不要」と考える人が増えている背景には、いくつかの要因があります。
まず大きいのは、プライベートの時間を大切にする価値観が強まっていることです。
長時間労働を避けたい、趣味や自己投資の時間を確保したいという考えが広がり、業務時間外の会社行事に積極的に参加する動機が薄れてきています。
また、お酒離れの傾向も見逃せません。
飲み会文化そのものに魅力を感じない人が増えており、特に若い世代ではアルコールに依存しないコミュニケーションが好まれるようになっています。
さらに、上下関係や忖度が強く働く場に居心地の悪さを感じ、「忘年会に参加しても楽しくない」と判断する。
加えて、コロナ禍以降に社会人になった層にとっては「そもそも大規模な飲み会に慣れていない」という事情もあります。
そのため、忘年会を当然のように受け入れてきた中高年世代と比べると、忘年会に対する拒否反応が出やすいのです。
結果として、「忘年会に行きたくない」と考える声は年々強まり、若手を中心に「不要派」が定着しつつあります。
忘年会に行きたくない人の主な理由
忘年会は「一年の労をねぎらう場」とされてきましたが、実際には参加したくないと感じる人も少なくありません。
その背景には、金銭的な負担や拘束時間の長さだけでなく、お酒や人付き合いへの苦手意識、さらには気を遣う場面の多さによる疲労感があります。
ここでは、多くの人が「忘年会に行きたくない」と思う代表的な理由を具体的に整理していきます。
金銭的負担が大きい
忘年会に行きたくないと感じる理由の一つに、参加費の負担があります。
もちろん会社によっては経費で賄ってくれる場合もありますが、一般的には会費制であり、1回の参加で数千円かかるのが相場です。
さらに、二次会や三次会に参加すれば、合計で1万円以上になることも珍しくありません。
特に若手社員や新入社員は基本給が高くないのがほとんどなため、この出費に経済的な負担を感じやすいでしょう。
加えて、年末はクリスマスや帰省、旅行などで出費が重なる時期であり、「本当は貯金や趣味に回したい」と考える人も多いでしょう。
こうした状況から、「仕事に必要だから仕方なく払っている」と感じる人が増え、結果として忘年会に消極的な気持ちになるのです。
金銭的負担は表立っては言いづらい理由ですが、実際には非常に大きな要因となっています。
拘束時間が長くプライベートを削られる
忘年会に行きたくない理由の二つ目は、拘束時間の長さです。
忘年会は業務終了後に開催されることが多いため、帰宅時間が遅くなりがちです。
一次会だけで2〜3時間、さらに二次会・三次会まで続けば深夜まで拘束されることもあります。
その結果、翌日の予定に影響したり、プライベートの時間が奪われたりすることにつながります。
特に家庭を持つ人や、自己研鑽・趣味に時間を充てたい人にとっては「自分の時間が削られる」ということが大きなストレスになります。
最近ではワークライフバランスを重視する人が増えているため、忘年会に割く時間を「無駄」と感じる声も強まっているのです。
業務外の拘束と考えると、忘年会に行きたくないと思うのも自然なことと言えるでしょう。
お酒や人付き合いが苦手
忘年会が敬遠される理由の三つ目は、お酒や人付き合いへの苦手意識です。
飲み会の場では「飲めること」が前提とされる雰囲気が残っており、アルコールを勧められることにストレスを感じる人も少なくありません。
また、そもそも体質的にお酒が飲めない人や、飲み会の盛り上がりについていけない人にとって、忘年会は苦痛の場になりがちです。
さらに、形式的な会話や表面的な付き合いを強いられることもあり、人付き合いそのものに疲れを感じる人もいます。
現代では「飲みニケーション」に価値を見出さない世代が増えており、「無理に参加してまでお酒や人付き合いを消費したくない」という考え方が広まっています。
そのため、忘年会に行きたくないと感じる人が増えているのです。
気を遣う相手が多くて疲れる
最後に挙げられるのは、気を遣う相手の多さです。
忘年会では上司や先輩、取引先など、普段以上に人間関係に配慮しなければならない場面が多くあります。
席次のマナーやお酌の習慣など、形式的な対応を求められることも多く、心からリラックスできない人も少なくありません。
特に若手社員は「場を盛り上げなければならない」という暗黙のプレッシャーを感じやすく、結果として精神的な疲労が大きくなります。
仕事終わりに休むどころか、かえってストレスが増える場と感じる人が多いのはこのためです。
「忘年会に行きたくない」と考える背景には、単なる飲み会嫌いではなく、こうした気疲れが積み重なっているケースが多いのです。
忘年会に行かないことに対する見られ方
「忘年会に行きたくない」と思っても、実際に欠席したらどのように周囲から見られるのかは気になるポイントでしょう。
特に「評価に響くのではないか」「職場で浮いてしまうのではないか」と不安になる人は少なくありません。
しかし、実際には忘年会の参加・不参加が人事評価に直結することはほとんどありません。
ただし、会社の雰囲気や人間関係によっては多少の影響を受ける可能性があるのも事実です。
ここでは、忘年会を欠席した際にどのような見られ方をされるのかを解説していきます。
実際のところ「評価に響く」可能性は低い
まず安心してほしいのは、忘年会に参加しなくても人事評価や昇進・昇給に直結することはほとんどないという点です。
会社における評価は、基本的には日々の業務遂行能力や成果、チームへの貢献度などが基準となります。
「飲み会に参加しないから評価を下げる」というのは、合理的な人事制度を導入している会社では考えにくいことです。
さらに、近年は働き方の多様化が進み、プライベートの時間を大切にする価値観が尊重されるようになっています。
そのため、上司や人事も「参加は任意であり強制ではない」というスタンスを取る企業が増えているのです。
特にコロナ禍を経てオンライン懇親会や食事会の縮小が進んだことで、「飲み会に出ない=評価が下がる」という考え方は古いものになりつつあります。
もちろん、忘年会を通じて上司や同僚と交流を深めることは人間関係にプラスの影響を与える可能性があります。
しかし、それはあくまで「プラスα」であり、参加しなかったからといってマイナスに働くことはほとんどありません。
日常業務で誠実に取り組み、チームに貢献していれば、忘年会に行かなくても評価に悪影響を及ぼすことはないと考えてよいでしょう。
職場の雰囲気次第で「浮く」リスクはある
一方で、職場の文化や雰囲気によっては「浮いてしまう」リスクがあるのも事実です。
例えば、体育会系の風土が強く、飲み会を「チームの結束を深める場」と位置づけている会社では、忘年会を断ることで「付き合いが悪い」「協調性に欠ける」と受け止められる可能性があります。
特に上司や経営層が飲み会を重視している場合、参加を断ると「ノリが合わない人」と見られやすいでしょう。
また、社員数が少なくアットホームな職場では、一人が欠席するだけでも目立ってしまい、「なぜ来ないのだろう」と不自然に感じられるケースもあります。
この場合、評価に直結するわけではありませんが、人間関係のなかで微妙な距離感が生まれてしまうことも考えられます。
ただし、これは「必ず悪い印象を持たれる」という話ではなく、あくまで職場文化次第です。
最近では「飲みニケーション」を必須としない企業も増えており、忘年会を欠席しても気にされない環境も珍しくありません。
つまり、忘年会を断ったことで浮くかどうかは、自分の会社の雰囲気や上司の価値観に大きく左右されると理解しておくとよいでしょう。
人間関係を保ちたいなら最低限の配慮が必要
忘年会に行きたくないときでも、人間関係を円滑に保つためには最低限の配慮が欠かせません。
単に「行きません」とだけ伝えるのでは、無愛想に受け止められ、人によっては不快に感じてしまう可能性があります。
欠席する場合は、仕事の都合や家庭の事情、体調管理などを理由として、丁寧に断る姿勢を心がけましょう。
例えば「その日は家族の予定があり、残念ながら参加できません」「体調を整えたいので今回は失礼します」といった形で理由を添えると角が立ちにくくなります。
また、「楽しんできてください」「次の機会にぜひ参加したいです」といったフォローの一言を加えることで、関係性を良好に保つことができます。
さらに、忘年会に出席しない代わりに、日常業務で積極的に協力したり、感謝の言葉を伝えたりすることも大切です。
飲み会の場ではなく日々のコミュニケーションを通じて関係を築けば、忘年会に不参加でも信頼を損なうことはありません。
結局のところ、人間関係を良好に保てるかどうかは「欠席そのもの」ではなく、「断り方」と「普段の行動」によって決まるのです。
忘年会を断る方法|社内・取引先別
忘年会に行きたくないと感じても、単純に「行きません」と伝えるのは、場の空気を悪くしたり人間関係に影響を与えるリスクがあります。
断り方ひとつで「配慮のある人」という印象にも「自己中心的な人」という印象にもなり得るため、適切な言い回しを選ぶことが大切です。
ここでは、社内の忘年会と取引先との忘年会に分けて、角が立たない断り方を具体的に解説します。
社内の忘年会を断る場合
社内での忘年会は、同僚や上司との人間関係に直結するため、断り方には特に注意が必要です。
大切なのは、「参加できない理由は、やむを得ない事情がある」と相手に納得してもらえる理由を添えて伝えることです。
たとえば、家庭や健康に関わる内容は理解を得やすく、無理に突っ込まれることも少ないでしょう。
OK例文
「家庭の事情で子どもの世話が必要でして、今回は参加を見送らせていただきます。」
「最近体調を崩しやすいため、医師からもアルコールを控えるよう言われており、今回は遠慮させていただきます。」
NG例文
「正直、面倒なので行きません。」
「行きたくないので欠席します。」
後者のような理由は、率直すぎて「協調性がない」と思われる可能性が高く、職場での信頼を損ねる原因になりかねません。
どうしても参加したくない場合でも、「仕事や人間関係を大事にしている姿勢」が伝わる断り方を心がけることが重要です。
また、参加できない代わりに「後日ちょっとした差し入れをする」などの配慮を加えると、良好な関係を保ちやすくなります。
取引先との忘年会を断る場合
取引先からの忘年会の誘いは、断り方を間違えるとビジネス上の信頼関係に影響する可能性があります。
大切なのは、「仕事を軽視しているわけではない」という姿勢を示しながら、丁寧にお断りすることです。
スケジュールや業務上の都合を理由にすると、角が立ちにくく理解を得られやすいでしょう。
OK例文
「スケジュールの都合で参加が難しく、大変心苦しいのですが、改めて年始にご挨拶に伺わせていただければ幸いです。」
「年度末業務が重なっており、今回は参加できそうにありません。大変申し訳ございませんが、今後とも変わらずよろしくお願いいたします。」
NG例文
「正直、興味がないので参加しません。」
「忘年会は苦手なので行きたくありません。」
NG例のような伝え方は、相手に「ビジネスを軽んじている」と受け取られる可能性があり、信頼関係を損なうリスクがあります。
断る際には、「参加できないのは残念だが、今後の関係は大切にしたい」という気持ちを添えることが大切です。
また、直接会えない分、年始の挨拶やメールで感謝の気持ちを表すことで、フォローアップにつながります。
忘年会が苦手でも楽しむ方法
忘年会に参加すること自体に抵抗を感じる人は少なくありませんが、完全に断るのは気が引ける、あるいは職場の人間関係を考えて仕方なく出席する場合もあります。
そんなときは「忘年会をどう楽しむか」という視点を持つことが大切です。
無理に盛り上がらなくても、自分なりに工夫をすればストレスを減らして過ごすことができます。
ここでは、忘年会が苦手な人でも参加を少し楽に感じられる方法を紹介します。
一次会だけ参加する
忘年会を苦手に感じる人の多くは「長時間の拘束」に負担を感じています。
二次会、三次会と続くと深夜まで時間を取られてしまい、プライベートの時間が削られることがほとんどです。
そのため、一次会だけ参加して帰る人は実は少なくありません。
一次会の時間はおおよそ2〜3時間程度で終わるため、「これだけなら付き合える」と考える人も多いのです。
また、一次会は全員が揃う場であり、会社としても「顔を出した」という印象を持ってもらいやすい場です。
一次会に出席しておけば「付き合いが悪い」と思われにくく、無理に二次会以降に参加しなくても問題ないケースがほとんどです。
実際、若手や家庭を持つ社員は一次会で帰ることが一般的になっており、過剰に気にする必要はありません。
大事なのは、一次会だけで切り上げる場合でも「今日はここまでで失礼します」と一言添えること。
笑顔で帰れば角も立たず、むしろ自分のペースを保ちながら人間関係も守ることができます。
会話のテーマを準備しておく
忘年会が苦手な理由の一つに「上司や同僚との会話に困る」という点があります。
普段業務の話しかしない相手ですから、いざ飲み会で向き合うと沈黙が続いてしまい、「気まずい時間を過ごすくらいなら行きたくない」と感じてしまう人も少なくありません。
そこでおすすめなのが、事前に会話のテーマをいくつか準備しておくことです。
具体的には、業務に直結しすぎない軽い話題が適しています。
たとえば「最近見た映画やドラマ」「趣味の話」「旅行やグルメの話題」などは、多くの人が答えやすく会話も広がりやすいテーマです。
また、仕事関連でも「今年印象に残った出来事」「来年の目標」など、前向きで誰もが話しやすい内容にすると、自然と盛り上がりやすくなります。
会話のネタを持っていると「沈黙したらどうしよう」という不安を軽減でき、自分自身の気持ちも楽になります。
忘年会は必ずしも盛り上げ役になる必要はなく、「相手に質問を投げかける」だけでも十分に会話は成立します。
話を聞く姿勢を見せるだけで印象が良くなることもあるため、会話のテーマを少し準備するだけで、忘年会を過ごしやすい時間に変えることができます。
アルコール以外の飲み物で参加する
忘年会といえば「お酒を飲む場」というイメージが根強くありますが、近年はノンアルコールで参加する人も増えてきています。
多くの飲食店ではノンアルコールビールやカクテル風のソフトドリンクが用意されており、アルコールが苦手な人でも自然に溶け込める環境が整っています。
特にコロナ禍以降は健康やライフスタイルを優先する考え方が浸透し、「無理に飲まなくてもいい」という雰囲気が強まっています。
そのため、ノンアルを選んだからといって冷たい目で見られることはほとんどありません。
実際に「車で来ているから」「翌日も仕事があるから」など理由を添えれば、周囲も納得してくれる場合が多いのです。
重要なのは、自分の体質や事情を正直に伝えること。
無理に飲んで体調を崩すよりも、最初から「今日はソフトドリンクでいきます」と伝える方が周囲も安心します。
お店側もノンアルの選択肢を豊富にしているため、今では気兼ねなく楽しめる時代になっています。
アルコール以外の飲み物を選ぶことは決して失礼ではなく、自分らしく参加するための賢い方法だといえるでしょう。
忘年会にどうしても行きたくない時の最終手段
どうしても忘年会に参加したくない場合、無理をして出席する必要はありません。
忘年会はあくまで社内の交流を深める場であり、義務ではないからです。
ただし、欠席する際には「ただ行きたくないから行かない」という姿勢では周囲の印象を損ねてしまう可能性もあります。
そこで大切なのは、丁寧な断り方や日常業務での信頼関係の維持、さらに別の方法で感謝を伝える工夫です。
本章では、忘年会を欠席する際に心がけたい具体的なポイントを解説します。
無理に出席せず、欠席の意志を丁寧に伝える
冒頭でも触れたように、忘年会は本来「強制参加」の場ではありません。
業務の一環ではなく、あくまで社内の懇親の場です。
そのため、どうしても気が進まない場合やプライベートの事情がある場合には、無理をして出席する必要はないでしょう。
ただし大切なのは、欠席する際の伝え方です。
単に「行きたくないので欠席します」と伝えるのでは、上司や同僚に不快感を与える恐れがあります。
たとえば「家庭の事情で出席が難しい」「体調管理を優先したい」など、前向きかつ理解を得やすい理由を添えて伝えるのが無難です。
また、欠席の連絡はできるだけ早めに行うことが重要です。
直前のキャンセルは相手に迷惑をかけやすく、不要な印象の悪化につながりかねません。
誠意を持った伝え方をすれば、「無理してまで出席する必要はない」と理解してもらえるケースが大半です。
出席しない分、日常業務で信頼関係を積み重ねる
忘年会に欠席しても、日常の業務でしっかりと信頼を築いていれば大きな問題にはなりません。
むしろ「普段の仕事ぶりが誠実で頼りになる人」という位置付けができていれば、行事に参加しなくても評価が下がることはほとんどありません。
逆に、日常業務で手を抜いていたり、周囲とのコミュニケーションを怠っていたりすると、欠席がネガティブに捉えられる可能性が高まります。
たとえば、報連相を丁寧に行う、チームメンバーをフォローする、期限を守って確実に成果を出すなど、基本的な仕事の積み重ねが信頼関係を築く基盤になります。
さらに、日常的に同僚や上司に感謝を伝える習慣があれば、「忘年会に来られないのは仕方ない」と受け止めてもらいやすくなるでしょう。
忘年会は一日限りのイベントですが、日々の働きぶんは継続的に見られています。
そのため「普段の姿勢」で信頼を勝ち取ることこそが、忘年会に無理して参加しなくても良い環境を作る鍵になります。
他の形で感謝を示す
忘年会に参加しない代わりに、別の形で「今年もありがとうございました」という感謝を伝えることも効果的です。
欠席そのものが悪い印象につながるわけではありませんが、気遣いをプラスすることで職場の人間関係がより円滑になります。
具体的には、仕事納めの日にちょっとしたお菓子を差し入れる、オフィスで「一年間ありがとうございました」と一言添えるなど、無理のない方法で十分です。
また、取引先やチームメンバーに年末のメールやメッセージで感謝を伝えるのも良いでしょう。
形式ばったものではなくても、「お世話になりました」「来年もよろしくお願いします」といった一言があるだけで、相手に好印象を与えられます。
忘年会という場に出られなくても、「人との関係を大切にしたい」という姿勢を示すことは可能です。
むしろ自分に合った形で誠意を伝える方が、自然で負担の少ないコミュニケーションにつながります。
まとめ
忘年会に「行きたくない」と感じるのは、決して珍しいことではありません。
金銭的な負担や拘束時間の長さ、気を遣う人間関係など、誰にとってもストレスの要因となり得るため、参加をためらう人が増えているのは自然な流れです。
特に近年はコロナ禍をきっかけに働き方や価値観が大きく変化し、忘年会自体が不要だと考える人も少なくありません。
実際のところ、欠席したからといって評価に直結するケースは少なく、むしろ自分の体調やプライベートを優先する姿勢が尊重される風潮も強まっています。
とはいえ、職場の雰囲気や上司との関係性によっては「なぜ来ないのか」と気にされる可能性もゼロではありません。
そのため、行きたくないときには無理に我慢するのではなく、丁寧に欠席の理由を伝えたり、一次会のみの参加で区切りをつけるなど、柔軟に対応することが大切です。
また、参加しない分は日常の業務で信頼を積み重ねたり、別の形で感謝を伝えることで、人間関係を円滑に保つことができます。
忘年会はあくまで任意のイベントであり、絶対に参加しなければならないものではありません。
大切なのは「行きたくない」という気持ちを押し殺すことではなく、自分の考えや状況に合わせて、最適な選択をすることです。
無理のない形で忘年会に向き合い、仕事とプライベートのバランスを上手に取ることが、これからの働き方においてより重要になるでしょう。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!