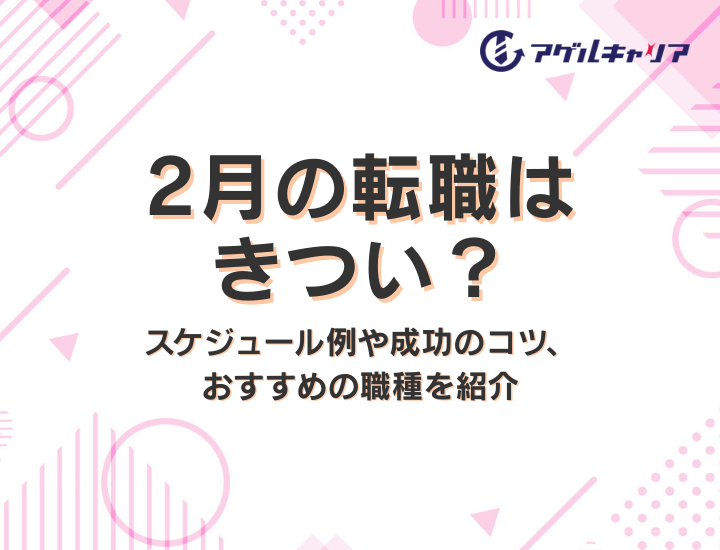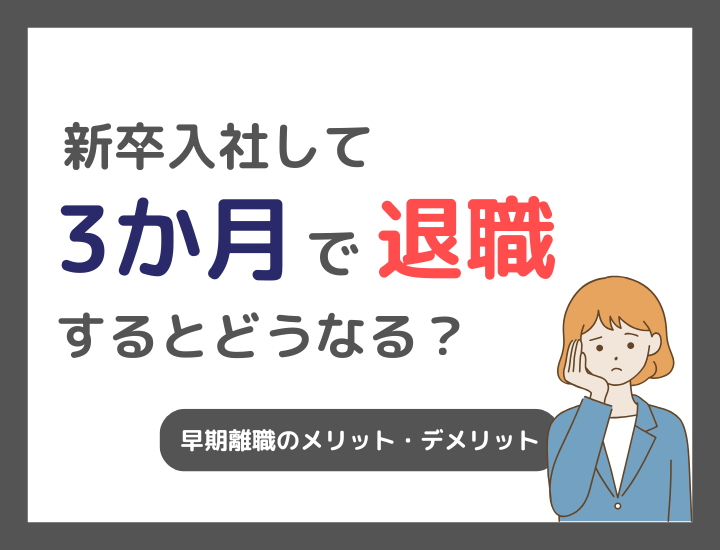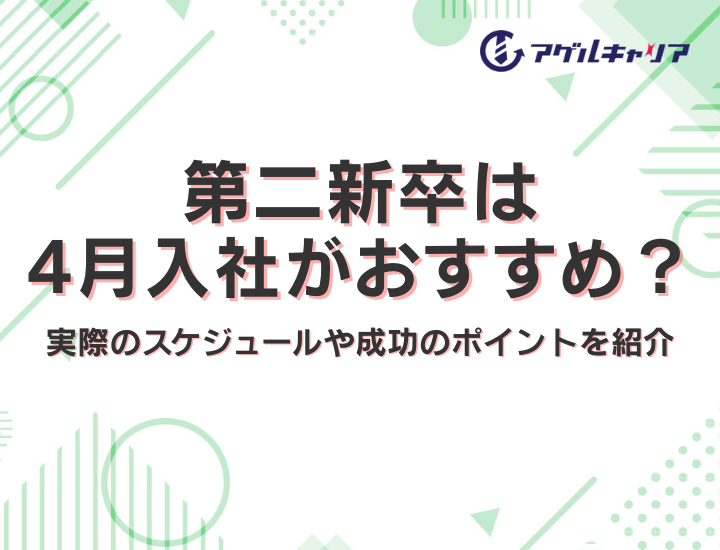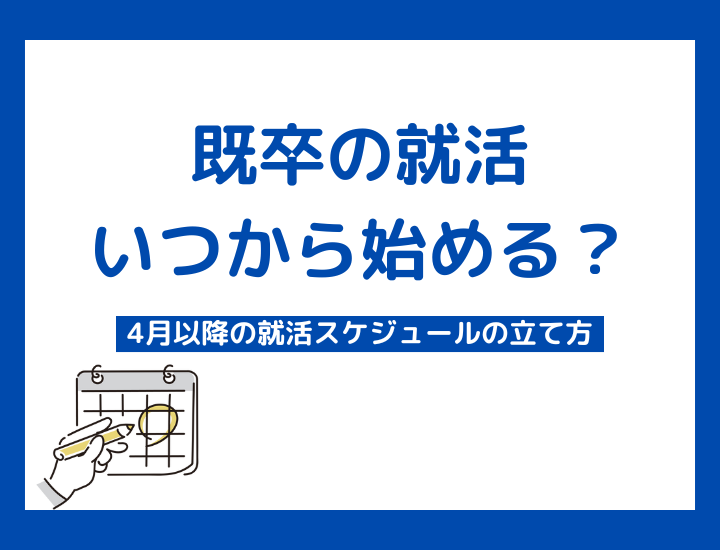
既卒が就活を始めるベストタイミングとは?4月以降の就活スケジュールの立て方
はじめに
「既卒だから就活は難しい」と感じていませんか?確かに、4月以降の就職活動では新卒と比べて求人の選択肢が狭まり、採用企業の数が少ないという現実があります。
しかし、既卒だからといってチャンスがないわけではありません。
実は、既卒者を積極的に採用する企業や、新卒枠で応募できる制度を用意している企業も存在します。
本記事では、既卒が4月以降に就活を始める際のベストタイミングや、成功のためのポイントについて詳しく解説します。
また、企業が既卒者に求める要素や、内定率を高めるための対策についても紹介。
就職活動をスムーズに進めるための具体的な行動プランを知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
そもそも「既卒」とは
求人情報を見ていると「既卒歓迎」などのキーワードをよく目にすることでしょう。
そもそも「既卒」の定義が気になるところですよね。
既卒とは文字通り学校を卒業した人を指しますが、第二新卒なども存在するため、実際にどのような違いで棲み分けられているのかが知りたいのではないでしょうか。
ここでは、既卒の厳密な定義と第二新卒などの違いをご紹介します。
既卒の定義
「既卒」とは、学校(大学・短大・専門学校・高校など)を卒業したものの、卒業後に正社員としての就職をしていない人を指します。
一般的に、新卒採用の枠に応募できるのは卒業年度の学生ですが、既卒者はこの枠から外れるため、主に中途採用や既卒向けの求人を探すことになります。
ただし、厚生労働省が「3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!」と促している通り、企業によっては「卒業後3年以内であれば新卒扱い」とするケースがあります。
この場合は、既卒でも新卒採用枠での応募が可能です。
また、フリーターや契約社員・派遣社員として働いている場合でも、正社員経験がなければ既卒として扱われることが多いです。
そのため、自分の状況に合った就職活動の戦略を立てることが重要です。
既卒の就職市場は年々広がっており、未経験でもポテンシャル採用を行う企業も増えています。
タイミングや準備次第で正社員としてのチャンスをつかむことが可能です。
第二新卒との違い
第二新卒は、一般的に「卒業後1〜3年以内に正社員として就職し、その後転職を希望する人」を指します。
短期間ながらも正社員経験があるため、業務経験やビジネスマナーを備えていると評価されやすく、新卒採用と中途採用の中間的な扱いを受けることが多いです。
第二新卒は社会経験がある人のため、新卒1年目でも2年目でも、転職しようとすると「中途採用」として応募する人が一般的。
少ないながらもある程度のキャリアをアピールして転職市場で戦わなければならないため、苦戦する人も多くいます。
とはいえ、第二新卒は基礎的な社会人マナーを身につけた若手人材なので、多くの企業が欲していることも事実。
既卒が就活する際は、強力なライバルとなるでしょう。
なお、既卒と第二新卒では企業側の採用基準や選考のポイントが異なるため、自身の状況に合った就活戦略を立てることが重要です。
既卒が4月以降に就活をすることの難しさ
既卒は新卒での就活に比べると、内定までの難易度がぐっと上がります。
実際にどの程度上がるのか、なぜ難しいのかを把握した上で具体策を考えましょう。
既卒採用をしている企業が少ない
4月以降に就活を始める既卒者にとって、大きな課題の一つが「既卒採用をしている企業が少ない」という点です。
多くの企業は新卒一括採用を基本としており、3月までに内定者を確保するため、4月以降は新卒採用枠がほぼ埋まっている場合が多くなります。
そのため、既卒者を新卒枠で受け入れる企業は限られ、中途採用に応募する場合でも、実務経験が求められることが一般的です。
また、既卒者を対象とした求人は通年採用を行う企業や、一部のベンチャー企業・中小企業に限られる傾向があります。
そのため、希望する業界や職種によっては、選択肢が大きく狭まってしまう可能性があります。
このように、4月以降の就活では応募可能な企業の数が減少するため、効率的に情報収集を行い、自分に合った企業を早めに見つけることが重要です。
エージェントなどを活用し、既卒者を積極的に採用している企業を効率的に探すのが良いでしょう。
通年採用の求人案件は難易度高め
通年採用の求人案件は難易度が高いことも、既卒就活の難しさの理由の一つです。
なぜなら、新卒採用のピークが3月までに終わるため、4月以降の求人は「経験者優遇」や「即戦力」を求めるケースが多く、未経験の既卒者には厳しい状況が生じるからです。
先述した通り、多くの企業では新卒一括採用を基本とし、4月以降に通年採用枠を設けている企業は限られています。
特に大手の場合は新卒採用が基本なので、通年採用枠ではポテンシャルよりも即戦力としてのスキルや実務経験が求められる傾向にあります。
そのため、既卒者が応募できる求人の選択肢は狭まり、競争率も高くなるのが現状です。
さらに、通年採用を行う企業の多くは、中途採用市場とも競合するため、社会人経験のある転職希望者と同じ土俵で戦わなければなりません。
特に強力なライバルとなるのが、基礎的な社会人スキルが身についた第二新卒です。
ライバルたちに勝つための何かしらのスキルを身につけてアピールしなければ、難易度は高いままでしょう。
就活時にマイナスイメージを抱かれる
既卒として4月以降に就職活動を始める際、多くの企業が新卒採用を終えているため、選考の機会が限られることが大きな課題となります。
特に、企業によっては「なぜ卒業後すぐに就職しなかったのか?」という疑問を抱かれ、マイナスイメージを持たれる可能性があります。
新卒一括採用が主流の日本では、卒業後すぐに就職することが一般的。
既卒者に対して「能力や意欲に問題があるのでは?」と疑問視する企業も少なくありません。
また、既卒の期間が長くなるほど、「ブランクがあることでスキルや知識が衰えているのでは?」という懸念を持たれやすくなります。
そのため、書類選考の段階で不利になるケースもあります。
こうしたマイナスイメージを払拭するためには、就職しなかった理由をポジティブに説明し、これまでの経験や自己成長をアピールすることが重要です。
特に、アルバイトや資格取得、インターン経験など、仕事に活かせる具体的な活動を伝えることで、企業側の不安を和らげることができます。
諦める必要はない!既卒でも就活に成功できるワケ
既卒だからといって就職を諦める必要はありません。
最近では若手人材を確保したい企業が多いため、あえて既卒者を歓迎している企業もありますし、先述した通り卒業後3年以内なら新卒採用枠に応募できるケースも少なくありません。
既卒だからといって就活を諦めるのではなく、自分を活かせる企業を見つけて積極的に挑戦していきましょう。
既卒を歓迎している企業もある
実は、既卒を歓迎している企業も少なくありません。
特に、近年は人手不足の影響もあり、既卒者を積極的に採用する企業が増えています。
企業が既卒者を歓迎する理由の一つは、「ポテンシャルの高さ」です。
既卒者は学生時代に比べて社会経験が少しでも増えており、自分の適性やキャリアプランをより明確に考えられるケースが多いと評価されます。
また、新卒一括採用とは異なり、通年採用を行う企業も多いため、タイミングに関係なく応募できるのもメリットです。
さらに、ベンチャー企業や成長中の企業では、柔軟な採用基準を持ち、熱意や実績を重視する傾向があります。
そのため、既卒であっても意欲をアピールできれば十分に採用される可能性があります。
卒業から3年以内は新卒枠で応募できる
先述した通り、多くの企業では卒業後3年以内であれば新卒枠で応募可能としています。
そのため、既卒でも新卒採用のチャンスを活かせるのです。
特に4月以降は、春採用や通年採用を行う企業が増え、既卒者にも有利な時期です。
まずは自己分析を行い、希望する業界や職種を明確にしましょう。
その後、新卒向けの就活サイトや企業の採用ページをチェックし、エントリーを進めるのがポイントです。
また、面接対策や履歴書のブラッシュアップも並行して行いましょう。
さらに、ハローワークや転職エージェントを活用すると、既卒向けの求人情報を得やすくなります。
特に、第二新卒枠を設ける企業も多いため、柔軟な選択肢を持つことが重要です。
ポイント|大手企業は既卒でも「新卒」として見てくれる
卒業後3年以内の既卒者を新卒枠で採用する企業の多くは、大手企業です。
先述の通り、厚生労働省が「卒業後3年以内の既卒者を新卒枠で応募可能にする」よう企業に推奨しています。
これは、就職活動のタイミングを逃した人の雇用機会を増やし、労働市場の流動性を高める狙いがあります。
大手企業はこのような社会的な流れを反映し、より柔軟な採用方針を取る傾向があるため、既卒にもチャンスが巡ってくるというわけです。
既卒が内定をもらいやすい時期とは?
既卒の就活は新卒に比べると楽ではありません。
だからこそ、タイミングを見極めて効率よく就活をするのも大切です。
既卒が内定をもらいやすい時期は年に2回あります。
それが、3月・4月の春採用と、8月・9月の秋採用です。
それぞれなぜ内定がもらいやすいのか、企業側の背景も含めて解説します。
3月・4月
既卒者にとって3月・4月は内定を獲得しやすい時期です。
その理由は、企業の採用スケジュールと新卒市場の動きが関係しています。
まず、新卒採用では、4月入社に向けて前年の春から選考が始まりますが、内定辞退や欠員補充のために追加募集を行う企業が3月頃から増える傾向にあります。
特に、大手企業や有名企業は、新卒採用の枠を埋めるために既卒者も対象にすることが多くなります。
また、4月は新しい期のスタートとなる企業が多く、新たな採用計画が始まるタイミングでもあります。
そのため、企業側も新たに人材を確保しようとする動きが活発になり、既卒者にもチャンスが広がります。
さらに、3月は大学卒業のタイミングでもあり、既卒者として本格的に就職活動を始める人が増える時期です。
企業もその流れを意識し、卒業直後の既卒者を新卒枠で受け入れやすくなっています。
既卒者はこの時期を逃さず、企業の追加募集や春採用の情報をチェックし、積極的に応募することが重要です。
8月・9月
既卒が内定をもらいやすい時期として、8月・9月が挙げられるその理由の一つが、大手企業の二次募集・追加募集が活発になることです。
4月から始まる新卒採用では、6月ごろまでに多くの企業が一次選考を終えますが、内定辞退者が出ることで追加募集を行う企業が増えるのが8月・9月の特徴です。
特に、新卒採用枠を充足させたい企業にとって、既卒者も貴重な人材となります。
また、この時期は中小企業やベンチャー企業の秋採用(9月~11月)が本格化するタイミングでもあります。
これらの企業は、新卒市場で大手企業と競争するのが難しく、夏以降に採用枠を広げる傾向があります。
既卒者も対象とした選考を実施するケースが多く、チャンスが広がります。
さらに、8月・9月は新卒市場が落ち着き、企業の採用担当者が既卒者や第二新卒に目を向けやすい時期でもあります。
大手の採用活動が一段落するため、既卒者の応募にも柔軟に対応できるようになるのです。
このように、企業側の追加募集・秋採用の増加、採用担当者の余裕が生まれることが、8月・9月に既卒者が内定をもらいやすい理由となっています。
企業が既卒者を評価するポイント
既卒が内定率をアップさせるためには、企業側が評価してくれるポイントを理解した上で就活対策をしましょう。
ここでご紹介するのは、企業側が既卒者を採用する上での評価基準となるポイントです。
主な4つをご紹介するので、具体的に見ていきましょう。
既卒となった理由がポジティブであるか
既卒となった理由がポジティブな未来を想像させるようなものかは、長期的な雇用を目的とする企業にとって重要なポイントです。
そのため、「ただ単に就職活動に失敗した」「何となく就職しなかった」という理由ではなく、前向きな目的や成長のための期間だったことを示すことが重要です。
例えば、「学生時代に就活をしていたが、受けていた業界と異なる業界に挑戦したくなり、改めて自己分析を行いながら準備をしていた」「留学や資格取得に取り組み、スキルを磨いていた」といった理由は、自己成長の姿勢をアピールできるため、企業から評価されやすくなります。
逆に、「なんとなく就職のタイミングを逃してしまった」「特に理由はないが就職しなかった」といったネガティブな理由では、採用担当者に「この人は入社後も計画性を持って行動できるのか?」という不安を抱かせる可能性があります。
したがって、既卒としての期間をどのように過ごし、どんな学びや成長があったのかを具体的に伝えることが、企業に好印象を与えるポイントになります。
明確なキャリアプランを持っているか
明確なキャリアプランを持っている人は、将来性を感じてもらいやすくなります。
既卒者の場合、新卒と異なり「なぜ卒業後すぐに就職しなかったのか?」という疑問を持たれやすくなります。
そのため、単に「働きたい」という意志だけでなく、将来の目標やキャリアプランを具体的に説明できることが重要になります。
企業は、採用した人材が長期的に活躍できるかを見極めるため、応募者の職業観や成長意欲を重視します。
「なぜこの業界・職種を志望するのか」「入社後にどのように成長し、会社に貢献していくのか」を明確に語れることが、採用につながる大きなポイントです。
また、既卒期間中にどのような活動をしていたかも評価の対象になります。
アルバイトや資格取得、自己学習、ボランティア活動などを通じて、自分のキャリアに役立つ経験を積んでいた場合、目的意識を持って行動できる人材として好印象を与えることができます。
既卒だからといって不利になるわけではなく、むしろしっかりとしたキャリアプランを持ち、成長意欲をアピールできれば、大きなチャンスにつながるのです。
入社意欲と熱意の量は十分か
既卒の場合、ポテンシャルの高さを重視されます。
単なる就職希望ではなく、「この企業で働きたい!」という強い意志を示すことが重要です。
企業側は、既卒者の採用に際して「すぐに辞めてしまわないか」「入社後にしっかり活躍できるか」を不安視することがあります。
そのため、志望動機や自己PRを通じて、長期的に企業へ貢献する意思や具体的なキャリアビジョンを伝えることが求められます。
また、熱意を示す方法として、企業研究を徹底し、他社ではなくその企業を選んだ理由を明確に伝えることが効果的です。
面接では、業界知識や企業の強みを理解した上で、自分がどのように貢献できるかを具体的に話すことで、採用担当者に好印象を与えられます。
「この会社で働きたい」という強い意欲と熱意こそが、既卒者の採用を左右する大きなポイントとなるのです。
人柄と企業文化がマッチしているか
社会人経験がない既卒者の場合、即戦力よりも長期的に成長できるかどうかが見られます。
そのため、企業は応募者の価値観や考え方が自社の文化に合っているかを慎重に判断します。
例えば、ベンチャー企業であれば、主体性やチャレンジ精神が求められるでしょう。
大手企業であれば協調性や組織の一員としての適応力が重視されます。
企業側としては、どんなにスキルがあっても、社風に合わない人材は定着しにくいと考えるため、「自社で長く活躍できるか」を見極めるのです。
また、既卒者は新卒に比べて就職活動の期間が長くなりがちですが、その間にどのような経験を積み、どのような考えを持ったのかを伝えることが重要です。
「この企業で働きたい理由」とともに、「自分の価値観が企業と合っていること」を具体的に示せれば、企業側も安心して採用を決断しやすくなります。
既卒が4月以降の就活でやるべきこと
既卒となってから就活を始める際、4月から綿密な計画を立てることが大切です。
まずは自分が就職したいと思う理想のタイミングをゴールとした上で、そこから逆算してスケジュールを立てましょう。
ここからは、就職活動における各ステップにやるべきことの詳細です。
参考にしてください。
就活スケジュールの設計
既卒者が4月以降に就活を始める際に、計画的にスケジュールを立てることが大切です。
就活は早くても3ヶ月ほど必要ですので、自分が就職したいと思う理想の時期から逆算して計画を立てましょう。
まず、1カ月目は自己分析と企業研究に充てましょう。
自分の強みや価値観を整理し、どの業界や職種が合っているのかを明確にします。
同時に、新卒枠や第二新卒枠で応募可能な企業のリストアップを行い、応募先を絞ります。
2カ月目は本格的な応募と面接対策です。
履歴書・職務経歴書をブラッシュアップし、企業ごとにカスタマイズすることが重要です。
また、模擬面接を通じて受け答えの精度を高め、自信を持って面接に臨めるようにしましょう。
この時期には春採用を行っている企業も多いため、積極的にエントリーを進めるのがポイントです。
3カ月目以降は選考を継続しつつ、秋採用の準備を進めます。
8月・9月には追加募集や秋採用が活発になるため、焦らず柔軟に対応しましょう。
また、ハローワークや転職エージェントを活用し、幅広い選択肢を持つことも重要です。
計画的に動くことで、4月以降でも十分に内定を獲得するチャンスがあります。
自己分析
就活の第一歩としてまず取り組むべきなのが自己分析です。
自己分析を行うことで、自分の強みや価値観を明確にし、企業選びや面接での自己PRに活かすことができます。
特に既卒の場合、「なぜこれまで就職しなかったのか」「この期間に何をしていたのか」を問われることが多いため、自分の経験や考えを整理しておくことが重要です。
自己分析の簡単なやり方は次の3つなので、ぜひ自分のノートなどに自由にまとめてみましょう。
学生時代や既卒期間に取り組んだこと(アルバイト、ボランティア、資格取得など)を書き出し、「なぜそれを選んだのか」「そこから何を学んだのか」を考えましょう。
2.自分の強みや価値観を整理する
「自分が得意なこと」「やりがいを感じること」「どんな環境で力を発揮できるか」を考え、企業選びの基準を明確にします。
3.他者の意見を取り入れる
これは周りに協力者がいることが前提ですが、友人や家族に「自分の長所」を聞いてみると自己分析の精度が上がります。
新しい視点で自分を見ることで、正しい判断をすることができるのです。
自己分析をしっかり行うことで、企業とのマッチ度を高め、納得のいく就職活動ができます。
キャリアプランの策定
自己分析の結果をもとに、「どんな仕事をしたいのか」「どのようにキャリアを築いていきたいのか」というキャリアプランを策定しましょう。
まずは自己分析で引き出した内容を整理し、自分の強みや興味のある業界・職種を整理しましょう。
過去の経験やアルバイト、ボランティア活動などから得たスキルや価値観を洗い出し、仕事にどう活かせるかを考えます。
そこからようやくキャリアプランの策定に入ります。
既卒者の場合は、中長期的にみて「5年後・10年後にどのような働き方をしたいか」をイメージし、そのために今どのような企業や職種を選ぶべきかを検討しましょう。
例えば、未経験からでも成長できる環境を選ぶのか、それとも専門性を活かせる業界を目指すのかなど、自分に合った方向性を定めます。
キャリアプランが明確になれば、志望動機や面接での受け答えにも説得力が生まれます。
単に「就職すること」が目的ではなく、「どんなキャリアを築くか」を意識することが、既卒の就活成功につながるポイントです。
就職エージェントへの登録
既卒の就活は何かと壁にぶつかることが多いですから、就活のプロであるエージェントの活用がおすすめです。
エージェントに登録すると、専任のキャリアアドバイザーがつき、自己分析や履歴書・職務経歴書の作成、面接対策までサポートしてくれます。
特に、既卒向けの求人を多く扱っているエージェントなら手厚いサポートのもと、自分に合った企業を効率よく見つけやすくなります。
また、エージェントを通じてしか応募できない「非公開求人」に出会えるのも大きなメリットです。
大手企業や成長企業の既卒歓迎求人は、一般の求人サイトには掲載されず、エージェント経由でのみ紹介されることが多いため、登録することで選択肢が広がります。
さらに、エージェントは企業との交渉も代行してくれるため、給与や入社時期の調整、面接の日程調整などの負担を軽減できます。
特に、就活経験が少ない既卒者にとって、プロのサポートがあることで安心して選考に臨むことができます。
既卒者におすすめのエージェントとしてアゲルキャリアがおすすめです。
既卒・第二新卒向けの求人を豊富に取り扱い、一人ひとりに合ったサポートを提供しています。
4月以降の就活は競争が少なく、チャンスが増える時期でもあります。
応募企業の精査
効果的な就活をするには、自分にマッチした企業をいかに効率良くかが大切です。
そのためには、あらかじめ応募先企業の条件を精査しましょう。
この時期は、大手企業の追加募集や中小企業の通年採用が活発になりますが、すべての企業が良質な職場環境を提供しているとは限りません。
特に、慢性的な人手不足により常に採用活動を行っている企業には注意が必要です。
応募前に、企業の離職率や労働環境を確認することが大切です。
口コミサイトや企業の公式HP、SNSなどを活用し、社員の働き方や社風をリサーチしましょう。
また、説明会や面接の場で「なぜこの時期に募集しているのか?」を企業側に質問することで、採用の背景を把握することもできます。
さらに、応募企業が既卒者の採用実績があるかどうかを確認するのもポイントです。
既卒者を積極的に受け入れている企業であれば、研修制度やサポート体制が整っている可能性が高く、入社後の適応もしやすくなります。
焦って就職先を決めるのではなく、長く働ける企業かどうかを見極めることが、既卒就活の成功につながります。
既卒が就職内定率を高めるための対策
応募先企業が決まったら、これまで以上に集中して選考対策をしましょう。
特に既卒就活の場合、同じ会社を受ける人が多いことが想定されます。
同じく既卒者もいますし、第二新卒という強力なライバルもいるでしょう。
これからご説明することを念頭に、綿密な就活対策をしましょう。
応募先企業の情報収集
応募先企業が決まってから実際にレジュメを送る前に、応募先企業をよく調査しましょう。
ただ応募数を増やすだけではなく、企業の特徴や採用方針を理解した上で対策をすることで、選考通過率を高めることができます。
まず、企業の公式HPや採用ページをチェックし、事業内容・社風・求める人物像を把握しましょう。
次に、口コミサイトや社員のSNS、転職エージェントの情報などを活用し、実際の職場環境や働き方について調べるのが効果的です。
特に、既卒者の採用実績がある企業を選ぶことで、入社後のサポートが期待できます。
また、企業研究をしっかり行うことで、面接時に「なぜこの企業を志望したのか?」という質問にも説得力を持って答えられます。
適切な情報収集を行い、自分に合った企業を選ぶことが、既卒就活成功のカギとなります。
行きたい業界の業界研究
いきたい業界が決まったら、業界研究を徹底しましょう。
業界の動向や将来性を理解することで、自分に合った企業を見つけやすくなり、効果的な志望動機を作成できるようになります。
まず、興味のある業界の市場規模や成長性、主要企業の特徴を調べましょう。
例えば、IT業界は成長が続いており、未経験でも学習意欲が評価されるケースがあります。
一方で、安定した業界を重視するなら、インフラや医療業界が選択肢に入るかもしれません。
また、業界ごとの採用基準や求められるスキルもリサーチが必要です。
例えば、営業職が多い業界ではコミュニケーション能力が重視される一方、技術職では専門知識の習得が求められることが多いです。
業界研究を通じて、自分の強みとマッチする分野を見つけることができれば、企業選びや面接の説得力が増し、内定率アップにつながります。
レジュメ対策
就活の第一関門が書類選考です。
レジュメにまとめる内容は、テンプレート通りではなく自分なりの言葉で具体的に仕上げましょう。
他の誰かと被らない、あなたならではの言葉をしっかり伝えることで、採用担当者の心を掴むことができます。
特に重要なのが、志望動機と自己PRの項目です。
具体的にどう伝えれば効果的にまとまるか、それぞれご紹介します。
志望動機対策
志望動機では、まず企業研究の情報をもとにその企業の魅力や共感した点を具体的に述べましょう。
その上で、自身の強みや経験がどう活かせるかを結びつけることで、説得力が増します。
例えば、「大学時代に培った分析力を活かし、貴社のマーケティング戦略に貢献したい」といった形です。
また、既卒期間の経験をポジティブに伝えることも重要です。
アルバイトや資格取得の経験を踏まえ、「この期間で得た学びが御社の業務に役立つ」とアピールすると好印象につながります。
「この企業だからこそ働きたい」という熱意を具体的に伝えることが、内定率アップのカギです。
自己PR対策
自己PRでは、「結論→具体的なエピソード→企業での活かし方」の流れを意識すると、説得力が増します。
たとえば、アルバイトやボランティア活動、資格取得などの経験を交え、「自主的にスキルを磨く姿勢がある」とアピールすると好印象です。
また、企業が求める人物像を理解し、それに合った強みを強調することも大切です。
「この会社だからこそ活かせる自分の強み」を伝えられれば、内定率を高めることができます。
既卒の就活はエージェントの活用がおすすめ
エージェントを活用するメリットは、履歴書・職務経歴書の添削や面接対策、非公開求人の紹介など、自己応募では得られないサポートを受けられる点です。
また、既卒の就活では「どの時期に動くか」も重要ですが、エージェントを通じて最新の求人動向を知ることで、より良いタイミングで応募できます。
特に既卒者におすすめのエージェントが、アゲルキャリアです。
アゲルキャリアは既卒・フリーター・第二新卒に特化したエージェントなので、未経験でも就職しやすい企業を紹介してもらえます。
また、アゲルキャリアなら最短2週間での内定獲得も可能なので、今すぐ相談してみるのがおすすめです。
特に4月以降は新卒採用が一段落し、既卒枠の求人が増える時期です。
このタイミングでエージェントを利用し、効率的に就活を進めましょう。
まとめ
既卒の就活は新卒に比べるとぐんとハードルが上がりますが、綿密なスケジュールと徹底した事前準備をすれば、内定に近づけることができます。
就職する時期を目標として決めた上でスケジュールを立てましょう。
そして、自己分析と企業研究、業界研究をしっかり行った上で選考対策に入りましょう。
また、既卒が企業にアピールする際、「既卒となった理由」を問われることがよくあります。
この時にネガティブな背景が垣間見えないようにすることも注意点です。
キャリアプランなども踏まえた上で、ポジティブな回答ができるようにまとめておきましょう。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!