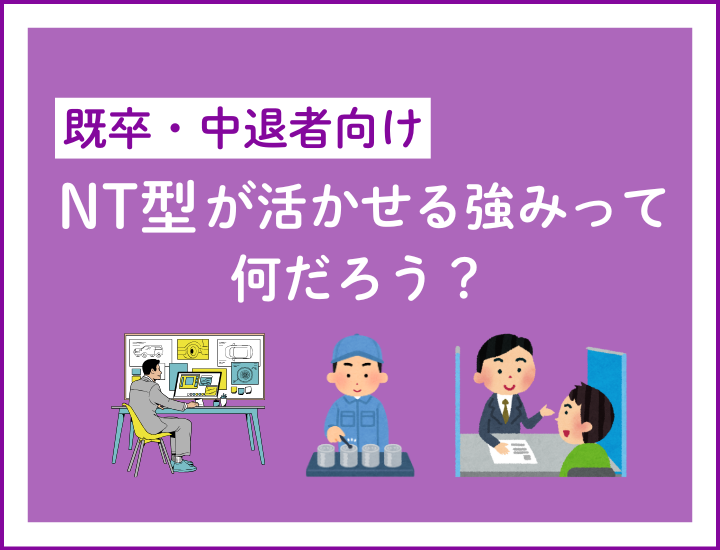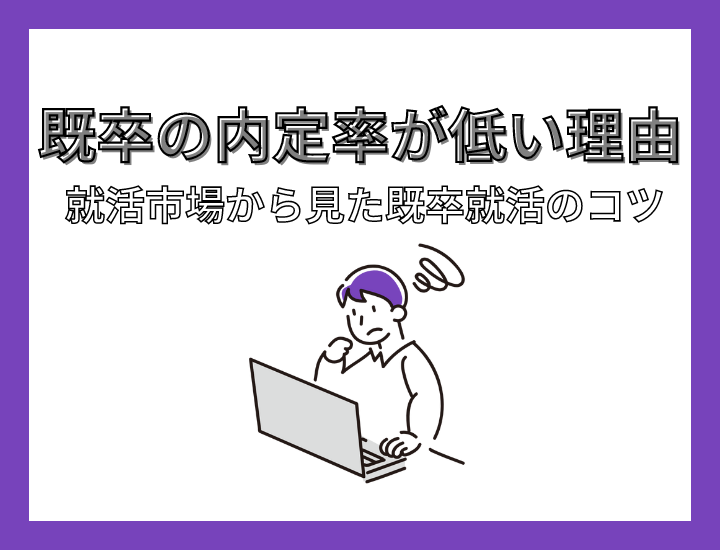
【2025年版】既卒者の内定率|営業職を視野に入れた就活のコツも紹介
はじめに
既卒者として営業職への就職を検討している方に向け、2024年度の内定率や効果的な就職活動のポイントについて解説します。
近年、企業の採用傾向は変化し、既卒者を積極的に採用する企業が増加しています。
営業職においては、経験やスキルよりも、意欲や適性が重視される傾向にあるため、既卒者でも十分に内定を得るチャンスがあるのです。
本記事では、既卒者の定義や営業職の特徴、2024年度の内定率の実情、そして成功につながる就職活動の方法まで、幅広い内容を網羅しています。
これから就職活動を始める方はもちろん、すでに活動中の方にも役立つ情報を提供しています。
営業職への就職を目指す既卒者の方々にとって、有益な指針となれば幸いです。
【既卒における営業の内定率】既卒とは
既卒とは、学校卒業後に正職員としての就労経験が一度もない人を指します。
卒業後にアルバイトや無職の状態で過ごした場合も、正職員として働いた経験がなければ、既卒とされます。
年齢による区分はありませんが、多くの企業が「卒業後3年以内」の既卒者を採用対象としているのが現状です。
正社員としての就職を目指すのであれば、アルバイト生活に甘んじることなく、早期に就職活動を始めることが重要です。
新卒との相違点
既卒者と新卒者の大きな違いは、卒業後の就業経験の有無です。
新卒者は卒業後すぐに就職活動を行い、企業は将来性を評価して採用します。
一方、既卒者は卒業後に就職活動を行わなかったため、正職員としての経験がありません。
企業は、既卒者に対して「なぜ新卒時に就職しなかったのか」と疑問を抱くことが少なくありません。
そのため、既卒者は就職活動において自己分析やスキル向上を通じて、自らの成長をアピールし、企業の疑念を払拭することが大切です。
ただし、近年では既卒者を新卒者と同等に評価し、採用する企業も増えています。
既卒者は、新卒者よりも自己分析や企業研究に時間をかけている場合があり、その点を高く評価する企業も存在します。
第二新卒との相違点
既卒と第二新卒は似ていますが、定義が異なります。
既卒は学校卒業後に正職員として働いた経験がない人を指すのに対し、第二新卒は新卒入社後、3年以内に退職した人を意味します。
第二新卒は、短期間ながら正職員としてのキャリアがあるため、就職市場での評価は既卒者よりも高い傾向にあります。
したがって、既卒者が就職活動を行う際には、第二新卒が競合として立ちはだかる可能性がある点に留意が必要です。
フリーターとの相違点
既卒者とフリーターの違いは、就業経験の有無です。
どちらも学校を卒業していますが、フリーターはアルバイトやパートタイムでの就業経験がある点が異なります。
フリーターは、自分の都合に合わせて働けるのが特徴ですが、既卒者は正職員としての就業経験がありません。
そのため、企業が就労意欲や能力に懸念を抱く場合があります。
しかし、自己分析やスキルアップを通じて成長を示すことで、既卒者も内定を得る可能性は十分にあります。
【既卒における営業の内定率】2024年卒の就活市場
「2024年卒の就職・採用市場」のデータを見ると、2024年卒の就職・採用市場は、引き続き学生優位の状況にあります。
2024年3月卒業予定の大学生および大学院生の大卒求人倍率は1.71倍となり、2023年卒の1.58倍から0.13ポイント増加しました。
コロナ禍以前の2019年卒(1.88倍)、2020年卒(1.83倍)の水準に近づいています。
従業員規模別に見ると、全規模で求人総数が増加しており、企業の採用意欲が堅調に伸びていることがわかります。
特に、従業員数が「300人未満」の企業では、2023年卒の増加率0.5%から、2024年卒では11.6%と大幅な増加が見られました。
大学生の就職内定率も高水準を維持しています。
2024年卒の大学生は、3月卒業時点で96.8%の内定率を記録し、2022年卒(96.4%)および2023年卒(96.8%)とほぼ同水準でした。
月別推移では、調査開始時点の2月1日から前年を上回る水準で推移しており、企業が早期に内定を出している傾向がうかがえます。
6月1日時点の内定率は79.6%で、6月選考解禁後(2017年卒以降)では最も高い数値となりました。
データから見てもわかるように、2024年卒の就職・採用市場は学生にとって有利な状況です。
ただし、従業員数「5,000人以上」の大手企業においては求人倍率が0.41倍と、依然として就職希望者数が求人総数を大きく上回っており、大手企業への就職は依然として狭き門となっています。
既卒の内定率
2024年の既卒者の内定率は、マイナビの調査によると、2024年の既卒者の内定率は34.8%という結果が出ています。
一方、同時期における大卒者の就職率は98.1%であり、既卒者が厳しい状況に置かれていることが明らかです。
既卒者の就職活動が困難な背景には「企業側の既卒者に対するマイナスイメージ」や「既卒者向け求人の不足」といった要因が挙げられます。
しかしながら、近年では既卒者を積極的に採用する企業が増加しており、政府も既卒者採用を支援する施策を導入しています。
環境の変化に加え、自己分析やスキル向上、企業研究など適切な対策を講じることで、既卒者も内定を獲得できる可能性は十分にあります。
【既卒における営業の内定率】既卒就活が厳しい理由
既卒者の就職活動が厳しいとされる背景には、企業が既卒採用に対してあまり重要性を感じていないという点が挙げられるでしょう。
多くの企業が新卒採用を中心に考えているため、既卒枠を設けていなかったり、採用担当者が懸念を抱いて不採用にするケースが見られます。
以下に、既卒就活が厳しいとされる具体的な理由を3つのポイントにまとめて解説します。
既卒採用をしている企業が少ないから
大半の企業は新卒採用に注力しており、春の新卒採用で人材が充足することが多いため、既卒採用に力を入れる必要がないのが現状です。
既卒採用を行う企業も存在しますが、主に新卒採用枠が定員割れした場合に限られます。
多くの企業が人手不足に直面しているとはいえ、若手人材を採用する際は、新卒として一斉に育成する方が効率的だと考えられています。
中途採用枠で不利になるから
既卒者が就職活動を行う際、通年採用や秋採用を実施する企業に応募することが一般的です。
しかし、キャリアのある転職者が多く応募している枠でもあります。
転職者は他企業での社会経験やスキルを持っているため、経験のない既卒者にとっては非常に強力な競争相手となります。
新卒者と異なり、計画的な育成が難しく、転職者と比べてスキルや即戦力としての魅力が乏しい点で、不利な立場に置かれがちです。
卒業後の空白期間に懸念する採用担当者もいるから
採用担当者の中には、既卒者に対して空白期間に疑念を抱く人もいます。
卒業後の期間に何をしていたのか、なぜ新卒で就職しなかったのかという点に対して、マイナスの印象を持たれることがあります。
例えば、留学などキャリアに繋がるポジティブな理由で既卒となった場合は問題ありませんが、特に理由のない空白期間がある場合、採用担当者の不安要素となることが少なくありません。
すべての採用担当者がそうではありませんが、既卒者を積極的に採用する企業以外では、懸念を払拭する努力が必要です。
【既卒における営業の内定率】企業からの印象
ここでは、既卒者が営業職を目指す際に知っておくべき企業の印象と、内定率を向上させるための具体的な方法について解説します。
営業職は既卒でも内定を獲得しやすい?
既卒者が営業職を目指す際に気になるのは、「他の職種と比較して内定率が高いのか」という点です。
結論として、営業職は他の職種に比べ、既卒者でも内定を獲得しやすい傾向にあります。
理由として、営業職は慢性的な人材不足が挙げられます。
近年、多くの企業が人材確保に注力しており、特に顧客との関係構築を担う営業職は、企業の成長において重要な役割を果たすため、積極的な採用が行われているのです。
さらに、営業職は「人物重視」の採用傾向が強いことも、既卒者にとって有利な点です。
企業は過去の職務経験よりも、コミュニケーション能力や熱意、目標達成への意欲といった素質を重視する傾向にあります。
そのため、新卒時に就職できなかった場合でも、自己分析やスキル向上を通じて成長をアピールすれば、内定を得るチャンスは十分にあると言えるでしょう。
企業は既卒の営業職志望者をどう見ている?
企業の既卒者に対する印象は、ポジティブな側面とネガティブな側面が共存しています。
若手人材である既卒者を有望と捉える一方で、「なぜ新卒時に就職しなかったのか」と疑問を持たれることもあります。
ポジティブな評価としては、以下のとおりです。
- 企業理念や事業内容に共感し自らの意思で入社する姿勢
- 新卒者より早期に入社できる柔軟性
ただし、以下のようなネガティブな評価もあります。
- 人柄に問題があるのではないか
- 仕事への熱意や継続力が欠けているのではないか
ネガティブな印象を払拭するためには、次の対策が有効です。
- 自己分析の徹底:自身の強みや成長ポイントを明確にする
- 企業研究の実施:志望動機を明確にし、なぜその企業で営業職として働きたいのかを伝える
- 面接対策:既卒になった理由を正直に説明し、どのように成長したのか具体的にアピールする
上記を意識することで、企業側の不安を軽減し、好印象を与えることが可能です。
【既卒における営業の内定率】営業職とは
営業職は、企業に利益をもたらす重要な役割を担う職種です。
自社のサービスや商品を顧客に提案・販売し、契約を獲得することが主な業務となります。
しかし、単に「購入してください」と勧めるだけでは商談は成立しません。
契約に至るためには、アポイントを取り、顧客の潜在的なニーズを把握し、その課題に対する解決策を提案するプロセスが必要です。
営業職には、法人向けのBtoB(Business to Business)営業と、一般消費者向けのBtoC(Business to Consumer)営業があり、さらに働き方にはさまざまな種類があります。
例えば、ルート営業や飛び込み営業、電話でアポイントを取るテレアポ、電話やメールを活用するインサイドセールスなどです。
また、基本給に加え、契約数に応じた歩合制を採用するケースも多く見られます。
BtoCの営業
BtoC(Business to Consumer)営業は、一般消費者を対象に行う営業活動です。
購入の主体が消費者自身であり、利用者でもあるため、多様なニーズや要望に柔軟に対応する必要があります。
BtoC営業では、購入動機が合理性よりも感情に依存する傾向にあります。
消費者は自身の欲求・好み・経験・感情に基づいて購買判断を行うため、感情的な訴求が重要です。
近年、BtoCの購買行動はオンライン化が進んでいます。
インターネットやスマートフォンの普及により、消費者はオンラインで商品やサービスを検索・比較し、購入するケースが増加しています。
そのため、BtoC営業では、Webサイトやソーシャルメディア、メールマーケティングなど、オンラインプラットフォームを活用した営業手法が不可欠です。
BtoBの営業
BtoB(Business to Business)営業は、企業が法人を対象に行う営業活動です。
決裁者や意思決定者と実際の利用者が異なる点が特徴であり、広い視野と専門知識が求められます。
BtoB営業では、自社のサービスや商品が企業にどのような利益やメリットをもたらすのかを明確に伝えることが重要です。
主な手法としてはルート営業が挙げられ、営業担当者は定期的に顧客を訪問し、長期的な信頼関係を構築します。
企業間の取引は複雑であるため、営業担当者には顧客のニーズを深く理解し、適切な提案を行うスキルが求められます。
専門知識を提供し、顧客の課題解決をサポートすることで、信頼関係を築き、継続的な取引へとつなげていくことが重要です。
【既卒における営業の内定率】主な業務
営業職は企業に利益をもたらす重要な職種ですが、具体的な業務内容について理解が曖昧な方もいるかもしれません。
営業には、個人向け(BtoC)と法人向け(BtoB)があり、営業スタイルは顧客対象や手法によって異なります。
しかし、業務内容に関しては大きく「新規顧客開拓」と「既存取引先への営業」に分類されることを覚えておきましょう。
新規顧客開拓
新規顧客開拓とは、これまで取引のなかった潜在顧客にアプローチし、新たな取引先を獲得する業務です。
ビジネスの成長には、新規顧客の開拓が不可欠です。
新規顧客を獲得するための手法には、以下のようなものがあります。
- 飛び込み営業:指定した地域を訪問し、直接資料を持参して提案する方法
- テレアポ:リストに基づき電話をかけ、商談のアポイントを取る手法
- メール営業:見込み顧客に対してメールで提案を送付する方法
- 問い合わせフォーム活用:企業の公式Webサイトのフォームからのアプローチ
- セミナー・勉強会:イベントを通じて顧客と接触し、商談につなげる方法
- SNS営業:SNS上の公開プロフィールを活用し、メッセージでアポイントを取る手法
ただし、新規顧客開拓は拒絶されることが多く、飛び込み訪問や電話営業では門前払いされるケースも少なくありません。
そのため、精神的な負担を感じやすい業務とも言えます。
既存取引先への営業
既存取引先への営業は、いわゆるルート営業と呼ばれる手法です。
新規開拓とは異なり、すでに取引関係のある顧客に対して営業活動を行います。
ルート営業の主な業務内容には、以下のようなものがあります。
- 現状確認・点検:過去に提案・納品した商品やサービスの状況を確認する
- 課題解決提案:顧客の課題やニーズを把握し、最適な商品や戦略を提案する
- 新商品の提案:オプション製品や新商品を紹介し、追加の契約を促進する
- 資料作成・事務作業:提案資料や見積書の作成、注文処理や社内報告書を作成する
ルート営業では、顧客との信頼関係を築き、維持することが何より重要です。
長期的な取引を実現するためには、顧客の要望に真摯に対応し、適切なサポートや提案を行う姿勢が求められます。
【既卒における営業の内定率】向いている人の特徴
営業職は結果が重視される職種ですが、単に商品やサービスを販売するだけでは十分ではありません。
顧客の意思を尊重せずに強引に売り込めば、後にクレームや契約破棄につながるリスクがあります。
そのため、緊張感を持ち、顧客に最大限配慮しながら業務に取り組む姿勢が求められるのです。
ここでは、営業職に向いている人の特徴を紹介します。
コミュニケーション能力がある
営業職は顧客と直接向き合う職種のため、コミュニケーション能力は欠かせません。
ビジネスにおけるコミュニケーション能力は、単に誰とでも打ち解ける力ではなく、以下の要素が含まれます。
- 論理的かつ具体的に説明する提案力
- 顧客の潜在的なニーズを引き出す傾聴力
顧客のニーズを的確に引き出せなければ、適切な提案ができず、成約には至りません。
また、相手の理解度や感情を察知する能力も重要です。
例えば、提案中に顧客が不安そうな表情を見せた場合は「ここまででご不明点はございますか?」と声をかけましょう。
また、顧客が不快な様子であれば、すぐに察知して謝罪するなど、状況に応じた柔軟な対応が求められます。
キャッチアップの感度が高い
常に最新の情報を収集し、迅速に取捨選択できる人も営業職に適しています。
現代は情報が急速に更新されるため、効率よく必要な情報を集め、不要な情報を見極める能力が必要です。
情報感度が高い人は、質の高い情報を先取りし素早く行動に移せるため、業務の質やスピードが向上しやすい傾向にあります。
日頃から様々な事柄に関心を持ち、情報収集の習慣がある人は、優れた営業職としての素質を備えていると言えるでしょう。
ストレス耐性がある
営業職は、ストレスを感じる場面が多い職種です。
飛び込み営業やテレアポで断られる、商談がうまく進まない、契約寸前で失注するなど、思い通りにいかない状況は日常的に発生します。
そのため、ストレスに適応し、迅速に切り替えられる力が求められます。
たとえ厳しい対応を受けても、「断られても当然」と割り切り、前向きに業務を続けられる人が営業職に向いているのです。
また、苦しい状況が続いても耐えられる忍耐力や、仕事とプライベートをしっかり切り替えられる能力も重要です。
業務中は集中し、帰宅後や休日にはリフレッシュするなど、メリハリをつけられる人はストレス耐性に優れた営業職となるでしょう。
【既卒における営業の内定率】働くメリット
営業職は既卒者でも比較的内定を獲得しやすい職種ですが「離職率が高い」「仕事がきつそう」といったマイナスイメージから、応募をためらう人も少なくありません。
確かに、顧客のペースに合わせながら毎月のノルマを達成する必要があるため、厳しさを感じる場面は多いでしょう。
しかし、営業職で得られるメリットは、デメリットを上回る魅力があります。
ここでは、営業職で働くことで得られる主なメリットを3つ紹介します。
どの企業でも経験が活きる
営業職の大きなメリットは、身につけたスキルやノウハウが他の企業でも活かせる点です。
営業活動で培うスキルは、業界や職種を問わず必要とされるものです。
例えば、クライアントとの文書作成や対面でのやり取りを通じて、基本的なビジネスマナーが自然と身につきます。
また、営業活動では企画やマーケティング部門などとも連携するため、企業全体の業務フローを理解する力が養われます。
さらに、成果を出せる営業職は、他企業からのヘッドハンティングや好待遇のオファーを受ける可能性もあるでしょう。
企業とのミスマッチを感じた場合でも、転職しやすいという点は大きな利点です。
能力次第で収入がアップする
「努力した分、収入に反映してほしい」と考える方には、営業職は非常に適した職種です。
多くの企業では、基本給に加えてインセンティブ制度が設けられています。
インセンティブは「歩合給」「出来高給」「業績手当」などとも呼ばれ、契約件数や売上が一定基準を超えると追加で支給されます。
年次や役職に関わらず、成果次第で収入が増える仕組みです。
ただし、基本給が少なく、成績によって給与が大きく変動することもあります。
そのため、金銭的な報酬にやりがいを感じ、成果を出すために努力できる方には最適です。
人脈を増やせる
営業職では、社外の多様な人と関わるため、人脈を広げやすい点がメリットです。
顧客や取引先との関係だけでなく、同僚が持つ顧客とのつながりも人脈の一部となります。
人脈が広がれば、営業活動において思わぬタイミングでチャンスが生まれたり、ノルマ達成が難しい時に助けとなったりする可能性があります。
また、将来的に転職を検討する際にも、人脈がサポートしてくれることもあるでしょう。
日常業務だけでなく、異業種交流会やセミナーに参加したり、SNSを活用したりすることで、さらに人脈を広げることも可能です。
【既卒における営業の内定率】営業職がおすすめの理由
既卒者の就職活動は、新卒者と比較すると不利な立場に置かれることが多いのは事実です。
卒論や病気療養など正当な理由があったとしても、新卒ではないというだけで就職市場での競争は厳しくなります。
ここでは、営業職がおすすめとされる理由を2つ紹介します。
求人数が多い
営業職は他の職種と比べて、求人数が圧倒的に多いことが特徴です。
営業職が企業活動において、欠かせない役割であるためです。
企業が業績を伸ばしたり、新規事業を展開したりする際には、必ず営業人員の確保が必要になります。
また、既存の契約が永続的に続く保証はないため、新規顧客の開拓を続けなければ業績を維持できません。
そのため、多くの企業が毎年営業職の採用を行っています。
さらに、営業職は離職率が比較的高い点も求人数が多い要因です。
顧客への対応やノルマ達成のプレッシャー、取引先に合わせた不規則な勤務時間など、精神的・肉体的に負担が大きい職種であることは否めません。
そのため、企業は一定期間内に離職する可能性を見越し、積極的に人材を採用しています。
経験・スキルが乏しくても挑戦できる
営業職は、他の職種に比べて特別な資格や高度なスキルが求められない点も特徴です。
営業職で最も重要とされるのは、最終的に成果を出す力です。
もちろん、営業職に必要とされるスキルは多岐にわたりますが、資格や過去の経験よりも、コミュニケーション能力や目標達成への意欲が重視される傾向にあります。
たとえ経験が浅くても、基本的なスキルを習得し、やる気と実力があれば成果を上げることは可能です。
結果を出せば、年次に関係なく評価され、ベンチャー企業など実力主義の職場では早期に役職に就くこともあります。
このため、経験が少ない既卒者であっても、やる気やポテンシャルを示せれば内定を獲得しやすい職種と言えるでしょう。
【既卒における営業の内定率】既卒を積極採用している企業が増加
既卒者の就職活動は依然として厳しい状況にありますが、近年では既卒者を積極的に採用する企業が増加傾向にあります。
背景に挙げられるのは、企業が抱える深刻な人手不足です。
特に、大手企業や知名度の高い企業を除き、多くの企業が採用枠を充足できず、既卒者の採用に目を向けるケースが増えています。
さらに、少子高齢化の進行により、若手人材の不足が深刻化していることも要因です。
ゼロベースであってもポテンシャルと熱意を持ち、スキルアップを目指す若手人材は、企業の将来にとって貴重な存在です。
新卒採用で人材が確保できない場合、企業は既卒者の採用に力を入れ始めます。
既卒者の採用を行う企業に焦点を絞って就職活動を行えば、自分に合った優良企業に出会える可能性が高まるでしょう。
卒業後3年以内なら新卒枠で応募できる
厚生労働省は「3年以内既卒者は新卒枠で応募受付を!!」という方針を打ち出し、学校卒業から3年以内の既卒者に対して新卒枠での応募を認めるよう呼びかけています。
そのため、新卒採用の機会を逃した場合でも、卒業から3年以内であれば、新卒枠で再チャレンジすることが可能です。
呼びかけの背景には、日本の労働人口の減少があります。
優秀な人材は大手企業に集中しがちであり、中小企業は慢性的な人手不足に悩んでいます。
対策として、既卒者を新卒と同等に扱い、新たな人材として歓迎する企業が増えているのです。
既卒者はこうした制度を積極的に活用し、就職活動に取り組むことで、内定獲得のチャンスを広げられるでしょう。
【既卒における営業の内定率】就活のコツ
既卒者が効率よく内定を獲得するためには、計画的に就職活動を進めることが重要です。
これから就活を始める方、また現在苦戦している方も、各フェーズでつまずかないよう、以下のポイントを押さえましょう。
早めの行動を心がける
既卒であることに不安を感じ、行動を先延ばしにしていてはライバルに先を越されてしまいます。
新卒のタイミングで就職活動に間に合わなかった経験がある場合、同じ失敗は繰り返さないようにしましょう。
現時点で可能なことから始めることが大切です。
就職エージェントへの登録や求人のリサーチなど、できることから早めに取り組みましょう。
スケジュールを立てる
就職活動で内定を獲得するには、最短でも3か月ほどの期間が必要です。
求人のリサーチ、企業研究・自己分析・面接対策・履歴書・職務経歴書の準備など、多くのタスクが発生します。
焦りから無計画に行動すると、失敗のリスクが高まります。
「3か月後に内定を獲得する」という目標を設定し、スケジュール帳に具体的な計画を落とし込みましょう。
計画性を持つことで、効率的に就職活動を進められます。
卒業後の空白期間を説明できるようにする
面接では必ずと言っていいほど「卒業後の空白期間」について質問されます。
採用担当者が懸念を抱かないよう、空白期間をポジティブな理由として説明できるように準備しておきましょう。
- 語学を活かした仕事を目指し、海外留学をしていた
- 志望企業の選考に漏れたため、再チャレンジを目指していた
- 内定を得たものの、希望業界を目指すために辞退した
説明後には「経験を通じてどう成長したか」「今後どのように活かしていくか」を伝えることが重要です。
具体的なアピールができれば、企業の懸念を払拭できます。
既卒採用に積極的な企業を選ぶ
既卒採用に積極的な企業を優先的に受けることで、内定獲得の可能性が高まります。
通年採用やキャリア採用を行う企業は、新卒採用を中心とする企業よりも既卒者に対する理解が深い傾向にあります。
- 平均年齢が20代のベンチャー企業
- 求人情報に「既卒歓迎」と記載されている企業
- 人手不足が顕著な業界(飲食・介護など)
まずは上記に該当する企業に焦点を絞り、内定獲得を目指しましょう。
理想とする企業や条件がある場合はまず就職し、経験を積んだ後にキャリアアップ転職を検討するのも一つの戦略です。
スキル・資格を取得する
既卒者は、スキルや資格を取得することで「即戦力」としてのアピールが可能です。
企業側が抱く「就労意欲の低さ」や「能力不足」といった懸念を払拭する手段となります。
- MOS(Microsoft Office Specialist):基本的なパソコンスキルを証明
- 簿記2級以上:財務知識の理解を示す
- TOEIC:英語力を客観的に示し、外資系やグローバル企業で有利
- 宅地建物取引士(不動産業界)
- ファイナンシャルプランナー(金融業界)
- 基本情報技術者(IT業界)
上記の資格を取得することで、専門スキルを証明し、就職活動を有利に進められます。
さらに、コミュニケーション能力やビジネスマナー、行動力といった基本的なスキルも磨いておきましょう。
資格取得と並行して、自己分析や企業研究、面接対策も進めることで、総合的な準備が整い、内定獲得の可能性が高まります。
【既卒における営業の内定率】選考対策のステップ
既卒者が効率よく内定を獲得するためには、計画的に選考対策を進めることが重要です。
就職活動を始めてから内定を得るまでには、早くても3か月程度かかります。
ゴールを3か月後に設定し、各ステップを計画的に進めましょう。
1.自己分析
自己分析は新卒時にも経験した方が多いかもしれませんが、既卒としての就活においても欠かせません。
自分自身の現状や強みを正確に把握し、面接で説得力のある回答ができるよう準備しましょう。
学生時代の自己分析結果を見直すことで、忘れていた経験や新たな発見があるかもしれません。
今の自分をリアルに分析し、より効果的なアピールを可能にしましょう。
2.スケジュール立案
就職活動を効率よく進めるには、明確なスケジュールを立てることが重要です。
以下のポイントを考慮して計画を立てましょう。
- 開始時期:できるだけ早いタイミングで就活を開始する
- 内定獲得の目標時期:3か月後を目安に設定する
- タスク管理:求人探し・企業研究・自己分析・面接対策など、各タスクの締切を明確にする
- ツール活用:ExcelやGoogleスプレッドシートで進捗管理を行う
計画性が甘いと行動が遅れがちになるため、目標から逆算して具体的なスケジュールを作成しましょう。
3.業界研究
業界研究は、希望する業界の動向や市場のニーズを理解するために重要です。
以下の方法で情報を収集しましょう。
- ビジネス系ニュースサイトで業界関連のキーワードを検索する
- 業界団体の公式ホームページを確認する
- 業界トップ企業が出版する書籍やレポートを読む
業界研究を深めることで、面接での「業界志望理由」や「業界に対する見解」について具体的な回答ができるようになります。
4.企業研究
応募先企業の情報を網羅的に調べ、志望動機や自己PRに具体性を持たせましょう。
企業研究によって、以下のポイントを明確にできます。
- 志望する理由はなにか
- なぜ他社ではないのか
- 自分のスキルや経験をどう活かせるか
企業の公式サイトや企業出版物を活用し、詳細な情報を収集しましょう。
5.求人案件探し
求人を探す際は、「既卒歓迎」のキーワードに注目しましょう。
また、自分が譲れない条件(労働環境・休日・勤務地など)も考慮しながら検索すると効率的です。
就活サイトの活用はもちろん、就職エージェントに相談するのも有効です。
キャリアアドバイザーが適性に合った求人を紹介してくれるため、ミスマッチを防げるでしょう。
6.選考書類の作成
選考書類は、採用担当者が最初に目にする重要な判断材料です。
書類選考を通過するためには、見た目の印象と内容の質を意識して作成することが大切です。
見た目のポイント
適度な余白を設け、丁寧な文字で記入することで、清潔感や誠実さを伝えましょう。
バランスの取れた構成で、読みやすさを意識し、句読点も適切に配置します。
また、誤字脱字は厳禁です。
修正液や消せるボールペンは使用せず、ミスがあれば書き直しましょう。
内容のポイント
自己PRは効果的に行いましょう。
「資格」や「趣味・特技」欄は人柄をアピールする重要な要素です。
また自己PRには、具体的なエピソードや周囲からの評価を含めると説得力が増します。
採用担当者の視点で読み返し、内容が明確でわかりやすいか確認しましょう。
7.面接対策
面接で良い印象を残すには、想定される質問に対する回答を準備することが重要です。
基本的な質問に対する回答を用意し、面接に臨みましょう。
- 自己紹介をしてください
- 志望動機は何ですか
- この業界を選んだ理由は何ですか
- あなたの長所を教えてください
- 逆に短所だと思うことはありますか
- 他に受けている会社はありますか
また、業界特有の質問や、時事ネタに関する質問がされることもあります。
その際、業界研究や企業研究で得た知識が役立ちます。
面接に備え、最新の業界ニュースや志望企業に関連する情報を把握しておきましょう。
準備を徹底することで、説得力のある回答ができ、自信を持って面接に臨めます。
まとめ
既卒者が営業職を目指すことは、決して不利な状況ではありません。
むしろ、社会人としての経験や成熟した人間性が高く評価される可能性があります。
重要なのは、早めに行動を開始し、計画的に就職活動を進めることです。
自己分析・企業研究・面接対策といった各ステップを丁寧に進めることで、内定獲得の可能性は大きく高まります。
営業職は求人数が多く、特別な経験がなくても挑戦しやすい職種です。
さらに、近年では既卒者を積極的に採用する企業も増加しています。
自信を持ち、計画的に就職活動を展開することで、納得のいく就職先を見つけられるでしょう。
SHARE この記事を友達におしえる!