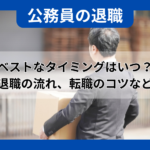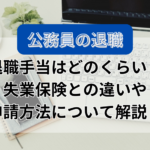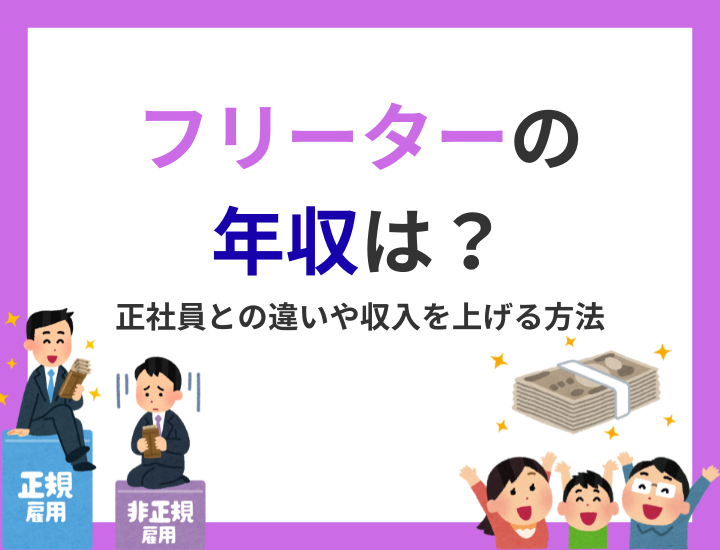公務員がボーナスをもらい退職するのはベスト?おすすめの時期から転職のコツまで詳しく解説
- 【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】公務員のボーナス支給時期
- 【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】退職のタイミングはいつがベスト?
- 【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】5月・12月退職のメリット
- 【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】退職手当の計算方法
- 【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】公務員のボーナスの平均支給額
- 【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】今一度公務員を辞めるリスクを考えよう
- 【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】公務員からの転職で年収が下がるケース
- 【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】公務員から転職した方が良いパターン
- 【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】転職で年収を落とさないためのコツ
- まとめ
「公務員として働いているけれど、退職のタイミングでボーナスをもらえるのか心配…」と感じている方もいるでしょう。
また、「退職後に転職しても年収が下がらないか不安だな…」という悩みもあるかもしれません。
退職や転職は人生の大きな節目であり、特に公務員としてのキャリアを考えるとき、ボーナスを含めた退職のタイミングは重要なポイントです。
この記事では、公務員の方が最適な退職時期を見極めるために、
- ボーナスをもらうタイミング
- おすすめの退職時期
- 年収を落とさない転職のコツ
について、解説しています。
退職を考える際に、ボーナスや転職後の年収についての不安を抱えることは自然なことです。
しかし、しっかりと情報を集めて準備をすれば、最適な選択ができるでしょう。
ぜひ参考にしてください。
【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】公務員のボーナス支給時期
公務員のボーナス支給時期は、各地方自治体によって決まっています。
ここからは、
- 夏のボーナスがもらえる時期はいつ?
- 冬のボーナスがもらえる時期はいつ?
- 【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】一般企業との違い
- 一般企業との違い
- 賞与や査定期間
について解説します。
夏のボーナスがもらえる時期はいつ?
一般的に、夏のボーナスは6月末から7月初めに支給されます。
この時期に支給される理由は、年度の始まりである4月から数ヶ月が経過し、業務の成果や業績がある程度評価できる時期であるためです。
公務員のボーナスは、基本給や勤続年数、評価などに基づいて計算されるため、支給額は個人差があります。
冬のボーナスがもらえる時期はいつ?
冬のボーナスは、12月頃です。
具体的な支給日は自治体や職種によって異なりますが、通常は12月中旬から下旬にかけて支給されます。
この時期にボーナスを受け取るためには、退職時期を慎重に考慮しましょう。
ボーナスをもらった後に退職したい場合、ボーナスを受け取ってからの退職が最適です。
また、ボーナスを受け取るためには、支給日まで在職していることが条件となるため、退職のタイミングを慎重に計画しておきましょう。
【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】一般企業との違い
公務員と一般企業では、ボーナスの支給基準や査定期間に違いがあります。
これらの違いを知ることで、退職のタイミングを見極める手助けとなるでしょう。
ここからは、一般企業と公務員の退職時期におけるボーナスの違いについて解説します。
一般企業との違い
公務員と一般企業のボーナス支給における違いは、まず支給の基準にあります。
公務員のボーナスは国家や地方自治体の財政状況や法律に基づいて決定され、安定していることが特徴です。
一方、一般企業のボーナスは企業の業績や個人の評価に大きく依存します。
一般企業では業績が悪化すればボーナスが減額されたり支給されない場合もあります。
さらに、査定期間にも違いがあります。
公務員は通常、半年ごとの査定期間が設けられており、これに基づいて夏と冬にボーナスが支給されます。
一般企業では、査定期間が異なる場合も多く、企業ごとに独自の基準が設けられています。
賞与や査定期間
公務員のボーナスは、通常、夏と冬の年2回支給され、支給額は法律で定められた基準に基づいています。
査定期間は、一般的に4月から翌年の3月までの1年間で行われ、業務の評価や勤務態度が反映される形です。
公務員のボーナスは安定している分、査定が厳しいと感じる方もいるかもしれません。
しかし、実際には評価基準が明確で、予測しやすいのが特徴です。
一般企業では、業績や個人の成果に大きく左右されることが多いですが、公務員の場合は、組織全体の業績よりも個人の勤務評価が重視されます。
このため、安定した収入を求める方には魅力的な制度といえるでしょう。
【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】退職のタイミングはいつがベスト?
公務員を退職する際、ボーナスを視野に入れるならベストなタイミングは5月末です。
公務員の給与条例については、期末・勤勉手当は、基準日(6/1,12/1)前1箇月以内に退職した職員についても同様とするとされています。
つまり5月末に退職すれば、ボーナスを満額近く支給されるということです。
6月以降でもほぼ満額でボーナスを受け取れますが、社会保険料控除の関係により、結果として5月31日がお得になります。
冬のボーナスでも十分な額を受け取れますが、退職金が1年分計算されないというデメリットがあります。
そのためボーナスをできるだけ多く貰いたいという場合は、5月31日(あるいは11月30日)が最も適しています。
【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】5月・12月退職のメリット
5月・12月退職のメリットのメリットには、以下の3つがあります。
- 満額に近いボーナスが受けられる
- 有給休暇を最大限に取れる
- 12月ごろ退職なら年度末にキリよく仕事納めができる
満額に近いボーナスが受けられる
先述のとおり、5月に退職すれば満額に近いボーナスが受けられます。
基準日である6月1日前(1箇月以内)に退職した職員についても、ボーナス支給されることが明記されているからです。
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第18条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対しそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第2項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
5月1日付で退職した職員についても、ボーナスが必ず支給されます。
この条例に基づいて言えば、11月1日に退職した場合も同様に冬のボーナスが受け取れるということです。
ただし冬は3月締めの事業が多く、繁忙期になっています。
そのため冬ごろの退職は引継ぎや退職手続きなどが難しくなる可能性があることは知っておきましょう。
有給休暇を最大限に取れる
5月に退職すれば、有給休暇を最大限に取れます。
公務員の場合は、1月1日に有給休暇が20日付与されるのが一般的です。
もし有給休暇を使わないで働き続けていたら、繰越休日が20日も追加されてトータルで40日間休めます。
4月ごろに辞めれば、ボーナスを受け取ることができつつ、1ヶ月以上休むことが可能です。
12月ごろ退職なら年度末にキリよく仕事納めができる
12月ごろ年度末にキリよく仕事納めができます。
公務員は3月が年度末であり、4月1日に組織全体で人事異動が行われます。
12月ごろに有給休暇込みで休むとなれば、年度末ごろにキリよく仕事を終わらせることができるでしょう。
4月以降に辞めるとなれば、人事異動で周囲に迷惑をかけてしまうことがあるかもしれません。
もし12月ごろに辞めることが周囲に伝わっていれば、情報を事前に共有してじっくりと引継ぎができます。
【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】退職手当の計算方法
国家公務員も地方公務員の退職手当については、以下の計算によって金額が決められています。
基本額の中にある勤続期間別支給割合とは、勤続年数によって割合が高くなるものです。
そして退職理由別とは、定年退職を迎えているのか、自己都合による退職によるのかといった理由の部分になります。
定年退職の方が割合は高くなる傾向があり、自主退職の場合は受け取る金額が下がってしまう点が特徴です。
なお総務省の「令和4年地方公務員給与の実態」によれば、静岡県の退職金が23,843,000 円と最も高く、佐賀県が19,345,000 円と最も低い金額でした。
このように都道府県によっても退職金の額は大きく変動しますが、勤続年数によっても多少変化します。
【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】公務員のボーナスの平均支給額
内閣官房内閣人事局「令和3年6月期の期末・勤勉手当」「令和3年12月期の期末・勤勉手当」によれば、国家公務員のボーナス平均支給額は次のとおりです。
2021年6月期:約661,100円
2021年12月期:約651,600円
東京都の地方公務員について「夏季の特別給の支給」「冬季の特別給の支給」によれば、国家公務員のボーナス平均支給額は次のとおりです。
2021年6月期:745,459円(控除後)
2021年12月期:712,889円(控除後)
地方公務員については、国家公務員の金額に基づき決定されます。
いずれの場合も民間企業と異なり、公務員のボーナスは法律で定められているため、業績によって金額が左右されるということはなく、安定した額を受け取れます。
【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】今一度公務員を辞めるリスクを考えよう
公務員から転職を考えている人は、次のような公務員を辞めたときのリスクについて今一度考えてみましょう。
- 安定感を失う可能性がある
- 民間企業で活躍できない可能性がある
- 社会的な信用が低くなるおそれがある
- 周囲に説得が必要がことがある
本当に退職した方が良いのかについて自分の中で慎重に考えて、転職活動をすることが大切です。
安定感を失う可能性がある
公務員を退職する際に最も懸念されるのは、安定感を失う可能性です。
公務員は、給与や雇用の安定性が高く、定年までの長期的なキャリアが見込める職業です。
そのため、退職を考える際には「本当に安定を手放して良いのだろうか」と不安に感じる方もいるでしょう。
この安定感は、家計の計画や将来のライフプランを立てる上で大きな安心材料となります。
しかし、転職先の企業が業績不振や経営方針の変更により、突然の解雇や給与の大幅な減額を行う可能性もあります。
これらのリスクを十分に理解し、対策を講じることが重要です。
民間企業で活躍できない可能性がある
公務員が民間企業で活躍できない可能性がある理由のひとつは、職場文化や業務スタイルの違いです。
公務員時代には安定した環境で働いていたため、急な変化や競争が激しい民間企業の環境に適応するのが難しいかもしれません。
また、公務員としてのスキルが民間企業で求められるスキルと一致しない場合、即戦力として期待されることが少なく、評価が低くなる可能性があります。
さらに、民間企業では成果主義が重視されるため、個人の成果が給与や評価に直結します。
これに対して公務員は年功序列が基本であり、このギャップに戸惑うこともあります。
これらの課題を克服するためには、事前に民間企業の文化や求められるスキルを理解し、適応力を高めることが重要です。
社会的な信用が低くなるおそれがある
公務員を退職すると、社会的信用が低くなる可能性があります。
公務員は安定した職業であり、多くの人々から信頼される立場にあります。
そのため、公務員としての肩書きは、住宅ローンの審査やクレジットカードの申請などで有利に働くことがあります。
しかし、退職して一般企業に転職すると、その安定性が失われることも。
特に、転職先が不安定な業界や未経験の分野である場合、その不安はさらに増すかもしれません。
解決策としては、転職先でのキャリアをしっかりと築き、信頼を再構築することが重要です。
また、退職前に金融機関での手続きを済ませるなど、事前準備をしておくと安心です。
公務員を辞めることで一時的に社会的信用が低下する可能性がありますが、計画的な行動で乗り越えられるでしょう。
周囲に説得が必要がことがある
公務員が退職を考える際、周囲の理解を得ることが重要です。
特に家族や友人、同僚にとっては、公務員という安定した職業を辞めることに対する不安や疑問があるかもしれません。
このような状況では、退職理由や将来のビジョンをしっかりと説明することが求められます。
例えば、新しい職場でのキャリアアップや自身の夢を追求することが理由であれば、それを具体的に伝えると良いでしょう。
また、転職先の情報や計画を共有することで、周囲の不安を和らげることができます。
さらに、転職活動の進捗や結果を適宜報告することで、信頼を築くことが可能です。
【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】公務員からの転職で年収が下がるケース
公務員からの転職で年収が下がるケースは、主に次の4つが考えられます。
- 未経験の分野に転職した
- 業績の悪い業界へ転職した
- 手当のない企業へ転職した
- 自身の市場価値が低い
未経験の分野に転職した
未経験の分野に転職することは、新しい挑戦として魅力的に感じるかもしれませんが、年収が下がるリスクも伴います。
公務員としての経験が直接活かせない場合、新しい職場での即戦力としての期待が薄れ、初任給が低く設定されることも。
特に、専門的なスキルや知識が求められる分野では、未経験者がスタートラインに立つために時間がかかる可能性もあります。
また、未経験の分野に転職する際には、業界の動向や求められるスキルを事前にしっかりと調査することが重要です。
業績の悪い業界へ転職した
業績の悪い業界へ転職すると、年収が下がる可能性が高まります。
特に公務員からの転職では、安定した収入を期待している方も多いでしょう。
しかし、業績が低迷している業界では、ボーナスが削減されたり、昇給が見込めなかったりすることがあります。
このため、転職先の業界の現状や将来性を十分に調査することが重要です。
また、業績が悪い業界では、リストラや倒産のリスクも高まります。
こうしたリスクを避けるためには、転職前に業界の動向をしっかりと把握し、業績が安定している企業を選ぶことが大切です。
業界の選択は、将来のキャリアに大きな影響を与えるため、慎重に行いましょう。
手当のない企業へ転職した
手当のない企業へ転職した場合、公務員時代と比べて年収が下がる可能性があります。
公務員は基本給に加え、さまざまな手当が支給されることが一般的です。
住居手当や通勤手当、扶養手当などが挙げられます。
しかし、民間企業では手当が少ない、または全くない場合もあります。
そのため、手当のない企業に転職すると、同じ基本給でも実質的な収入が減少することがあります。
こうした状況を避けるためには、転職先の企業がどのような手当を提供しているのかを事前に確認することが重要です。
転職前に企業の給与体系や福利厚生をしっかりと調査し、手当がどの程度支給されるのかを把握しておくことが、年収を維持するために必要です。
自身の市場価値が低い
公務員からの転職を考える際、自身の市場価値が低いと感じる場合があります。
これは、長期間同じ職場で働いていると、外部の業界動向や新しいスキルの習得が遅れることが原因です。
市場価値を高めるためには、まず自分の強みや経験を客観的に見つめ直していきましょう。
また、転職を視野に入れる際は、業界研究やトレンドの把握を行い、必要なスキルを積極的に学ぶのも有効です。
さらに、転職エージェントを活用することで、自分の市場価値を客観的に評価してもらうのもひとつの方法です。
【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】公務員から転職した方が良いパターン
公務員から転職した方が良いパターンは、次の3つです。
- 公務員では成長が見込めないと感じている
- 転職で将来年収アップする確信がある
- 自分のやりたい仕事がある
公務員では成長が見込めないと感じている
公務員として働く中で、「このままでは成長が見込めないかもしれない…」と感じる方もいるかもしれません。
公務員は安定した職業ですが、仕事内容や昇進のペースが固定されているため、自己成長を感じにくい場合があります。
特に、日々の業務がルーチンワークに感じられたり、新しいスキルや知識を習得する機会が少ないと感じる場合、成長の停滞を感じるでしょう。
このような状況に陥った場合、転職を検討することもひとつの選択肢です。
転職先では、自分が得意とする分野や興味を持つ業界に挑戦することで、新たなスキルを身につけたり、キャリアアップを図ることが可能です。
また、民間企業では成果に応じた評価制度が整っていることが多く、努力次第で昇進や給与アップが期待できるでしょう。
転職で将来年収アップする確信がある
転職によって今より年収がアップしていくという確信があれば、転職を考えてみましょう。
例えば注目されている分野でサービスを手がけるスタートアップ・ベンチャー企業などは、事業の成長性が見込まれるため、将来的に利益が上がる可能性があります。
明確な経営理念を持っている、社員がいきいきと働いているという企業であれば、働き続けることで年収が上がっていくでしょう。
成長企業で自分の能力が活かせると思ったなら、すぐに転職に踏み切っても良いケースです。
自分のやりたい仕事がある
本当に自分のやりたい仕事があるという場合は、公務員から民間企業に転職してみても良いでしょう。
自分がやりたい仕事はモチベーションを高めながら取り組むことができ、成長スピードも早くなり、上司から高い評価を得られる可能性があるからです。
またやりがいを感じながら仕事ができるので、いきいきと長く働き続けることができるでしょう。
今の仕事よりも興味・関心のあることがあるのなら、転職活動を視野に入れてみても良いかもしれません。
【公務員のボーナスを視野に入れた退職のタイミング】転職で年収を落とさないためのコツ
公務員から民間企業への転職で年収を落とさないためのコツは、以下の4つがあります。
- 十分に業界研究をする
- 自身のキャリアビジョンを考える
- 公務員が活かせる経験・スキルを考える
- 転職エージェントを活用する
十分に業界研究をする
まず、転職を考える際には、興味のある業界についての最新情報を集めましょう。
例えば、その業界の成長性や将来的な見通し、主要企業の動向などを把握することで、転職先を選ぶ際の判断材料になります。
さらに、業界の給与水準や福利厚生についても調べておくことが大切です。
これにより、転職後の生活設計が具体的になり、年収が下がるリスクを減らせます。
求人情報や業界レポートを活用し、希望する職種の平均給与を確認することが有効です。
このように、業界研究を通じて得た情報は、転職活動を有利に進めるための武器となります。
しっかりと準備をして、自信を持って次のステップに進みましょう。
自身のキャリアビジョンを考える
キャリアビジョンとは、将来どのような仕事をしたいのか、どのようなスキルを身につけたいのかを具体的に描くことです。
これを明確にすることで、転職先の選択がより的確になり、後悔のないキャリアチェンジが可能になります。
まず、自分の強みやこれまでの経験を振り返り、それがどのように次の職場で活かせるかを考えましょう。
「自分に何ができるのか、どこで活躍できるのかがわからない…」と感じる方もいるかもしれません。
そんな時は、転職エージェントやキャリアコンサルタントに相談するのもひとつの手です。
「将来どのようなポジションで利益に貢献していくか」を考え、キャリアビジョンを練っておきましょう。
公務員が活かせる経験・スキルを考える
民間企業で公務員が活かせる経験・スキルは何があるのかを考えてみましょう。
きちんと能力を洗い出して働いていけば、民間企業が持ちがちな「公務員は即戦力として期待できない」という悪いイメージを払拭できます。
例えば、公務員の場合次のような強みがあるのではないでしょうか。
- 法律や条例に関する専門知識
- 窓口サービスで培ったコミュニケーションスキル
- 部署内の調整能力や外部との交渉能力など
一つずつピックアップしていけば、公務員で得た経験やスキルが民間企業で役立つことは多々あります。
自分がどのような能力を持っているのか考えて、転職活動をしましょう。
転職エージェントを活用する
年収を落とさない転職を目指すのであれば、転職エージェントを活用するのもひとつの手段です。
転職エージェントは、さまざまな業界・職種を取り扱っていて、なかには年収の高い求人を紹介してくれることもあるからです。
また求人紹介だけでなく、転職エージェントではキャリアアドバイザーから次のような転職サポートが受けられます。
- 転職相談
- 履歴書・職務経歴書の添削
- 面接対策
- 面接日程の調整
- 内定後の条件交渉など
これらのサポートが充実しているため、一人で転職活動を進めるよりもスムーズで、内定獲得のチャンスも広がっていきます。
なお転職エージェントには、あらゆる業界・職種を取り扱う総合型転職エージェントと、特定の分野に強い特化型転職エージェントの2種類があります。
「できるだけ多くの企業と出会いたい」という人は総合型を、「既に志望業界・職種が絞られている」という人は特化型を利用すると良いでしょう。
自分にとって使いやすい転職エージェントを見つけることがポイントです。
まとめ
今回は、公務員としてのキャリアを考え、退職とボーナスに関心を持つ方に向けて、解説しました。
公務員としての退職を考える際、ボーナスを最大限に活用することが重要です。
ボーナスを受け取る時期を見極めることで、経済的な余裕を持ちながら次のステップに進むことができるでしょう。]
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!