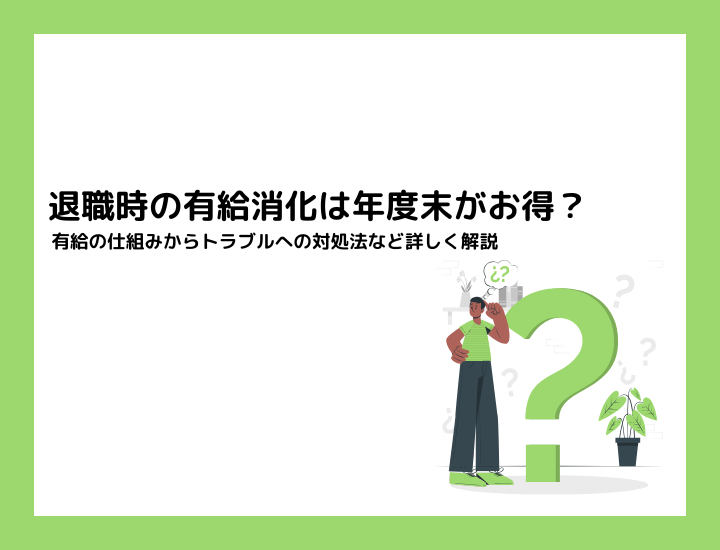
退職時の有給消化は年度末がお得?有給の仕組みからトラブルへの対処法など詳しく解説
はじめに
年度末の退職を検討している方にとって、有給休暇の扱いが一つの悩みの種となっているかもしれません。
退職に際して、有給を全て使い切ることができるのか、会社との間でトラブルが発生しないかといった不安を抱える方も多いのではないでしょうか。
しかし、有給休暇は労働者に保障された正当な権利であり、自分の希望するタイミングで利用することが可能です。
本記事では、年度末に退職する際の有給休暇に関する重要なポイントを詳しくご紹介します。
有給消化の具体的な流れや注意点、押さえておきたいポイントについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。
【年度末退職の有給】年度末退職の有給消化はできる?
結論として、年度末に退職を予定している場合でも、有給休暇を消化することは可能です。
有給休暇は、すべての労働者に平等に認められた権利であり、その利用目的を会社に伝える必要はありません。
年度末のような忙しい時期であっても、有給休暇を取得することに制限はなく、自由に活用することが基本的なルールとなっています。
退職のタイミングについては、年間を通じていつでも申し出ることができますが、特におすすめなのは年度末や月末です。
理由として、退職後の月は社会保険料の個人負担が増加する可能性があるため、月の初めに退職すると経済的な負担が大きくなる場合があります。
年度末退職を目指す場合には、事前にスケジュールを立てて、自分が持つ有給休暇を効率的に消化することが重要です。
自分が消化できる有給日数を把握しながら、計画的に準備を進めることで、よりスムーズな退職が実現するでしょう。
【年度末退職の有給】有給休暇のルール・仕組み
ここで、有給休暇のルールや仕組みについて、改めて整理しておきましょう。
一般的に有給を取得するには、以下の2つの条件を満たす必要があります。
- 入社から6ヶ月が経過していること
- 所定労働日の8割以上出勤していること
上記2つの要件を満たした場合、10日の有給休暇が付与されます。
つまり、入社から半年以上勤務していれば、若手社員でも10日間の有給休暇を取得できるのです。
さらに、勤続年数に応じて有給日数は増加し、6年6ヶ月以降は毎年20日が付与される仕組みになっています。
長期間勤務するほど、有給の取得日数が多くなることを覚えておきましょう。
以下は、勤続年数に応じた有給日数の付与例です。
| 勤続年数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
ただし、有給休暇には2年の有効期限がある点に注意が必要です。
例えば、2023年4月1日に入社し、半年後に10日の有給が付与されたとします。
そのうち8日を使用しないまま2025年10月1日を迎えると、未使用の2日は失効してしまいます。
有給休暇は無期限で保持されるものではなく、時効により消滅する仕組みであることを理解しておきましょう。
したがって、有給の最大保有日数は40日までとなります。
期限切れを防ぐためにも、計画的に有給を消化することが重要です。
自己都合退職による有給消化
自己都合退職であっても、有給休暇を取得する権利に差はありません。
会社都合退職であろうと自己都合退職であろうと、退職前に有給休暇を消化する権利は労働基準法によって等しく保障されています。
もし上司から「自己都合退職では有給消化は認められない」といった発言があれば、それは違法行為に該当します。
そのような場合は、人事部や総務部に相談し、それでも解決しない場合は弁護士に相談することを検討しましょう。
有給休暇の取得は法律で認められた権利であり、会社は原則としてこれを拒否することはできません。
退職日より前に有給休暇の取得希望を伝えておけば、問題なく消化できるので安心してください。
引き継ぎなしの有給消化
法律上、有給休暇を取得する際に必ず引き継ぎを行う必要はありません。
仮に会社から「引き継ぎが終わらない限り有給休暇は使えない」と言われた場合、それは法的根拠のない主張に過ぎません。
ただし、全く引き継ぎを行わずに有給休暇を強行すると、会社との関係が悪化する可能性があります。
円満退職を目指すのであれば、可能な範囲で最低限の引き継ぎを行い、その上で有給休暇について会社と相談するのが賢明です。
もし会社が求める引き継ぎが過剰である場合、その旨を明確に伝え、交渉することも重要です。
引き継ぎはあくまで退職を円滑に進めるための手段であり、有給休暇の取得を妨げる理由にはならないことを覚えておきましょう。
時季変更権について
会社には、従業員が希望する有給休暇の時期が業務に支障をきたす場合、その時期を変更できる「時季変更権」が認められています。
しかし、退職日が確定している場合、会社はこの権利を行使できません。
時季変更権は、有給休暇の取得時期を調整するためのものであり、退職後の日程を変更はできないためです。
そのため、退職前に有給休暇を消化することについては、会社は従業員の希望を基本的に尊重しなければなりません。
有給休暇の消化は従業員の正当な権利であり、会社が正当な理由なくこれを拒否することはできない点をしっかり認識しておきましょう。
【年度末退職の有給】消化までの基本的なスケジュール
年度末で退職する際に有給休暇を円滑に消化するためには、基本的なスケジュールをしっかり把握しておくことが重要です。
以下に具体的な流れをまとめました。
1.退職の意思と有給消化の希望を伝える
まず、退職の意思を伝える際に、有給休暇を消化したいという希望も合わせて伝えましょう。
退職の意向を伝えるタイミングは、会社の就業規則で定められている場合があるため、事前に確認が必要です。
退職日や最終出勤日は会社と相談して決定する必要があります。
この時点で有給消化の希望を伝えておくことで、後々のスケジュール調整がスムーズに進みます。
有給消化の希望は一方的に伝えるのではなく、引き継ぎ期間を十分に考慮し、会社に理解してもらえるように説明することが重要です。
2.有給休暇の残日数を正確に把握する
次に、自分が保有している有給休暇の残日数を正確に把握しましょう。
給与明細や出勤簿で確認できる場合もありますが、会社によっては入社時から有給休暇が付与されるなど規定が異なる場合もあるため、就業規則を確認するのが確実です。
思っていたよりも残日数が少ないということがないように、早めに確認しておくことが大切です。
また、会社によってはリフレッシュ休暇などの特別休暇制度がある場合もありますので、こちらも合わせて確認しましょう。
3.退職までのスケジュールを調整する
退職日と最終出勤日が決まったら、業務の引き継ぎスケジュールと有給消化のスケジュールを具体的に立てましょう。
最終出勤日から退職日までの期間を有給消化に充てられます。
有給消化の期間は、残日数や業務の状況によって調整する必要があります。
また、引き継ぎがスムーズに進むように、引き継ぎマニュアルを作成したり、後任者への紹介をしたりすることも重要です。
4.有給消化の申請と実行
会社と合意したスケジュールに基づいて、有給休暇の申請を行いましょう。
有給休暇の取得理由を伝える必要はありませんが、「退職に伴う有給消化のため」と説明すれば十分です。
有給休暇は労働者の権利であり、会社は原則として拒否はできません。
しかし、会社や同僚に迷惑をかけないように、事前にしっかりと引き継ぎを行い、円満な退職を心掛けましょう。
5.退職後の手続き
有給消化が終わると、いよいよ退職となります。
退職後には、会社から離職票や源泉徴収票などの書類を受け取る必要があります。
これらの書類は、転職活動や失業保険の手続きなどに必要となるため、大切に保管しておきましょう。
また、退職後も会社から連絡がある場合に備えて、連絡先を伝えておくことも大切です。
【年度末退職の有給】年度末に退職するときの有給の消化方法
年度末に退職する際の有給休暇の消化方法としては、大きく分けて次の2パターンがあります。
- 最終出勤日前に有給を消化していく
- 最終出社日後に有給を消化していく
有給がまとまって残っている場合は、多くの方がこのいずれかを選ぶことになるでしょう。
それぞれの特徴を詳しく見ていきます。
最終出勤日前に有給を消化していく
まずは、最終出勤日前に有給休暇を消化していく方法です。
この場合、退職日が実質的に最終出勤日となります。
この方法には、以下のようなメリットがあります。
- デスク周りの片付けや、社内外への挨拶が可能になる
- 有給消化の前に一定の日数出勤することで、引継ぎ資料の作成や後任者への情報共有を行う時間を確保できる
引継ぎが不十分になりそうな場合は、有給消化が始まる前にしっかりとスケジュールを組み、必要な作業を終わらせておくことが大切です。
計画的に動くことで、円満に退職を迎えることができます。
最終出社日後に有給を消化していく
次に、最終出社日のあとに有給休暇を消化していく方法です。
この場合、有給消化が終了したタイミングで退職扱いとなります。
この方法のメリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 出勤を気にせず、有給消化中に転職活動を進めやすい
- スケジュールの調整がしやすい
ただし、この方法を選ぶ場合は、以下に注意が必要です。
- 有給休暇の日数を正確に把握しておくこと
- 最終出社日に会社へ行けないため、引継ぎは早めに進めること
特に、引継ぎに関しては最終出社日より前倒しで計画を立てておくことが重要です。
余裕を持って準備を進めることで、スムーズな退職が可能になります。
【年度末退職の有給】年度末に退職するときの有給消化の流れ
年度末に退職するときの有給消化の流れを紹介します。
- 事前に上司へ相談・報告する
- 年度末から逆算して消化できる有給日数を確認する
- 引継ぎを終わらせるようにスケジュールを組む
一部「【年度末退職の有給】消化までの基本的なスケジュール」と重複する部分もありますが、こちらで紹介するのはあくまで「年度末での退職」を前提とした内容となっています。
事前に上司へ相談・報告する
退職を進めるにあたり、まずは上司への相談と報告が欠かせません。
退職理由に加え、退職希望日や引継ぎスケジュールについて具体的に伝えることが重要です。
事前にしっかり相談・報告をしておけば、周囲が年度末に慌てることなく、スムーズな退職が期待できます。
法律上は、退職の申し出から2週間で退職が可能とされていますが、実際には業務内容や役職によって難しい場合もあります。
そのため、年度末退職を考えている場合は、年明け前、遅くとも1月中には上司に相談することをおすすめします。
年度末から逆算して消化できる有給日数を確認する
退職前に消化できる有給日数を把握するため、年度末から逆算して計算を行いましょう。
逆算することで、有給消化の具体的なスケジュールが立てやすくなり、最終出勤日がいつになるかを明確にすることができます。
計画を立てずに進めてしまうと、有給を消化しきれない可能性があるため注意が必要です。
特に繁忙期や比較的余裕のある週を考慮しながら、有給休暇を効率よく消化するスケジュールを組みましょう。
また、就業規則で定められた休日は、有給休暇としてカウントされない場合があります。
そのため、事前に就業規則を確認し、必要に応じて上司や総務に確認を取ることが大切です。
引継ぎを終わらせるようにスケジュールを組む
有給休暇の日数を考慮しながら、引継ぎを終わらせるスケジュールを立てましょう。
引継ぎが十分に行われていないと、有給を取得しづらい雰囲気が生じる恐れがあり、円満退職が難しくなることもあります。
業務マニュアルの作成や案件情報の共有など、引継ぎに必要な作業は多岐にわたります。
一日で終えられる作業ではないため、少なくとも1週間程度の引継ぎ期間を確保することが理想的です。
また、取引先を担当している場合、有給消化中に対応が難しくなる旨を事前に伝え、次に担当する人の名前を共有しておくとよいでしょう。
これにより、取引先との信頼関係を維持しつつ、スムーズな引継ぎを行うことができます。
会社への感謝の意を示しながら、万全な引継ぎ準備を進めていくことが、円滑な退職につながるポイントです。
【年度末退職の有給】有給消化時に考えられるトラブル・対処法
社会人としての責任を全うする中で、有給休暇を消化するのは簡単ではありません。
ここでは以下の順に、有給消化時に考えられるトラブルと対処法について見ていきましょう。
- 引継ぎが終わらない
- 有給が利用できない
- 有給が消滅してしまう
- 有給の分の給与が支払われない
有給消化の際に起こり得るトラブルを未然に防ぐためにも、計画的なスケジュール管理と適切な対応を心がけましょう。
円満な退職を実現するためには、法的な権利を理解しつつ、柔軟な対応を心がけることが重要です。
引継ぎが終わらない
引継ぎが終わらないことは、有給消化を計画する際に最も多い問題の一つです。
特に、引継ぎスケジュールが十分に組まれていない場合、後任者が業務を引き継げずにトラブルへ発展することがあります。
さらには、上司から「引継ぎが終わるまで在籍してほしい」と言われ、退職日を延ばさざるを得なくなる場合もあります。
こうした事態を避けるためには、退職予定を早めに上司へ相談し、社内で情報を共有することが重要です。
年度末から逆算して引継ぎスケジュールをしっかり組むことで、周囲への配慮を示しながら円満退職を目指せるでしょう。
有給が利用できない
有給消化そのものができないという問題も発生することがあります。
上司から「忙しいから休めない」「退職時は有給消化ができない規則がある」などと断られることがありますが、法律に違反している対応です。
有給休暇は労働者の権利であり、最低でも年間5日間の取得が義務化されています。
このような場合には、社内のコンプライアンス部門や労働組合へ相談し、それでも解決しない場合は労働基準監督署へ申し出るのが有効です。
さらに深刻な場合には、弁護士へ相談することも選択肢となります。
有給が消滅してしまう
有給休暇を消化できずにそのまま退職してしまい、有給が消滅してしまうケースも見られます。
引継ぎが長引いたり、繁忙期で休めなかったりすることが原因となる場合が多いでしょう。
また、上司から「休まないでほしい」と要請され、物理的に取得が難しかったという例もあります。
この場合は、有給を買い取る制度を利用できるかどうかを確認し、未消化分を給与として請求する方法を検討すると良いでしょう。
有給の分の給与が支払われない
有給休暇の給与が支払われないトラブルが発生する場合があります。
たとえば、有給を消化して年度末に退職した後、給与明細を確認して初めて未払いに気づくケースです。
有給を無給扱いにすることは不当な行為とされており、不足分については会社に対して書面で請求を行うことが可能です。
もし請求が拒否された場合には、事前に証拠を用意した上で、最寄りの労働基準監督署へ相談するとよいでしょう。
有給休暇に関する有効な証拠には、以下のようなものがあります。
- 有給取得条件を満たしていることが確認できる「雇用契約書」
- 残りの有給日数が記載された「給与明細書」や「勤怠管理表」
- 有給取得を拒否された際の音声記録やメールの文面など
これらの証拠を揃えておけば、労働基準監督署への相談がスムーズになり、未払いの有給分を回収できる可能性が高まります。
【年度末退職の有給】年度末に有給を消化するときの注意点・ポイント
年度末に有給を使い切りたいと考えても、業務の多さや責任の重さから退職が難しい場合があります。
ここでは、年度末に有給休暇を消化する際の注意点と実践方法を解説します。
- 現職と内定先との二重就労にならないようにする
- 有給休暇消化中に転職活動をする
- 引き留めには冷静に対応する
- 解決が難しい場合は相談する
- 年度末以外での月末退職も視野に入れる
ここで紹介するポイントを押さえることで、スムーズに有給を消化しながら次のステップに進む準備が整います。
現職と内定先との二重就労にならないようにする
現在の職場と新しい内定先で同時に働く状態を避けましょう。
二重就労とは、現職の雇用契約が続いている間に別の企業で働くことを指します。
この状態は多くの企業の就業規則で禁止されており、発覚した場合には最悪のケースとして懲戒解雇となり、退職金が支給されない可能性があります。
有給休暇を消化する際は、退職日の翌日以降に新しい職場で働き始めるようにスケジュールを調整しましょう。
また、現職または内定先のどちらかで二重就労が認められている場合でも、雇用保険の手続きが滞るリスクがあるため、現職に「雇用保険資格喪失手続き」を依頼することが重要です。
有給休暇消化中に転職活動をする
有給休暇中に転職活動を行うのは問題ありません。
早めに行動を始めることで、退職後の空白期間を回避できます。
空白期間が長引くと精神的な負担が増し、効率的な活動が難しくなることもあります。
また、転職活動には応募書類の準備や交通費など予想以上のコストがかかりますが、在職中であれば収入が確保されているため安心して進められるでしょう。
有給消化中に説明会や面接の予定を計画的に入れることで、効率的に転職活動を進められます。
引き留めには冷静に対応する
退職の意思を伝えると、上司から引き留められることが考えられます。
「人手不足」や「繁忙期」という理由で説得される場合もありますが、退職は従業員に与えられた権利であり、後ろめたさを感じる必要はありません。
スムーズな退職を実現するためには、引継ぎを十分に行うことが大切です。
後任者が決まっていない場合には、引継ぎマニュアルを作成し、誰でも業務が理解できる状態にしておくと良いでしょう。
また、退職時には感謝の意を忘れずに伝えることが重要です。
解決が難しい場合は相談する
有給休暇の消化に関してトラブルが発生した場合、速やかに相談しましょう。
直属の上司や人事部、法務部に相談し、それでも解決しない場合は労働組合や労働基準監督署に相談する方法があります。
労働組合は会社に対して団体交渉を行い、有給取得の拒否や未払いに対処してくれることがあります。
ただし、必ずしも問題が解決するとは限らないため、場合によっては労働基準監督署や弁護士に相談することも検討してください。
年度末以外での月末退職も視野に入れる
退職のタイミングに特にこだわりがない場合は、年度末以外の退職も検討する価値があります。
例えば、4月1日に新しい有給が付与される企業では、4月末まで在籍することでより多くの有給を活用できます。
また、賞与の支給タイミングを考慮して6月末や7月末に退職を計画するのも良い方法です。
10月の求人ピークに合わせて転職活動を行い、12月末の退職を目指す選択肢もあります。
自分の状況や時期を踏まえながら、最適な退職のタイミングを慎重に判断しましょう。
【年度末退職の有給】直前まで残っている場合の対処法
退職日が迫る中で有給が残ってしまった場合でも、諦める必要はありません。
ここでは、有給を最大限に活用するための2つの対処法について解説します。
退職のスケジュール変更
有給消化が難しいと感じた場合、まず検討すべきは退職日の調整です。
退職日を後ろにずらすことで、有給消化のための期間を確保できます。
例えば、10月末に退職予定だった場合、11月上旬まで退職日を延ばすことで、その間に有給を消化できます。
この方法のメリットは、有給休暇を実際に取得できる点です。
有給休暇は労働者の権利であり、会社は原則として拒否ができません。
また、引き継ぎ期間を十分に確保することで、会社との関係を円満に保ったまま退職できます。
ただし、退職日を動かす際には、転職先との入社日や、その他のスケジュールを考慮する必要があります。
会社側との交渉では、有給消化の希望を伝えつつ、業務の引き継ぎをきちんと行う意思を示すことが大切です。
具体的な退職日、有給消化期間、最終出勤日を伝え、会社と合意できるスケジュールを調整しましょう.
有給の買い取り
もし、退職日をどうしても動かせない事情がある場合は、残った有給休暇の買い取りを会社に交渉してみましょう。
会社が有給を買い取ることは、通常の勤務時は違法ですが、退職時には例外的に認められます。
例えば、転職先への入社日が決まっていて、どうしても退職日をずらせない場合に有効な手段です。
この方法のメリットは、有給休暇を消化する時間がない場合でも、金銭的な補償を受けられる点です。
ただし、会社には有給休暇を買い取る義務はないため、必ず買い取ってもらえるとは限りません。
また、ブラック企業の場合、買い取りの約束を反故にされるリスクもあるため、注意しましょう。
買い取りを希望する際は、事前に会社に確認し、書面やメールなどで記録を残しておくことが大切です。
また、有給の買い取り額は、通常の給料と同じ金額で計算されるのが一般的です。
もし、会社が買い取りを拒否する場合は、弁護士に相談することも視野に入れると良いでしょう。
【年度末退職の有給】年度末の有給に関するQ&A
最後に、年度末に有給を取得する際に疑問が出るポイントをQ&A形式でまとめました。
- 有給休暇の買い取りはある?
- 有給消化中のボーナス支給はある?
- 有給取得を拒否されたらどうする?
- 有給が残ったまま退職するとどうなる?
- 有給消化中に転職はできる?
記事内で解説した内容のおさらいにもなるため、これから退職を考えている人はぜひ参考にしてみてください。
有給休暇の買い取りはある?
基本的に、有給休暇の買い取りは認められていません。
有給は働く人が心身をリフレッシュするための制度として設けられているため、買い取りによってその目的を損なう行為は原則として禁止されています。
ただし、いくつかの例外が存在します。
- 退職時に未消化となった有給
- 法定基準を上回る有給が付与された場合
- 時効で消滅した有給
これらの場合には、買い取りが可能とされるケースもあります。
買い取りを希望する際は、就業規則を事前に確認し、該当する規定を把握しておくことが大切です。
有給消化中のボーナス支給はある?
有給消化中であっても、それは勤務日として扱われるため、通常ボーナスは支給対象となります。
ただし、ボーナス額は業績評価などによって変動するため、有給を理由に減額される可能性がないとは言い切れません。
また、退職が確定している場合、会社の判断でボーナスが減額される場合があることを念頭に置いておく必要があります。
有給取得を拒否されたらどうする?
会社が有給取得を拒否することは労働基準法に反する行為です。
そのため、万が一拒否された場合には、次の対応を取ることが推奨されます。
- 他部署や人事部に相談する
- 労働組合に連絡を取る
- 労働基準監督署に相談する
ただし、時季変更権を行使された場合は例外となります。
時季変更権とは、「業務上どうしても対応が難しい場合に雇用主が有給取得のタイミングを変更できる権利」を指します。
例えば、専門性の高い業務や納期の厳しいプロジェクトが理由として挙げられるケースがあります。
時季変更権が行使された場合でも、有給取得そのものの拒否はできません。
年度末退職を予定している場合には、事前に雇用主と相談し、スケジュールを調整することが重要です。
有給が残ったまま退職するとどうなる?
有給休暇を残したまま退職すると、その有給は消滅し、二度と利用することができなくなります。
退職日を過ぎてしまうと、たとえ残っていた有給休暇を後から申請したり、消化したりすることは一切できなくなります。
これは、有給休暇を「捨てる」のと同じ状態になってしまうことを意味するでしょう。
しかし、退職日よりも前であれば、有給休暇は必ず消化できます。
もし、スケジュール的に有給を消化することが難しい場合は、会社に有給の買取を交渉するという選択肢もあります。
重要なのは、退職日を迎える前に有給消化の希望を会社に伝えることです。
会社によっては、引き継ぎや人員不足を理由に有給消化を渋る場合もありますが、有給休暇は労働基準法で定められた労働者の権利であり、会社がこれを拒否することは違法です。
自己都合退職の場合でも、有給休暇を消化する権利は変わりません。
もし会社が有給消化を認めない場合は、担当部署や弁護士に相談することも可能です。
有給消化中に転職はできる?
有給休暇消化中に転職先で働くことは、原則として可能です。
ただし、いくつか確認すべき点があります。
まず、現職と転職先の両方の就業規則で二重就労が許可されている必要があります。
もしどちらかの企業で二重就労が禁止されている場合、就業規則違反となり、解雇されるリスクも考えられます。
したがって、有給消化中に転職先で働く場合は、必ず事前に両方の企業に事情を説明し、了承を得ることが重要です。
また、雇用保険は二重加入ができないため、転職前の企業で「雇用保険の資格喪失手続き」を事前に行ってもらう必要があります。
この手続きを済ませないと、転職先で雇用保険に加入できません。
転職先から「早く来て欲しい」と要望があった場合でも、自分がまだ有給消化中であることを伝え、必ず両社の就業規則を確認しましょう。
確認を怠ると、就業規則違反となるだけでなく、後々のトラブルにつながる可能性があります。
有給消化中の転職は副業扱いになるため、慎重な対応が必要です。
まとめ
退職する際には、その月の保険料が増加するリスクを考慮する必要があります。
そのため、可能であれば年度末や月末の退職を検討すると良いでしょう。
また、多くの方が悩むポイントとして、有給休暇の消化が挙げられます。
全ての有給を使い切るには、退職日から逆算して計画的にスケジュールを立てることが重要です。
さらに、会社に迷惑をかけないためにも、引き継ぎ業務をしっかりと完了させておくことが求められます。
もしも会社側が有給取得を拒否する場合、それは労働基準法に違反する行為となります。
そのような状況に陥った場合は、毅然とした態度で適切な対応を行うことが大切です。
この記事が、転職活動を進める際の一助となれば幸いです。
SHARE この記事を友達におしえる!

