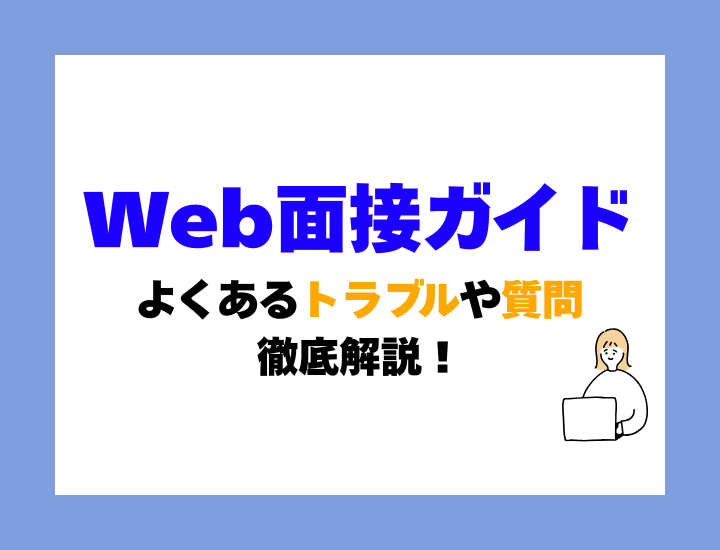年度末転職のタイミングと市場動向!成功の秘訣とおすすめの理由10個を解説
はじめに
転職に有利な時期といえば年度末を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
確かに年度末は新年度の体制に向けて企業の採用活動が活発化し、求人数が多くなる時期です。
一方でこの時期に合わせて転職活動する求職も者の数も多いため、準備不足で臨むと活動が難航する可能性が高い時期でもあります。
転職活動は、準備を含めると一般的に3~6ヶ月の期間を要するとの見方が一般的です。
転職活動を成功させるためには、転職したい時期に合わせ、余裕を持ったスケジュールで準備をしていくこと必要があります。
この記事では、転職活動の成功に向け、活動におすすめの時期をいくつかの観点から調べてみましょう。
年度末以外にも意外に転職に適したタイミングはあります。
ぜひご自身の転職活動の成功に向けたスケジューリングにご活用ください。
【年度末の転職】転職のベストタイミング
一般的には転職のベストタイミングは、求人数が増加する年度末と、下半期のスタート前の8~9月といわれています。
ただし、このタイミングはライバルであるほかの求職者も増えるため、この時期が転職活動に有利だとは一概にはいえません。
転職市場の動向を踏まえると、ライバルを避けられる穴場期間もおすすめです。
求人数の多いタイミングとライバルの少ない穴場期間をそれぞれご説明します。
求人数が増加する2〜3月と8〜9月
年間でも求人数の多いのは、2~3月と8~9月といわれています。
企業の立場では、12月末や3月末での退職を見越して採用数を増やし、4月からの新年度に向けた体制を整える時期です。
同様に、10月からの下半期に向けて8~9月も採用が活発化します。
求人数が豊富な時期は応募先の選択肢が多く、自分の条件にあった求人を見つけやすいというメリットがあります。
希望条件に合う中から、複数比較してより良い条件のものを選ぶことも可能です。
一方で、求職者目線でも活動しやすい時期でもあります。
夏・冬の賞与を受け取り、年度末であれば年末調整も済んだ後となるためです。
この時期に合わせて計画的に転職活動を進める求職者も多く、条件の良い求人には多くの応募が集まります。
ライバルに負けないためには、入念に準備しておくことが必要です。
ライバルが少ない4〜5月の転職活動の穴場
意外かもしれませんが、新年度が始まった後の4~5月も転職活動におすすめの時期です。
採用活動は一段落し求人の数は減りますが、この時期に採用活動をする企業は採用意欲が高い場合が多く見られます。
この時期の求人理由は、新体制発足後に発生した人員不足や退職者の穴埋めなど緊急性が高い場合が多く、採用の本気度が高まるためです。
求職者側で見ても、以前から転職を希望していた人は年度末で決着している場合がほとんどです。
そうでない人は新体制のスタートで忙しい時期にあたり、転職するにしても夏のボーナスを受け取ってからと考える人も多いため、転職市場のライバルの数はぐっと少なくなります。
企業の本気度が高く、ライバルが少ないこの時期はチャンスです。
あえてこの時期を狙って求人を見てみると、希望の条件でスムーズに転職が成功する可能性があるため検討してみましょう。
大型連休のあと
転職を考えるなら、大型連休の後がタイミングとしてベストです。
企業は休暇明けに新たな採用計画を実行することが多く、求人数が増える傾向にあります。
連休直後に採用が活発化する理由は、企業側の業務が通常運転に戻り、年度末の組織再編に向けた人材補充が進むためです。
特にゴールデンウィークや年末年始の休暇明けは、採用活動が本格化します。
求職者は、転職市場の動向を見極めながら計画的に動ける点がメリットです。
ゴールデンウィーク明けは、4月入社の影響で新たな欠員が発生し、即戦力を求める企業が増えます。
年末年始の休暇明けも企業が新年度の組織編成を進めるため、積極的に採用活動をしていくでしょう。
ボーナス受け取り後
年度末の転職を考える際は、ボーナスを受け取った後に退職しても良いでしょう。
転職先での収入が安定するまでの生活資金を確保し、経済的な不安を軽減できるため、余裕を持って次の企業を探せます。
ただし企業の人事制度によっては、一定の在籍期間を満たさなければ支給対象外となる場合があり、直前で退職すると受け取れないケースもあるでしょう。
そのため転職後の収入を最大化するためにも、受領時期を考慮したスケジュールを立てることが重要です。
冬のボーナスが支給される12月以降や、夏のボーナス後の7月は転職希望者が増え、企業側も人員補充を進めます。
ボーナス支給後は求職者の動きが活発になることもあり、競争が激しくなる前に準備を進めるのが効果的です。
自分の仕事が一区切りしたタイミング
転職は担当している業務が一区切りしたタイミングもおすすめです。
円満退職しやすくなるだけでなく、転職活動にも集中できます。
業務が中途半端な状態で退職すると、引き継ぎに時間がかかり、自身の評価にも影響を与えることがあるかもしれません。
プロジェクトの完了や年度の締めを迎えた後は、職場にとっても調整がしやすい時期なのでタイミングとしてベストです。
例えば大型案件の納品が完了した後や、年度末の業績報告が終わったタイミングは、退職の申し出をしやすくなります。
また後任の選定や業務の引き継ぎを計画的に進められるため、職場との良好な関係を維持しながら転職を進められるでしょう。
スムーズな転職を実現するためには、仕事の節目を意識し、最適なタイミングで転職活動を始めるようにしましょう。
職場で体制変更があったとき
職場の体制が変わったタイミングも一つの選択肢です。
職務範囲や評価基準が変わると、これまでの経験やスキルが十分に活かせなくなる可能性があります。
また昇進や待遇の見直しが行われたときに、期待していた役職に就けなかった場合も、転職を検討する要因となるでしょう。
例えば部署の統合によって業務負担が増えたり、新たな上司との相性が合わなかったりするケースが挙げられます。
自身のキャリアプランにマッチした環境で成長するためには、組織の変化を見ながら、最適な転職のタイミングを見極めることが大切です。
転職経験者が選ぶ、最適な転職時期
いざ転職活動を経験すると、最適な転職時期に関係があるのは有利かどうかだけではありません。
時期によって、転職活動のしやすさや入社後の新しい環境になじみやすいかどうかとの観点でも違いがあることを覚えておきましょう。
ここからは、転職経験者の視点で「有利かどうか」以外の観点でのおすすめの時期をご紹介します。
春と秋の長期休暇を活用した転職活動
転職活動は、準備だけでも相応の時間がかかります。
具体的に行うべきこととは、転職の理由や条件の明確化・応募求人の選定。自己分析および企業分析・それらを踏まえた履歴書や職務経歴書・志望理由書の応募書類の作成などです。
転職を成功させるためにも応募までの準備にはしっかりと時間をかけましょう。
考えを整理しアウトプットする必要があるため、まとまった時間がある方が取り組みやすくなります。
春のゴールデンウイークや秋のシルバーウイークなど長期休暇を転職活動のスタートにすると、考えを整理してから活動を始めやすく、活動中に軸がぶれずにすむのでおすすめです。
入社時期による企業の受け入れ体制の違い
どれほど良い環境であっても、転職で新しい職場環境に飛び込むことには大きなストレスを伴います。
タイミングによって企業の受け入れ体制も異なるため、スムーズに新しい環境に適応しやすい時期を選ぶのも1つの方法です。
4月入社または10月入社であれば、同じタイミングで入社する人が多いため研修体制が整っている可能性が高くなります。
第二新卒であれば、4月入社により新卒入社の人と同じ研修を受けることが可能です。
一方で人事異動や組織変更も発生する時期のため、現場の受け入れ体制が十分でない場合もあります。
そのような企業では、4月・10月以外で業種・職種の繁忙期を外した入社タイミングのほうが、現場で手厚くフォローしてもらえる可能性が高まることを念頭に置きましょう。
未経験分野に飛び込む場合などは、入社後の適応しやすさを重視して転職活動のスケジュールを立てることが勧められています。
転職活動時の気温の影響度
近年は採用活動をオンラインで行うケースも増えていますが、最終選考など一度は対面での面接が取り入れられている場合が一般的です。
面接はスーツで行うため、夏の時期は暑さが厳しいとのデメリットがあります。
一方、寒い冬の時期はコートやマフラーなど荷物が増えがちになることがデメリットです。
また、気温が低く風邪などが流行る時期のため体調管理に注意する必要があります。
転職活動では、普段の業務に加えてプライベートの時間に応募や面接などの予定が入ることが多く、どうしても疲労がたまりやすい状態です。
スムーズに選考を進めるためには体調管理が重要なため、気温や現在のお仕事の繁忙期など、ご自身の体調にあったスケジュールを選びましょう。
【年度末の転職】転職しない方が良いタイミング
以下のようなタイミングでは、転職しない方が安全です。
- 経済的な余裕がない
- 転職への気持ちがまとまっていない
- 入社して1年も経っていない
経済的な余裕がない
転職は経済的な余裕がない状態での決断は避けましょう。
転職活動には時間がかかることがあり、次の職場が決まるまで収入が途絶える可能性があるため、安定した資金を確保しておくことが重要です。
面接の交通費や引っ越し費用、資格取得の際の学習費用など、転職活動には多くの出費が発生します。
入社後すぐに収入が安定するとは限らず、給与の支給日が前職と異なることで、一時的に資金繰りが厳しくなることもあるでしょう。
貯蓄が不足していると、焦って転職先を決めてしまい、理想の転職を築く妨げになるかもしれません。
そのため最低でも3~6か月分の生活費を確保してから転職活動を始めると、経済的な不安を抱えずにじっくりと企業選びができます。
退職後はすぐに転職できる保証はないため、慎重に計画を立てなければなりません。
焦らずにまずは収入・貯金を見直し、安心して活動できる状態を整えましょう。
転職への気持ちがまとまっていない
転職を成功させるためには、明確な目的を持つことが欠かせません。
転職理由の方向性が定まっていない状態で行動すると、選択を誤って後悔する可能性が高まります。
意思が固まっていないまま転職活動を始めると、企業選びの基準が曖昧になりがちです。
結果として、待遇や職場環境に対する優先順位を見誤り、入社後にミスマッチを感じるケースが増えます。
例えば「今より年収を上げたい」「専門スキルを活かせる仕事に就きたい」など、具体的な目標が明確であれば、企業選びの基準が明確になります。
逆に、「現職が合わない気がする」といった漠然とした理由では、適切な判断が難しくなるでしょう。
転職を決断する前に、何を優先するのかを明確にすることで、より良い選択ができるようになります。
入社して1年も経っていない
転職を考える際、入社して1年未満のタイミングでの決断は慎重に検討することが大切です。
十分な経験を積む前に退職すると、次の職場でも同じ問題に直面する可能性があります。
短期間で転職する場合、企業側から「忍耐力が足りない」「すぐに辞めるリスクがある」と判断されることが多くなります。
業務内容や職場環境に十分慣れていない段階では、現状の課題が一時的なものなのか、本当に転職が必要なのかを見極めることが重要です。
新しい環境に適応するには半年から1年程度の期間が必要です。
最初は仕事が上手くいかなくても、上司や同僚との関係が築かれ、業務に慣れるにつれて状況が改善することも少なくありません。
短期間での退職を繰り返さないためにも、まずは現在の職場での成長機会を十分に活かし、冷静に判断することが重要です。
春からの転職活動がおすすめの10の理由
転職活動のスケジュールは、さまざまな観点から検討する余地があります。
一般的に有利と言われる時期だけが正解ではありません。
自分にとっての優先順位をもってベストなタイミングを決めていくことが大切です。
さまざまな観点で良いポイントを網羅できる時期として、春から転職活動を始めるというスケジュールも検討してみましょう。
下記項目以降、春からの転職活動をおすすめする8つの理由を説明します。
1.企業の採用意欲が高い
事業年度に合わせた年度末のタイミングをあえて外すことで、採用意欲が高い企業に出会いやすくなります。
一般的な企業では、4月に新入社員を迎えた後の6月以降が中途採用の募集時期です。
しかし中には、あえて新年度を迎えたタイミングで中途採用する企業があります。
新しい事業年度に入り新体制で臨んだものの、人手不足の問題が表面化したり退職者が出たりして穴埋めしなければならない急を要する事態が生じた場合などが主な理由です。
そのような事情がある企業側は、できるだけ早く即戦力となり得る人材を採用したいとの意欲を持っています。
そのため、選考が早く進み、タイミングが合う人が優先的に採用されるケースも少なくありません。
この時期に希望の求人に出会えれば、選考がスムーズに進む可能性が高くなります。
2.転職活動者が減少傾向でチャンスが多い
4月になると、年度末のハイシーズンが落ち着き、転職市場の求職者の数は減少します。
新年度を迎え新体制として活動しはじめるため、在職して責任のある立場に就いている人などは、転職を検討していてもなかなか行動に移せない環境に置かれてしまう時期です。
一方、企業側は活躍してくれる転職希望者を求めて求人を強化している場合があります。
転職活動者が減少傾向であれば、同じような希望条件を求めているライバルが少ないことはメリットです。
ライバルが少ない分、選考の通過率が高まり、入社のチャンスは増えることを期待できます。
転職希望先企業が決まっている場合や他の人と似たような希望条件を望んでいる場合などは、新年度が始まり転職活動者が減少する春の時期を狙ってみましょう。
3.仕事の区切りがつけやすい
国内の企業では、4月から翌年3月までを一事業年度としているケースが一般的です。
年度末に決算処理を行い、4月から新たに各部署での業務がスタートします。
業界・業種にかかわらず、半期または年度のプロジェクト・目標などを4月から立てることが一般的です。
新入社員も含め、みんなで一丸となって自社の利益向上や業績拡大に向けて努力を傾けます。
春からの転職活動では、他の社員とスタートラインがさほど時期がずれません。
そのため、区切りよく業務を開始できます。
前職で自分が任されていた業務の引き継ぎも、3月の年度末で同僚などに引き継げるため、双方にとって区切りがつけやすい時期です。
4.引き継ぎがしやすい
前職でどのような業務や責任を担っていた場合でも、退職する際は他の社員などに引き継ぎをしなければなりません。
企業ごとに組織や人事の体制が異なるため一概にはいえないものの、退職のタイミングによってはせっかく引き継いだ社員が人事異動になってしまったとの事例が時折見受けられます。
引き継ぎにかけた時間や努力が無駄になってしまう残念な結果です。
多くの企業で新年度を迎える春の時期は、組織の変更や人事異動が行われる時期でもあります。
そのため、春からの配属先が決まっている社員に引き継ぎを行うことが可能です。研修制度も充実していることも多くあります。
企業側の受け入れ態勢が万全な春の時期は、引き継ぎの不安や心配を減らせる良いタイミングです。
5.入社後に馴染みやすい
転職する際の不安要素として、入社後に馴染めるかどうかを挙げる人は多いのではないでしょうか。
初めて転職する際は特に不安になります。
転職先企業の社員が受け入れてくれるかどうかが気になる点です。
入社後に馴染みやすいかどうかを重視する場合も、春の時期はおすすめです。
決算期を終えて新たな気持ちで迎える新年度は、新入社員も不安や期待を抱いて出社します。
長年勤めている社員でも、組織の変更または人事異動などで新たな部署に配属されるケースは少なくありません。
新規事業が立ち上げられて、新しい業務を始める人もいます。
そのような環境のため、自分だけが業務に慣れていないわけではありません。
同じような不安や心配を抱えている人が周囲にいる可能性が高いため、コミュニケーションを取りやすく、馴染みやすいタイミングです。
6.責任あるポジションを任されやすい
春からの転職活動は、キャリアアップを狙う上で有利なタイミングです。
年度初めは組織編成が行われる時期であり、新たなポジションが生まれやすいため、責任のある役職に就くチャンスが広がります。
企業は、組織体制を整えるために、新年度のスタートと同時にリーダー候補やマネジメント層の採用を強化します。
成長企業では事業拡大に伴い、新しい役職が設けられるケースも増えるので、春から転職活動を始めることで、重要なポジションを得られる可能性が高まるでしょう。
4月や5月の求人では、新規プロジェクトの立ち上げや管理職の採用が多く見られます。
上手くタイミングを狙うことで、経験を活かしながら、より高い役職へのキャリアアップが実現しやすくなるでしょう。
転職の成功には、適切な時期を選ぶことが欠かせません。
7.GWを利用した準備期間
転職の経験があれば、転職が思いのほか心身に疲れを感じたのを思い出すのではないでしょうか。
新しい環境に飛び込むのは、誰にとっても力が要ります。
周囲を取り巻く人が変わり、業務内容を覚えることが必要です。
同業界・同業種への転職でも、企業ごとに社風や社則が異なるため、今までどおりのままでは通用しません。
緊張感を持って業務を遂行する場合が通常です。
その点を踏まえ、春の転職活動は、5月のゴールデンウイークを有効に活用できます。
忙しい毎日を過ごし続けている自分をいたわってリフレッシュ期間に充てたり、新しい業務内容を覚えるための学習期間に充てることが可能です。
また、ゴールデンウイークの長期休暇を転職の準備に充てることもできます。
転職活動を始める前にまとまった時間を準備に充てられることで、質の高い応募書類を作れるだけでなく、自身の納得感の高い転職が実現しやすくなることがメリットです。
8.夏のボーナスをもらってからの転職が可能
どのような種類の仕事も、何かしら問題・課題にぶつかります。
大変だと思う場合でも、ボーナスなどの報酬があれば、モチベーションアップにつながるのではないでしょうか。
転職する場合も、ボーナスを受け取ることも視野に入れて無理のない計画が立てられます。
国内の企業では、夏・冬のボーナス支給が一般的です。
4月が年度初めの場合、通常前年度の10月から翌年3月までの下半期に残した実績や評価を基に、夏のボーナスが支給されます。
冬のボーナス算定時期は、今年度上半期の4月~9月です。
ボーナス算定期間に勤務していない場合、月額または日割りで計算されるケースが多くあります。
ゴールデンウイーク前後から転職活動を開始し、6~7月に選考・内定、引き継ぎや有給消化を経て7~8月に退職とのスケジュールであれば夏のボーナスをもらえます。
ボーナス支給を見据えたスケジュールを立ててみましょう。
9.さまざまな業種・職種と出会える
春は多様な業界の求人が増える時期であり、理想の転職先を見つけやすいタイミングです。
企業が新年度に向けて採用計画を見直すことで、幅広い業種や職種の選択肢が広がります。
新卒採用と並行して中途採用も活発になるため、未経験者向けのポジションから専門性の高い職種まで、多彩な募集が見込まれます。
4月からの新規事業立ち上げに伴い、新しい職種が生まれることもあり、選択肢が増えていくでしょう。
例えば、IT業界では新技術の導入に伴うエンジニアの採用が増加し、コンサルティング業界では新規案件対応のための人材募集が強化される傾向があります。
時期を見ながら転職活動を進めることで、より多くの選択肢の中から最適なキャリアを選ぶことができます。
多様な業界の動向を見極めながら、春の採用市場を活用しましょう。
10.過ごしやすい気候での転職活動
夏が本格化する前に活動を終了するスケジュールになるので、暑い中スーツでの移動をしなくてすみます。
面接前に汗などを気にせず、快適に活動ができるでしょう。
以上のように、転職市場の動向やボーナス時期、気候などの観点をバランスよく網羅できるのが春からの転職活動です。
このタイミングでは希望する求人が見つからなくても、十分に準備できた状態で年度末のハイシーズンを迎えられるためライバルに差をつけやすくなります。
転職を検討する人はぜひゴールデンウイークを動き出しの目安にしてみてください。
【年度末の転職】年度末転職市場の背景と特徴
転職市場が1年で最も盛り上がると言われる年度末。
その背景には、求職者からも企業からも選ばれる理由があります。
この時期ならではの特徴もご紹介しましょう。
求職者:冬のボーナス後の退職が多い
求職者の視点では、12月の冬のボーナスを受け取った後、新年度に向けて転職活動を始めやすい時期です。
年末年始に1年を振り返り目標や抱負を新たにする人が往々にして見られます。
企業の求人数が増えるため、それに合わせて行動する点が特徴です。
企業:新年度前に人員補充を目指す
企業側の視点では、次年度からの事業計画に合わせて必要な人員を補充する時期に当たります。
12月や3月のタイミングで退職者が出やすいため、年度末には人員不足となることは珍しくありません。
4月には新卒入社者が入ってくるため、教育に力を割く必要があり、転職者は1~3月のうちに採用してしまいたいと考える傾向にあります。
こうした背景から、年度末は転職市場のハイシーズンです。
【年度末の転職】年度末転職活動のメリットと注意点
以上を踏まえて、一般的に転職のベストタイミングと言われる年度末転職ですが、メリットだけでなく注意点もあります。
成功につなげるためには早めの動き出しがポイントです。
【転職者側】メリット:多くの求人と短い転職期間
年度末には、数多くの求人が出ており、選択肢が豊富です。
普段あまり求人が出ていない企業も、この時期には募集しているというケースがあります。
そのため、自分の条件に合う応募先が見つかりやすくなりますし、複数の企業からより条件の良いものを選びやすくなることがメリットです。
また、この時期多くの企業では、年度内に採用完了を目指しています。
1月に活動開始し、2~3ヶ月の短期間で決着がつく場合が多く、活動が長引かずに済む傾向です。
注意点:ライバルが多く、スケジュールがタイト
注意点として、ライバルとなる他の求職者の数が多く、短期決戦となる分、スケジュールがタイトです。
事前の準備を十分行い、自分にあった応募先をよく見極めなければ、せっかく応募しても選考通過できない可能性が高くなってしまいます。
注意点:十分な教育が受けられない可能性も
注意点として、新年度直前の転職では、十分な研修や教育を受けられない可能性があります。
企業は年度末に向けて業務の引き継ぎや決算対応に追われるため、新入社員への指導に十分な時間を割けない場合があります。
特に新しい職場の業務フローや社内ルールを学ぶ機会が限られると、早期に成果を求められる環境で苦労することがあるかもしれません。
年度末の転職を検討する際は、入社後の研修体制やサポート環境を事前に確認し、スムーズに業務へ適応できる準備を整えることが大切です。
【企業側】メリット:いい人材に出会える
年度末の転職市場が活発になることは、転職者側だけでなく、企業側にとっても自社に必要な人材を見つける良いチャンスです。
国内全般で、さまざまな理由により転職活動する人がいます。
中には、専門分野での経験やスキルを持ち合わせている人もおり、人材の種類が豊富です。
同業種・異業種を問わず、自分らしく仕事できる環境を求めて転職希望している人も少なくありません。
求人に対して応募者数が多ければ多いほど、自社の社風・方向性に合う人材に出会えるチャンスが高まります。
年度末の転職市場を活用し、業績を拡大し、利益を上げるために活躍してくれる人材を探してみましょう。
注意点:求人が多く時間がない
年度末の転職市場は、期待が大き過ぎてうまくいかなかったとの声も時折聞かれます。
メリットだけに注目するのではなく、注意点も覚えておきましょう。
覚えておきたい注意点は、転職市場での求人情報が多い場合、自社の求人要綱が埋もれてしまいがちになる点です。
同業界・同業種間で、他社が求人情報を大々的に出している場合などは特に気を付ける必要があります。
自社に必要な人材が転職希望していても、検討の対象にならなければ自社に応募してもらえません。
新卒の就活と異なり時間がさほどないため、転職希望者の目に魅力的に映るような工夫が必要です。
転職市場で他社の求人情報を小まめにチェックし、自社の採用条件を他社と比較する方法も試してみましょう。
転職時期別の市場動向
いつが転職のベストタイミングかは人によって異なります。
自分にとってのベストタイミングを考える上で、1年の流れとお金が関わるタイミングを把握しておきましょう。
1年間の転職市場と時期別の特徴
まず、採用する企業の側の視点で1年間の転職市場を見ていきましょう。
■1~3月 新年度の体制に向けた採用が活発化
次年度の事業計画に基づき、新体制のための採用活動が1月頃から活発化していきます。
12月末・3月末で退職者が出るタイミングで人員が不足するタイミングです。
4月からの新体制に合わせて採用していくため、スピーディーに選考が進む可能性があります。
第二新卒者を新卒と合わせて育成を行う目的で、4月1日入社での求人を行う時期です。
3月後半以降は新卒入社の受け入れなどで忙しくなり求人が減少していきます。
■4月 中途採用は一時停滞
新卒入社の受け入れや次年度の新卒採用活動で人事部は繁忙期になります。
中途採用は、年度末までの採用を目標に動く企業が多く、3月後半から4月にかけて中途採用のニーズは落ち込む傾向です。
一方、大手企業の中途採用が減るため、中小企業やベンチャー企業があえてこの時期を狙って採用活動を行っている場合もあります。
■5~7月 今年度の採用活動始動
ゴールデンウイーク明けから事業計画・人員計画に沿った採用活動がスタートしていきます。
4月入社者が早期退職した場合など、新体制で不足人員が出ている場合もあり採用熱が高い時期です。
6~7月は夏のボーナスの時期にあたり、ボーナスを受け取って退職者が出る時期でもあります。
■8月 長期休暇で選考スピードが落ちる時期
下期の計画に向けた採用活動が始まり応募者も増える一方で、夏休みを挟むため選考スケジュールが決まりづらくなります。
転職活動が長引きがちなので注意しましょう。
■9~10月 年度末に次いで中途採用の求人増加
下期計画への採用活動で求人が増えます。
年度末に次いで求人数が多くなる時期です。
■11~12月 次年度4月入社者の募集がスタート
翌年4月1日から入社予定者の募集が始まります。
冬のボーナス支給時期でもあり、退職者が出てくるため、欠員の募集もかかります。
ただし、8月同様年末年始の休暇もあり選考が進みづらい場合があるので注意してください。
ボーナスを考慮した転職時期
転職活動のスケジュールの検討にあたっては、現職でのボーナスが受け取り可能な時期も考慮できます。
まずは就業規則でボーナスの支払い規定を確認しましょう。
ただし退職意向を伝えるのはボーナスを受け取った後にする方が安全です。
ボーナス支給時期の1か月前を目安に応募をスタートし、ボーナスを受け取った後に内定を獲得し、退職交渉に入るイメージで動けると効率が良くなります。
第二新卒や社会保険料の負担を軽くするタイミング
その他に考慮すべきタイミングとして、第二新卒の場合で、退職日と社会保険料負担の関係をご紹介します。
第二新卒の場合は、ベンチャー企業など通年で第二新卒を募集しているケースもあるものの、大手企業の場合は第二新卒を受け入れる時期が決まっている場合が多い傾向です。
転職タイミングは、新卒採用の充足状況が見えてきた7~9月頃、もしくは次年度の新卒と研修のタイミングを合わせられる1~3月頃がおすすめとされています。
最後に、無事転職先が決まり退職意向を伝えた後、交渉によって退職日をいつにするか決めていくことが必要です。
タイミングによって社会保険料の負担額が変わることに注意しましょう。
前提として会社に勤めているときは、社会保険料は会社と社員が折半で支払っており、会社が保険料の半額を負担してくれています。
退職する場合、退職日の翌日が「資格喪失日」となり、資格喪失日を含む月の保険料は元の会社が負担してくれません。そのため自分で保険料全額を負担するか、配偶者などの家族の扶養に入るかのいずれかになります。
全額負担を回避するためには、退職日と入社日の設定に注意しましょう。
具体的には、退職日と転職先への入社日を同じ月にする(例:6月15日退職→6月20日入社)、もしくは退職日を月末・入社日を月初にする(例:6月30日退職→7月1日入社)ようにしましょう。
資格喪失日を含む月の保険料が転職先と折半になり、負担額を減らすことが可能です。
【年度末の転職】年度末の転職スケジュール
年度末をもって退職を検討している人の多くは、新年度の4月から次の職場に転職したいとの願いを持っている人が多いのではないでしょうか。
年度末は、求人情報が多いものの、採用活動がスピーディーに進むケースが多くあります。
タイトなスケジュールの中で転職を成功させるために、事前に流れを把握しておきましょう。
事前に準備すること
転職を決意したなら、退職希望日の1か月前までには直属の上司に伝えることが一般的です。
ただし、企業ごとにルールが異なるため、就業規則を確認しておく必要があります。
また、中途採用したい企業側の事情はさまざまです。
大抵の企業では、即戦力となる人材を求めています。
事前に、応募先企業の調査をしっかり行い、社風・事業内容・今後の方向性などを情報収集しておきましょう。
どのような人材を求めているのか、何を期待されるのかをある程度予想しておきます。
応募先企業に関する情報収集結果を基に、自分の持つ経験やスキルなどを自己分析しましょう。
情報収集や自己分析などの事前準備は、転職成功につながります。
書類作成をして応募する
一般的な企業では、応募する際に、履歴書や職務経歴書などの書類を作成する必要があります。
新年度の入社時期に合わせたいのであれば、スムーズな応募がポイントです。
応募先企業に関する調査および自己分析を基に、自分の強みやアピールポイントを事前に明確にしておくと、書類作成が容易になります。
年度末は求人情報が多いため、複数の企業が気になるケースも多々あります。
最初の応募企業に落ちてしまった場合、速やかに次の候補企業に応募しなければなりません。
複数企業に並行して応募する際は、書類の提出など企業側の求めに対してスピーディーに対応する心構えが必要です。
面接を行い内定をもらう
履歴書や職務経歴書などの書類選考に通過した後は、面接の段階へと進みます。
年度末で転職する予定の場合、書類選考から面接までの時間が短いケースが多いため、自分のスケジュール管理が大切です。
基本的に、書類選考に通過した後、応募先企業の採用担当者から面接の日程に関する連絡が入ります。
現職の予定をきちんと把握し、一度決めた面接日時をずらしてもらわなければならない都の状況が生じないよう十分注意しましょう。
無事に面接を終え、企業側との折り合いがうまくいった場合、内定をもらえる流れです。
内定をもらった後は、退職日および入社日を本格的に決定します。
【年度末の転職】転職活動を成功させるためのポイント
どの時期に転職活動をするのがベストタイミングかは、それぞれの人の状況によって異なります。
自分にとってベストなタイミングを見極め、条件にマッチした企業に出会うことが大切です。
どの時期に活動する場合でも、転職活動を成功させるために、以下のポイントがあります。
焦って動き出すことなく、しっかり考える時間を確保するようにしましょう。
転職理由と志望動機の明確化
何より大事なことは、なぜ転職したいか、転職目的の明確化です。
転職することで何を実現したいのかが分かっていないと、自分自身が満足できる選択肢を選べません。
自分にとって必要な条件を言語化し、優先順位をつけておきましょう。
転職理由が明確になっていれば、膨大な求人からどういった基準で選べば良いかがはっきりします。
自分でも探しやすくなりますし、転職エージェントを利用する際にも自分の希望にあった求人を紹介してもらいやすくなるため重要です。
明確な転職理由を持つことで、「なぜこの業界を選ぶのか」「なぜこの職種を選ぶのか」がはっきりし、おのずと志望動機も明確になります。
自分で納得し自信をもって伝えられる状態であれば、選考にも通過しやすくなることを覚えておきましょう。
自己PRの工夫
自分の納得感だけでなく、企業の採用担当者にも「活躍してもらえそうだ」と納得してもらうことが必要です。
そのためには、志望動機や自身の強みなど、面接で問われるさまざまな内容を、簡潔に分かりやすく、かつ一貫性を持って語れるよう準備しなければなりません。
採用担当者はたくさんの応募者と面接をしています。
回答内容がまとまっていないと、結局何を言いたかったのかが伝わらなかったり、印象にあまり残らなかったりする可能性が高くなり残念です。
相手目線で伝わりやすい表現や話し方になるよう準備しておきましょう。
また、企業は採用に多大なコストをかけており、せっかく採用した人材には長く働き続けてもらいたいと考えています。
面接でさまざまな質問をするのは、自社にマッチし、長く活躍し続けられる人材を確実に見極めるという狙いが主な理由です。
一つ一つの質問への回答が簡潔で分かりやすくても、複数の質問に対する回答内容に一貫性がないと、アピールしている内容への納得感を持ってもらえません。
自分で一貫性があるかどうか自信がない場合は、応募書類の準備や面接の練習に転職エージェントなどの第三者の協力を受けフィードバックをもらうことをおすすめします。
譲れる条件と譲れない条件を明確にする
転職する理由を考慮する際は、現職での反省点も踏まえ、譲れる条件と譲れない条件を明確にしましょう。
なぜ今の職場を辞めたいのかを考え、どのような職場なら満足できるかを考え、ノートなどに書き出してみます。
自分が求める全ての好条件を叶える企業を見つけるのは、現実的ではありません。
しかし、優先順位を付けておくことにより、入社後のミスマッチを防げます。
例えば、年収・職場環境・福利厚生・通勤時間などの面で、自分がストレスと感じている部分を絞って考慮してみましょう。
残業時間や通勤時間など、譲れない条件を明確にして転職先を探せます。
応募企業を絞らない
転職理由や譲れない条件を明確にした上で求人情報を検索していると、数ある企業の中から応募したいと思う企業が絞られてきます。
応募先企業に関する情報収集に時間がかかるため、1社に絞ったほうが良いのではないかと思うことがあるでしょうか。
時間が限られている中転職活動をするため、複数企業に関する情報を集める時間はないと感じるのも無理はありません。
しかし、転職活動は十分な事前準備をした場合でも必ずしも成功するとは限らないことを覚えておきましょう。
万が一の場合に備えて、第二および第三希望を考えておくことが勧められています。
転職エージェントを活用する
一般的に、12月のボーナスを受け取った後に退職した人が転職活動を活発に始めるのは、年度末が多いといわれています。
転職市場の動向を踏まえて、企業側も数多くの求人情報を出している現状です。
多くの転職希望者が努力を重ねているため、十分な準備をしたと自分で思っていても、残念ながら内定につながらないケースがあります。
自分では分からない弱みなどを見つけるためにも転職エージェントの活用がおすすめです。
書類作成や面接対策などを含む、スピーディーな転職サポートに定評があるアゲルキャリアをぜひご活用ください。
【年度末の転職】転職のタイミングに迷ったときに考えること
転職のタイミングに迷ったときは、以下のことについて考えてみましょう。
- 何年働いているか考える
- 現在の年齢を考える
- 経済的な損得を考える
何年働いているか考える
転職を成功させるには、現職での勤務年数を考慮することが重要です。
一定期間の経験を積んでから転職することで、市場価値を高め、有利な条件で新たなキャリアを築けます。
勤務年数が短いと、採用担当者から「すぐに辞める可能性がある」と判断され、選考が不利になることがあるでしょう。
1年未満での転職は、業務スキルや実績の蓄積が不十分と見なされることが多くなります。
3年以上働いている場合は、専門性やリーダーシップの経験が評価されやすく、キャリアアップの選択肢が広がります。
一方で1~2年の勤務では、新しい環境での適応力をアピールする必要があるでしょう。
現在の年齢を考える
転職のしやすさは、年齢によっても左右されます。
自身のキャリアの成長を考え、年齢に応じた適切なタイミングを選ぶことが必要です。
20代は未経験職種への挑戦がしやすく、30代以降は専門スキルやマネジメント経験が求められる傾向があります。
転職時に求められる役割が変化するため、年齢に合ったキャリアプランを立てることが重要です。
20代後半から30代前半は、リーダー職や管理職へのステップアップが期待され、転職で年収アップの可能性も高まるでしょう。
一方で、40代以降では即戦力としての成果が求められるため、転職先の選択肢が限られることもあります。
自身の市場価値を把握し、長期的な視点で転職を考えることが成功の鍵となります。
経済的な損得を考える
転職には収入の変動が伴うため、経済的な影響を慎重に見極めることが必要です。
収入の安定を確保した上で転職を決断することで、無理のないキャリアチェンジが可能になります。
転職後すぐに収入が増えるとは限らず、場合によっては試用期間中の給与が低く設定されることもあります。
また退職タイミングによってはボーナスや退職金を受け取れないリスクも考えられます。
例えばボーナス支給後に退職すれば、転職活動の準備期間に経済的な余裕を持つことが可能です。
また年収アップを目指す場合は、業界ごとの給与水準を調査し、現職と比較した上で転職先を選びましょう。
【年度末転職】年度末転職の成功に向けて
一般的に転職に有利と言われる年度末の転職は、企業の求人が盛んで、さまざまな条件から応募先を検討できるベストタイミングです。
一方で、応募者の数も多く短期決戦になる分、希望の転職先の内定を勝ち取るためには事前に入念な準備をしておくことが重要でもあります。
企業の採用意欲が高い春の時期など、見方を変えれば年度末以外にも転職に適しているといえる時期はさまざまです。
どのタイミングでの転職がベストになるかは人によって異なります。
いずれのタイミングであったとしても、どのような条件であれば転職成功といえるかはあなたの転職の目的次第です。
まずは転職理由と志望動機を明確にし、納得のいく転職活動になるよう余裕を持ってスケジュールを立てていきましょう。
タイミングに迷う方は春のゴールデンウイークを動き出しのきっかけにすると、じっくり自身と向き合い十分な備えをした上で転職活動に臨みやすくなります。
キャリアに迷いのある方は、ぜひ連休を自分と向き合い整理する時間に充ててみてください。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!