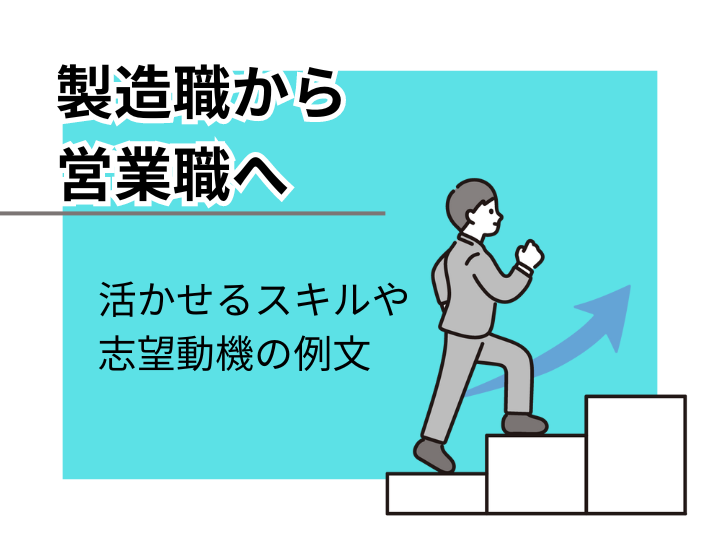年度末の退職は問題ない?やるべきことやタイミングなども合わせて解説
はじめに
年度の区切りとなる時期は、多くの人がキャリアの節目を考えるタイミングでもあります。
特に年度末から新年度にかけては、企業の方針転換や人員整理などが重なることもあり、退職を決断する人が増える傾向にあるでしょう。
この記事では、年度末に退職を検討している方に向けて、事前に準備すべき事項を詳しく解説します。
また、退職後に転職活動を始めるべきか、それとも在職中に進めるべきかという選択肢についても考察します。
さらに、退職の決断に迷いが生じた場合に確認しておきたいポイントについても触れていきます。
【年度末の退職】「年度末」の定義
「年度末」という言葉は、主に会計年度の終わりを指し、日本では多くの企業や官公庁が3月31日をその日と定めています。
年度末の時期は、組織が一つの区切りを迎えるタイミングとして、人事異動や新年度の準備が活発に行われることが特徴です。
一方で、12月末も年末として区切りの良い時期とされますが、年度末とは異なる意味を持ちます。
企業によっては、冬の賞与が支給される時期であり、これを機に退職を考える人も多いでしょう。
12月末に退職を決断すると、会社側で年末調整をしてもらえるという利点がある一方で、求人数が減少することや賞与が満額支給されない可能性といったデメリットも見逃せません。
一方、3月末の年度末は退職者が多いことから、求人数が増える傾向にあります。
ただし、人事部門が非常に忙しい時期でもあるため、転職活動をスムーズに進めるには難しさも伴います。
また、年度末に退職する場合は、年末調整を自身で行う必要が生じる点も考慮すべきです。
年末と年度末はどちらも節目として意識されますが、役割や意味合いには明確な違いがあります。
年度末は組織の会計年度の締めくくりを指すのに対し、年末は暦年の終了を意味するものと理解するとよいでしょう。
【年度末の退職】メリット
年度末の退職は、新たなスタートを切る良い機会となります。
ただし、いくつか注意すべき点も存在します。
ここでは、特に12月末に退職する場合のメリットについて詳しく解説します。退職を検討中の方はぜひ参考にしてください。
ボーナスを受け取れる
12月末に退職する大きなメリットとして、冬のボーナスを受け取れる可能性が高い点が挙げられます。
多くの企業では12月上旬にボーナスが支給されるため、支給後に退職することで、金銭的な不安を軽減し、余裕を持って転職活動に取り組むことができます。
ただし、満額支給されるかどうかは注意が必要です。退職の意思を伝えるタイミングや契約内容によっては、支給額が減額されるケースもあるでしょう。
満額支給を希望する場合は、12月以外の退職時期を検討することも選択肢に含めると良いでしょう。
このように、12月末の退職はボーナスを受け取れる可能性がある一方で、減額のリスクも伴うことを理解しておくことが重要です。
年末調整をせずに済む
もう一つのメリットとして、12月末に退職すると会社で年末調整を済ませてもらえる点が挙げられます。
通常、12月に会社が年末調整を行うため、12月末に退職することで、自身で確定申告をする手間を省けます。年末調整とは、会社が源泉徴収した所得税と実際の納税額を調整する手続きのことです。
もし12月末以前に退職した場合や、年収が2,000万円を超える場合は、自分で確定申告を行う必要がありますが、12月末退職であれば、これを避けることができます。
このように、12月末退職には、手続きの負担を軽減できるという利点があります。
社会保険料の負担を抑えられる
12月末に退職するメリットとして、社会保険料の負担を抑えられる点も見逃せません。
月末に退職した場合、その月の社会保険料は会社が負担するため、自己負担を避けられるのがポイントです。
一方、月の途中で退職すると、翌月分の国民健康保険や国民年金の支払いが必要となり、約3万円の追加負担が発生する可能性があります。
ただし、12月末に退職する際には、給料から2ヶ月分の社会保険料が天引きされるケースもあるため、注意が必要です。これは、給料の締め日が月末の場合、社会保険の資格喪失が翌月となるためです。
以上のように、12月末退職には社会保険料の負担を軽減できるメリットがある一方で、一時的な負担増加の可能性もあることを踏まえて検討することが大切です。
【年度末の退職】デメリット
年度末での退職は、新たな一歩を踏み出すきっかけとなる一方で、注意が必要なデメリットも存在します。ここでは、12月末に退職する場合に生じる可能性のあるデメリットについて詳しく解説します。退職を検討している方は参考にしてください。
年度末の退職はメリットも多い一方で、繁忙期の影響や転職活動への不利、税金手続きの複雑さといったデメリットが存在します。十分な準備をもって判断することが求められます。
繁忙期と重なりやすい
12月末に退職すると、企業の繁忙期と重なりやすく、手続きがスムーズに進まない可能性があります。
この時期は、多くの企業で年末調整や決算業務が集中し、人事部門が多忙になるためです。
たとえば、12月末に退職の意思を伝えると、人事担当者の対応が遅れたり、引継ぎが十分に行われない場合も考えられます。
また、忘年会などのイベントが多く、退職の挨拶をするタイミングを見つけるのが難しくなることもあります。
退職を円滑に進めるためには、できるだけ早めに上司へ意向を伝え、余裕を持って準備を進めることが重要です。
こうした点を踏まえ、12月末の退職には繁忙期との兼ね合いがあることを理解しておきましょう。
転職活動で不利になりやすい
12月末に退職すると、税金関連の手続きが複雑になる可能性がある点にも注意が必要です。
通常、会社員は年末調整によって所得税が調整されますが、12月末に退職する場合、自分で確定申告をしなければならないケースがあります。
特に、年収が2,000万円を超える場合や、副業で20万円以上の収入がある場合は、自動的に確定申告が必要となります。
また、12月末以前に退職した場合も同様に、自ら年末調整を行わなければなりません。
確定申告には、所得税の計算や必要書類の準備といった複雑な作業が伴い、時間と手間がかかります。
そのため、税理士などの専門家に相談することも選択肢に入れるべきでしょう。
12月末の退職を検討する際には、税金関連の手続きが煩雑になる可能性を事前に理解しておくことが重要です。
税金の計算が複雑になる
12月末に退職する場合、税金の計算が複雑になる可能性があるというデメリットがあります。
通常、会社員は会社で年末調整をしてもらえますが、12月末に退職する場合は、自分で確定申告をしなければならないケースがあるからです。
具体的には、年収が2000万円を超える高収入の方や、副業で20万円以上の収入がある場合は、会社で年末調整をしてもらえないため、自分で確定申告をする必要があります。
また、12月末以前に退職した場合も、年末調整を自分で行う必要が出てきます。
確定申告は、所得税の計算や必要書類の準備など、複雑な手続きが必要となるため、時間と手間がかかります。
したがって、12月末の退職を検討している場合は、確定申告が必要になるかどうかを確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することも検討しましょう。
このように、12月末の退職は、税金の計算が複雑になる可能性があり、確定申告が必要になる場合があることを理解しておく必要があります。
【年度末退職】退職時期に関して知っておくべきこと
退職時期を決定するためには、まず転職活動にどれくらいの期間が必要かを把握しておくことが重要になります。
結論として、転職活動の開始から退職までには、一般的に3〜4ヶ月程度の期間を見込むべきです。
たとえば、12月末に退職する場合は9月から、3月末に退職する場合は前年の12月から転職活動を始めるのが理想的です。
おおまかなスケジュールとしては、転職活動の開始から内定が出るまでに1〜3ヶ月、内定後から実際に退職するまでに1〜1.5ヶ月ほどの時間が必要と認識しておきましょう。
転職活動が順調に進めばこのスケジュールが短縮される場合もありますが、進行が遅れるケースも想定して余裕を持った計画を立てることが大切です。
スムーズにいかない場合や予期せぬ事情で進行が遅れることを考慮し、バッファを持って準備することをおすすめします。
現職での退職交渉は、退職希望日の1〜1.5ヶ月前に行うのが理想的です。
理由として、退職の意思を伝えても、即座に退職が可能ではなく、手続きや業務の引き継ぎに一定の時間が必要だからです。法律上は退職の意思を2週間前に伝えれば問題はありませんが、現実的には厳しい場合が多く、トラブルを引き起こす可能性があります。
たとえ法律的には問題がなくても、引き継ぎが慌ただしくなり、職場内での混乱を招くことがあります。
さらに、多くの場合で有給休暇の消化も考慮する必要があります。そのため、退職交渉は退職日から逆算して1〜1.5ヶ月前に行うスケジュール感を持って進めることが重要です。
円滑な退職手続きを実現するためにも、早めの計画と行動が求められます。
退職に有利なタイミングとして年度末はおすすめ
年度末は退職に適したタイミングとされ、新年度から新しい職場でスタートを切る絶好の機会といえます。この時期は、多くの企業が新年度に向けて人員を増やすため、求人数が豊富になる傾向があります。
特に求人数が増えるのは、10月と3月です。10月の求人数がピークとなるタイミングを狙うには、9月から行動を始めることがポイントです。
10月から準備を始めると、すでに多くの求人が選考段階に進んでいたり、応募が締め切られていたりする可能性があります。
また、転職活動を始める際には、希望する職種やポジションの方向性を明確にし、職務経歴書などの書類を準備する必要があります。
つまり、10月が求人数のピークであるにも関わらず、この時期に転職活動を始めてしまうと、準備に時間を取られ、有利なタイミングを逃すリスクがあるのです。
そのため、9月から動き出し、事前準備を万全にしておくことが重要です。
一方、3月の求人数ピークを目指す場合は、前年の12月から転職活動をスタートすると良いでしょう。
3月に求人数が増加する背景には、多くの企業で退職者が出る時期であることが挙げられます。
あなたが勤務している企業でも、3月末に退職する予定があれば、欠員を補充するために求人を出すはずです。
ただし、3月の転職活動にはデメリットもあります。
この時期は企業の人事部門が非常に忙しく、面接の日程調整が難しかったり、選考がスムーズに進まなかったりする可能性があります。
そのため、年明けから動き出して余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。そして、3月末で退職し、4月から新しい職場に入社できるよう計画を立てると良いでしょう。
年度末の退職は賞与をもらうことを意識する
年度末に退職を検討する際には、賞与の受け取りについても注意が必要です。
企業ごとに賞与の支給規定は異なりますが、一般的に6〜7月頃や12月頃に支給されるケースが多いでしょう。
年に一度まとめて支給する企業もあれば、年2回に分けて支給する企業もあります。
しかし、年度末に退職する場合には、賞与を受け取れずに退職するリスクも考えられます。
たとえば、賞与を受け取ってから退職しようと計画していたにも関わらず、退職の意思を伝えた時点で退職日を前倒しにされ、賞与支給日の前に退職扱いとなったり、支給額が大幅に減額されてしまうケースも0ではありません。
確実に賞与を受け取りたい場合は、賞与が支給された後に退職交渉を行うことを検討すると良いでしょう。また、賞与の受取条件は社内規定によって異なります。
たとえば、「支給日に在籍していること」が条件の企業もあれば、「〇月〇日時点で在籍していれば〇月分の賞与が支給される」といったルールを持つ企業もあります。
損を防ぐためにも、退職前に必ず社内規定を確認し、自分の状況に合ったタイミングで退職を進めることが重要です。
社会保険料についても確認しておく
転職を検討する際には、社会保険料についても事前に確認しておくことが重要です。
特に転職後に年収が大幅に増加する場合、それに伴って社会保険料も上昇する可能性があります。
また、退職日を月末に設定するかどうかも社会保険料に大きく影響します。月末以外に退職すると、社会保険料の自己負担や手続きの負担が増えることがあるため注意が必要です。
会社に所属している間は、社会保険料の手続きは会社が代行し、給与から天引きされる仕組みになっています。さらに、保険料の半額は会社が負担してくれているため、個人の負担は軽減されています。しかし、退職して無所属になると、社会保険料は全額自己負担となります。その場合、配偶者や親などの扶養に入る手続きを行う必要がある場合もあります。
また、厚生年金や健康保険の保険料は、毎年4月から6月に支給された給与額を基準に計算されます。
この計算によって決まった保険料が、その年の9月から翌年8月までの期間にわたり適用される仕組みです。
転職のタイミングを調整することで、社会保険料の負担を最適化できる可能性があるため、事前の確認と計画が大切です。
【年度末退職】年度末に退職するためにやること
年度末にスムーズに退職するためには、以下の7つのステップをしっかり実行することが重要です。
- 自分自身の退職の意思を固める
- 直属の上司に退職の意思を伝える
- 退職日を決めて退職願を提出する
- 有休消化の計画を立てる
- 引き継ぎのために業務を整理しておく
- 会社に返却するものなどを整理しておく
- お世話になった人に挨拶していく
それぞれの項目について、具体的なポイントを解説します。
自分自身の退職の意思を固める
退職の意思をしっかり固めることは、退職準備の最初のステップです。
一見当たり前に思えるかもしれませんが、実際に退職を決断する場面では、「本当に辞めるべきなのか」「このまま働き続けた方が良いのではないか」と迷いが生じることも少なくありません。
このように意思が曖昧な状態で退職の意思を伝えてしまうと、上司や同僚からの引き留めに対して対応が難しくなることがあります。
たとえば、「条件を改善するから残ってほしい」「このプロジェクトが終わるまでは退職を待ってほしい」といった提案を受けた場合、意思が固まっていないと、退職を先延ばしにしてしまう可能性があります。
多くの場合、引き留めの理由は「人手不足が発生する」「管理者としての評価が下がる」といった組織や上司側の都合であることがほとんどです。
そのため、引き留め交渉により退職時期がずれると、転職先に迷惑をかけるだけでなく、転職活動そのものが停滞してしまう恐れがあります。
スムーズな退職を実現するためには、どのような条件であっても揺るがない明確な退職意思を持つことが重要です。自分自身のキャリアや目標に基づいて意思を固め、退職に向けた準備を進めましょう。
直属の上司に退職の意思を伝える
退職の意思を固めたら、まず最初に直属の上司にその意向を伝えることが重要です。
最初に上司ではなく、さらに上の上司や同僚に先に伝えてしまうと、不要なトラブルの原因となるため注意が必要です。
また、退職の意思を伝える際には、チャットやメールなどの文面ではなく、直接顔を合わせて伝えることが大切です。
事前に「この日のこの時間にお時間をいただけますか」とアポイントメントを取り、一対一で面談できる場を設けて意思を伝えましょう。
その際には、希望する退職日を具体的に提示することがポイントです。
さらに、退職理由を聞かれる場合には、現在の不満や否定的な要素を避けることが賢明です。
たとえば、「新たに挑戦したいことが見つかった」など、前向きな理由を伝えることで円満に進めやすくなります。
退職日を決めて退職願を提出する
退職日は自分だけで決めるのではなく、上司と相談しながら決めることが基本です。
業務の引き継ぎや有給休暇の消化などを考慮し、誠意を持って調整を進めましょう。
一部の人は、上司に退職の意思を伝えるタイミングで退職願を提出しますが、これは一般的には必要ありません。
正式な退職日は、上司との相談を経て確定した後に、退職願を作成して提出します。
退職願には多くの場合、「一身上の都合により退職いたします」と記載します。他に理由がある場合でも、この形式で問題なく受理されます。
上司に退職の意思を伝えても、退職願が提出されなければ人事部門は正式な手続きを進められません。退職日が決まったら、速やかに退職願を記入し、上司に提出するようにしましょう。これにより、退職のプロセスが円滑に進むようになります。
有休消化の計画を立てる
有給休暇は労働者の正当な権利であり、退職前にできる限り消化するための計画を立てることが大切です。
有給休暇の日数は年度初めに付与されるもので、年度途中で増えることはありません。そのため、転職活動を開始する時点で有休の残日数を確認し、スケジュールに組み込んでおくと良いでしょう。
有給休暇の残日数に応じて、退職希望日までの引き継ぎ期間や資料準備の期間を調整する必要があります。
一部の企業では、有休の買い取りを提案される場合もありますが、有給休暇は労働者が休息を取ることを目的としているため、買い取りは基本的に認められていません。
特に年度末の退職は企業の繁忙期と重なることが多いため、他の従業員のスケジュールに影響を与えないように、有休の計画を慎重に立てることが重要です。
引き継ぎのために業務を整理しておく
退職が決まったとしても、現在の業務をおろそかにすることは避けるべきです。
スムーズに退職するためには、引き継ぎのための業務を整理し、計画的に進めることが求められます。
まずは、自分が担当している業務をリスト化し、優先順位を決めます。
その上で、上司と相談しながら引き継ぎを進めていきます。
また、後任者が業務をスムーズに引き継ぐため、必要な資料を作成することも重要です。
たとえば、以下のような情報を整理しておくと引き継ぎが円滑に進みます。
- 現在の業務状況
- 取引先のキーパーソンや担当者の特徴
- クライアントの要望や性格、今後の展望
これらの作業を早めに進め、退職の1週間前までには引き継ぎを完了させることを目指します。
残りの期間は、何か問題が発生した際に対応できる余裕を持っておくと良いでしょう。
会社に返却するものなどを整理しておく
退職時には、入社時に会社から貸与された物品を確実に返却する必要があります。
代表的な例として、以下のようなものがあります。
- 健康保険証
- 社員証
- 社章
- 業種によっては制服
これらを返却しないとトラブルの原因となり、余計な手間が発生する可能性があります。
加えて、会社から受け取るべき書類も確認しておきましょう。
退職後の手続きに必要な主な書類は以下の通りです。
- 離職票
- 雇用保険被保険者証
これらの書類がなければ退職の証明ができず、失業手当や再就職手続きに支障をきたす可能性があります。
書類の受け取り方法は企業によって異なり、手渡しの場合もあれば後日郵送される場合もあります。
返却物と受け取る書類については、人事担当者に事前に確認し、漏れがないようにしましょう。
お世話になった人に挨拶していく
退職日までに、これまでお世話になった方々への挨拶を欠かさず行いましょう。
社内でお世話になった同僚や上司だけでなく、取引先の関係者にもきちんと挨拶をすることが重要です。
理想は、直接会って感謝の気持ちを伝えるのが望ましいですが、時間が限られている場合には電話やメールを活用して必ず挨拶を行いましょう。
この一手間をかけることで、退職後も良好な関係を維持できる可能性が高まります。
転職先で取引先と再び関わることがあった場合、事前の挨拶が役立つことも少なくありません。
挨拶を行う際は、後任者と一緒に訪問し、引き継ぎをスムーズに進めるための取り次ぎを行うことも大切です。
後任者が取引先と顔を合わせることで、今後のやり取りがより円滑になります。
また、挨拶する相手が重要な役職についている場合や、より上のポジションにいる場合は、必要に応じて上司に同行をお願いすると良いでしょう。
挨拶のスケジュールはしっかりと管理し、忙しい時期であっても余裕を持って進められるよう計画を立てることが大切です。こうした丁寧な対応が、退職後のキャリアや人間関係においてプラスに働くでしょう。
【年度末退職】円満退職しやすいタイミング
円満退職を実現するためには、タイミングの選定が重要です。以下の2つのタイミングが特に適しているといえます。
- 仕事のキリが良いタイミング
- 退職スケジュールに余裕があるタイミング
それぞれのタイミングについて解説していきます。
仕事のキリが良いタイミング
仕事のキリが良いタイミングは、円満退職を実現するための最適なタイミングです。
たとえば、現在進行中のプロジェクトが完了する時期や大きな業務の一区切りがついた時期が該当します。
このようなタイミングで退職の意思を伝えることで、プロジェクト完了と同時に退職することが可能となり、会社側にも負担をかけにくくなるでしょう。
会社側にとっても、プロジェクトが完了するまで残ってもらえる安心感や、その後の人員配置を計画しやすいというメリットがあります。
さらに、年度末にはプロジェクトの締めくくりが設定されていることが多く、キリの良いタイミングと年度末が重なることも珍しくありません。
特に管理部門の場合、年度末や決算期などの区切りの時期が良いタイミングとなるでしょう。
退職スケジュールに余裕があるタイミング
年度末は多くの企業で繁忙期と重なりやすいため、退職スケジュールに余裕を持つことは難しい場合もあります。
しかし、それでも円満退職を目指すには、スケジュール管理を徹底して余裕を確保する努力が必要です。
そのためには、以下のような準備を行うことが重要です。
- 業務の棚卸しを早めに行う
- 引き継ぎ計画を綿密に立て、着実に進める
- 抜け漏れのないよう進捗状況を確認する
スケジュールに余裕を持たせることで、引き継ぎ作業がスムーズに進み、結果としてトラブルの発生を防ぎやすくなります。
また、早期に退職の意思を伝えることで、上司や人事担当者が組織変更や人員配置を調整するための時間を確保でき、全体の調和を保つことが可能です。
相手側にも余裕を与えるスケジュールを心がけることで、よりスムーズで円満な退職を実現できるでしょう。
【年度末退職】退職してから転職活動、転職が決まってから退職?
転職活動を始めるタイミングは人それぞれですが、大きく分けると以下の2つのケースがあります。
- 退職してから転職活動を行うケース
- 転職が決まってから退職を行うケース
それぞれのケースについて、どのようなメリット・デメリットがあるかを解説していきます。
退職してから転職活動を行うケース
退職後に転職活動を始める場合、以下のようなメリットがあります。
- スケジュールの自由度が高い:平日の日中でも面接に対応できるため、企業のスケジュールに柔軟に合わせることができます。
- 転職活動に集中できる:現職の仕事に縛られることなく、転職活動に専念できるため、準備や面接対策に十分な時間を確保できます。
- スムーズな入社が可能:退職交渉を内定後に行う必要がないため、入社までの流れがスムーズです。
しかし、退職後の転職活動には以下のデメリットもあります。
- 収入が途絶える:退職後は収入がなくなるため、生活費や転職活動費の負担が増え、金銭的な不安を抱える可能性があります。
- 焦りからのミスマッチ:早く次の職場を決めたいという焦りから、自分に合わない企業を選んでしまうリスクがあります。
- ブランク期間の懸念:転職活動が長引いた場合、ブランク期間が生じ、企業からの評価が下がる可能性があります。
転職が決まってから退職を行うケース
在職中に転職活動を行い、内定を得てから退職する場合のメリットは以下のとおりです。
- 収入の安定:在職中のため、毎月安定した収入を得ながら精神的な余裕を持って転職活動に取り組むことができます。
- ブランク期間がない:転職先への入社がスムーズに進み、経歴に空白期間が生じる心配がありません。
- 条件の再検討が可能:内定後に現職と比較して、キャリアプランを再検討する時間を持つことができます。
一方で、次のようなデメリットがあります。
- スケジュール調整の困難:現職の業務と転職活動を並行する必要があるため、面接などの日程調整が難しくなる場合があります。
- 退職・入社時期の調整:現職の退職時期と転職先の入社時期の調整に手間がかかることがあります。
- 仕事と転職活動を同時に進めるため、時間的にも精神的にも負担が大きくなりがちです。
【年度末退職】年度末の退職に迷った場合に確認すべきポイント
年度末の退職を検討する際、迷いが生じた場合には次の3つの観点を確認してみることをおすすめします。
- 転職自体を迷った場合
- 求人数が多い時期か否かの確認
- 転職エージェントの活用
それぞれのポイントについて解説していきます。
転職自体を迷った場合
転職に対して迷いを感じているのであれば、まずは「なぜ転職したいのか」という理由を冷静に見つめ直しましょう。
「現在の職場で△△が不満だから」「理想的なキャリアを築ける環境を探したいから」といった動機は人それぞれです。
重要なのは、自分自身の考えを整理することです。
たとえば、転職のメリットやデメリットを紙に書き出してみることで、頭の中をクリアにできます。このプロセスが、次の一歩を進むための助けとなるでしょう。
また、退職の意思を伝えると撤回は難しいため、慎重に考える時間を設けることが大切です。
自分が納得できる方向へ進んでいるかを確認し、後悔のない判断を目指してください。
求人数が多い時期か否かの確認
求人市場は10月や3月に活発になる傾向がありますが、自分が希望する業界や職種においても求人数が増えているかを確認する必要があります。ポジションによっては求人数の増加時期が異なることもあるため、情報を精査しておきましょう。
転職活動中に興味を持った企業やポジションがあれば、積極的に応募することも視野に入れるべきです。
特に年度末の退職を目指す方にとって、求人数が多いかどうかは転職成功の鍵を握る重要な要素です。求人動向をしっかりとチェックし、タイミングを見極めることが重要です。
転職エージェントを活用する
転職活動において心強い味方となるのが転職エージェントです。
エージェントは面接日程の調整や面接対策、職務経歴書の添削、キャリア相談など幅広くサポートしてくれます。
転職に少しでも不安や疑問を感じている場合は、エージェントに相談することを検討してみてください。
プロフェッショナルの知識と経験に基づくアドバイスは、悩みを解消し、より良い判断につながる可能性があります。一人で悩みを抱え込むよりも、専門家に相談することでスムーズに進められるでしょう。
転職エージェントは基本的に無料で利用できるため、積極的に活用する価値があります。
不安を軽減し、成功に向けて最善の選択をするための手段として、ぜひ検討してください。
まとめ
年度末の退職は、非常に賢い選択といえるでしょう。
ただし、この時期は多くの企業にとって繁忙期にあたるため、余裕を持ったスケジュールを立て、計画的に進めることが重要です。
転職活動から退職までの期間として、最低でも3ヶ月以上を見積もることをおすすめします。
予期せぬ問題が生じる可能性も考慮し、余裕を持たせることが大切です。この準備期間が、不必要なトラブルを回避し、理想のキャリアを築く土台となります。
自分がやるべきことをリストアップし、一つひとつ確認しながら進めていくことで、退職後のスムーズなキャリアチェンジが実現するでしょう。ぜひ計画的に動き出し、新しい道へ踏み出してください。
SHARE この記事を友達におしえる!