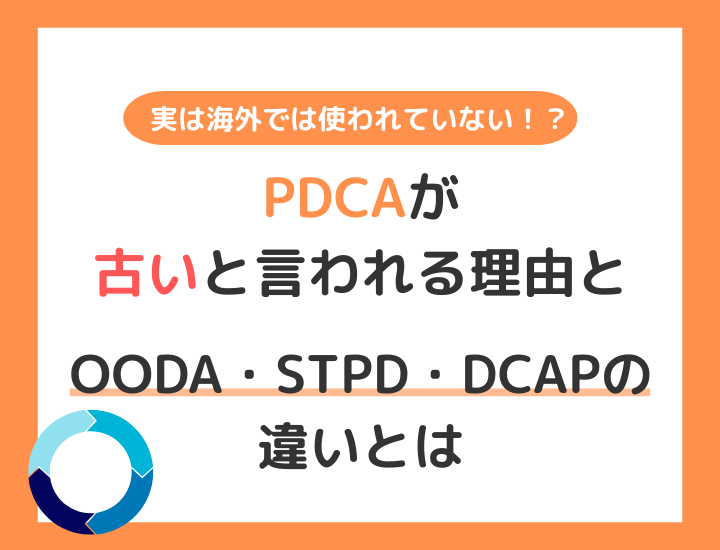
PDCAが「古い」7つの理由|代替となるOODA・STPD・DCAP・PDRとは
はじめに
チームの成果を最大化するうえで、多くの企業が導入しているのがPDCAサイクルです。
しかし、現場では「何度回しても数値が伸びない」「計画倒れで終わってしまう」といった悩みを抱える管理職も少なくありません。
ビジネス環境の変化が激しい今、従来のフレームワークが機能しにくくなっていることも一因です。
この記事では、PDCAを取り巻く課題に触れつつ、OODAやSTPD、DCAP、PDRといった新しいマネジメント手法の特徴や違いをわかりやすく整理します。
PDCAとは
PDCAは、業務や組織活動を継続的に改善していくための管理サイクルとして、多くの企業で導入されてきました。
以下では、PDCAの基本構成と誕生の背景について整理していきます。
PDCAを構成する4つの要素
PDCAは以下の4段階で構成されています。
それぞれのステップは、次の改善に向けた基盤を築くために必要不可欠です。
PDCAサイクルの4ステップと主な役割
| ステップ | 意味 | 主な内容 |
|---|---|---|
| Plan | 計画 | 目標設定、施策立案、スケジューリングなど |
| Do | 実行 | 計画に基づく業務の推進 |
| Check | 評価 | 実施結果の確認、進捗や課題の洗い出し |
| Act | 改善 | 次の計画への反映、改善点の明確化 |
上記のプロセスを繰り返すことで、業務が段階的に進化していく仕組みです。
ただし、実行に移す前段階であるPlanに時間がかかりすぎると、変化の早い現代では対応が遅れることもあり、改善のサイクルが停滞する要因になることもあります。
PDCA発祥の歴史
PDCAのルーツは、アメリカの統計学者エドワーズ・デミング博士が提唱した「品質管理の科学的アプローチ」にあります。
第二次世界大戦後、日本に導入されてからは製造業を中心に一気に普及し、特に日本企業の「改善文化」に深く根づくこととなりました。
〈PDCAが広まった主な背景〉
- デミング博士による啓発活動
- トヨタ生産方式などへの実装
- 日本的経営における「継続的改善」への適合性
当初は品質管理が主目的でしたが、次第に人事、営業、サービス業などへも広く展開されていきました。
今ではマネジメントの基本形ともいえる存在ですが、近年ではスピード重視の現場との相性に課題を感じる声も多く、新しい代替フレームワークへの関心が高まっています。
PDCAが古いといわれている理由7選
PDCAが「古い」とされる背景には、変化のスピードや働き方の多様化など、現代のビジネス環境が大きく関係しています。
ここでは、PDCAが古いといわれている主な理由を7つに整理して紹介します。
- PDCA自体が「目的」になってしまうから
- 変化の速さについていけないから
- 回すのに時間がかかるから
- 新たな発想の障害になるから
- ルーティンワークよりプロジェクトが増えているから
- AI技術が急速に発展しているから
- 日本でしか使われていないから
PDCA自体が「目的」になってしまうから
PDCAはあくまで手段であるはずが、形骸化することで「PDCAを回すこと」が目的になってしまうケースがあります。
本来は成果を生み出すための手法であるにもかかわらず、チェックシートを埋めることや会議のための会議に終始し、本質を見失う現場も少なくありません。
結果的に現場での行動が停滞し、数値改善に結びつかない事態を招いてしまうのです。
- 「計画倒れ」のままDoに進めない
- Checkフェーズで終わり、改善が放置される
- 行動よりも資料作成に注力されがち
変化の速さについていけないから
現在の市場はテクノロジーと消費者行動の変化が極めて速く、半年先の計画すら通用しないこともあります。
PDCAのように「まず計画ありき」のスタイルでは、機会損失やスピード感の低下を引き起こしかねません。
環境が動的である以上、静的なフレームワークだけでは追いつけず、より即応性の高い手法への移行が求められています。
回すのに時間がかかるから
PDCAの計画フェーズにおいて詳細な目標設定やスケジュール策定に多くの時間を要するため、実行に着手するまでにスピードが落ちる傾向があります。
特にスタートアップやアジャイルな開発体制が求められる現場では、迅速に仮説検証を繰り返すスタイルが好まれ、従来型のPDCAは重たく感じられることが多くなっています。
新たな発想の障害になるから
PDCAは再現性の高い業務に適している一方で、「過去の延長」で計画を立てる傾向が強いため、新規事業やゼロベース思考には不向きです。
革新的なアイデアを求めるプロジェクトにおいては、Checkフェーズで前例と異なる内容が否定されることもあり、挑戦の芽を摘んでしまうリスクがあります。
ルーティーンよりプロジェクトが増えているから
近年は、定型業務ではなく非定型・プロジェクト型の業務比率が高まっており、「回す」ことが前提のPDCAはプロジェクトの瞬発性と相性が良くありません。
プロジェクトでは「まずやってみる」柔軟性や仮説思考が重視され、計画通りに運ぶことが目的ではなく、柔軟にピボットしながらゴールに向かうことが求められます。
AI技術が急速に発展しているから
AIやデータ分析の進化により、現場でリアルタイムに意思決定ができる環境が整ってきました。
事前の計画よりも「その場で判断して動く」ことの価値が増しており、PDCAのような段階的なフローよりも、即応性のあるマネジメント手法の方が現代には合っているという見方が広がっています。
日本でしか使われていないから
PDCAは日本の製造業では根付いているものの、世界的にはあまり浸透していないのが実情です。
特に欧米企業やスタートアップでは、OODAやアジャイルの考え方の方が主流となっています。
グローバル展開を視野に入れるならば、世界標準のマネジメント思考に触れておく必要があるでしょう。
PDCAにはメリットもある
PDCAに対して「古い」「使いにくい」といった意見もありますが、適切に活用すれば得られる効果は多くあります。
ここでは、代表的な4つのメリットについて見ていきましょう。
- 課題を正確に把握できる
- 目標が具体化する
- 今やるべきことに注視できる
- 目標達成力を構築できる
課題を正確に把握できる
PDCAのCheckフェーズでは、目標に対する進捗や結果を数値や事実に基づいて評価します。
このプロセスを通じて、表面化していなかった問題点やボトルネックが可視化され、感覚ではなくデータに基づいた判断が可能になります。
特にチーム運営では、属人的な視点に頼らず、共通認識として課題を共有できる点が大きな強みです。
PDCAで把握しやすい課題の例
- 業務遅延の原因
- 目標未達の傾向
- 計画と実績のギャップ
目標が具体化する
Plan(計画)フェーズで明確な目標を定義するため、曖昧な努力ではなく「成果を出すための条件」がチーム全体に共有されます。
目標設定の要素とPDCAの影響
| 項目 | 意味 | PDCAがもたらす影響 |
|---|---|---|
| 数値目標 | 売上・成約数など定量化された指標 | 行動の精度と方向性が明確化 |
| 実施スケジュール | いつ・誰が・何をするかの計画 | 時間的な見通しが共有されやすい |
| 優先順位 | 取り組むべき内容の整理 | 効率的なアクションが可能になる |
メンバーの認識のばらつきを防ぎ、行動に一貫性をもたらす基盤として機能します。
今やるべきことに注視できる
PDCAは「いま何に集中すべきか」を可視化するための思考補助にもなります。
特に、複数業務が交錯する環境では、業務の優先順位が明確になることが大きなメリットです。
- フェーズごとのタスク管理が容易
- 「今ここ」に集中する文化が育つ
- 無駄な手戻りが減る
日々の意思決定に迷いが少なくなり、チーム全体の行動に統一感が生まれやすくなります。
目標達成力を構築できる
PDCAは一度回して終わりではなく、繰り返し実践することで「改善の型」を蓄積していけます。
失敗を許容しつつも、次の挑戦に確実に学びを反映できる構造が魅力です。
PDCAを継続することの効果
| 継続的なPDCAの効果 | 説明 |
|---|---|
| 組織の思考力が向上 | 振り返りと改善で分析力が身につく |
| チームの成功体験が増える | 成果の出し方を共通言語として持てる |
| 再現性ある行動が取れる | 目標達成に向けたプロセスが習慣化する |
経験に基づいた強いチームをつくるには、こうした反復的な思考の訓練が重要です。
PDCAが向いている企業の特徴
PDCAに課題を感じる声がある一方で、今なお有効に機能している組織も存在します。
ここでは、PDCA運用に適している企業の代表的な特徴を3つ紹介します。
安定的な業務プロセスが多い
日々の業務がルーティン化されており、変化よりも再現性が重視される組織には、PDCAがうまく適合します。
手順の明確化や継続的な品質改善が求められる現場では、各フェーズが持つチェック機能と改善サイクルが効果を発揮します。
PDCAが向いている業務例
- 生産ラインや物流業務
- 品質保証・管理部門
- 店舗運営などマニュアル化された現場
継続的な改善が前提となる環境では、PDCAが業務の安定化に寄与しやすくなります。
定量評価を重視するマネジメント体制がある
PDCAの「Check」フェーズでは、結果を客観的な数値で確認し、次の改善アクションに結びつけていきます。
そのため、日常的にKPIや業績指標を用いて管理している企業ほど、PDCAのロジックと親和性が高くなります。
span style=”font-weight: bold”>定量的マネジメントとPDCAの相性
| 特徴 | PDCAとの相性理由 |
|---|---|
| KPIで評価している | Check→Actの精度が高まる |
| データ主導の意思決定を行う | 結果分析と改善策の妥当性が検証可能 |
| 成果を定期的に振り返る文化 | PDCAのサイクルが定着しやすい |
階層型の組織構造を採用している
PDCAはトップダウンで計画を立案し、下層に展開するという運用形式にマッチしやすいフレームです。
階層的な管理体制が整っている企業であれば、役割ごとにPDCAを分割・担当させることで、段階的かつ計画的に改善を進めることが可能になります。
階層型組織とPDCA運用の相性
- 各階層で役割と責任が明確に分担されている
- 上層での計画と現場での実行がセットで機能する
- 報告とフィードバックの流れが仕組み化されている
組織の中で情報が段階的に伝達・実行される構造を持つ企業にとって、PDCAは整合性の高いマネジメントツールとなります。
PDCAを効果的に回すポイントも把握すべき
PDCAを導入しても成果につながらないと感じる場合、サイクルの「質」に課題があるケースが多く見られます。
ここでは、PDCAを実務に活かすための5つの具体的なポイントを解説します。
計画は「目的」と「手段」を分けて立てる
Planフェーズでは、目的と手段が混同されがちですが、両者を明確に区別しておくことで、行動のブレを防ぐことができます。
目的は「何のために行うのか」、手段は「どうやって実現するか」です。
この違いを整理しておくことで、仮に手段がうまく機能しなくても、目的に立ち返って再設計がしやすくなります。
目的と手段の設計例
目的3か月以内にCVRを1.5倍にする手段①LP構成の改善を実施する手段②広告訴求内容を再検討する
| 項目 | 設計の内容 |
|---|
Doフェーズでは完遂よりも「試す」意識を持つ
実行段階では、最初から完璧な施策を狙うのではなく「仮説を試す」くらいのスピード感を持つことが大切です。
PDCAの初期段階で完璧主義に陥ると行動が遅れ、Checkに至るまでの学びが得られません。
むしろ早期に実施して反応を確認し、次の改善へ進める意識が、サイクルの回転数と精度を上げるポイントになります。
Checkでは数値と背景の両面を見る
評価フェーズでは結果の数字だけでなく、なぜそうなったかという要因まで分析する姿勢が欠かせません。
数字が目標を上回った場合でも、運によるものか、戦略が機能した結果かを検証しないままでは次に活かせません。
- KPIの達成状況(数値)
- 達成・未達の理由(背景)
- 実行における障壁や工夫の有無
数値に加え、メンバーの声や現場のリアルも合わせて評価に反映しましょう。
Actフェーズでは次の「Plan」を含めて設計する
改善は「変えること」ではなく「次につなげる設計を施すこと」です。
改善点の抽出だけで終わらせず、新たなPlanにどう活かすかまで落とし込むことで、PDCAの循環がより滑らかになりますたとえば、改善内容を次期のKPIに直接組。
み込むことで、サイクルが段階的に成長していく形になります。
チーム全員がPDCAを回せる体制にする
PDCAはリーダー1人で完結するものではなく、チーム全体で共有・実行されてこそ真価を発揮します。
フェーズごとに役割分担を明確にしたり、定例MTGで進捗の確認・改善案のすり合わせを行ったりすることで、全体のサイクルが滞りなく循環します。
- チェックシートで進捗を可視化
- フェーズごとの責任者を設定
- 振り返りを共有の場として定着させる
属人化を防ぎ、サイクルを組織の習慣として根づかせることが重要です。
現代に適した「OODAフレームワーク」
変化の激しいビジネス環境では、迅速な意思決定と行動が求められます。
そこで注目されているのが、アメリカ空軍由来のOODAフレームワークです。
ここでは、OODAの構成要素やPDCAとの違い、実践する際のメリット・デメリットなどを詳しく紹介します。
OODAを構成する要素
OODAは「Observe(観察)」「Orient(状況判断)」「Decide(意思決定)」「Act(行動)」の4ステップから成り立っています。
戦場のような不確実性の高い場面で、素早く状況を把握し、臨機応変に動くために生まれた概念です。
ビジネスに応用すると、以下のような役割に置き換えられます。
OODA各ステップの概要
| ステップ | 意味 | 役割の概要 |
|---|---|---|
| Observe | 観察 | データ・現場の声・環境変化を素早く捉える |
| Orient | 状況判断 | 過去の経験・価値観・目的に照らして状況を分析 |
| Decide | 意思決定 | 現場に合った最適な行動方針を選択する |
| Act | 行動 | 決定内容を即座に実行に移す |
PDCAとOODAの違い
PDCAは「計画ありき」で物事を進める体系ですが、OODAは「状況の変化に応じて即座に動く」点に重きが置かれています。
PDCAは予測と整合性に強みを持ちますが、OODAは即応性と柔軟性が特徴です。
PDCAとOODAの主な違い
| PDCA | PDCA |
|---|---|
|
|
不確実性が高まる現代においては、OODAのような思考法の必要性が高まっています。
OODAのメリット
OODAの最大のメリットは「行動の速さ」です。
観察から行動までを迅速に回せるため、変化に対して瞬時に反応できます。
情報収集と状況判断がセットで進むため、判断に迷う時間が短縮され、競合より一歩先に動けるようになります。
- ボトルネックの早期発見
- 場当たりではない「動的対応」の実現
- 実行重視の文化が根づく
特にスタートアップやアジャイル開発の現場においては、OODAが非常に有効とされています。
OODAのデメリット
OODAには柔軟性という強みがある一方で、長期的な戦略や全体最適の視点が欠けやすいという課題もあります。
個人やチームごとに判断が分かれやすく、統一感のない行動に陥る恐れもあります。
また、経験や分析力が不足した状態では、誤った判断につながるリスクも否めません。
- 方針が統一されない恐れがある
- 慣れていない組織では混乱が生じやすい
- 計画に基づく評価軸が曖昧になりやすい
こうした側面を理解したうえで、目的やチーム構成に応じた適用が必要です。
OODAの具体例
OODAは営業やマーケティング、カスタマーサポートなど、意思決定と実行が連続する職種で導入されています。
たとえば営業現場では、顧客の表情や言動(Observe)からニーズを読み取り(Orient)、最適な提案内容を瞬時に決め(Decide)、その場でプレゼンに移る(Act)といった流れで活用されています。
- 顧客の反応をその場で観察
- 過去の商談結果をもとに状況を判断
- 最適な話法を即座に決定
- タイミングを逃さず提案を実施
状況が秒単位で動く場面では、OODAが力を発揮しやすいといえるでしょう。
OODAの注意点
OODAを導入する際は「判断基準の共有」と「情報の透明性」が重要です。
個人任せにしてしまうと暴走のリスクが高まるため、全員が共通の目的と判断軸を持って動けるよう、定期的なフィードバックの場や意思決定のレビュー体制を設けることが求められます。
- 判断基準をチームで統一しているか
- 行動の背景が言語化・共有されているか
- 評価や改善のサイクルが止まっていないか
スピード感と秩序を両立させるためには、組織全体でのOODA理解と設計が欠かせません。
マネジメント管理に最適な「STPDサイクル」
成果が出ないPDCAの代替案として注目されているのが「STPDサイクル」です。
スピードと柔軟性を両立しやすく、マネジメントの現場でも取り入れやすいのが特徴です。
以下で、STPDの構成やPDCAとの違い、メリット・デメリット、活用の際の注意点などを詳しく解説します。
STPDを構成する要素
STPDとは、「See(観察)」「Think(思考)」「Plan(計画)」「Do(実行)」の4ステップから成るサイクルです。
特に「観察」と「思考」を先に置くことで、現場の状況に即した戦略が立てやすくなります。
STPD各ステップの概要
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| See | 状況や課題を客観的に観察する |
| Think | 原因や仮説を思考で深掘りする |
| Plan | 打ち手や対策を計画に落とし込む |
| Do | 立てた計画を即座に実行に移す |
上流で「観察」と「思考」に時間をかけることで、より解像度の高いアクションが実行できる構造です。
PDCAとSTPDの違い
PDCAが「まず計画」から始まるのに対し、STPDは「まず観察と分析」を重視する点が大きな違いです。
STPDは状況理解と仮説検証を起点とするため、より実態に即した計画が可能となります。
PDCAとSTPDの主な違い
| PDCA | STPD |
|---|---|
|
|
現場での柔軟な判断や対応力が求められる場面では、STPDの方が有効なケースも増えています。
STPDのメリット
STPDは、現場の状況や課題に応じて柔軟にアプローチできる点が最大の強みです。
計画に入る前に「見て・考える」工程を設けることで、より正確な判断が可能となります。
- 現状把握から始めるため、ズレが起こりにくい
- 計画の質が高まり、実行フェーズが効率化する
- 形式より実態重視の思考が促される
課題解決型のマネジメントに特に向いており、変化の大きなプロジェクトや少人数チームでも活用しやすいフレームです。
STPDのデメリット
一方で、STPDには注意点もあります。
初動の「See」と「Think」に時間をかけすぎると、意思決定や実行が遅れるかもしれません。
また、ルーチン業務への適用にはやや不向きな場面もあります。
- 初期段階に時間を割きすぎてしまう可能性
- 実行重視の現場ではテンポが合わないこともある
- 明確な評価軸を設けないと主観的な判断に偏りやすい
導入に際しては、業務内容との相性やチームの習熟度を見極めて活用することが重要です。
STPDの具体例
たとえば顧客対応の現場では、クレームが発生した際に「See」で内容と状況を丁寧に観察し、「Think」で原因を探り、改善案を「Plan」で策定、「Do」で即時実行するといった流れが想定されます。
状況の変化に柔軟に対応できる点が現場運用と非常にマッチします。
- See:顧客からのフィードバックを観察
- Think:不満の根本原因をチームで議論
- Plan:応対フローの見直しを計画
- Do:新フローのテスト運用を開始
短期改善サイクルを回したい業務で特に効果を発揮します。
STPDの注意点
STPDを組織に定着させるには、メンバー全員が「観察」と「思考」に価値を感じられる土壌を育てる必要があります。
また、Doの段階で止まってしまわないように、観察や思考だけで満足しない習慣づくりが重要です。
- 観察・思考の内容を言語化して共有する
- PlanとDoに明確な期限を設ける
- 評価と振り返りの時間を必ず確保する
フレームの効果を最大化するためには、プロセスを習慣化しやすい設計にすることが求められます。
実行を優先する「DCAPサイクル」
近年注目されているのが、「まず動く」ことを重視するDCAPサイクルです。
計画に時間をかけすぎて動き出せないというPDCAの弱点を補う実行起点型のフレームワークとして、スピーディな組織運営を目指す中小企業を中心に導入が進んでいます。
ここではDCAPの構成やPDCAとの違い、活用の際の注意点について紹介します。
DCAPを構成する要素
DCAPは「Do(実行)」「Check(検証)」「Action(改善)」「Plan(計画)」の順に進行するサイクルです。
最初から完璧な計画を立てるのではなく、まず行動してから評価・改善を加え、最後に計画に落とし込むという点が特徴です。
DCAP各ステップの概要
| ステップ | 意味 | 主な役割 |
|---|---|---|
| Do | 実行 | 小さく素早く試すことから始める |
| Check | 検証 | 実行結果を定量・定性で振り返る |
| Action | 改善 | 得られた情報をもとに軌道修正する |
| Plan | 計画 | 次回に向けた施策を体系化して残す |
実践を通じたフィードバックループが前提になっているため、実行力のある組織文化と非常に親和性が高い構成です。
PDCAとDCAPの違い
PDCAが「計画重視」の手法であるのに対し、DCAPは「まず行動すること」に主眼を置いています。
理想を描いてから動くのではなく、現実を知ったうえで次の計画を練るという流れに変化しています。
PDCAとDCAPのの主な違い
| PDCA | DCAP |
|
|
現場主導のフローを求める企業には、PDCAよりも現実的に機能する可能性があります。
DCAPのメリット
DCAPの強みは、行動と学習のスピードが格段に早まる点にあります。
「完璧なプランを待つよりも、まずやってみる」姿勢が定着することで、現場のフットワークが軽くなります。
また、変化が激しい市場でも柔軟な対応がしやすくなるでしょう。
- 仮説と実践を短いサイクルで回せる
- 計画に縛られないため、新たなアイデアが出やすい
- チームに行動重視のカルチャーが根づく
結果として、メンバーの主体性や成長スピードにも良い影響を与えやすくなります。
DCAPのデメリット
DCAPは計画の優先度が低いため、全体戦略の不整合や場当たり的な行動につながるリスクがあります。
組織の規模や成熟度によっては、DCAPの運用がかえって混乱を生むこともあるでしょう。
- 長期視点が欠けると戦略がぶれやすい
- 全員が動けばいいという誤解が生まれやすい
- 行動結果を体系的に蓄積しないと再現性が弱まる
行動の質と振り返りの仕組みをセットで整備しておくことが、導入を成功させるうえで重要です。
DCAPの具体例
たとえば新規事業の立ち上げ時には、計画よりも市場へのアプローチが先行します。
まずは簡単なプロトタイプで試験運用(Do)を行い、ユーザーの反応を見て(Check)、改善策を練り(Action)、そのうえで正式サービスとしての設計(Plan)に落とし込んでいきます。
- Do:仮説ベースでアイデアを即試す
- Check:データや反応から傾向を分析
- Action:改善ポイントを反映させる
- Plan:再現性ある方法を定式化
スピード感が求められるプロジェクトでは、特に有効なアプローチです。
DCAPの注意点
DCAPを成果につなげるには「動いて終わり」ではなく、Check・Actionを通じて学びを定着させるプロセスが欠かせません。
記録や共有の文化を併用しないと、行動が点のまま終わってしまうリスクがあります。
- 実行後の検証を必ずルール化する
- 成果・失敗の記録をチーム全体で共有
- 改善策を次のアクションに具体化する
個人ではなくチーム単位でPDCAよりも高速に回すことを意識すると、DCAPは非常に強力な武器になります。
準備が大切になる「PDRサイクル」
成果につながらないPDCAに悩むリーダー層にとって、近年注目されているのが「PDRサイクル」です。
あらかじめ結果を描くことで、逆算して必要な行動に集中できるこの手法は、成果志向のチームづくりにおいて有力な選択肢となり得ます。
ここではPDRの構成やPDCAとの違い、導入時の留意点などを解説します。
PDRを構成する要素
PDRは「Prepare(準備)」「Do(実行)」「Review(振り返り)」の3ステップで構成されています。
特徴は最初の「Prepare」にあり、ゴールや成果イメージを明確にしてから行動に移るという順序が徹底される点です。
PDR各ステップの概要
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| Prepare | 目的・目標・評価指標を事前に定義する |
| Do | 計画に基づいたアクションを実行する |
| Review | 成果やプロセスを多角的に振り返る |
特に「成功の定義を最初に明文化する」ことが、チーム全体の認識統一と行動の精度を大きく左右します。
PDCAとPDRの違い
PDCAは改善を重ねながら業務をブラッシュアップしていくプロセスであるのに対し、PDRは「最終成果を先に設定する」逆算型のアプローチです。
途中で軌道修正するPDCAに対し、PDRは最初に照準を合わせてから進むため、無駄な動きが減りやすくなります。
| PDCA | PDR |
|---|---|
| 計画ベースで動きながら学ぶ | 繰り返し改善に強みがある |
| ゴールから逆算して戦略を立てる | 目標達成に直結する行動に集中できる |
KPIドリブンで短期間に成果を求める場面では、PDRの有効性が際立ちます。
PDRのメリット
PDRのメリットは、チーム全体が「目的志向」で動けるようになる点です。
成功の定義が明確なため、行動の方向性にブレが生じにくく、判断基準も共有しやすくなります。
また、振り返りフェーズで「準備と結果のズレ」を明確に捉えやすい点も、成長サイクルの促進につながります。
- 成果の再現性が高まる
- チームの思考が目的に集約される
- 計画倒れを防ぎ、実行重視の動きになる
ゴールファーストな設計を重視する組織では、特に効果的なフレームといえるでしょう。
PDRのデメリット
一方で、PDRは「事前準備が不十分なまま走り出す」と失敗のリスクが高くなります。
また、振り返りが甘くなると改善につながらない恐れがあり、Doで得た情報をしっかりと整理して次に活かす仕組みが重要です。
- 準備段階に時間とリソースが必要
- 成果ばかりに目が向き、プロセスが軽視されがち
- 振り返りが曖昧だと成長につながらない
見切り発車や「準備不足のままの実行」を避けるためにも、初期設計を丁寧に行う必要があります。
PDRの具体例
たとえば営業チームであれば、「今月の目標受注件数〇件」という成果をまず定義し、そこから逆算して「アプローチ件数」「提案の質」「クロージングのタイミング」などの実行計画を立てます。
その後、計画に沿って動き、最終的にレビューで成果とプロセスを分析するという流れになります。
- Prepare:受注目標と評価基準の設定
- Do:アプローチ→提案→成約の実行
- Review:目標との乖離・成功要因を振り返り
営業だけでなく、人事評価・プロジェクト設計などでも応用可能です。
PDRの注意点
PDRを活用するには「準備を軽視しない文化」と「振り返りを言語化する力」が求められます。
目標が共有されていなければ、行動の方向性がバラバラになってしまいますし、レビューの質が低いと次の成果にもつながりません。
PDRを成功に導くチェックリスト
- 目標やKGIは言語化されているか
- Doでの進捗が定量的に把握できているか
- Reviewで得られた学びが再利用されているか
形式だけで終わらせず、思考の質を高める設計と習慣化が重要です。
まとめ
PDCAに代わる選択肢として注目されるOODA・STPD・DCAP・PDRは、それぞれ意思決定の速さや思考の深さ、行動重視・成果逆算など異なる強みを持ちます。
どれが正解かではなく、業務内容やチーム体制、組織の成熟度に応じて選び分ける視点が重要です。
ポン
- 計画に縛られすぎず柔軟に動きたいのか
- 目的達成に逆算的に迫りたいのか
現場が求めるアプローチによって、最適解は変わります。
今一度自社の課題と向き合い、形骸化したPDCAから一歩進んだフレームの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
SHARE この記事を友達におしえる!



