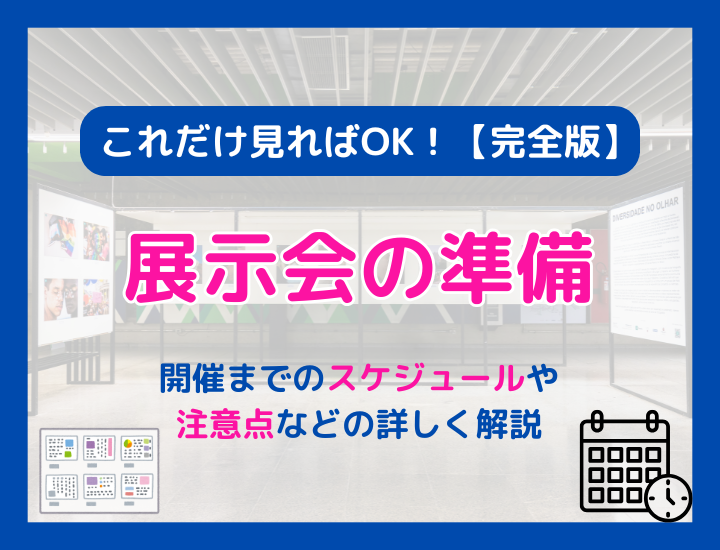
展示会の準備はどうしたらいい?開催までのスケジュールや注意点などの詳しく解説
はじめに
展示会は、顧客との新たな接点を築く絶好のビジネスチャンスです。
来場者の多くが情報収集や比較検討を目的としており、的確なアプローチが成約につながる可能性があります。
本記事では、展示会営業を成功に導くための基本的な考え方や、押さえておきたいポイントを整理しました。
準備段階から現場対応、そして展示会後のフォローアップに至るまで、各フェーズで実践すべき行動を具体的に解説しています。
「展示会の場を活かして売上につなげたい」と考えている営業担当者は、ぜひ参考にしてください。
展示会に必須の準備物
展示会に必須の準備物には、以下のようなものがあります。
展示会で成果を出すためには、事前の準備が営業活動の質を大きく左右します。
見た目や印象だけでなく、接客や情報提供の精度を支えるツールを揃えておくようにしましょう。
名刺やカタログは基本中の基本ですが、ノベルティやアンケート用紙といった細かな準備も来場者との接点を深める要素になります。
準備段階での手間を惜しまず、商談機会を最大限に活かせる状態を整えておくことが、展示会成功のポイントです。
| 準備物 | 内容・目的 |
|---|---|
| 名刺・名刺ケース | 商談時に欠かせない。
複数枚まとめて持参し、清潔感あるケースに収納しておく。 |
| カタログ・パンフレット | 商品やサービスの情報をコンパクトに伝える。
持ち帰りやすさや読みやすさも考慮する。 |
| 展示物 | 実物やモックアップ、パネルなど。
視覚的に訴求できる展示内容で興味を引きつける。 |
| ノベルティ | 来場者に印象を残すための記念品。
ロゴ入りの文具や雑貨など、実用性があると効果的。 |
| アンケート用紙 | 見込み顧客のニーズ把握に活用。
短く簡潔な質問項目で、負担をかけずに情報を収集できる。 |
| ブース装飾 | 企業イメージを反映させた装飾でブランディング強化。
色やレイアウトも統一感を重視する。 |
| 接客マニュアル | スタッフ間の対応を統一し、来場者に一貫した印象を与える。
役割分担や対応方針を明確に記載。 |
展示会の準備はスケジュール管理が大切
展示会を成功させるためには、綿密なスケジュール管理が求められます。
なぜなら、出展までの準備工程は多岐にわたり、どれか一つでも遅れると全体の進行に大きな影響を及ぼすからです。
例えば出展の4~5カ月前には目的の明確化や予算設定、展示会選定など基本方針を定める必要があります。
その後も、ブース設計、資料制作、人員確保、集客計画と段階的な対応が求められ、各フェーズにはそれぞれ締切が設けられているのが一般的です。
各準備の段階について担当者を割り振り、タスク管理を徹底しなければ、納期遅れや品質低下につながりかねません。
展示会は短期間で多くの成果を得る機会であり、準備不足はその貴重なチャンスを逃すリスクとなります。
計画的なスケジュール設計と進捗の可視化が、展示会営業を成功につなげる土台です。
次に、段階別で必要なスケジュール管理を見ていきましょう。
出展の4〜5カ月前に準備すること
出展の4〜5カ月前は、以下の事柄について準備しておきましょう。
- 出展目的の設定
- 参加費用の見積もり
- 出展する展示会の確定
- 出展の手続き
- ブースの場所決め
- 当日までのスケジュール作成
出展目的の設定
予算と目標は、展示会への出展が決まったタイミングで同時に決定することを心がけましょう。
目標には、例えば以下のような項目を設定します。
- 名刺獲得件数
- アプローチ件数
- 商談の件数
これらの目標を決めておくことで、展示会当日の活動や、フォローアップの計画が立てやすくなります。
特に名刺獲得件数は、その後の契約にも関係する重要な要素です。
必ず設定することを心がけましょう。
ただし、名刺獲得件数は、展示会の規模や、当日の会場における導線、周囲の出展状況にも左右されることがあります。
過去のデータや競合他社の動向などを参考にして、現実的な目標を設定することが大切です。
参加費用の見積もり
展示会に参加することが決まったら、まずは事前に参加費用を細かく見積もることから始めましょう。
展示会にかかる参加費用には、以下のようなものがあります。
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 出展費用 | 展示会主催者から請求される出展料や管理料など |
| ブース設備費 | ブースの大きさや形状に応じて必要な、テーブルや椅子、照明などのレンタル料や設置料 |
| ブース装飾費 | ポスター、パンフレットなどの制作費や印刷費 |
| 集客費 | 事前に招待状やメールマガジンなどで告知するための広告費や郵送費 |
| 人件費 | ブースで対応するスタッフの給与や交通費、宿泊費など |
予算は予期せぬトラブルや追加発注などで変動する可能性もあるので、余裕を持ったプランニングが必要です。
また、かけられる予算や時間によって、獲得したい見込み顧客の数や質も変わってきます。
高い費用をかければ、より多くの人にアピールできることでしょう。
場合によっては、大口の顧客が獲得できることもあるかもしれません。
ただし、かけたコストを回収できないなどのリスクがあるため、お金をかければかけるほどよいかというとそうとも言いきれません。
逆に低い費用ですませれば、コストパフォーマンスは高まりますが、自社商品が競合他社に埋もれてしまい、結果的に契約数をそこまであげられないことも考えられます。
達成したい目標を考えながら、逆算して予算を設定することが、展示会営業を成功させるポイントです。
出展する展示会の確定
展示会準備では、出展するイベントの選定も最重要です。
展示会の性質や来場者層によって得られる成果が大きく異なります。
例えばBtoB向けの商品を扱う場合、業界特化型の展示会を選ぶことで、確度の高いリードを獲得できるようになるでしょう。
過去の実績や来場者データ、開催地域も判断材料に含めて精査することが重要です。
自社の営業戦略と照らし合わせ、出展価値が高い展示会に絞り込むことで、精度の高い展示会を実施できます。
出展の手続き
出展の意思を固めたら、すぐに必要な手続きを開始しましょう。
なぜなら申込締切やブースの希望調整が早期に締め切られる場合が多いためです。
手続きは、主催者への申請書類提出や出展料の支払い、出展規約の確認などが含まれます。
期限を逃すと希望の展示スペースを確保できない可能性があるため、社内で責任者を決めて進行を管理しましょう。
スムーズな申請手続きが、準備全体を順調に進める基盤になります。
ブースの場所決め
展示会で集客効果を最大化するため、4〜5カ月前にはブースの場所を確認しておくようにしましょう。
来場者の動線上にブースを配置できれば、足を止めてもらいやすくなり、名刺交換や商談につながりやすくなります。
入口付近やセミナー会場の近くは人通りが多く、高い集客効果が見込めます。
一方で、壁際や奥まった場所では視認性が低くなるリスクがあるでしょう。
出展場所は早い者勝ちで埋まることも多いので、申込時点で戦略的に希望を出す姿勢が求められます。
当日までのスケジュール作成
展示会の準備では、全体のスケジュールを明確に管理することが大切です。
準備項目が多岐にわたるため、疎かにすると作業の漏れや遅れが発生しやすくなります。
印刷物の発注やブース施工の依頼には納期があり、逆算して動かなければ間に合いません。
スケジュールには各担当者の役割や締切日を明記し、定期的に進捗を確認する体制を整えましょう。
計画的な進行管理をすれば、展示会本番のクオリティを高めていくことができます。
出展の3カ月前に準備すること
出展の3カ月前は、以下の事柄について準備しておきましょう。
- コンセプトの決定
- 展示物などの作成
- ブースの運営
- ブースレイアウト・デザインの決定
- ノベルティの選定
- デモンストレーションの計画
- 施工会社の選定
コンセプトの決定
3カ月前の展示会の準備においては、出展の目的とコンセプトを明確にすることが最優先です。
訴求したいターゲットや、自社の強みをどう伝えるかを整理することで、ブースの設計や資料作成にも一貫性が生まれます。
「新商品の認知拡大」や「既存製品の導入促進」など、目的を絞ることでメッセージに軸を生み出すことが可能です。
そして社内で関係部署と連携し、マーケティング戦略と整合性を取りましょう。
コンセプトが曖昧なまま進めると、訴求内容がぼやけ、来場者に印象を残せません。
訴求力を最大化するためにも、出展の3カ月前にはある程度の方向性を固めることが大切です。
展示物などの作成
展示物などを事前に作成することも重要です。
事前に作成するべき印刷物には、以下のようなものがあります。
| 用意するもの | 注意事項 |
|---|---|
| 展示物 | デザインを自社のイメージカラーと合わせるなどして統一感を出す
キャッチコピーも工夫して目を引くようにする カタログやチラシなどの資料 見込み客に自社の情報を伝える 持ち帰りやすいサイズにする |
| ノベルティ | 予算に余裕があれば作成する |
| アンケート | 見込み客のニーズや反応を把握するために必要
来場者の負担を最小限にとどめるためにも、質問項目は必要最低限に絞っておく |
| マニュアル | 社内用の資料
展示会営業で何をするかを明確化する 目的や目標・役割分担・接客方法・フォローアップ方法などを記載しておく |
印刷物は、作り慣れていない場合や、新規で作成する場合は、思ったよりも時間がかかるケースも多いものです。
展示会への出展が決まった時点から、計画的に作成することを心がけましょう。
ブースの運営
展示会の現場でスムーズに動けるように、事前にブース運営の仕組みを構築しておきましょう。
準備不足のまま本番を迎えると、来場者対応に混乱が生じ、チャンスロスにつながります。
スタッフの役割分担、来場者の動線、接客マニュアル、名刺交換やアンケートの流れなどの整理が、運営の基本的な流れです。
ブース運営の基本設計を整えておけば、現場での対応力が高まり、顧客満足度の向上にも直結していくでしょう。
全体の動きを準備フェーズでしっかりと可視化し、円滑な運営を目指す姿勢が大切です。
ブースレイアウト・デザインの決定
ブースのレイアウトとデザインは、集客と良い印象を残すために欠かせない準備です。
展示会が視覚的な訴求力が弱ければ、他社に埋もれてしまうこともあるでしょう。
例えば高さを活かした立体的な構成や、照明を効果的に使った演出によって注目度が高まります。
また動線設計により、来場者の滞在時間を伸ばすことも可能です。
企業ロゴやメッセージを強調したデザインは、ブランドイメージの定着にもつながります。
展示会は、レイアウトとビジュアルに戦略性を持たせることで、来場者の印象に残りやすいものとなるでしょう。
ノベルティの選定
印象に残るノベルティを用意することで、来場者との接点が増えて、記憶に残りやすくなります。
手に取った瞬間に嬉しさや実用性を感じるアイテムであれば、企業への好感度も大きく上がるでしょう。
具体的に言えば、文房具やエコバッグ、スマホ関連グッズなどは、日常的に使用されやすく、高い宣伝効果があります。
ノベルティに関しては、ターゲット層や展示会のテーマに合わせたアイテム選定が重要です。
限られた予算の中でも効果的なノベルティを選ぶことで、来場者との長期的な関係づくりが構築できるでしょう。
デモンストレーションの計画
商品やサービスの魅力を伝えるには、デモンストレーションを計画的に組み立てることも大切です。
デモンストレーションのように動きや変化を伴う実演は、パンフレットでは伝えきれない利点を明確に示せます。
製品の操作性や導入後の業務効率など、実体験を通じたアプローチは信頼性の向上にも寄与します。
演出の時間配分やトーク内容も細かく設定しておくことで、当日の進行をスムーズに進められるでしょう。
デモンストレーションは相手の興味を引くだけでなく、商談が進展するきっかけとしても効果的です。
施工会社の選定
ブース設営を外部に依頼する場合は、信頼できる施工会社を早期に選定することが重要です。
施工内容やスケジュールの調整が密に発生するため、相互理解とできるだけ迅速な対応が求められます。
施工業者を選ぶ際は、実績や得意分野、対応力などをチェックし、自社のコンセプトと相性の良い業者を選びましょう。
過去の施工事例を確認することで、希望するレベルが実現可能かどうか判断しやすくなります。
準備期間に余裕を持たせ、安心して任せられるパートナーを見つけることができれば、展示会の成功につながるでしょう。
出展の2カ月前に準備すること
出展の2カ月前は、以下の事柄について準備しておきましょう。
- 出展内容の確認・計画調整
- 見込み客に案内状を送る
- 人員の確保
- スタッフのシフト作成
出展内容の確認・計画調整
展示会の2カ月前には、出展内容の再確認と全体計画の調整をしましょう。
2カ月前にやっておかなければ、準備の遅れや方向性にズレが生じ、本番のパフォーマンスが落ちるおそれがあります。
展示製品やサービスの選定に変更が生じていないか、ブースレイアウトや演出の整合性が取れているかを再点検しなければなりません。
また来場者層に合わせて、訴求内容を微調整することも重要です。
さらに他部門との連携状況や業務の進捗もここで見直す必要があります。
出展計画を細部まで見直すことで、リスクを未然に防ぎ、当日のクオリティを維持しながら当日を迎えられるでしょう。
見込み客に案内状を送る
展示会の日程が決まったら、見込み来場者に案内状を送付します。
案内状には、以下のような情報を明記します。
- 展示会の目的や内容
- 自社ブースの場所
- 来場特典
- 自社サイトのQRコードやURL
また、日程が近づいてきたら、メールやSNSで展示会の情報を発信します。
特にSNSでは、写真や動画などを使って展示会の魅力をアピールできます。
効果的に活用することを心がけましょう。
プレスリリースを出すことも有効な手段です。
プレスリリースがメディアに取り上げられると、企業の知名度や信頼度が一気に高まります。
展示会直前も、再度メールや電話で連絡を取るかどうか検討しましょう。
ただし、あまりに頻繁に連絡をすると、見込み顧客からかえって敬遠されてしまう場合もあるため注意しましょう。
人員の確保
展示会を無事成功させるためには、適切な人員配置が必要です。
必要な人数が揃わなければ、来場者対応が滞り、十分な成果につながらないおそれがあります。
規模の大きい展示会であればなおさらで、製品説明に長けた社員や営業経験のあるスタッフ、受付や資料配布に適した人材など、役割ごとに適任者を割り振らなければなりません。
あわせて、サポートスタッフのリストアップや急な欠員への備えもしておくと安心です。
人員計画を早めに確定すれば、展示会についての教育や業務理解の時間も十分に確保できます。
展示会はチームワークで成否が決まるため、人的資源の確保は最優先事項だと言えるでしょう。
スタッフのシフト作成
当日の展示会で混乱が発生しないように、事前にしっかりとシフト表の作成と共有をしておきましょう。
明確なスケジュールがなければ担当業務が曖昧になり、対応の質が落ちてしまう可能性があります。
例えば来場者が集中しやすい時間帯には説明要員を多めに配置し、休憩時間をずらして確保することで、柔軟に対応することが可能です。
また体力的な負担を考慮すると、交代制やバックアップ体制を取り入れることも効果的でしょう。
事前に全員とシフトを共有し、質問や調整にも対応できる状態にしておくことで、現場でもスムーズな運営ができます。
出展の1ヶ月前にすること
出展の1カ月前は、以下の事柄について準備しておきましょう。
- スタッフの配置
- 資料の準備
- 展示物の配送準備
- 集客活動
スタッフの配置
展示会をスムーズに進めるためには、スタッフの配置が重要です。
以下のような役割分担を事前に決めておきましょう。
| 役割 | 内容 |
|---|---|
| 責任者 | 展示会全体を統括し、スタッフの動きや状況を把握する
トラブルが発生した場合は対応する |
| 呼び込み担当 | 展示ブースに来場者を誘導する
興味を持ってもらえるようにアピールする |
| 説明責任担当 | 展示品やサービスについて詳しく説明する
来場者のニーズや質問に答える |
| クロージング担当 | 来場者との商談をまとめる
名刺交換やアフターフォローの約束をする |
これらの役割は、スタッフの得意分野や性格に合わせて決めると効果的です。
ただし、来場者によっては、担当者が何度も変わってしまうことに不信感を持つ場合もあります。
展示会中はスタッフ同士で連携しながら、円滑なコミュニケーションを取ることを心がけましょう。
資料の準備
展示会前の資料準備は、来場者への印象を大きく左右する大事な要素です。
説明時に使用する資料の質が、企業イメージや成約率に直結します。
パンフレットや製品カタログ、会社案内などを最新情報に更新し、分かりやすく整理された内容に仕上げるようにしましょう。
あわせて、説明用パネルやスライド資料も視覚的に魅力あるものに仕上げると、来場者の目に留まりやすくなります。
資料は、印刷会社への発注や校正で多くの時間が発生するため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。
誰が見ても理解できるような完成度の高い資料は、営業活動の武器としても機能します。
展示物の配送準備
展示物の輸送準備は、会場での設営をスムーズに進める上で欠かせない工程です。
発送準備が不十分だと、配送トラブルや不備が当日の展示に大きな影響を及ぼすおそれがあります。
搬入スケジュールに合わせて出荷日を逆算し、梱包リストや管理チェック表を作成しておくと、抜け漏れを防ぐことが可能です。
また什器や備品、展示用サンプルなどは壊れやすい物も多いため、梱包方法にも十分な配慮をしなければなりません。
会場へ直送する場合であれば、受取体制も事前に確認し、あらゆるトラブルを未然に防ぎましょう。
安全かつ確実な輸送準備をしておくことで、当日の展示会も安心して運営ができます。
集客活動
展示会で成果を出すためには、事前の集客活動が極めて重要です。
来場者数はそのまま商談機会の数に直結することも多く、どれだけ集客できるかが成功の分かれ目になると言えるでしょう。
例えば自社の顧客データベースを活用し、招待メールやダイレクトメールを送ることで、関心度の高い見込み顧客に直接アプローチが可能です。
また自社ウェブサイトやSNSで展示内容や見どころを積極的に発信し、専用の予約フォームを設置すれば、事前にアポイントを獲得できます。
事前にきっちりと準備しておけば、当日の対応がスムーズになり、効率的な商談が可能となるでしょう。
さらに同時開催される他イベントとの連携や、パートナー企業とのクロスプロモーションをすることで、来場者数の増加も期待できます。
社内での役割分担やスケジュールの明確化も事前に行うと、展示会全体の運営が円滑になり、結果的により多くの成果を上げられるようになるでしょう。
展示会当日までに確認しておくこと
展示会当日までに、必ず以下の事柄について確認しておきましょう。
- 必要な備品の準備
- 展示会当日のリハーサル
- 動線の確認
- SNSの発信
必要な備品の準備
展示会当日をスムーズに迎えられるように、使用する備品を事前に全て準備しておきましょう。
しっかりと準備しておくことで、滞りのない運営ができるようになり、スムーズな対応が可能です。
延長コードやテープ、文房具類、名刺ホルダー、予備の販促物などは、見落としがちな必需品でしょう。
またブース設営に必要な工具類や清掃用品も確認しておくと良いでしょう。
チェックリストを作成し、チームで確認作業を行うことで抜け漏れを防げます。
万全な備品準備は、当日のトラブルを未然に防ぎ、商談に集中できる環境が整います。
展示会当日のリハーサル
展示会本番での対応力を高め、事前にしっかりとリハーサルをしておきましょう。
動きや会話の流れをあらかじめ確認しておくことで、実践時のパフォーマンスが安定します。
具体的に言えば、スタッフ同士でロールプレイを行い、来場者の対応手順や製品説明の流れをシミュレーションしておくと、本番でも自然な応対が可能です。
さらに想定される質問やアクシデントへの対処法を共有しておけば、焦らず冷静に対応できるようになるでしょう。
リハーサルを実施することで、社員・スタッフ一人ひとりの不安も解消され、チーム全体の士気と連携も向上します。
動線の確認
展示会当日の来場者対応を円滑に進めるには、会場内の動線を事前に確認しておく必要があります。
なぜならスムーズな誘導や混雑回避ができないと、ブースでの滞在時間が短くなり、商談の機会を逃してしまう可能性があるからです。
入場口からブースまでの経路、通路の幅、パンフレットやサンプルの配置場所などを事前に把握し、最適な導線設計を検討しましょう。
また説明担当者と受付担当の立ち位置や動きも決めておけば、場面ごとの役割分担が明確になります。
事前に動線を確認しておくことで、ブース運営の効率と接客品質を高められます。
SNSの発信
次回の出展における来場者数を増やすためにも、SNSを使って当日の様子をリアルタイムで発信することは非常に重要です。
展示会の雰囲気や内容を伝えられるほか、SNS上で見込み顧客とのコミュニケーションを促進することができます。
なお、SNSで発信する際には、以下のポイントに注意しましょう。
- 来場者の許可を得てから写真や動画を撮影する
- 個人情報や企業情報などをふくまないようにする
- ハッシュタグやキャッチコピーなどを工夫して目立たせる
展示会終了後の流れ
展示会終了後は、次のような流れがあります。
美化清掃に努める
- 配布物の在庫管理
- 情報整理・社内報告
展示会終了後は、会場運営側や次に使用する企業との信頼関係を保つために、ブース内外の美化清掃を徹底しましょう。
ゴミの分別や掲示物の撤去、備品の回収などを丁寧に行えば、現場の印象を良くするだけでなく、主催者からの評価にもつながります。
また会場のルールに従って退出時の確認作業を行うことも大切です。
清掃を怠ると、次回の出展時に不利益が生じる可能性もあるため注意しましょう。
展示会は準備から後片付けまでが一連の業務であり、最後まで丁寧な対応を心がけることが企業姿勢を示す上でも非常に重要です。
配布物の在庫管理
次回の出展準備や営業活動に直結するため、展示会終了後は、配布物の在庫状況を正確に把握しておきましょう。
例えばパンフレットやノベルティがどれだけ残っているかを記録し、効果的に使い切るための方法を社内で共有すると、無駄な発注を防げます。
特に人気があったアイテムを分析すれば、今後のプロモーション戦略にも活用できるようになるでしょう。
在庫の管理は単なる数合わせではなく、マーケティングデータの一部としての価値があります。
資料の整理と残数管理を徹底することで、展示会の成果を次の行動へとつなげていくことが可能です。
情報整理・社内報告
営業活動や製品開発へのフィードバックを迅速に反映させるため、展示会後は、得られた情報を整理し、速やかに社内で報告しましょう。
来場者の属性や商談の内容、競合の展示状況などを記録し、報告書としてチーム全体に共有すれば、関係者間での情報格差を防げます。
また社内報告によって成果を可視化すれば、次回以降の改善点も明確になるでしょう。
展示会の成功は、当日のパフォーマンスだけでなく、終了後の活用によって決まります。
得られた情報を放置せず、迅速かつ正確に活用することが、事業を成長させる鍵となるでしょう。
展示会終了後にやっておくこと
展示会が終了したあとは、いよいよ展示会営業によって獲得できた見込み顧客との商談のフェーズに入ります。
契約につなげやすくするための、以下のポイントについて解説します。
展示会で得た情報の報告・整理
展示会終了後には、現場で得た情報を正確に整理し、関係部署に速やかに報告しましょう。
なぜなら得られた知見を社内で共有することで、営業戦略や製品改善に活かせるからです。
例えば来場者の反応や商談内容、競合他社の展示方法などを記録し、関係者と情報を共有すれば、次回の出展準備に役立ちます。
形式としては報告書や議事録、データ一覧などを用意し、内容を分かりやすく可視化するのが理想的です。
展示会は単なるイベントではなく、ビジネスチャンスを得る場であるため、情報を放置せず活用につなげるようにしましょう。
費用対効果を確認する
展示会の成果を評価するには、投入したコストに対する効果を数値で確認することが欠かせません。
費用対効果を検証することで、今後の予算計画や出展可否の判断材料になります。
出展費用や人件費、準備にかかったコストと、名刺獲得件数や商談数、新規取引数などの成果を比較し、KPIの達成度を確認することが大切です。
事前に目標を設定しておけば、客観的な評価がしやすくなります。
感覚ではなく数値に基づいた分析を行うことで、経営判断の精度も高まっていくでしょう。
展示会の効果を正確に把握することは、次の戦略策定を練るための重要なステップです。
改善点の洗い出し
展示会終了後は、改善点の洗い出しをしっかりと行いましょう。
振り返ることで何に注意したら良いかがわかるようになり、次回の成功につながります。
綿密な反省と分析を行うことで、課題を具体的に把握でき、より高い成果を目指せます。
例えば、実施した結果「ブースが目立たなかった」「スタッフの説明が曖昧だった」「配布資料に不足があった」などがあるかもしれません。
当日の問題点をリストアップし、関係者同士でしっかりと情報を共有することが大切です。
アンケート結果やスタッフからのフィードバックも、課題発見の貴重な材料になります。
小さなミスも決して放置せず、次に活かす意識を持つようにしましょう。
展示会は継続的な改善によって成果を積み上げていくイベントであり、振り返りはその起点です。
交換した名刺を整理する
展示会で交換した名刺を放置していては、せっかくの商談チャンスを逃してしまいます。
まず、展示会が終了したらすぐに、交換した名刺を整理し、リストにしましょう。
リストには、以下のような情報を明記します。
- 契約の見込みが高いのか低いのか
- 今後どのようにアプローチすべきか
これにより、優先順位をつけて効率的なフォローアップができます。
お礼のメールを送る
また、展示会に来場した顧客に対してお礼のメールを送ることで、関係を深められます。
メールは、以下のような内容を盛り込むようにしましょう。
- 来場のお礼
- 商品の関連情報
また、展示会当日の来場者の反応やニーズに合わせて、メールの内容は個別にカスタマイズしましょう。
例えば、案件につなげられそうな場合は、アポイントを意識したメールを送ります。
案件につながるか不明な場合は、今後も定期的に最新情報などを送ることや、不明点や相談事について連絡をもらえれば迅速に対応することなどを明記しましょう。
お礼のメールは、展示会が終了してからすぐに送ることで、来場者の記憶に残りやすくなります。
継続的に情報提供する
会で名刺交換した見込み客には、SNSやメールなどで継続的に情報提供することも重要です。
また、情報を一方的に送るだけでなく、発信の中で顧客とのコミュニケーションが取れるかどうかも検討します。
例えば、アンケートや電話などを実施することで見込み客の満足度や悩み事をヒアリングできれば、見込み顧客のニーズをうまく把握できるでしょう。
展示会準備における注意点
メリットも多い展示会営業ですが、注意点も存在します。
展示会営業を実施する前に抑えておきたい注意点について見ていきましょう。
展示会準備には日数がかかる
展示会営業は、準備の完成度次第で契約数や名刺交換数などの成果が大きく変わります。
効果が見込めるレベルで展示物を準備するには、それなりの日数がかかることを理解しておきましょう。
展示会の準備にかかる具体的な手順には、以下のような流れがあります。
事前に準備にかかる工数を把握し、計画的に作業を進めます。
コストがかかる
展示会に出展するには、様々なコストがかかります。
例えば、出展料や人件費はもちろんのこと、チラシやポスターの制作費や印刷代、備品レンタル代やブース制作費なども必要です。
これらを合わせると、1回の参加にかかる予算は数百万円にのぼる場合もあります。
展示会営業では、必ずしもかけたコストが回収できるわけではありません。
事前に予算を設定し、また、展示会営業中の目標をきちんと設定することで、できる限り売り上げにつながる施策を考えましょう。
参加するだけでは、売上にはつながらない
展示会では多くの見込み顧客と接触できますが、その場で即決受注になることはほとんどありません。
また、受注にすぐつながるとも限りません。
展示会では多くの競合他社と同じ会場内でアピールしなければならず、その中で自社の商品やサービスを差別化することは非常に難しいからです。
さらに、展示会に来場した人が全員購買意欲があるわけではなく、見て回るだけの人もそれなりの数で存在します。
展示会参加のためにかけたコストが契約の形で回収できればベストですが、どうしても難しい場合は、企業のブランド力や信用力を高めるなど、将来への布石として展示会を利用することも検討してみましょう。
まとめ
展示会営業は、潜在顧客と直接対話できる貴重な機会です。
しかし、その機会を最大限に活かすには、事前準備から実施中、アフターフォローまでの一連の流れをしっかりと把握しておく必要があります。
特に、展示会の前に目標を設定しておくことは非常に重要です。
かけたコストを回収できるかどうかを考えながら、当日の展示会にのぞみましょう。
展示会営業は難しいと感じるかもしれませんが、やり方次第で大きなビジネスチャンスにつながります。
ぜひ本記事を活用して、展示会営業に挑戦してください。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!



