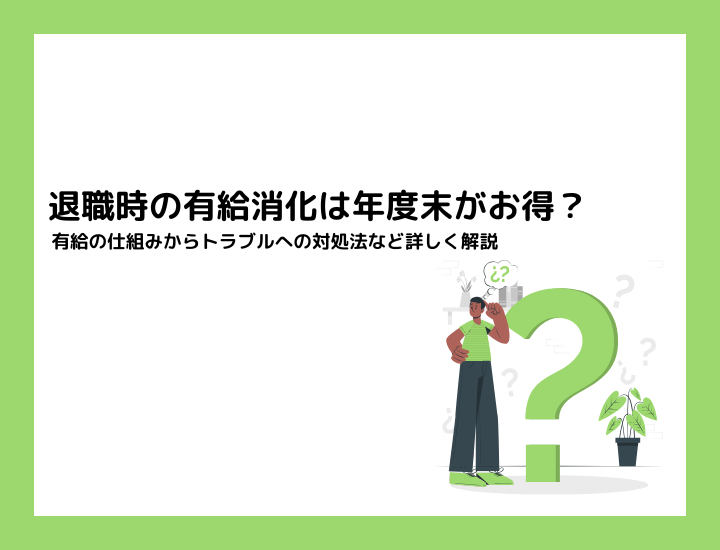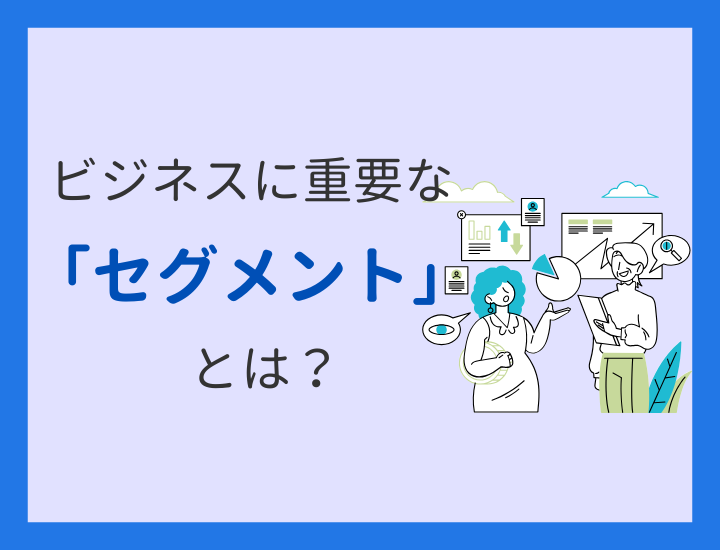
セグメントとは?重要性や分類・指標、ビジネスへの活かし方を紹介
はじめに
ビジネスシーンにおいて「セグメント」という考え方は、成果を高めるために欠かせない要素となっています。
顧客や市場を細分化し、戦略的にアプローチすることで、より効果的なマーケティングや営業活動を実現できるからです。
しかし、セグメントの意味や分類方法、実際の活用方法について、十分に理解できていない人も少なくありません。
この記事では、セグメントの基礎知識から、マーケティングや営業における具体的な活用法まで、体系的にわかりやすく解説していきます。
セグメントとは
セグメントとは、市場や顧客を特定の基準に基づいて細かく分類する作業です。
分類基準はさまざまで、年齢、居住地、性別、職業、購買行動、価値観など多岐にわたります。
たとえば、同じ商品でも若年層とシニア層では訴求ポイントが異なるため、効果的なマーケティングにはセグメント分けが必要です。
セグメントは顧客理解を深め、アプローチ方法を最適化するための第一歩といえるでしょう。
上記のような切り口を使い、顧客グループを絞り込むことで、限られたリソースの中でも効果的に成果を上げやすくなります。
セグメントの目的
セグメントの目的は、対象となる顧客の特徴やニーズを把握し、最適な商品・サービス提案を行うことです。
全体を対象にするよりも、特定のグループに合わせた施策を実施するほうが、訴求力や成約率は格段に高まります。
たとえば、スポーツ用品を販売する場合でも、ランニング愛好者向けと登山愛好者向けではアプローチが異なります。
セグメントを明確にすることで、無駄なコストを抑えながら効果的な営業活動が可能になるでしょう。
また、競合との差別化を図ることも可能です。
セグメントが注目される背景
現代においてセグメントが重要視される背景には、顧客ニーズの多様化と市場の成熟化があります。
インターネットやSNSの普及により、消費者は膨大な情報をもとに多様な価値観を持つようになりました。
ひと昔前のように「万人向けの商品」では通用しにくくなり、より個別化されたアプローチが求められる時代です。
また、競争が激化しているため、限られた市場で確実に成果を出すためにも、ターゲットを絞り込んだ施策が必要とされています。
「ターゲット」との違い
「セグメント」と「ターゲット」は似た言葉ですが、意味は異なります。
セグメントは初期段階に市場や顧客を分類するプロセスを指し、一方ターゲットは戦略策定時にその中から自社が狙うべき顧客層を選定する行為を意味します。
つまり、セグメントが「分ける作業」であるのに対し、ターゲットは「選ぶ作業」にあたります。
それぞれの違いを意識していないと、効果的な戦略設計が難しくなるため注意が必要です。
セグメントをしないとどうなるのか
セグメントを行わないまま営業活動やマーケティングを進めると、ターゲット層に最適な情報やサービスを提供できず、成果が著しく低下する恐れがあります。
ニーズや興味関心が異なる顧客すべてに画一的なアプローチをしてしまうと訴求力が弱まり、成約率の低下や広告コストの無駄につながりかねません。
さらに、社内リソースの配分が非効率になり、優先度の低い層へのアプローチに時間や人材を浪費してしまうリスクも高まります。
セグメント設計を怠ることは、機会損失のみならず、企業全体の成長を鈍化させる要因にもなりかねません。
顧客理解を深め、最適なアプローチを行うためにも、的確なセグメントを意識しましょう。
セグメントに関連する「セグメンテーション」とは
セグメンテーションとは、顧客や市場を共通点によって分類するプロセスを指します。
たとえば、年齢・性別・地域・価値観などの基準で市場を細かく分ける作業が該当します。
こうして分類された区分を「セグメント」と呼び、それぞれのグループに最適なマーケティング施策を展開することで、より効果的なアプローチが可能になるのです。
セグメントとセグメンテーションは混同しやすいですが、役割は明確に異なります。
セグメントは「分類されたグループ」そのもので例として、20代女性・都市部在住層と表せる。
セグメンテーションは「グループに分ける作業」を意味します。
例えば、年齢・性別・居住地で市場を区分できます。
セグメンテーションを適切に行うことで、無駄なアプローチを避けながら、効果的にターゲット層へアプローチできるマーケティング基盤が整います。
セグメントの4つの分類
セグメントは、特定の視点に基づき細分化されるのが一般的です。
代表的な分類基準には以下の4つがあり、それぞれ異なる特徴を持っています。
- 地理的変数
- 心理的変数
- 行動変数
- 人口動態変数
ここでは、セグメントの各分類について詳しく解説します。
地理的変数
地理的変数とは、居住地域や気候、都市・地方の区分など、地理的な特徴に基づいて市場を分割する方法です。
たとえば、寒冷地向けの商品開発や、都市部と地方で異なる広告戦略を展開する際に活用されます。
地理的変数は、地域ごとのニーズを正確に捉えるうえで重要な指標となるでしょう。
心理的変数
心理的変数は、消費者の性格やライフスタイル、価値観といった内面的な要素に基づく分類です。
たとえば「環境保護を重視する層」や「ブランド志向の高い層」など、同じ属性でも購買行動が異なることがあります。
ターゲットの心理を理解することで、より共感を呼ぶアプローチが可能になります。
行動変数
行動変数では、購買頻度、利用状況、製品やサービスに対する態度などの行動パターンに基づいて分類します。
たとえば「頻繁に購入するロイヤル顧客」と「セール時だけ購入する顧客」とでは、適切な施策も異なるでしょう。
行動ベースでセグメントすることで、購買意欲をより高める施策設計が可能になります。
人口動態変数
人口動態変数は、年齢・性別・職業・収入・学歴など、個人の基本情報に基づく分類です。
たとえば「20代女性・学生」や「30代男性・会社員」といった区分が一般的です。
人口動態変数は広範な市場全体を俯瞰できるため、ターゲット選定の出発点として多用されています。
セグメントの種類・特性
セグメントは、分類方法によって特徴が異なります。
ここでは以下4つの視点から、それぞれの特性について解説していきます。
・デモグラフィックセグメンテーション
・サイコグラフィックセグメンテーション
・ジオグラフィックセグメンテーション
・ビヘイビアルセグメンテーション
デモグラフィックセグメンテーション
デモグラフィックセグメンテーションは、年齢、性別、職業、年収、学歴といった人口統計情報を基に市場を区分する手法です。
多くの業界で活用されており、マーケティング施策の出発点となるケースが少なくありません。
年齢層別プロモーション(例:20代向けコスメ)
性別別商品の展開(例:メンズ向けスキンケア)
ターゲット像を明確に描きやすいため、商品やサービスの訴求内容を調整しやすくなります。
サイコグラフィックセグメンテーション
サイコグラフィックセグメンテーションは、価値観(エコ志向・ブランド志向)やライフスタイル(アウトドア志向・インドア志向)、趣味嗜好といった心理的特性に注目した分類方法です。
デモグラフィック情報だけでは捉えきれない、行動や意識の傾向を把握できます。
消費者の「なぜその行動を取るのか」に焦点を当てた施策を打ちたい場合に有効です。
ジオグラフィックセグメンテーション
ジオグラフィックセグメンテーションは、地理的要素をもとに市場を細分化するアプローチです。
都市部・地方、国、地域別といった括りで分類され、気候や文化的背景を考慮することもあります。
地域ごとに異なるニーズに応える製品設計や販売戦略の策定に役立ちます。
ビヘイビアルセグメンテーション
ビヘイビアルセグメンテーションは、消費者の行動パターンを軸にして市場を分類する方法です。
購買頻度、使用状況、製品へのロイヤルティなどを分析してセグメントを設計します。
- 購入タイミング(定期購入・セール時購入)
- ブランドへの忠誠心(ロイヤルユーザー・浮動層)
顧客ごとの行動傾向を踏まえることで、よりきめ細かなアプローチが可能になります。
セグメントに必要な4R
効果的なセグメントを実現するには、単なる分類だけでなく4つの重要な観点を押さえることが求められます。
ここでは、マーケティング戦略に欠かせない「4R(Rank・Realistic・Reach・Response)」について詳しく解説します。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| Rank(優先順位) | ビジネス効果の高いターゲット層を選別して集中する視点 |
| Realistic(規模の有効性) | 実現可能な市場規模が確保できるターゲットかを検討する視点 |
| Reach(到達可能性) | 適切なチャネルを通じてターゲットに接触できるかを見極める視点 |
| Response(測定可能性) | アプローチ後に効果測定が可能なターゲット設計を意識する視点 |
Rank(優先順位)
ターゲット候補の中から、最もビジネスインパクトが大きい層を選定する視点がRankです。
リソースが限られる現状では、すべての顧客層に等しくアプローチするのは非効率となります。
購買意欲・収益性・拡張性といった観点から優先順位を付け、戦略的に狙うべきセグメントを定める必要があるでしょう。
- 市場規模
- 収益ポテンシャル
- 自社リソースとの親和性
優先順位付けを怠ると、効果の薄い施策に時間やコストを浪費するリスクが高まります。
Realistic(規模の有効性)
選定したセグメントが、実際にビジネスチャンスとして十分な規模を持っているかを確認する視点がRealisticです。
理想的なターゲット像を設定できたとしても、市場が小さすぎると投資回収が困難になってしまいます。
- 市場の成長性
- 競合状況
- 顧客ニーズの明確さ
実現可能なターゲティングを目指すには、定量的なデータに基づいた市場調査が不可欠です。
Reach(到達可能性)
ターゲットとするセグメントに対して、適切にアプローチできるかを測る基準がReachです。
ターゲットがどこに存在し、どのチャネルを使えばリーチできるかを具体的に把握しておかなければなりません。
- 媒体・チャネル選定
- ターゲットに合わせたメディア設計
- オンラインとオフラインの使い分け
認知・接触できないターゲットを設定しても、マーケティング活動は空回りしてしまいます。
Response(測定可能性)
施策実施後に、効果検証が可能なセグメント設計になっているかを考える視点がResponseです。
ターゲット別にレスポンスを把握できれば、PDCAを回しながら精度向上を図れます。
- セグメントごとのKPI設定
- キャンペーン効果測定
- データ収集体制の整備
測定が難しいセグメントでは、改善につながる仮説検証ができず、持続的な成長が見込めなくなります。
マーケティングにおけるセグメント
マーケティング戦略を立案するうえで、セグメントの概念は非常に重要な役割を果たします。
ターゲット層を明確にし、それに応じた施策を展開するために、まずはセグメントを設定することが必要です。
ここでは、セグメントと関連の深い「STP分析」や、実際のマーケティングへの活用例について解説します。
STP分析との関連
マーケティングの基本フレームワークであるSTP分析は、セグメント(Segmentation)、ターゲティング(Targeting)、ポジショニング(Positioning)の3つの要素で構成されています。
最初に市場を細分化してセグメントを設定し、次に有望なセグメントをターゲットとして選び、最後に自社製品・サービスの立ち位置(ポジション)を明確にしていきます。
上記のプロセスにより、マーケティング施策の精度が高まり、限られた資源を効率よく活用できるようになります。
セグメント設定があいまいなままだと、ターゲティングやポジショニングもうまく機能しないため、最初のセグメント作業が重視されるのです。
マーケティングへの活用例
セグメントを適切に設定すると、より効果的なマーケティング施策を展開できるようになります。
たとえば、次のような活用方法が挙げられます。
- 年代別に最適な広告クリエイティブを作成
- 居住地に応じたキャンペーン内容を設計
- 購買履歴をもとにリピーター施策を実施
ターゲットごとに施策を最適化することで、広告のクリック率や購買率を大きく向上させることが可能です。
また、効果測定も容易になるため、次回以降の施策改善にもつなげやすくなります。
マーケティング成功のためには、セグメント設計とその活用を一貫して行う姿勢が重要です。
セグメントを営業に活用する方法
セグメントはマーケティングだけでなく、営業活動においても大きな力を発揮します。
ターゲットの精度を高めることでアプローチの無駄を減らし、成約率向上に直結させることが可能です。
ここでは、営業にセグメントを活かす具体的な方法を解説します。
営業においてセグメントが重要な理由
営業現場においてセグメントの意識を持つことは、効率的なアプローチと成果向上に直結します。
やみくもにアプローチを重ねるよりも、ターゲットを絞り込んで適切な提案を行うほうが、成約率を高めやすくなります。
セグメントを活用する主なメリットは次のとおりです。
- ターゲットのニーズに合わせた提案が可能
- 無駄な営業活動を削減できる
- 受注後の満足度やリピート率が向上する
適切なセグメント設計によって、顧客との関係構築や提案活動の質が格段に向上します。
単に効率を追うのではなく、相手に響く提案を実現するためにも、営業担当者自身がセグメント設計の意識を持つことが重要です。
新規顧客獲得に向けての営業リスト作成
営業活動の成果を高めるには、セグメントに基づいた精緻な営業リスト作成が欠かせません。
やみくもにリストを作成するのではなく、ターゲットを明確に絞ることで、効果的なアプローチが可能となります。
たとえば、以下のような視点でセグメントを切り分けると精度が上がります。
- 地域(ジオグラフィック)
- 業種・業界(デモグラフィック)
- 企業規模(デモグラフィック)
- 購買傾向(ビヘイビアル)
上記の情報を整理し、ニーズに応じたアプローチを設計すれば、成約の可能性が高いリストを効率的に作成できるでしょう。
ターゲットの特徴を把握したうえでリストアップを行うことが、営業成果を左右する大きな要素となります。
契約成立までの流れの円滑化
セグメントを適切に活用することで、顧客とのやり取りをよりスムーズに進められるようになります。
ターゲット層を明確にしておくと、ニーズや課題を事前に把握できるため、商談時に的確な提案を行いやすくなります。
具体的には、次のような点に注目しましょう。
- 顧客の興味関心に沿った資料を準備する
- ニーズに合った製品・サービスを提案する
- 想定される懸念点や質問事項に先回りして対応する
顧客に対して一貫性のあるコミュニケーションを取ることも重要です。
セグメントごとにパターン化された課題やニーズを踏まえた提案を行えば、商談の流れが滞ることなく進み、成約までのスピードアップが期待できるでしょう。
ターゲット理解を深めることが、契約率向上に直結します。
セグメントの効果を測定する方法
セグメント施策が実際に営業成果へ結びついているかを確認するには、適切な指標を設定して効果測定を行う必要があります。
ここでは以下の視点から、セグメントの効果を測定する方法を紹介します。
- 売上・成約率の変化を確認する
- ターゲット層の反応率を比較する
- 顧客満足度を測定する
- LTV(顧客生涯価値)を測定する
- コンバージョン率を測定する
- 売上成長率を測定する
売上・成約率の変化を確認する
セグメントの効果を測定するうえで、最も基本的かつ重要な指標のひとつが売上や成約率の変化です。
セグメンテーションによってターゲットを細分化した後、各グループに向けた施策を実施し、売上の伸びや成約率の向上をチェックします。
成果が出ていれば、セグメント設定やアプローチ方法が適切だったといえるでしょう。
確認する際には、施策実施前後で数値を比較するだけでなく、施策を打っていないグループとの比較も有効です。
たとえば、売上金額の増加率や新規契約件数の推移、リードから制約へのコンバージョン率の変化というような観点でチェックします。
これらを追うことで、単なる一時的な売上変動ではなく、ターゲット設定そのものの効果を見極めることが可能になります。
必ず数値で裏付けを取りながら、次の施策へとつなげましょう。
ターゲット層の反応率を比較する
セグメント施策の精度を確認するためには、ターゲット層ごとの反応率を比較する方法も有効です。
反応率とは、アプローチした件数に対して、実際にアクションを起こしてくれた割合を指します。
メール開封率や資料請求率、イベント参加率など、さまざまな指標を設定して測定できます。
各セグメントごとに同じ条件で施策を実施し、反応率を見比べることで、どのグループが最も良い成果につながっているかが明確になります。
仮に期待していた層よりも別の層の反応がよければ、今後のターゲティング戦略を見直すヒントにもなります。
数値で効果を可視化することが、施策改善のスピードを高めるポイントです。
顧客満足度を測定する
セグメントの精度を高めるうえで、顧客満足度を測定することも欠かせません。
顧客が製品やサービスにどの程度満足しているかを数値化すれば、ターゲティングが適切だったかどうかを検証できます。
一般的には、アンケート調査やNPS(ネット・プロモーター・スコア)などを用いて、満足度を可視化する方法が用いられます。
満足度調査で見るべき主な指標として、サービス全体への満足度や担当者への対応満足度、購入後のサポート体制満足度、価格やコストパフォーマンスの満足度が挙げられます。
とくに、セグメントごとに回答結果を分けて分析することで、どのターゲット層に対してアプローチが適切だったかを客観的に評価できるようになります。
高い満足度を得られたセグメントは、今後も重点的にアプローチすべき層といえるでしょう。
反対に満足度が低かった場合は、商品設計や提案方法の見直しが必要です。
LTV(顧客生涯価値)を測定する
セグメント戦略の効果を正しく判断するためには、LTV(顧客生涯価値)の測定も重要な指標となります。
LTVとは、顧客が取引を継続する間に企業にもたらす利益の総額です。
単なる一回限りの売上ではなく、長期的な収益性を把握することで、どのセグメントに注力すべきかの判断材料が得られます。
LTVを測定する際は、以下の項目に着目することがポイントです。
- 顧客単価(平均購入金額)
- 購入頻度(年間の取引回数)
- 継続期間(取引が続いた年数)
- 総利益率(売上に対する利益率)
セグメントごとにLTVを比較することで、見た目の売上規模に惑わされず、本当に価値ある顧客層を見極められるようになります。
たとえば購入単価は低くてもリピート率の高い層は、長期的に見ると非常に利益率の高いターゲットかもしれません。
単発の成果だけで判断せず、LTVの視点を持つことが、戦略精度を高めるうえで不可欠です。
コンバージョン率を測定する
セグメント別の成果を可視化するためには、コンバージョン率の測定も欠かせません。
コンバージョン率とは、Webサイトや営業活動を通じて、資料請求・商談設定・成約などの目標アクションに至った割合を指します。
コンバージョン数÷アクセス数(またはアプローチ数)×100(%)
ターゲットごとのコンバージョン率を比較することで、訴求内容や営業施策がセグメントに適しているかを数値で把握できるようになります。
仮にアプローチ件数が多くても、コンバージョン率が低ければ、ターゲットのニーズに合っていない可能性が高いと判断できます。
反対に、アプローチ数が少なくても高いコンバージョン率が出ているセグメントは、営業リソースを重点的に投下すべき有望な市場といえるでしょう。
感覚に頼らず、データに基づいた検証を心がけましょう。
売上成長率を測定する
セグメント戦略が効果的だったかを判断するには、売上成長率の測定も重要です。
売上成長率とは、一定期間における売上の増加割合を示す指標であり、セグメントごとの売上変動を比較することで、施策の成果を客観的に評価できます。
(当期売上高-前期売上高)÷前期売上高×100(%)
上記の数値をセグメント別に算出することで、どのターゲット層で売上が伸びているか、逆に伸び悩んでいるかを把握できます。
たとえば、若年層向けの商品施策に注力した結果、該当セグメントだけ売上成長率が高まったのであれば、マーケティング戦略の有効性が裏付けられます。
一方で、成長率が鈍化しているセグメントについては、商品の訴求内容や営業プロセスを見直すきっかけにもなります。
単純な売上高だけでなく、成長率にも着目することが、継続的な改善とターゲティング精度向上につながる要因です。
まとめ
セグメントを正しく理解し、適切に活用することは、ビジネスの成果を大きく左右する重要な要素です。
ターゲットを明確にすることで、限られたリソースを最大限に生かし、より高い効果を得られるでしょう。
マーケティングだけでなく、営業活動でもセグメントの視点を取り入れることで、効率的な顧客対応や成果向上につながります。
ぜひ本記事の内容を参考に、自社に合ったセグメント活用を実践し、ビジネスの成長に役立ててください。
SHARE この記事を友達におしえる!