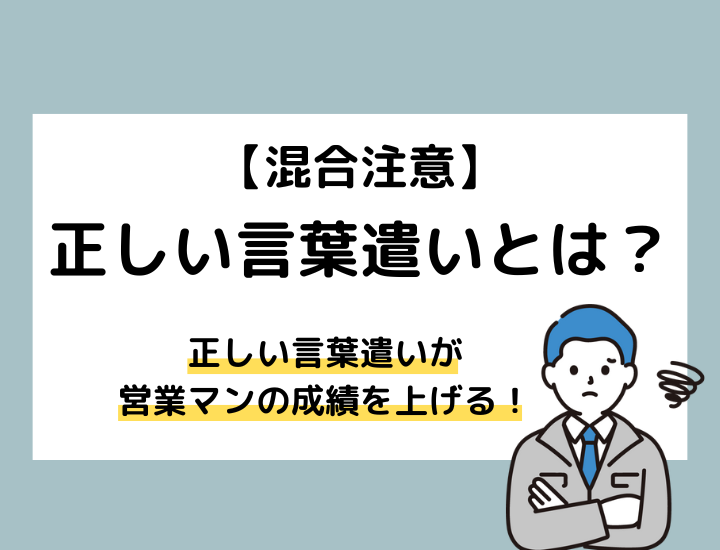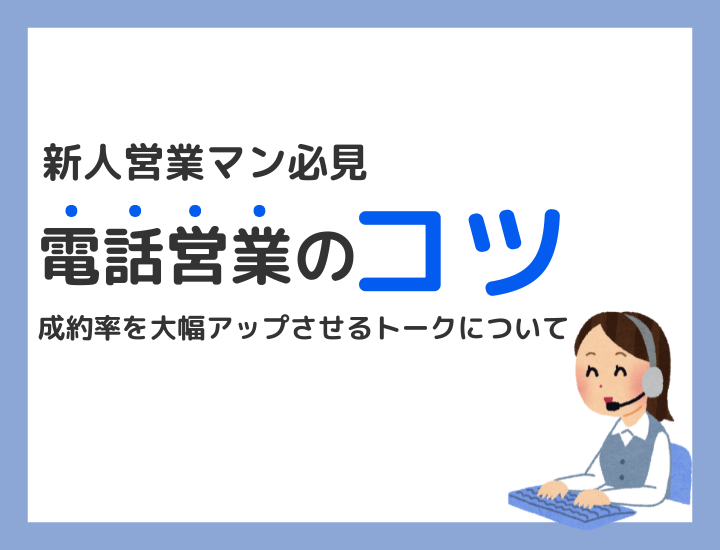
新人営業マン必見!電話営業での成約率を大幅アップさせるトークのコツ
はじめに
営業としてスタートをしたばかりの新社会人の皆さんは、まず最初に電話営業を行うことでしょう。
電話営業は、見込み顧客に電話でアプローチをして自社のプロダクトの営業をする手法です。
何十にも何百にもなる見込み顧客リストにひたすら架電をして、興味を持ってもらえたらアポイントを取得し、その後商談をする流れです。
そのため、同期よりもいかに早く受注率を上げるかは、電話営業の行動数と質にかかっています。
今回ご紹介するのは、新人営業が押さえておくべき電話のマナーと、アポイント率・成約率を上げるための営業テクニックです。
実際に電話営業をする前に準備しておくべきことや基本的なマナーを中心にご紹介するので、とくに新社会人になりたての方におすすめです。
ぜひ本記事を読んで、これからの営業活動の質の向上を目指しましょう。
電話をかける前の準備
何も準備をせずに、とにかく営業の電話をかけるのはあまりにも雑な仕事だと言えます。
それでは営業の成功率も上がらず、実績も伸びないでしょう。
まずは電話をかける前に準備をしなければなりません。
どのような準備が必要なのか解説していくので、まずは以下を参考に営業の電話をかける前の準備を進めてみましょう。
準備にはもちろん時間を必要としますが、難しいことは1つもないので、実績をあげるためにもじっくり準備をするのがおすすめです。
周りを整理する
関係ないように思いますが、自分の身の回りは綺麗にしておくべきです。
特に机周りを整理整頓し、すぐに必要な資料を取り出せるようにしておくと、スムーズなやり取りができるでしょう。
電話中にお客様を待たせてしまうことは、不快な印象を与えたり、お客様の満足度を下げたりしてしまう原因になります。
これは電話をかけるときだけでなく、受けるときも重要なポイントです。
急な質問に対しても、すぐに資料が取り出せるように、自分の身の回りを整理して、資料のある場所を把握しておきましょう。
机の回りや自分の身の回りは、常に整頓しておくのが望ましいです。
下調べをする
電話をかける相手の下調べを怠らないようにしましょう。
下調べをすることによって、何を売り込めば良いのかが明確になる可能性があります。
営業の成功率を高めるためには、相手が必要とするものを予測する力も必要です。
特に法人営業の場合は、企業の資料やホームページ、実績などから幅広い下調べが可能です。
企業の下調べをしっかり行って、企業が必要としているもの、もしくは企業にとって有用なものを探すのが営業を成功させるためのコツだと言えます。
名刺を用意しておこう
もしもすでに対面していて、名刺をもらっている場合は、手元に置いておくのが良いでしょう。
それによって、名前だけでなく役職をスムーズに確認できます。
営業において、お互いの信頼は重要なポイントになるでしょう。
名刺を手元に置いておけば、相手に名前や役職を聞き返さずに済むだけでなく、覚えていることに対して好印象を得られる可能性があります。
こういった小さなところから信頼関係は築かれるので、意外と重要なポイントです。
メモを用意する
まずは、電話をしながらスムーズにメモを取れるように準備しておきましょう。
メモは、次回の営業時に活用できるように整理しておくことが大切です。
話したお客様ごとに、質問内容や悩み、反応などをまとめて記録しておくと、次回のアプローチがスムーズになり成約率の向上につながります。
特に新規開拓営業は断られやすいため、適切にメモを残さないとチャンスを逃してしまうこともあります。
しっかりと記録を残し、次回の営業に活かせるようにしましょう。
なお、メモを取る際は、紙よりもデータベースに記録するのがおすすめです。
顧客情報を一元管理できるなどの顧客管理システム(CRM)を導入している場合、紙よりもこちらを優先して記録しましょう。
過去のやり取りをすぐに確認でき、より的確な提案が可能になります。
また、チーム内で情報を共有しやすくなるため、担当者が変わってもスムーズに対応できるメリットもあります。
もう営業をかける予定のないお客様の情報は、必要に応じて整理・削除し、管理しやすい状態を維持しましょう。
正確なメモを残し、次回の営業につなげることが、成功への近道です。
トークスクリプトを用意する
電話営業のコツとして、トークスクリプトを用意するという方法があります。
まずトークスクリプトとは、電話をかける際の台本のようなものです。
どんな順序で話すのか・その目的は何か・こんな質問にはこんな風に答えようといった、自分のすべき発言をメモした台本です。
これによって「次にすべき質問は何かな」と考える必要がなく、営業に集中できる効果が期待できます。
もしもマニュアルなど、企業ですでに用意されているものがあれば、それを使用してももちろん問題ありません。
マニュアルがあるとしても、しばらく経験を積む中で気づいたことを改善して、自分なりのトークスクリプトを作るのもおすすめです。
ある程度自分の仕事がマニュアル化できると、営業もかけやすくなってくるはずです。
営業で電話をかけるときのマナー
営業における電話応対のマナーとは、単に言葉遣いだけ気をつけておけばいいというものではありません。
こちらから相手の取引先へ電話をかけるときや、相手から電話を受けるときのそれぞれにマナーがあります。
たとえばこちらから電話をかけるときには、「社名と自分の名前を名乗る」、「用件は簡潔にする」、「かける時間帯に注意する」などのマナーがあるのです。
ここではこのような「電話をかけるときのマナー」について具体的に解説します。
正しい電話のかけ方を学ぶために、ぜひ参考にしてください。
社名と自分の名前を名乗る
相手に電話をかける際、社名と自分の名前を名乗ることは、ビジネスマナーの基本です。
第一声ではっきりと伝えることで、相手に安心感を与え、スムーズな会話につながります。
まずは、社名と自分の名前を伝えた上で、担当者がいるかどうかを確認しましょう。
例
「〇〇(会社名)の〇〇(自分の名前)と申します。
いつもお世話になっております。
〇〇部(相手の所属部署)の〇〇様(相手の指名や肩書き)はいらっしゃいますでしょうか?」
相手が電話に出たら、もう一度社名と名前を名乗ってから用件を伝えるようにしましょう。
また、相手の連絡先が携帯電話の場合でも、社名と自分の名前を省略せずに名乗ることが大切です。
なお、もし担当者が不在だった場合は、 「何時ごろお戻りの予定でしょうか?」 と尋ね、折り返しのタイミングを確認しておきましょう。
このひと手間で、無駄な再架電を減らし、営業効率を上げることができます。
また、 「改めてお電話したいのですが、ご都合の良い時間帯を伺ってもよろしいでしょうか?」 と聞くことで、相手にとって負担の少ない時間を狙って連絡できるため、話を聞いてもらえる確率も上がります。
用件は簡潔にする
用件を簡潔に伝えることは、電話営業の基本マナーとして非常に重要です。
最初にダラダラと前置きを話してしまうと、相手の貴重な時間を奪ってしまうだけでなく、要点が伝わりにくくなります。
また、電話をかける側にとっても、無駄な時間を費やす原因となるため、効率的ではありません。
スムーズな電話営業を行うためには、「〇〇の件でお電話いたしました」と結論から伝えることを意識しましょう。
最初に要件を明確にすることで、相手のストレスを軽減でき、話をスムーズに進めやすくなります。
さらに、電話をかける前に、話す内容をメモにまとめておくと、伝え漏れを防ぎつつ、簡潔な説明がしやすくなります。
もし話が長くなりそうな場合は、「〇分ほどお時間をいただいてもよろしいでしょうか?」と、事前に相手の都合を確認することも大切です。
相手にとって快適で、自分にとっても効率的な電話営業を心がけましょう。
電話が終わったら指で電話を切る
電話営業では、通話を終える際のマナーも重要です。
特に卓上電話の場合、受話器を雑に置く「ガチャ切り」は重大なマナー違反となるため、絶対に避けましょう。
「ガチャン!」と大きな音を立てて受話器を置くと、相手の耳に直接響き、不快な印象を与えてしまいます。
ビジネスシーンでは、こうした小さな配慮が相手の心象を大きく左右するため、丁寧な対応を心がけることが大切です。
受話器を置く際は、まず指でフックを押して通話を切り、それから静かに受話器を戻すと、不要な音を立てずに済みます。
こうすることで、相手に対して礼儀正しく、気遣いのできる営業マンという印象を与えられるでしょう。
また、こちらから電話を切るのは、相手がなかなか切らない場合に限ります。
その際も、いきなり切るのではなく「お電話、切らせていただきます」と一言添えると、より丁寧な対応になります。
細かい部分ですが、こうした心遣いが信頼関係を築く一歩となるため、意識して実践しましょう。
電話をかけるべきではない時間帯
電話応対のマナーとして、相手の業務状況に配慮し、適切な時間帯に電話をかけることは非常に重要です。
特に、業種によっては忙しい時間帯が異なるため、注意が必要です。
一般的に、電話をかけるべきではない時間帯として、「朝一番」「昼休み」「営業時間外」「業務終了間際」などが挙げられます。
1.朝一番(始業直後)
多くの企業では朝礼やミーティング、申し送りなどが行われるため、始業から1時間ほどは避けるのが無難です。
たとえば、9時始業の会社であれば、10時以降にかけると良いでしょう。
2.昼休み
昼休憩中は、社員がリフレッシュしたり食事を取ったりする貴重な時間です。
この時間帯に電話をかけると、相手に不快感を与える可能性が高いため控えましょう。
3.業務終了間際
終業時間ギリギリの電話は、相手の退勤準備を妨げるため避けるべきです。
特に、締め作業が発生する業種(例えば、金融機関や事務職)では、この時間帯は非常に忙しくなるため、極力控えたほうが良いでしょう。
また、業界によっては、特に避けるべき時間帯が異なります。
特定の業種にアプローチをする際は気をつけてください。
業種ごとのNG時間帯
医療・クリニック:診察時間中は対応が難しいため、昼休憩(12時〜14時頃)や診察終了後の時間帯(17時以降)を狙うと良いでしょう。
飲食業:ランチタイム(11時~14時)やディナータイム(17時~20時)は接客で忙しいため、アイドルタイム(15時〜16時頃)を狙うのがおすすめです。
小売業・販売業:開店直後や閉店間際、またピークタイム(昼・夕方)は避け、落ち着く時間帯を見極めましょう。
製造業・工場:シフト制のため、休憩時間や交代のタイミング(例:12時〜13時、15時〜16時)は避けたほうが無難です。
学校・教育機関:授業時間中は電話対応が難しいため、昼休み(12時~13時)や職員が比較的手が空く時間帯(16時以降)を狙うと良いでしょう。
どうしても上記の時間帯に電話をかける必要がある場合は、「朝早くから申し訳ありません」「お忙しい時間に恐れ入ります」「お昼時に失礼いたします」などと一言お詫びの言葉を添えると印象が良くなります。
相手のスケジュールに配慮した時間帯に電話をかけることで、スムーズなコミュニケーションにつながり、営業の成功率もアップします。
事前にできる準備はしっかりする
用件を簡潔に伝えるために、話す内容を事前にスクリプト(台本)にしておきましょう。
メモ帳と筆記用具は必ず手元に用意しておき、相手からの要望などを書き留められるようにしておいてください。
また、電話をかける相手の社名や所属部署名、役職名や名前の読み方など、先方の基本情報はきちんと確認しておいてください。
事前に確認しておくと、電話口でのもたつきや呼び間違いを防げます。
きちんと準備をしたうえで電話をすれば、精神的にも余裕をもてるでしょう。
電話を受けるときのマナー
電話をかけるときと同じように、受けるときにもマナーがあります。
たとえば「電話は3コール以内に取る」、「もしもし、と言わない」などがそれにあたります。
新人の営業マンにとって、電話をかけるときと同様、受けるときにもとても緊張するものです。
電話受付の担当者でなくとも、営業部宛にかかってきた電話に出るケースはあるので、営業マンは基本のマナーを身につけておくべきでしょう。
ここからは電話を受けるときのマナーについて具体的に解説します。
ここを参考にして電話を受けるときのマナーを身につけ、堂々と電話に出られるようになっていただきたいと思います。
3コール以内に取る
電話がかかってきたら3コール以内に出るのは、一般的なビジネスマナーとされています。
3コール以内に電話に出てもらえないと、かけた人からすると「待たされている」と感じてしまうケースが多いのです。
電話に出るのが遅いと、クレームに発展するとまでは考えづらいですが、社員教育ができていない会社だと思われる可能性はあります。
また大事な商談の連絡なのに、相手が待ちきれずに電話を切ってしまい、大きなチャンスを逃してしまう、といったことも起こりかねません。
会社の印象や業績にもつながることなので、ぜひ電話は3コール以内に取ってください。
もし3コール以上鳴ってしまった場合は、「大変お待たせいたしました。
○○株式会社、○○でございます」と一言お詫びの言葉を添えるようにしましょう。
「もしもし」は使わず「お電話ありがとうございます」から始める
電話を受けるときの注意点として、会社に電話がかかってきたときは「もしもし」と言わない、というマナーは必ず覚えておいてください。
「もしもし」を使うのは、ビジネスマナーにおいてはNGとされています。
不用意に使ってしまうと、相手に対し失礼な印象を与えてしまうので要注意です。
先方から電話がかかってきたら、「お電話ありがとうございます。
〇〇(会社名)の〇〇でございます」といった具合で、明るく電話に出るようにしてください。
相手の社名・お名前を繰り返す
電話を受けたときに会社名と自分の名前を名乗ると、通常は相手も会社名と名前を伝えてくれます。
このとき、相手が名乗り終わったら必ず復唱するようにしてください。
復唱すれば、相手の会社名や名前の聞き間違いを防げます。
このとき同時にメモを取っておくと「うっかり忘れてしまった」という事態を回避できます。
いつでもメモが取れるように、メモ用紙と筆記用具は手元に準備しておきましょう。
また復唱の際に「〇〇(会社名)の〇〇(相手の名前)様でございますね」と言う方もいますが、これは間違いです。
「ございます」は自分に対して使う丁寧語なので、相手のことを言うのには不適切です。
こちらが相手のことを言うときは、「いらっしゃいますね」を使うのが正しい言葉遣いなので、ぜひ覚えておいてください。
取り次ぎは一度保留をする
受けた電話の内容によっては、別の人に取り次ぐ場合もあると思います。
そのときは、「〇〇でございますね。少々お待ちください」と返答し、電話を保留にしてください。
保留をせずに相手を待たせてしまうと、周囲の雑音が聞こえるので不快な思いをさせてしまいます。
近くにいる人に取り次ぐ場合でも、必ず保留にしましょう。
また、保留にする時間は基本的に30秒程度といわれています。
取り次ぎに30秒以上かかるようであれば、「こちらから折り返しお電話を差し上げます」などと伝えましょう。
「相手の時間をうばってしまう」という意識をもち、必要以上に待たせないようにすることが大切です。
自分で対応できない場合は、一度確認する旨を伝える
かかってきた電話の内容が、自分だけでは解決できず、誰かに相談する必要のある場合もあるでしょう。
そのような場合、一度確認を取りたいという旨を相手に伝えることが大切です。
自分だけでは判断できない内容について、誰にも相談せず曖昧な返答をしてしまうのは大変失礼です。
「恐れ入ります。その件については確認が必要なので、少々お時間をいただきたいのですが、折り返しお電話を差し上げてもよろしいでしょうか?」と、一度確認したい旨をしっかりと相手に伝えましょう。
個人情報は口外しない
電話をかけてくる相手の中には、携帯電話の番号など社員の個人情報を聞き出そうとしてくる人もいます。
そのような人達の中には、取引先を装って個人情報を抜き出し、悪用しようとする者もいるでしょう。
個人情報の漏えいは、会社全体の損失につながる恐れもあります。
携帯電話の番号や社員の名前など、社内の個人情報にあたることは決して相手に教えてはいけません。
怪しいと思った場合は、「本人に確認したうえで、必要な場合は折り返しご連絡を差し上げます」などと伝えましょう。
営業電話を成功させるためのコツ
営業電話を成功させるためのコツとしては、以下の9つのことを意識するのがおすすめです。
覚えることは少し多く感じますが、ひとつずつでもクリアしていくことで電話営業でのアプローチの質が高まります。
一つずつでも構いませんので、コツを意識しながら進めてみてください。
- 断られて当たり前という意識を持つ
- 一本の電話ですべてを完結させようとしない
- 相手が目の前にいる意識で話す
- 説明口調にならず端的に話す
- 自分から断られるような話し方をしない
- 架電するタイミングを変えてみる
- トークスクリプトを作成する
- メリットやデータを提示する
- トークスキルを改善し続ける
それぞれのコツについて具体的に解説していきます。
断られて当たり前という意識を持つ
営業電話の成約率は決して高くなく、ベテランのテレアポ担当者でも全てのアプローチが成功するわけではありません。
むしろ、ほとんどの場合は断られることが前提です。
そのため、営業電話をかける際には「断られて当たり前」という意識を持ち、必要以上に落ち込まないことが大切です。
相手の立場に立って考えてみましょう。
突然、見知らぬ相手から営業電話がかかってきたら、すぐに話を聞く気にはなりにくいものです。
「忙しい」「急な話に対応できる心構えがない」「そもそも営業に興味がない」など、断る理由はさまざまです。
つまり、電話口で話を聞いてもらえるだけでも貴重なチャンスと捉えることができます。
また、営業電話の目的は必ずしも即座に契約を取ることでははありません。
まずは相手に興味を持ってもらうことが重要です。
そのためには、一方的な売り込みではなく、相手の要件をヒアリングしながら、ニーズに合った提案をする姿勢が求められます。
たとえアポイントにつながらなくても、良い印象を残せば、後日改めてチャンスが巡ってくる可能性もあるでしょう。
営業電話では、100件かけて1件のアポイントが取れれば良いということも珍しくありません。
そのため、「必ず成果を出さなければ」と気負うのではなく、「今日は〇〇件アプローチすることを目標にする」といった形で基準を変えると、精神的な負担を軽減できます。
まずは、断られるのが普通だと割り切り、気楽に挑戦できるメンタルを整えましょう。
一本の電話ですべてを完結させようとしない
営業電話でやりがちなのが、一本電話ですべてを完結させようとすることです。
営業電話をいきなりかけて、契約にまで至るケースは相当の幸運と言っても良いでしょう。
突然電話をかけて、相手のニーズに合致してすぐに商品が欲しい、サービスを利用したいとはならないことが基本です。
とくに企業を相手に架電をする場合には、契約に至ることはないでしょう。
営業電話をかける際には、ステップごとにゴールを決めておくと良いでしょう。
アポイントを獲得するという最終ゴールがある場合、アポイントを獲得できなくても担当者と話すことはできたか、担当者の反応はどうだったか、担当者が不在の場合は担当者の名前を聞くことができたか、都合の良い時間がいつかなどです。
ゴールをいくつか設定しておき、いくつ目標を達成できたかなどにすると、スムーズに進みやすくなります。
次のアクションにつなげやすいようにするという意識で行うと良いでしょう。
相手が目の前にいる意識で話す
営業電話は相手の顔や表情、リアクションなどがわからないため、気付かぬうちに失礼な物言いになっている、早口になってしまっているなどのケースがあります。
もし対面で話しているとしたら、相手のリアクションなどを読み取りながらゆっくり話す、概要に止めるなどを行えるでしょう。
しかし電話越しでは、きちんと意識していないと難しいため、相手が目の前にいる意識で話していきます。
相手を気遣いながら話すことができれば、たとえ電話越しであったとしても、相手に好印象を与えることは可能です。
「お忙しいところ恐れ入ります」など、社会人としてのマナーを忘れずに丁寧に話すようにしましょう。
営業では相手に信頼してもらわなければ、契約に至りません。
相手が目の前にいることを意識しながら、スムーズに会話ができるようにフレーズを用意しておくなどの対策をしていきましょう。
説明口調にならず端的に話す
営業電話では、相手の貴重な時間をいただいているという意識を持つことが大切です。
上手くいかないケースの多くは、話が長くなりすぎてしまうことにあります。
特に、誠実に対応しようとするあまり、商品やサービスの説明に力を入れすぎてしまうと、説明口調が強くなり、相手の興味を引く前に話を聞く姿勢を失わせてしまう可能性があります。
営業電話の目的は、一度の通話ですべてを完結させることではなく、次のアプローチにつなげることです。
そのため、提案内容を短くまとめ、要件を明確に伝えることを意識しましょう。
話が冗長になると、相手に「時間を取られている」と感じさせてしまい、信頼関係を築く前に会話が終わってしまうこともあります。
ファーストコンタクトでは、相手の興味を引くために、伝える情報を端的に絞ることが重要です。
まずは簡潔に提案のポイントを伝え、相手が関心を示したら、さらに詳細な情報を提供する流れを作ると、スムーズに信頼関係を構築できます。
営業電話では「短く、わかりやすく、次のステップにつなげる」ことを意識し、効果的なアプローチを心がけましょう。
自分から断られるような話し方をしない
営業電話では断られることを前提にアプローチしますが、自分から断られやすい流れを作らないことも重要です。
例えば、「今、お電話大丈夫でしょうか?」という一見丁寧なフレーズは、相手の都合を気にしすぎるあまり「今は忙しいので…」と断られる要因になってしまいます。
このような状況を避けるためには、「お忙しいところ恐れ入ります」と言い切ることで、スムーズに要件へと進めることができます。
弱気な姿勢ではなく、適度な自信を持って丁寧に提案することが大切です。
また、アポイント獲得の際も話し方に工夫を加えることで成功率が変わります。
「〇〇日の15時にお伺いしてもよろしいでしょうか?」と聞くと、「その時間は都合が悪い」と断られる可能性が高くなります。
そこで、「来週の木曜日と金曜日の午後の時間帯で、ご都合の良い時間を教えてください」と選択肢を提示することで、相手のスケジュールに合わせやすくなり、興味を引きやすくなります。
さらに、提案の段階でも相手が関心を持ちやすいように、要件を端的に伝えることがポイントです。
「本日は◯◯についてのご提案でお電話いたしました」と要点を先に伝えることで、相手が内容を理解しやすくなります。
電話営業では、最初のアプローチでいかに相手の興味を引き、スムーズに会話を進めるかが成約率アップのカギとなります。
架電するタイミングを変えてみる
なかなか担当者までつながらない場合は、架電するタイミングを変えてみましょう。
午前中にかけても外出や会議などでつながらない場合は、午後の時間帯にかけてみるなどです。
なお、会社に在籍しているタイミングはターゲットの業種や形態によって変わってきます。
一回の架電でつながらない場合は、いつ頃ならいらっしゃいますかなど、訪ねておくことで情報を揃えることにつながります。
加えて、アポイントの電話があったことを伝言してもらうなどをお願いしておくと、次に架電した際に話が進みやすくなります。
実際につながった人とは何時頃に架電したのかなど、情報を集めて、つながらない場合にはタイミングを変えて根気強く電架をしてみてください。
トークスクリプトを作成する
トークスクリプトとは、架電をしてつながった場合のオープニングトークから、相手の返答によって質問を変えていくメイントーク、アポイント獲得などのクロージングトークまでの道筋を示したものです。
営業電話で成果を挙げている企業は、このトークスクリプトを用意していることが多いです。
トークスクリプトに沿って話をしていくことで、内容が脱線することなく、スムーズに進めることが可能です。
加えて「よくある質問集」なども別途用意しておくことで、顧客からの質問にもその場で対応できます。
質問集に用意していない質問が来た場合は「、この場では正確な回答はできないので、後日改めて回答させていただいてもよろしいでしょうか?」など、次につなげるためのステップとしても用いても良いでしょう。
なお、トークスクリプトは完璧ではありません。
実際に業務を行なっていく中で改善点が出てきますので、都度改善を行い、ブラッシュアップしていくことが大切です。
誰が架電をしても営業品質が保てるようにするのが、トークスクリプトになります。
メリットやデータを提示する
メリットや好印象を与えるデータを提示することもコツの一つです。
大切なことは、抽象的なメリットやデータではなく、具体的なメリットやデータを提示することです。
たとえば「大変素晴らしいサービスです」や「多くの人が良い商品であるというアンケート結果が出ています。」などは、抽象的な表現です。
「残業時間を40%削減できる」「生産性が30%向上した」など、数字を用いたメリットやデータを伝えることが具体的なものになります。
こうしたメリットやデータを伝えるためには、事前に商品やサービスについての深い知識が必要になります。
また、ターゲットにどのようなメリットが刺さるかも考える必要があります。
事前に紹介したい商品やサービスについて調べ、ターゲットの課題について考え、シンプルな言葉でメリットやデータを提示できるようにしましょう。
トークスキルを改善し続ける
トークスキルを改善し続けることも成果を出すためには、重要です。
とくにアポイントの件数や成約件数などによって報酬が変わる場合には、一件一件のトークを振り返っていくことで、その後の成果が大きく変わっていくと言っても過言ではありません。
振り返る際には、良かった点と反省点を記録していくと最適です。
声のトーンやスピード、きちんと会話をしていたかなど、事前にチェックポイントを用意して確認していくと良いでしょう。
さらに可能であれば、自分の会話を録音して聴き直すのも良い方法です。
録音を聞くと、自分が話している時に抱いていた印象と異なることが多々あります。
第三者の目線で聞くことにつながるので、改善点がわかり、次の架電に活かすことが可能です。
こうした確認ポイントを意識しながら、トークスキルを改善し続けてみましょう。
営業の電話対応でのポイント
営業中の電話対応にも、もちろんコツがあります。
印象の良い電話のほうが、お客様も話しやすいものです。
ある程度つくろった雰囲気で話すほうが良いのか、それとも素で話したほうが良いのかなど、気になる点はいくつかあると思います。
電話口で仕事をすることになると「オペレーターのようにわかりやすく話さなければいけない」と考える人もいるかもしれません。
それでは、営業の電話はどのように対応するのが良いのか紹介していきます。
これはあくまでも参考として、自分のやり方を損なわない程度に実践するのがおすすめです。
いつもの声のトーンで話す
「営業の電話だから、オペレーターのように明るく高いトーンで話した方がいいのでは?」と考えるかもしれません。
しかし、営業の電話で高すぎるトーンを使うと、軽い印象を与えてしまい、無意識のうちに「営業感」が強く出てしまうことがあります。
営業らしい雰囲気が伝わると、受付の時点で断られる可能性が高くなるため注意が必要です。
特に、受付を突破するためには、トーンを少し低めにした方が効果的です。
なぜなら、低めの落ち着いたトーンで話すことで「取引先の担当者」のように聞こえ、受付の相手に安心感を与えられるからです。
実際、既存の取引先からの電話は落ち着いたトーンであることが多く、その雰囲気を再現することで、スムーズに担当者につないでもらえる可能性が高まります。
ただし、地声が極端に低すぎると、相手に聞き取りづらさを感じさせてしまうこともあります。
その場合は、普段より少しだけトーンを上げることを意識するとよいでしょう。
自分の声のトーンが適切かどうか不安な場合は、上司に聞いてもらい、フィードバックをもらうのがおすすめです。
もし周囲に相談しづらい場合は、ボイスレコーダーを使って自分の声を録音し、聞きやすさを確認するとよいでしょう。
適切なトーンを意識することで、営業電話の成功率を大幅に向上させることができます。
ゆっくりと話す
これは電話口でなくとも重要なことですが、会話をする際はゆっくり話しましょう。
こちらの伝えたいことを明確に伝えるため、さらには聞きやすくするために重要です。
まだ営業の電話に慣れていない人は、緊張から早口になってしまうことも考えられます。
そんなときには一度深呼吸をして、ゆっくり話せるように心掛けましょう。
イメージが必要であれば、アナウンサーの話すスピードを意識すると良いです。
アナウンサーくらいのスピードで話せれば、こちらの伝えたいことはしっかり伝わるでしょう。
内容を手短に話す
「こちらの伝えたいことはすべて伝えたい」と考えてしまうかもしれませんが、それは相手が聞くことに飽きてしまう可能性が高いです。
話の無駄を省き、商品・サービスの魅力を端的に話すことが重要です。
それによって、長い時間話を聞いてもらえる可能性が生まれます。
また雰囲気を和ませようと、雑談が増えるのもあまり効果的ではありません。
雑談が多いと、相手がこちらの伝えたいことを理解しづらくなり、話の間に不安を与える可能性があります。
最初は端的に、商品の魅力や説明を話して様子を見ましょう。
最後まで丁寧な対応を意識する
顧客からの評価を下げないように、最後まで丁寧なコミュニケーションを心掛けましょう。
もし営業を断られても、その場で気持ちを切り替え、冷静に対応することが大切です。
強引なアプローチは避け、あくまで誠実な態度を貫きましょう。
企業の評価は、どこから顧客に伝わるかわかりません。
一度でも悪い印象を与えてしまうと、今後の提案の機会を失う可能性があります。
逆に、最後まで丁寧な対応をすることで、「この営業担当者は感じが良い」「また話を聞いてみたい」といった興味を引くこともできます。
営業の電話では、最初から最後まで相手の気持ちを意識し、気持ちの良い対応を心掛けましょう。
電話を切る瞬間まで、明るく礼儀正しい姿勢を崩さないことが、信頼につながります。
電話でよく使う敬語表現
営業マンにとって、取り引きや接客をするうえで正しい言葉遣いは必須だといえます。
これは電話応対においても同様です。
敬語は相手を敬う丁寧な言葉遣いであり、ビジネスマナーにおいて欠かせないものです。
正しい言葉遣いができなければ、相手に不快な印象を与え、信頼関係を失ってしまうことになりかねません。
ここからは電話でよく使う敬語表現について解説していきます。
正しい敬語の使い方を身につけ、相手から好感をもってもらえるようにしましょう。
相手に関連するものは尊敬語を使う
尊敬語は、相手のことを直接立てて、敬意を表すために使う言葉です。
相手や相手の所有物、考え方や行動など、相手に関連するものが主語の場合に使います。
これらを敬う場合には、「お」「ご」「御(おん)」などの接頭語をつけましょう。
たとえば、相手の会社のことについて言う場合は、「御社」と言います。
尊敬語の例
尊敬語は、主に次の3つのグループに分類されます。
「本日はお電話いただきありがとうございます」
「お忙しい中、恐れ入ります」
②それ自体が敬語の意味を表すグループ
おっしゃる(「言う」の尊敬語)→「〇〇様がおっしゃいますように・・・」
いらっしゃる(「行く」「来る」の尊敬語)→「本日は何時ごろこちらへいらっしゃる予定でしょうか。」
召し上がる(「食べる」「飲む」の尊敬語)→「どうぞ、召し上がってください」
③「れる・られる」「ご(お)…になる」などを付け加えるグループ
「こちらの資料をお読みになってください」
「〇〇様は、何時ごろお戻りになる予定でしょうか」
自分に関連するものは謙譲語を使う
謙譲語は、自分や自分の会社、所有物、考えや行動を主語にする場合に使います。
自分をへりくだり、相手のことを間接的に高める言い方のことです。
自分のことや自分の所有物などをへりくだる場合は、「弊」「拙」「小」などの接頭語をつけましょう。
たとえば、自分の会社のことについて言う場合は、「弊社」「小社」と言います。
謙譲語の例
謙譲語は、主に次の3つのグループに分類されます。
「資料を拝見いたします。」
「私どもの考えは〇〇〇〇でございます。」
②それ自体が謙譲の意味を表すグループ
いただく(「もらう」の謙譲語)→「さっそく、資料を送らせていただきます。」
伺う(「行く」「来る」の謙譲語)→「それでは、明日の〇時にそちらへ伺います。」
存じる・存じ上げる(「知る」の謙譲語)→「その件については存じ上げております。」
③「お…する」「ご…いただく」などを付け加えるグループ
「明日、こちらからあらためてお電話いたします。」
「折り返しご連絡いただき、ありがとうございます」
全体を通して丁寧語を意識する
丁寧語は、話し手が自分の言葉を丁寧に言うことで、聞き手への敬意を示す言い方です。
語尾に「です」「ます」「ございます」をつけたり、名詞に「お」「ご」をつけたりします。
ビジネスシーン全体にいえることですが、電話のやりとりにおいても、常に丁寧語を意識して相手と会話することが大切です。
丁寧語を適切に使えば、相手からの印象をよくすることも可能でしょう。
電話でよく使う言葉
これまで紹介した敬語表現以外にも、電話応対でよく使われる言葉があります。
代表的なものをいくつか紹介するので、ぜひ参考にしてください。
・アポ
これは「アポイントメント」の略で、英語のappointomentがもとになっています。
面会の約束や予約の意味があり、社内外の人との約束に対し予定が取れているかを確認するときによく使われます。
・「明日」「明後日」
通常、これらの言葉は「あす」「あさって」と読みます。
しかし電話応対では「みょうにち」「みょうごにち」と読むのがマナーとされています。
ほかにも、「今」は「ただいま」「現在」、「今日」は「本日」と言い換える必要があるので、覚えておきましょう。
・担当者が帰ってしまったときの表現
このような場合は、「あいにく本日は失礼させていただきました」と言いましょう。
「退社しました」という表現は、帰宅以外に退職の意味も含み混同されやすいので、避けたほうがいいでしょう。
まとめ
ここまで、営業における電話応対のマナーについて解説してきました。
電話営業では、第一声のアプローチから相手の興味を引きつけ、スムーズなコミュニケーションを取ることが重要です。
また、言葉遣いや声のトーンを意識し、相手の気持ちに寄り添った対応を心がけることで、信頼関係を築きやすくなります。
さらに、提案内容に対する疑問や反論が出た際には、適切な切り返しを行いながら、相手のニーズに合った提案を行うことが成約率アップにつながります。
今回の内容をしっかりと活用し、自信を持って電話営業に取り組める営業マンを目指してください。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!