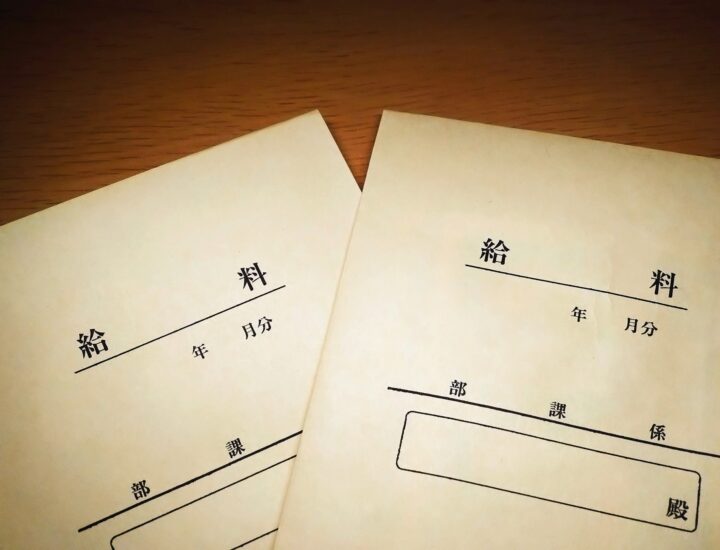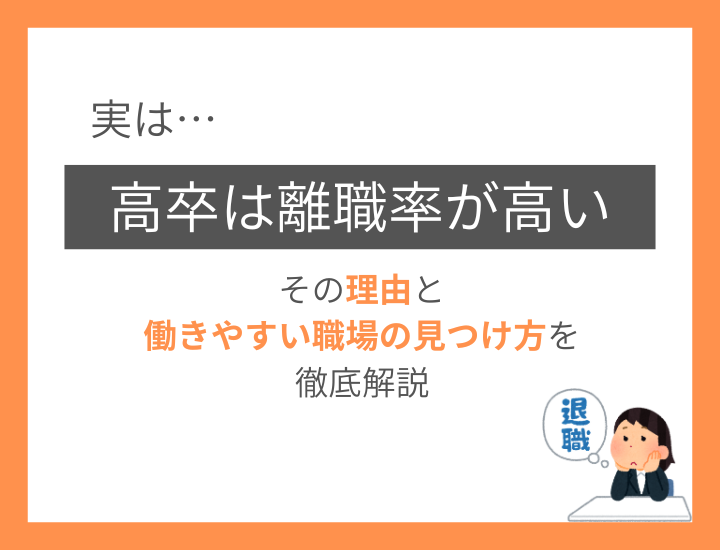
高卒の離職率はどのくらい?高くなる原因と業界別の実態、働きやすい職場を見つける方法
はじめに
高卒人材の就業定着は、企業と個人双方にとって重要な課題です。
厚生労働省の調査によれば、高校を卒業して就職した人の3年以内離職率は依然として高い水準にあります。
早期退職が起きると採用や育成にかかる負担が増えるだけでなく、組織の安定性にも影響が及びます。
就職する本人にとっても、短期間で転職を繰り返すことはキャリア形成に不安を残す要因となるでしょう。
本記事では、高卒者の離職率に関する最新データや傾向、離職が増える背景を整理するとともに、定着しやすい職場の特徴や改善策を紹介します。
長期的に働きやすい職場を選ぶための参考にしてください。
高卒の離職率の現状とデータ
高卒者の就業継続について考えるうえで、まず離職率の統計を把握することが欠かせません。
数字を通じて全体像を確認することで、現状の課題や将来への見通しを明確にできます。
以下では最新の統計や大卒との比較、年次推移・企業規模別の傾向などを具体的に見ていきましょう。
出典:厚生労働省|新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します
最新統計から見る高卒の3年以内離職率
高卒者の3年以内離職率は、比較的高水準といえます。
- 令和3年3月卒の3年以内離職率:38.4%
- 前年度(令和2年3月卒)からの変化:+1.4ポイント
- 年次内訳:1年目16.7%、2年目12.2%、3年目9.4%
3年累計38.4%という水準は、入社直後ほど離職が起こりやすい傾向を示します。
1年目で16.7%に達する構造は、軽視できません。
採用直後からの受け入れ体制や業務理解の支援を強める必要があります。
入社初年度の立ち上がりを支え、2年目・3年目へ滑らかに移行できる環境づくりを進めましょう。
大卒との比較から分かる高卒の傾向
学歴ごとの離職率を比較すると、高卒と大卒では数値に明確な差があります。
大卒の3年以内離職率は約3割弱で推移しているのに対し、高卒は大卒を上回る数字が出ていました。
特に入社直後から数年以内に退職する傾向は、高卒の方が強く出ています。
| 学歴区分 | 3年以内離職率 |
| 高卒 | 約38% |
| 大卒 | 約31% |
上記の数字から、高卒人材は就業初期の離職リスクが大卒より高いと理解できます。
年次推移に見る長期的な変化
年次推移の変化は、離職対策の内容や持続性を判断するうえで重要な材料となります。
| 卒業年次 | 3年以内離職率 |
| 平成8年3月卒 | 48.1% |
| 平成12年3月卒 | 50.3% |
| 令和2年3月卒 | 37.0% |
| 令和3年3月卒 | 38.4% |
平成期の離職率は5割近くに達し、非常に高い水準だったことがわかります。
その後は低下傾向をたどりましたが、直近では令和2年卒の37.0%から令和3年卒の38.4%へと再び上昇しています。
景気などによる一時的な変化だけでなく、職務理解や育成の仕組みが整っているかといった職場環境へ目を向けましょう。
事業所規模による離職率の違い
高卒の事業所規模別の離職率は、以下のとおりです。
| 事業所規模 | 高卒3年以内離職率(令和3年3月卒) |
| 5人未満 | 62.5% |
| 5~29人 | 54.4% |
| 30~99人 | 45.3% |
| 100~499人 | 37.1% |
| 1,000人以上 | 27.3% |
小規模な事業所ほど、離職率が上がる傾向にあります。
背景に挙げられるのは、教育体制や支援資源の充実度などです。
入社後すぐに辞めやすい時期と特徴
離職は、入社後すぐに発生する場合もあります。
- 3年以内離職率の構成:1年目16.7%、2年目12.2%、3年目9.4%
- 退職が増えやすい時期:入社1年目の4~5月、入社1年目の8~10月
- 背景として想定される状態:不明点の多さ、独り立ち前後の不安、同期比較による焦り
- 特徴的傾向:6カ月未満の超早期離職が多い
高卒の離職率が高い主な原因5つ
高卒就職者の早期離職には、複数の背景があります。
それぞれの要因を把握することで、働き続けられる職場を探す際の参考になるでしょう。
入社後の仕事内容のミスマッチ
新入社員が離職を検討する際、特に多いのが仕事への期待と現実の食い違いです。
高校新卒の採用では求人情報が公開されてから応募までの期間が非常に短く、企業研究に十分な時間を確保できない場合が多くあります。
そのため、入社してから仕事内容が想像と違うと感じるケースが目立ちます。
実際、退職者の中には「入社後に会社の印象が悪い方向へ変わった」と答える割合が半数近くに達していました。
限られた情報で進路を選択したことによる理解不足が、早期離職の大きな要因になっています。
人間関係のトラブルと孤立感
働き続けるうえで人間関係は欠かせない要素ですが、最初の会社を辞めた理由の第1位として「人間関係が良くなかった」と答える割合が29.0%に上っています。
上下関係の厳しさや職場内のコミュニケーション不足が主な原因です。
さらに、近年の若年層はプライバシーを重んじる傾向が強いため、親睦を深める目的で行われた言動がかえって負担となる場合もあります。
職場で孤立を感じやすい環境が続くと、働き続ける意欲は低下し、結果として離職につながりやすくなります。
給与や福利厚生など労働条件の不満
勤務条件に関する不満も、大きな離職要因の一つです。
厚生労働省の調査では、労働時間や休暇制度や賃金への不満が多く挙げられていました。
高校卒業者の初任給の平均は16万7400円であり、水準を下回る場合には待遇面で不利だと感じやすくなります。
さらに、社会経験がない状態で入社するため、求人票に記載された条件と実際の労働環境との乖離を強く感じやすいことも不満の要因です。
待遇と実態の差が積み重なることで、退職を選択する割合が高まります。
職務内容と適性のズレ
配属された職務にやりがいを見いだせず、適性が合わないと感じる場合も早期退職のきっかけになります。
離職理由の上位に「仕事内容」が挙げられており、高校生は具体的な仕事内容を事前に想像することが難しいため、入社後にギャップを感じることが少なくありません。
自身の能力を十分に活かせないと感じたり、成長を実感できない状況が続いたりすると、働き続ける意欲は薄れていきます。
結果として、適性との不一致が離職率を押し上げる要因になります。
教育体制やキャリアパスの不足
職場に教育体制が整っていない場合、新入社員は不安を抱えながら仕事に取り組むことになります。
十分なサポートを受けられないまま業務を任されると、過度なストレスを感じやすくなります。
また、将来のキャリアパスが示されていない環境では、成長意欲を持つ人材が先を見通せず、モチベーションを失ってしまうでしょう。
スキルアップや昇進の機会が乏しいと、長期的に勤続しようとする意欲が削がれ、結果的に離職につながってしまうのです。
業界・職種別に見る高卒の離職率
高卒就職者の離職率は、業界ごとに大きな差があります。
厚生労働省の調査によると、特に宿泊業や飲食サービス業など、サービス色の強い分野で離職率が高い傾向が見られます。
一方で、産業全体を通じてみても高卒特有の要因だけでなく、職種そのものの特性が影響していることも明らかになっています。
| 順位 | 産業 | 3年以内離職率(高卒) |
| 1位 | 宿泊業・飲食サービス業 | 65.1% |
| 2位 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 61.0% |
| 3位 | 教育・学習支援業 | 53.1% |
| 4位 | 医療・福祉 | 49.3% |
| 5位 | 小売業 | 48.6% |
もっとも高いのは宿泊業・飲食サービス業で、65.1%と過半数を超える水準に達しています。
大卒者でも同様に高く、学歴ではなく業界の労働環境そのものが反映されているといえるでしょう。
また、生活関連サービス業や娯楽業も60%を超えており、不規則な勤務時間や体力的負担が定着率を下げる要因になっていると考えられます。
さらに教育・医療・福祉・小売業など人と接する機会が多い業種も高い数値を示しており、職務内容や労働条件が離職率に直結していることが分かります。
高卒でも働きやすい業界・職種
就職後に長く働き続けたいと考える場合、離職率が低めで安定した業界を選ぶことが大切です。
ここでは、高卒でも働きやすい代表的な業界・職種を紹介します。
製造業
家電や自動車などを手がける企業は、比較的安定した給与と雇用を提供しています。
生産ラインの経験を積みながら資格取得を目指せる点も魅力で、ものづくりに関心のある人におすすめです。
製造現場はチームで動くため、協調性を重視する人にも向いています。
仕事を通じて専門スキルを磨けるため、成長を実感しやすいのも特徴です。
建設業
社会インフラを支える仕事は景気の影響を受けにくく、将来にわたり安定が期待できます。
経験を重ねて技能を磨くことで専門職としての価値を高められます。
資格取得がキャリアアップにつながりやすいため、努力を成果に変えたい人にとって有利な環境です。
特に体力を活かしたい人や、現場で実践的に学びたい人に向いており、手に職をつけたいという希望を実現できます。
物流・運輸業
生活に欠かせない物流は景気に左右されにくく、安定した需要があります。
倉庫作業や配送業務など幅広い職種があり、自分の適性に合わせて選択できます。
経験を積むことで管理職や指導者へ進む道も用意されているため、キャリア形成の可能性も広がるでしょう。
夜勤やシフト勤務がある一方で、収入が安定しやすい点は魅力です。
働きながら体を動かすことが好きな人や、運転技術を活かしたい人にとって相性が良い職場といえます。
介護・福祉業
介護・福祉業も需要が拡大し続けている分野であり、人の役に立つやりがいを感じやすい点が特徴です。
資格を取得しながら経験を積める仕組みが整っており、キャリアパスが明確になっている場合も多くあります。
人との関わりが日常的に発生するため、コミュニケーション力を伸ばしたい人には適しています。
利用者や家族からの感謝の言葉が、働く原動力になることも少なくありません。
安定性とやりがいを両立したい人に選ばれやすい業界です。
IT・通信業
IT・通信業は、デジタル化が進む現代において成長を続ける分野です。
未経験から挑戦できる職種も増えており、研修制度や資格取得支援を通じてスキルアップが可能です。
特に将来のキャリアの幅を広げたい人には魅力が大きい業界でしょう。
学び続ける意欲があれば安定的な働き方を築けるため、情報や技術に関心がある人に適しています。
さらに、業務経験が他分野への転職時に役立つことも多く、キャリア形成の柔軟性が高い点も特徴です。
販売・サービス業
販売・サービス業では接客を通じて対人スキルを培えるため、将来的に異なる職種へ転じる際にも役立つ基礎力を養えます。
勤務時間や雇用形態の選択肢が多く、自分の生活に合わせやすい働き方が可能です。
人と接するのが好きな人や、柔軟な勤務を望む人にとって向いています。
ただし繁忙期や長時間勤務が発生するケースもあるため、求人票や面接で条件を確認しておく必要があります
定着率の高い会社の特徴5選
長く安心して働きたいと考えるなら、定着率の高い会社の特徴を知っておくことが重要です。
自分に合った職場を選ぶためには、仕事内容や働き方、職場の人間関係や待遇、健康面のサポートなど、複数の要素を比較する視点が必要です。
適性に合った業務配分
社員の能力や性格に応じた業務配分がされている企業は、働きやすさを実感しやすくなります。
不得意な仕事ばかり任されるとモチベーションは下がりますが、得意分野や興味に近い業務を担当できれば意欲的に働けます。
新入社員の場合は経験が浅いため、少しずつ責任を広げていく形で仕事を任せてもらえるかどうかが重要です。
段階的にスキルを高められる環境では、やりがいを感じながら長く働ける可能性が高まります。
柔軟な働き方を可能にする制度
勤務時間や休暇制度に柔軟性があると、家庭やプライベートとの両立がしやすくなります。
近年はフレックスタイム制度やリモートワークの導入によって、自分に合ったスタイルを選べる企業が増えています。
特に若手社員にとっては、生活リズムを守りながら無理なく働けることが定着率を高める要因となるでしょう。
柔軟な制度を持つ職場では、ライフステージが変化しても働き続けやすい点が魅力です。
良好な人間関係を育む仕組み
人間関係は、働き続けるうえでもっとも重要視したいポイントの一つです。
社内イベントやメンター制度を設け、コミュニケーションを円滑にする取り組みがある会社は、孤立感を抱きにくくなります。
相談しやすい雰囲気があると、困難に直面した時も早めに解決でき、安心して業務に取り組めます。
仲間意識が強まればチームとして成果を出しやすくなるため、結果的に職場への定着度が高まるでしょう。
給与や福利厚生の充実
給与水準や福利厚生の充実度は、就職後の満足度に直結します。
基本給だけでなく、住宅手当や資格取得支援などの制度が整っていると、生活基盤が安定しやすくなります。
以下は、定着率の高い企業でよく見られる待遇の例です。
| 項目 | 具体例 |
| 基本給 | 業界平均以上の給与水準 |
| 手当 | 住宅手当・通勤手当・資格手当 |
| 福利厚生 | 退職金制度・社宅制度・健康診断 |
健康やメンタルを支えるサポート
定着率が高い企業は、社員の心身の健康を大切にしています。
定期健康診断や産業医による相談体制のほか、メンタル面で支援を受けられる窓口を用意している職場もあります。
過度な残業を抑える仕組みや、有給休暇を取得しやすい環境も重要です。
体調を崩さずに働けることは長期的な就労に直結するため、健康サポートの充実度は企業選びの際に必ず確認しておくべきポイントです。
高卒者が転職で成功するためのステップ
転職を成功させるためにはやみくもに応募するのではなく、自分の強みや目的を明確にした上で戦略的に行動することが重要です。
特に高卒者の場合は、学歴よりも実務経験や適性を重視する企業を選ぶ必要があります。
以下では、高卒者が転職活動を進める際に意識すべきステップを紹介します。
自分の強みと適性を見極める
まず必要なのは、自分の得意分野や適性を理解することです。
過去のアルバイト経験や前職での業務から、自分が成果を出しやすかった場面を振り返ると強みが見えてきます。
体力を活かせるのか、人と接するのが得意なのか、あるいは技術を学び続けたいのか整理することで適した職場を選びやすくなります。
自己分析を丁寧に行えば、転職活動での志望動機にも説得力を持たせられるでしょう。
離職理由をポジティブに変換する
面接では離職理由を必ず聞かれるため、ネガティブな印象を与えない答え方を準備することが大切です。
例えば「人間関係が合わなかった」と伝えるのではなく「チームワークをより大切にできる職場で力を発揮したい」と言い換えることで前向きな姿勢を示せます。
自分の成長意欲を強調すれば、採用担当者に好印象を与えられます。
経験を否定するのではなく、学んだことを次につなげる姿勢を意識することがポイントです。
長く働ける職場を選ぶ
転職先を決める際には、給与だけでなく職場環境や教育体制も確認する必要があります。
特に高卒者にとっては、長期的に働ける環境が整っているかどうかが大きな判断基準になります。
| 確認すべきポイント | 具体的な例 |
| 教育体制 | OJTや研修制度が充実しているか |
| 働き方 | シフトの柔軟性や残業削減の取り組み |
| 福利厚生 | 住宅手当・資格支援・健康管理制度 |
面接で伝えるべきキャリアを意識する
面接では自分の経験や強みを伝えると同時に、将来どのようなキャリアを築きたいのかを明確に示すことが重要です。
採用担当者は即戦力だけでなく、長期的に成長していけるかどうかを見ています。
そのため「資格を取得して専門性を高めたい」「チームをまとめる立場を目指したい」といった将来像を語ると効果的です。
方向性が具体的であればあるほど、意欲を持って働ける人材と評価されやすくなります。
未経験から挑戦できる転職先を探す
高卒であっても、未経験者を歓迎する業界や職種は数多く存在します。
介護や物流、ITなどは特に未経験からのスタートがしやすい分野です。
研修制度や資格支援制度を活用すれば、知識や技術を身につけながら働けます。
新しい環境に飛び込む際は不安もありますが、成長を実感しやすい職場を選ぶことで長期的なキャリア形成につなげられます。
高卒が転職で成功するためには転職エージェントの活用がおすすめ
転職を成功させるためには、一人で求人を探すよりも専門的なサポートを受けることが有効です。
特に高卒者や第二新卒、既卒などの若手層に強みを持つ転職エージェントを活用することで、自分に合った職場に出会える可能性が高まります。
「アゲルキャリア」は専任のアドバイザーが面談を通じて希望や適性を丁寧に把握し、最短1週間で内定獲得につなげる支援を行っています。
無料で相談できるため、経済的な負担を気にせずにスタートできます。
また、豊富な求人情報を基にマッチングを行うため、初めての転職活動でも安心です。
さらに、企業とのやり取りや面接調整も代行してくれるので、応募者は準備に集中できます。
高卒という学歴だけで判断されるのではなく、自分の強みや将来像を生かせる職場を選ぶためにアゲルキャリアを利用してみてはいかがでしょうか。
まとめ
高卒者の離職率は依然として高い水準にありますが、背景には仕事内容のミスマッチや人間関係、労働条件の不満など複数の要因が存在します。
一方で、業界や職種によって定着率には明確な差があり、製造業や物流、介護・福祉・ITといった分野では長期的に働きやすい傾向も見られます。
企業側も柔軟な勤務制度や教育体制の整備、評価制度の明確化などで改善を進めており、高校や家庭の支援も定着率向上に欠かせません。
求職者自身も自己分析や適職の見極め、転職エージェントの活用を通じて、より良いキャリアを築くことが可能です。
学歴に左右されるのではなく自分の適性や将来像を重視し、信頼できるサポートを受けながら職場を選ぶことが安定したキャリア形成につながります。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!