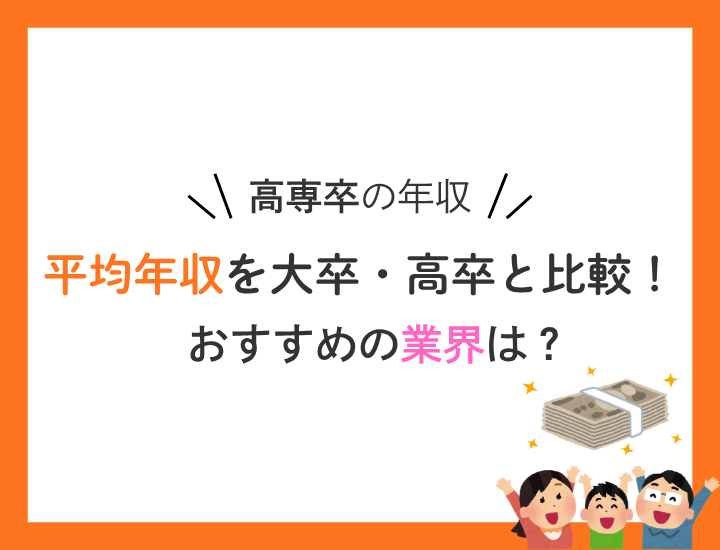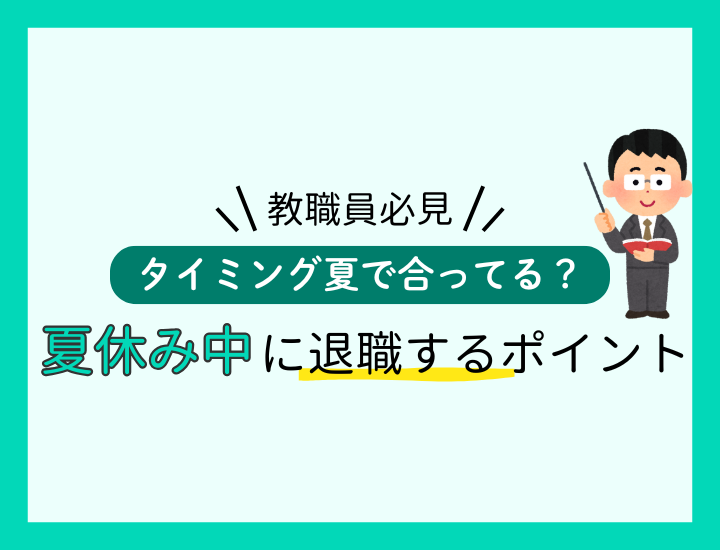はじめに
高専を卒業して社会人として数年が経つと、「自分の年収は妥当なのか」「同世代と比べて高いのか低いのか」と疑問に思う人は少なくありません。
高専卒は専門知識を持つ人材として評価され、初任給は高卒よりも高い水準にありますが、大卒と比べると格差が気になるケースもあります。
この記事では、高専卒の平均年収や初任給を学歴別に比較し、業界ごとの傾向や将来的な賃金格差についてもデータを用いて解説します。
さらに、キャリアアップや転職で収入を伸ばすための方法についても紹介します。
【高専卒の年収】初任給と平均年収を学歴別に比較
ここでは高専卒の最新データを紹介するとともに、大卒や高卒との違いを比較します。
自分の年収が学歴ごとの相場と比べてどうなのかを把握することで、今後のキャリアを考える際の参考にしましょう。
高専卒の平均年収
高専卒の給与水準は、高卒よりも高く、大卒と同程度の初任給からスタートするのが特徴です。
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によれば、以下のように初任給と年代別の平均給与が公表されています。
新規学卒者の学歴別にみた賃金
| 学歴 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 高専・短大卒 | 223,900円 | 231,000円 | 221,100円 |
年代別の平均給与(高専・短大卒)
| 年齢 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 20~24歳 | 230,400円 | 239,900円 | 226,800円 | 25~29歳 | 258,600円 | 277,200円 | 251,000円 |
| 30~34歳 | 279,600円 | 311,400円 | 259,700円 |
| 35~39歳 | 299,100円 | 350,400円 | 270,500円 |
| 40~44歳 | 312,000円 | 378,300円 | 285,700円 |
| 45~49歳 | 330,100円 | 413,300円 | 303,200円 |
年齢とともに着実に給与が伸び、40代半ばには平均で月33万円程度に達します。
年収でいうと396万円+賞与です。
特に男性は30代後半から大きく伸びやすく、管理職や主任クラスに昇進する時期と重なるのが背景です。
一方、女性は出産や育児でキャリアが中断するケースがあるため平均はやや低めですが、近年はキャリア継続者の増加により男女差は縮まりつつあります。
高専卒は実践的スキルを武器に安定した収入が得やすい学歴といえます。
大卒の平均年収
大卒は、初任給から高専卒と同水準でスタートしますが、年齢を重ねるにつれて給与の伸びが大きく、40代以降で収入差が広がっています。
新規学卒者の学歴別にみた賃金
| 学歴 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 大卒 | 248,300円 | 251,300円 | 244,900円 |
年代別の平均給与(大学卒)
| 年齢 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 20~24歳 | 250,800円 | 251,500円 | 250,200円 |
| 25~29歳 | 283,900円 | 290,300円 | 276,700円 |
| 30~34歳 | 325,200円 | 340,500円 | 300,000円 |
| 35~39歳 | 373,200円 | 392,800円 | 331,300円 |
| 40~44歳 | 406,200円 | 433,000円 | 338,900円 |
| 45~49歳 | 459,200円 | 493,300円 | 365,700円 |
大卒は20代後半から30代にかけて給与が大きく伸び、40代半ばでは高専卒との差が約13万円開いています。
特に男性の場合、管理職や専門職への登用が増えることで収入が急速に上がる傾向があります。
一方、女性は依然として平均値が低めですが、近年はキャリアを継続する人が増えており、差は徐々に縮小しています。
高専卒と比べた場合、大卒は「昇進機会の豊富さ」「企業内での処遇」によって年収が優位になりやすく、特に大企業ではその傾向が顕著です。
年収でいうと552万円+賞与と高専卒よりも150万円以上と差があるといえます。
高卒の平均年収
高卒は社会に早く出られるメリットがある一方、給与水準は大卒や高専卒に比べて低めです。
厚生労働省の統計によると、初任給は以下のとおりです。
新規学卒者の学歴別にみた賃金
| 学歴 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 高卒 | 197,500円 | 200,500円 | 191,700円 |
年代別の平均給与(高卒)
| 年齢 | 全体 | 男性 | 女性 |
| 20~24歳 | 217,300円 | 223,300円 | 209,600円 |
| 25~29歳 | 243,000円 | 252,600円 | 223,700円 |
| 30~34歳 | 265,400円 | 280,500円 | 229,300円 |
| 35~39歳 | 282,900円 | 302,300円 | 236,200円 |
| 40~44歳 | 301,100円 | 328,200円 | 241,600円 |
| 45~49歳 | 316,700円 | 348,200円 | 247,000円 |
この水準を年収に換算すると、例えば40代半ばの平均給与31.6万円は年間約379万円+賞与です。
同年代の高専卒は約400万円+賞与、大卒は約550万円+賞与であり、学歴による差は明らかです。
ただし、高卒は就職年齢が早いため、20代前半から安定した収入を得られるメリットがあります。
働きながら資格取得やスキルアップを重ねれば昇給のチャンスも広がります。
反対に、キャリア形成を意識せず働き続けると、大卒や高専卒との差がさらに大きくなる可能性があるため、若いうちから将来を見据えた行動が必要かもしれません。
【高専卒の年収】卒業後の進路
ここからは、高専卒業後の進路について見ていきます。
大きく分けると「就職」と「進学」の2つがあり、毎年の統計では約6割が企業に就職し、残りは大学編入や専攻科への進学です。
進路の違いは将来のキャリアや年収の伸びに直結するため、それぞれの割合や特徴を知っておくことが大切です。
就職率と進学率
高専卒業生のおよそ6割が就職を選び、残りの多くは大学編入や専攻科への進学を希望しています。
就職率は景気に左右されにくく、直近のデータでも安定して90%を超える水準を維持しており、企業からの需要の高さがうかがえます。
進学者は主に国公立大学の工学部や専攻科に進み、さらに高度な専門知識を身につけることで将来的に研究職や開発職へ進むケースが多くみられます。
就職は早く収入を得られるメリットがあり、進学はキャリアの幅を広げやすいという特徴があります。
それぞれにメリットがあるため、自分の将来像に合わせて選択することが重要です。
産業別の就職者数ランキング
2025年度の統計によると、高専卒業生の就職先は製造業に大きく偏っています。
以下は卒業者の就職者数上位10産業です。
2025年度 高専卒業生の産業別就職者数ランキング
| 順位 | 産業 | 就職者数(人) |
| 1位 | 製造業 | 2,311 |
| 2位 | 情報通信業 | 787 |
| 3位 | 建設業 | 546 |
| 4位 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 376 |
| 5位 | 運輸業・郵便業 | 300 |
| 6位 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 272 |
| 7位 | サービス業(他に分類されないもの) | 161 |
| 8位 | 公務 | 140 |
| 9位 | 卸売業・小売業 | 75 |
| 10位 | 不動産業・物品賃貸業 | 54 |
ランキングを見ると、製造業が全体の約45%を占め、圧倒的に多いことがわかります。
次いで「情報通信業」が増加傾向にあり、IT・デジタル分野でも高専卒の需要が拡大しています。
また、建設業やインフラ系(電気・ガス・熱供給・水道)も上位に入り、社会基盤を支える分野で高専生が活躍しています。
人気企業ランキング
2025年度の高専卒業生の就職先をみると、製造業やインフラ系の大手企業が上位を占めています。
以下は人気の高い企業上位10社です。
2025年度 高専卒業生の人気就職先ランキング
| 順位 | 企業名 |
| 1位 | 旭化成株式会社 |
| 2位 | 西日本旅客鉄道株式会社 |
| 3位 | 三菱電機株式会社 |
| 4位 | 中国電力ネットワーク株式会社 |
| 5位 | 京セラ株式会社 |
| 6位 | ダイキン工業株式会社 |
| 7位 | 国土交通省 |
| 8位 | 関西電力株式会社 |
| 9位 | 株式会社メンバーズ |
| 10位 | 株式会社FIXER |
上位には電機、化学といった製造業の大手企業に加え、鉄道・電力などインフラ系の企業も名を連ねています。
特に三菱電機やダイキン工業、京セラといった製造業大手は毎年高専生からの人気が高く、技術力を活かせる職場環境が整っている点が魅力です。
また、近年はIT・デジタル分野の企業(メンバーズ、FIXERなど)もランクインしており、就職先の幅が広がっていることがわかります。
従来の製造業中心から、インフラ・ITまで広がっているのが2025年度の特徴です。
【高専卒の年収】将来的な賃金格差
ここからは、高専卒と大卒・高卒の間に生じる賃金格差について解説します。
初任給では大きな違いが見られないものの、年齢を重ねるにつれて昇進や昇給のスピードに差が出やすく、生涯賃金や退職金では明確な格差が生まれます。
男女差や企業規模による違いも含めて確認しておくことで、自分のキャリア設計に役立てることができるでしょう。
生涯賃金
高専卒の年収を考える際には、長期的な収入である「生涯賃金」を確認することが大切です。
初任給は大卒と大きな差がないものの、40年働いた場合には学歴・性別・企業規模によって明確な差が出ます。
学歴別 生涯賃金(定年まで、退職金を含まない・2023年 男性正社員)
| 学歴 | 企業規模計 | 1,000人以上 | 100–999人 | 10–99人 |
| 高校卒 | 2億800万円 | 2億4,200万円 | 2億700万円 | 1億8,300万円 |
| 高専・短大卒 | 2億3,300万円 | 2億6,900万円 | 2億2,200万円 | 1億9,100万円 |
| 大学卒 | 2億5,100万円 | 2億8,700万円 | 2億3,800万円 | 2億600万円 |
学歴別 生涯賃金(定年まで、退職金を含まない・2023年 女性正社員)
| 学歴 | 企業規模計 | 1,000人以上 | 100–999人 | 10–99人 |
| 高校卒 | 1億5,400万円 | 1億7,600万円 | 1億5,500万円 | 1億3,800万円 |
| 高専・短大卒 | 1億7,500万円 | 2億100万円 | 1億7,300万円 | 1億5,900万円 |
| 大学卒 | 2億1,900万円 | 2億2,900万円 | 1億9,600万円 | 1億6,900万円 |
この表から、高専卒は高卒より有利であるものの、大卒との差は男女ともにあることがわかります。
男性の場合、高専卒は高卒より約2,500万円多く稼げますが、大卒よりは約1,800万円少ない水準です。
女性では、高専卒は高卒より約2,100万円多い一方、大卒との差は約4,400万円に広がります。
退職金
男女別の退職金は以下のとおりです。
学歴別 退職金(2023年 男性、女性・正社員)
| 学歴 | 企業規模計 | 1,000人以上 | 100–999人 | 10–99人 |
| 高校卒 | 1,440万円 | 1,840万円 | 1,140万円 | 700万円 |
| 高専・短大卒 | 1,460万円 | 1,920万円 | 1,050万円 | 950万円 |
| 大学卒 | 1,840万円 | 2,140万円 | 1,510万円 | 1,210万円 |
このデータからわかるように、高専卒の退職金は高卒とそこまで変わらず、大卒とは大きな差があります。
企業規模計で比較すると高卒が約1,440万円、高専卒が約1,460万円、大卒が約1,840万円と、大卒との差は約400万円です。
また、企業規模による違いも大きく、1,000人以上の大企業では高専卒でも約1,920万円の退職金が見込めますが、中小企業では1,000万円前後にとどまります。
【高専卒の年収】キャリアアップする方法
ここからは、高専卒が年収を伸ばすためのキャリアアップ方法について解説します。
初任給や平均年収では大卒と大きな差がなくても、長期的には昇進や昇給の機会の違いから格差が広がりやすいのが実情です。
ただし、資格取得や大学編入、転職といった行動次第で収入を増やす方法はあります。
資格を取得する
高専卒が年収を高める方法のひとつが資格取得です。
技術職では国家資格や専門資格を持っていることで昇進や昇給につながるケースが多く、就職や転職の際の評価も高まります。
例えば、「技術士補」「電気主任技術者」「危険物取扱者」などは製造業や電気系の分野で重宝される資格です。
また、公務員試験を受けて技術系職種に進む方法も。
近年は情報分野の需要も高まっており、基本情報技術者や応用情報技術者などのIT系資格を取得することでキャリアの幅を広げられます。
資格は努力の成果が数字として示されるため、年収アップを目指すうえで取得を検討してみるのもいいのではないでしょうか。
大学へ編入する
高専は専門知識や実践力を養える一方で、学位は「準学士」です。
大学に編入すれば「学士」の学位を取得でき、大卒と同等の評価を受けやすくなるため、昇進や転職において優位に立てます。
特に大企業や研究職、開発職を目指す場合、大学への編入をおすすめします。
編入は、高専で学んだ内容が単位として認められるため効率的に学べる一方、卒業までに必要な期間は延びるため、社会に出る時期が遅れるデメリットもあります。
また、大学進学には学費や生活費の負担が伴うため、経済的な負担も考えなければいけません。
一方で、大学編入には大きなメリットがあります。
学士を取得すれば大学院進学も可能となり、研究職や専門職に進むチャンスも広がります。
さらに、学歴上「大卒」として扱われることで、将来的な生涯賃金や退職金においても高専卒のままより多くなる傾向があります。
起業する
高専では実験や実習を通じて技術を磨くため、製造業やIT分野などで事業を立ち上げる基盤を持ちやすいのが特徴です。
特に新しい製品や技術サービスを生み出すビジネスは、高専で得た専門性を直接活かせる分野といえるでしょう。
文部科学省や経済産業省の補助金制度、自治体のスタートアップ支援、さらに高専OBや地域産業支援機関のネットワークを活用すれば、資金調達や人材面でのサポートを受けやすくなります。
こうした環境を利用すれば、リスクを抑えながら挑戦できるのもメリットです。
もちろん、起業には資金繰りや顧客獲得といった課題があり、安定収入を得られる会社員と比べれば不安定な側面もあります。
失敗しても再チャレンジしやすい時代だからこそ、高専卒ならではの専門スキルを強みに、自らの事業を築くという選択肢も検討してみてはいかがでしょうか。
転職する
新卒で入社した会社に長く勤めるのも選択肢のひとつですが、キャリアの途中で環境を変えることで、収入や仕事内容を大きく改善できるケースは少なくありません。
特に大企業や成長分野への転職は、年収アップに直結する可能性が高いといえます。
近年では、製造業や電気・機械分野に加え、ITや通信分野でも高専卒の需要が拡大しています。
成長産業に移ることで、20代後半から30代でも100万円単位で年収が増える事例も珍しくありません。
また、転職は収入面だけでなく、仕事内容や働き方を見直す機会にもなります。
研究開発や設計といった専門職に挑戦する、あるいは待遇や福利厚生が整った企業へ移るなど、キャリア全体の満足度を高められるのも大きなメリットです。
一方で、転職にはタイミングや準備が重要です。
スキルや資格を整理して市場価値を明確にすること、転職エージェントを活用して非公開求人や条件交渉を行うようにしましょう。
高専卒は即戦力として評価されやすいため、転職市場でも需要があります。
今の収入や待遇に不安を感じているなら、一度キャリアを見直し、自分の強みを活かせる企業への転職を検討するのもおすすめです。
転職エージェントを活用して希望に合った転職先を見つける
転職エージェントを利用することで、効率的に条件の良い転職先を見つけられます。
転職エージェントは大手メーカーやIT企業の非公開求人を多数公開しているケースも多く、一般公開されていない好条件の案件に出会える可能性が高いのが特徴です。
また、担当者が職務経歴書や履歴書を添削してくれるため、スキルや経験を企業に伝わりやすい形に整えられます。
面接対策では想定質問への回答の準備をサポートしてもらえるため、選考通過率が上がりやすくなるでしょう。
特に製造業やIT業界に強い転職エージェントを選べば、高専卒の専門性を評価してくれる企業にも出会えるチャンスがあります。
現在の給与に不満がある人やキャリアを伸ばしたい人は、まず複数の転職エージェントに登録して比較し、自分の条件に合う求人を探すのが有効な方法です。
まとめ
高専卒の初任給や平均年収は大卒と大きな差がなく、スタート時点では有利な立ち位置にあります。
しかし、長期的に見ると昇進や昇給の機会の差から、大卒との間に生涯賃金や退職金で格差が生じやすいのも事実です。
とはいえ、高専卒には就職率の高さや実践的な技術力といった強みがあり、資格取得や大学編入、転職などの選択を通じて十分に収入を伸ばせる可能性があります。
さらに、転職エージェントを活用すれば、自分のスキルを評価してくれる企業や好条件の求人に出会える機会も広がります。
年収やキャリアに不安を感じている方は、まず情報を集め、自分に合ったキャリアアップを見つけていきましょう。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!