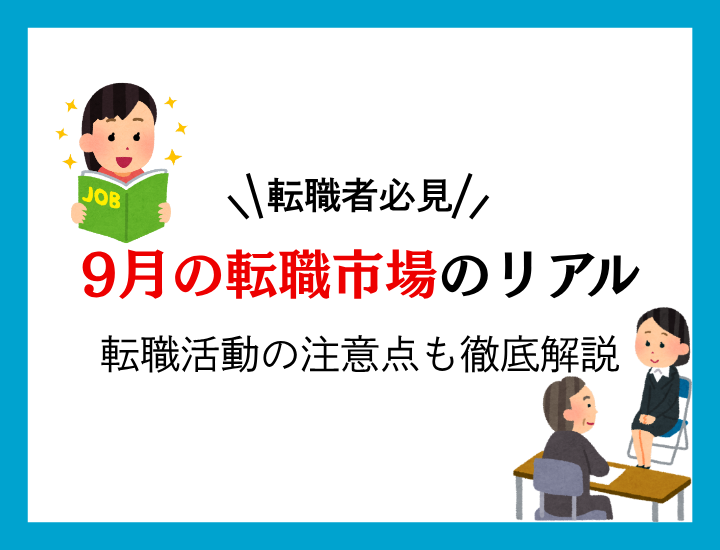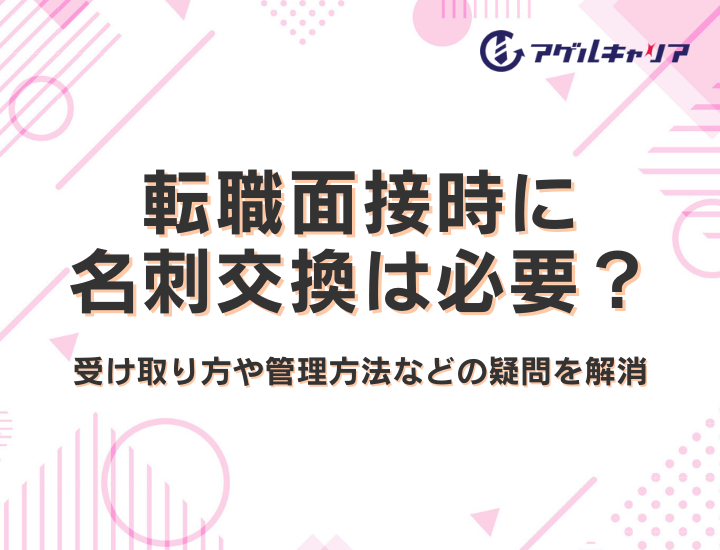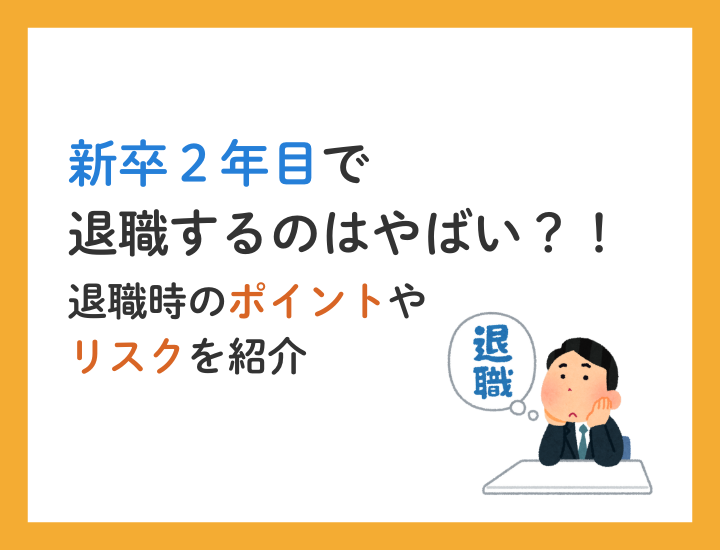
新卒2年目で退職するのはヤバい?7つの理由や3つの特徴を解説!
新卒入社して2年目は、ある程度仕事に慣れてくる時期でもあるでしょう。
働くことの楽しさを実感できたり、自分の職業に誇りを持てるようになるタイミングでもあります。
しかし、実は新卒2年目で退職を検討する人も少なくありません。
その理由は様々ですが、慣れたからゆえに良いところも悪いところも見えてくるようになり、他の会社に転職をしたい意欲が強くなってくるようです。
そこで考えることが、新卒2年目という社会人歴が浅い状態で退職をすることに、どういうリスクがあるのかということではないでしょうか。
今回の記事では、新卒2年目で退職を検討している人に向けて、退職時のリスクなどについてご紹介しています。
第二新卒として新たなスタートを切るために必要なプロセスもご紹介しているので、転職活動まで視野にいれた行動計画を立てたい方は、ぜひ参考にしてください。
新卒2年目で退職する人は10人中1人
実は新卒2年目で退職をする人は、年々増加傾向にあります。
厚生労働省が発表した新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)によると、就職後3年以内の離職率は新規高卒就職者38.4%、新規大卒就職者34.9%ということがわかりました。
このことから想定できるのが、新卒2年目で退職する人は少なくとも10人に1人以上はいるということです。
また、業種別に見てみると、宿泊業や飲食業などのサービス系業種は56%以上もの新規学卒者が3年以内に退職をしており、2人に1人は退職をしているという結果となりました。
そのほかにも、生活関連サービス業や娯楽業、医療福祉系などの業種の離職率が高いようです。
サービス系の業種は不定休かつ残業も多いことから、退職を検討する人が多いのでしょう。
現在「会社を辞めたい」と感じている人の多くは早期離職ということに後ろめたさを感じているかもしれません。
しかし、多くの人が退職という選択肢をとっていることを加味すると、さほど恥ずかしいことではないと言えるでしょう。
新卒2年目が退職したいと思う7つの理由
新卒2年目の方が退職を考えたきっかけは人それぞれですが、どの理由もポジティブなものではないようです。
具体的には、以下の7つが挙げられます。
- 収入に不満がある
- 仕事内容にミスマッチを感じる
- 人間関係が悪い
- 就業規則に不満がある
- ノルマを求められる
- 企業の将来に不安がある
- 待遇以上の仕事を要求される
- 入社前との話が変わっている
これらは一つの小さな不満から始まり、ほかに様々な理由が派生するようにして出てくるため、最終的に「辞めたい」と思うようになるのでしょう。
収入に不満がある
給与については規定があるため、入社前に把握していることが前提でしょう。
しかし、実際に入社してみると、総支給額と手取り額の差に驚き「少ない」と感じることが大半です。
初任給が25万円だとしても、そこから税金や保険料が差し引かれると20万円に満たない手取り額になります。
20万円の手取り額があれば一人暮らしができる程度ですが、近年は物価高の影響もあり、支出費用が圧迫されやすくなっています。
切り詰めて生活していると「ほかに待遇の良い会社はないかな」という気持ちが芽生え始め、転職を検討するようになるのです。
仕事内容にミスマッチを感じる
こちらも新卒あるあると言っても過言ではありませんが、入社前のイメージと実際の仕事内容にギャップを感じてしまうことです。
就活時の企業説明会や面接で聞いた話からイメージした業務と実際の仕事が異なり、ミスマッチを感じる人は少なくありません。
企業説明会や面接は、企業が学生に自社のアピールをする場なので、仕事のつらさや職場環境について多くは語りません。
キラキラしたイメージを持ってもらえるようにアピールするため、学生時代は今の会社に対してポジティブな気持ちを持っていたことでしょう。
そんな状態から実際に入社をしてミスマッチを感じると、働くモチベーションが下がり、仕事にもハリがでません。
ギャップに目をつぶって我慢しながら働いていても、強いストレスを感じる場合や疲れやすくなるので一刻も早く改善することが好ましいでしょう。
その改善策として、「転職」という選択肢が見えてくる人が大半です。
人間関係が悪い
人間関係の悩みは大小あれど、どの会社でもつきものです。
上司からチクっと言われたり、嫌味な先輩がいたりすると、一刻も早くその環境から逃れたいと感じるようになるのです。
また、最近は世の中全体がコンプライアンスを徹底している状況ですが、まだまだパワハラやセクハラ、いじめなどが問題視される会社も少なくありません。
こうした事象が発生した場合は、まず部署異動で解決できる可能性があるため相談した方が良いでしょう。
しかし、社員一人の異動は会社側でもじっくり検討する必要があることです。
その間も嫌なことが続けば耐えられず、早い段階で退職という選択肢をとる人が大半です。
もしあなたが人間関係が悪い職場で我慢しながら働いているのであれば、ストレスや疲れが大きくならないように早めに退職をするのが良いでしょう。
就業規則に不満がある
新卒2年目で退職する理由の一つが、就業規則についての不満です。
就業規則に記載されている、給料面や労働時間、休日、超過勤務手当などについて不満がある人は少なくありません。
例えば以下のようなものがあります。
・「待遇や福利厚生が悪い」
・「評価制度が曖昧」
・「超過勤務手当が付かない」
上記のような理由で就業規則に不満がある、新卒2年目の方が多い傾向にあります。
不満は社員のモチベーションを低下させる原因になり、企業側からしても損害になります。
そのため、改善を求めて上司に相談するのも良いです。
ただし、すぐに変わるものではないので、転職という選択も一つの手でしょう。
就業規則の不満は、様々な場合がありますが、いずれもストレスや慢性的な疲労感の原因になる可能性があるため注意しましょう。
新卒2年目で就業規則に不満があり、退職を考えている方は参考にしてください。
ノルマを求められる
とくに営業に配属された新卒2年目は、ノルマに苦戦して退職を検討したくなるようです。
新卒1年目の時は研修やOJT、先輩同行のもとで商談をすることが中心ですが、新卒2年目となると大抵は独り立ちします。
これまで以上に大きな売上目標が与えられるようになり、数字に追われる毎日です。
ノルマが達成できなければ叱られることもありますし、遅くまで残業を強いる会社があるのも事実です。
「アポ5件取れるまでやりきろう」
「未達分をカバーするために、提案プランを練り直そう」
このような熱意ある上司の指示も、疲れ切っている状態では聞く気にもならないでしょう。
そんな毎日に嫌気がさして、「会社を辞めたい」という気持ちが強くなってくるのです。
企業の将来に不安がある
企業の将来に不安を感じ新卒2年目で退職する方もいます。
例えば「パワハラやセクハラが常習化している」「残業代が支払われていない」といった、いわゆるブラック企業の場合や、会社の金銭事情が良くない場合です。
ブラック企業で長く務めていると、精神的にも肉体的にも消耗してしまい、体を壊す原因になります。
会社が法律違反をしている場合は、継続して働くだけで罪になる可能性があるため退職しなければなりません。
また、会社の金銭事情が厳しくなると給与やボーナスが未払いになる可能性があります。
ただ、会社の金銭事情を理由に退職する際は、企業ではなく自分の責任であると伝えるようにしましょう。
上記で説明したような状況であれば、なるべく早く退職したほうが良いでしょう。
ただし、不景気で全体的に業績が悪化している場合、転職先が見つからないケースがあります。
なので、法律違反がない会社で給与が支払われている状況であれば、退職より前に転職先を見つけましょう。
企業の将来に不安を感じている方は参考にしてください。
待遇以上の仕事を要求される
新卒2年目にもなると、これまで以上にたくさんの仕事を任せられるでしょう。
それをポジティブに考えられれば良いのですが、タスク量が多いとそんな気持ちにもなりません。
仕事に慣れてきた新卒2年目は、独り立ちをして仕事を進めることに違和感がなくなってきた時期でしょう。
しかしようやく仕事を覚えてきた段階で新たな仕事が振られると、プレッシャーを感じて会社を辞めたくなるものです。
また、一つ下の世代に仕事を教えたりすることもあるため、とても忙しくなります。
なお、このような退職理由は、マンパワーが足りていない企業によく見られます。
マンパワーが足りないゆえに利益が上がらず、社員に還元できる待遇も雀の涙程度。
さらに、数ない人数で仕事を回すために新卒2年目という新人にも重いタスクを与えざるを得ない状況でもあります。
待遇に対して業務量が多い場合や責任が大きいなどの不満があると、会社の将来に不安を感じて退職を検討するようになるようです。
入社前との話が変わっている
かなり稀ですが、いわゆるブラック企業と呼ばれる環境の会社は、入社前の説明が不足していたり、虚偽に近い伝え方をしてくることがあります。
入社前に参加した会社説明会や面接で聞いた内容と実態が異なっていた場合は、当然会社に対して不信感を覚えるものです。
例えば入社前の説明会では「残業ゼロ」「週休2日制」と伝えていても、実際はサービス残業が当たり前、自宅へ持ち帰る仕事もあり、休日出勤も免れない…などという環境の職場も存在します。
これはあなたに一切落ち度はありませんし、なるべく早く転職を考えたほうが良いでしょう。
こうした働き続けると、肉体的にも精神的にもきつくなり、最悪の場合、体調を崩してしまいます。
ストレスで体調を崩すと働く意欲さえ失われてしまい、すぐに転職するのすら困難となる可能性が高くなります。
精神的に安定している状態で転職をした方が成功しやすいので、早めの退職が得策と言えるでしょう。
新卒2年目で退職すべき人の特徴3選
新卒2年目で退職すべき人のやめる理由を解説していきます。
ただし、転職が必ず成功するわけではありません。
退職すべき人の特徴について下記で詳しく説明するので、新卒2年目で退職を考えている人は参考にしてください。
以下の順番で解説していきます。
- やりたい仕事が明確に決まっている人
- パワハラ・セクハラを受けている人
- 会社が倒産する可能性がある人
やりたい仕事が明確に決まっている人
やりたい仕事が明確に決まっている人は新卒2年目でも退職すべきです。
特に、現在の仕事となりたい職業が全く違う場合は、転職の準備を早くした方が良いでしょう。
将来のビジョンが決まっていて、現在の職業では達成できないのに、親や上司から「とりあえず3年働くべき」と言われている人もいますが、自分と合わない会社に3年勤める必要はありません。
面接の際は「〇〇の仕事をしたい」といった姿勢で受け、「新卒の段階ではなぜ分からなかったのか」という説明もできるように準備が必要です。
また、万全の状態で面接を受けに行けるよう、志望動機や自己PRでアピールしたい内容を明確に説明しましょう。
転職したい明確な理由があれば、新卒2年目で退職しても問題ありません。
むしろ、転職を考えているのに明確な理由もなく3年働く方が、マイナスのイメージに繋がる可能性があるので注意してください。
パワハラ・セクハラを受けている人
パワハラやセクハラは、言わずもがな最低な行為です。
もしあなたがパワハラやセクハラを受けている場合、新卒2年目だとしてもすぐに退職すべきです。
なお、パワハラ・セクハラは部署異動により改善できる可能性があるため、会社側としてはまず異動を提案されるでしょう。
解決できれば良いのですが、嫌な思い出が多い会社で働き続けることに違和感を感じる人が大半なため、潔く退職をするようです。
なお、パワハラやセクハラに耐えながら仕事をすると、強いストレスを感じて体力的にも精神的にも弱ってしまいます。
もしこれに該当するようなハラスメントを受けていた場合、無理をして体調を崩す前に転職をした方が良いでしょう。
会社が倒産する可能性がある人
会社の業績不振で倒産のリスクがある人も、退職を視野に入れて行動するようです。
業績が悪い会社ではリストラされる可能性があります。
リストラされた経験はキャリアに傷として残ってしまうため、自ら早めに退職をする人が多いのです。
また、倒産寸前の会社は待遇が悪く、最悪の場合給与の未払いなどが発生するリスクもあります。
とくにベンチャー企業など小さな会社の場合は、倒産前に実際に給与未払い問題が発生したこともあります。
会社の懐事情がよくないと感じたら、早めに転職をしてしまうのが得策でしょう。
新卒2年目で辞めない方がいい場合
仕事や会社に対してリスクを感じたら、自分を守るためにも会社を辞めることが正しいかもしれません。
しかし、次のような人は辞めることの方がリスクが大きいため、一度考え直した方が良いでしょう。
・不満が仕事内容だけの場合
・キャリアにおける目標や目的がない場合
浅はかな理由でリスクを考えずに退職をすると、転職時にも後悔するかもしれません。
不満が仕事内容だけの場合
単純に「仕事がつまらない」「飽きてしまった」といった理由での退職、リスクでしかありません。
転職をしてもまた同じ状況になるかもしれないためです。
新卒2年目だとある程度仕事にも慣れが出てくるため、「つまらない」と感じてしまうこともあるでしょう。
しかし、仕事の面白さは1年や2年では実感できないものです。
3年目や4年目もやり続けてある程度実績を出してこそ、達成感ややりがいを得られます。
人間関係や待遇への不満がない限りは、もう少し頑張って見てはいかがでしょうか。
時間が解決してくれることもありますし、仕事をやり続けることで新たな視点での面白さを実感できるかもしれません。
目標・目的がない人
目標や目的が決まっていない新卒2年目の方も勢いで退職してしまうのは避けましょう。
転職の面接では、面接官にマイナスの印象を与えない退職理由や明確なキャリアビジョンが求められます。
そのため、目標や目的がなく前職を辞めると転職活動が難しくなり、内定も得られません。
新卒2年目で退職すると貯金にも限界があるため、急いで転職先を探してしまい、転職を成功させられる可能性が低くなります。
退職を考えている人は、目標や目的を決めるためにもどんな仕事が自分に合っているのか自己分析をしてみましょう。
それでも退職以外の考えがないという人は、上記のようなお金の問題が起きないよう、転職先を決めてから退職してください。
リスクヘッジも行いながら退職と転職活動を進めましょう。
新卒2年目で退職しても転職を成功させる5つのポイント
新卒2年目で退職しても、第二新卒として転職することができます。
しかし第二新卒で応募をする求職者は意外にも多いため、同じ年齢層・同じレベルのライバルたちに勝つことを想定しなければなりません。
転職に成功させるためのポイントは、次の5つです。
・在職中に活動する
・自己分析を徹底的する
・過去の経験を活かせる職種を考える
・転職エージェントを活用する
・資格を取得する
上記のとおり、新卒2年目で退職しても転職を成功できる人は事前準備が完璧な状態で面接を受けています。
それぞれの項目で、転職を成功させるためのポイントについて詳しく説明するので参考にしてください。
在職中に活動する
在職中に転職活動を行えば、新しい転職先が決まった状態で退職ができるので何かと安心です。
退職してから焦って転職活動をしても、収入がない焦りを感じて企業選びにかける時間が短くなってしまいます。
とくに新卒2年目は税金が増えますし、無職の期間中の生活費もかかります。
そのため、収入が安定している退職前に転職活動を行い、退職後にすぐ転職できるよう準備する必要があります。
ただし、辞めたいと考えた理由が精神的・肉体的に影響している場合であれば、退職して一定期間失業保険をもらいながら転職活動を行っても良いでしょう。
精神的に病んでしまうと、すぐに転職活動ができなくなる場合があるため、辞めたい理由と自分の精神状態に応じて行動計画を立てると良いでしょう。
自己分析を徹底的にする
自分に合った職場環境や適職を知るために、自己分析をしておきましょう。
自分自身を見つめ直し、強みや弱み、思考性を改めて知ることで、自分に適した環境がわかるようになります。
そうすれば転職先を選ぶ際にミスマッチが防げますし、入社後にまたすぐ退職をしてしまうことも防げるでしょう。
また、転職の面接では自己PRや志望動機を聞かれますが、自己分析をしている人は有利です。
自己理解が高まれば具体的なエピソードをもとに自己PRができますし、自分の言葉で熱意ある志望動機を伝えることもできます。
前職を辞めた理由についても、自己分析をすると自分を客観視できるので答えやすくなるでしょう。
過去の経験を活かせる職種を考える
過去の経験を活かせる職種で転職活動をすると、内定がもらえる確率が上がるでしょう。
企業側からすると、経験者は即戦力を期待できるので、内定をもらえる確率が未経験者より高いためです。
また、実務経験者でなくても、スキルがあれば上記と同様に内定の確率があがるでしょう。
そのため、現在働いている企業と同じ職種で違う会社に転職する場合は、あと1年勤務してスキルを磨くのも1つの選択肢です。
1年の実務経験より2年働いている方が、企業としてはスキルが向上していると考えるため、第二新卒を狙いやすくなります。
ただし、今の会社では成長できそうにない場合は転職した方が良いので、必ず2年勤務というわけではありません。
すぐに転職するメリット、デメリットを考えてから行動するようにしてください。
転職エージェントを頼る
転職エージェントを頼るという方法も新卒2年目で転職を成功させるために良い方法です。
転職エージェントを利用すると、面接対策やキャリアプランの相談、書類添削など手厚いサポートを受けられるメリットがあります。
なお、新卒2年目の転職活動におすすめしたいエージェントは、アゲルキャリアです。
アゲルキャリアは主に第二新卒などの20代前半の求職者に人気の転職エージェントで、まさに新卒2年目で転職をしたい人におすすめ。
扱っている求人のほとんどは未経験OKの案件なので、思い切ってジョブチェンジをしたい人にもおすすめです。
レジュメ作成のサポートもしてくれますし、担当のキャリアアドバイザーとの面談は通算10時間以上でも一切費用はかかりません。
登録して損はないと言えるサービス内容なので、ぜひ覗いてみてください。
資格を取得する
新卒2年目の方は転職を成功させるために資格を取得しましょう。
転職活動をする際、仕事に活かせる資格を取得しておくと、内定をもらえる確率があがります。
なぜなら、企業が求める人材は即戦力になる人ほど、教える時間を省けるからです。
例えば、事務系の仕事に転職を考えている人は、以下のような資格があります。
・マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS)
・簿記
・ITパスポート
自分が転職しようとしている業界で、必要な資格を取得してから応募すると、アピールをしやすくなるでしょう。
現在勤めている企業を退職する前に、資格を取得できるのがベストです。
新卒2年目で転職を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
新卒2年目で退職するときに気を付けるべき3つのポイント
退職する際のポイントを3つ解説していきます。
退職するときには、計画的な行動が求められます。
それぞれのポイントについて詳しく説明するので、新卒2年目で退職を考えている人は参考にしてください。
以下の順番で解説していきます。
- 退職後の進路を明確に決める
- 長続きしないと思われる可能性がある
- 自己分析をしないと同じ状況にな
退職後の進路を明確に決める
新卒2年目で退職する人は、これからのキャリアを失敗させないようにキャリアプランを決めておきましょう。
転職を繰り返してしまう人の多くは、明確なキャリアプランを持っていません。
理想とするキャリアがなければ「何となく」で仕事を選んでしまうため、曖昧な理由で退職と転職を繰り返してしまうのです。
まずは自分の将来の理想像を思い描いてみて、逆算するように各年齢で何をすべきかの小さな目標を立てましょう。
そしてそのために今何をすべきかを考えるのです。
もし退職後の進路が決められない方は、転職エージェントに相談してみましょう。
エージェントに相談すると、プロの観点からキャリアプランを立てるヒントを得ることができます。
自分のスキルや市場価値について知ることで、理想と現実とのギャップがわかり、これからどういう行動を取れば理想に近づけるかが見えてきます。
早期離職に対する印象がよくないことは念頭に置こう
新卒2年目で退職することには、いくつかのリスクが伴います。
まず、転職活動において「短期間で辞めた」という経歴がマイナスに働く可能性があります。
採用担当者から「すぐに辞めてしまうのではないか」「忍耐力が足りないのではないか」と懸念されることがあり、次の就職先が見つかりにくくなることもあります。
特に、同じ業界や大手企業への転職はハードルが上がる傾向にあります。
また、周囲からの印象も気になるポイントです。
家族や友人、元職場の同僚から「せっかく入社したのにもう辞めるの?」と否定的な意見を持たれることもあります。
特に、同世代がまだ同じ会社で働いている中での退職は、将来への不安を感じやすくなるかもしれません。
さらに、キャリアの面でも注意が必要です。
社会人経験が浅いため、次の仕事で即戦力として活躍できるスキルが十分に身についていない可能性があります。
そのため、転職する際は「なぜ辞めるのか」「次の職場で何をしたいのか」を明確にし、計画的に行動することが大切です。
退職理由を明確にしないと同じ状況になる
退職理由が何であれ、本質的な理由を明確にしておきましょう。
本当に退職する必要があったのかを突き詰めて考えなければ、転職をしてもまた同じ理由で簡単に退職してしまうかもしれません。
今の仕事を辞めることで何が得られるのか、人生において必要なプロセスなのかを言語化できるまでにしておかなければ、キャリアプランまで崩れてしまうでしょう。
まとめ
新卒2年目で退職をしても、第二新卒として転職をすることができます。
しかし、新卒2年目の早期離職者は意外にも多いため、転職活動に向けて事前準備と計画的な行動設計が必要となります。
明確な退職理由とキャリアプランをまとめておくことは前提として、二度と失敗しないように会社選びをしましょう。
相性の良い会社と出会うためには、自己分析が必須です。
さらに、転職エージェントを活用してプロの観点からあなたにぴったりの会社を紹介してもらいましょう。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!