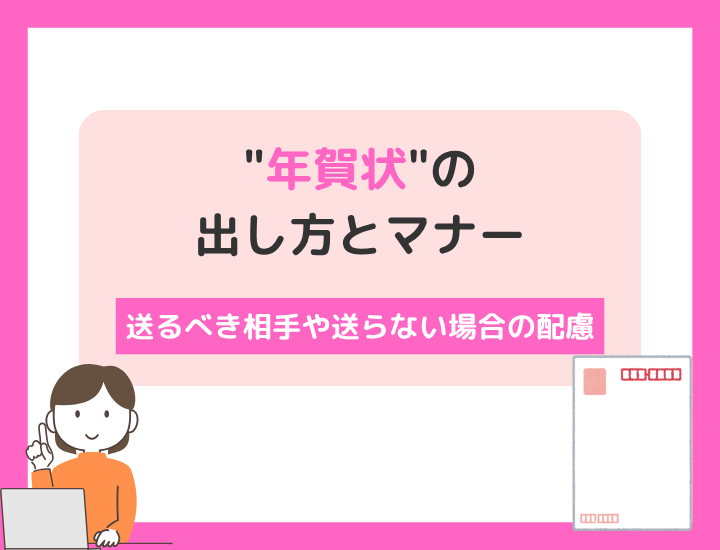
【例文つき】ビジネス年賀状の出し方とマナー|送るべき相手や送らない場合の配慮
はじめに
取引先や上司などとの関係性を保つ手段として、年賀状は長く活用されてきました。
紙の年賀状を取り巻く環境は近年変化しており、ビジネスにおいても送付の是非を悩む人が増えています。
年賀状の慣習が薄れつつある一方で、配慮を欠いた対応は信頼の低下を招く要因となり得ます。
誤解や失礼を避けるには、年賀状の意味や送るべき相手、送らない場合の伝え方を正しく理解することが重要です。
送付の可否は個人や企業の方針によって異なりますが、相手の立場や状況を考慮した対応こそが、信頼を積み重ねる土台となります。
この記事では、年賀状を出すか迷った際の判断軸からマナー、具体的な文例に至るまで、実務に役立つ情報を体系的に解説していきます。
ビジネス年賀状は出すべきか
ビジネス上の年賀状に迷いを感じる場合は、意味や背景、影響について理解を深めることが大切です。
以下では、ビジネス年賀状の役割や送らない理由、印象への影響や関係性への効果、そして判断基準について説明します。
ビジネス年賀状の本来の意味と役割
年賀状は、新年の挨拶を通じて感謝と信頼の気持ちを伝える文化として根付いてきました。
明治時代に郵便制度が整備されて以降、直接会えない相手への挨拶手段として一般化し、社会全体で定着した背景があります。
ビジネスの場面では、礼儀や誠意を示す手段として年賀状が活用されており、日頃顔を合わせる機会が少ない相手にも、自社の姿勢や思いを伝えられます。
印刷された文面に加えて短い手書きの一言を添えることで、受け取った相手に温かさや誠意が伝わるでしょう。
年始の節目に丁寧な挨拶を行うことで関係維持の意思が明確になり、相手に良い印象を残せます。
出さない企業・人が増えている背景
年賀状の送付を控える企業や個人が増加している背景には、社会全体の価値観や業務環境の変化があります。
ペーパーレス化の推進によって紙媒体の使用を見直す動きが広まり、年末の多忙な時期に作業負担を減らす目的も関係しています。
経費削減や業務効率化が求められる中で、年賀状の印刷や郵送にかかる費用や時間を省略する方針が選ばれるようになりました。
また、心のこもっていない挨拶をやめる「虚礼廃止」の考え方が浸透したことも影響しています。
郵便料金の引き上げも負担のひとつとなっており、年賀状文化の継続を難しく感じる企業が増えているのが現状です。
出さない場合に考えられる印象の変化
以前まで年賀状をやり取りしていた関係先に対して急に送付をやめた場合、相手に不信感や違和感を与える可能性があります。
取引先によっては、年賀状の有無を関係性のバロメーターと捉えることもあり「関係が終わったのかもしれない」「礼儀を欠いているのではないか」といった印象を持たれるかもしれません。
ビジネスにおいては、細かな対応が信頼関係に直結するため、挨拶の省略が予期せぬ誤解を招くことがあります。
年賀状を送らないと決めたのであれば事前に先方へ伝えておくことで、相手との関係を良好に保てるでしょう。
関係維持・強化における年賀状の効果
年賀状は、相手とのつながりを改めて意識させる年始の挨拶として有効です。
印刷された文面に加えて、手書きで一言添えることにより、温かみのある対応が相手の印象に残ります。
メールなどのデジタル手段では伝わりにくい誠実さや感謝の気持ちを、紙面を通じて届けられる点が特徴です。
年に一度の機会であるため、日常の業務では伝えられない思いを形にして届けられます。
取引先や顧客との関係をより良好に保ちたいと考える場合、年賀状はきっかけづくりとしても非常に効果的な手段です。
年賀状を出すか迷った際の判断基準
年賀状の送付を検討する際は、相手との関係性や社内の方針を踏まえて判断する必要があります。
以下に、判断の目安となる代表的な基準をまとめました。
| 判断項目 | 内容 |
|---|---|
| 社内の方針 | 所属している企業や部署で年賀状を出すかどうか |
| 相手の傾向 | 取引先が年賀状を重視している企業文化かどうか |
| 過去の履歴 | 以前の年に年賀状のやり取りがあったかどうか |
| 関係の深さ | 単発ではなく今後も継続する可能性が高いかどうか |
| 業界の慣習 | 礼儀や儀礼が重要視される業界に属しているかどうか |
年賀状を出すか迷った場合は、上司や同僚に相談し、状況に即した対応を決めることが望ましいでしょう。
送る・送らないの判断には、相手に与える印象の影響も含めた丁寧な配慮が求められます。
ビジネス年賀状を出すべき相手
年賀状を送付する相手を選定する際は、業務上のつながりの深さや今後の関係性を踏まえて判断することが大切です。
形式的な礼儀ではなく、実際のやり取りや信頼構築の必要性を基準に送付先を見極めることが求められます。
| 出すべき相手 | 詳細 |
|---|---|
| 取引先企業(法人宛) |
|
| 担当者個人(名指し宛) |
|
| 社内の上司・先輩 |
|
| 顧客・利用者 |
|
業務の頻度や関係性の強さに応じて送付先を選定することで、ビジネス年賀状が信頼関係を支える手段として機能します。
ビジネス年賀状の基本マナー5選
ビジネス年賀状では、見た目や言葉遣いだけでなく、相手への敬意を示すマナーを守ることが不可欠です。
以下では、送付時に必ず押さえておくべき5つの重要な基本マナーを順に紹介します。
宛名は肩書きや氏名を正確に記載する
宛名の記載は年賀状全体の印象を左右するため、形式や敬称を丁寧に確認する必要があります。
住所は都道府県から省略せず、丁目や番地まで正確に記載しましょう。
数字には漢数字を使い、縦書きの場合は特に読みやすさにも配慮が求められます。
企業名は「株式会社」などを略さず正式名称を使用し、部署や役職も正しく記載するのが礼儀です。
個人宛には「様」、会社や部署宛には「御中」を用い、両方を併用することは避ける必要があります。
また、役職を敬称のように扱わないよう注意し、「部長様」ではなく「部長 氏名 様」と分けて記載するのが適切です。
異動などで部署や肩書きが変更されている可能性もあるため、最新情報を事前に確認しておくことが大切です。
賀詞は相手や立場に合わせて使い分ける
賀詞にはさまざまな形式があり、相手の立場に応じて適切に選ぶ必要があります。
1〜2文字の賀詞(「寿」「賀正」「迎春」など)は略式に該当し、目上の人物やビジネスの相手に対しては避けるのが基本です。
ビジネス年賀状では「謹賀新年」「恭賀新年」「謹賀新春」など四文字の賀詞が一般的であり、丁寧な表現として好まれます。
文章形式の賀詞も使いやすく「謹んで新春のお慶びを申し上げます」や「新年おめでとうございます」などが該当します。
賀詞を選ぶ際には、二重表現にならないよう注意が必要です。
すでに賀詞が印刷されているはがきに、あらためて挨拶文を加えると意味が重複してしまうことがあるため、文面全体のバランスを考慮して記載しましょう。
忌み言葉や句読点は使用しない
年賀状は慶事に関する挨拶であるため、縁起が悪い言葉や句読点の使用は控えるのがマナーです。
以下、不吉な印象を与える言葉は避ける必要があります。
- 去る
- 枯れる
- 終わる
- 失う
- 病む
特に「去年」は「去る年」と読まれることから不適切とされ、「昨年」または「旧年」に置き換えるのが適切です。
文章中に「。」や「、」といった句読点を使用しないのも重要な慣習です。
「区切り」や「終わり」といった意味合いを連想させることが理由として挙げられます。
読みやすさに不安を感じる場合でも、改行や文の流れを工夫することで、句読点を使わずに整った文面を作成できます。
元旦に届くように投函日を逆算する
ビジネス年賀状は、元旦に確実に届くよう計画的に準備することが求められます。
郵便局では12月15日から年賀はがきの受け付けを開始し、12月25日までに投函すれば元旦配達が保証されます。
年末は業務が立て込みやすいため、11月中から文面作成や宛名確認を進めておくと安心です。
もし25日を過ぎてしまった場合は、遅くとも松の内(関東では1月7日、関西では1月15日)に届くよう急いで手配しましょう。
また、文中に「元旦」と記載している場合は、1月1日に届かないと不適切な印象を与えるため、遅れが想定される場合は「一月」や「正月」と書き直すことが大切です。
日付の表現ひとつで信頼度が変わる可能性もあるため、細かな調整が重要になります。
書き損じや訂正は新しいはがきで対応する
ビジネス年賀状では、丁寧さが何よりも重視されます。
記載ミスがあった際は、修正テープや二重線での訂正は行わず、新しいはがきに書き直すことが必須です。
一文字の誤字であっても、修正済みの状態で送付するのは失礼にあたります。
書き損じた年賀はがきは郵便局で新しいはがきや切手と交換することが可能であり、一定の手数料を支払えば再利用ができます。
また、筆記具の選び方にも配慮が必要です。
薄い色や赤、グレーなどは弔事を連想させるため避けるべきです。
はっきりとした黒のインクを使い、読みやすい文字で記載するように心がけましょう。
年始の丁寧な挨拶を届けるためには、細部に至るまで気配りが必要です。
ビジネス年賀状での印象をより良くする5つの方法
ビジネス年賀状においては、基本マナーに加えて印象を良くする工夫が重要です。
手間を惜しまず心のこもった一言を添えることで、受け取る側の印象が格段に向上します。
以下では、印象アップに効果的な5つの具体的な工夫について紹介します。
感謝を具体的に伝える文章を添える
ビジネス年賀状では、前年の支援や協力に対する感謝の気持ちを明確に言葉で表すことが大切です。
定型文に加えて、具体的なエピソードや助けられた場面を一文添えると、相手に誠意が伝わりやすくなります。
例えば、業務上で支えてもらったプロジェクトや印象に残ったやりとりに軽く触れるだけでも十分効果があります。
心のこもった感謝の表現は、読み手に対して丁寧な印象を与え、関係性をより良好なものにするきっかけになるでしょう。
短文でも感謝の気持ちが伝わるよう、ありきたりではない言葉選びが重要です。
忙しい時期であっても、文章に少し工夫を加えるだけで印象が大きく変わります。
新年の抱負や目標を短く盛り込む
自分自身の目標や成長への意気込みを簡潔に記載すると、前向きな印象を相手に与えられます。
目標は抽象的なものではなく、業務に関係する内容や自身の立場に即したものを選ぶと効果的です。
あくまで主役は受け取る相手であるため、自己主張が強くならないよう表現には注意が必要です。
「新しい役割に挑戦してまいります」や「〇〇の分野で貢献を目指します」など、前向きな一言を含めることで、読後感の良い年賀状に仕上がります。
新年のスタートにふさわしい前向きな言葉は、受け取った相手にも好影響を与えることがあります。
相手の活動や業績を労う言葉を入れる
年賀状に相手の取り組みや成果をねぎらう言葉を加えることで、より丁寧な印象を与えられます。
一方的な感謝ではなく、相手の努力にも目を向けているという姿勢が伝わると、信頼関係を深めることにもつながります。
以下は、労いの言葉として活用しやすい表現の例です。
- 昨年の貴社のご活躍には深く感銘を受けました
- 多忙な中でもご対応いただき心より感謝しております
- 御社の事業成長に敬意を表し、今後の発展を期待しております
- 貴重なお力添えに対し、深く御礼申し上げます
活動や業績への共感が感じられる一文を加えることで、形式的な印象を和らげられます。
干支や季節感のある表現を活用する
文章に季節や干支を意識した表現を盛り込むと、年賀状全体の印象が華やかになります。
干支の話題は親しみやすく、自然な話題提供にもなりますが、派手になりすぎないように控えめな表現を選ぶことがポイントです。
干支に直接言及しなくても、新年の訪れを感じさせる表現を使うことで、相手に季節感を伝えられます。
「穏やかで健やかな年を迎えられたことと拝察いたします」や「寒さ厳しき折 くれぐれもご自愛ください」などが有効です。
年の始まりという特別なタイミングにふさわしい表現を盛り込むことで、形式だけにとどまらない内容へと昇華させられるでしょう。
汎用性の高い定型フレーズを準備する
多くの宛先に年賀状を送る場合、定型の挨拶文を複数用意しておくと効率的に作成できます。
ビジネス年賀状では、敬語表現や丁寧語を適切に使用したフレーズが求められます。
使い回しが利く表現でも、冒頭の挨拶や締めくくりを工夫することで、画一的な印象を避けられるでしょう。
複数のパターンを事前に準備しておくことで、相手ごとに使い分けがしやすくなり、文面のバリエーションを保てます。
社内のチームで、テンプレートを共有しておくのも有効な手段です。
準備された定型文をベースに一言加えるだけで、手間を減らしつつ丁寧な印象を与えられます。
【宛先別】ビジネス年賀状の例文集
ビジネス年賀状では、宛先の立場や関係性に応じて文面を工夫することが大切です。
形式だけに頼らず、相手とのやりとりを踏まえた表現を用いることで、丁寧かつ印象の良い年賀状になります。
以下で、宛先別に使える例文を紹介します。
新規取引先宛
本年も御社の発展に貢献できますよう 一層の努力を重ねてまいる所存です
今後とも末永いご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
貴社のますますのご繁栄と皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます
令和七年 元旦
新たな関係構築を意識し、丁寧な表現を中心に構成している例文です。
感謝と今後の協力を求める姿勢をはっきりと伝えることで、信頼感を高められます。
定型を基本としながらも、協業への意欲を文中に反映する点がポイントです。
担当者個人宛
本年も引き続きお力添えを賜れますようお願い申し上げます
貴職のますますのご活躍とご健康を心よりお祈りいたします
令和七年 元旦
個人宛の年賀状では、感謝の気持ちを具体的に表現することが大切です。
組織としてだけでなく、個人への配慮が伝わるように言葉を選びましょう。
少し砕けた表現を交えると、より親近感のある内容になります。
上司や先輩宛
本年はさらに成果を挙げられるよう 精進を重ねてまいります
至らぬ点も多いかと存じますが ご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます
本年もどうぞよろしくお願いいたします
令和七年 元旦
社内の上司や先輩への年賀状では、日頃の指導への感謝と新年の意気込みを伝える構成が基本です。
過度に砕けた表現は避け、謙虚な姿勢と誠実な意欲を示しましょう。
ビジネス年賀状出し忘れ時のフォロー用例文
年賀状を出し忘れてしまっても、適切なフォロー文を送ることで丁寧な印象を与えられます。
謹んで初春のお慶びを申し上げます
ご丁寧な年賀状をいただき誠にありがとうございました
年末年始の慌ただしさの中ご挨拶が遅れましたこと
心よりお詫び申し上げます
旧年中はひとかたならぬご厚情を賜り厚く御礼申し上げます
本年も変わらぬご交誼のほど 何卒よろしくお願い申し上げます
令和七年 一月
ご丁寧な年賀状をいただき誠にありがとうございました
新年のご挨拶が遅れましたことを心よりお詫び申し上げます
旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます
今後とも変わらぬご指導を賜りますようお願い申し上げます
本年が貴社にとりまして実り多き一年となりますようお祈り申し上げます
フォロー文を書く際には、まず相手からの年賀状に対する感謝の言葉を述べることが基本です。
そのうえで、返信が遅れてしまった理由を簡潔に伝え、失礼があったことをお詫びします。
1月7日までは通常の年賀状形式で返信が可能ですが、過ぎた場合には「寒中見舞い」に切り替えるのが礼儀にかなった対応です。
文面中に「元旦」と記載するのは、1月1日に届くことを前提としているため、返信の際には「一月」や「正月」という表現を用いるようにします。
また、形式だけで済ませず、なるべく紙のはがきで返すことで、相手に対する敬意を示せるでしょう。
ビジネス年賀状におけるデザインの選び方
ビジネス年賀状においては、文面だけでなくデザインの選定も受け手に与える印象を左右します。
以下では、年賀状を受け取った相手に信頼と誠意が伝わるデザイン選びのポイントを、5つの視点から紹介します。
ビジネス向けにふさわしい落ち着いた配色を選ぶ
色味の印象は、年賀状全体の雰囲気を大きく左右する要素です。
ビジネスで使用する年賀状においては、原色やネオンカラーなど目立つ色合いは避け、以下の控えめで重厚感のある色が好まれます。
- 紺
- 深緑
- 墨
- えんじ色
筆文字や和柄との相性が良い配色を選ぶと、年賀状全体に品格が生まれます。
また、個人宛てであっても、家庭の中で家族が目にする可能性があるため、カジュアルすぎる印象のものは避けた方が無難です。
彩度を抑えた寒色や金箔風のワンポイントなど、上品な装飾があるデザインを選ぶことで、節度を保ちつつ新年の華やかさも表現できます。
企業イメージに沿ったデザインに統一する
組織として年賀状を出す場合は、各担当者による自由なデザインではなく、企業全体で一貫性を持たせることが望まれます。
社内で統一されたテンプレートや色味、ロゴの配置を定めることで、ブランドとしての信頼感や誠実な姿勢が伝わります。
| 企業イメージの傾向 | 推奨されるデザイン例 |
|---|---|
| 高級感・信頼重視 | 筆文字+和紙調背景+金・銀のアクセント |
| 親しみやすさ重視 | 干支モチーフ+柔らかい水彩タッチ+余白を活かしたレイアウト |
| スタイリッシュ系 | モノトーン+シンプル構成+ロゴをワンポイントで配置 |
| 伝統重視企業 | 梅・松竹梅・鶴亀などの和風図案+落ち着いた和色系統 |
企業の方針やブランドカラーを意識しながら選定することで、相手に一貫した印象を与えられます。
読みやすいフォントとレイアウトを採用する
文字の視認性と全体の配置バランスは、ビジネス年賀状の印象を左右する要素です。
華やかすぎるデザインフォントや極端に小さい文字は、読みづらくなる原因となります。
明朝体や楷書体などの伝統的な書体を選び、文面に応じて適切な文字サイズを設定することが大切です。
また、行間や余白を十分に確保し、窮屈な印象を与えないよう工夫する必要があります。
メッセージの強調部分を太字にするなど、視線の誘導を意識した配置を整えると読みやすさが向上します。
内容の良さが伝わらない原因の多くは視認性にあるため、フォントやレイアウトは最後まで丁寧に調整しましょう。
干支モチーフを効果的に取り入れる
年賀状では、干支のモチーフを取り入れることで季節感と年始の華やかさを演出できます。
ただし、ビジネス用途では装飾が過剰になると軽い印象を与えるため、控えめに配置することが望ましいでしょう。
- 背景に薄く干支のシルエットを入れる
- 文面の下部に小さくワンポイントとして配置
上記を参考に、主張しすぎない形で取り入れるとバランスが取れます。
キャラクター化された干支ではなく、水墨画風や筆絵調のイラストを選ぶことで、落ち着いた印象を与えられます。
ロゴや社名を自然に組み込む
企業としての年賀状であることを示すには、ロゴや社名を適切に配置する必要があります。
ただし、宣伝的な要素が強くなると年賀状本来の目的が薄れてしまうため、控えめな位置で視認性を保ちましょう。
はがきの左下や裏面のフッター部分などに配置すると、目立ちすぎずに自然な形で企業情報を伝えることが可能です。
また、社名は略称ではなく正式名称を用いることで丁寧な印象につながります。
写真や家族向けの私的な要素はビジネスシーンにふさわしくないため、掲載は避けましょう。
年賀状を送らない場合のビジネスマナー
年賀状を廃止する動きが広がる中で、送付をやめる場合でも相手に対する敬意や説明が欠かせません。
一方的に「送らない」ことを選択すると誤解を生みやすいため、意図を明確に伝え、代替手段を整えるべきです。
以下では、年賀状を送らない際に守るべきマナーについて5つの視点から紹介します。
送らない理由と背景を明確に説明する
年賀状の送付をやめる場合は、理由をはっきりと伝えることが重要です。
「経費削減」や「ペーパーレス推進」といった経営上の方針や、形骸化した儀礼や習慣をやめる「虚礼廃止」の企業文化に基づく判断であると説明することで、相手に不要な不信感を与えずに済むでしょう。
理由が不明瞭なまま年賀状が途絶えると、関係性の変化や感情的な切り離しと受け取られる可能性があるため、丁寧な文面を通じて廃止の背景を正確に共有してください。
特に、継続的な取引がある相手に対しては、一言の説明が今後の信頼関係に大きく影響します。
「送らない」旨の連絡は前もって行う
年賀状を送らないと決めた場合は、年末より前に相手へ連絡することが理想的です。
直前になって伝えた場合や、年明けに通知を送った場合は、対応が遅れた印象を与えるおそれがあります。
12月上旬までに「本年より年賀状の送付を控えさせていただきます」といった内容を含んだ手紙やメールを届けることで、相手も心構えができ、形式上のすれ違いが起こりにくくなります。
連絡の方法は紙の挨拶状またはビジネスメールが適していますが、どちらの場合でも、事務的な印象にならないよう丁寧な文章構成を意識しましょう。
送らないことに関する適切な案内文を用意する
送付中止の理由を相手に伝える際は、事前に整った案内文を用意しておくことが効果的です。
文面には時候の挨拶に続いて、年賀状を控える理由、今後も変わらぬ関係を望んでいること、そして相手の繁栄を祈る言葉を含めると礼節が感じられる印象になります。
案内文に含めるべき要素は、以下のとおりです。
- 時候の挨拶(例:師走の候、歳末の候など)
- 旧年中のお礼
- 年賀状廃止の理由(例:虚礼廃止・環境配慮・業務効率化など)
- 今後の関係維持への配慮
- 相手の健康や繁栄を祈る結びの言葉
あらかじめテンプレートを準備し、相手や用途に応じて微調整できる形にしておくと便利です。
代替手段としてメールやSNSを提案する
紙の年賀状に代わる手段として、メールやSNSなどのデジタル挨拶が検討されることもあります。
ただし、すべての相手が受け入れるとは限らないため、移行時には丁寧な配慮が必要です。
例えば、初年度は年賀状とメールの両方を送り、次年度からデジタルのみとする段階的な切り替えが効果的です。
電子媒体を使用する際も、テンプレートだけではなく個別の一言を添えることで、機械的な印象を回避できます。
年賀状を送らなくても関係を維持できるよう工夫する
年賀状の送付をやめることで、年始の挨拶の機会が失われることになります。
そのため、他の場面で感謝の気持ちや信頼の表明を行うことが重要です。
年度末の挨拶や、商談後のフォローアップで個別メッセージを送ることで、関係維持が可能になります。
また、社内報・メールマガジン・オンラインイベントなどを活用することも、企業としての誠実な姿勢を伝える方法としておすすめです。
形式に縛られず、継続的な対話の場を工夫することが、年賀状に頼らない信頼構築のポイントです。
まとめ
ビジネスの現場における年賀状は、単なる形式ではなく関係性を築く手段としての役割を果たします。
送付する場合には、相手との関係性を意識した文面やデザインを整えることが信頼感につながります。
一方、送らない判断をする場合にも、理由の説明や代替手段の提示によって丁寧な対応が可能です。
年賀状という伝統的な慣習を通じて、自社の姿勢や誠意を伝える機会として活用することが求められます。
文面・タイミング・表現の工夫次第で、印象は大きく変化します。
ビジネスにおける円滑な人間関係の構築を目的として、年始の挨拶を慎重に設計することが大切です。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!




