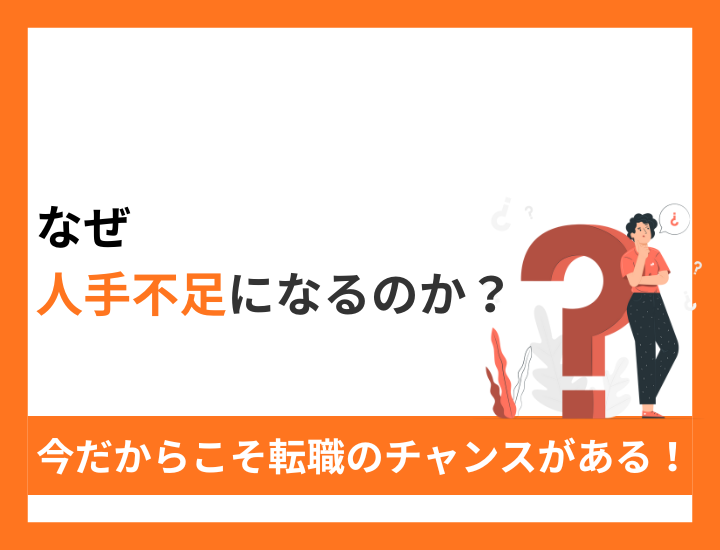
なぜ人手不足になるのか|今だからこそ転職のチャンスがある!
はじめに
近年、日本では多くの業界で「人手不足」が深刻な課題となっています。
求人情報を見れば募集件数は増加していますが、実際には採用がうまく進まず、企業も求職者も悩みを抱える状況です。
その背景には、人口減少や高齢化といった社会構造の変化だけでなく、働き方や価値観の多様化、雇用のミスマッチなど複数の要因があります。
この記事では、日本の人手不足がなぜ起きているのか、その原因や影響をデータや事例を交えて解説し、さらに人材不足が顕著な業界や転職のチャンスについても紹介します。
日本の人手不足の原因
日本の人手不足は、単なる採用難ではなく社会全体の構造変化から生じています。
少子高齢化による労働人口の減少や非正規雇用の増加、働き方に対する価値観の変化など、複数の要因が重なり合っているのが現状です。
さらに、企業と求職者のスキルのミスマッチや優秀な人材の海外流出も課題です。
ここでは、その背景を解説します。
高齢化社会と人口減少
日本の人口は2010年をピークに減少局面へ入り、総務省統計局の将来人口推計でもこの傾向は続くと予測されています。
特に生産年齢人口(15〜64歳)は1995年の約8,700万人を境に減少に転じ、2023年では約7,400万人、2055年には5,300万人台まで減る見込みです。
これは総人口の減少だけでなく、高齢化の進行が大きな要因です。
65歳以上の高齢者割合は1980年の約9%から2023年には30%前後に達するとされ、労働力人口のバランスが大きく崩れています。
労働力を担う世代が急速に減少する一方で、介護や医療など高齢化社会に必要な分野の需要は拡大しており、結果として多くの業界で人手不足が進行しているのです。
非正規雇用の増加
厚生労働省の調査によると、非正規雇用者は長期的に増加傾向にあり、2024年には雇用者全体の約37%を占めています。
特に女性や高齢者の割合が高く、女性では約半数が非正規として働き、高齢者では定年後の就業手段として選ばれることが多いのが特徴です。
非正規雇用は柔軟な働き方を可能にする一方で、賃金水準や雇用の安定性に課題があります。
そのため、長期的なキャリア形成が難しく、結果として人材の定着につながりにくいのが現状です。
企業側もコスト削減を目的に非正規雇用を拡大してきましたが、その副作用として必要な人員を確保し続けることが難しくなり、人手不足の深刻化を招いています。
人材のミスマッチ
現在の日本では「求人はあるのに採用できない」企業と、「仕事を探しても希望条件に合わない」求職者がいます。
厚生労働省の統計でも有効求人倍率は高水準を保っていますが、実際の採用率は必ずしも比例していません。
背景には、企業が求める専門スキルや経験に対し、求職者が十分に応えられないというスキルギャップがあります。
特にITや専門技術職など成長分野では人材不足が顕著で、一方で単純労働や非正規の求人が過剰に募集されるケースも見られます。
このように需要と供給のアンバランスが続くことで、労働市場の「ミスマッチ」が拡大し、結果として人手不足が解消されにくい状況となっているのです。
仕事に対する価値観の変化
近年、特に若い世代を中心に「仕事に対する価値観」が大きく変化しています。
かつては長時間働いてでも安定した収入や昇進を目指すことが一般的でしたが、今ではワークライフバランスやライフスタイルの充実を重視する傾向が強まっています。
プライベートの時間を確保しやすい勤務体系や、柔軟な働き方を実現できるリモートワーク、フレックスタイム制度を希望する若者も増加。
また、給与や待遇だけでなく「人間関係の良さ」や「働きやすい職場環境」といった要素を就職先選びの基準とするケースも多いのが特徴です。
こうした価値観の変化は、企業の人材確保に影響を及ぼしていると言えるでしょう。
待遇面が整っていても労働時間が長い、上司との関係がストレス要因になるといった職場では、若手が定着せず離職が相次ぎ、人手不足が一層深刻化します。
逆に、柔軟な働き方や社員の声を取り入れる企業は、若手からの支持を得やすく、採用の強みにつながります。
このように、労働環境の見直しは人手不足対策として欠かせない要素となっているのです。
労働者の海外流出
海外在留邦人数調査統計の統計によれば、長期滞在者や永住者の数は年々増加しており、2024年で海外在留邦人は約130万人を超えています。
特にアジアや欧米諸国への移住が増えており、現地で高収入やキャリアアップを実現する人が少なくありません。
この動きの背景には、日本国内の労働環境や賃金水準に対する不満があると考えられています。
長時間労働や昇給機会の少なさに比べ、海外では実力や成果を重視する制度が整っていることから、若手人材が魅力を感じて移住を決断するケースが増加。
こうした流れは、日本企業にとって優秀な人材を確保する上で大きな障害となっています。
特に技術職や専門分野の人材が海外に流出すれば、国内の人手不足をさらに深刻化させる要因となり、将来的には国際競争力の低下にもつながっているのが現状です。
参照:海外在留邦人数調査統計
人手不足と人材不足の違い
「人手不足」と「人材不足」という言葉はしばしば混同されますが、意味が異なり、それぞれが抱える課題も大きく違います。
「人手不足」とは、業務を遂行するための労働力そのものが不足している状態を指します。
特定のスキルや資格の有無にかかわらず、単純に働く人数が足りないために現場が回らなくなるケースです。
典型的なのは介護や建設、運輸、宿泊業などで、募集をかけても応募が集まらず、既存の従業員に負担が集中する結果、長時間労働や離職につながる悪循環が発生しています。
一方「人材不足」は、人数はある程度確保されていても、企業が求めるスキルや知識、経験を持つ「適切な人材」が不足している状態を意味します。
特にITエンジニアや医療従事者のように専門性が高い職種では顕著で、求人を出しても条件に合う応募者が現れず、採用が長期化するケースが少なくありません。
結果として、プロジェクトの遅延やサービスの質低下といった影響が生じます。
つまり、人手不足は「量的な問題=人数不足」、人材不足は「質的な問題=スキル不足」の違いです。
人手不足が企業に及ぼす影響
人手不足は単に採用活動が難しくなるだけでなく、企業の経営や事業運営に深刻な影響を及ぼします。
特に中小企業や地方の事業者では、必要な人材を確保できないことが経営課題となっており、現場の負担増や生産性の低下を招いています。
また、従業員の離職率が高まることで人員がさらに不足し、悪循環に陥るケースも少なくありません。
人手不足が長期化すれば、最終的には事業の縮小や倒産リスクへとつながる可能性もあります。
ここからは、人手不足がどのような影響を企業にもたらすのかを解説します。
中小企業・地方への影響が大きい
人手不足は大企業よりも中小企業や地方に大きく影響しています。
特に地方では、若年層が都市部へ流出する傾向が続いており、地域に根ざした企業が慢性的な労働力不足に直面しています。
人材が確保できないことで、業務の効率低下や新規事業への取り組みが難しくなり、競争力の低下にもつながります。
また、人手不足を補うために一人当たりの業務量が増加し、従業員の負担が重くなる結果、離職や採用難がさらに加速する悪循環も見られます。
特に人口減少が著しい地域では、事業そのものを継続できなくなるケースも増えており、地方経済全体への影響が懸念されています。
従業員の離職率が上がる
先でも解説しましたが、人手不足が続くと、一人ひとりの従業員にかかる負担は必然的に大きくなります。
現場では長時間労働や休日出勤が常態化し、体力的・精神的な疲労が蓄積されやすくなります。
その結果、モチベーションの低下や職場への不満が高まり、最終的に離職へとつながる可能性も。
特に若年層や中堅層は転職市場の活発化も背景に「より良い環境で働きたい」と考えやすく、条件の良い企業へ流出する傾向が強まっています。
逆に、高齢の従業員が無理をして働き続けざるを得ない状況も多く見られ、これが労働災害や健康問題のリスクを高めています。
従業員の離職が進むと、残された社員にさらなる負担がかかり、人手不足が一層深刻化する「悪循環」に陥ります。
結果として、組織全体の生産性や士気が低下し、企業の存続にも影響を及ぼしかねません。
事業縮小や倒産につながる
人手不足が長期化すると、企業は必要な業務をこなせなくなり、生産性が大きく低下します。
特に製造業やサービス業では、人員不足が原因で納期遅延やサービス品質の低下が発生し、顧客離れを招くリスクが高まります。
新規案件を受ける余裕がなくなることで、売上の拡大どころか現状維持すら難しくなり、最終的に事業規模の縮小を余儀なくされる企業も少なくありません。
さらに深刻なのは倒産リスクの増大です。
帝国データバンクの調査でも「人手不足倒産」は近年増加傾向にあり、2024年には過去最多の350件に達しました。
特に地方や中小企業では代替要員の確保が困難なため、一人の退職が経営に直結することもあります。
このように、人手不足は単なる労働力の問題にとどまらず、企業の存続や地域経済全体に大きな影響を及ぼす深刻な課題となっているのです。
転職のチャンス?人材不足の業界ランキング
人手不足は企業にとって深刻な課題である一方で、求職者にとっては大きなチャンスともなります。
特に慢性的に人材が不足している業界では、積極的な採用活動が行われており、未経験からでも挑戦できる可能性が広がっています。
ここからは、業界ごとの現状と人手不足の背景について解説します。
医療・福祉
医療・福祉分野は、人手不足が特に深刻な業界のひとつです。
厚生労働省の統計によれば、高齢化の進行に伴い医療・介護サービスの需要は年々拡大していますが、それに対応するだけの人材確保が追いついていません。
特に介護職員は長時間労働や肉体的負担が大きく、賃金水準が低いことから離職率が高い状況が続いています。
医療現場でも、看護師や介護福祉士など専門資格を持つ人材が不足しており、既存スタッフへの負担が増加しています。
その結果、患者や利用者に提供できるサービスの質が低下する恐れがあるほか、現場のストレスが離職をさらに招くという悪循環が発生しています。
今後は、待遇改善や働き方改革に加え、外国人労働者の受け入れやデジタル技術の導入など、多面的な対策が不可欠となるでしょう。
運輸業・郵便業
運輸業や郵便業は、EC市場の拡大によって需要が急増している一方、人手不足が深刻な業界です。
ネット通販の普及で荷物量は年々増え続けていますが、ドライバーや仕分けスタッフの確保が追いつかず、現場は慢性的な人員不足に悩まされています。
加えて、長時間労働や体力的な負担が大きいことから若年層の応募は少なく、高齢化が進んでいる点も大きな課題です。
国土交通省の調査でも、トラック運転手の平均年齢は上昇しており、将来的にはさらに担い手が減ると予測されています。
郵便業でも同様に、再配達や広い配達エリアをカバーする業務が重荷となり、働き手が不足しています。
特に地方では採用が難しく、少人数で業務を回すため、一人当たりの負担が大きくなりやすいのが実情です。
こうした状況を改善するには、労働環境の見直しや人材確保の工夫に加え、再配達を減らす仕組みづくりやデジタル技術の導入など、具体的な取り組みが求められています。
建設業
建設業は日本の産業の中でも特に人手不足が深刻な分野です。
国土交通省の調査によれば、建設業従事者の平均年齢は2021年時点で47歳を超えており、技能労働者の高齢化が加速しています。
若年層の入職者が減少している一方で、公共事業や都市再開発、災害復旧工事など需要は高まっており、現場の労働力不足が顕著になっています。
さらに、建設業は体力的な負担が大きく、労働時間も長くなりがちなため、若手人材から敬遠されやすいのが現状です。
その結果、熟練技術を持つベテランに業務が集中し、後継者不足が深刻化しています。
また、人手不足によって工期が遅延するケースや、安全管理に支障が出るリスクも指摘されています。
将来的にはインフラ維持や防災対策に支障をきたす恐れがあり、建設業全体の持続性を左右する大きな課題となっています。
情報通信サービス
情報通信サービス業界は、デジタル化やDXの進展により需要が急速に拡大している一方で、深刻な人材不足に直面しています。
特にシステムエンジニアやプログラマー、セキュリティ関連の専門人材は需要が高く、求人倍率も他業種と比べて突出して高い水準です。
経済産業省の調査でも、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると推計されており、この分野の人手不足は長期的な課題とされています。
AI、クラウド、IoTといった先端分野では即戦力が求められますが、経験者が限られているため、採用が困難なのが現状です。
その結果、企業は人材獲得競争を強いられ、待遇改善や教育制度の整備に積極的に取り組む動きが広がっています。
情報通信サービス業界は、今後の経済成長を支える重要な分野である一方、人材不足がボトルネックとなる可能性が高いため、教育・研修や外国人材の活用など幅広い対策が必要です。
旅館・ホテル
旅館・ホテル業界は、観光需要の回復やインバウンドの増加によって需要が拡大している一方で、人手不足が深刻な業界です。
訪日外国人客数はコロナ禍を経て急速に回復しており、それに伴い宿泊施設の稼働率も上昇しています。
しかし、フロント、清掃、接客、調理といった幅広い業務を担うスタッフが十分に確保できていません。
人手不足の背景には、長時間勤務や不規則なシフト、体力的な負担の大きさがあり、特に若年層が敬遠しやすい傾向があります。
また、賃金水準が他業種に比べて低い場合が多く、働き手の定着率が低いのも課題です。
その結果、サービスの質が低下したり、宿泊客の受け入れ数を制限せざるを得ないケースも。
今後は待遇改善や働き方の見直しに加え、多言語対応や自動チェックインシステムなど、デジタル技術の活用によって人手不足を補う取り組みが求められる業界といえるでしょう。
人手不足だからこそ気を付けたい!転職における注意点
人手不足のニュースを耳にすると、「誰でも採用されやすいのでは」と考える人も少なくありません。
しかし実際には、企業が求める人材は明確であり、スキルや経験の有無によって採用の可否が大きく左右されます。
さらに、転職は入社することがゴールではなく、その後に安定して働き続けられるかが重要です。
人手不足の状況を追い風にするためには、応募準備や自己分析を丁寧に行い、自分に合った企業選びを心がけていきましょう。
ここでは、転職活動で特に注意すべきポイントを解説します。
採用されるためにはスキルが必要
人手不足の業界であっても、必ずしも採用されるとは限りません。
企業は即戦力として活躍できる人材を求める傾向が強く、業務に直結する経験や資格を持つ応募者は採用されやすい一方、未経験者は不利になる場合があります。
特に医療・福祉やIT、建設といった専門性の高い分野では、資格や実務経験の有無が採用の大きな分かれ道となります。
ただし、全くの未経験者でも「学ぶ姿勢」や「基本的なスキル」をアピールできれば採用につながる可能性があります。
パソコン操作やコミュニケーション能力、チームで働く力などは多くの職場で評価されるでしょう。
また、近年は人材不足を背景に研修制度を整える企業も増えており、入社後にスキルを習得できる環境が用意されている場合もあります。
重要なのは、自分の持っている強みを整理し、応募する企業が求めるスキルと結びつけて伝えることです。
選考対策はしっかり行う
人手不足の状況にあっても、企業は採用に慎重です。
履歴書や職務経歴書の内容が不十分であれば書類選考で落とされることも珍しくなく、面接の準備不足は採用の大きなハードルになります。
そのため、転職活動では「人手が足りないから簡単に受かる」という考え方はやめましょう。
まずは、自分の経験やスキルを客観的に整理し、応募先の企業が求める人物像に沿ってのアピールが大切です。
面接では志望動機やキャリアプランを明確に伝えることが求められます。
さらに、過去の成功体験や課題解決のエピソードを準備しておくと安心です。
人手不足の中でも企業は「定着して長く活躍できる人材」を探しています。
十分な選考対策を行うことで、採用される可能性を高められます。
自分に合った企業を選ぶ
人手不足の今だからこそ、求職者にとっては幅広い選択肢が広がっています。
しかし、目先の採用のしやすさだけで企業を選ぶと、入社後にミスマッチを感じて早期離職につながる恐れも。
そのため、転職活動では「自分に合った企業かどうか」を慎重に見極めることが重要です。
まず、給与や福利厚生といった待遇面だけでなく、労働時間、職場の人間関係、キャリアパスなども確認しましょう。
自分が持っている資格やスキルを活かせる職場であれば、成長ややりがいを感じやすくなり、長期的に働き続けやすくなります。
また、転職サイトや口コミ、説明会や転職エージェントを活用して社風を把握するのもおすすめです。
近年では「働きやすさ」や「柔軟な働き方」を重視する人が増えており、そうした視点を取り入れることで希望の仕事に就ける可能性があります。
今の職場に不満があるならば、この機会に転職活動をしてみてはいかがでしょうか。
自分の価値を知るなら転職エージェントの利用もおすすめ
転職活動を進めるうえで、自分の市場価値を客観的に把握することは欠かせません。
しかし、自分だけで正確に判断するのは難しく、強みや改善点を見落とすこともあります。
そこで有効なのが転職エージェントです。
転職エージェントは、応募書類の添削や面接練習のサポートだけでなく、企業が求める人材像を踏まえて求人を紹介します。
さらに、年収相場や業界ごとの需要を教えてもらえるため、自分のスキルがどの程度評価されるのかを把握できるでしょう。
これにより、現職よりも待遇の良い企業へ転職できる可能性が高まったり、未経験分野でも採用の可能性がある求人に挑戦しやすくなります。
人手不足が続く今こそ、転職エージェントを活用し、自分に合ったキャリアアップにつなげていきましょう。
まとめ
日本で人手不足が深刻化している背景には、少子高齢化や人口減少、非正規雇用の増加、価値観の変化、さらには人材の海外流出などさまざまの要因があります。
こうした課題は中小企業や地方経済に大きな影響を与え、離職率の上昇や事業縮小・倒産リスクの増加につながっています。
一方で、人材不足が目立つ業界では採用意欲が高まっており、求職者にとっては転職のチャンスです。
転職エージェントを活用すれば、自分の市場価値を把握し、より良い条件での転職を実現できる可能性が高まります。
人手不足という社会的な課題を理解しつつ、自分のキャリアに活かせる行動をとっていきましょう。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!






