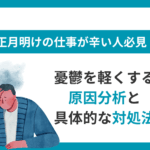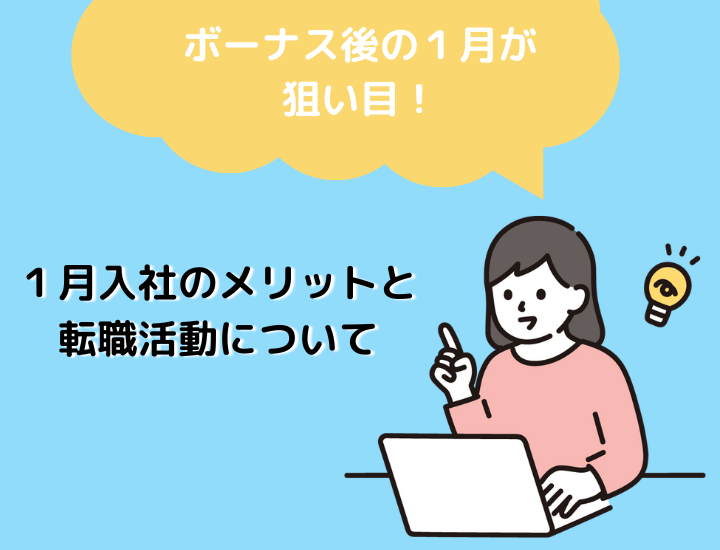2025〜2026年の正月休みはいつから?一般企業&公的機関の平均的な休日を解説
はじめに
正月休みは、家族や友人と過ごしたり旅行に出かけたりと、一年の中でも特に大切な時間です。
予定を立てる際に気になるのが、「正月休みはいつから始まるのか?」ということではないでしょうか。
正月休みは、業種や利用する施設によって大きく異なります。
一般企業はカレンダー通りに休みを設定するケースが多い一方で、郵便局や金融機関、市役所といった公共機関には独自の休業日程があり、事前に確認しておかないと手続きや振込ができずに困ってしまうことも少なくありません。
さらに、医療機関の場合はクリニックや総合病院で休業期間が異なるため、通院や薬の準備が必要な方は特に注意が必要です。
本記事では、2025年から2026年にかけての正月休みが「いつから」始まるのかを、一般企業から郵便局、金融機関、市役所、そして医療機関まで網羅的に解説します。
休み前に必要な準備もあわせて紹介するので、年末年始を安心して迎えるための参考にしてください。
一般的な企業の年末年始休業はいつから?
日本の正月休みは、企業や業界によって開始日や期間が異なりますが、多くの場合「12月末から1月初旬」にかけてまとまった休暇を取得できます。
2025〜2026年の正月休みは、12月27日(土)から1月4日(日)までが目安となります。
しかし、法律で定められた祝日に加え、会社独自の休日設定がされるため、実際の休み期間には差が出ます。
ここでは、多くの人が気になる一般的な企業の年末年始休業のスタート時期について、基本的なパターンから業界ごとの傾向まで詳しく解説していきます。
カレンダー通りが基本
一般的な企業の年末年始休業は、12月最後の土日から翌年1月3日にかけての6〜9日間が基本とされています。
日本の官公庁や大多数の民間企業が、土曜・日曜・祝日を公休日としているため、このスケジュールを採用しています。
たとえばオフィスワーク中心の企業では、この期間を一斉休業とするのが一般的です。
また、大企業や上場企業の場合、連休を長く設定するケースも少なくありません。
例えば、2025年の年末休暇は12月27日(土)から開始することが一般的ですが、前倒しして12月26日(金)から年末年始休暇として設定する企業もあります。
一方で、中小企業やベンチャー企業では、12月30日(火)から休みに入る場合もあります。
例えば2025年12月の場合、27日と28日は土日ですが、29日は月曜日となります。
そのため、29日は暦通り平日として出勤となる場合もあります。
企業規模や経営方針によって柔軟に変わるケースも少なくないのです。
したがって、年末年始に休みを取る際は、自分の勤める会社の就業規則や年間カレンダーを事前に確認しておくことが大切です。
土日との兼ね合いで休みが延びるケースもある
年末年始休業は、土日や祝日と重なることで休暇期間が延びるケースがあります。
一般的な年末年始休暇は12月最後の土日から1月3日までですが、2026年のカレンダーでは1月4日が日曜日となるため、そのぶん連休が長くなります。
12月27日(土)からの連休だとすると、翌年1月4日(日)まで9連中です。
2025年〜2026年にかけての正月休みは、例年よりも長いと言えるのです。
これだけ長い休暇が取れれば、旅行や帰省を始めとしてさまざまなイベントが楽しめますよね。
ただし、多くの企業が9連休であることを考えると、交通機関や観光地が混雑する可能性が高いです。
予約が必要な場合は、年末年始の予定が決まった段階でできるだけ早めに行動を起こすことをおすすめします。
サービス業は休みがないこともある
前述したパターンは国内の企業の大多数の例ですが、すべての業界が一斉に休むわけではありません。
特に小売業、飲食業、宿泊業、交通業界など、年末年始に需要が高まる業種では「書き入れ時」となるため、むしろ繁忙期を迎えるケースが多いです。
たとえばデパートやスーパーでは「初売り」「福袋セール」などのイベントがあり、年明け早々に営業を開始する店舗が一般的です。
飲食業界でも、帰省客や観光客の利用が増えるため、通常以上の稼働を求められます。
また、鉄道・航空・バスなどの交通機関は帰省ラッシュに対応する必要があり、年末年始こそ最大の繁忙期です。
さらに医療や介護関連の現場も、社会インフラを支える存在であるため、完全に休業することはできません。
そのため「正月休みがほぼない業界」として位置づけられることもあります。
このように業種によって年末年始の勤務状況は大きく異なるため、自分や家族の予定を立てる際には業界ごとの休暇の特徴を理解しておくと安心です。
郵便局の正月休みはいつから?
郵便局の正月休みは、例年12月31日〜1月5日までの6日間です。
ただし、業務内容や窓口の種類によって休業日が異なります。
本章では、窓口業務の最終営業日や休業開始日、利用者が注意すべき点を整理します。
郵便業務の計画や手続きを年末に済ませたい方は必見の内容です。
郵便物や荷物の配達に関する注意点
年末年始は郵便物や荷物の取り扱い件数が急増するため、通常時期と比べて発送から到着までに時間がかかる可能性があります。
特に、年賀状や贈答品のゆうパックなどが集中する12月下旬から1月初旬は、配送網が一時的に混雑し、配達に遅れが出やすくなります。
配達に関しては以下のような点に注意が必要です。
- 12月31日~1月2日頃までは配達業務を休止するケースが多く、配達再開後も処理件数が膨大なため、通常より数日遅れる場合があります。
ゆうパック・書留・速達・EMS
- 休まず配達が行われますが、地域によっては荷物量の増加により配達時間が普段より遅れる可能性があります。特に天候の影響を受けやすい地域では要注意です。
再配達サービス
- 年末年始も一部地域で対応していますが、配達員の人員が限られるため、希望通りの時間帯に届けられないケースがあります。
また、郵便局の窓口は12月31日〜1月5日かけて休業するのが一般的ですが、「ゆうゆう窓口」が併設されている大規模局であれば、年末年始休暇中でも一部サービス(小包受付・切手販売など)が利用可能です。
とはいえ、ゆうゆう窓口も混雑する傾向があるため、発送は早めに済ませることをおすすめします。
まとめると、年末年始は「配達休止」「荷物量増加」「窓口休業」が重なり、通常より発送が遅くなるのはほぼ確実です。
大切な荷物や手紙は、少なくとも年内最終営業日の数日前までに手続きを終えるのが安心です。
事前に済ませておくべき手続き
年末に近づくにつれて、郵便局の配達スケジュールが遅くなる傾向にあります。
それに向けて、やるべきことは早めに済ませておきましょう。
例えば年賀状の発送については早めの行動が吉です。
1月1日に届くようにするためには、12月25日までに投函していなければなりません。
また、振り込みや貯金など金融のやり取りも注意しましょう。
前述した通り、郵便局は12月31日から休みに入るので、ゆうちょ銀行も同様のスケジュールで休日に入ります。
そのため、年内に振り込みが必要な支払いがある人は注意しましょう。
30日ギリギリの振り込みをする場合、ゆうちょ銀行の営業時間である15時を超えてしまうと相手先に振り込まれるのは翌年になります。
毎年このように「ギリギリ」の行動をする人が多いため、窓口も非常に混雑しがちです。
金融のやり取りはとてもシビアですから、できるだけ安心して行動できるよう、29日より前に対応しておくことをお勧めします。
金融機関の正月休みはいつから?
金融機関は、メガバンクも地方銀行も12月31日から1月3日を休日としていることが一般的です。
一般企業や郵便局に比べると少し短いですし、ATMというありがたいサービスも存在する分、カスタマー側としては余裕を持って行動できそうですね。
しかし、ATMの利用時間帯や手数料に関して注意すべき点や、送金や引き落としのタイミングにずれが生じる場合もあります。
ここでは、それらの利用に関する注意点を解説します。
ATM利用の可否や手数料に関する注意点
金融機関の正月休みは、一般的に12月31日から1月3日頃までの間に多くの窓口業務が休止となります。
銀行の店舗窓口が休業している間も、ATMは稼働していることが多いですが、注意が必要です。
まず、ATMは設置場所によって稼働時間が異なり、商業施設やコンビニに設置されているものは利用可能な場合が多い一方、銀行の店舗内にあるATMは店舗休業に合わせて停止することがあります。
次に手数料についてですが、平日・営業時間内に比べ、正月期間中は「時間外扱い」となり、通常よりも手数料が高くなるケースがほとんどです。
特に他行ATMやコンビニATMを利用すると追加手数料が発生することが多いため、利用前に確認が必要です。
また、休日期間はシステムメンテナンスが行われることもあり、残高照会や振込など一部のサービスが利用できない場合があります。
急な現金の必要や送金に備えて年末のうちに必要な額を引き出しておいたり、インターネットバンキングの利用可否を確認しておくと安心です。
正月休みはATMが「使えるかどうか」だけでなく、「いくら手数料がかかるか」にも注意を払うことが大切と言えます。
送金・引き落としのタイミングを確認すべき理由
金融機関の正月休みは、通常の土日祝日よりも長く取引が停止する期間が長くなるため、送金や引き落としのタイミングを事前に確認しておくことが非常に重要です。
特に12月末から1月初旬にかけては、給与振込や家賃、公共料金、クレジットカード利用代金などの自動引き落としが集中する時期でもあります。
金融機関が休業していると、振込依頼をしても実際に相手口座へ入金されるのは休業明けになるため、期日までに入金が必要な場合は支払い遅延につながる恐れがあります。
また、引き落としも同様に、休業日に設定されていると翌営業日に処理されるため、残高不足や延滞扱いになるリスクが高まります。
さらに、ネットバンキングやATMの操作自体は可能でも、処理が実行されるのは営業再開後というケースも多く、安心して利用するためには事前の確認が欠かせません。
年末年始は休業日数が連続するため、取引スケジュールに余裕を持ち、早めに送金や入金を済ませておくことが、トラブル回避の大切なポイントとなります。
市役所・役場など役所関係の正月休みはいつから?
市役所や町役場などの公的機関は、一般的に12月29日から1月3日までの間、年末年始の休業となることが多いです。
2025年は12月27日と28日が土日で、かつ1月4日が日曜日のため、厳密にいうと12月27日(土)から1月4日(日)の9日間が休みということになります。
例年よりも休みが長いため、こちらも手続き上の注意点や緊急時の対応について知っておく必要があるでしょう。
役所関係の手続きの注意点
2025年は12月27日(土)から翌年1月4日(日)の9日間を休日とするため、この期間は窓口業務が停止します。
住民票の取得や印鑑登録、各種証明書の発行、戸籍・住民異動の手続きなど、通常平日に行える手続きができません。
また、各種税金や公共料金の納付も、休日扱いとなり、納期限が前倒しまたは後ろ倒しになる場合があります。
緊急時には、役所のウェブサイトや自動応答サービスで対応可能な情報が確認できますが、窓口での対応は休み明けとなる点に注意が必要です。
さらに、年末年始は郵便物の配達も通常より遅れることがあるため、書類の郵送手続きも計画的に行うことが重要です。
特に引越しや婚姻届、パスポートの申請など、期限が決まっている手続きは、休暇前に済ませておくことを推奨します。
事前に公式ウェブサイトや掲示板で休業日や緊急対応について確認することで、手続きの遅れやトラブルを避けることができます。
緊急時の対応について
2025年は12月27日(土)から翌年1月4日(日)の9日間は窓口業務や電話対応は通常行われないため、住民票の発行や税金の手続きなど、日常的な行政サービスは利用できません。
しかし、緊急を要する事態に備えて、各自治体では休日・夜間用の緊急連絡窓口や当番制の職員が対応できる体制を整えています。
例えば、火災や水害、救急医療に関わる連絡先は、自治体の公式ウェブサイトや電話案内で確認できますし、消防署や警察署、救急センターと連携して迅速に対応が可能です。
また、一部の自治体では公共下水や道路の冠水、ガスや水道の事故など、生活インフラに関わる緊急連絡用の専用ダイヤルも設置されています。
正月休み期間中に緊急対応が必要な場合は、まず公式情報を確認し、指示された窓口に連絡することが重要です。
これにより、休日でも迅速かつ安全に行政サービスが提供される体制が整っています。
医療機関の正月休みはいつから?
年末年始は多くの医療機関が休診期間に入るため、受診を希望しても対応してもらえないケースがあります。
特にクリニックや一般診療所は12月29日頃から休みに入ることが多く、診察再開は1月4日以降となるのが一般的です。
一方で、大規模な総合病院では一部の外来部門を休診にしつつも救急外来は稼働していることが多く、急な体調不良や事故などにも対応できます。
また、休日当番医制度や地域の救急相談窓口を把握しておくことで、万が一の時にも安心です。
年末年始を安心して過ごすためには、かかりつけ医の休診日を事前に確認し、薬や診察の必要がある場合は早めに対応しておくことが重要です。
クリニックなどの一般診療所
地域に根ざしたクリニックや診療所の多くは、12月29日頃から1月3日まで休診とするケースが一般的です。
これはカレンダー通りに休暇を設定する医療機関が多いためで、年末年始を挟んで約5〜6日間の休みが発生します。
患者としては、年末に体調を崩した場合や薬の処方が必要な場合に困ることもあるため、事前準備が欠かせません。
特に持病がある方や定期的に薬を処方してもらっている方は、12月中旬までに受診し、必要な薬を確保しておくと安心です。
また、年末は予約が混み合いやすくなるため、できるだけ早めに診察の予定を立てておくことが望ましいでしょう。
総合病院など大規模病院
総合病院や大学病院といった大規模な医療機関では、外来診療の一部が休診になる一方で、入院病棟や救急外来は通常通り稼働していることが多いです。
一般外来は12月29日から1月3日頃まで休診とされるケースが多く、診察を受けたい場合は年内最終日の外来受付時間を事前に確認しておく必要があります。
ただし、重症患者への対応や救急医療体制は維持されているため、突然の体調不良や事故があった場合にも受け入れ先は確保されています。
とはいえ、年末年始は救急外来が非常に混雑する傾向があるため、軽症であれば休日当番医や地域の急患センターを利用することも検討しましょう。
救急外来や休日当番医の探し方
年末年始に急な病気やけがをした場合、通常のクリニックや外来が休みで困ることがあります。
こうした時に役立つのが救急外来や休日当番医制度です。
各自治体では、年末年始を含む休日に対応可能な医療機関を指定しており、地域のホームページや広報誌で確認できます。
また、救急安心センター(#7119)に電話すると、症状に応じて受診の必要性や対応可能な医療機関を案内してもらえます。
子どもの場合は小児救急電話相談(#8000)が利用可能です。
これらの制度を活用することで、正月休み中でも安心して医療サービスを受けることができます。
事前に連絡先をメモしておき、万が一に備えておくことをおすすめします。
業界別に見る正月休み開始日の傾向
正月休みがいつから始まるのかは、業種によって大きく異なります。
一般企業の多くは例年12月29日頃から休みに入りますが、業界ごとの業務特性によって開始日や休暇の長さが変わってくるのが実情です。
建設業や小売業のように早めに休みに入る業界がある一方で、物流や交通機関、サービス業は年末ギリギリまで稼働するケースが多く見られます。
また、コンビニや飲食業、ホテル業などでは「正月休みがほぼない」といっても過言ではありません。
ここでは、それぞれの業界がどのようなスケジュールで年末年始を迎えるのかをご紹介します。
詳しく見ていきましょう。
休みに入るのが早い業界
建設業や小売業は、他業界と比べて早めに正月休みに入る傾向があります。
まず建設業では、年末の工事を区切りとして12月28日より前に休暇に入ることが一般的です。
公共工事を含め、多くの現場は年始に安全祈願をしてから工事を再開する習慣があり、業界全体で長めの休暇を取る風土が根付いています。
一方で、小売業は年末商戦のピークであるクリスマスを終えた頃から初売りまでの期間、業務が一気に落ち着きます。
そのため、早めに仕入れや売り場整理を済ませてから休みに入る会社も少なくありません。
特に衣料品や雑貨ブランドを展開している会社では、店舗こそ年末年始営業をしているものの、本社機能自体は前倒しで休業とすることが多く見られます。
こうした業界は「年内に区切りをつけやすい」性質があるため、比較的余裕をもって正月休みに入れるのが特徴です。
休みに入るのが遅い業界
物流、交通機関、そしてサービス業は、年末ギリギリまで稼働する業界です。
物流業界は年末の荷物量が一年で最も多くなるため、12月31日まで配送業務を続けるケースが多く、実質的に休みに入れるのは1月1日から数日程度です。
交通機関も同様で、新幹線や高速バス、航空会社などは年末年始の帰省ラッシュ対応に追われ、むしろ繁忙期に入ります。
サービス業では、飲食店や娯楽施設が「大晦日営業」「カウントダウンイベント」などを開催するため、12月31日までフル稼働というのが一般的です。
このように、生活インフラや人の移動に関わる業界は「休みに入るのが遅い」どころか、むしろ正月直前が繁忙期にあたる点が特徴といえるでしょう。
正月休みがほぼない業界
コンビニ、飲食業、ホテル業は「正月休みがほぼない業界」といえます。
コンビニは365日24時間営業を基本としており、正月期間も通常通り営業します。
飲食業も、特にファストフードやファミリーレストランは年末年始に利用する人が多く、むしろ売上のピークを迎える場合があります。
ホテル業は観光需要や帰省客の宿泊が集中するため、12月末から1月初旬にかけて繁忙期を迎え、休みを取ることはほとんどできません。
こうした業界では、正月休みを一斉に取るのではなく、スタッフが交代制で勤務にあたり、落ち着いた時期に「振替休日」を取得するのが一般的です。
そのため、カレンダー通りの休暇を期待するのは難しく、勤務する側はスケジュール調整や体調管理が重要になります。
正月休みを前に準備しておきたいこと
正月休みは、銀行や郵便局、市役所、そして医療機関といった生活に直結する施設が長期的に休業するため、事前準備を怠ると不便やトラブルに直結します。
特に2025〜2026年の年末年始は、曜日の並びによって休業期間が例年より長くなる可能性があり、注意が必要です。
金融関連の振込や支払い、市役所での各種証明書取得、さらに医療機関での薬の確保は、休みに入る前に済ませておくべき最重要ポイントといえます。
ここでは、年末年始を安心して迎えるために必要な準備について具体的に解説していきます。
銀行・郵便局の振込や支払いを年内に済ませる
銀行や郵便局は、基本的に12月31日頃から1月3日まで休業となるケースが一般的です。
休み期間中でもATMは稼働していることが多いですが、振込や送金は「翌営業日扱い」になるため、資金移動のタイミングを誤ると支払いが遅れてしまう可能性があります。
また、金融機関によっては正月期間中にATM手数料が通常より高くなる場合もあるため、事前に確認が必要です。
郵便局についても、荷物や郵便物の配達が遅延することがあるため、年末に発送したいものがある場合は早めの投函・持ち込みが安心です。
特に公共料金や家賃などの引き落としが年末年始にかかる場合、残高不足で未払いにならないよう、必ず口座残高を確認しておきましょう。
市役所で必要な証明書を取得しておく
市役所や区役所、町村役場といった公的機関も、一般的に12月29日から1月3日まで休業します。
2025年から2026年でいうと、12月27日(土)から1月4日(日)までが休業です。
そのため、戸籍謄本や住民票、印鑑証明書といった書類は、正月休みに入る前に取得しておくことが大切です。
特に転職や住宅ローン契約、車の購入などで証明書が必要になる場合、年末年始に間に合わないと手続きが大幅に遅れてしまうこともあります。
最近ではマイナンバーカードを使えばコンビニで証明書を発行できる自治体も増えていますが、年末年始はシステム停止の可能性もあるため、余裕を持って取得しておくことが望ましいでしょう。
また、緊急でどうしても必要になる場合に備えて、事前に自治体のホームページで「年末年始の窓口対応」について確認しておくと安心です。
医療機関・薬の準備
医療機関も年末年始は休業となるケースが多く、特に個人クリニックや診療所は長期休みになることが一般的です。
持病がある方や定期的に薬を処方されている方は、必ず正月前に薬を受け取っておきましょう。
常備薬や処方薬が足りなくなると、休み期間中に体調を崩した際に対応が難しくなります。
また、薬局も年末年始は営業時間が短縮されることがあるため、早めに薬を受け取るのが安心です。
大規模病院や総合病院は救急外来が稼働している場合がありますが、待ち時間が非常に長くなる傾向があるため、できるだけ利用を避けた方が良いでしょう。
さらに、小さなお子様や高齢の家族がいる家庭では、解熱剤や胃腸薬、風邪薬といった市販薬も含めて、家庭用の常備薬をしっかり揃えておくと安心して正月を迎えることができます。
まとめ
2025〜2026年の正月休みは、企業や業界によって開始日や休業期間が異なります。
一般企業は12月27日土)頃から1月4日(日)までが目安となりますが、金融機関や郵便局、市役所などの公的機関も同様に休業するため、年末前に必要な手続きを済ませておくことが重要です。
また、医療機関は長期休みに入る場合が多く、常備薬や処方薬の準備は必須です。
2025年のように、カレンダーの並びによって休みが長期化する年は、振込や証明書の取得、薬の確保などを早めに行うことで安心して新年を迎えることができるでしょう。
今回の記事を参考に、業界別の休暇傾向を把握し、生活に直結する手続きや準備を計画的に進めることが、正月休みを快適に過ごすための最大のポイントです。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!