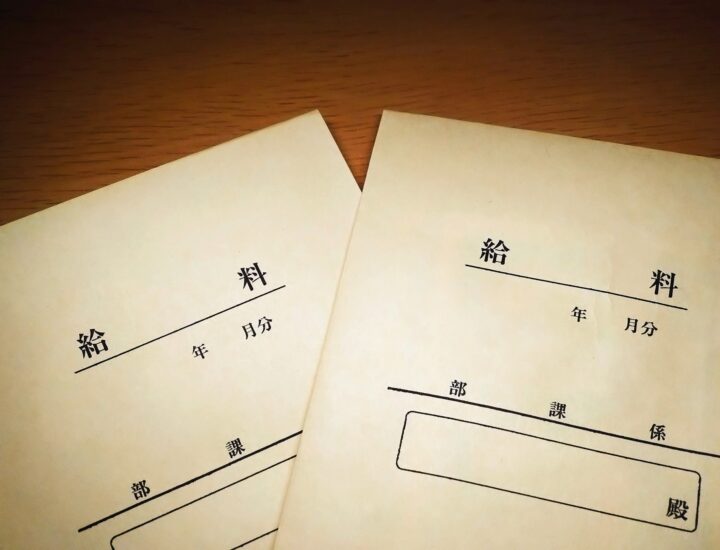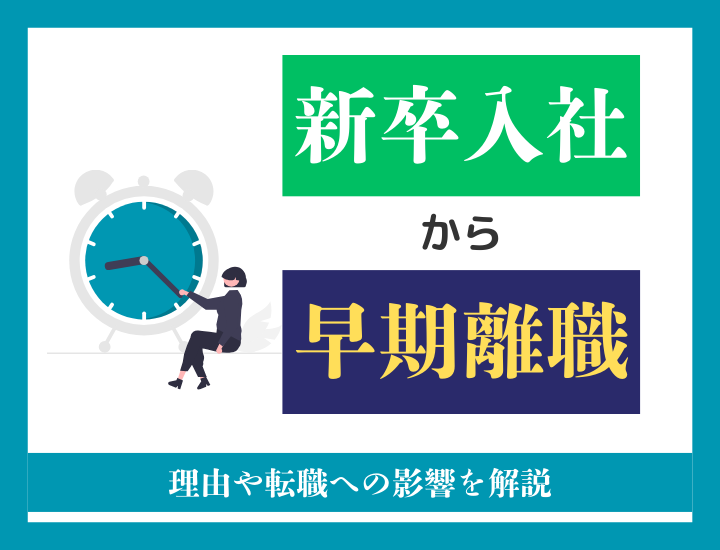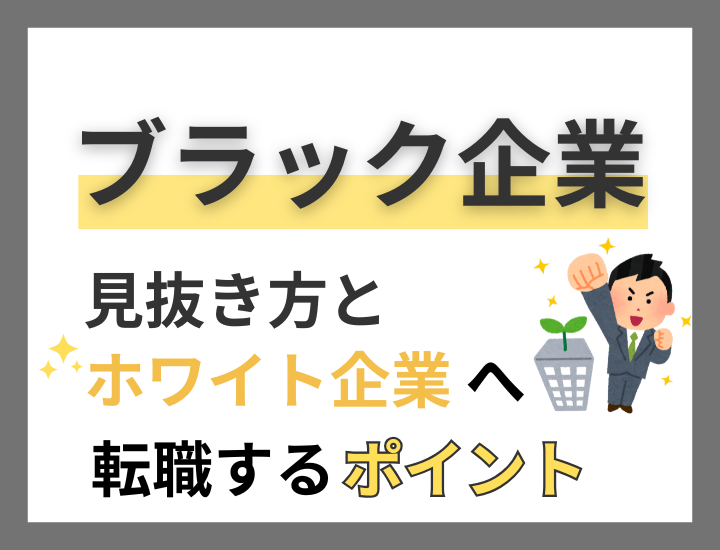第二新卒の給料の実態とは?
第二新卒の給料は「新卒と同じなのか」「転職すると下がるのか」といった疑問を多くの方が抱くテーマです。特に社会人経験が1〜3年の時期はキャリアをどう進めるか迷う人が多く、給料事情は転職を考えるうえで避けて通れない要素です。ここでは最新データや具体的なシミュレーションをもとに、第二新卒の収入実態を徹底的に解説します。
第二新卒の平均年収はどれくらい?
国税庁の「民間給与実態統計調査」(2024年度版)によると、20〜24歳の平均年収は男性307万円、女性258万円、全体で282万円となっています。これはあくまで全国平均ですが、社会人2〜3年目に当たる第二新卒世代の多くはこの範囲に収まります。
dodaの「平均年収ランキング」(2024年12月)では、22〜25歳の平均年収が317万円とされており、国税庁の統計と大きな差はありません。つまり第二新卒の相場は280万〜320万円程度が目安だといえるでしょう。
ただしこの金額は「平均値」であり、業界や職種によって100万円以上の差が生まれることも珍しくありません。特に営業やエンジニアなど成果やスキルが直接給与に反映される職種は、同じ第二新卒でも年収が大きく変動します。
年収の推移|20代前半〜後半でどう変わる?
第二新卒の時期(22〜25歳頃)は、昇給スピードがまだ緩やかです。国税庁調査を基にすると、22歳時点で年収286万円、25歳で351万円と、わずか3年間で60万円以上伸びることが分かります。特に25歳以降は昇格やボーナス支給額が増えるため、同じ「20代前半」でも実際の生活感は大きく異なります。
一方で、企業や業界によっては昇給がほとんどないケースもあり、24歳になっても年収が280万円程度に留まる人もいます。この差は「業種選び」と「会社の昇給制度」の違いによって生まれるため、転職時には長期的な給与テーブルを必ず確認する必要があります。
地域別・男女別の給料格差
地域差も無視できません。東京や大阪など大都市圏では、同じ職種でも地方都市より30〜60万円高い水準が一般的です。例えば東京のITエンジニアの第二新卒平均年収は330〜350万円ですが、地方では280万円前後にとどまることもあります。
男女差については、総合職比率の違いが大きく影響します。dodaの調査によると、24歳時点で男性321万円、女性289万円と約30万円の差があります。これは女性の方が一般職や地域限定職を選択する割合が高いためで、能力差というより「働き方の違い」が反映されています。
手取りと生活シミュレーション
額面年収300万円の場合、社会保険料や税金を引くと手取りは約240万円、月20万円前後です。これを実際の生活に当てはめてみましょう。
都内一人暮らしの場合:家賃7万円、食費3万円、光熱費1.5万円、通信費1万円、雑費2万円で、残りは約5万円。貯金や娯楽に回せる金額はごく限られます。
地方一人暮らしの場合:家賃が4万円程度に抑えられるため、都内より毎月3万円程度の余裕が生まれます。
実家暮らしの場合:生活費を大幅に抑えられ、年間で100万円以上の貯蓄も可能。第二新卒で貯金をしたいなら実家暮らしは有利です。
生活環境が年収の価値を左右する
同じ年収でも、生活スタイルによって余裕度は大きく変わります。特に都内で一人暮らしをする場合、額面300万円ではカツカツの生活になりがちです。そのため「収入額」だけでなく「生活環境」や「支出構造」を意識することが重要です。第二新卒で転職を考える際には、給料だけでなくライフスタイル全体を見直して判断するのが賢明です。
第二新卒で転職した場合の給料の変動
第二新卒で転職すると給料は上がるのか、下がるのか。これは多くの人が抱える疑問です。結論から言えば「どちらの可能性もある」が正解です。第二新卒の転職はキャリアが浅い分、評価のされ方や採用枠の条件に左右されやすいため、年収が下がる人もいれば、逆に大きくアップする人もいます。ここでは給料が下がるケースと上がるケースを、それぞれ具体的に解説します。
年収が下がる理由とは?
第二新卒での転職で年収が下がる主な理由には、次のようなものがあります。
- 新卒と同じ扱いを受けるケース:社会人経験が浅いため給与テーブルがリセットされ、初任給水準からの再スタートになる。
- 未経験業界・職種への挑戦:キャリアチェンジでは研修からやり直しになることが多く、給与水準も新卒と同等に設定される。
- 賞与の有無:月給は同じでも、転職先で賞与制度がなければ年間収入は大幅ダウン。
- 焦り転職:早く辞めたい気持ちが先行し、条件交渉をせずオファーを受けてしまう。
例えば「入社1年で退職したケース」では、採用担当から「実務経験不足」と見なされやすく、新卒扱いになるリスクが高まります。額面では月給20万円前後、年収にして250〜280万円まで下がることも珍しくありません。さらに賞与がない会社だと実質的な生活レベルは新卒時より下がってしまうことさえあります。
また、キャリアチェンジの例として、営業職から事務職へ移ると給与水準が下がることが多いです。事務職は一般的に昇給幅も小さいため、短期的には「収入ダウン」を受け入れる覚悟が必要になるでしょう。
年収が上がるケースとは?
一方で、第二新卒の転職が「収入アップ」につながるケースも少なくありません。代表的なパターンは以下の通りです。
- 給与水準の高い業界・職種に移る:IT、不動産、金融、コンサルなどは平均給与が高く、未経験でも年収350〜400万円からスタートできる。
- 現職の給与が低すぎる場合:中小企業やスタートアップで年収250万円程度だった人が、同年代の平均水準の会社に転職するだけで50〜80万円のアップにつながる。
- 給与交渉の成功:前職での実績を明確にアピールできれば、希望年収を反映してもらえる可能性がある。
- 成果報酬・インセンティブ制度:営業職などでは歩合給により入社1年目から年収500万円を超えることも。
実際の事例を紹介しましょう。販売職から不動産営業へ転職したCさん(24歳)は、基本給は25万円でしたが、インセンティブ制度により初年度で年収480万円を達成しました。これは前職比+200万円の大幅アップです。逆に、同じ第二新卒でも事務職へ転職したDさんは、残業削減や働きやすさを優先した結果、年収が50万円下がりましたが「ワークライフバランスが改善された」と満足しています。
データで見る第二新卒の転職後の給料変化
リクルートワークス研究所の調査(2019年)によれば、1年以内に転職した人の約40%が「年収が下がった」と回答しています。一方、年収が上がった人は30%を超えており、2年目以降の転職では上がった人の割合が41.8%まで増加します。このデータから分かるのは、「第二新卒=必ず年収ダウン」ではないということです。
特に「経験を活かせる職種」や「給与水準の高い業界」では、第二新卒でも収入アップのチャンスがあります。むしろ現職の待遇に不満がある人ほど、転職で逆転できる可能性が高いと言えるでしょう。
短期的な年収よりも長期的視点が重要
第二新卒の転職で意識すべきなのは、短期的な給料の増減だけではありません。たとえ入社時に年収が下がったとしても、その会社でスキルが身につき、30代で大きく収入を伸ばせる環境なら「一時的なマイナス」は将来への投資になります。
例えば、25歳でITエンジニアとして年収280万円でスタートしたEさんは、資格取得と経験を積んで28歳で年収450万円に到達しました。第二新卒の時期はキャリア形成の入口であり、この時期に選んだ環境が後の年収カーブを大きく左右するのです。
つまり、第二新卒で転職する際には「今いくらもらえるか」だけでなく「5年後にいくら稼げるか」を基準に判断することが重要です。
第二新卒で転職した場合の給料の変動
第二新卒で転職すると給料は上がるのか、下がるのか。これは多くの人が抱える疑問です。結論から言えば「どちらの可能性もある」が正解です。第二新卒の転職はキャリアが浅い分、評価のされ方や採用枠の条件に左右されやすいため、年収が下がる人もいれば、逆に大きくアップする人もいます。ここでは給料が下がるケースと上がるケースを、それぞれ具体的に解説します。
年収が下がる理由とは?
第二新卒での転職で年収が下がる主な理由には、次のようなものがあります。
- 新卒と同じ扱いを受けるケース:社会人経験が浅いため給与テーブルがリセットされ、初任給水準からの再スタートになる。
- 未経験業界・職種への挑戦:キャリアチェンジでは研修からやり直しになることが多く、給与水準も新卒と同等に設定される。
- 賞与の有無:月給は同じでも、転職先で賞与制度がなければ年間収入は大幅ダウン。
- 焦り転職:早く辞めたい気持ちが先行し、条件交渉をせずオファーを受けてしまう。
例えば「入社1年で退職したケース」では、採用担当から「実務経験不足」と見なされやすく、新卒扱いになるリスクが高まります。額面では月給20万円前後、年収にして250〜280万円まで下がることも珍しくありません。さらに賞与がない会社だと実質的な生活レベルは新卒時より下がってしまうことさえあります。
また、キャリアチェンジの例として、営業職から事務職へ移ると給与水準が下がることが多いです。事務職は一般的に昇給幅も小さいため、短期的には「収入ダウン」を受け入れる覚悟が必要になるでしょう。
年収が上がるケースとは?
一方で、第二新卒の転職が「収入アップ」につながるケースも少なくありません。代表的なパターンは以下の通りです。
- 給与水準の高い業界・職種に移る:IT、不動産、金融、コンサルなどは平均給与が高く、未経験でも年収350〜400万円からスタートできる。
- 現職の給与が低すぎる場合:中小企業やスタートアップで年収250万円程度だった人が、同年代の平均水準の会社に転職するだけで50〜80万円のアップにつながる。
- 給与交渉の成功:前職での実績を明確にアピールできれば、希望年収を反映してもらえる可能性がある。
- 成果報酬・インセンティブ制度:営業職などでは歩合給により入社1年目から年収500万円を超えることも。
実際の事例を紹介しましょう。販売職から不動産営業へ転職したCさん(24歳)は、基本給は25万円でしたが、インセンティブ制度により初年度で年収480万円を達成しました。これは前職比+200万円の大幅アップです。逆に、同じ第二新卒でも事務職へ転職したDさんは、残業削減や働きやすさを優先した結果、年収が50万円下がりましたが「ワークライフバランスが改善された」と満足しています。
データで見る第二新卒の転職後の給料変化
リクルートワークス研究所の調査(2019年)によれば、1年以内に転職した人の約40%が「年収が下がった」と回答しています。一方、年収が上がった人は30%を超えており、2年目以降の転職では上がった人の割合が41.8%まで増加します。このデータから分かるのは、「第二新卒=必ず年収ダウン」ではないということです。
特に「経験を活かせる職種」や「給与水準の高い業界」では、第二新卒でも収入アップのチャンスがあります。むしろ現職の待遇に不満がある人ほど、転職で逆転できる可能性が高いと言えるでしょう。
短期的な年収よりも長期的視点が重要
第二新卒の転職で意識すべきなのは、短期的な給料の増減だけではありません。たとえ入社時に年収が下がったとしても、その会社でスキルが身につき、30代で大きく収入を伸ばせる環境なら「一時的なマイナス」は将来への投資になります。
例えば、25歳でITエンジニアとして年収280万円でスタートしたEさんは、資格取得と経験を積んで28歳で年収450万円に到達しました。第二新卒の時期はキャリア形成の入口であり、この時期に選んだ環境が後の年収カーブを大きく左右するのです。
つまり、第二新卒で転職する際には「今いくらもらえるか」だけでなく「5年後にいくら稼げるか」を基準に判断することが重要です。
第二新卒が年収を上げるための戦略
第二新卒で年収を上げるには「戦略」が欠かせません。新卒のように一括採用で横並びの給与が決まる時期は終わり、この段階からは「自分で選び、工夫して交渉する」ことが収入差を生み出します。ここでは第二新卒が年収を上げるために実践すべきポイントを詳しく解説します。
スキルアップと資格取得の重要性
給与交渉や求人応募で有利になる最大の武器は「スキルと資格」です。特に第二新卒はまだ実務経験が浅い分、客観的に証明できる資格が強いアピール材料になります。例えばIT業界では「基本情報技術者」「応用情報技術者」、不動産業界では「宅地建物取引士」、会計・経理なら「日商簿記2級」などが即効性のある資格です。
資格を持っていなくても、オンライン学習や業務外での勉強を続けていることを伝えるだけで「学習意欲が高い人材」と評価されることがあります。第二新卒はポテンシャル採用の側面が強いため、伸びしろを示すことが給与アップの交渉材料になるのです。
また、英語力を証明するTOEICや、グローバル系の資格を持っていると、外資系企業や大手企業での採用時に待遇が良くなる可能性があります。キャリア初期に学んだことは今後の基礎体力になるので、給与だけでなく将来のキャリア価値を高める投資と考えましょう。
前職経験を活かす“隣接業界転職”
年収を下げずに転職する最も現実的な方法は「隣接業界・職種」への転職です。例えば、法人営業をしていた人がメーカーの営業やITサービスの営業に移る場合、商談スキルや顧客対応の経験は即戦力として評価されやすく、給与が維持またはアップする可能性が高いです。
逆に、全く未経験の業界に飛び込む場合は、新卒同様の給与テーブルに設定されやすいため、収入ダウンにつながりやすいのが現実です。「これまでの経験をどう活かすか」を考えた転職戦略が、年収を落とさないポイントになります。
実例として、事務職から人事アシスタントに転職したFさんは、給与は維持しつつ「採用」「労務」といった幅広い経験を積み、その後のキャリアアップで年収50万円増を実現しました。隣接分野を選んだことが功を奏したケースです。
業界選びのポイント
業界ごとの給与水準を知ることは非常に重要です。例えば、金融・不動産・コンサル・ITは20代前半でも350万円以上が期待できる一方、小売や飲食、福祉系は年収250〜280万円程度にとどまることもあります。求人票に書かれた月給だけでなく、「昇給率」「賞与」「福利厚生」もチェックし、トータルで比較することが必要です。
特に注目すべきは「昇給カーブ」です。初任給は低くても昇給が早い業界では、数年で年収が大きく伸びる可能性があります。逆に初任給が高くても昇給がほとんどない業界では、長期的に見ると不利になる場合があります。
つまり、第二新卒の給与戦略は「短期的な額面年収」と「長期的な生涯年収」の両方を意識して業界選びを行うことが肝心です。
転職エージェントの活用法
第二新卒での給与交渉は、自分一人で行うにはハードルが高いです。そこで重要になるのが「転職エージェントの活用」です。転職エージェントは企業との関係性を持っているため、応募者が直接言いにくい給与や条件の交渉を代行してくれます。
例えば、リクルートエージェントでは「職務経歴書の添削」や「推薦状の作成」に加えて、企業への給与交渉を行ってくれるケースが多くあります。マイナビエージェントは20代・第二新卒のサポートに特化しており、未経験職種への挑戦を後押しする求人も豊富です。
また、dodaやビズリーチは求人数が多く、比較しながら給与水準の高い求人を探すのに適しています。えーかおキャリアのように「定着率97%」といったフォローに強みを持つサービスもあり、長期的なキャリアを考える人におすすめです。
給与交渉は一人で戦うのではなく、プロのサポートを得ることが年収アップの近道です。実際、転職エージェントを経由して転職した人の7割以上が「年収アップに成功した」というデータも出ています。
戦略的に「見せ方」を工夫する
給与を上げたいなら「自分の価値をどう伝えるか」が重要です。職務経歴書には「業務内容」だけでなく「成果」を数字で書きましょう。例えば「売上◯%アップに貢献」「新規顧客◯件獲得」など、数字で示すことで採用担当に分かりやすく伝わります。
さらに面接では「これまでの経験が御社でどう活かせるか」を具体的に話すことで、給与アップを交渉する余地が生まれます。第二新卒は経験が浅いからこそ、「可能性」だけでなく「既に出せる価値」を強調することが欠かせません。
給与交渉のポイント
第二新卒が年収アップを狙うなら、給与交渉は避けて通れないプロセスです。とはいえ「まだ若いのに交渉なんてできるの?」と不安に思う方も多いでしょう。確かに社会人経験が浅い分、強気に出るのは難しいですが、適切な準備とタイミングを知っていれば、年収を下げずに転職することは可能です。ここでは交渉の具体的なポイントを解説します。
交渉のタイミングと方法
給与交渉を行うベストタイミングは「最終面接前」または「内定前後」です。最終面接に入る段階では企業側も採用の意思を固めつつあるため、この時点で希望年収を伝えると交渉の余地が生まれます。一方、内定通知後に初めて希望を伝えると「印象が悪い」と受け取られることもあるので注意が必要です。
また、一次面接や二次面接で「希望年収は?」と聞かれた際に、はっきり答えられるよう準備しておきましょう。ここで「いくらでもいいです」と答えてしまうと、自分の市場価値を低く見積もられてしまいます。逆に根拠を持って「前職の年収が◯万円でしたので、最低でも同水準を希望します」と伝えられると、誠実さと自己分析力をアピールできます。
交渉の方法は直接口頭で伝えるのが基本です。メールで希望年収を伝えるのは簡単ですが、「責任感がない」「大事なことを文章で済ませる人」という印象を与えてしまう可能性があります。できる限り面談や電話などで直接やり取りするのが望ましいでしょう。
成功するための準備
給与交渉で成功するためには「準備」がすべてです。準備不足のまま「もっと給料が欲しい」と訴えても、企業側は納得してくれません。具体的には以下の点を整えておく必要があります。
- 市場調査:応募する業界・職種の平均年収を調べ、自分の希望が妥当かを確認する。
- 前職の実績:売上貢献、業務効率化、顧客満足度向上など、具体的な成果を数字で用意する。
- 将来性の提示:「入社後3年でリーダー職を目指す」「資格取得で業務範囲を広げる」など、今後の成長を示す。
例えば、前職で「新規顧客を1年で30社獲得し、売上を15%伸ばした」といった数字を提示すれば、企業も「給与を上げても元が取れる人材だ」と判断しやすくなります。若手であっても成果や努力を具体的に伝えることで、交渉を有利に進められるのです。
好印象フレーズとNG回答例
給与交渉では「伝え方」によって印象が大きく変わります。以下は実際の面接で役立つ表現例です。
好印象のフレーズ例
- 「御社の給与規定を尊重したうえで、可能であれば前職同等の◯万円程度を希望いたします」
- 「スキルを活かして御社に貢献できると考えておりますので、前職よりやや上の水準を検討いただければ嬉しいです」
- 「長期的に成果を出す覚悟がありますので、将来的な昇給のチャンスについてもお伺いしたいです」
NG回答例
- 「いくらでも大丈夫です」→自分の市場価値を下げる。
- 「とにかく高い年収が欲しいです」→動機が不純に見える。
- 「御社の提示額には納得できません」→敵対的に映る。
大切なのは「企業の規定を尊重しつつ、自分の希望を根拠とともに伝える」姿勢です。相手に歩み寄る姿勢を見せながら、譲れないラインは明確に示すことが理想です。
エージェントを通じた交渉のメリット
第二新卒にとって、給与交渉を自分で行うのは心理的なハードルが高いものです。そこで役立つのが転職エージェントです。エージェントは普段から企業とやり取りをしており、求職者が直接言いにくい給与や条件を代わりに交渉してくれます。
例えばリクルートエージェントでは「推薦状」を企業に送る際に希望年収を記載することがあり、これによって内定時点で条件交渉がスムーズに進むケースがあります。マイナビエージェントは若手支援に特化しているため「年収は下げたくない」という20代のニーズに合わせた交渉をしてくれるのが特徴です。
「直接伝える勇気がない」場合は、転職エージェントに依頼することで心理的負担を減らしつつ希望を通せるのも大きなメリットです。
第二新卒の給料に関するよくある質問
第二新卒の給料に関する疑問は非常に多く寄せられるテーマです。特に新卒と同じ扱いになるのか、昇給やボーナスはどうなるのかといった点は、多くの転職希望者が気になるところです。ここでは、よくある質問にQ&A形式で答えていきます。
第二新卒は新卒と同じ扱いになるのか?
結論から言えば「企業によって異なる」が正解です。大手企業では給与テーブルがきっちりと決まっているため、第二新卒は新卒と同じ給与水準からスタートするケースが多いです。例えば、社会人経験が1〜2年あっても「キャリアリセット」と見なされ、22歳の新卒社員と同じ初任給ラインからやり直しということもあります。
ただし、前職で得たスキルや実績を活かせる職種に転職した場合は、経験者採用として扱われるケースもあります。特に営業職やエンジニア職では「即戦力」と判断されることが多く、新卒より高い給与からのスタートも珍しくありません。つまり「新卒扱いになるかどうか」は応募する業界や職種によって大きく変わるのです。
転職後の給料はどう決まるのか?
転職後の給与は、基本的に以下の3つの要素で決まります。
- 企業の給与テーブル:企業ごとに基本給や昇給幅が定められており、その枠組みの中で給与が設定されます。
- 前職の給与水準:多くの企業は「前職給与を参考にする」ため、極端に下げられることは少ないですが、業界が変わるとリセットされることも。
- スキル・経験・交渉力:資格や実績があると給与交渉の余地が広がります。エージェント経由なら交渉がスムーズになることも多いです。
例えば、ITエンジニアとして実務経験が1年ある場合は「新卒枠」ではなく「経験者枠」として評価されることもあります。一方、未経験で事務職などにキャリアチェンジする場合は、新卒と同じ給与から再スタートとなることが多いです。
第二新卒で大手企業に入ったら給料は上がる?
大手企業は給与水準が高いため、第二新卒でも転職すれば年収アップにつながる可能性があります。例えば、地方の中小企業で年収260万円だった人が、大手メーカーに転職して年収350万円になるケースはよくあります。
ただし大手企業は競争率が高く、第二新卒の採用枠が少ない場合もあります。また、入社後は昇進や昇給が年功序列的になる傾向が強いため、「入社直後に大幅アップ」というより「長期的に安定して高い水準を得られる」点に強みがあります。
ボーナスはどれくらいもらえる?
企業によって大きく差がありますが、一般的に第二新卒も正社員であればボーナス支給の対象になります。ただし入社初年度は在籍期間が短いため、満額ではなく「在籍月数に応じて按分支給」となるのが一般的です。
また、外資系やベンチャー企業では「ボーナスなし」「成果報酬のみ」というケースもあるため、求人票や面接で必ず確認しておきましょう。ボーナスがあるかどうかで年間収入は50万円以上変わるため、見落とすと大きな差が出ます。
昇給率はどのくらい?
昇給率は業界や企業規模によって大きく異なります。大手企業では毎年5,000〜10,000円程度の昇給が一般的ですが、ベンチャー企業では実力次第で入社2年目から月給が5万円以上増えることもあります。
第二新卒にとって重要なのは「今の年収」より「将来どのくらい伸びるか」です。仮に入社時は年収300万円でも、3年後に400万円まで伸びる会社なら、中長期的に見れば有利な選択といえるでしょう。
生涯年収に影響する?
「第二新卒で転職すると生涯年収は下がるのでは?」という不安もよく聞かれます。確かに短期的に収入が下がる可能性はありますが、長期的に見ればキャリアの方向性次第で逆に大きく伸ばせます。
例えば、給与水準が低い業界にそのまま留まるより、第二新卒のうちに年収の高い業界へ転職してキャリアを積む方が、30代以降の生涯年収は大幅に高くなる可能性があります。つまり第二新卒の時期は「多少下がっても将来に向けた投資」と考えることができるのです。
第二新卒の年収アップに向けた成功事例
実際に第二新卒で転職して年収アップを実現した人の体験談は、多くの転職希望者にとって参考になります。ここではいくつかの成功事例を紹介しつつ、どのような戦略が有効だったのかを解説します。
成功した転職者の体験談
ケース1:販売職から不動産営業へ転職したAさん(24歳)。前職では年収260万円程度でしたが、転職後は基本給25万円+インセンティブ制度により初年度で年収470万円を突破。営業スキルを磨きながら、成果に応じて収入が大きく伸びました。
ケース2:地方の中小企業で事務をしていたBさん(23歳)。年収は240万円と低めでしたが、マイナビエージェントを活用し大手メーカーの人事アシスタントへ転職。年収は320万円に上がり、昇給カーブも期待できる環境を得ました。
ケース3:飲食業界で長時間労働をしていたCさん(25歳)。「ワークライフバランスを改善しつつ年収を維持したい」との希望で、エンジニア職へキャリアチェンジ。最初は年収280万円でしたが、資格取得と実務経験を積んだ結果、3年目には450万円に到達しました。
年収アップに成功した業種・職種
第二新卒で年収アップを実現しやすいのは、次のような業界・職種です。
- 不動産営業:高額インセンティブがあり、結果を出せば20代で年収600万円も可能。
- ITエンジニア:スキル次第で需要が高く、未経験からでも資格やポートフォリオ次第で高待遇が狙える。
- 金融業界(証券・保険など):資格があれば評価されやすく、成果報酬制度も充実。
- コンサルタント:論理的思考力や問題解決能力を活かせる人は、若手でも高い給与水準からスタートできる。
逆に、小売や介護、飲食など人材不足の業界は初任給は比較的低めですが、安定性や社会的ニーズが高いという強みもあります。自分の価値観と照らし合わせて判断することが大切です。
まとめ:第二新卒の給料を上げるために必要なこと
第二新卒の給料は「下がる可能性」もあれば「大きく上がるチャンス」もあるのが現実です。重要なのは、単に目先の金額にとらわれず、長期的なキャリア形成を見据えて判断することです。
今後のキャリアプランを考える
一時的に給料が下がっても、将来的にスキルを磨き年収を大きく伸ばせる環境なら、長期的にはプラスに働きます。「5年後・10年後の自分がどうなっていたいか」を明確にして、給与だけでなく成長や働き方のバランスを考えましょう。
転職活動の重要なポイント
成功するためには以下の点が欠かせません。
- 業界・職種ごとの給与水準を把握する
- 資格やスキルを武器にする
- エージェントを活用して給与交渉を代行してもらう
- 短期的な年収だけでなく「生涯年収」を意識する
これらを実践すれば、第二新卒であっても「給料が下がるから仕方ない」という諦めではなく、「戦略的に年収を上げていく」選択が可能になります。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!