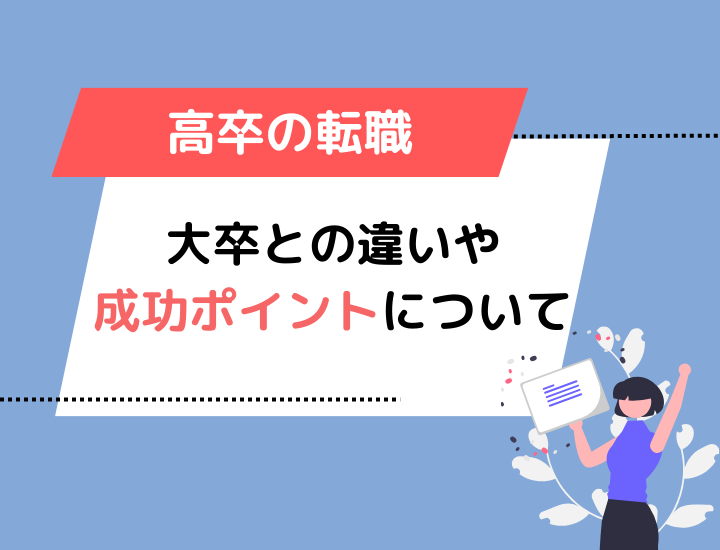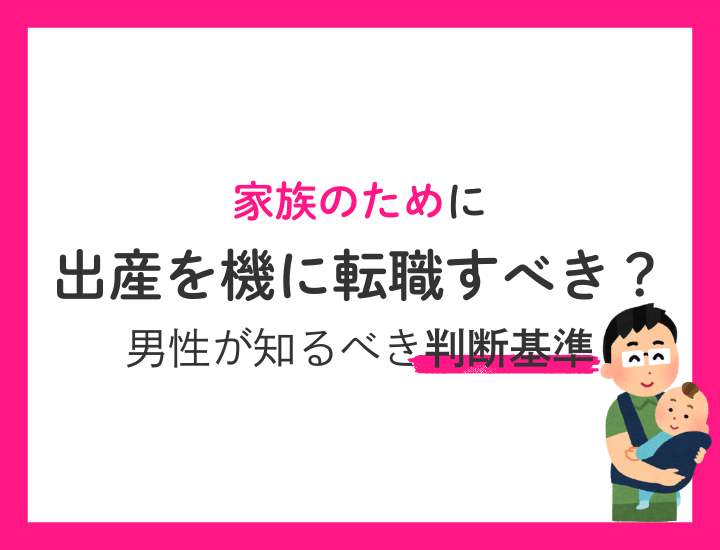話すのが好きな人必見!向いている仕事一覧と活かし方
「話すのが好き」を仕事に活かす方法
「人と話すのが好き」という強みは、社会で大きな武器になります。特に現代の職場では、専門スキルや知識以上に、人との関係を築き、相手を動かす力が評価されやすくなっています。話す力は、人材不足やサービス業の多様化が進む日本において、今後ますます重要度を増すスキルです。
例えば営業や教育、カウンセリング、イベント運営など「話すこと」そのものが成果に直結する仕事は数多く存在します。また直接的に話すことが中心でない職場でも、チームで成果を上げるためには必ずコミュニケーション能力が求められます。つまり「話すのが好き」という特性を持つ人は、選べるキャリアの幅が広いのです。
このセクションでは、自分の「話す力」の特徴をどう整理し、それをキャリアに結びつけるかを解説します。
自分の強みを理解する
「話すのが好き」と一口に言っても、人によって強みの出方は異なります。会話を盛り上げるのが得意な人もいれば、聞き役として安心感を与えられる人、論理的に説明できる人、人前で堂々と話せる人など、タイプはさまざまです。
例えば友人から「一緒にいると楽しい」と言われる人は場を和ませる力があり、接客やイベント業に向いています。一方「あなたと話すと安心する」と言われる人はヒアリング型の強みがあり、カウンセラーや医療介護職で力を発揮できます。さらに「プレゼンが上手」と言われる人は営業や教育の現場に適性があります。
自分がどの場面で一番自然に力を発揮できるかを言語化することは、キャリア選びに直結します。自己分析ノートをつけたり、他者からのフィードバックを集めるのも効果的です。
話すことを活かせる職種を探す
自分の強みが整理できたら、求人やキャリア情報の中から「話す力」が求められる仕事を探しましょう。ポイントは求人票の「求める人物像」に注目することです。「明るく対応できる方」「傾聴力がある方」「コミュニケーション力を活かしたい方歓迎」と書かれている求人は、まさに話すのが好きな人にぴったりです。
また近年はリモートワークの普及により、オンラインでの会話力も求められるようになっています。画面越しでも表情や声のトーンで安心感を与えられる人材は、営業・教育・カスタマーサポートなど幅広い分野で重宝されます。
このように、話す力を活かす方法は多様です。大切なのは「自分の強みを把握し、それを必要としている職場を選ぶ」ことです。次のセクションでは、具体的にどのような職業が「話すのが好きな人」に向いているのかを詳しく見ていきましょう。
話すのが好きな人に向いている職業
「話すのが好き」という強みは、多くの職業で活かせます。特に、人との関わりが仕事の中心となる営業職や教育関連、カウンセラーなどは代表的な選択肢です。ここでは、話す力を活かせる職種を詳しく紹介し、それぞれの仕事内容ややりがい、向いている人の特徴まで解説します。
営業職
営業職は「話すのが好きな人」に最もおすすめの職業のひとつです。顧客の課題を聞き出し、自社の商品やサービスで解決策を提案するため、会話力がそのまま成果に直結します。特にルート営業やカウンター営業などは、雑談を交えながら信頼関係を構築する力が大切です。
営業は成果が数字に表れるためプレッシャーもありますが、その分成果に応じてインセンティブや昇進のチャンスも豊富です。「人と話すことが自分の成績や収入に直結する」という実感を得られるのは大きな魅力です。
カウンセラー
心理カウンセラーやキャリアカウンセラーなどは「聞く力」と「安心感を与える話し方」が求められる職業です。相手の悩みや不安を受け止め、整理しながら解決の方向性を示していくため、会話を通じて人を支えることができます。
カウンセラーは資格が必要になる場合もありますが、福祉や教育、企業の人事など幅広い場面で需要が拡大しています。特にメンタルヘルスへの関心が高まる近年、「人の気持ちに寄り添える話し方」を持つ人は重宝される傾向にあります。
講師・教育関連
学校の先生、塾講師、企業研修の講師など「教育」に関わる職業は、説明力とコミュニケーション力が不可欠です。話すのが好きな人は、授業や研修で相手を惹きつけ、モチベーションを高める役割を果たせます。
また教育の現場は「相手の成長を間近で見られる」喜びも大きな魅力です。生徒や受講者の「わかった!」という表情を直接見られるのは、話す力を活かす仕事ならではのやりがいです。
イベントプランナー
イベントプランナーは、結婚式や展示会、地域イベントなどの企画・運営を担う仕事です。顧客との打ち合わせや当日の進行、スタッフとの連携など、コミュニケーションが中心となる業務ばかりです。
突発的なトラブルに対応する場面も多く、冷静に状況を整理しながら話で人を動かす力が重要です。「人を喜ばせたい」「場を盛り上げたい」という気持ちを持つ人にはぴったりです。
このように、営業・カウンセラー・教育・イベントプランナーなどは「話すのが好き」という強みを最大限に発揮できる職業です。次のセクションでは、これらの仕事を選んだときに得られるメリットと、注意すべきデメリットについて解説していきます。
話す仕事のメリットとデメリット
「話すのが好き」という強みを仕事に活かすと、やりがいや成長の機会が数多く得られる一方で、精神的・体力的な負担も伴います。ここでは、代表的なメリットとデメリットを具体例とともに詳しく解説します。
メリット:人間関係が豊かになる
話す仕事では、顧客・同僚・取引先など多様な人と関わるため、自然と人間関係の幅が広がります。営業で築いた信頼が長期的なビジネスにつながったり、教育や介護の現場で「ありがとう」と感謝される瞬間を得られるなど、日常的に人との絆を深めることができます。
また心理学の研究でも、幸福度の高さは収入よりも人間関係の質に影響されるとされており、話すことを軸にした仕事は人生そのものの充実度を高める可能性が高いのです。
メリット:スキルが身につき市場価値が高まる
話す仕事を通じて、プレゼン力・傾聴力・課題解決力といった「ポータブルスキル(業種を越えて通用するスキル)」が磨かれます。これらはAIや自動化では代替しにくいため、今後も評価され続ける力です。
たとえば営業経験を活かして人事や広報へキャリアチェンジしたり、接客経験をもとにカスタマーサクセスに転職したりと、幅広い業界で応用可能な資産となります。
メリット:AI時代でも価値が残る
近年AIの発達により多くの業務が自動化されていますが、人と人との会話には「感情に寄り添う力」が不可欠です。医療や介護、教育や接客の場面では、表情や声のトーン、気遣いといった要素が信頼を生みます。これらはAIが再現するのが難しく、人間ならではの強みが活かせる分野として今後も安定した需要が期待できます。
デメリット:ストレスや疲労が溜まりやすい
一方で、人と話す仕事は精神的に疲れやすい側面があります。接客や営業では理不尽なクレームや厳しい交渉を経験することも多く、感情労働として心に負担を抱えるケースも少なくありません。
特に共感力の高い人は、相手の悩みを自分ごとのように抱え込み「共感疲労」に陥りやすい傾向があります。そのため、適度な距離感とセルフケアの習慣が必要です。
デメリット:成果主義や長時間労働のリスク
営業やイベント業界などでは成果主義が色濃く、数字や結果が強く求められます。成果が出ないと評価が下がり、モチベーションの維持が難しくなることもあります。また、イベントや接客業では夜間や土日の勤務が発生し、生活リズムが乱れやすいのも現実です。
ただし近年は、オンライン営業やリモート接客の導入により負担軽減が進んでいます。環境を選ぶことで、デメリットを和らげることは可能です。
このように、話す仕事には「人とのつながりを資産にできる大きな魅力」と「ストレスや成果プレッシャーといった難しさ」の両方が存在します。次のセクションでは、こうした環境で成果を上げるために必要なスキルを具体的に解説していきます。
話す仕事で求められるスキル
「話すのが好き」という強みを活かすには、単におしゃべりが得意なだけでは不十分です。ビジネスの場では、相手の状況や立場を考慮しながら適切に会話を進めるスキルが求められます。ここでは、話す仕事で特に重要な3つのスキルを具体例を交えて紹介します。
コミュニケーション能力
最も基本となるのはコミュニケーション能力です。自分の考えをわかりやすく伝える力に加え、相手の話をよく聞き、本音や感情をくみ取る傾聴力も含まれます。
営業では「顧客が何に困っているか」を聞き出す力が必要ですし、教育現場では「どこでつまずいているか」を把握することが重要です。「話す力」と「聞く力」のバランスを取ることで、相手の信頼を得られます。
このスキルは一朝一夕で身につくものではありませんが、日常的に意識して実践を繰り返すことで確実に伸ばせます。
感情のコントロール
人と話す仕事では、常に相手の感情と向き合う必要があります。ときには理不尽なクレームや厳しい要求を受けることもあるでしょう。その際に必要なのが感情をコントロールする力です。
心理学ではこれを「感情労働」と呼び、サービス業や接客業では特に大きな負担とされています。冷静に状況を判断し、感情を乱さずに対応できる人は信頼され、昇進やキャリアアップにもつながります。
深呼吸やマインドフルネス、休憩の習慣などを取り入れることで、感情コントロール力を日常的に鍛えることが可能です。
問題解決能力
話す仕事の本質は「会話を通じて課題を解決すること」です。単に会話を楽しむのではなく、相手が求める答えや改善策を見つける必要があります。そのために不可欠なのが問題解決能力です。
たとえば営業では「予算がない」という顧客に対して、代替案や分割提案を考える必要があります。教育現場では「勉強にやる気が出ない」生徒に対して、モチベーションを引き出す工夫をすることが求められます。
会話のゴールを「相手の課題解決」と設定することで、信頼を得るだけでなく、自分自身の成果にもつながります。
このように、話す仕事で成功するには「コミュニケーション能力」「感情のコントロール」「問題解決能力」の3つをバランスよく磨くことが重要です。次のセクションでは、これらのスキルを活かして高収入を狙える仕事について解説します。
高収入を狙える話す仕事
「話すのが好き」という強みは、高収入を目指すキャリアに直結します。特に成果主義や専門性の高い職種では、会話力やプレゼン力がそのまま収入に影響することも少なくありません。ここでは代表的な高収入の「話す仕事」を取り上げ、特徴やキャリアパスを詳しく解説します。
コンサルタント
経営コンサルタントやITコンサルタントは、企業の課題を解決に導く専門職です。クライアントから課題を聞き取り、改善策を提案するため、論理的な話し方と信頼を得る会話力が欠かせません。
未経験から挑戦する場合は、まず企業の企画職やシステム関連の職種で経験を積み、その後にコンサルティング会社へ転職するルートが一般的です。成果報酬型のプロジェクトも多いため、若くして年収800万円〜1,000万円以上を目指せる職業でもあります。
さらにコンサルタント経験を積むと独立も可能になり、自分自身で顧客を抱えてフリーランスや起業家として活躍できる道も開けます。専門性と話す力を掛け合わせれば、大きな収入アップが期待できるでしょう。
営業マネージャー
営業の現場で成果を出し続けると、チームを束ねる営業マネージャーへの昇進が見えてきます。マネージャーの役割は「自分の営業成績」ではなくチーム全体を動かす力です。部下のモチベーションを高め、戦略を立案し、顧客との交渉をまとめ上げるなど、会話力が幅広く求められます。
営業マネージャーの年収は大手企業で800万〜1,200万円に到達するケースも多く、インセンティブや役職手当が上乗せされるため、高収入を狙えるポジションです。人を導くリーダーシップと説得力ある会話力が求められる分、やりがいも大きいのが特徴です。
アナウンサー
テレビやラジオで活躍するアナウンサーは「言葉のプロフェッショナル」といえる職業です。正確な発声や滑舌はもちろん、臨機応変な対応力や表現力も求められます。キー局勤務であれば年収800万円〜1,200万円、人気フリーアナウンサーになればさらに高額を狙うことも可能です。
競争率は非常に高く、倍率数百倍に達する採用試験もあります。そのため、アナウンススクールでの専門訓練や、局アナからフリーへのステップアップといった長期的な準備が必要です。それでも「自分の声や言葉で人を動かす」という喜びは、他の職業では得難い魅力があります。
また、アナウンサー経験はナレーションや司会業、講師業などにも応用可能で、将来的なキャリアの幅も広いのが強みです。
このように、コンサルタント・営業マネージャー・アナウンサーといった職業は「話す力」がそのまま高収入につながります。次のセクションでは、ワークライフバランスを重視する人のために、土日休みが取りやすい「話す仕事」を紹介します。
土日休みが取りやすい話す仕事
「話すのが好き」な人の中には、収入ややりがいだけでなく、ワークライフバランスを重視したい方も多いでしょう。特に土日休みを確保できるかどうかは、生活リズムやプライベートの充実度に直結します。ここでは、土日休みを取りやすい代表的な職業を紹介します。
公務員
市役所や区役所、県庁などで働く公務員は、基本的に土日祝が休みです。窓口業務では市民からの相談や申請対応を行い、わかりやすく説明する力や柔軟な対応力が求められます。
例えば「住民票の発行」や「子育て支援の相談」など、生活に直結するやり取りを行うため、感謝される場面も多い仕事です。「あなたに対応してもらえて良かった」と直接言われる瞬間がモチベーションにつながります。
さらに、公務員は福利厚生が充実しており、産休・育休や有給休暇も取りやすい環境が整っています。給与水準は民間と比べると大幅に高いわけではありませんが、安定性と休日の確保を重視する人には最適です。
教育関連職
学校の教員、塾講師、大学職員など教育関連の仕事も、比較的土日休みを確保しやすい職種です。ただし、学校行事や入試シーズン、塾の講習会などでは休日出勤が必要になる場合もあります。
教育現場の魅力は、生徒や学生と直接関わり、その成長を間近で見守れることです。授業や進路指導を通じて「先生のおかげで頑張れた」と言われる瞬間は、大きなやりがいにつながります。
また、教育分野で培ったスキルは人材育成や企業研修、教材開発などにも活かせるため、将来的なキャリアチェンジの幅も広いのが特徴です。安定した休日を確保しながら、人と深く関わる仕事をしたい人におすすめです。
オフィスワーク(事務・人事・広報)
人と話す要素がありながら、カレンダー通りの休みを取りやすいのがオフィスワーク系の職種です。人事や広報は特に「話す力」を活かせる場面が多く、社員面談や採用面接の対応、社内イベントの企画運営などで活躍できます。
事務職は「話す」イメージが少ないかもしれませんが、電話対応や社内調整、顧客対応など意外と会話が必要なシーンが多く存在します。安定した働き方をしつつ、人との会話を大切にできるのが魅力です。
このように、公務員・教育関連職・オフィスワークなどは「話す力を活かしながら土日休みを確保できる職業」です。次のセクションでは、話す仕事を目指す際に役立つ資格について解説します。
話す仕事に必要な資格
話す仕事では、経験やスキルだけでなく、資格があることで転職やキャリアアップが有利になる場合があります。特に「コミュニケーション力」を客観的に証明できる資格や、専門知識を裏付ける資格があると、企業からの信頼度も高まります。
秘書検定
秘書検定は、ビジネスマナーや敬語、電話対応、来客応対などのスキルを証明できる資格です。話す力だけでなく、丁寧で分かりやすい説明力を示す指標として評価されます。
企業の受付や人事・広報などで「即戦力として活躍できる人材」と見なされやすく、転職時にもアピールポイントになりやすい資格です。
サービス接遇検定
接客や応対スキルを評価する資格で、ホテル、飲食、医療関連など、人と直接関わる仕事に役立ちます。お客様やクライアントに信頼される話し方や振る舞いを学べるため、話す仕事全般に活かせます。
特にカスタマーサポートや営業職では、この資格を持っていることで「安心して任せられる人材」と評価されるケースが増えています。
TOEIC・英語系資格
海外対応や外資系企業、観光・接客業などでは、英語力を証明する資格が有利です。TOEICのスコアは、書面だけでなく面接での会話力の裏付けとしても活用できます。
英語を使った電話対応やプレゼンテーションなど、話す仕事の幅を広げたい人にとって有力な資格です。語学力があることでキャリアの選択肢が格段に増えるのもメリットです。
話す力を証明するその他の資格
ほかにも、話す仕事に役立つ資格として以下のようなものがあります。
- サービス介助士:福祉や高齢者対応で必要な会話力や心遣いを証明
- コミュニケーション検定:対人スキルや説明力を測定
- ビジネス実務法務検定:法律や規則に関する知識を持つことで安心して話せる能力をアピール
資格を持つことで、単に「話すのが得意」という自己評価ではなく、客観的に能力を証明できるため、面接や転職活動での説得力が増します。
次のセクションでは、話す仕事の中でも特に需要が高く、未経験でも挑戦しやすい職種について解説します。
未経験から始めやすい話す仕事
「話すのが好きだけど、これまで話す仕事の経験はない…」という方でも大丈夫です。話す力は、業界や職種を問わず活かせるポータブルスキル(持ち運び可能な能力)です。未経験でも挑戦しやすく、育成前提で採用されやすい職種を紹介します。
コールセンター(インバウンド/アウトバウンド)
未経験でも採用されやすい代表的な仕事がコールセンター業務です。インバウンド(受電)業務では、お客様の問い合わせに対し、的確に対応しながら話す力を磨くことができます。
アウトバウンド(架電)業務は営業要素が強くなりますが、マニュアルやトークスクリプトが用意されているケースが多いため、未経験者でも安心です。
短期間で話し方や対応スキルが鍛えられるため、「まずは話す仕事の現場を体感したい」という人にも向いています。
接客・販売スタッフ
アパレルや家電量販店、カフェなどの接客業は、常にお客様と会話する機会があります。自然なコミュニケーションを通して、相手のニーズを引き出す力を養うことができます。
とくに飲食業やアパレルは未経験歓迎の求人が多く、学生時代のアルバイト経験が活かせる場合もあります。接客経験を積めば、将来的にリーダー職や店舗マネージャーへのキャリアアップも可能です。
人材系アドバイザー・キャリアカウンセラー
求職者と面談し、最適な求人を紹介する人材アドバイザーの仕事は、話す力が大きな武器になります。相手の悩みや希望を丁寧に引き出し、信頼関係を築くスキルが求められるため、未経験でも「話すのが得意」な人は歓迎されやすいです。
特に20代向けの転職支援サービスなどでは、同世代であることが共感を生みやすく、フラットな会話が強みになります。
営業職(インサイドセールスなど)
「営業はハードルが高そう」と思われがちですが、最近では訪問ではなく電話やWebでの営業(インサイドセールス)が主流になってきています。研修やOJTが充実している企業も多く、話すのが好き=武器になる仕事です。
成果が数字として見えるため、達成感も得やすく、コミュニケーション能力に自信がある方はぜひ検討してみましょう。
話す仕事は「未経験だから無理」と諦める必要はありません。話すことが好きという気持ちは、間違いなく強力なポテンシャルです。次のセクションでは、話す仕事で長く活躍していくためのキャリアの築き方を紹介します。
話す仕事でキャリアを築くステップ
話すのが得意という強みを、長期的なキャリアへとつなげるには、目の前の業務をこなすだけでなく、計画的な成長戦略が必要です。ここでは、話す仕事で「やりがい」と「安定」を両立するためのステップを紹介します。
ステップ1:現場経験を積んで“自分らしい話し方”を身につける
まずは現場での経験が何よりも大切です。接客、営業、コールセンターなど、どんな職場であっても「人と話すこと」に慣れ、自分なりのペースや表現を見つけていきましょう。
経験を重ねることで、マニュアルに頼らない“あなただけの会話力”が磨かれていきます。これは他の誰にも代替できない強みとなります。
ステップ2:フィードバックを受けて改善を繰り返す
話す仕事では、「話しっぱなし」ではなく、相手の反応を見て調整する力が重要です。上司や同僚、時にはお客様からの声を素直に受け止め、改善していく姿勢が求められます。
「話す力=伝わる力」であることを意識し、相手に届く言葉を選ぶトレーニングを積みましょう。
ステップ3:資格やスキルで専門性をプラスする
「ただ話せる」から、「●●分野に詳しい×話すのが得意」へと進化すると、市場価値が格段に上がります。心理学、英語、医療、法律など、興味のある分野と組み合わせて学んでみましょう。
また、話す内容のロジックや構成力を高めるために、プレゼンテーションやロジカルシンキングの研修を受けるのも効果的です。
ステップ4:マネジメントや講師ポジションへのキャリアアップ
ある程度の経験を積んだら、後輩指導やチーム運営など、次のステップに進むチャンスがやってきます。特に教育担当や研修講師、マネージャーなどは、話す力+指導力が評価されるポジションです。
「話すことで人を導く」キャリアは、年齢を重ねても続けやすく、社会的意義も大きいのが特長です。
ステップ5:SNSや副業で自分の“話す力”を発信
近年では、YouTubeやTikTok、Voicyなどで「話すこと」を副業やパーソナルブランディングに活かす人も増えています。
企業に属さずとも、“話すことそのもの”が価値となる時代。本業とは別に、自分の得意を活かした発信を始めてみるのも一つの道です。
こうしたステップを意識しながら進んでいけば、「話すことが好き」という個性を軸に、あなたらしいキャリアがきっと描けるはずです。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!