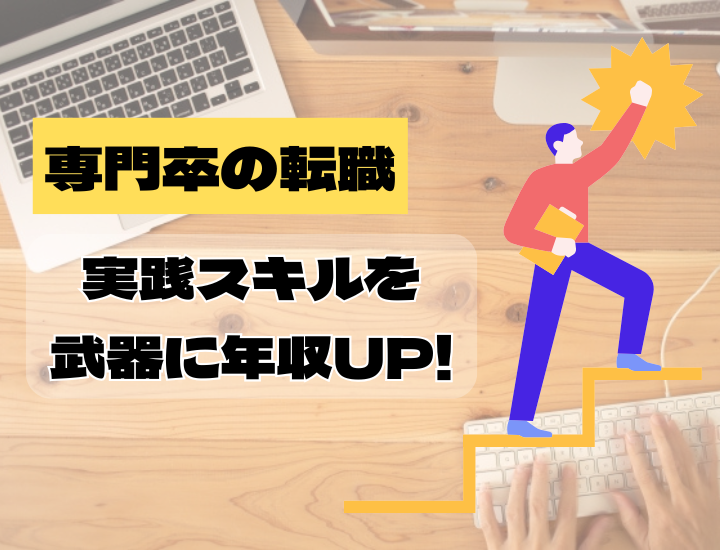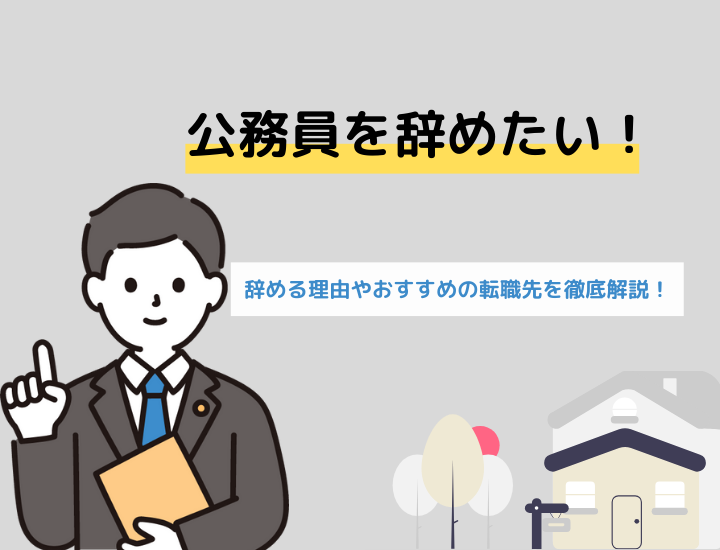はじめに
近年の転職市場では、実務経験やスキルを重視する企業が増えており、学歴だけで評価されることは少なくなってきています。
しかし、専門学校卒業の方の中には、転職活動において学歴が不利に働くのではないかと不安を抱える方も多いでしょう。
実際のところ、専門学校での学びは、即戦力となる実践的なスキルや専門知識の習得に特化している点で、むしろ強みとなる可能性も秘めています。
本記事では、専門卒の方が転職市場でどのように自身の強みを活かし、希望する転職を実現できるのか、具体的な方法をお伝えしていきます。
専門学校卒と大卒の転職市場の違い
転職市場において、専門学校卒と大学卒では求人の傾向に違いが見られます。
大卒向けの求人は総合職や管理職候補として募集されることが多い一方、専門卒者向けの求人は、特定の専門スキルや資格を活かせる職種が中心となっています。
しかし、これは必ずしもデメリットではありません。
むしろ、専門的なスキルを持つ人材として、企業から即戦力として高く評価されるケースも増えています。
とくに技術職や専門職においては、学歴よりも実務能力が重視される傾向が強まっています。
専門卒の転職は大卒と比べると不利なのか
結論から言えば、専門卒というだけで転職が不利になることはありません。
確かに、一部の大手企業では学歴要件を設けている場合もありますが、多くの企業では実務経験やスキル、人物面を重視する傾向にあります。
専門学校で習得した技術や知識が、直接業務に活かせる職種においては、むしろ専門卒者の方が評価されるケースも少なくありません。
大切なのは、自身の専門性をどのように活かせるかを明確に示すことです。
学歴別の年収差
令和4年賃金構造基本統計調査では、学歴ごとの年収が下記のように結果がでています。

学歴別の年収の平均は、高校が約274万円、専門学校が約294万円、高専・短大が約293万円、大学が約363万円、大学院が約464万円でした。
これらより、学歴が高いほど賃金が高くなる傾向があるとわかります。
ただし、こちらはあくまで平均です。
専門性の高い職種や技術職では、学歴に関係なく、スキルや実績に応じた評価を受けることも十分にありえます。
とくに、IT業界や専門技術を要する業界では、資格保有や実務経験が重視され、専門卒でもスキル次第で大卒以上の年収を得ている方も多く存在します。
また、転職によってさらなるキャリアアップを果たし、年収アップを実現している事例も増えています。
高卒・専門卒・短大卒それぞれの特徴と強み
転職市場において、学歴の違いはそれぞれ独自の強みを作り出します。
高卒、専門卒、短大卒は、それぞれが持つ特徴を活かすことで、効果的な転職活動を展開することが可能です。
ここでは、各学歴における具体的な強みと、それを活かした転職戦略について詳しく見ていきましょう。
専門卒者の転職における強み
専門卒者の最大の強みは、実践的な専門知識とスキルを持っていることです。
専門学校では、特定の業界や職種に特化した実践的なカリキュラムを提供しているため、即戦力として評価される可能性が高くなります。
また、在学中に関連資格を取得している割合が高いことも大きなアドバンテージとなるでしょう。
たとえば、IT系の専門学校を卒業した場合、プログラミングやネットワーク構築などの実務的なスキルを持っています。
さらに、情報処理技術者試験などの資格を保有していることが多く、企業にとって即戦力となり得ます。
美容系や医療系の専門学校卒業者も同様で、現場で必要とされる技術や知識を体系的に学んでいることが評価されます。
高卒者の転職における強み
高卒者の強みは、早期から実務経験を積んでいることにあります。
大卒や専門卒と比較して、より長い実務経験を持っていることが多く、その間に培った現場力は非常に価値があります。
とくに製造業や営業職などでは、実践的な経験と現場での問題解決能力が高く評価されます。
また、若いうちから実務に携わることで、職場でのコミュニケーション能力や業務の効率化能力が自然と身についていることも強みです。
理論よりも実践を重視する職種では、この実務経験の豊富さが大きなアドバンテージとなり、転職市場での競争力を高めることができるでしょう
短大卒者の転職における強み
短大卒者の特徴は、専門的な知識と幅広い教養をバランスよく身につけていることです。
2年間という期間で、専門分野の学習と一般教養科目をコンパクトに学ぶことができ、両方の要素を持ち合わせていることが強みとなります。
とくに、事務職や営業職などでは、この幅広い知識とバランスの取れた教養が活きてきます。
また、短期間で効率的に学習する能力が身についているため、新しい職場での適応力も高いと評価されます。
さらに、専門学校よりも一般教養が充実していることから、総合職としてのキャリアを築きやすい特徴があります。
専門卒が転職で有利になる3つの理由
専門学校卒業者が転職市場で有利になる理由として、下記3つが挙げられます。
- 専門的な技術・資格を持っている
- 実践的な経験を積んでいる
- 業界特化型の知識がある
近年では、即戦力となる人材を求める企業が増加しており、専門的なスキルをもつ専門卒者を高く評価してくれます。
人材不足が深刻化する昨今で、実践的な知識と技術を持つ専門卒者の需要は、ますます高まる傾向にあります。
ここからは、専門卒者が転職市場で評価される具体的な理由についてくわしく解説します。
専門的な技術・資格を持っている
専門学校での学びの特徴は、業界で必要とされる技術や資格の取得に特化していることです。
たとえば、IT分野であればプログラミング言語やネットワーク技術、医療分野では医療事務や看護技術など、実務で即座に活用できる専門的なスキルを習得しています。
また、多くの専門学校では、カリキュラムの一環として資格取得をサポートしているため、業界で認められた資格を持っていることも大きな強みとなるでしょう。
とくに国家資格や業界で認知度の高い資格の取得率は、専門学校は高めといわれています。
これらの資格は転職時の重要な武器となります。
加えて、資格取得に向けた学習過程で得られる深い専門知識は、実務での問題解決能力の向上にも直結します。
実践的な経験を積んでいる
専門学校のカリキュラムの特徴として、実習や演習の時間が多く設けられていることが挙げられます。
これにより、在学中から実践的な経験を積むことができます。
たとえば、デザイン系の学校であれば実際のクライアントワークを経験したり、調理師養成学校であれば実際の調理場での実習を行ったりします。
さらに、多くの専門学校では企業との連携プログラムを実施しており、インターンシップや企業プロジェクトへの参加機会も豊富です。
このような実践的な経験は、就職後の実務にスムーズに対応できる力となり、企業からも高く評価されます。
新しい設備や技術に触れる機会も多々あり、業界の最新動向にも精通していることが多いです。
これらも大きなアドバンテージとなっています。
業界特化型の知識がある
専門学校では、特定の業界に特化した専門的な知識を体系的に学ぶことができます。
業界用語や最新トレンド、業界特有の課題や解決方法など、その分野で働くために必要な知識を包括的に身につけることができます。
また、多くの専門学校の講師陣は、実務経験者や現役のプロフェッショナルで構成されているため、実践的な知識やノウハウを直接学ぶことができます。
さらに、業界のネットワークづくりという面でも、専門学校での学びは有利に働きます。
同じ志を持つ仲間や、業界で活躍する講師との繋がりは、転職活動時にも貴重な情報源となります。
このような業界特化型の知識と人脈は、転職後の早期戦力化を可能にし、企業にとって大きなメリットとなります。
専門卒が転職時にアピールすべき4つのポイント
専門学校での経験を転職活動で最大限に活かすためには、戦略的なアプローチが必要不可欠です。
採用担当者に自身の価値を正確に伝えるためには、具体的な実績とその活用方法を明確に示さなければなりません。
ここからは、専門卒者が特に意識すべき具体的なアピールポイントについて、実践的な方法とともに詳しく解説していきます。
学んだ専門スキルの具体的な提示
転職活動では、専門スキルを具体的な数値や成果と共に提示することが重要です。
たとえば、Webデザインを学んだ場合、「Adobe製品を使用して5つの企業サイトを制作し、そのうち2つが実際にクライアントに採用された」といった具体的な実績を示すことができます。
また、チーム制作でのリーダー経験や、クライアントとの直接のやり取りなど、技術以外の付随するスキルも重要なアピールポイントとなります。
とくに言及したいポイントとしては、そのスキルによって何が実現できるのか、企業にどのような価値を提供できるのかという視点での説明です。
場合によっては、ポートフォリオサイトやGitHubなどの技術的な実績を示せるプラットフォームも効果的に活用しましょう。
在学中の実績や成果
専門学校での学びの成果は、できるだけ定量的に示すことが効果的です。
たとえば、学内コンペでの入賞実績、学外プロジェクトでの成果、研究発表での評価など、具体的な数値や第三者評価を含めて説明しましょう。
また、課題制作での工夫点や、困難を乗り越えた経験なども、具体的なエピソードとして伝えることで説得力が増します。
さらに、業界団体主催のイベントやコンテストへの参加実績、インターンシップでの評価なども、専門性を裏付ける重要な実績となります。
これらの経験を通じて得られた気づきや成長についても、具体的なエピソードを交えながら説明することで、学びに対する真摯な姿勢をアピールできるといえるでしょう。
取得資格の活用方法
資格保有をアピールする際は、単なる資格名の列挙ではなく、その資格によって何ができるようになったのかを具体的に説明することが重要です。
たとえば、情報処理技術者試験の資格であれば、システム設計からセキュリティ対策まで、どの領域でどのような課題解決ができるのかを具体的に示します。
また、資格取得のために行った学習プロセスや、その過程で得られた知見についても言及すると良いでしょう。
さらに、複数の資格を組み合わせることで可能となる付加価値や、今後取得予定の資格についても触れることで、継続的な自己啓発への意欲を示すことができます。
資格は、実務能力を証明する客観的な指標として、転職活動での重要な差別化要素となります。
職務経歴書での専門性アピール
職務経歴書は、専門性を体系的にアピールできる重要なツールです。
経歴書の構成では、専門学校での学びと実務経験を効果的に関連付けることが重要です。
たとえば、専門学校で学んだ理論や技術が、実際の業務でどのように活かされているのかを具体的に示します。
また、自己PRセクションでは、専門性を軸としたキャリアビジョンを明確に示し、志望企業でその専門性をどのように活かし、どのような価値を提供できるのかを具体的に説明します。
さらに、専門分野における最新動向への知見や、関連する技術・知識の学習状況なども記載することで、専門性の維持・向上への意欲を示すことができます。
職務経歴書は、あなたの専門性を総合的にアピールする場として、慎重に作り込む必要があります。
高・専・短卒で年収アップを実現できる職種
ではここからは、高校・専門学校・短大を卒業した人が、転職で年収アップをしやすい職種を紹介します。
転職を考える際、年収アップは重要な検討要素の一つです。
とくに今までの経歴で得た強みを発揮できる職種は数多く存在し、適切なキャリア選択によって着実な収入増を実現できます。
とくに収入アップが期待できる代表的な職種は下記のとおりです。
- 技術職系
- 営業職
- 専門職系
- サービス業
- 事務職
各職種について、くわしく見ていきましょう。
技術職系
技術職は、専門学校卒業者が最も活躍できる分野のひとつです。
とくにIT業界では、プログラミングやネットワーク、セキュリティなどの専門知識を持つエンジニアの需要が高まっています。
実際に、プログラマーやシステムエンジニアの平均年収は、経験を積むことで大幅な上昇が期待できます。
また、建築や電気、機械設計などの技術職も、資格と実務経験を組み合わせることで、年収アップの可能性が広がるでしょう。
技術職系は、新技術への適応力を持つ技術者への需要が高く、継続的な学習意欲がある人材が、より高い報酬を得られる傾向にあります。
営業職
営業職は、専門知識を活かしたコンサルティング型の提案が可能な職種です。
医療機器営業やIT製品の営業など、専門的な知識が要求される分野では、専門学校での学びが直接的に活かせます。
営業職の魅力は、基本給に加えて歩合給やインセンティブなどの変動給が期待できることです。
さらに、顧客との信頼関係構築には専門知識が不可欠であり、専門学校で培った知識は、高額案件の成約にもつながります。
実績を重ねることで、年収が大きく伸びる可能性が高い職種といえます。
専門職系
医療事務、介護福祉士、保育士などの専門職は、資格を活かせる典型的な職種です。
これらの職種は、慢性的な人材不足が続いており、経験者への需要が特に高まっています。
また、美容師やエステティシャンなどの美容関連職も、技術力と経験を積むことで、独立開業も視野に入れることができるでしょう。
ほかにも、会計や法務などの専門事務職も、資格取得と実務経験を組み合わせることで、着実な収入アップが期待できます。
複数の専門資格を組み合わせることで、より高い価値を提供でき、会社からも評価されやすいです。
サービス業
ホテル・旅館業や外食産業などのサービス業界では、専門学校で学んだホスピタリティやマネジメントスキルが大いに活かせます。
調理師や製菓衛生師などの資格を持つ人材は、技術力を磨くことで、より上位のポジションや好条件での転職が可能です。
また、顧客サービスの質が直接的に評価される業界であるため、専門的なスキルと経験を持つ人材は重宝されます。
さらに、語学力などを組み合わせることで、インバウンド需要にも対応できる人材として、より高い待遇を得られる可能性があります。
事務職
一般的な事務職でも、専門学校で学んだスキルを活かすことで、より高い待遇を得ることが可能です。
とくに、経理事務や人事事務などの専門事務職では、資格を持っていることが大きなアドバンテージとなります。
また、DXが進む現代では、IT関連の知識やスキルを持つ事務職人材への需要も高まっています。
データ分析やシステム管理などの付加価値を提供できる人材は、従来の事務職より高い年収を期待できるといえるでしょう。
業界特化型の知識を持つ専門事務職は、その専門性を活かしてキャリアアップを図りやすいです。
専門卒の転職を成功させる方法
専門卒の転職を成功に導くためには、戦略的なアプローチと綿密な準備が不可欠です。
ただ漠然と求人サイトを眺めるのではなく、自身の強みを最大限に活かせる転職先を見つけることが重要です。
専門卒ならではの特徴を活かした具体的な転職成功のためには、下記3つのポイントを押さえましょう。
- 業界研究と求人市場の把握
- スキルの棚卸しと強みの整理
- 転職エージェントの活用
それぞれのポイントについて説明します。
業界研究と求人市場の把握
効果的な転職活動を行うためには、まず徹底的な業界研究と求人市場の動向把握が重要です。
専門学校で学んだ分野に関連する業界では、最新のトレンドや技術革新、法改正などの情報をしっかりと押さえておきましょう。
業界専門誌や関連ウェブサイト、セミナーなどを通じて、市場動向や求められる人材像を把握した上で、次の転職先を考えてみてください。
また、求人情報だけでなく、その業界で活躍している専門卒の先輩社会人の事例も参考になります。
LinkedInやWantedlyなどのビジネスSNSを活用して、同じ専門学校出身者のキャリアパスを研究することで、自身の可能性を広げることができます。
さらに、業界団体や職能団体が主催する勉強会や交流会に参加することで、生きた情報を得ることもできるでしょう。
スキルの棚卸しと強みの整理
専門学校で習得したスキルや知識を、現在の市場ニーズに照らし合わせて整理することが重要です。
具体的には、専門学校での学習内容、取得資格、実習経験、さらには現在の職場で得た実務経験などを詳細にリストアップしてみてください。
このとき、単なるスキルの列挙ではなく、それぞれのスキルで実現できる具体的な成果や、企業にもたらせる価値を明確にすることが重要です。
また、専門スキル以外の強みも見落とさないようにしましょう。
たとえば、専門学校での課題制作やグループワークで培ったチームワーク力、実習先での接客経験、学園祭といったイベント運営経験なども、企業にとって魅力的なスキルとなり得ます。
これらの経験を具体的なエピソードとして整理し、面接での説明材料として準備することで、より説得力のあるアピールが可能になります。
転職エージェントの活用
転職エージェントの活用もとても効果的です。
専門スキルを持つ人材を求める企業の中には、転職エージェントを通じてのみ募集をかけているケースも多くあります。
エージェントとの面談では、自身の経歴や希望する転職先についてくわしく説明しましょう。
とくに専門学校での学びや実習経験、現在の業務内容などについて具体的に伝えることで、より的確な求人を紹介してもらえます。
また、エージェントを活用すれば、履歴書や職務経歴書の作成支援、面接対策など、きめ細かなサポートを受けることが可能です。
なお、エージェントとの関係構築では、定期的なコミュニケーションを心がけ、市場動向や求人情報について積極的に情報交換を行うことが重要です。
これにより、より質の高い転職支援を受けることができ、希望に沿った転職先との出会いの可能性が高まります。
専門卒転職者のよくある質問
転職活動を始めるにあたって、専門学校卒業者の多くが様々な不安や疑問を抱えています。
- 未経験職種への転職は可能ですか?
- どのタイミングで転職活動を始めるべきですか?
- 専門分野と違う業界への転職は難しいですか?
- 面接でよく聞かれる質問とその対応方法は?
- 職歴が短いのですが転職できますか?
これらは転職相談の現場で頻繁に寄せられる質問です。
具体的な対応方法とともに解説していきます。
未経験職種への転職は可能ですか?
未経験職種への転職は十分に可能です。
とくに、専門学校で培った基礎知識や学習能力は、新しい分野への挑戦において大きな強みとなります。
実際に、多くの企業が専門的なバックグラウンドを持つ人材を、その学習能力や適応力を評価して採用しています。
ただし、全くの未経験分野へ転職する場合は、事前準備が重要です。
たとえば、転職先で必要となる基本的な知識やスキルを独学で習得したり、関連する資格を取得したりすることで、自身の可能性をアピールできます。
また、副業やアルバイトなどで実務経験を積むことも、未経験分野への転職を有利に進める方法のひとつです。
どのタイミングで転職活動を始めるべきですか?
転職活動の開始時期は、業界の特性や自身の状況によって異なりますが、一般的には希望する転職時期の3〜6ヶ月前から始めましょう。
これは、求人探しから内定獲得、そして現職の引き継ぎまでを考慮した期間です。
専門職で転職活動をおこなう場合、スキルの確認や実技試験などが必要となることもあり、余裕を持った準備期間が重要です。
また、業界の繁忙期や採用時期なども考慮に入れる必要があります。
業界の特性を理解した上で、最適なタイミングを見極めましょう。
専門分野と違う業界への転職は難しいですか?
専門分野とは異なる業界への転職は、一見すると困難に思えるかもしれませんが、決して不可能ではありません。
むしろ、専門学校で身につけた専門知識や技術は、異なる業界でも十分に活かすことができます。
たとえば、デザイン系の専門学校卒業者が、そのクリエイティブな視点を活かしてマーケティング職に転職するなどの例があります。
重要なのは、自身のスキルや経験を新しい業界でどのように活かせるかを具体的に説明できることです。
また、転職先の業界について十分な理解を示し、なぜその業界を選んだのかという明確な動機を持っていることも、面接では重要なポイントとなります。
面接でよく聞かれる質問とその対応方法は?
面接では、応募者の人物像を多角的に理解するために、様々な質問が投げかけられます。
ここでは、特に頻出の質問とその効果的な回答方法について詳しく説明していきます。
【自己紹介に関する質問】
「簡単な自己紹介をお願いします」という質問では、学歴、職歴、保有資格などの基本情報に加え、自身の強みや志望動機のエッセンスを2-3分程度で簡潔にまとめることが重要です。
専門学校での学びや実習経験、そこから得られた知見についても触れると良いでしょう。
【転職理由に関する質問】
「なぜ転職を考えているのですか」という質問では、現職場や前職場の批判は避け、キャリアアップや新しい挑戦への意欲など、前向きな理由を説明することが望ましいです。
具体的には、「より専門性を高めたい」「習得したスキルを活かせる環境を求めている」といった建設的な回答が効果的です。
【志望動機に関する質問】
「なぜ当社を志望されたのですか」という質問では、企業研究の成果を示しつつ、自身のキャリアプランとの整合性を説明します。
企業の理念や事業内容と、自身の専門性やスキルがどのようにマッチするのかを具体的に述べることが重要です。
【強みと弱みに関する質問】
「あなたの強みと弱みを教えてください」という質問では、強みについては具体的なエピソードを交えて説明し、弱みについては克服に向けた取り組みも併せて説明することが効果的です。
専門学校での学びや実務経験を通じて培った専門性は、重要な強みとしてアピールできます。
【キャリアビジョンに関する質問】
「今後のキャリアプランを教えてください」という質問では、3-5年程度の具体的な目標と、それを達成するための行動計画を説明します。
資格取得計画や、スキルアップの方向性なども含めると、より説得力のある回答となります。
【入社後の抱負に関する質問】
「入社後、具体的にどのような貢献ができますか」という質問では、自身の専門性やスキルを活かした具体的な提案ができると良いでしょう。
ただし、現実的で実現可能な提案を心がけることが重要です。
職歴が短いのですが転職できますか?
職歴が短くても転職は可能です。
専門学校卒業者の場合、在学中の実習経験や資格取得が評価されることが多く、それらを効果的にアピールすることで、職歴の短さをカバーできます。
ただし、短期間での転職を繰り返すことは、将来的なキャリア形成において不利になる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
転職先選びでは、自身のキャリアビジョンに合致した企業を選ぶことが重要です。
また、面接では転職理由を明確に説明し、長期的なキャリア展望を示すことで、職歴の短さによるマイナスイメージを払拭することができます。
現職での具体的な成果や、独学での自己啓発の取り組みなどをアピールすることも効果的です。
まとめ:専門卒の強みを活かした転職を
専門学校卒業者の転職において、最大の武器となるのは実践的なスキルと専門知識です。
学歴による制限を気にするよりも、専門学校で培った技術力、取得した資格、実習経験などを積極的にアピールすることが重要です。
とくに技術職やIT関連、医療系などの専門性が求められる職種では、即戦力として高く評価される可能性が高いでしょう。
また、転職市場では実務能力重視の傾向が強まっており、専門卒者にとって追い風となっています。
転職成功のカギは、自身の強みを明確に理解し、それを効果的にアピールすること。
業界研究と市場動向の把握、転職エージェントの活用など、戦略的なアプローチを心がけることで、専門性を活かしたキャリアアップを実現できます。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!