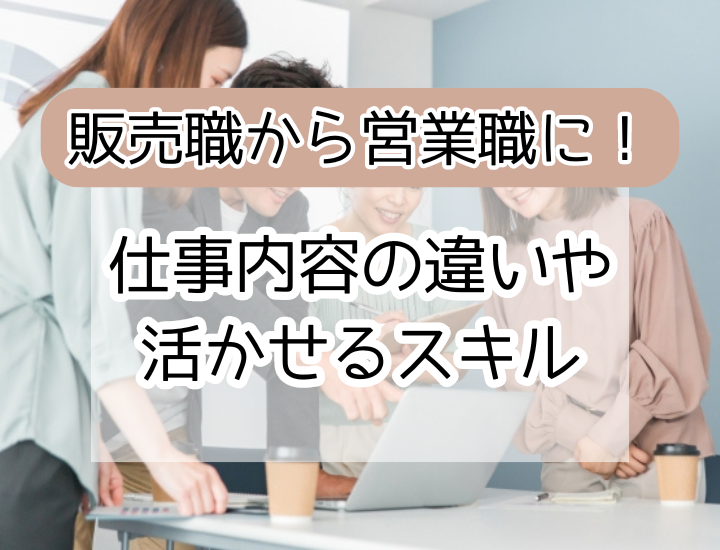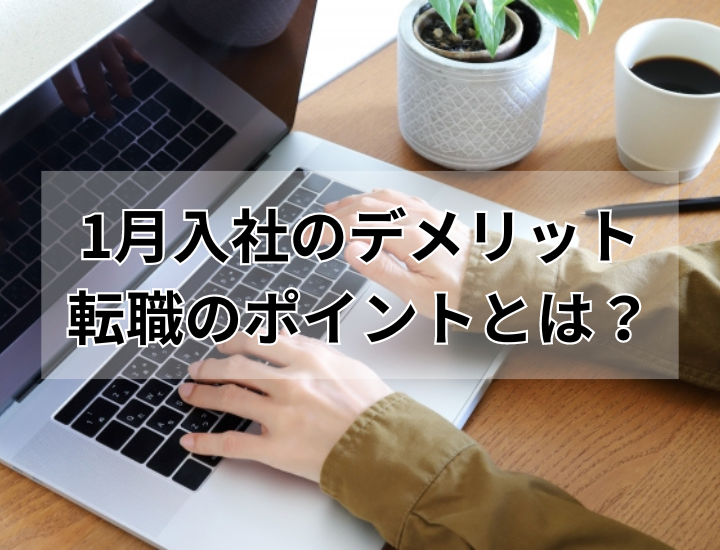
1月入社のデメリット6選|メリットや転職のポイント、ボーナスとの関係性について
はじめに
年末年始を迎えるタイミングで、新しい年に向けて転職を検討する方も増えるのではないでしょうか。
1月は、年度の切り替えの時期として多くの人に選ばれる人気のタイミングですが、冬のボーナスや年末調整といった気になるポイントも見逃せません。
「1月に転職することのメリットとデメリットは?」「ボーナスはどう扱われる?」といった疑問を解消することで、より充実した転職活動を目指せます。
本記事では、1月入社を検討する際に押さえておきたいポイントや不安解消のためのヒントを詳しくお伝えします。
【1月入社のデメリット】1月入社するデメリット
ここでは、1月入社に伴うデメリットを詳しく見ていきます。
1月は転職に適した時期として注目されがちですが、注意すべきポイントも存在します。
ポジティブな側面だけでなく、リスクや懸念点にも目を向けることで、より良い選択をすることが可能になります。
時期的に忙しい
年末年始は多くの企業で長期休暇が取られるため、その前後はどうしても業務が立て込むことが多くなります。
特に、現職の引き継ぎ作業については、早めの準備が求められるでしょう。
たとえば、有給休暇を消化したい場合、12月初旬や中旬には業務を終える必要があるため、見越して引き継ぎ計画を立てる必要があります。
また、12月は稼働日数が少ないため、通常業務が忙しくなる傾向もあります。
このような状況を考慮し、円滑に引き継ぎを行うには計画的な準備が必要です。
冬のボーナスが満額受け取れない可能性がある
1月の転職を予定している場合、冬のボーナスをどのように扱うかは大きな検討事項となります。
多くの企業では12月にボーナスが支給されますが、退職者への支給額は企業の裁量に委ねられるため、満額を受け取れる保証はありません。
最善の策としては、ボーナス支給を確認してから退職の意思を伝えることですが、その場合、1月入社が難しくなる可能性もあります。
また、転職後の最初のボーナスについても、算定期間に在籍していない期間があるため、満額を受け取るのは難しいと考えられるでしょう。
転職後1度目のボーナスは満額受け取れない
現職のボーナスについて触れましたが、転職先での最初のボーナスも満額支給されることはほとんどありません。
ボーナスには算定期間が設けられており、夏のボーナスの場合、多くの企業では10月から翌年3月が対象期間となります。
そのため、1月に新たな職場に入社した場合、少なくとも算定期間のうち3ヶ月間は在籍していないことになります。
この未在籍期間を考慮すると、初回のボーナスは満額の半分以下となる可能性が高いでしょう。
転職先でのボーナスを満額受け取るためには、10月に入社するのが最適です。
しかし、そうすると現職での冬のボーナスが減額される可能性があり、両方を満額で受け取るのは難しい現実があります。
ボーナス額を考慮することは大切ですが、それ以上に重要なのは、理想とする企業で働くという目標に集中することです。
ボーナスに目を奪われすぎず、長期的な視点で転職を検討することをおすすめします。
ライバルが多い
1月は長期連休を挟んで転職を実現しやすい時期であり、多くの求職者にとって好タイミングとされています。
しかし、そのメリットの裏にはライバルの多さという課題が存在します。
同じ時期に転職を目指す人が多いため、特に魅力的な求人には応募が集中し、競争倍率が高くなる傾向があります。
たとえば、大企業や待遇の良い企業の求人では、ライバルが多いことで選考を突破するハードルが上がるかもしれません。
このような時期に転職活動を成功させるためには、早めの行動と徹底した事前リサーチが重要です。
希望する企業がいつ頃中途採用を行うか、またその情報をどのように把握するかがポイントになります。
特定の企業や業界を希望している場合、時期にこだわらず求人が出た時点で活動を開始することが望ましいでしょう。
スケジュールが組みにくい
1月入社を目指すことは、想像以上にスケジュール管理が難しい場合があります。
企業側が入社時期の調整に対応してくれるなら問題は少ないですが、通常は求人が出された時点で企業側は早急な人材確保を求めています。
そのため、「1月入社」を希望すると、企業の予定に合わない場合があります。
たとえば、9月に内定が出た場合に「1月入社を希望」と伝えると、企業が難色を示すことも考えられます。
多くの企業では、求人掲載後すぐに入社してもらうスケジュールを想定しているため、入社時期にこだわる場合は事前に採用スケジュールを確認しておくことが重要です。
求人情報には、選考期間や入社予定時期が明記されているケースも多いため、情報を丁寧に確認することで1月入社に向けた計画を立てやすくなります。
計画的かつ柔軟に進めることが重要です。
応募先を選択しづらい
1月以降は、4月入社を見据えた企業の求人が一気に増える時期です。
選択肢が多いことは求職者にとって好ましい状況ですが、転職の方向性が定まっていない場合、どの企業に応募すべきか迷う原因にもなります。
このような状況では、応募先を絞り込むのが難しくなることがあります。
さらに、1月は多くの人が転職活動を始めるタイミングでもあります。
そのため、求人に対する競争が激化しやすく、ライバルが増えることもデメリットのひとつです。
特に、11月から12月は売り手市場の傾向がありますが、1月以降は買い手市場に変わるため、求職者にとって不利になるケースもあります。
加えて、多くの企業が4月入社を目指して採用活動を行うため、採用スケジュールが詰まりやすくなります。
面接の日程が重なる、複数の企業から同時に連絡が来るなど、スケジュール管理が難しくなることが考えられるでしょう。
転職の軸をしっかりと定め、計画的に活動を進めることが重要です。
自分のキャリアにおける優先順位を明確にし、どのような条件を重視するのかを具体化することで、応募先の選択に迷うリスクを軽減できます。
また、転職エージェントを活用するのも有効な方法です。
エージェントを利用すれば、応募先選びやスケジュール管理をサポートしてもらえるだけでなく、効率的な転職活動を実現するためのアドバイスを受けられます。
【1月入社のデメリット】1月入社するメリット
1月入社にはデメリットだけでなく、多くのメリットも存在します。
メリットとデメリットを比較検討することで、自分にとって最適なタイミングを見極めやすくなるでしょう。
ボーナスを受け取ってから退職できる
1月入社を目指す最大の利点は、現職の冬のボーナスを受け取った後で退職ができる点です。
多くの企業では冬のボーナスの支給時期が12月に固定されており、1月に転職する場合、ほぼ確実にボーナスを手にした後での退職が可能です。
特に、ボーナスの査定時期に在籍していれば、よほどの事情がない限り満額を受け取れる可能性が高いでしょう。
ただし、注意すべき点として、規模の小さな企業では、社長や経営陣の裁量によりボーナスが減額される場合もあります。
一方で、大企業や就業規則がしっかりと整備された職場では、個人の感情に左右されることなくボーナスが支給されるため、そのような心配はほとんどありません。
区切りが良い
年末年始の長期連休を挟むことで、気持ちの切り替えがしやすいのもメリットです。
通常、月末退職から月初入社の場合、心身の余裕がないまま新しい職場に挑むことになります。
しかし、年末年始を挟むことで、少なくとも1週間程度の休息期間が確保できるため、現職での業務に区切りをつけ、心機一転して新しい職場に挑む準備が整います。
また、年末年始は社内イベントや忘年会が行われる場合が多く、退職の挨拶を伝える機会にも恵まれるため、円満退職を実現しやすいタイミングともいえるでしょう。
同期が多い場合がある
1月は転職を希望する人が多く、企業によっては同時期に複数の人が入社することがあります。
このため、会社の規模次第では同期が複数いる状況も珍しくありません。
同期がいる場合、同じタイミングで新しい環境をスタートする仲間がいるため、会社に馴染みやすくなり、孤独感や不安を軽減できます。
また、1月は新年会や交流イベントを開催する企業も多く、職場の人間関係を築きやすい時期です。
一般的な入社時期では交流の機会が少なく、慣れない環境で相談相手が見つからず、不安を感じることもあります。
しかし、1月入社で同期や上司、先輩と新年会などで自然に関係を築けると、職場での悩みを気軽に共有できる環境が生まれるでしょう。
求人が多い
転職市場では、求人の量は時期によって変動します。
特に求人数がピークに達するのは11月で、9月頃から徐々に増え始めます。
1月入社を目指す場合、10月から11月頃には本格的な転職活動をスタートするのが理想的です。
求人数が多い時期は選択肢が広がるため、自分に合った職種や企業を見つけやすく、転職成功率も上がるでしょう。
ただし、求人数が増えると同時に、同じように転職を目指すライバルも増えるため、準備不足のままでは思わぬ失敗を招く可能性があります。
そのため、しっかりと計画を立て、企業研究や履歴書・面接準備を怠らないことが重要です。
気持ちを切り替えやすい
1月入社のメリットとして挙げられるのが、年末年始の長期連休を活用できる点です。
週末だけの短い休みを挟んで新しい職場に行く場合、心の準備が整わないことがありますが、年末年始を挟むことでゆっくりと休息を取れるでしょう。
家族や友人と過ごす時間が増えたり、旅行に出かけたりすることでリフレッシュでき、自然と気持ちが前向きになります。
結果、ポジティブな状態で新しい環境に飛び込めるため、スムーズな転職が可能となります。
1月入社は、長期連休を利用して心身をリセットし、新たな挑戦に向けて良いスタートを切るための絶好のタイミングといえるでしょう。
【1月入社のデメリット】夏のボーナスが減額される理由
1月に転職した場合、最初の夏のボーナスが減額される可能性が高いでしょう。
ボーナスの査定期間と、期間内での在籍状況が大きく影響するためです。
以下に夏のボーナスが減額される理由と具体的な影響について詳しく解説します。
査定期間と在籍期間の影響
1月入社の場合、夏のボーナスの査定期間中に在籍している期間が非常に短いため、満額支給はほぼ期待できません。
多くの企業では、夏のボーナスの査定期間を10月から3月まで、冬のボーナスを4月から9月までとしており、この期間中の在籍状況が評価に反映されます。
たとえば、1月に入社すると、10月から3月の査定期間のうち在籍期間は約3ヶ月となり、半分以下の期間しか評価対象とならないことになります。
このため、最初の夏のボーナスは大幅に減額されるか、場合によっては寸志程度、あるいは支給されない可能性も考えられます。
ボーナス算定の仕組み
ボーナスの算定方法は企業ごとに異なりますが、主に以下の3種類が一般的です。
- 基本給連動型:基本給に一定の係数を掛けて支給額を決定する方法。
査定期間中の在籍期間が短いと、その分ボーナス額も少なくなります。 - 業績連動型:会社の業績や個人の成果に応じて支給額が変動する方法。
入社直後は貢献度が低いと判断される場合が多く、減額される可能性があります。 - 決算賞与型:業績に基づいて一時的に支給されるタイプ。
業績の影響が大きく、支給されないこともあります。
さらに、試用期間がある場合、その期間はボーナスの評価対象外とされることが一般的です。
1月入社の社員は、こうした要因によってボーナスがさらに減額されるリスクがあります。
ボーナス減額による具体的な影響
減額されたボーナスは、生活設計や資金計画に影響を与える可能性があります。
ボーナスはまとまった金額であるため、貯蓄や特別な支出に充てることを考えている人にとっては、想定していた金額が得られないことが大きな課題となるでしょう。
特に転職直後は、引っ越し費用や新生活に必要な物品購入など出費がかさむ時期でもあります。
ボーナス減額は、こうした出費を補うのを難しくするかもしれません。
また、現職の夏のボーナスを満額受け取った後で転職を検討することで、ボーナスがもらえない期間を短縮する選択肢もあります。
【1月入社のデメリット】1月入社でボーナスを多めにもらうには
工夫次第で、1月入社でもボーナスをより多く受け取ることが可能です。
以下では、1月入社でボーナスを最大化するための具体的な方法について解説していきます。
1月入社とボーナスの関係性については、以下の記事もあわせて参考にしてください。
1月の転職・入社はいつからボーナスが貰える?ボーナスの仕組みから1月入社を目指すときの注意点まで詳しく解説
査定期間を把握する
ボーナスを最大化するためには、まず査定期間を正確に把握することが不可欠です。
一般的には、夏のボーナスの査定期間は前年の10月から3月、冬のボーナスは4月から9月とされています。
しかし、企業ごとに異なる場合があるため、転職先の就業規則や採用情報を確認する必要があります。
たとえば、夏のボーナスの査定期間が10月から3月の場合、1月入社では査定期間の半分程度しか在籍していないことになり、満額の支給を期待するのは難しいでしょう。
このような情報を事前に把握することで、入社日を調整し、ボーナスを最大限に受け取る戦略を立てられます。
査定期間が不明な場合は、面接時に採用担当者や人事に直接確認するのがおすすめです。
入社日を調整する
入社日を調整することで、ボーナスの受け取り額を増やせる可能性があります。
たとえば、夏のボーナスの査定期間が10月から3月の場合、1月よりも2月や3月に入社した方が査定期間内の在籍日数を増やせます。
ただし、入社を遅らせすぎると査定期間に全く在籍しないことになり、ボーナスが支給されないリスクもあるでしょう。
また、入社日によって研修や業務開始日が調整される場合もあるため、ボーナスだけでなく入社後のスケジュール全体を考慮することが大切です。
目標達成に注力する
入社後に目標達成に注力することも、ボーナスを増やすための有効な方法です。
多くの企業では、個人の目標達成度がボーナスの査定に大きく影響します。
売上目標の達成、契約件数の増加、あるいは業務上の成果が評価されるため、日々の業務で成果を出すことが重要です。
1月入社で査定期間が短い場合でも、目標達成による高い評価が得られれば、夏のボーナスを満額に近づける可能性があります。
また、上司や同僚からの評価が向上することで、その後のキャリアアップにもつながるでしょう。
転職先の評価基準を理解する
ボーナスを最大化するためには、転職先の評価基準を事前に理解することも重要です。
企業によっては、目標達成度以外にも能力評価や勤務態度、出勤日数などが査定に含まれることがあります。
評価基準を把握することで、どのような行動がボーナスに反映されるのかを知り、それに基づいて戦略を立てられます。
採用情報や企業ホームページには評価基準が記載されている場合があるため、事前に確認しておきましょう。
また、面接時に具体的な評価基準を質問することも効果的です。
冬のボーナスを見据える
1月入社の場合、夏のボーナスだけに注力せず、冬のボーナスを重視する戦略も効果的です。
冬のボーナスの査定期間は4月から9月までとされており、1月入社の場合、査定期間を十分にカバーできます。
そのため、冬のボーナスでは満額に近い金額を受け取れる可能性が高くなります。
入社後の半年間で積極的に成果を出すことにより、評価を高め、冬のボーナスを増やすことが可能です。
また、一部の企業では、冬のボーナスを夏より多く支給するケースもあるため、この時期に注力することでさらなる収入増加が見込めます。
【1月入社のデメリット】1月に入社するためのスケジュール
1月入社を目指す場合、しっかりとしたスケジューリングが成功につながるポイントとなります。
準備不足やスケジュールの管理ミスにより、入社時期が12月や2月にずれてしまうことも珍しくありません。
ここでは、1月に入社するための具体的なスケジュールについて解説します。
準備は秋から始める
1月入社を計画する際、転職準備は秋頃からスタートするのが理想的です。
応募時期は10月から11月が適していますが、履歴書や職務経歴書の作成は9月頃から取り組んでおくと安心です。
特に初めての転職では、職務経歴書の記載内容に悩むことがあるかもしれません。
新卒時代に慣れた履歴書やエントリーシートとは異なり、職務経歴書では過去の業務経験や担当したプロジェクトの詳細を書く必要があります。
たとえば、役職だけでなく、具体的にどのような業務に携わり、どのような成果を上げたかを明記する必要があります。
予想以上に時間がかかることも多いため、早めの準備を心掛けましょう。
また、応募の際には履歴書と職務経歴書が必要なことが一般的です。
事前にこれらを整えておくことで、気になる企業が見つかった際にすぐに応募できます。
企業のスケジュールを参考にする
企業の採用スケジュールを参考にすることも、1月入社を実現するために重要なポイントです。
多くの求人ページには「応募→書類選考(1週間)→面接→採用通知(2週間)」と具体的なスケジュールが記載されている場合があります。
また「応募から採用決定まで約1ヶ月」といった情報が記載されている場合もあるでしょう。
10月に採用スケジュールが1ヶ月程度の求人を見つけた場合、そのタイミングで応募すると1月入社が難しいことがあります。
一方で、その求人を見送った場合、11月から12月に再び同じ求人が掲載される保証はありません。
そのため、「1月入社」という時期を優先するか、「希望する企業」を優先するかを明確にしておくことが大切です。
もし、どうしても入社したい企業がある場合は、1月入社にこだわらず、見つけたタイミングで応募するのが良いでしょう。
【1月入社のデメリット】1月に転職するためのポイント
1月に転職を成功させるには、しっかりとした準備と戦略が必要です。
何となく行動してもうまくいく場合もありますが、計画的に進めることで成功率を高められます。
ここでは、1月転職を成功に導くための具体的なポイントを解説します。
スケジュールを考える
まずはスケジュールをしっかりと立てることが重要です。
1月入社を目指す場合、9月頃から転職準備を始めるのが理想的です。
特に履歴書や職務経歴書の作成には時間がかかるため、早めに準備を進めておきましょう。
最近ではWordやExcelでの作成が一般的になっていますが、企業によっては手書きの履歴書を好むところもあります。
手書きの場合、応募する企業ごとに作成する必要があるため、想像以上に時間と労力がかかります。
仕事をしながら転職活動を進める場合、週末しか時間を割けないケースも少なくありません。
そのため、履歴書と職務経歴書の作成にどれくらいの時間が必要かを把握し、応募をスムーズに行えるようスケジュールを組んでおきましょう。
複数の転職サイトを利用する
転職活動では複数の転職サイトを利用することで、より多くの求人情報にアクセスできます。
企業によっては、複数のサイトに求人を掲載している場合もあれば、特定のサイトのみに掲載している場合もあります。
また、非公開求人があるサイトも多いため、事前に複数のサイトへ登録しておくことで、幅広い選択肢を得られるでしょう。
転職サイトへの登録時には、職務経歴やスキルを詳細に記入することが求められることが多いので、準備を進めておけば、求人を見つけた際にすぐ応募できる状態になります。
自己分析を徹底する
自己分析をしっかりと行うことは、1月入社を目指す転職活動において欠かせません。
自己分析を通じて、自分の強みや弱みを明確にし、転職先でどのように活躍できるかを具体化できます。
たとえば、自分が関わったプロジェクトや達成した目標を振り返り、職務経歴書に具体的に記載することで、採用担当者に好印象を与えられます。
また、面接においても自己分析が役立つでしょう。
「自身のスキルがどのように企業に貢献できるか」を自信を持って説明することで、企業側にあなたの価値を効果的にアピールできます。
さらに、自己分析を通じて、自分が転職先に求める条件を明確にすることも可能です。
これにより、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的に活躍できる職場を選択できるでしょう。
【1月入社のデメリット】1月入社で気をつけること
1月に入社を目指す場合、いくつか注意すべき点があります。
以下に、1月入社をスムーズに進めるためのポイントを解説します。
源泉徴収票の提出
1月入社で特に注意が必要なのが、源泉徴収票の取り扱いです。
源泉徴収票は、その年の給与や税額、控除額を記載した重要な書類で、退職時に前職の会社から発行されます。
1月に転職する場合、12月で給与支払いが完了していれば、新しい職場に源泉徴収票を提出する必要はありません。
ただし、12月分の給与が翌年1月に支払われる場合は、転職先への提出が必要になることがあります。
もし判断が難しい場合は、転職先に確認するのが安心です。
また、源泉徴収票以外にも、転職時には各種書類の提出を求められることが多いため、入社が決まった際には必要書類を早めに確認し、準備を整えておきましょう。
入社日を決めておく
入社日については、面接前に自分の希望を明確にしておくことが大切です。
1月入社を希望していても、企業側が早期入社を求めるケースも0ではありません。
たとえば、12月に面接を受けた場合、人員補充を急ぐ企業では、年末の数日間だけでも出社してほしいと考えることがあります。
入社日の希望をあいまいに伝えると、後で変更を求められる可能性があり、企業側の印象を損ねることにもつながります。
そのため、1月入社を希望するのであれば、面接の段階でしっかりと伝え、変更のないスケジュールを提案するよう心掛けましょう。
【1月入社のデメリット】転職を成功させるために必要なこと
1月入社に限らず、転職を成功させるためには、計画的な準備が欠かせません。
偶然うまくいくこともあるかもしれませんが、必要なステップをしっかりと踏むことで成功率を大きく高められます。
以下に転職活動で重要なポイントを解説します。
企業分析を行う
転職活動において、企業分析は最初に行うべきステップです。
企業分析とは、応募先の業務内容や企業理念、規模感、文化などを調査することを指します。
難しそうに感じるかもしれませんが、企業のホームページや採用情報を確認するだけで多くの情報を得ることができます。
また、仕事内容が希望に合っていても、企業の文化や理念が自分に合わないケースもあります。
こうしたミスマッチを防ぐためにも、事前にしっかりとリサーチしておきましょう。
さらに、最近は企業口コミサイトが増えており、現社員や元社員のリアルな意見を確認することも可能です。
転職理由を考えておく
面接では「なぜ転職するのか」や「退職理由」を聞かれるのが一般的です。
この質問は、企業側が応募者の長期的な適性を見極めるための重要なポイントとなります。
たとえば、「仕事内容が嫌だから転職したい」という理由では、面接官にネガティブな印象を与えてしまう可能性があります。
一方で、「キャリアアップを目指したい」「新しい挑戦をしたい」といったポジティブな理由であれば、面接官に前向きな姿勢を伝えられるでしょう。
転職理由を考える際は、自分の中でネガティブな要素を排除し、ポジティブな動機を強調するよう意識してください。
履歴書と職務経歴書を作り込む
正社員の転職では、書類選考が第一関門となります。
履歴書や職務経歴書は、応募者が自分のスキルや経験をアピールするための重要なツールです。
履歴書では自己PRを簡潔かつ効果的にまとめ、職務経歴書には過去のプロジェクトや具体的な成果を詳しく記載します。
たとえば「売上を〇%向上させた」や「プロジェクトを成功に導いた」といった実績を数値で示すと、説得力が増します。
面倒に感じるかもしれませんが、書類作成で手を抜くと書類選考を通過できずに次のステップへ進むことが難しくなります。
転職の目的を明確にする
転職活動を成功させるには、明確な目的を持つことが必要です。
目的が曖昧だと、転職後にミスマッチが生じ、再び転職を繰り返すリスクが高まります。
たとえば、給与や休日といった待遇面を改善したいのか、仕事内容を変えたいのか、目的を具体的にすることで、応募先の選定がスムーズになります。
目的が明確であれば、希望する条件に合った企業を効率的に探すことができ、長期的に満足できる転職を実現できるでしょう。
在職期間中に転職活動を行う
転職活動は、在職中に進めることを基本とします。
退職してから転職活動を始めると、空白期間が生じるリスクが高まります。
空白期間は、面接官から「計画性に欠ける」と判断される可能性があり、マイナス評価となることもあるでしょう。
また、空白期間が長いと生活費の負担が増し、焦って転職を決めてしまうケースもあります。
在職中に転職先を決めておくことで、生活面の不安を減らし、余裕を持って転職活動を進められます。
【1月入社のデメリット】転職は時期だけにこだわりすぎないことも大切
1月入社を目指すことには多くのメリットがありますが、転職活動において時期だけにこだわりすぎるのは逆効果になる場合もあります。
以下では、1月入社に固執せず、柔軟に転職活動を進めるためのポイントを解説します。
1月にこだわりすぎない
確かに1月入社には、区切りの良さや新たなスタートを切りやすいなどの利点があります。
しかし、誰もが必ず1月に転職できるわけではなく、希望の業種や企業の状況によっては、時期をずらす選択も必要です。
たとえば、転職したい業種の求人が1月には出ていない場合、無理に別の業種を選んでしまうと、希望するキャリアパスから外れてしまう可能性があります。
結果、入社しても長く続けられないという事態になりかねません。
転職活動では、時期と同じくらい、あるいはそれ以上に自分のキャリアや働きたい企業を優先する視点が重要です。
自分の転職したい企業を中心に考える
転職活動では、時期よりも転職先を軸に考えることが成功への近道です。
すでに転職したい企業が決まっている場合は、企業の求人タイミングに合わせることが重要です。
企業によっては中途採用の時期が1月に設定されていない場合もあります。
その際に無理に1月入社にこだわると、希望する企業へのチャンスを逃してしまう可能性もあるでしょう。
一方、転職して1年も経てば、入社時期による違いはほとんど気にならなくなります。
業種についても同様です。
すでに希望する業種がある場合、1月という時期よりも、業種や企業の採用状況に合わせた行動が大切です。
まとめ
1月入社は、年度の切り替えとして適した時期であり、求人数が増えるというメリットがあります。
一方で、ボーナス減額の可能性や競争率の高さといった課題も伴います。
しかし、1月入社のデメリットは、事前の準備と適切な対策を講じることで克服可能です。
転職を成功させるには、時期に固執するのではなく、自己分析や企業研究を徹底して行い、自分に合った職場を選ぶことが大切です。
綿密な計画を立て、早めに準備を進めることで、理想の転職を実現し、満足のいくキャリアを構築できるでしょう。
SHARE この記事を友達におしえる!