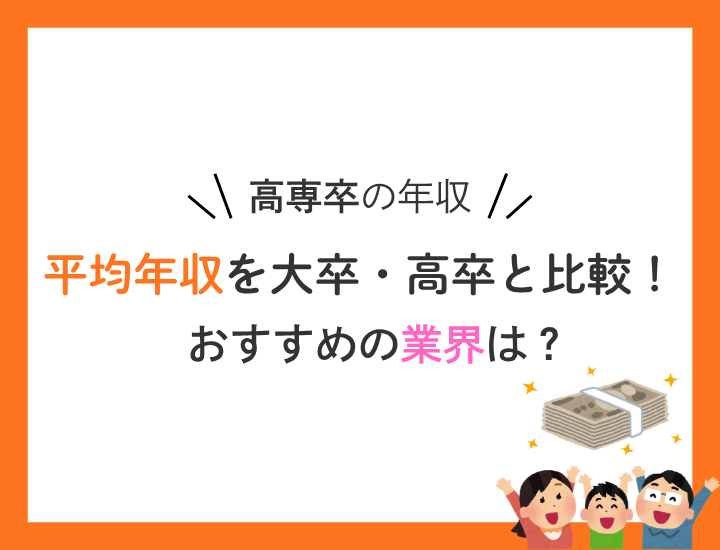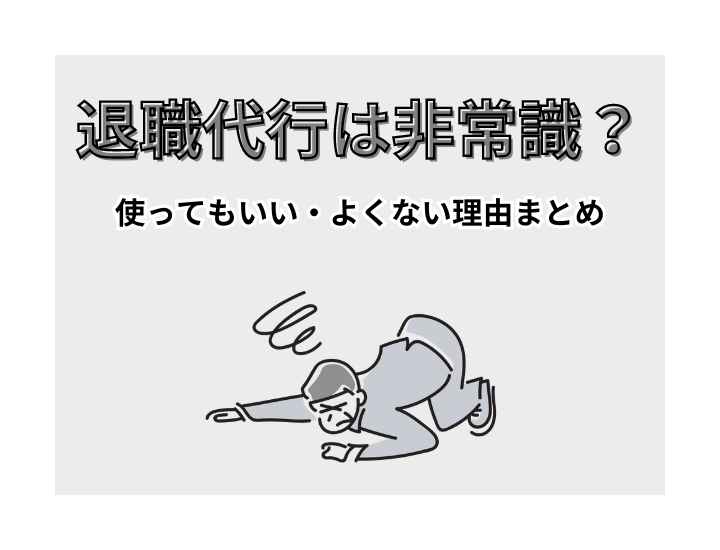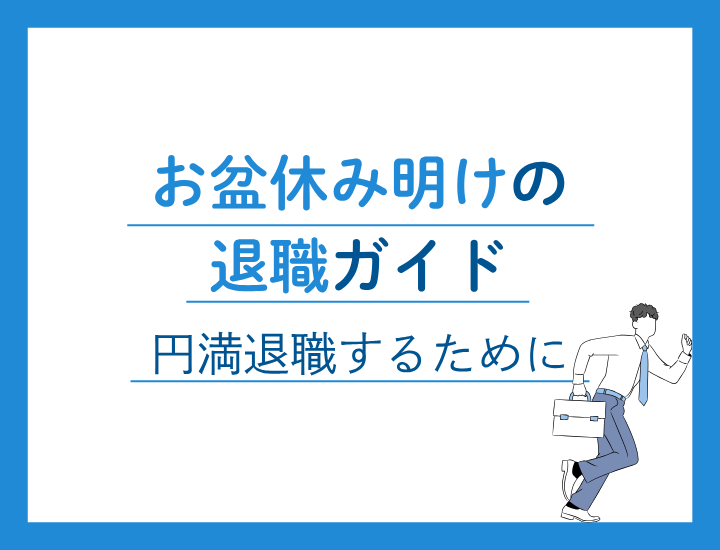
お盆休み明けは会社を辞める人続出!?円満な退職方法とは
はじめに
お盆休みは年に数回ある大型連休の一つであり、新入社員にとってはゴールデンウィークに続く2回目の長期連休です。
基本的にはリフレッシュになるはずですが、仕事内容や人間関係など、連休中でも仕事のことを考えてしまうかもしれません。
特に、普段考える時間が長ければ、長期連休で考えすぎて辞める選択肢も出てきます。
そのとき気になるのが、お盆休み明けすぐに仕事を辞められるかどうかです。
そもそも、お盆休み中に仕事を辞めたいと思っても、連休中のためすぐには行動できません。
この記事では、お盆休み明けに仕事を辞める方法を中心に、辞めたくなる理由や辞めるための順番を解説していきます。
また、従業員を辞めさせないために企業がすべき努力もあります。
個人で仕事を辞めたい方も、企業で離職率を下げたい担当者の方も参考にしてみてください。
お盆休み明けに辞めたくなる理由
まずは、なぜお盆休み明けに仕事を辞めたくなるのか、主な理由を解説します。
現在、仕事を辞めたいと考えている方だけではなく、企業の担当者の方もなぜ従業員が辞めたくなるのかを考えてみてください。
休みで憂鬱になる
お盆休みのような長期休暇は、心身のリフレッシュには最適な期間です。
しかしその一方で、休みの終わりが近づくとともに「また仕事が始まるのか…」という憂鬱な気持ちに襲われる人も少なくありません。
特に普段から日曜日など出勤日前日に憂鬱さを感じやすい方は、連休後の出社に対して強いストレスを感じやすくなります。
このような精神的負担は、仕事へのモチベーションを著しく低下させ、「もう辞めたい」と思ってしまう大きな要因になります。
長年同じ職場で働いていればある程度は慣れて乗り越えられるかもしれませんが、入社したばかりの新入社員や、転職して間もない方は、職場にまだ馴染めていない分だけ不安や憂鬱を強く感じがちです。
そのため、「お盆明けに退職を申し出よう」と決意してしまう人も出てきます。
中には、お盆休み中から既に辞意を固めているケースもあります。
ただし、突然の退職は周囲との関係に影響を与えるため、後述するように円満退職を目指すには手順を踏むことが重要です。
考える時間が長い
お盆休みは、その年のカレンダーや有給休暇の併用によっては非常に長い連休です。
そのため、遊びに行くだけではなく考える時間も長くなります。
仕事に不満がなく、楽しんでいるのであれば問題はありません。
しかし、不満を抱えていたり別の業界に興味がある場合など、転職や退職を考える時間にもなります。
特に、旅行や遊びなどに出かけず家で過ごす場合、ほかの求人や口コミサイトを目にする機会が増えるかもしれません。
いまの職場よりも良い職場を見つけると、多くの方は転職を考えるのではないでしょうか。
現状に不満があれば、周りの会社や環境が良く見えるものです。
考える時間が長く多くの人と接するお盆休みは、退職や転職について考えることが多いといえます。
ボーナス時期が近い
多くの企業では、夏のボーナスが支給された後、お盆休みに入ります。
そのため、ボーナスを受け取ってから退職するには良い時期といえます。
仕事に不満がなければ、衝動的に辞めたいという感情が出てくることもありません。
しかし、転職を考えていると、あえて辞める時期として選ぶこともあるでしょう。
特に、お盆休みは時間も多くあるため、転職先や、やりたい仕事を探すのにも適しています。
もし、お盆休み期間中に次のやりたいことを見つけた場合は、ボーナスをもらった後は良い転職時期です。
また、ボーナスが業績に応じた支給なのであれば、前年度より極端に下がる可能性もあります。
こういった場合は、ボーナス支給額が下がったことで仕事を続ける意欲がなくなるかもしれません。
これも、お盆休み明けに仕事を辞めたくなる理由の一つです。
周りの話を聞く機会が多くなる
お盆休みは長期連休のため、地元を離れて暮らしている方は帰省することもあるでしょう。
帰省すると家族だけではなく、地元の友人と会う機会が多くなります。
さまざまな人と接することで、自分よりも待遇面の良い会社の話を聞くかもしれません。
給与だけではなく休日や勤務時間など、自分の勤めている会社よりも良い話を聞けば、羨ましくなるものです。
こうなると、現状より良い待遇の会社への転職を考えるかもしれません。
また、現在の仕事が好きでも給与が低い場合など、家族から転職をすすめられることもあります。
あくまで自分がする仕事ということから過度に周りを気にする必要はないものの、人と会う機会が増えれば不満や悩みも増えてしまいます。
地元に帰りたくなる
地元を離れて就職した場合、お盆休みの帰省で戻りたくなるかもしれません。
田舎から上京すると、都会の空気感が合わないこともあります。
帰省すると、改めて地元の良さを感じることも珍しくありません。
特に、友人の多くが地元に残っているのであれば、休日がいまより充実する可能性もあります。
また、親のために地元に帰るという選択肢があるかもしれません。
介護ではなくても年齢を重ねて生活が大変そうにみえれば、地元で再就職することも選択肢に入るはずです。
お盆休みの帰省は地元の良さを再確認する機会でもあり、仕事を辞める、転職するといったことを決めるきっかけにもなります。
お盆休み明けに仕事を辞めるための順番
辞めるのがお盆休み明けかどうかにかかわらず、退職には順番があります。
会社によって多少の違いはあるものの、ここで解説する内容が基本です。
退職したい旨を上長に伝える
退職の意思を固めたら、まずは直属の上司に相談しましょう。
このとき重要なのは、順番を守ることです。
たとえば、主任が自分の上司である場合には、課長や部長、さらには社長へいきなり退職を申し出るのは適切ではありません。
企業では上下関係や報告のルールが重視されるため、上司を飛び越えて上層部に伝えるのはマナー違反とされ、社内の評価や印象を損ねる原因にもなりかねません。
また、意外と見落とされがちなのが「同僚に先に話さないこと」です。
親しい同僚であっても、上長より先に退職の話を漏らしてしまうと、噂が広まり、職場の雰囲気が乱れる可能性があります。
退職は個人の重要な決断であり、正式に伝えるまでは慎重に行動するべきです。
もし退職をまだ迷っている段階であっても、「今後について悩んでいる」といった形で上司に相談するのはおすすめです。
軽く気持ちを共有しておくことで、後のやり取りがスムーズになり、円満な退職へとつながりやすくなります。
退職願や退職届けを提出する
退職の意思を会社に正式に伝えるためには、退職願や退職届の提出が必要です。
退職願は「退職したい」という希望を伝える書類で、退職届は「退職する」という決定事項を通知するものです。
多くの企業では、どちらかを提出することで退職手続きが始まります。
ただし、提出が必要な書類の種類や提出方法は企業によって異なります。
たとえば中小企業では、書面の提出を求められず、口頭での意思表示だけで手続きが進むこともあります。
一方で大企業では、形式的に退職届の提出が求められるケースが一般的です。
こうした違いがあるため、まずは自社の就業規則や人事部門に確認しておくことが大切です。
また、提出のタイミングにも注意が必要です。
退職の意思表示は就業規則に定められた期日(たとえば退職希望日の2週間前など)を守る必要があります。
書類の準備を進めつつ、社内ルールに則って手続きを行いましょう。
スムーズな退職のためにも、必要な情報を事前に確認しておくことが重要です。
貸与物の返却と受け取り書類を確認する
退職の手続きが終われば、後は貸与物の返却と受け取り書類の確認です。
貸与物といってもさまざまですが、主には制服や名札、保険証などでしょう。
ただし、自分が思っている以上に貸与物が多いこともあるため、事前に上長や総務部などに確認しておいてください。
退職後に貸与物の返却が完了していなかった場合、改めて会社に出向かなくてはいけません。
受け取り書類ですが、基本的には下記の2つです。
- 源泉徴収票
- 雇用保険被保険者証
場合によっては下記の書類も受け取りが必要になるため注意しましょう。
- 年金手帳
- 離職票
年金手帳は会社に提出している場合のみですが、預けている場合には受け取りが必要です。
離職票に関しては退職時に受け取るものではなく、後で自宅に郵送されます。
離職票は失業保険を受ける場合には必要になるため、受け取りを忘れないようにしてください。
また、大企業であれば離職票を送付することが多いものの、多くの企業では希望がなければ発行しないということも珍しくありません。
転職先が決まっているのであれば必要ありませんが、しばらく休養するのであれば離職票は必須です。
退職日までにやっておきたいこと
続いて、退職前にすることを解説します。
すべて絶対ではありませんが、退職後も負担なく進めるためには、できる部分はやっておいたほうが良いことばかりです。
納得のいく退職理由の精査
退職を決意する前に、まずは「なぜ辞めたいのか」と、自分の中で納得のいく理由かどうかを明確にしましょう。
例えば「上司との関係がうまくいかない」「スキルが活かせない」「将来に不安を感じる」など、漠然とした不満でも構いません。
これらの理由を紙に書き出すなどして可視化することで、自分自身の気持ちを客観的に整理できます。
特に注意したいのは、お盆休みなどの長期休暇明けに突発的に辞めたい気持ちが湧いた場合です。
これは一時的な気分の落ち込みによるものかもしれず、冷静な判断が必要です。
一方で、以前から継続的に退職を考えていた場合は、退職理由の精査が重要です。
長期的なストレスや、将来的なキャリアアップが見込めないといった理由であれば、退職は前向きな選択と言えるでしょう。
また、退職理由は転職活動の面接でも必ず問われる項目です。
曖昧な回答では、採用担当者にマイナス印象を与える可能性があるため、ポジティブかつ論理的に説明できる理由を準備しておくことが大切です。
納得のいく退職理由を見つけることは、円満な退職とスムーズな転職の両方につながります。
転職活動を始める
人によっては会社を退職してから転職活動を始めるかもしれません。
少し社会に疲れてしまった場合や、やりたいことが見つかっていない場合など、休息期間や考える時間が欲しくなることもあります。
しかし、会社を辞めてからの期間が長くなるほど、再就職は難しくなります。
これは、一般的に何もしていない期間が評価されないからであり、「会社が嫌で辞めた人」というイメージがつきやすいからです。
できれば、退職前に転職活動を始めておきましょう。
次の職場が決まっていることが一番の良い方法ではありますが、活動を始めておくだけでも問題ありません。
面接の時間が取れないのであれば、履歴書や職務経歴書を作成する、求人情報をチェックするといった内容だけでも大丈夫です。
少しでも動き出すことにより、転職が決まりやすく、働くモチベーションになります。
できる限り円満に退職する
退職を決意したら、できるだけ円満に退職することを意識して残りの仕事をこなしましょう。
「円満退職」を意識することで円滑に退職できるだけでなく、今後のキャリアにも良い影響を与えるためです。
職場でのトラブルや規定違反、感情的なやり取りによる退職は、あなたの社会的評価を下げ、特に同業種への転職では悪影響を及ぼす可能性があります。
同業界で転職をする場合は企業同士のつながりも多く、前職での評判が転職先の耳に入ることもあります。
万が一ネガティブな情報が広がってしまえば、せっかくの転職機会を逃すかもしれません。
そのため、会社の就業規則に則って、適切な退職手続きを踏むことが大切です。
とはいえ、どうしてもハラスメントなどが原因で直接伝えることが困難な場合は、無理をせずに退職代行サービスの利用も検討しましょう。
現在では、法的に正当な形で退職を代行してくれる信頼できる業者も増えています。
「辞めたいけど言い出せない」と悩んで心身をすり減らすよりも、専門家に頼ることで精神的な負担を減らし、前向きな一歩を踏み出せます。
自分にとって最良の方法で、誠実かつ冷静に退職を進めることが、円満退職と次のステップへの近道です。
仕事を辞めない方が良い場合とは
お盆休み明けに仕事を辞めることは、必ずしも良いことばかりではありません。
人によっては辞めることで今後の社会人生活に悪影響を及ぼす可能性もあるため、慎重に考えてみてください。
新卒1年目
新卒入社して1年目なのであれば、お盆休み明けに退職することで今後に悪影響があるかもしれません。
最近は日本でも転職者が増えてきてはいますが、まだまだ終身雇用の考えも残っています。
入社して3年以上働いてからの転職であれば、十分に社会人としてビジネスマナーを学び、仕事も一人前にできると考えられます。
しかし、1年未満で退職すると、社会人としてのマナーや技術は身に付いていないと考えられることが一般的です。
そのため、新卒1年以内の退職歴があると、今後も上手く転職できない可能性が高くなります。
「続かない人」という印象がつきやすいだけではなく、同業種でも経験者としては見られません。
基本的に経験者募集の求人は、3年以上を求められることが多くあります。
新卒1年目は、まだ仕事も一人でこなしていないことが多く、企業としては評価しづらい人材です。
人間関係
仕事を辞める理由の中で、常に上位に入ってくるのが人間関係です。
人間関係が悪ければ、どれだけ好きな仕事でも続けるのは難しいかもしれません。
しかし、ハラスメントや仕事を教えてくれないなど、極端に劣悪な関係でなければ改善可能です。
適切にコミュニケーションをとると、意外にも人間関係が良くなることもあります。
そのため、「気が合わない」、「なんとなく苦手」といった理由であれば、まずは積極的にコミュニケーションをとってみてください。
話してみれば仲良くなれる可能性もあり、仕事を辞める必要はなくなるかもしれません。
仕事内容
仕事内容に不満があって辞めるつもりなのであれば、部署移動も検討してみてください。
ほとんどの会社は部署がいくつかに分かれており、現場や営業、事務などさまざまです。
全く別の部署へ移動することにより、仕事内容に不満があれば一新して働けます。
また、人間関係も部署移動で解決できるかもしれません。
ただし、小規模な会社であれば、部署を分けずマルチタスクになっていることもあります。
こういった場合は部署移動で解決することはできないため注意しましょう。
現場職から営業への移動といったように、いままでの職種と大きく異なる場合には不安があるかもしれません。
それでも、転職するよりも慣れ親しんだ職場で仕事を続けられるのは、大きなメリットです。
こんな場合は仕事を辞めるのもアリ
前項では、お盆休み明けに仕事を辞めない方が良い場合を解説しました。
しかし、時には、すぐに辞めるべき場合もあります。
いくつか解説するため、自分の状況が当てはまっているか確認してみてください。
ハラスメントが横行している
まずは、ハラスメントが横行している職場です。
ハラスメントにもいくつか種類がありますが、代表的なのはパワハラとセクハラでしょう。
例えば、日常的に怒鳴られる、結婚やパートナーについてしつこく聞かれるなどです。
また、怒鳴ったり怒られたりがなくとも、上司がイライラを見せるようにしていたり、物にあたったりなど、直接の被害がなくてもパワハラにあたる場合もあります。
最近はハラスメントに対して各企業がより気をかけてはいますが、完全にはなくなっていないのが現状です。
基本の対策は会社に設置されている相談窓口へ問い合わせることですが、過度なストレスを与えられていては相談も難しいかもしれません。
ストレスが溜まり続ければ精神面に不調をきたしてしまい、今後の仕事にも悪影響を与えてしまいます。
最悪の場合は長期の休養が必要になることも珍しくはないため、ハラスメントが横行している会社は早めに辞めるべきと考えられます。
労働環境に問題がある
長時間労働や休日出勤など、労働環境に問題があると長くは続けられません。
どれだけ好きな仕事であっても、毎日夜遅くまで残業し、休日も出勤しているのであれば休まる時はないでしょう。
こういった場合には、勤続年数が短かったとしても辞めるべきです。
勤務期間が短かったとしても、「労働環境に問題があることで仕事に集中できなかった」、「キャリアアップを目指せる環境ではない」といった転職理由を説明できます。
ハラスメントと同じで、労働環境の問題は精神面に不調をきたすかもしれません。
今後のことを考えれば、いま無理に我慢するよりも退職、転職を選択すべきです。
自分の健康状態に影響が出ている
どんなに待遇や給与が良くても、健康を損ねてまで働き続ける意味はありません。
仕事は人生の一部に過ぎず、何よりも大切なのは心身の健康です。
たとえば、慢性的なストレスや睡眠不足、不安感、胃痛、頭痛など、明らかに身体や精神に異常を感じるようになったら、それは無理をしているサインかもしれません。
また、出勤前に体調が悪くなったり、日常生活に支障が出るといった状態が続く場合、早急に環境を見直す必要があります。
健康を害した状態では、集中力が続かずパフォーマンスも下がり、キャリアの成長どころか逆に悪影響を及ぼすこともあります。
今の職場が自分に合っていないと感じるなら、無理に居続ける必要はありません。
心と体の声に耳を傾け、自分らしく働ける環境を探すことも前向きな選択です。
退職や転職は「逃げ」ではなく、「より良い未来を選ぶための手段」と捉えましょう。
仕事を辞めずに続けるメリット
お盆休み明けは長期連休後ということもあり、仕事を辞めたくなることも少なくありません。
しかし、仕事を続けることによるメリットも大きいため、人によっては辞めない選択肢が良い場合もあります。
技術が身に付く
仕事を長く続けるほど、その職種の技術が身に付きます。
年数を重ねるほどできることが増えていくため、その後の転職も有利になるでしょう。
もし、1年未満などの短い期間で退職した場合、経験という面では少ないと捉えられるかもしれません。
実際に、求人での経験者募集では3年以上としていることがほとんどです。
つまり、経験が浅ければ転職で経験者として採用されることはなく、よくても未経験採用になってしまいます。
経験者と未経験では給与にも大きな差が出ることが多く、経験と技術が必要なのは明確です。
また、技術面だけではなく社会人としてのスキルが向上するのもメリットです。
社会人スキルはどのような職種でも必要であり、転職でも必ず役立ちます。
人間関係を構築しやすい
長く同じ会社で働くほど、人間関係が構築されていきます。
もし転職した場合は、当然ですが一から関係性を作り直さなければいけません。
長く働いていると職場の人たちと気心が知れていたりと、楽に働けます。
転職すると、いままでに構築した人間関係は一から始める必要があり、数年以上働いた職場の後では辛く感じるかもしれません。
特に、どの職場でも上手く人間関係が構築できるわけではなく、苦労する可能性もあります。
もし、転職してから「以前の職場のほうが人間関係が良かった」と感じても、時間をかけて構築していくしかありません。
同じ会社で働き続けるほど人間関係を気にする必要もなく、楽に働き続けられます。
年収が上がりやすい
転職にはさまざまな理由がありますが、給与面も大きな理由の一つではないでしょうか。
若い頃は入社する会社によって給与差が大きく、不満に感じることが多いかもしれません。
しかし、多くの会社では毎年の昇給を基本にしており、在籍期間が長くなるほど給与が高くなります。
もちろん、会社によって昇給額は異なるものの、中小企業でも1年で5,000円ほどの昇給が見込めます。
少なく感じるかもしれませんが、10年勤めれば月に5万円の昇給です。
また、大企業であれば1年での昇給率が1万円を超えることも珍しくありません。
転職するといままでの昇給がなくなり、一からのスタートになってしまいます。
経験や実績があれば転職後の初任給も現在の給与を加味した内容になりますが、未経験であれば大きく下がってしまいます。
そのため、給与だけが目的の転職であれば、大きく上がる見込みがある場合しかメリットはありません。
長く働くほど給与は高くなるため、勤続年数が長いのであれば転職しないという選択も必要です。
お金の不安がない
仕事を辞めるということは、収入が無くなるということです。
転職先が決まっている場合には関係ありませんが、辞めてからすぐに働く予定がない場合や、アルバイトなどで生計を立てるのであれば注意してください。
辞めてからすぐに転職活動を始めるのであっても、2ヶ月ほどの余裕があると安心です。
また、アルバイトは正社員と違い、最初の給与が支払われるのは早くても1ヶ月後です。
この場合は、働くことが決まっていても最低でも1ヶ月分の生活費が必要でしょう。
仕事を辞めると、どうしてもお金の不安が付いてきます。
辞めずに働き続けるとお金の不安がないため、大きなメリットといえます。
【企業向け】従業員を辞めさせないためにできること
お盆休み明けは、従業員が退職を考えるタイミングとして企業にとっても要注意の時期です。
優秀な人材の流出を防ぐには、職場環境の見直しや待遇の改善など、企業側の取り組みが不可欠です。
ここでは、社員のモチベーション維持や定着率向上のために、企業が今すぐできる具体的な対策をご紹介します。
労働環境を適切化する
従業員の離職を防ぐためには、まず現在の労働環境が適切かどうかを見直すことが重要です。
労働環境が悪いと、従業員の不満が蓄積し、結果として退職を選ぶケースが増えてしまいます。
特に、長時間労働や休日出勤が常態化していたり、有給休暇が取りづらかったりする職場では、従業員のワークライフバランスが崩れ、モチベーションが大きく低下します。
改善策としては、まず労働時間の見直しを行い、過度な残業を減らすための管理体制を整えましょう。
たとえば、定時退社日を設ける、勤怠管理システムを導入する、上司が率先して早く帰る文化を作るなどが有効です。
また、有給休暇の取得率向上を目指す取り組みも重要です。
計画的付与制度を活用するほか、チーム内での業務分担を見直すことで、誰かが休んでも業務が滞らない体制を構築できます。
さらに、リモートワークやフレックスタイム制の導入も、柔軟な働き方を実現し、従業員満足度を高める効果が期待できます。
このように、物理的・精神的な働きやすさを整えることで、従業員の定着率を向上させることができます。
福利厚生を充実させる
社会保険や厚生年金、雇用保険が主な福利厚生と考えている方が多いかもしれません。
しかし、これらは法定福利厚生であり、企業に義務付けられているものです。
従業員が重視するのは、義務付けられていない法定外福利厚生かもしれません。
法定外とある通り、義務付けられているものではなく、企業が独自に設定する福利厚生です。
法定外福利厚生は、食事手当や住宅手当などが主な種類といえるでしょう。
これらの手当が充実していると、同じ給与でも手取りの金額が大きく変化します。
周りの知人と同じ税込年収であったとしても、福利厚生が充実していると年間で数十万円もの差になることも珍しくありません。
従業員にとって魅力的な福利厚生が充実していれば、辞めるという選択肢は少なくなります。
評価制度を取り入れる
退職する理由として多いもののひとつに、給与面があります。
例えば、長く働いていても昇給する見込みがないと、転職を考える人が多くなるかもしれません。
「先輩や上司を見ていても昇給していない」、「どうすれば昇格、昇給するのかわからない」といった場合は不安になってしまいます。
こういったことを解決するには、適切な評価制度を取り入れることです。
どういった働き方をすれば昇格や昇給するのかを明確にしておけば、従業員には目標ができます。
目標があれば仕事に対する取り組み方も前向きになり、転職という選択肢は少なくなるものです。
研修制度を見直す
もし、新入社員が1年目のお盆休み明けに辞めてしまうのであれば、研修制度を見直すべきかもしれません。
新入社員が研修期間中に辞めてしまうことは珍しくなく、どうしても独り立ちする前に辛くなってしまうこともあります。
こういった場合は、相談先を設け、不要なカリキュラムを取り除くことが大切です。
ただでさえ新入社員は学生時代とのギャップに戸惑っています。
社会人としての悩みが多く、社内の誰にも相談できない環境はよくありません。
定期的に上司や先輩が話を聞く、相談できる場を設ける必要があります。
カリキュラムは、いままでに研修を受けた社員の意見を参考にしてみてください。
その中で、「必要ないと感じた」、「辛かった」といった内容があれば、思い切ってそのカリキュラムをなくすのもひとつの方法です。
従業員のマネジメントスキルを磨く
従業員の離職を防ぐためには、退職を申し出る社員への対応だけでなく、上司や先輩社員のマネジメントスキルを向上させることが非常に重要です。
マネジメントスキルとは、単に部下を管理・指導する能力ではなく、「人と向き合い、寄り添う力」も含まれます。
理想的なマネジメントとは、分かりやすい説明や指示だけでなく、部下の気持ちに寄り添い、精神的な支えになることができるマネジメントです。
たとえば、部下がミスをした際に頭ごなしに叱責するのではなく、なぜミスが起きたのかを一緒に考え、今後どうすれば良いかを共に探る姿勢が求められます。
「上司の指示が毎回変わって混乱する」「説明が曖昧でどう動けばいいのかわからない」といった状況が続くと、従業員のモチベーションは低下し、やがて離職につながります。
一方で、信頼できる上司がそばにいると、仕事への安心感が生まれ、定着率も向上します。
企業としては、定期的なマネジメント研修を設け、全社的にスキルアップを図ることが効果的です。
まとめ
お盆休みは長期連休の一つであり、考える時間が多いことから退職に向かって動き出す人も少なくありません。
まずは、なぜ仕事を辞めたいのかを考え、退職、転職しても後悔しないようにしましょう。
辞めることを決めたのであれば、退職の手順も大切です。
特に同じ業界に転職するのであれば、悪い噂が広がらないためにも円満退職を目指してください。
また、離職率の高さで悩んでいる企業は、少しの見直しで劇的に変化することもあります。
労働環境の適切化や福利厚生の充実など、できる部分から初めて見るとよいでしょう。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!