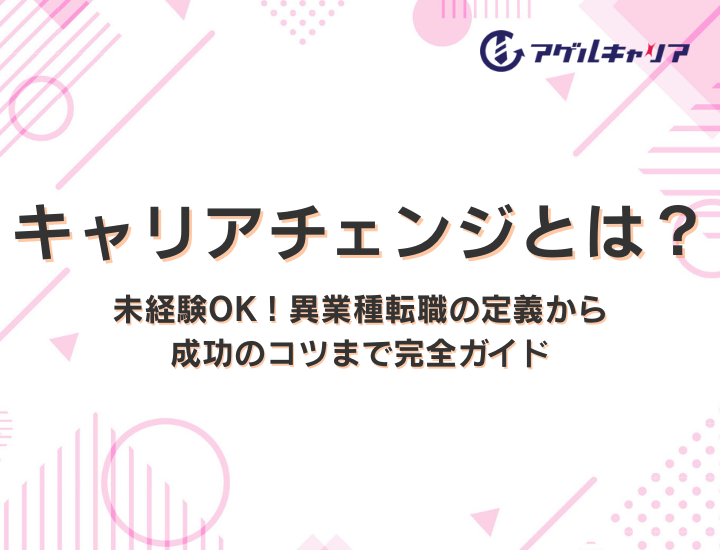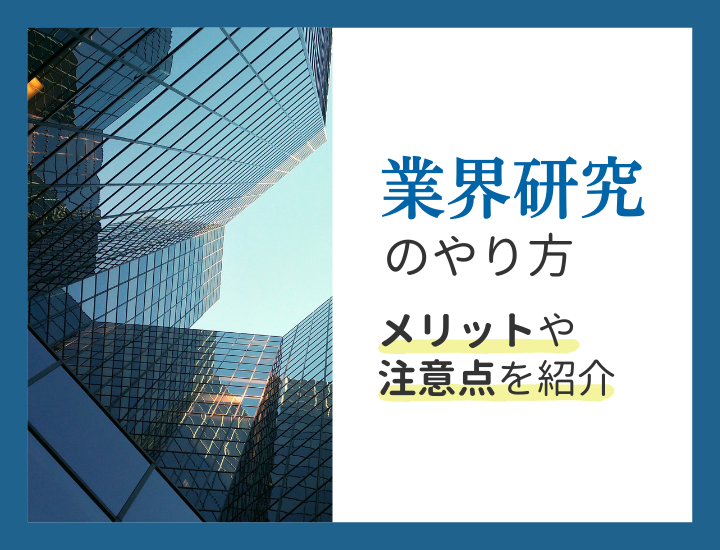新卒3年以内で辞めるのは悪くない!後悔しない決断と転職成功のポイント
はじめに
新卒で入社してから数年以内に退職を検討する若手は少なくありません。
採用された当初は期待に胸を膨らませていたものの、現実とのズレや環境への不満、キャリアに対する不安から離職を考えるケースが増えています。
今回は、新卒入社3年以内に辞めることが本当に悪い選択なのかを整理し、後悔しない決断や転職成功のためのポイントを紹介します。
具体的な理由やメリット・デメリット、準備の仕方について順を追って解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。
新卒入社3年以内に辞めるのはアリか?
「転職は3年以上経験を積んでから」という価値観は根強く残っていますが、実際のデータはそれを裏付けているのでしょうか。
ここでは統計的な離職率の実態を確認し、業界や企業規模による差異も見ていきます。
自身の選択を検討するうえでの参考にしてください。
3年以内に辞めるのは3割
厚生労働省の調査によれば、令和3年3月に卒業した新卒大学生のうち、3年以内に離職した割合は34.9%と公表されています。
新卒入社の約3人に1人が3年以内に会社を去っている計算であり、決して珍しい現象ではありません。
とくに宿泊業や飲食サービス業などの業界では離職率が5割を超えるなど、業界や職種によっても大きな差が見られます。
社会全体で見ても、3割前後という水準は長年ほぼ横ばいで推移しており、早期離職が特別なケースではないことがわかります。
安易な判断ではなく、客観的なデータをもとに選択肢を検討する視点が大切です。
1年以内に辞めるのは1割
さらに短期間である1年以内の離職についても、統計が示されています。
厚生労働省の同じ調査によると、大学卒の新卒社員のうち、おおむね10%前後が入社から1年で退職しています。
とくに新生活が落ち着きはじめる5月以降に辞める人が増える傾向が見られ、人間関係や仕事内容への不満が強く影響していると考えられるでしょう。
1年以内というタイミングでも一定数の離職者が存在するため「こんなに早く辞めていいのか」と悩む必要はありません。
大切なのは、自身の将来にとって必要な行動かどうかを見極めることにあります。
業界・企業規模別の離職率の違い
離職率は業界や企業の規模によって離職率には顕著な差が見られます。
下の表のように、宿泊業や飲食サービス業が高く、金融業や製造業は比較的低い水準にとどまっているのが実情です。
また、従業員数が少ない企業ほど定着率は低い傾向が出ています。
| 業界・規模 | 離職率(3年以内) |
|---|---|
| 宿泊・飲食 | 約50% |
| サービス業 | 約40% |
| 製造業 | 約20% |
| 金融業 | 約15% |
| 大企業 | 低い |
| 中小企業 | 高い |
新卒が3年以内に離職する理由
実際に新卒社員が3年以内に退職を選ぶ理由は一様ではありません。
ここでは、代表的な要素を整理していきます。
背景にある課題を知ることで、自分の悩みがどこにあるのかも見えてくるはずです。
仕事内容が合わない
新卒社員の中には、配属先での業務が適性と大きくずれていると感じる人が多くいます。
選考時に描いていたキャリア像と実際の役割が異なり、やりがいや達成感が得られないことが原因です。
とくに入社直後は職種や部署を選べないケースも多く、不得意な分野に従事することもあります。
スキルを活かせない状況や、成果が評価されにくい環境に置かれると、早期に転職を検討する傾向が強まります。
仕事内容と自身の志向性のミスマッチが長期化することで、モチベーションの低下につながってしまうでしょう。
待遇に不満がある
給与水準や評価制度が期待以下であると、生活面や将来設計に不安が生じやすくなります。
初任給が同年代の平均よりも低い場合や、残業や休日出勤が多いのに報酬が見合わない場合、努力が報われない感覚を持つ人が少なくありません。
とくに同級生や友人の状況と比較しやすい時期であり、自分が不利な立場に置かれているという意識が強まることがあります。
待遇面の不平等感は職場への信頼を損ない、離職を後押しする要因になります。
人間関係が辛い
職場内の人間関係は、仕事の継続に大きな影響を与える要素です。
上司の理不尽な指導や同僚との摩擦によって強いストレスを抱える新卒社員が目立ちます。
相談でる相手が見つからず孤立感が高まる職場では、精神的負担が限界に達しやすい状況です。
リクルートマネジメントソリューションズの調査では、十分な支援を受けられないことが早期離職の上位要因に挙げられています。
人間関係の改善には時間がかかるため、環境を変える決断が現実的な選択肢となるケースが多くなります。
会社の将来に対する不満がある
勤務先の業績不振や経営方針への不信感が強まると、長期的なキャリア形成に不安が生じやすくなります。
業界全体が縮小傾向にある場合や、トップの方針が見えにくい企業では、成長の見込みが薄いと判断されやすいでしょう。
将来的に価値のある経験が積めない環境にとどまるよりも、別の場所でスキルや実績を積むほうが有益だと考え、転職を選ぶ人が増えています。
入社後のギャップに耐えられない
入社時に説明を受けた業務内容や条件と、現実の職場環境が大きく異なると強い不満が募ります。
求人票や面接で聞いた話と実際の業務や職場風土に大きな差がある場合、適応することが難しいと感じる新卒社員は少なくありません。
とくにZ世代の若手社員は、誠実で透明性のある情報提供を重視するため、入社前後のギャップへの不信感が強くなる傾向があります。
Z世代ならではの価値観の不一致がある
最近では、世代固有の価値観が離職を後押しするケースも増えています。
Z世代は柔軟な働き方や公正な評価、ワークライフバランスの充実を強く求める傾向があり、尊重されない企業文化の中では不満が蓄積します。
年功序列や長時間労働が根強く残る職場環境との相性が悪いと、短期間で転職を検討するきっかけになるでしょう。
また、Z世代が希望するキャリアの方向性を実現しやすい未経験歓迎の職種も多数あるので、念のため把握しておくべきです。
- 営業職
- 販売・接客職
- 事務職
- ITエンジニア(ポテンシャル採用)
新卒3年以内で離職しても後悔しないための準備
新卒入社から3年以内に転職を選ぶ際は、事前の準備をしっかり行うことで後悔を防ぎやすくなります。
慌てて辞めてしまうと次のキャリアに悪影響が出るリスクがあるため、転職活動の「軸」を決め、条件や価値観を明確にし、退職に伴う負担を理解することが重要です。
各ポイントを具体的に整理し、冷静に進めるための基礎を固めましょう。
転職活動前に「軸」を決める
転職活動を始める前に、自身の軸となる価値観や優先順位を明確にする必要があります。
軸が定まっていないと、転職先選びで迷いが生じ、妥協や後悔につながりやすくなります。
軸を決めるためには、今の仕事で満たされなかった要素や、これからのキャリアで実現したい方向性を書き出し、優先順位をつけて整理する方法が有効です。
たとえば「専門性を高めたい」「ワークライフバランスを重視したい」など、具体的な言葉で表現することがポイントです。
退職後に重視したい条件や価値観を整理する
転職先を決める際に重視する条件や価値観を明文化することで、入社後の後悔を防ぎやすくなります。
代表的な条件と、具体的な例を以下の表にまとめました。
| 重視する条件 | 具体例 |
|---|---|
| 年収 | 現在よりも高い水準で安定した給与 |
| 仕事内容 | 専門性が身につく業務や成長を実感できる業務 |
| 勤務時間 | 残業が少なく定時退社が可能な環境 |
| 企業文化 | 多様性が尊重される風通しのよい職場 |
| 評価制度 | 公平で透明性の高い評価システム |
退職のリスクと心理的負担を知る
早期に退職する場合、一定のリスクが伴うことも理解しておくべきです。
たとえば、転職先が決まらない期間が長引くことや、周囲からの視線が気になることなどが挙げられます。
また、離職期間が空いてしまうと選考で不利になる可能性もあります。
さらに、自己否定感や将来への不安が大きくなる場合もあります。
しかし、事前に情報収集をして準備を整えれば、こうした不安を軽減することは十分可能です。
自分自身の状況と市場の動向を正しく把握し、冷静な判断を心がけることが重要です。
新卒入社3年以内に離職するメリット
新卒で入社して間もなく転職する場合、ネガティブなイメージを持つ人も少なくありません。
しかし、実際には短期間で決断することで得られるメリットも存在します。
ここでは、早期離職のポジティブな側面を具体的に紹介します。
第二新卒の求人で転職活動できる
第二新卒という立場は企業側からの需要が高く、未経験歓迎の求人に応募しやすい特徴があります。
社会人としての基礎が身についており、柔軟性や若さが評価されやすいため、ポテンシャル重視の採用に期待できます。
とくに、教育コストを抑えつつ新しい戦力を求めている企業からは積極的に採用されやすいでしょう。
第二新卒向けの求人は他の年代よりも幅広く選択肢があり、キャリアチェンジを目指しやすい点がメリットです。
未経験の業界・職種に挑戦しやすい
新卒3年以内のタイミングは、未経験職種に挑戦する最後のチャンスともいわれています。
第二新卒市場では、過去の経験よりも将来の可能性を重視して採用が行われるため、別の業界や職種に方向転換しやすいのが特徴です。
新しい分野への挑戦を考えるなら、新卒3年以内というタイミングを逃さず活用しましょう。
年収アップを狙える可能性がある
年収アップを狙える可能性がある
現職で給与水準が低く、成果が正当に評価されていないと感じる場合、転職によって年収を改善できる可能性があります。
とくに成長産業や人材不足が顕著な職種では、経験の浅い若手にも高い報酬を提示する企業が増えています。
もちろん希望する条件を満たすには、事前に相場を調べたり、自身のスキルや強みを整理したりする準備が欠かせません。
適切に市場価値を伝えられれば、短期間でも収入面でプラスに転じるケースは少なくありません。
新卒入社3年以内に離職するデメリット
新卒から3年以内に退職する選択には、メリットだけでなくリスクや不利益も伴います。
選考ではネガティブに見られやすい理由が複数存在するため、自分が抱えるリスクを把握し、対策を考えることが重要です。
以下では、新卒入社3年以内に離職する具体的なデメリットについて解説します。
忍耐力がないと受け取られる可能性がある
短期間で退職する人材に対して、企業はしばしば「忍耐力が欠けているのではないか」という印象を持ちます。
採用コストをかけて雇用する以上、一定期間の定着を期待する企業が多いためです。
とくに面接では「またすぐ辞めてしまうのでは」といった懸念を持たれることもあり、継続力や責任感を証明するための説明が欠かせません。
短期間での退職理由を準備しておき、前向きで合理的な理由として伝えられるかが大きなポイントとなります。
経験が足りずキャリア採用してもらえない
短期間での退職は、実務経験や専門性の不足につながりやすい点がリスクです。
とくにキャリア採用の場では、即戦力として求められるスキルや成果をアピールしにくくなる傾向があります。
以下に、勤続年数別に求められやすいスキルや立場のイメージをまとめました。
| 勤続年数 | 求められやすいスキル・評価 |
|---|---|
| 1年未満 | ポテンシャル・柔軟性・素直さ |
| 1〜3年 | 基礎スキル・業務習熟度・主体性 |
| 3年以上 | 専門性・実績・リーダーシップ |
1年未満ではポテンシャル評価が中心ですが、年数が増えるにつれ即戦力性や実績が重視されます。
経験不足を補うためには、成長意欲や学ぶ姿勢を具体的に伝える努力が重要です。
人間関係を一から構築する必要がある
転職先では、これまで築いてきた人間関係や信頼がリセットされます。
新しい環境に適応するためには、再びゼロから信頼を獲得し、周囲との関係を構築し直す必要があります。
人間関係の再構築は精神的な負担となりやすく、適応にストレスを感じる人も少なくありません。
とくに短期間で転職を繰り返すと、適応疲れが蓄積しやすくなるため、環境を変える決断は慎重に行うことが大切です。
社内で信頼を得る過程には時間がかかるため、準備期間を持ちながら行動することが望ましいでしょう。
退職金がもらえない可能性がある
企業によっては、退職金の支給条件として「勤続3年以上」といった規定が設けられています。
そのため、短期で離職した場合、退職金が一切支払われないケースが珍しくありません。
退職金は将来的にまとまった金額となる場合が多いため、転職時の損失につながります。
目先の条件だけでなく、長期的な資産形成の視点も持ちつつ決断する姿勢が求められます。
経済的な影響を見越して貯蓄や転職先での待遇を比較するなど、計画的に進めることが必要です。
入社後3年まで離職を待たなくていい理由
「最低でも3年は続けるべき」という考え方が根強い一方で、早期離職のほうがキャリア形成に有利となるケースもあります。
とくに明確な目標や適性が見えている場合は、タイミングを先延ばしにするより、早めに行動したほうが結果につながりやすい傾向があります。
ここでは、入社後3年を待たずに決断すべき理由について整理します。
明確な目標があるなら早期に行動した方がいい
入社時から将来的な目標やキャリア像がしっかりと定まっている場合、早い段階で行動することで成長の機会を最大化できます。
現職で過ごす時間が長くなるほど、業界の慣習や職種の専門性に縛られて方向転換が難しくなるためです。
未経験でも挑戦しやすい第二新卒のうちに必要な環境へ移ることで、スタートが早い分、経験の積み上げや専門性の習得に余裕が生まれます。
長期的な目標に沿って戦略的に行動することが、キャリア形成では重要です。
キャリアチェンジは早めの方がいい
業界や職種を変えるキャリアチェンジは、タイミングが早いほど成功しやすい特徴があります。
第二新卒として採用される時期は、ポテンシャルや成長意欲が重視されるため、未経験からの挑戦が可能です。
年齢を重ねるにつれて経験重視の選考が増えるため、柔軟に動ける時期のほうがリスクを抑えられます。
以下に、早期転職が有利となる理由を整理しました。
- 第二新卒市場の対象として積極的に採用される
- 年齢の若さから柔軟性が評価されやすい
- 未経験職種への挑戦が歓迎されやすい
- 方向性の修正が早いほどキャリアへの影響が小さい
- 採用担当者が教育コストをかけやすい立場にいる
柔軟に動けるタイミングを活用することで、理想に近いキャリアチェンジを実現しやすくなります。
人間関係のストレスは早期対策が必要
職場の人間関係が原因で強いストレスを感じている場合、無理に我慢を続けることは心身の健康を損ねるリスクがあります。
長く耐え続けることでストレスが慢性化し、うつ病や体調不良といった深刻な症状に発展する可能性が高まります。
新卒社員はとくに相談しづらい立場にあるため、環境改善が見込めない場合は早めに新しい職場を選択する決断が必要です。
適切なタイミングで行動することが、健康的に働き続けるための重要なポイントになります。
向いている職の方がやりがいがある
自分の強みや適性に合った職種や業務を選ぶことで、モチベーションが高まりやすく、仕事の満足感も向上します。
苦手意識の強い業務を長く続けることは精神的な負担となり、成果や成長の妨げになる可能性があります。
適性のある環境に移ることで得意分野を発揮しやすくなり、結果としてキャリアの成長スピードも加速するでしょう。
自分が活躍できる場所を見つけるために、早めに方向転換する判断が求められます。
新卒3年目の転職活動の流れ
新卒3年以内のタイミングで転職活動を進める場合、計画性のある進め方が成功のカギとなります。
ここでは、新卒3年目の転職活動における一連の流れを、以下のステップ別に解説します。
- 転職する理由を再考する
- 自己分析する
- 業界・企業分析する
- 選考対策する
転職する理由を再考する
最初のステップは、自身がなぜ転職を希望するのかを明確にする作業です。
理由が曖昧なままでは、転職後に同じ悩みを繰り返してしまう可能性があります。
仕事内容の不満や人間関係、待遇・将来性など、自分が何に対して不満を感じ、どのように変えたいのかを深掘りして整理することが必要です。
整理した理由は、面接の場で退職理由を伝える際の説得力にもつながります。
自己分析する
次に必要なのは、自分自身の強みや適性、価値観を再確認する自己分析です。
どのような職種や業界に向いているか、どのような働き方を求めているかを言語化しておくことで、方向性が定まりやすくなります。
自己分析の結果は履歴書や職務経歴書の内容にも活用でき、選考でのアピールポイントの根拠となります。
強みや弱みを正しく把握することで、次のステージへ進みやすくなるでしょう。
業界・企業分析する
希望する業界や企業が決まったら、その業界の動向や企業の特性を徹底的に調べることが欠かせません。
業界分析を怠ると、せっかく転職してもまた同じ理由で辞める可能性が高くなります。
業界全体の市場規模や成長性、働き方の特徴や企業ごとの文化を調べることで、適性や価値観に合った環境が見つかりやすくなります。
以下に、業界ごとの特徴例をまとめました。
| 業界 | 特徴 |
|---|---|
| IT・Web | 成長産業、未経験からでも挑戦可能 |
| 製造業 | 安定志向が強い、専門知識が求められる |
| サービス業 | 人手不足が顕著、ワークライフバランスに注意 |
| 金融業 | 安定性が高いが、成果主義が色濃い |
業界の特徴を理解しておくと、応募時の志望動機やキャリアプランに一貫性を持たせやすくなります。
選考対策する
応募先が決まったら、書類作成や面接対策をしっかり行う段階です。
履歴書や職務経歴書は、自己分析や業界分析の内容を反映させることで具体性が増します。
面接では退職理由や志望動機についての質問が必ずあるので、前向きな表現で説明できるよう準備しましょう。
実際の面接の場で想定問答を練習することで、自信を持って選考に臨めるようになります。
新卒3年以内の転職を成功させるコツ
新卒入社から3年以内での転職は、短期間での決断だからこそ戦略が重要です。
何も考えずに転職活動を進めてしまうと、再びミスマッチが発生するリスクがあります。
ここでは、成功する転職のために意識したいポイントを整理しました。
転職先で経験が活かせるか考える
前職で培った経験やスキルが、新しい職場でどう活かせるかを考えることが重要です。
短期間であっても、身につけた基礎力や社会人マナー、業務に対する姿勢は必ず次の職場で活きます。
新しい環境で即戦力として期待されるためには、これまでの経験を具体的に振り返り、転職先にどのように貢献できるかを説明できるようにしておくことが必要です。
自己分析の際に強みを洗い出し、面接で積極的に伝える準備を進めておきましょう。
その仕事をしたい理由を明確にする
志望動機が曖昧なままでは、選考での説得力が弱まります。
なぜその職種や業界を選ぶのか、なぜその企業で働きたいのかを言葉にできるようにすることが求められます。
過去の経験や将来の目標と関連付けることで、納得感のある志望理由となるでしょう。
以下に、説得力のある志望理由を構築するためのポイントをまとめました。
- 経験やスキルをどのように活かしたいのか具体化する
- 業界の将来性や魅力に共感した理由を説明する
- 企業の理念やビジョンと自身の価値観が一致する点を示す
- 新しい環境で成長したい分野や習得したいスキルを明確にする
上記の要素を整理しておくと、面接の場で好印象を与えやすくなります。
転職先の職種で起こる苦労や大変さを理解する
新しい職場や職種に対して理想だけを描いてしまうと、現実とのギャップで再び悩む可能性があります。
事前に転職先の職種に伴う苦労や大変な部分を理解しておくことで、入社後に感じるストレスを減らせます。
業界研究や社員インタビューなどを活用し、現場で求められるスキルや責任、業務の難しさまで把握する姿勢が重要です。
自分がどう対応していくかまで想定しておくと、実践力があると評価されやすくなります。
選考で退職理由を聞かれたら
転職活動の面接では、必ずといっていいほど退職理由を質問されます。
短期間での離職はネガティブに受け取られやすいため、伝え方を工夫することが重要です。
ここでは、退職理由を伝える際のポイントと回答例を紹介します。
ポジティブな言葉を使って表現しよう
退職理由を話すときは、ネガティブな事実をそのまま伝えるのではなく、前向きな表現に置き換えることが大切です。
「できなかった」「合わなかった」といった言葉より「より成長できる環境を求めている」「新しい目標に向かうために決断した」といった表現にすることで、主体性や意欲が伝わります。
短期間での退職も、戦略的な選択であることを示すことが評価につながります。
悪口や嘘は御法度
前職の上司や同僚、会社の悪口を述べると、協調性や社会性に欠ける印象を与えてしまいます。
また、事実と異なる説明をすると、選考過程で矛盾が生じる可能性が高くなります。
事実をベースにしながらも、前向きに表現することが大切です。
問題点を冷静に分析し、改善意欲につなげている姿勢を示すと説得力が増します。
【回答例】仕事が合わなくて退職した場合
仕事内容と自身の適性が合わなかったケースでは、適性を見極めたうえで新たな環境で挑戦したい旨を伝えましょう。
前職では業務に取り組む中で、自身の強みがより活かせる分野に挑戦したい気持ちが強くなりました。
今後はこれまでの経験を基に、新しい環境で専門性を高めたいと考えています。
【例】待遇に不満を持って退職した場合
待遇への不満をストレートに表現せず、スキルや貢献に見合う環境を求めているという前向きな姿勢に置き換えましょう。
【回答例】人間関係が辛くて退職した場合
人間関係の問題は、表現に注意が必要です。
環境を変えて新たに挑戦したい姿勢を強調します。
企業側が考える新卒3年以内の離職理由
新卒社員の早期離職は、企業にとっても大きな課題です。
教育や採用にコストをかけたにもかかわらず、短期間で人材が流出する状況は経営に悪影響を与えます。
採用側の視点から見ても、離職の背景や定着しやすい人材の特徴を理解することが重要です。
ここでは、企業が認識している離職の理由と、定着に寄与する要素を紹介します。
企業はなぜ離職が多いと考えているか
企業側は、新卒社員が早期に辞める原因について複数の問題が絡み合っていると認識しています。
以下に、主な理由をまとめました。
- 配属先の仕事内容が期待と大きく異なるため意欲が低下する
- 職場の人間関係や上司のマネジメントが不十分でストレスが増す
- 入社前に提供する情報と実際の労働環境が異なることによる不信感
- 長時間労働や低い給与水準が想像以上に負担になる
- 個々の価値観やキャリア観と企業文化が一致しない
上記の点を改善し、若手の定着率を高めるために説明会での情報提供を増やしたり、配属後のフォロー体制を強化したりといった取り組みを進めるのが企業側の課題です。
定着しやすい人材に共通するポイント
新卒社員の中でも、定着しやすい人材にはいくつか共通する傾向があります。
企業側が重視しているのは、環境への適応力や長期的な視点で働く意欲です。
定着しやすい人材の特徴は、以下を参照ください。
- どのような業務でも前向きに取り組む姿勢がある
- 周囲とのコミュニケーションを積極的に行い関係構築ができる
- 入社前から仕事内容や業界の現状を正しく理解している
- 仕事を通じて成長する意欲が強く自己研鑽を続けている
- 問題が起きた際に相談するなど自己解決にこだわり過ぎない柔軟性がある
上記の資質を持つ人材は、入社後にギャップが生じても乗り越えやすく、企業からの評価も高まりやすいでしょう。
転職エージェントに相談するのもおすすめ
転職活動を進めるうえで、ひとりで全てを決めるのは大きな負担です。
とくに新卒3年以内の転職では、キャリアの方向性や応募先の選び方に不安を抱える人が少なくありません。
そうした不安を軽減する手段として、転職エージェントの活用が効果的です。
アゲルキャリアでは、20代や第二新卒・既卒の支援に特化した専任エージェントが、最短1週間で内定獲得まで伴走してくれます。
面談を通じて希望や適性を見極め、個別に合う求人を提案するスタイルなので、効率的かつ安心して転職活動を進められる点が強みです。
自分ひとりで悩むよりも、プロのサポートを受けながら転職活動を進めることで、より満足度の高いキャリア選択が可能になります。
まとめ
新卒3年以内の離職は決して特別なことではなく、全体の約3割が早期に職場を去っているというデータが示すように、多くの人が経験しています。
早期にキャリアを見直すことにはメリットもあり、第二新卒としての市場価値を活かして新しい挑戦が可能です。
一方で、忍耐力や経験不足といった見られ方をされるリスクも存在するため、しっかりと準備をして決断することが重要です。
自己分析や業界研究を徹底し、転職理由や今後の方向性を明確にすることで、後悔しない転職活動が実現します。
さらに、アゲルキャリアのような専門性の高い転職エージェントに相談することで、効率よく理想のキャリアを築く支援を受けられます。
自分の未来を切り拓くために、正しい判断と行動でキャリアを前に進めていきましょう。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!