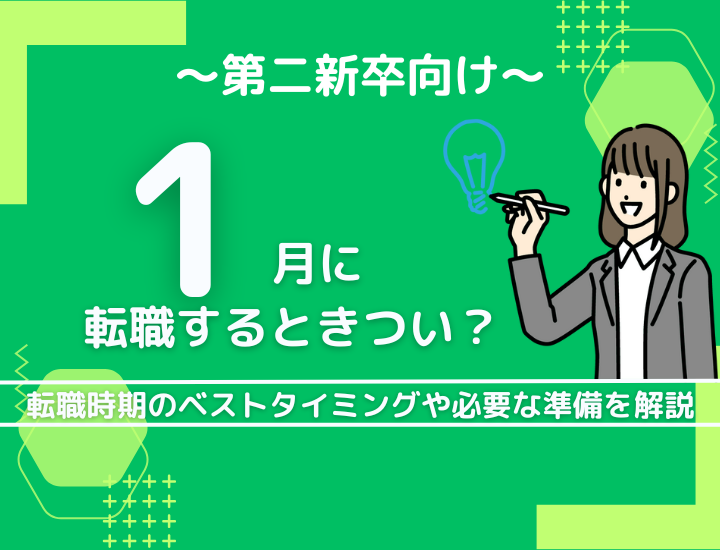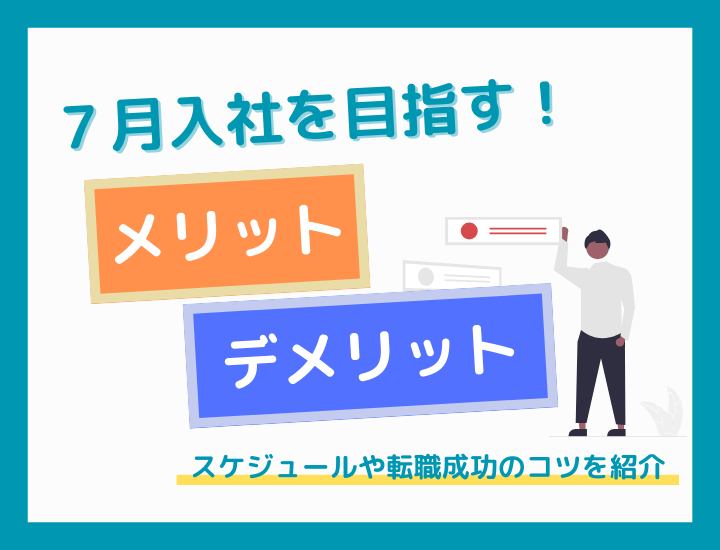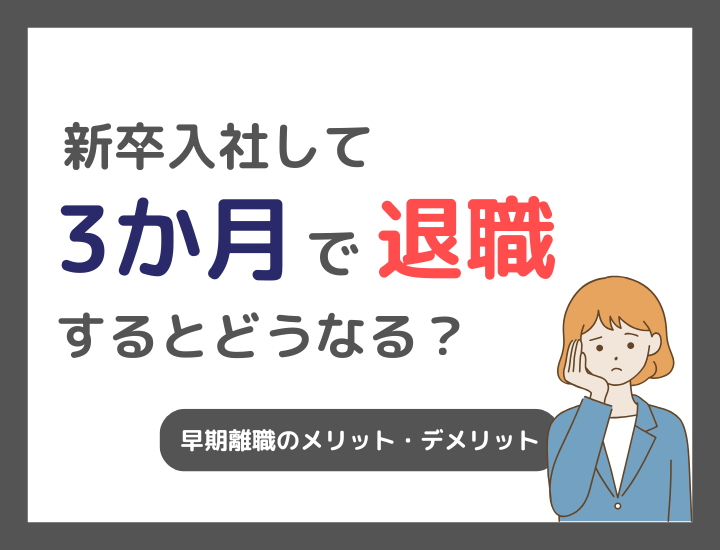
新卒者が三ヶ月で仕事を辞めたら?早期退職のメリット・デメリットや転職のポイント
はじめに
新卒入社からわずか三ヶ月で退職を考えることに、不安や後ろめたさを抱える方も少なくありません。
しかし、早期離職には確かにデメリットもある一方で、キャリアを見直す大きなチャンスにもなり得ます。
本記事では、新卒三ヶ月で辞めた場合の転職活動への影響、メリット・デメリット、転職成功のコツまでを詳しく解説します。
悩みを乗り越え、次のステップへと踏み出すための具体策を紹介していくので、ぜひ参考にしてください。
新卒入社三ヶ月で辞めたら転職で不利になる?
早期離職は企業側に懸念を抱かせやすい一方で、正しい準備をすれば転職チャンスを広げられます。
短期間での退職理由については、必ず面接で説明を求められるため、前向きな伝え方が重要です。
ただし、第二新卒枠を歓迎する企業も増えており、自己分析と志望動機作成を丁寧に進めることで、印象をプラスに変えることは十分可能です。
新卒入社後三ヶ月での退職は「第二新卒」
新卒から三ヶ月で会社を離れた場合、多くのケースで「第二新卒」として扱われます。
第二新卒とは、一般的に「卒業後3年以内に就業経験を経て離職した若手層」を指します。
既卒や通常の中途採用とは異なるポイントも押さえておきましょう。
各種分類の違い
- 第二新卒:卒業後就職し、3年以内に退職
- 既卒:卒業後、就業経験なし
- 中途採用者:一定の実務経験を持つ人
第二新卒は柔軟性やポテンシャル重視で採用されることが多く、とくに成長企業や中小ベンチャーにおいてニーズが高まっています。
三ヶ月で退職する新卒者の割合
三ヶ月以内に離職する新卒者は意外に少なくない現状があります。
大学卒のうち約5%、高卒や専門卒を含めるとさらに高い割合で早期離職が発生してるというデータもありました。
研修期間中や配属直後にミスマッチを感じ、離職を決断するケースが多い傾向です。
新卒時のミスマッチは個人の責任だけではなく、企業の育成体制にも課題がある場合が少なくありません。
損害賠償・違約金の有無
新卒三ヶ月で辞めた場合でも、原則として損害賠償や違約金が発生することはありません。
労働基準法により、退職の自由が認められており、会社側が損害賠償を求めることは基本的に認められていないからです。
特殊な契約(例:留学費用支援など)を伴う場合は、個別対応が求められるため、事前に契約書を確認することが重要です。
通常の早期退職では金銭トラブルに発展する心配はほぼありません。
新卒入社後三ヶ月で辞めた人に共通する理由
新卒入社後すぐに退職を選ぶ人には、いくつか共通する背景があります。
ここでは、とくに多く挙げられる理由を4つ取り上げ、それぞれの特徴や具体的な内容について詳しく解説していきます。
- 労働環境に不満があった
- 人間関係が劣悪だった
- 給与が良くなかった
- 仕事が向いていなかった
労働環境に不満があった
労働条件への不満は、早期離職の主要な要因の一つです。
実際に働き始めてみると、求人情報と実態に大きな差がある場合も珍しくありません。
具体的には、長時間残業や休日出勤、配属先での過剰な労働負荷、教育・研修制度がほとんど機能していないことが挙げられます。
このような過酷な状況に置かれた結果、心身に不調をきたし、やむなく短期間での退職を決断する新卒者が一定数存在します。
人間関係が劣悪だった
職場の人間関係に悩まされるケースも、三ヶ月以内の離職理由として非常に多く見られます。
上司からの理不尽な𠮟責やパワハラ、同僚との意思疎通不足による孤立、チームワークを無視した業務スタイルにストレスを感じる人が多く、新しい環境に適応する中で、周囲のサポートが得られないと強い孤立感に陥ってしまいます。
ストレスのある環境では本来の能力を発揮できず、自己肯定感も低下しがちです。
結果として、心身のバランスを保つために早期退職を選ぶことになるのです。
給与が良くなかった
入社前に期待していた給与水準と実際の待遇に大きなギャップを感じた場合、離職を考えるきっかけになりやすいでしょう。
とくに、収入に直結する部分への不満は生活設計にも直撃するため、深刻な悩みにつながります。
初任給が想定よりも少なく、昇給や賞与の仕組みも曖昧であると、将来の経済的な不安を感じやすくなります。
経済的な不安を抱えながら働き続けるのは精神的にも負担が大きく、キャリア初期段階での軌道修正を目指して早期転職を決断する人もいます。
仕事が向いていなかった
実際に業務に取り組んでみた結果、自分の適性と大きくズレていることに気づく場合もあります。
就職活動時には気づかなかった部分が、実務を通して明確になることは珍しくありません。
- 業務内容に興味が持てない
- 求められるスキルが自分に合わない
- 将来像が描けずモチベーションが続かない
上記のように感じた場合、無理に続けるよりも、新たなキャリアパスを見直す判断が早期離職へとつながることがあります。
自己分析のやり直しを通じ、より適した道を探す動きが生まれるのです。
新卒三ヶ月で退職するメリット6選
三ヶ月での早期離職はマイナスに見られがちですが、視点を変えればポジティブな側面も見えてきます。
ここでは、早期退職によって得られる6つのメリットについて具体的に紹介していきます。
- キャリアの軌道修正がしやすい
- ミスマッチのない転職が目指せる
- 自分に合わない環境を認識できる
- ストレスを回避できる
- 無駄な時間を使わずに済む
- 第二新卒にはニーズがある
キャリアの軌道修正がしやすい
早期に辞めることで、誤った方向に進んでしまうリスクを最小限に抑えられます。
経験が浅いうちであれば、未経験職種へのチャレンジも比較的受け入れられやすいため、柔軟な進路変更が可能です。
また、社会に出たことで本当に重視したい条件や働き方に気づくケースもあり、結果的に満足度の高いキャリア形成につながります。
ミスマッチのない転職が目指せる
実際に社会経験を経たからこそ、自己分析と企業選びの精度が格段に高まります。
就職活動時には見えなかった実態を知ったうえでの転職活動は、ミスマッチを防ぐ大きな武器になります。
実体験を踏まえたうえでの再スタートは、理想的な職場にたどり着きやすいというメリットを持っています。
自分に合わない環境を認識できる
早期に違和感を抱いたことは決してネガティブな経験ではありません。
むしろ、自分に合わない要素を認識できたこと自体が、今後の職場選びに大きな財産となります。
経験を活かして、次の職場選びではより慎重な目線で自分にフィットする環境を探せるようになるでしょう。
無駄な時間を使わずに済む
向いていない職場で何年も我慢してしまうと、取り返しのつかない時間を費やしてしまう恐れがあります。
早めに見切りをつけることで、次に進むための時間を有効に使えます。
スキル取得への早期着手やキャリアパスの再構築、成長市場へのチャレンジなどに時間をかけることができます。
未経験の職種にチャレンジする場合は、若手が求められる傾向があるため、早めの行動が重要です。
とくに成長産業やベンチャーなどに飛び込むには、スピード感が重要なため、早期行動のメリットは非常に大きいでしょう。
第二新卒にはニーズがある
短期間の離職歴があっても、「第二新卒」としての市場価値は非常に高まっています。
新卒と異なり、新卒研修を受けているためビジネスマナーが身についていており、採用コストを減らすことが出来ます。
また、若手人材であることから既成概念にとらわれにくく、柔軟な思考や順応力があることへの期待をする企業も多いようです。
多くの企業は、柔軟性と成長意欲を重視して第二新卒層を積極採用しています。
社会人経験が浅くても、チャンスは十分にあります。
早期離職を必要以上に悲観せず、戦略的に次のステップを踏んでいきましょう。
新卒三ヶ月で退職するデメリット5選
早期離職にはメリットもありますが、当然ながら注意すべきデメリットも存在します。
ここでは、新卒入社から三ヶ月以内に辞めた場合のリスクについて順番に解説していきます。
- 説得力のある退職理由が必要になる
- 応募できる企業に制限がかかることもある
- 転職癖がついてしまう可能性がある
- 前職より待遇が悪くなる
- 再離職を疑われる
説得力のある退職理由が必要になる
短期間での退職は、面接官に「なぜすぐ辞めたのか」という疑問を強く抱かせます。
表面的な理由では納得を得にくく、説得力のある説明が求められるようになります。
退職に至った背景に合理性があるか、次の職場で長く働く意欲が伝わるかは、面接で問われる重要なポイントになるでしょう。
とくに「会社が悪かった」だけでは信頼を得ることは難しいため、自己成長意欲と具体的な改善策を合わせて伝えることが重要です。
応募できる企業に制限がかかることもある
三ヶ月以内に辞めた経歴を持つ場合、すべての求人に自由に応募できるとは限りません。
とくに大手企業や中途即戦力を重視する企業では、応募条件に制限がかかるケースも出てきます。
転職先を探す際は柔軟な視野を持ち、中小企業や成長ベンチャーも積極的に検討する姿勢が必要です。
転職癖がついてしまう可能性がある
一度「辞めても大丈夫」という経験をすると、次も簡単に離職を選んでしまうリスクが高まります。
この傾向は無意識に染みつきやすく、キャリア形成に悪影響を及ぼしかねません。
転職を繰り返すと職歴に一貫性がなくなり、採用担当者から敬遠されるリスクも上がります。
慎重なキャリア設計が求められます。
前職より待遇が悪くなる
第二新卒として再出発する場合、前職よりも待遇が下がるケースも少なくありません。
とくに未経験職種への転向を希望する場合、初任給からやり直す覚悟が必要になることもあります。
待遇ダウンをネガティブに捉えず、将来的な成長やキャリアアップを見据えてポジティブに受け止める姿勢が重要です。
再離職を疑われる
短期離職歴があると、次の転職活動でも「またすぐ辞めるのではないか」という目で見られるリスクがあります。
企業は採用にコストと時間をかけているため、慎重な判断を下します。
再離職の不安を払拭するには、自己分析に基づいた一貫した志望動機と、将来を見据えた強い意志を伝えることが不可欠です。
新卒入社三ヶ月で転職する場合の流れ
三ヶ月以内に転職を考える際は、無計画に進めると後悔するリスクも高まります。
ここでは、スムーズに次のステップへ移行するための具体的な流れを4つのステップに分けて紹介していきます。
- 転職活動の準備をする
- 上司に辞めたいことを伝える
- 退職届を提出・受理してもらう
- 関係者に挨拶する
1.転職活動の準備をする
最初に取り組むべきは、自己分析と情報収集です。
勢いだけで辞めてしまうと、その後の転職活動が迷走しやすいため、冷静に準備を整えることが重要です。
また、希望条件の整理も欠かせません。
希望年収、業界、職種、勤務地など優先順位をつけることで、転職活動の軸がぶれにくくなります。
2.上司に辞めたいことを伝える
転職の準備が整ったら、次は現在の職場に退職の意思を伝えます。
この段階では、感情的にならず、冷静かつ簡潔に伝えることを心がけましょう。
退職を伝える際は、業務に支障が出ない時期を選ぶことや、事前にアポイントを取ってから報告するなど、相手への配慮をしながら伝えられると良いでしょう。
また、円満退職を目指すためには、会社や上司への不満を口にせず、あくまでも「自己成長のため」という前向きな理由を伝える姿勢が大切です。
3.退職届を提出・受理してもらう
口頭での退職意志表明だけでは手続きが完了しないため、正式に退職届を提出する必要があります。
書面で提出することで、退職の意志が正式に記録されることになります。
退職届は、退職希望日の1~2ヶ月前に提出するようにしましょう。
また、会社指定のフォーマットがあるかを確認し、提出後はされたか必ず確認するようにしてください。
受理後は退職日までの引き継ぎスケジュールが組まれるので、トラブル防止のためにも、提出した後はこまめに上司と連絡を取り合いましょう。
4.関係者に挨拶する
退職日が近づいたら、これまで関わった上司・同僚・取引先への挨拶を忘れずに行うことが重要です。
短期間の在籍であっても、社会人としての礼儀を尽くすことで、最後の印象を良いものにできます。
「短期間しかいなかったから」と気後れせず、感謝の気持ちを伝えることで、自身の社会人マナーも磨かれるでしょう。
新卒入社三ヶ月で辞めてから転職する10のコツ
三ヶ月以内で会社を辞めた後の転職活動では、通常の就職活動とは異なる視点が必要です。
ここでは、転職成功を引き寄せるために意識すべき10個の具体的なコツを詳しく紹介します。
- 就職と転職の違いを把握しておく
- 在籍中に転職活動を開始する
- 退職に至った理由を客観的に分析する
- 自分の価値観を再確認する
- 企業研究をして志望先のことを知る
- 希望条件に優先順位をつける
- ポジティブな退職理由を考える
- 面接で嘘をつかないように心がける
- 中小企業やベンチャー企業も視野に入れる
- 転職エージェントを活用する
就職と転職の違いを把握しておく
新卒時の就職活動と、転職活動は根本的に求められるポイントが異なります。
就職活動はポテンシャル重視で育成前提な一方で、転職活動は即戦力や適応力を重視する傾向があります。
自分の伝え方や自己PR内容も、学生時代の活動ではなく、社会人経験を中心にアピールしていく必要があります。
とくに社会経験を経た立場として、企業からの期待値が変わる点を理解しておきましょう。
在籍中に転職活動を開始する
可能であれば在籍中に転職活動を始めるほうが、経済面・精神面ともに安定します。
退職してから探す場合、焦りが出やすくなり、企業選びで妥協してしまうリスクも高まります。
無理なく活動を続けるために、面接日程の調整や連絡対応に注意しながら進めましょう。
退職に至った理由を客観的に分析する
単なる不満ではなく、自分の行動や選択を客観視することが重要です。
自己反省を深めることで、次に活かせる経験に変えられます。
まずは、当時の自分に何が足りなかったか、職場環境の何が合わなかったか、今後重視したい要素は何かを分析するとよいでしょう。
冷静な視点で振り返られれば説得力ある転職理由にもつながり、面接でプラスに働きます。
自分の価値観を再確認する
どのような働き方や環境を重視したいか、改めて自分の価値観を整理することも欠かせません。
結果、ブレない軸を持って求人選びができるようになります。
例えば、働き方であれば、リモートか出社かは、自身の生活スタイルに大きく影響するでしょう。
また、評価制度や給与体系、組織風土や文化も確認するべき項目になります。
過去の違和感をヒントに、自分に合う企業像を明確に描きましょう。
企業研究をして志望先のことを知る
求人票だけで判断せず、志望する企業の実態をしっかり調べることが大切です。
社風や事業戦略を理解すれば、入社後のギャップも減らせます。
- 企業理念・ビジョン
- 直近の業績・今後の展望
- 社員の口コミ・評判
事前にリサーチを徹底すれば、面接でも具体的な志望動機が語れるようになります。
希望条件に優先順位をつける
すべての希望を叶えようとすると、転職活動が長期化する可能性があります。
どこを譲れて、どこは譲れないかを明確にしておきましょう。
妥協する項目と絶対に譲れない項目を整理しておくことで、迷わず決断できるようになります。
ポジティブな退職理由を考える
早期退職の理由をそのまま伝えると、マイナス印象を与えてしまう危険があります。
ネガティブな理由も前向きな言葉に置き換えて伝えましょう。
例えば、「給与が低かった」は「成果に応じた評価を重視したい」、「人間関係が合わなかった」は「チームワークを重視する環境で働きたい」と変換することができます。
このように、前向きな表現にすることで、転職への意欲や成長志向を伝えやすくなります。
面接で嘘をつかないように心がける
面接では多少伝え方を工夫しても、事実を偽ることは避けるべきです。
経歴詐称や事実の隠蔽は、後々発覚すると信用を大きく損なう原因となります。
内定取り消しとなってしまうこともあるでしょう。
素直さと一貫性を大切にしながら、説得力あるストーリーを構築していきましょう。
中小企業やベンチャー企業も視野に入れる
大手企業にこだわりすぎると、選択肢が狭まりがちです。
成長性の高い中小企業やベンチャーにも目を向けることで、チャンスを広げることができます。
社員1人1人の裁量権が大きく、経営層とも近い距離で仕事ができることから、社内で自分の意見や提案が反映されやすいというメリットがあります。
昇進すれば、20代からマネージャーに抜擢されたり、新規事業立ち上げに関われたりすることもあるのです。
また、成果主義の傾向が強く、自分の実績が収入にも繋がるのでやりがいも大きくなるでしょう。
視野を広げることで、今まで気づかなかった可能性を掴めるかもしれません。
転職エージェントを活用する
一人での転職活動に不安を感じるなら、転職エージェントを活用するのも有効な選択肢です。
プロのサポートを受けることで、効率的に内定獲得を目指せます。
転職エージェントを利用すれば、市場には出回らないような優良求人の紹介から面接対策、内定まで完全サポートを受けることができます。
また、転職エージェントは、企業と直接条件の交渉ができるので、前職よりもよい条件で働ける可能性が高まります。
自己流で進めるよりも成功率が高まるため、積極的に活用を検討しましょう。
「転職三ヶ月の壁」もある
新しい職場に馴染んだと思った矢先に訪れるのが「転職三ヶ月の壁」です。
ここでは、転職後に直面しやすい転職三ヶ月の壁の原因と、乗り越えるための具体策について詳しく紹介していきます。
転職三ヶ月の壁に当たる原因
転職直後は緊張感や新鮮さで前向きに過ごせますが、三ヶ月が経過するころになると、次第に理想と現実のギャップが浮き彫りになりやすくなります。
業務内容が想像と違っていることや、人間関係での疎外感、成長機会の乏しさにより転職を考える人が増えるようです。
違和感に直面することで「また転職すべきか」と悩み始める人も少なくありません。
しかし、短期間で結論を急ぐと、同じ失敗を繰り返すリスクも高まります。
家族や転職エージェントなど第三者に相談して、納得できる決断をすることが大事です。
転職三ヶ月の壁を乗り越える方法
違和感を感じたときこそ冷静な行動が求められます。
転職三ヶ月の壁をうまく乗り越えるためには、感情に流されず、具体的な対策を講じることが大切です。
- 新たな目標を設定してモチベーションを維持する
- コミュニケーションを増やして関係性を深める
- 小さな成功体験を積み重ねて自己肯定感を高める
三ヶ月という短い期間での評価は、あくまでも一時的なものです。
柔軟に視点を変えながら、自分にとってベストな選択肢を模索していきましょう。
まとめ
新卒三ヶ月での退職は、確かに転職市場で慎重な対応を求められます。
しかし、自己分析を深め、前向きな志望動機を磨くことで、早期離職を乗り越えてキャリアを再構築することは十分可能です。
本記事で紹介した準備方法や面接対策を実践しながら、自分に合った道を見極めていきましょう。
短期離職を必要以上に悲観せず、新たな挑戦を通じて未来を切り拓く一歩を踏み出してください。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!