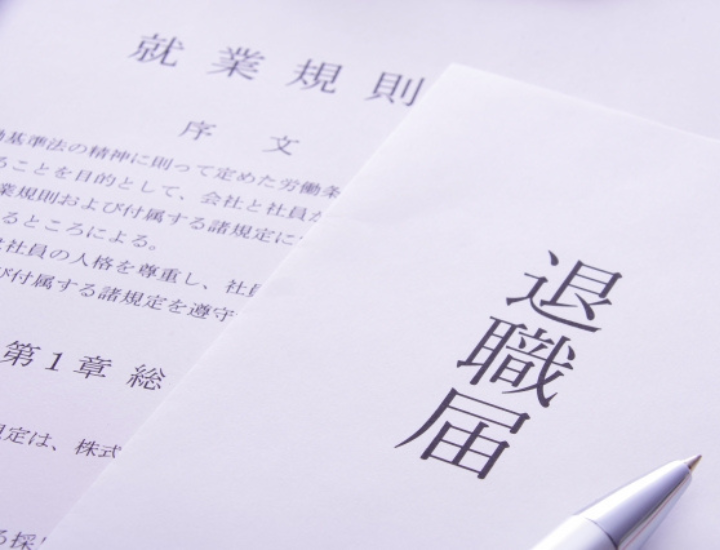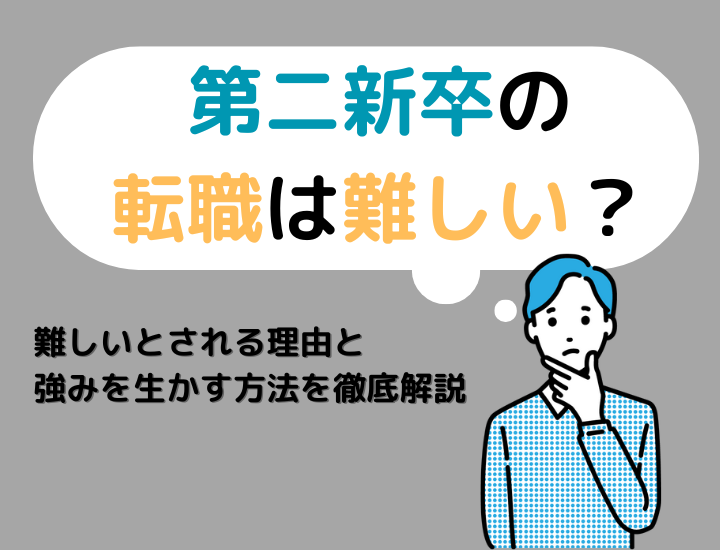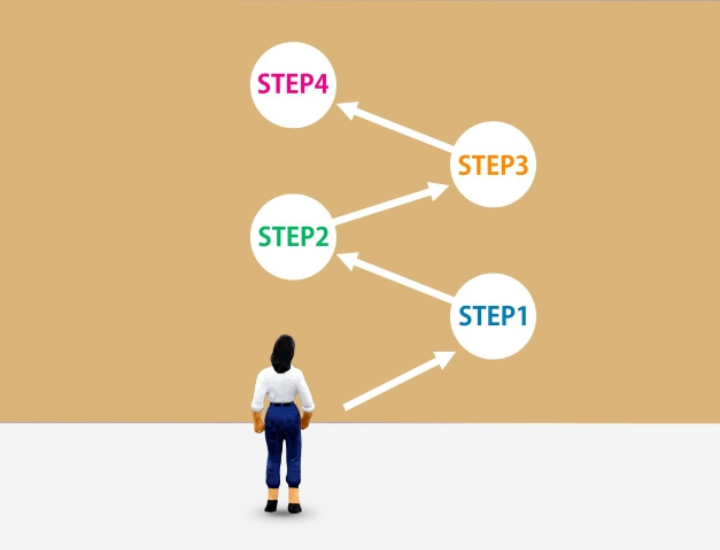
第二新卒の転職は辞めてからがおすすめ?在職中の転職とあわせて比較
はじめに
新卒で入社した会社を1〜3年ほどで退職した人材のことを、第二新卒といいます。
第二新卒は新卒と異なりある程度の社会人経験を有していることから、若年層の人材を獲得しようと考えている企業から重宝される傾向にあるのが特徴です。
ある意味では「転職しやすい状態」とも取れる第二新卒ですが、考えなくてはいけないのが転職活動を開始するタイミングでしょう。
転職しやすいとはいえ、今就いている仕事を辞めてから転職すべきか、在職しながら転職活動を進めるべきかは慎重に考えなければなりません。
そこで今回は、第二新卒が転職活動を開始するうえで気になる、転職活動を「辞めてから進めるべきか?」という疑問について解消していきます。
在職中と退職後、それぞれのタイミングにおける転職活動のメリット・デメリットや年齢との関係性、転職を成功させるコツもまとめています。
転職を検討している第二新卒、第二新卒になって転職を進めようと考えている新卒入社の方はぜひ参考にしてください。
在職中に転職活動をすることは違法?
在職中に転職活動をすること自体は、法律上全く問題ありません。
日本の労働法では、労働者に職業選択の自由が保障されており、退職するかどうか、転職活動をするかどうかは個人の自由です。
そのため在職中に求人サイトを利用したり、企業に応募したり、面接を受けたりする行為は違法行為ではありません。
ただし注意すべき点もいくつかあります。
勤務時間中に転職活動をすることは、職務専念義務や就業規則違反と判断される可能性があるためNGです。
履歴書や応募書類の作成、面接などは就業時間外に行うようにしましょう。
また社内のパソコンやメールアドレスを使って転職活動を行うのも避けるべきです。
在職中に転職活動を進める場合は、勤務先との信頼関係を損なわないよう、就業規則やビジネスマナーを守りながら慎重に進めましょう。
円満退職につなげるためにも、立つ鳥跡を濁さないような姿勢が求められます。
辞めてから転職活動を始める人は多い?
第二新卒を含む若手社会人の中には、「一度退職してから転職活動を始める」という選択をする人も少なくありません。
特に精神的・肉体的に余裕がなくなってしまったケースや、ブラック企業など労働環境に問題がある職場からの退職が多いでしょう。
「まずは退職して心身を整えたい」という理由で、離職後に活動を始める傾向が見られます。
転職者のうち「勤続9.5か月以内に辞めた経験がある人」は40.8%(マイナビ「中途採用実態調査2024年版」)というデータもあり、決して珍しい選択ではないと言えるでしょう。
ただし「辞めてからの転職」は収入が途絶えるリスクや、空白期間が長引くことによるマイナス印象といったデメリットもあります。
そのため辞めてからの転職活動を選ぶ人の多くは、「すぐにでも退職せざるを得ない理由がある」か、「貯蓄や次の転職先の見通しが立っている」など、何らかの準備が整っている場合がほとんどです。
自分にとって最適なタイミングを見極めなければなりません。
退職後・在職中どちらが良い?
第二新卒に限らず、転職活動を始めるタイミングについて考えることは必要不可欠です。
ここでは、退職後に転職活動を行うべき人・在職中に転職活動を行うべき人それぞれの特徴をまとめています。
自身がどちらに該当するか、参考のうえ転職活動を開始するタイミングを検討しましょう。
退職後に転職活動を行うべき人
一般的には在職中の転職活動がおすすめされますが、退職後の転職でも問題ないとされるパターンもいくつか存在します。
例えば、すでに転職先の候補が確定しており、かつ採用される自信がある方や、転職活動が迅速に進むことが予想できる方は、退職後に転職を検討しても差し支えありません。
人事権を持つ方から直接オファーを受けている場合や、市場価値の高い特別なスキルや資格を持っている場合などが該当するでしょう。
退職してからの転職は、職歴に空白期間が生じることが一般的にはマイナスとされますが、転職先の候補が確定しているようなケースでは、デメリットを感じることなく転職を成功させることが可能です。
また、労働環境の問題や家庭の事情など、すぐにでも退職しなければならない理由がある場合も、退職後の転職が適切です。
労働条件を例に挙げると、過度な残業やパワーハラスメントによるストレスが溜まり、心の健康を害する可能性がある場合、転職活動を含めて働くこと自体が難しくなる恐れがあります。
そのような状況では、早期に退職し、新たな職場を探すことが推奨されます。
もうひとつ、家庭の状況が退職を要する場合です。
例えば、配偶者の転勤に同行する必要がある、または親の介護が必要な場合などです。
このような状況では、キャリアに空白期間が生じても、その理由が明確であれば、応募先企業に理解されやすいでしょう。
退職後に転職活動を進めるメリットとデメリットについては、後述しているのでぜひ参考にしてください。
在職中に転職活動を行うべき人
「退職後に転職活動を行うべき人」の項目で紹介した特徴に当てはまらなければ、在職中の転職活動がおすすめでしょう。
加えて、金銭的に余裕がない、現職と次の職場で働く期間を空けたくない場合なども、在職中に転職活動を行うべき人の特徴です。
在職中に転職活動を行う場合は、まず希望する転職時期をベースに、余裕をもって行動計画を立てることが重要です。
転職活動に必要な時間を逆算し、スケジュールを確実に管理してください。
次に、応募する企業に現在の雇用状況を透明に伝えることが望ましいでしょう。
これにより、選考プロセス中のスケジューリングがスムーズに進むようになります。
また、転職活動の目的や求める職種・業界など、自身の転職における主軸をはっきりさせることも、目標に合った求人を効率的に見つけるうえで大切です。
転職活動の具体的なステップとしては、どのような活動をいつまでに実施するかを明確にし、それに基づいた行動計画を作成する必要があります。
例えば、応募書類の準備や求人情報の収集などは、可能な限り早期に始めることがおすすめです。
なお、在職中に転職活動を行うメリット・デメリットに関しても、後述する内容を参考にしてください。
年齢の若い第二新卒は辞めてからの転職でもチャンスあり
同じ第二新卒でも、年齢によって転職の成功率が変動します。
年齢による転職の成功率は特に、未経験の職種に転職するうえで顕著になるでしょう。
例えば「未経験の状態で営業職」を目指している、以下3名の場合だとどうでしょうか。
- 接客業での経験が3年の25歳
- 接客業での経験が5年の27歳
- 接客業での経験が7年の29歳
この場合は「1」の「接客業での経験が3年の25歳」が、もっとも転職の成功率が高いといえます。
一見すると社会人経験の長い「3」かもしれないと考えがちですが、あくまで「未経験」であることを考えると、今後の育成幅などを考慮するとより若い人材が優遇されると判断できます。
年齢を問わず経験値が優遇されるのは、あくまで同職種の転職や経験者を募集している場合と捉えておきましょう。
次に、第二新卒が転職で有利になる理由について見ていきます。
若さとポテンシャルで勝負できる
第二新卒は、社会人としての基礎を身につけながらも、まだ若く柔軟性が高い人材として企業から注目されています。
特に20代前半の求職者は、職務経験が浅くても「これからの成長に期待できる人材」として評価されやすく、ポテンシャル採用の枠に入りやすいのが特徴です。
そのため、たとえ現職を辞めてから転職活動をスタートしても、「まだ若いから」「これから経験を積めばいい」といった前向きな捉え方をされることが多いでしょう。
ブランクが短期間であれば大きなマイナスになりにくい傾向にあります。
また新卒と違い一定の社会経験があることで、基本的なビジネスマナーや仕事への責任感が備わっている点も企業にとっては魅力です。
自分の強みや将来のビジョンをしっかりとアピールできれば、若さと伸びしろを評価されて内定につながる可能性は十分あります。
特に未経験職種へのチャレンジを考えている方は、吸収力のある若手という立場が武器になるでしょう。
退職後でも、年齢という強みを活かせるうちに行動することが、転職成功への近道です。
退職理由をポジティブに受け止められやすい
第二新卒は、一般的に「やむを得ず退職した」というよりも「より自分に合った環境を求めて再スタートを切った」という前向きな姿勢が評価されやすい傾向にあります。
年齢が若い場合は、キャリアの方向性を模索する過程での転職と捉えられ、退職理由がマイナス要因として強く印象づけられることは少なくなるでしょう。
企業側も、若手人材には「早めに適職にたどり着くことが重要」という認識を持っており、入社後のミスマッチを避ける意味でも転職経験を前向きに捉えるケースが増えています。
前職で感じた課題や改善したい点を明確に語れると、自身の成長意欲や課題解決力があると判断され、面接時の印象も大きく向上するでしょう。
退職理由を話す際は、「何が合わなかったか」だけでなく、「次にどう生かすか」「どんな環境で力を発揮したいか」を合わせて伝えることがポイントです。
単なる愚痴ではなく自己分析の結果として評価されやすく、若手ならではの柔軟さと前向きな思考が伝わるアピールにつながります。
新卒採用と同じくニーズが高い
企業にとって、第二新卒は即戦力と将来性を兼ね備えた存在です。
社会人経験が1〜3年程度あるため、基本的なビジネスマナーや社内ルールに対する理解がある一方で、柔軟に新しい企業文化に適応しやすいと期待されています。
新卒採用を重視する企業では、毎年の新卒入社に加えて第二新卒枠を設けるケースも多く、「新卒並みの育成余地がある」「教育し直しが利く」人材として採用意欲が高まっています。
実際、採用市場では第二新卒専用の求人も数多く見られ、ポテンシャル採用枠の一つとして安定したニーズがあるでしょう。
また業界によっては「若手が不足している」「人材が定着しづらい」といった背景から、20代前半の求職者が非常に重宝されることもあります。
若さや吸収力のある段階で入社してほしいと考え、企業側も積極的に採用しています。
第二新卒は、新卒と同じように、意欲や人物重視で選考されることが多いでしょう。
自分自身の強みや志望理由をしっかり伝えることで、十分に内定を狙うことができるのが強みです。
未経験へも転職がしやすい
第二新卒は、他業種・他職種などの「未経験分野」への転職を希望する人にとって、大きなチャンスのある時期です。
企業側も「まだ若く、柔軟性が高い」「これから育てていける人材」として第二新卒を捉えており、経験よりも人柄やポテンシャルを重視する傾向が強くなっています。
社会人としての基本的なマナーや業務の流れを一度でも経験している点は、新卒にはない安心材料です。
そのため、未経験職でも一から教育しやすいと判断され、異業種からの挑戦も受け入れられやすいのが特徴と言えるでしょう。
第二新卒を対象にした未経験歓迎の求人も多く、営業職や人事、IT業界など幅広い分野で門戸が開かれています。
「前職では適性を発揮できなかったが、新しい分野で力を試したい」という姿勢を素直に伝えることで、むしろ成長意欲や前向きなキャリア志向として評価される場合もあるでしょう。
将来の可能性を広げたい第二新卒にとって、未経験職種への挑戦は現実的かつ有利な選択肢の一つです。
辞めてから第二新卒として転職活動するメリット
第二新卒が現職を辞めてからのメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
ここでは、第二新卒が辞めてから転職する、以下4つのメリットについて解説します。
- 転職活動のみへの注力が可能
- 心身をリフレッシュできる
- 失業保険を受給できる可能性
- スキルアップや資格取得期間の確保
転職活動のみへの注力が可能
退職後には、時間的・肉体的、そして精神的な余裕が生まれることが多いため、転職活動に専念しやすくなります。
そのため、面接の日程調整や自己分析、面接の準備にじっくりと取り組むことができるでしょう。
特に、現在の職場での業務量が多過ぎるために転職活動に充分な時間を確保できない方や、極度のストレスを感じている方にとって、辞めてから退職する選択肢は適しているかもしれません。
心身をリフレッシュできる
退職後に一定の休息期間を挟んで転職活動を始めることで、心身をリフレッシュできるのは、第二新卒にとって大きなメリットです。
前職でのストレスや疲労が蓄積されたままでは、前向きな姿勢で求人を探したり面接に臨んだりすることが難しいこともあるでしょう。
一度立ち止まることで、これまでの仕事を冷静に振り返り、自分が本当にやりたいことや適性を見直す時間が確保できます。
また規則正しい生活や趣味の時間、自己研鑽にあてることで、気持ちを切り替えた上で再スタートが切れるのも大きな利点です。
「何となく続けてきた仕事だった」「本音では別の道に進みたかった」という思いを抱えたまま働き続けるよりも、一度リセットすることで新たな選択肢が広がることもあります。
体調を整えたり、資格取得に挑戦したりと、有意義な時間の使い方ができれば、退職後のブランクもマイナスにはなりません。
冷静な判断力と前向きなエネルギーを取り戻すことが、転職成功への第一歩です。
失業保険を受給できる可能性
退職後、特定の条件を満たす場合であれば、ハローワークにて失業保険(正確には、求職者給付の基本手当)の申請が可能です。
収入が途絶えることへの不安で転職活動への一歩を踏み出せない方々にとって、自分が受給資格を有しているか確認することは一つの解決策となるでしょう。
自己都合で退職した場合でも、ハローワークに訪れ、求職登録を行うことで給付の受け取りが可能です。
ただし、積極的に就職活動を行い、いつでも就業可能な状態であるが、自身やハローワークの尽力にもかかわらず、職を見つけることができない「失業状態」にあることが必要です。
また退職日の2年以内に、合計で12ヶ月以上の被保険者期間を有している必要もあります。
スキルアップや資格取得期間の確保
退職後の時間を活用して、転職前に資格を取得したり、知識やスキルを向上させたりすることは非常に有益です。
例えばハローワークでは、失業保険を受給している方を対象とした「公共職業訓練(離職者訓練)」と、受給資格のない方向けの「求職者支援訓練」という、2つの訓練プログラムを提供しています。
これらの訓練は無料で受講可能であるため、退職後の時間を有効活用したい方はぜひ情報を収集してみましょう。
辞めてから第二新卒として転職活動するデメリット
第二新卒が現職を辞めてから転職するのはメリットがあるものの、以下に挙げるデメリットがあることもしっかり把握したうえでどのように転職活動を進めるのか考えることが大切です。
- 収入のストップ
- 希望条件を妥協してしまうおそれがある
- 職歴の空白欄
- モチベーション維持が困難
収入のストップ
退職が原因で収入がなくなると、転職活動を急いでしまい、本来望まない企業に入社してしまうことがあります。
収入源が途切れ、仕事がない状態は非常に不安定かつ心配の種となるため、金銭面に余裕がない場合は辞めてからの転職は適していないでしょう。
自分自身で「大丈夫」だと過信せず、退職前には生活費を含む必要経費の計画を綿密に立て、資金計画を確実に準備しておくことが賢明です。
希望条件を妥協してしまうおそれがある
第二新卒として退職後に転職活動をする場合、収入が一時的に途絶えることから「早く内定をもらわなければ」という焦りが生じやすくなります。
結果的に、本来重視していたはずの勤務条件や業務内容、職場環境などを妥協してしまい、自分に合わない企業に入社してしまう可能性があるでしょう。
貯金が少ない場合や家族の支援を得られない場合は、生活の安定を最優先せざるを得ず、希望とは異なる求人にも応募することがあるかもしれません。
結果として短期間で辞めてしまい、後悔してしまうケースも少なくないでしょう。
第二新卒はポテンシャル採用が多く、企業側も人柄や成長意欲を重視する傾向にあります。
しかしその分、自分らしい選択をするためには冷静さが必要です。
退職後に転職活動をする際は、焦らず計画的に行動することで、希望条件を守りながら納得のいく転職先を見つけられるようになるでしょう。
職歴の空白欄
転職過程において、職歴の中に空白期間が存在すると、一部の企業に不利な印象を与える可能性があります。
一般的に、転職活動には2〜3ヶ月程度を要するとされていますが、離職してからの期間がこれを超えて延びると、採用を検討している企業から「業務に対する感覚が鈍っているのでは?」や「何か採用に至らない理由があるのでは?」といった疑問を持たれます。
結果として、転職活動におけるハンディキャップになることがあるでしょう。
モチベーション維持が困難
退職してから時間が経過するにつれて、職に就いていない期間が延びると、自身のキャリアに対する方向性や目標を見失うことがあります。
職を離れることで、過去の職務経験を基にした自己評価が難しくなり、転職を通じて達成したい目標が曖昧になりがちです。
これにより、モチベーションの低下につながる場合もあります。
そのため、前職で叶えられなかった願望や、次なる転職で果たしたい目標を明確にすることが重要です。
辞めてから転職活動は何ヶ月以内にするべき?
第二新卒が退職後に転職活動を行う場合、一般的には3ヶ月以内に新しい職場を見つけるのが理想的です。
離職期間が長くなると「なぜ空白期間があったのか」「ブランク中に何をしていたのか」といった点について、企業側からの疑問や懸念が生じやすくなります。
もちろん、しっかりとした理由があれば長期の転職活動が不利になるとは限りません。
しかし選考においては「主体的に行動していたかどうか」が問われることがあります。
例えば自己分析を深めていた、資格の勉強をしていた、職業訓練に参加していたなどの説明ができれば、印象は大きく変わるでしょう。
一方で、あまりに急ぎすぎると希望条件を見失って妥協してしまうリスクがあります。
無理のない範囲で2〜3ヶ月を目安に転職活動をスタートさせるのが現実的です。
経済的な余裕や準備状況を踏まえて、計画的に動きましょう。
仕事を辞めてから転職活動をする際の注意点
仕事を辞めてから転職活動をする際の注意点は、以下の3つがあります。
- 経済的な余裕を確保しておく
- 空白期間の説明ができるようにしておく
- 社会保険・税金などの手続きを済ませる
経済的な余裕を確保しておく
仕事を辞めてから転職活動する場合、経済的な余裕を事前に確保しておきましょう。
なぜなら、収入が途絶える中での生活費や転職活動にかかる費用(交通費、証明写真代、スーツ代など)は意外と大きな負担になるからです。
貯金が十分でないと、焦って条件の悪い企業に決めてしまったり、本来の希望と合わない職場を選んでしまったりするリスクも高まります。
具体的に言えば、生活費の3〜6ヶ月分を目安に貯金しておくのが理想的です。
離職後は雇用保険(失業手当)を受給できるケースもありますが、給付までには待機期間や手続きが必要で、すぐに支給されるわけではありません。
そのため収入がない期間を見越した資金計画が必要です。
経済的な余裕があれば、じっくり自己分析や企業研究に取り組める時間も確保でき、納得のいく転職先を見つけやすくなります。
精神的にも安定した状態で活動を進めるために、金銭面の備えは欠かせません。
空白期間の説明ができるようにしておく
退職後に転職活動を始める場合、「なぜ退職後すぐに転職しなかったのか」という空白期間に対する質問は、面接でほぼ確実に聞かれます。
明確な説明ができないと「計画性に欠ける」「モチベーションが低い」といったマイナス評価につながる可能性もあるので、あらかじめ答えを準備しておきましょう。
例えば「資格取得のために勉強していた」「キャリアの棚卸しや自己分析をしていた」「体調を整える期間にしていた」など、前向きな理由と具体的な行動を組み合わせて伝えると説得力が増します。
反対に何もしていなかったという印象を与えると、自己管理能力に不安を持たれてしまうでしょう。
また空白期間が長引くほど説明の難易度も上がるため、転職活動を始めるタイミングはできるだけ早めに設定することも重要です。
空白期間をマイナスではなく、次の仕事に向けた「準備期間」としてポジティブに伝えられるよう、言葉選びにも注意しましょう。
社会保険・税金などの手続きを済ませる
仕事を辞めた後は、健康保険や年金、雇用保険、住民税などの手続きを速やかに行う必要があります。
現職を退職すると、それまで会社が行ってくれていた手続きがすべて自己責任となるため、転職活動と並行して対応しなければなりません。
健康保険は「国民健康保険への加入」または「任意継続被保険者制度の利用」を選ぶ必要があり、14日以内の申請が原則です。
そして厚生年金から国民年金への切り替え、ハローワークでの離職票提出による失業保険の申請なども忘れてはなりません。
さらに住民税は退職後に一括請求されるケースもあります。
退職後の数ヶ月は想定以上の出費が重なることもあるでしょう。
これらの支払いが滞ると信用にも関わるため、必要な手続きと納付スケジュールをあらかじめ確認しておくことが大切です。
経済的・生活的な不安を最小限に抑えるためにも、退職後はまず社会保険・税金の整理を最優先に進めていきましょう。
在職中に転職活動をするメリット
退職してから転職活動を進めるのに不安を感じる場合は、以下に挙げる在職中に転職するメリットを参考にしましょう。
ここで挙げるメリットは第二新卒はもちろん、在職しながら転職することに共通する内容とも言えるので、今後のキャリア形成における参考にしてください。
- 経済的不安の解消
- 希望条件を整理して転職が目指せる
- 職歴の空白期間防止
- 転職活動自体の見送り
経済的不安の解消
「転職先を確保してからの退職」には、経済的な心配が少ないという大きな利点があります。
これにより、転職活動を慌てることなく計画的に進めることができるでしょう。
自分に最適な職をじっくりと探求したい方や、貯蓄に対する不安を抱える方にとって、この方法は特に適していると言えます。
新卒採用で入社して早期で退職した第二新卒の多くは働いた期間そのものが短く、貯蓄も十分でないことも多いでしょう。
そのため、やはり経済的な困窮を避けるためにも、在職しながらの転職活動がおすすめな場合が大半です。
希望条件を整理して転職が目指せる
冷静に希望条件を整理した上で転職先を選べるという点は、在職中の転職活動のメリットでしょう。
収入や生活が安定している状態で活動でき「早く決めなければ」という焦りに駆られることが少なくなります。
自分にとって本当に必要な条件や譲れないポイントを丁寧に見極めることが可能です。
また現職での不満や改善したい点が明確なうちに転職先を探せます。
給与・労働時間・職場環境・人間関係など、より具体的な希望を転職軸として設定しやすくなるでしょう。
自分の希望を整理することで、応募先とのミスマッチも減り、結果的に満足度の高い転職につながりやすくなります。
無職の状態だと、どうしても「とりあえず内定が欲しい」という気持ちが強くなり、妥協や後悔の原因になりがちです。
在職中という安定した環境を活かし、自分自身としっかり向き合いながら転職活動をするようにしましょう。
職歴の空白期間防止
転職過程において、職歴中の空白期間は、採用を検討する企業から特に注目されることがあります。
「この期間中に何をしていたのか」という疑問は、面接の際によく問われる質問の一つです。
転職活動の平均期間がおおむね2〜3ヶ月であることを考慮すると、それを超える離職期間は、転職活動において不利な要素となる可能性があります。
長期のブランクがあると、ビジネスに対する感覚の鈍化や、スキル及び知識が最新のものから遅れているのではないかという懸念が生じがちです。
転職活動自体の見送り
在職中に転職活動を行うことのメリットの一つは、もし転職活動が思うように進まなかった場合でも、現在の仕事を継続することが可能であるという安心感です。
転職に伴う潜在的なリスク、例えば勤務地の変更や給与の減少などが心配な場合は、転職計画を見直すことも一つの選択肢です。
また、転職活動をしている過程で、現在の職場の価値や魅力に改めて気づくこともあるかもしれません。
しかし、面接の予定が入っている場合や内定を受けた場合には、速やかに相手方に連絡を取り、誠意を持って対応することが重要です。
在職中に転職活動をするデメリット4選
在職中に転職活動を進めることが、かえってデメリットになる場合もあります。
ここでは、今後第二新卒になる人材が在職中に転職活動を進める、以下4つのデメリットについて解説します。
- 準備時間の確保が困難
- 早期入社に対応できない
- 転職活動に追われることによる疲労
- 転職のスムーズさにおける不安
準備時間の確保が困難
転職活動においては、職務経歴書の作成や企業研究といった事前の準備が極めて重要です。
しかしながら、現職を続けながら転職活動を進める場合、準備に十分な時間を確保することが難しいという問題がしばしば起こります。
このような状況では、求人への応募が遅れがちになる、あるいは十分な準備をせずに面接を受ける必要があるといった不利な点も存在します。
早期入社に対応できない
「早期入社の要望に応えづらい」という点は、デメリットと言えるでしょう。
企業によっては「すぐにでも人材が欲しい」「内定後1か月以内に来てほしい」といった希望を持つケースもあります。
在職中で引き継ぎや退職手続きに時間がかかる人材は、採用のシーンにおいて敬遠される可能性があるでしょう。
特に人気の高い企業や採用スピードの早い業界では、選考段階で入社可能時期がネックになり、内定を逃すリスクもあります。
現職の就業規則で退職までに1~2か月の猶予を求められる場合、内定後にスムーズな転職スケジュールを立てにくい点も不利になりがちです。
そのため在職中に転職活動をする際は、事前に現職の退職時期を見越しておき、転職先企業にも正確な入社可能日を伝えましょう。
早期入社が難しいことをカバーするためには、スキルや人柄で納得してもらえるような準備も欠かせません。
転職活動に追われることによる疲労
在職中に転職活動を行う際は、日常生活のルーティーンに加えて、応募書類の作成や面接などの転職に関する活動が加わることになります。
多くの転職面接が平日に実施されるため、現在の職務との時間調整が課題となることが少なくありません。
時間管理をしつつ転職活動を進める中で、転職への努力が精神的な疲労を引き起こし、結果として活動を一時停止してしまう場合も多いでしょう。
転職のスムーズさにおける不安
転職先企業から内定を獲得した後も、現職での退職交渉が難航し、その過程で引き止められるなどの問題に直面することがあります。
通常、企業は内定後1〜3ヶ月以内の入社を望んでいますが、入社までの期間が4ヶ月以上に延びる場合、内定が取消されるリスクがあります。
特に、即戦力を求める急募の職種では、早期に入社可能な応募者が選ばれる傾向にあるため、注意が必要です。
在職中に転職活動をする際の注意点
在職中に転職活動をする際は、以下のことについて注意をしておきましょう。
- 現職に迷惑をかけないように振る舞う
- 情報の取り扱いを慎重に行う
- 退職交渉の段取りを考えておく
現職に迷惑をかけないように振る舞う
在職中に転職活動する場合、現職に迷惑をかけないように振る舞うことが非常に大切です。
雇用契約が継続している以上、与えられた業務に最後まで責任を持って取り組む姿勢が求められます。
転職活動が忙しいからといって、業務の質が落ちたり、遅刻や早退が増えたりすれば、同僚や上司の信頼を損ねることになりかねません。
無断で面接のために休暇を取ることも避けるべきです。
可能であれば有給休暇を活用し、計画的にスケジュールを調整しましょう。
退職を考えているからこそ、最後まで誠実な態度で職務を全うすることで、円満な退職につながります。
そして今後のキャリアにも悪影響を及ぼしにくくなるでしょう。
情報の取り扱いを慎重に行う
在職中に転職活動を行う場合、最も注意すべき点のひとつが「情報管理の徹底」です。
転職活動中であることが社内に知られると、同僚や上司との関係が気まずくなったり、職場での立場が不安定になったりするリスクがあります。
就業中に転職活動をしていることは法律上問題ありません。
しかし会社によっては評価に影響する可能性もあるため、情報は慎重に扱いましょう。
社内のパソコンやメールアドレス、電話回線などを使って転職活動をするのは厳禁です。
勤務中の私的利用は就業規則違反と見なされるおそれがあるため、応募ややり取りは必ず私用の端末やメールアドレスを使いましょう。
連絡も休憩時間や業務終了後にするのが基本です。
転職エージェントや応募先企業には「現職に知られていないこと」を事前に伝えておくと、配慮した連絡方法を選んでもらえる可能性があります。
自分の立場を守るため、情報の取り扱いには細心の注意を払いましょう。
退職交渉の段取りを考えておく
在職中に転職活動を進める上で、内定を得た後の「退職交渉」は避けて通れない重要なステップです。
スムーズに退職できるよう事前に段取りを考えておくことで、トラブルや引き留めを最小限に抑えられます。
まず確認しておきたいのが、現職の就業規則です。
多くの企業では「退職の申し出は1か月前までに」といったルールが定められています。
守らなければ円満退職が難しくなるでしょう。
業務の引き継ぎにかかる期間や繁忙期なども加味して、いつ申し出るのが最適かを逆算しておくと安心です。
さらに直属の上司への伝え方も重要です。
感情的にならず、これまでの感謝を伝えて、前向きなキャリアの意志として退職理由を説明すると、納得されやすくなります。
引き留めに遭った場合の対応も想定しておくと焦らずに済みます。
円満退職は次のキャリアにも好影響を与える要素です。
内定を得た段階で退職交渉の流れをシミュレーションしておきましょう。
在直中の転職活動を成功させるコツ
ここでは、第二新卒者が転職を成功させるうえで覚えておきたい、以下のコツについて解説します。
- 応募総数を増やす
- ポジティブな転職理由を考える
- 条件を設定する
- スケジュールを策定する
- 経験・スキルの棚卸しをする
- ビジョンを明確にする
- 転職期間の長期化に向けた対策をする
- 求められる人材を把握する
- オンライン対応している企業に応募する
- 第二新卒歓迎の求人を探す
- 転職エージェントを利用する
本項目にて紹介している「転職を成功させるコツ」は、第二新卒はもちろんその後の再就職にも役立つ内容となるため、ぜひ参考のうえ実践しましょう。
応募総数を増やす
在職中に転職活動を成功させるためには、限られた時間の中で効率よく選考を進める工夫が必要です。
一つが「応募総数を意識して増やす」ことです。
選択肢が増えることで、内定獲得のチャンスが広がるだけでなく、自分に本当に合った企業を見つけやすくなります。
在職中は、業務の合間を縫って活動するため、1社ごとの選考に時間をかけすぎてしまうと、他の可能性を逃すことにもなりかねません。
最初から応募先を絞りすぎず、ある程度幅を持たせた企業選びを意識すると良いでしょう。
応募数を増やす際は、スカウト型の転職サービスや転職エージェントの活用も有効です。
自分から探す手間を軽減しながら、企業側からのオファーを受けることで効率的に母集団を広げられます。
応募の段階では広く打つことを意識し、選考が進む中で本命を見極めていく姿勢が、在職中の転職活動では特に重要です。
ポジティブな転職理由を考える
転職活動を進める中で、書類の選考や面接が行われるようになります。
特に第二新卒の場合、面接の際に退職理由や転職の動機に関する質問がされることが一般的です。
多くの場合、前職に対する不満や不一致が転職の理由となっていることは面接官も予想しています。
ただし、その理由を直接的に述べることは、面接において好印象を与えることはありません。
不満を列挙することで「この人は入社後にも満足しない事態が発生したら直ちに退職するのではないか?」と懸念される可能性があります。
そのため、退職理由を説明する際には、正直さと適切な表現をバランス良く組み合わせることが大切です。
ネガティブな点も、成長の機会や新たな目標に向かう動機としてポジティブに捉え直して伝えることが大切です。
一般的にネガティブとされる理由を、ポジティブに言い換えた例を以下にまとめているので参考にしてください。
前職では、個々の競争意識が非常に強く、結果としてチームの結束力や相互コミュニケーションに課題が生じ、業務の進行にも影響が出ることがありました。
この経験を経て、チーム全員が協力しあい、相互に刺激を受け合えるような環境で働きたいと強く感じるようになり、その理想を追求するために転職を考えるに至りました。
前職では、年功序列に基づく給与体系が採用されていたため、実績を上げても給与への反映が見込みにくい状況でした。
このような経験を踏まえ、自分の努力や成果が直接報酬に結びつく実力主義を取り入れている企業への転職を望むようになりました。
さらに、自己の専門性を深めるために資格取得を目指し、その過程でサポートを提供してくれる職場環境にも魅力を感じています。
新規開拓営業を通じて多くの新しいお客様との出会いや対話を楽しむことができ、これは非常に刺激的な経験でした。
しかし、私はより一層、お客様個々と深く関わり、じっくりと対話することに価値を見出しています。
そのような関係性を築き、お客様のニーズに対して細やかに対応できる貴社の営業職に魅力を感じ、応募させていただきました。
条件を設定する
転職活動において、同じ過ちを繰り返さないためにも、企業選定の際には個人的な基準・条件を設けることが重要です。
無計画に仕事探しを始めると、求人情報の多さに圧倒されたり、内定を得たい一心で焦りを感じたりすることがあり、結果として現在の職場と似た環境の企業に転職してしまうリスクがあります。
このような状況を避けるため、自分にとって「妥協できない条件」と「柔軟に対応できる条件」を明確に分けて、企業選びを行うことが大切です。
例えば、現職での不満点や転職先で改善を望む点を書き出すことから始めると良いでしょう。
考えを整理し、自分に適した企業の選定基準を具体化することができるためです。
求める条件は人それぞれ異なり、それに応えられる職場も異なります。
個人の基準に基づいて探すことで、適切な企業が自然と絞り込まれていくはずです。
ただし、業種や職種に関しては、最初から狭い範囲に限定せずに探すことを推奨します。
予想外の業界に自分の希望を完全に満たす企業が存在するかもしれません。
そのため、自分自身で設定した基準を保ちつつ、広い視野を持って転職活動を進めることが、可能性を広げる鍵となります。
スケジュールを策定する
転職活動を効果的に進めるためには、活動の開始から目標達成までのスケジュールを明確に設定することが大切です。
スケジュール設定のプロセスでは、新たな職場での初日を目標として掲げ、そこから退職予定日、内定の獲得、応募プロセス、そして企業選定の各段階を時間軸に沿って逆算して計画します。
自分自身で明確な転職スケジュールを設定することにより、転職活動を段階的に、かつ効率的に進めることが可能になるでしょう。
一般的に、転職活動全体での期間は約3ヶ月程度とされています。
この期間設定には、退職に際しての業務引継ぎや有給休暇の消化など、個々の状況を踏まえた調整が必要になります。
それぞれの状況に応じた計画を立てることが、転職活動をスムーズに進めるための重要なポイントです。
経験・スキルの棚卸しをする
第二新卒者に対しては、新鮮さや成長の可能性だけでなく、これまでの社会人としての経験や習得したスキルが評価の対象となります。
以前勤めていた企業で培ったスキルや達成した成果を面接時に効果的にアピールすることが、好印象を与える可能性を高めるでしょう。
自分がこれまでに経験してきたこと、その経験から身に付けた特技やスキル、さらには取得した資格や知識を一覧化し、これらが転職先でどのように役立つかを具体的に計画することが肝心です。
ビジョンを明確にする
転職を成功させるためには、無計画に活動を開始するのではなく、目標を持って取り組むことが重要になります。
単に現状からの脱却を目指すのではなく「理想とするキャリアパスをどのように実現するか」を転職の主眼に置き、必要な行動計画を練るべきです。
始めに、自己の将来設計を明確にすることからスタートしましょう。
5年後や10年後にどのような職業人として自分を見ていたいのか、どの業界で、どのような業務を担いたいのかを詳細に思い描くことが肝心です。
また、面接時に自分のキャリアビジョンを語ることは、面接官に自社でどのように成長し、貢献できるかという具体的なイメージを持たせるための、重要なポイントとなり得ます。
曖昧なキャリアプランのまま転職活動を進めることは、絶対に避けるべきです。
もし転職が成功しても、将来的に再び職場に対する不満や悩みが生じたとき、辞職を考える可能性が高まってしまうためです。
持続可能な職業への意欲を維持するためにも、自身のキャリアに対する長期的なビジョンをしっかりと構築しましょう。
転職期間の長期化に向けた対策をする
退職後に転職活動を行う場合、次の職が決まるまでの期間が長期化することを考慮し、生活費を事前に用意しておくことが必要です。
最低でも3ヶ月分の生活資金を確保し、できればそれ以上の余裕を持った資金計画を立てることをおすすめします。
特に第二新卒の場合、経済的な蓄えが不十分な方が多いかもしれません。
退職してすぐに転職活動を開始したとしても、すぐに内定が得られない場合、生活が困難になるリスクがあります。
経済的な理由で転職活動を早期に終了させたり、諦めたりすることは、目的を達成できない結果となりかねません。
転職活動は計画通りに進むとは限らず、予期せぬ障害により活動期間が延びる可能性が常にあります。
もし貯蓄の準備が難しい場合は、現職を継続しながら転職活動を行うことが、より現実的な選択肢となります。
求められる人材を把握する
第二新卒における転職活動に際しても、新卒時と同じく業界や企業の綿密な研究は不可欠です。
業界全般の動向や、特定の企業がどのような属性を持つ人材を望んでいるのかを理解することにより、入社してからの期待と現実の齟齬を最小限に抑えることが可能になります。
企業がどのような人材を欲しているかは、転職先として希望する企業の求人情報や公式ウェブサイトや経営層が執筆するブログを読むなどして、情報収集を行うことで把握できるでしょう。
オンライン対応している企業に応募する
在職中に転職活動をするときは、オンライン選考に対応している企業を優先的に応募することが、効率良く活動を進めるためのポイントです。
最近では、一次面接や企業説明会をオンラインで実施する企業が増えています。
業務の合間や休日を活用してスムーズに選考を受けられる環境が整ってきていると言えるでしょう。
特に現職の就業時間と選考スケジュールが重なりやすい在職者にとっては、通勤時間や移動の手間が省けるオンライン選考は大きなメリットです。
交通費や有給休暇を使わずに複数社の面接を受けられるため、心理的・物理的な負担を軽減できます。
さらにオンライン対応企業は、柔軟な働き方やリモートワークを取り入れているのが一般的です。
ワークライフバランスを重視した転職を希望する方にも、マッチしやすいと言えます。
在職中に転職成功を目指すなら、企業の選考フローや面接方法にも注目しましょう。
オンライン対応の可否を事前に確認することが、戦略的な応募先選定につながります。
第二新卒歓迎の求人を探す
在職中に転職活動を成功させるためには、「第二新卒歓迎」や「未経験OK」と明記された求人に絞って応募することが非常に効果的です。
第二新卒はいわゆる若手層であり、企業側もポテンシャル採用として積極的に受け入れる姿勢を見せています。
第二新卒歓迎の求人では、社会人経験が浅くても「基本的なビジネスマナーが身についている」「若手ならではの柔軟性がある」といった点が評価されやすい傾向にあります。
経験よりも人柄や成長意欲が重視されることが多々あるでしょう。
したがって、現職での経験に自信がない人でも、前向きな姿勢をアピールすることで十分にチャンスを掴めます。
また第二新卒歓迎の企業は研修制度が整っていることも多く、入社後のキャッチアップ支援も受けやすい点が魅力です。
求人サイトやエージェントを活用して、「第二新卒」や「若手歓迎」のキーワードで検索すれば、効率良くマッチする求人を見つけられます。
転職エージェントを利用する
転職活動においては、自身だけで進める以外にも、転職支援サービスを活用することが一つの選択肢になり得ます。
現在、求人情報を集約して提供する転職サイトをはじめ、多様な転職支援サービスが存在します。
特に、転職に関する悩みやネックを解消してくれる、転職エージェントを利用するのもおすすめです。
転職エージェントによるサポート内容やメリットは、以下を参考にしてください。
- 専門的なアドバイス:転職エージェントは市場動向や業界の知識が豊富で、個人の経験やスキルに基づいた具体的なキャリアアドバイスを提供してくれます。
- 未公開求人の紹介:多くの魅力的な求人は一般には公開されず、エージェント経由でのみ応募が可能です。
- 履歴書・職務経歴書のブラッシュアップ:転職エージェントは履歴書や職務経歴書の添削を通じて、応募書類をより魅力的にするサポートを行います。
- 面接対策:企業の面接官が何を求めているのかについての洞察を提供し、面接対策のアドバイスを行います。
- 交渉サポート: 給与や勤務条件などの交渉を代行し、自身にとって最適な条件を引き出してくれます。
- 時間の節約:転職活動は時間がかかるプロセスですが、エージェントを利用することで効率的に求人検索や応募プロセスを進めることができます。
- アフターサポート:入社後もフォローアップを行い、新しい職場での適応をサポートしてくれます。
転職をサポートしてくれる各種サービスでは、豊富な求人情報の閲覧だけでなく、履歴書の添削サポートや職務経歴書作成のための便利なツールなど、転職活動をサポートする多岐にわたる機能が提供されています。
上手く活用することで、転職成功への道をよりスムーズに進めることが可能です。
まとめ
第二新卒として転職活動を進めるうえでは、現在勤めている会社を辞めてからか、在職しながらかどちらにするかは非常に重要です。
退職後・在職中どちらにもメリット・デメリットがあるため、自身がどちらに適しているか客観視したうえで転職活動を進める必要があります。
また今回は、第二新卒が転職活動を成功させるためのコツもまとめました。
第二新卒となって新たな道に進むことを検討している場合は、ぜひ本記事で紹介した内容を参考に、転職活動を成功させてください。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!