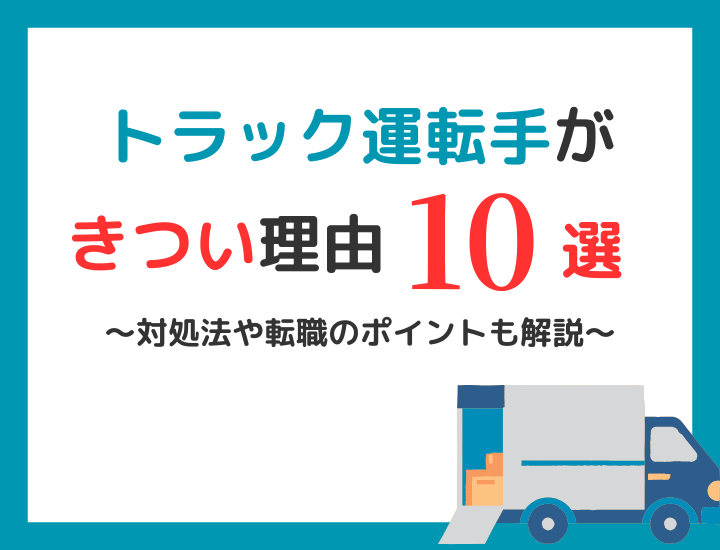
トラックの運転手が「やめとけ」といわれる理由10選|対処法や転職のポイント
はじめに
「トラックの運転手はきつい?」
「やめとけって聞くけど本当?」
そんな疑問を抱えていませんか?
トラックの運転手は物流を支える重要な仕事でありながら、過酷な勤務環境や不安定な収入などがネックになり、転職を考える人も少なくありません。
本記事では、トラックドライバーが「やめとけ」と言われる理由を10項目に分けて解説しつつ、実際の対処法や転職時のポイントもあわせて紹介します。
これから運転手を目指す人や、働き続けるか悩んでいる方が、正しい判断ができるようサポートする内容となっています。
トラックの運転手が「やめとけ」といわれる10の理由
トラック運転手の仕事に対して「やめとけ」と言われる背景には、過酷な労働環境や生活面での支障が関係しています。
ここでは、代表的な10の理由について詳しく見ていきましょう。
- 拘束時間が長くなりがち
- 祝日・連休は休みにくい
- 家庭の時間が取りにくい
- 生活リズムが崩れやすい
- 給料が低い
- 肉体的な負担が大きい
- 事故に遭うリスクがある
- マナーが悪い印象を持たれる
- 学歴が低いと思われる
- 清潔感がない
1.拘束時間が長くなりがち
トラック運転手は、一般的な職種に比べて1日の拘束時間が長くなる傾向があります。
たとえば荷待ちや渋滞、天候による遅延など、運転以外の時間も労働時間に含まれることが少なくありません。
国土交通省の調査によると、荷待ち時間を含む1運行の平均拘束時間は12時間を超えており、繁忙期にはそれ以上になることもあります。
また、労働基準法上の上限である16時間近くまで拘束されるケースも存在します。
- 荷待ち・荷下ろしに時間がかかる
- 道路状況による遅延(渋滞・事故・天候など)
- 宿泊を伴う長距離運行が多い
こうした事情から、拘束時間の長さが「やめとけ」と言われる原因の一つになっています。
2024年以降は時間外労働の規制が導入される予定ですが、現場の実態は依然として厳しいといえるでしょう。
2.祝日・連休は休みにくい
トラック運転手の業務は、祝日や大型連休も通常通り稼働していることが多く、他の職種と比べて休みを取りにくい傾向にあります。
特に物流業界は、消費者や企業の需要に合わせて稼働するため、連休中こそ配送ニーズが集中する場面も少なくありません。
たとえば年末年始やゴールデンウィーク、お盆など、一般的な企業が休みに入る時期は、逆に運送業では繁忙期となるケースが多いでしょう。
結果、家族との予定が合わせづらく、冠婚葬祭や旅行なども諦めざるを得ないことがあります。
平日休みが多いことから、人とスケジュールを合わせにくく、孤独を感じる人もいます。
こうした勤務形態の不自由さが「やめとけ」と言われる一因になっています。
3.家庭の時間が取りにくい
トラック運転手の働き方では、長時間の拘束や不規則な出退勤の影響で、家族との時間がなかなか取れないという声が多く聞かれます。
特に中長距離を担当するドライバーの場合、出発から帰宅まで1泊以上かかることもあり、家庭内の役割を果たしにくくなるケースも珍しくありません。
また、休日が平日中心で家族と予定が合いづらく、家族一緒に過ごす時間が短くなりがちです。
子どもの成長を見守る時間や、パートナーとのコミュニケーションが不足すると、家庭内の関係性にも影響が及ぶおそれがあります。
プライベートを犠牲にしやすい働き方が、特に家族を持つ人にとって「きつい」と感じる要因になっています。
家庭重視のライフスタイルを望む人には、ミスマッチといえるかもしれません。
4.生活リズムが崩れやすい
トラック運転手は勤務時間が日勤・夜勤・泊まり勤務など多様で、一定の生活リズムを保つことが難しい職種です。
早朝出発や深夜帯の走行が求められることも多く、体内時計が不安定になりがちです。
さらに、休憩時間が不規則だったり、仮眠で済ませる日も多いため、睡眠の質が低下するという問題もあります。
慢性的な寝不足や体調不良を抱えるドライバーも多く、生活習慣病のリスクも無視できません。
不規則な勤務が日常化することで心身への負担が蓄積されやすく「続けられない」と感じる要因にもなっています。
5.給料が低い
トラック運転手は「稼げる仕事」と言われる一方で、「割に合わない」と感じている人も少なくありません。
業種や企業、運ぶ荷物の種類によって年収に大きな差があるため、思ったより手取りが少ないと感じる人が出てきます。
特に小型トラックや地場配送では、労働時間に対して収入が低いケースが目立ちます。
また、歩合制を導入している企業では、配送件数や運行距離に報酬が連動しているため、効率的に回らなければ収入が伸びにくいという側面もあります。
- 長時間働いても残業代が満額出ない
- 荷待ち時間などが無給扱いになる場合も
- 歩合給制度で成果が安定しない
- 法規制により時間外労働が制限されつつある
労働に対する報酬のバランスに疑問を感じ、転職を検討するきっかけになることが多く、「やめとけ」と言われる根拠にもつながっています。
6.肉体的な負担が大きい
トラック運転手の仕事は、単なる「運転だけ」ではありません。
積み込みや荷下ろしといった力仕事、長時間の運転姿勢、狭い車内での生活など、肉体的にハードな要素が多く含まれています。
特に中高年のドライバーにとっては、腰痛や肩こり、関節の不調などの持病に悩まされることも珍しくありません。
さらに、悪天候や夜間の運行などによって体調管理が難しくなる場面もあります。
継続的な身体への負荷が、将来的な健康不安や離職理由につながりやすく、「長く続けるのは難しい」と言われる背景になっています。
7.事故に遭うリスクがある
トラック運転手は、常に交通事故のリスクと隣り合わせの仕事です。
長時間の運転により集中力が低下しやすく、疲労や眠気から判断ミスを起こすこともあります。
また、大型車両は視界が限られ、ブレーキの制動距離も長いため、一般車両より事故のダメージが大きくなりやすいのが現実です。
仮に自分に過失がなくとも、もらい事故に巻き込まれる可能性も否定できません。
事故の加害者・被害者どちらになっても精神的なダメージは大きく、それを避けたいという理由から他業種への転職を考える人も多くいます。
8.マナーが悪い印象を持たれる
一部のドライバーによる乱暴な運転や路上駐車の影響で、「トラック運転手=マナーが悪い」という印象を抱かれることがあります。
もちろんすべての運転手が該当するわけではありませんが、業界全体に対する偏見として根強く残っているのが現状です。
あおり運転や強引な割り込みなどの映像が拡散されやすい現代では、印象操作が一層加速する傾向も見られます。
- 信号直前での急な車線変更
- コンビニや道の駅での長時間駐車
- 交通ルールを無視した危険運転
- クラクションの多用や乱暴な言葉づかい
実際には安全運転を心がけるドライバーも多くいますが、目立つ行動だけが注目されやすいため、社会的な印象とのギャップにストレスを感じる方も少なくありません。
9.学歴が低いと思われる
もちろんすべての運転手が該当するわけではありませんが、業界全体に対する偏見として根強く残っているのが現状です。
トラック運転手に対するネガティブな偏見の一つに、「学歴が低い人がなる仕事」といった見方があります。
実際には高卒・大卒問わず、さまざまな経歴を持つ人が活躍しており、専門性や責任感が求められる職種であるにもかかわらず、社会的な評価が追いついていない面があります。
中には「他に選択肢がないからこの仕事をしている」と誤解されることもあり、やりがいを持って働いている人にとっては心外な印象でしょう。
本来は技術職に近い立ち位置であり、専門知識と安全意識が必要な職種であることを、もっと正当に評価される必要があります。
10.清潔感がない
トラック運転手の外見に対して「清潔感がない」というイメージを持たれることがあります。
作業着や汗をかく業務内容、長時間の運転による疲労などが見た目に影響しやすいためです。
加えて、車内での食事・仮眠・着替えなども日常的であるため、常に整った身だしなみを維持するのが難しいという実情もあります。
見た目だけで判断されることにストレスを感じる人も多くいます。
外的要因によって、不本意ながら「不潔」といった印象を持たれてしまう場面があるのも事実です。
ただし、実際には身だしなみに気を遣う運転手も増えており、イメージとのギャップを感じる人も少なくありません。
トラック運転手の仕事に関する基本
トラックドライバーの仕事に就く前には、以下の要素をしっかり把握しておくことが大切です。
- 業務内容
- 必要な免許・資格
- 年収の傾向
- 大型・中型の違い
業務内容
トラック運転手の仕事は、荷物の積み込み・運搬・荷下ろしまでを一貫して行う輸送業務です。
企業から企業へ配送するBtoB配送や、個人宅へのBtoC配送、ルート配送やスポット輸送など、働く会社や業種によって内容が異なります。
また、荷物によっては冷凍・冷蔵車両や特殊車両を使うケースもあります。
運転以外にも納品書の受け渡しや検品、荷待ち対応などが含まれるため、意外と幅広い作業が求められるのです。
必要な免許・資格
運転する車両のサイズによって、必要な免許は異なります。
2トントラックまでなら準中型免許、それ以上であれば中型または大型免許が必要です。
さらに、危険物を扱う場合は「危険物取扱者」、特定の重量物を吊り上げる業務では「玉掛け技能講習」など、業務内容に応じて追加資格が求められるケースもあります。
- 準中型免許:最大積載量2〜3t程度
- 中型免許:最大積載量5〜6.5t程度
- 大型免許:最大積載量6.5t超
年収の傾向
トラック運転手の年収は、運転する車両の大きさや走行距離、勤務体系によって大きく異なります。
一般的に地場配送よりも長距離輸送のほうが収入は高めの傾向にありますが、その分拘束時間も長くなりやすいでしょう。
全体の平均年収は約400万円前後とされており、歩合制や深夜割増がつく現場ではそれ以上になるケースも見られます。
- 長距離・夜間運行の有無
- 固定給か歩合制か
- 荷物の種類と作業負担
大型・中型の違い
中型トラックと大型トラックの違いは、積載量だけでなく運転感覚や業務内容にも現れます。
中型は比較的扱いやすく、主に近距離や地域内配送で活躍します。
一方、大型トラックは高速道路を使った長距離輸送や、大量の荷物を運ぶ業務が中心です。
大型は免許取得や維持費も高くなるものの、その分給与面や需要の安定性でメリットがあります。
中型と大型の主な違い
| 項目 | 中型トラック | 大型トラック |
|---|---|---|
| 積載量 | 約2〜6.5トン | 6.5トン超 |
| 業務範囲 | 近距離配送・地域ルート | 長距離輸送・幹線物流 |
| 必要免許 | 中型免許 | 大型免許 |
| 給与傾向 | 年収350〜450万円程度 | 年収450〜600万円以上の例もあり |
トラック運転手がきつい理由と関連する実態
ドライバーという職業が過酷だと言われる背景には、構造的な問題や社会変化に起因する要素が多くあります。
ここでは「人手不足」「2024年問題」「労災件数」の3点に注目して見ていきましょう。
慢性的な人手不足
トラック業界では長年にわたり人手不足が続いており、1人あたりの負担が増している状況です。
若手の新規参入が少ない一方で、高齢化が進んでいるため、現場では常に人手が足りないとされています。
結果、配送量が増えてもドライバー数が追いつかず、1人で複数の業務をこなさなければならなくなるのです。
特に長距離輸送では交代要員が確保しにくく、拘束時間の長期化にもつながっています。
2024年問題
>2024年4月から、働き方改革関連法の適用拡大により、ドライバーの時間外労働時間に上限が設定されています。
労働環境の是正が期待される一方、収入が減少する懸念も広がっています。
これまで残業代を収入の柱にしていたドライバーにとっては、生活の見直しを迫られる可能性もあるでしょう。
また、労働時間の制限によって配送量をこなせなくなると、現場にさらなるしわ寄せが生じる恐れもあるのです。
労災の件数
トラック運転手は業務中の事故やけがのリスクが高く、労働災害の発生件数も少なくありません。
長時間運転による疲労や注意力の低下、積み下ろし時の腰痛・転倒など、さまざまな場面で負傷リスクが伴います。
厚生労働省のデータによれば、運輸業全体の労災発生率は他産業よりも高水準で推移しています。
安全対策を講じても完全にリスクをゼロにすることは難しく、日常的に緊張感を伴う職業だといえるでしょう。
トラックの運転手がきついと感じたときの対処法5選
トラック運転手の仕事がきついと感じたときは、業務の選び方や日常の工夫によって改善を目指すことも可能です。
以下では、5つの対処法を紹介します。
- 短距離・小型トラックの運転手になる
- 車内を快適にする
- リフレッシュ方法を見つける
- 体力をつける
- 転職をする
短距離・小型トラックの運転手になる
長距離輸送や大型車両に比べ、短距離・小型トラックの仕事は拘束時間が短く、肉体的・精神的負担が軽減されやすい傾向にあります。
地場配送であれば日帰りが基本となるため、家庭との両立もしやすいでしょう。
また、荷物が軽量なケースも多く、積み下ろしの負担も軽減されます。
大型から小型へシフトするだけでも働き方が大きく変わる可能性があります。
- 拘束時間が比較的安定
- 家族との時間が確保しやすい
- 体力面の負担が少なめ
車内を快適にする
長時間を過ごす運転席を快適な空間に整えることは、ストレス軽減に大きくつながります。
シートクッションや腰当て、ネックピローなどのアイテムを取り入れることで身体の疲れを和らげることが可能です。
また、空気清浄機やアロマディフューザーを設置して車内環境を整えることで、気分転換もしやすくなります。
居心地の良い空間をつくることが、継続のモチベーションにもつながるでしょう。
リフレッシュ方法を見つける
トラック運転手にとって大切なのは、業務外の時間をいかに有効に使えるかです。
好きな音楽やラジオを聴きながら運転する、休憩中に軽いストレッチを行うなど、心身のリフレッシュ法を持っておくことで疲労の蓄積を防ぎやすくなります。
また、休日には趣味や運動に取り組み、仕事とのメリハリをつけることもおすすめです。
小さな息抜きの積み重ねが、ストレスの軽減につながります。
体力をつける
体力不足から仕事がきつく感じるケースも少なくありません。
運転以外にも積み込みや荷下ろしが伴うため、基礎体力があるかどうかは仕事のしやすさに直結します。
ジムに通う必要はなく、自宅でできる軽い筋トレやストレッチを継続するだけでも十分効果があります。
体が疲れにくくなれば、仕事中の集中力や安全意識も高まり、結果的に事故リスクの回避にもつながるでしょう。
転職をする
体力面や労働環境に限界を感じた場合は、無理に続けるのではなく転職という選択肢を考えることも有効です。
以下では、トラック運転手の経験を活かせる仕事を紹介します。
トラック運転手経験者におすすめの仕事
運転経験を活かせる職種には、以下があります。
- 配送センターでの構内作業員
- フォークリフトオペレーター
- 送迎バスドライバー
比較的決まった時間で働ける業務も多く、体力や時間面の負担を減らしたい方に向いています。
また、安全運転のスキルを評価する企業もあるため、無理なく経験を活かせる転職先を探すことが可能です。
トラックの運転手にはやりがいもある
大変な面ばかりが注目されがちなトラックドライバーの仕事ですが、実際にはやりがいや魅力を感じている人も多くいます。
ここでは代表的な5つのやりがいを紹介します。
- 人間関係に悩まされない
- 全国各地に行ける
- 人々の役に立ってると実感しやすい
- 自分でスケジュールを決められる
- 年齢や学歴を気にしなくていい
人間関係に悩まされない
運転業務が中心となるため、職場の人間関係によるストレスを感じにくいのが特徴です。
会社内での雑談やチームプレーが苦手な人でも、基本的に1人で業務をこなす時間が多いため、自分のペースで働けるのが魅力です。
また、他人に気を遣いすぎることなく、淡々と業務に集中できる環境を求める人にとっては、快適な職種といえるでしょう。
人付き合いが少ない分、精神的な疲れが少ない点も利点です。
全国各地に行ける
長距離ドライバーの仕事では、日本全国さまざまな土地を訪れる機会があります。
観光とは違った視点で街を見ることができ、仕事を通じて地域の風景や特色を知る楽しみもあります。
道中で立ち寄るサービスエリアやご当地グルメとの出会いもあり、移動そのものに楽しさを見出す人も多くいます。
運転が好きな方や、新しい景色に出会うことが好きな方にとっては、大きなモチベーションにつながるでしょう。
人々の役に立ってると実感しやすい
トラック運転手は、商品や資材を運ぶことで流通を支えている重要な存在です。
- 荷物を確実に届けてスーパーの棚が充実する
- 建設現場が予定通りに動く
- 個人宅に必要な商品が届く
上記のように、自分の仕事が社会全体に貢献していると実感しやすいのが特徴です。
目立たない仕事ながら誰かの生活を裏側から支えているという実感が、やりがいにつながるという声も多くあります。
自分でスケジュールを決められる
会社によって異なりますが、運行ルートや納品時間さえ守っていれば、途中の休憩や運転ペースなどを自分で調整できることもあります。
どのタイミングで食事を取るか、どのサービスエリアで休憩を取るかなど、細かい行動を自分で決められる自由さが魅力です。
マイペースに働きたい人や、過剰な管理を嫌う人にとっては、仕事の裁量がある点は大きなメリットとなるでしょう。
年齢や学歴を気にしなくていい
トラックドライバーの仕事は、年齢や学歴よりも運転技術と責任感が重視されます。
そのため、中途採用や再スタートを希望する人にとっても門戸が広い職種といえます。
特別な学歴や高度な資格がなくても、正社員として安定した収入を得ることが可能です。
また、定年後にセカンドキャリアとして選ぶ人も多く、長く働きたい人にも向いている職業です。
トラックの運転手に向いている人の特徴5選
すべての人に向いている仕事ではないからこそ、適性があるかどうかの見極めは重要です。
ここでは、ドライバー職に向いている人の代表的な特徴を5つ紹介します。
- 長時間の運転が苦ではない
- 同じルートを回ることがストレスではない
- 体力に自信がある
- 責任感がある
- 1人で黙々と仕事をしたい
長時間の運転が苦ではない
トラック運転手は長距離移動や拘束時間が長くなる傾向にあるため、運転そのものが好きな人や、長時間の運転を苦に感じない人に向いています。
音楽やラジオを聴きながら運転時間を楽しめる人であれば、単調な移動もストレスになりにくいでしょう。
反対に、車内で長く過ごすことに強い抵抗がある人は、業務そのものが大きな負担になる可能性があります。
運転時間を苦痛と感じないことは、継続しやすさにもつながります。
同じルートを回ることがストレスではない
ルート配送や地場配送では、毎日ほぼ同じ時間帯・同じ道を走ることも少なくありません。
こうした業務内容に対して飽きやストレスを感じにくい人は、安定した働き方を実現しやすいでしょう。
同じ景色やルートに安心感を覚えるタイプの人は、仕事に慣れるスピードも早く、効率的に業務をこなせるようになります。
日々の変化を求めるより、一定のリズムで仕事を進めたい人には適した環境です。
体力に自信がある
トラック運転手は運転以外にも、荷物の積み下ろしや荷台での作業など、身体を使う場面が多くあります。
長時間座り続けること自体も体に負担をかけるため、日常的に疲労と向き合える体力が求められる仕事です。
特に中型・大型トラックを担当する場合は、大量の荷物を扱うこともあり、持久力や筋力があれば仕事が楽になります。
運動習慣がある人や、体を動かすことに抵抗のない人は、業務に適応しやすいでしょう。
責任感がある
トラック運転手は、荷物を安全かつ確実に届けるという責任ある役割を担っています。
交通ルールを守りながら時間通りに配送を行い、万が一のトラブルにも冷静に対応できる判断力と誠実さが必要です。
荷物の内容によっては数百万円以上の価値があることもあるため、1つひとつの作業に丁寧さと慎重さが求められます。
自分の仕事が人や企業に影響するという意識を持てる人ほど、信頼される存在になれるでしょう。
1人で黙々と仕事をしたい
日々の業務がほぼ1人で完結するため、集団作業や会話が多い環境が苦手な人にとっては、非常に働きやすい職種です。
もちろん最低限の報連相は必要ですが、社内の人間関係やチーム内調整に煩わされることは少なく、自分のペースで動ける自由さがあります。
自律的に行動できる人や、1人で物事に集中したい人にとっては、他の職種にはない快適さを感じられるでしょう。
トラック運転手に向いていない人の共通点
一方で、以下に当てはまる人はトラックの運転手に向いていないと判断できるでしょう。
| 特徴 | 向いていない理由 | |
|---|---|---|
| 長時間同じ姿勢でいるのが苦手 | 運転中は長時間座ったままになるため、身体的・精神的に苦痛を感じやすい | |
| 単調な作業に飽きやすい | 同じルートを繰り返し走ることが多く、日々の変化を求める人には退屈に感じやすい | |
| 人と話すことでモチベーションが上がるタイプ | 業務の大半が1人で完結するため、会話の機会が少なく孤独を感じやすくなる | |
| 規則的な生活を重視したい | 早朝出発や深夜帰宅など生活リズムが不規則になりやすい | |
| 力仕事が苦手 | 荷物の積み下ろしや車両点検など、体力を使う場面が日常的に発生する | |
| 柔軟なスケジュール変更に対応できない | 渋滞・荷待ち・天候などの影響で予定通りに動けないことが多く、柔軟な対応力が求められる |
トラック運転手の将来性とは
トラック運転手の将来性は、一概に悲観できるものではありません。
確かに、2024年以降の時間外労働規制や高齢化による人手不足など、業界全体が変革を迫られている状況にはあります。
しかし一方で、物流はあらゆる産業の土台を支えており、ドライバーの需要が急激に減ることは考えにくいでしょう。
特に再配達削減や物流の効率化が求められる中で、地域密着型の小口配送や短距離輸送のニーズは今後も安定して続くと見込まれます。
また、自動運転技術の普及が進むとしても、まだ長距離・長時間運転の完全無人化には時間がかかるため、当面は人の手による運行が欠かせません。
働き方は今後変化するものの、現場での対応力や安全運転への意識がある人材には、引き続き求められる価値が残り続けるでしょう。
これからトラック運転手を目指す際の転職ポイント
トラックドライバーへの転職を考える際は、やみくもに応募するのではなく、事前の情報収集や準備が重要です。
トラック運転手を目指す際に押さえておきたい、以下7つのポイントについて見ていきましょう。
- 転職の理由をはっきりさせておく
- トラック運転手の実態を把握しておく
- 適性・条件を満たしているか確認する
- 応募先の信頼性や待遇をリサーチする
- 面接・書類の準備を怠らない
- 希望条件を整理する
- 転職エージェントを利用する
転職の理由をはっきりさせておく
まず、自分がなぜ運転手という仕事に興味を持ったのか、またなぜ他職種から転向したいのかを明確にすることが大切です。
転職の理由が曖昧なままでは、応募企業にも説得力のある志望動機を伝えることが難しくなります。
転職理由を言語化することで、自分に合った職場を見つけやすくなり、長期的な定着にもつながります。
将来像まで見据えたビジョンを描いておくことが、満足度の高い転職への第一歩です。
トラック運転手の実態を把握しておく
求人情報だけを見て判断するのではなく、実際の仕事内容や勤務環境を事前に理解しておくことが重要です。
- 1日の拘束時間
- 積み下ろし作業の有無
- 休日の取りやすさ
上記のように、具体的な実態を把握することで、自分に合うかどうかを冷静に判断できます。
SNSや口コミサイト、職業体験談を通じてリアルな声を集めておくと、ミスマッチのリスクを減らせます。
適性・条件を満たしているか確認する
トラック運転手として働くためには、必要な免許を持っているか、もしくは取得の意思があるかをまず確認しましょう。
また、長時間の運転に耐えられる体力や、事故を防ぐための集中力・判断力も求められます。
自分がトラック運転手の適性・条件にマッチしているかを見直してみることで、転職後のギャップに戸惑うリスクを軽減できます。
応募先の信頼性や待遇をリサーチする
企業ごとに労働環境や福利厚生の内容は大きく異なるため、応募前には必ず企業情報を調べることが欠かせません。
たとえば、労働時間の実態や有休の取得状況、社会保険の有無などを確認しておくと安心です。
また、離職率や社員の口コミも重要な判断材料となります。
目先の給与額だけで決めず、長く働ける環境かどうかを見極める視点が必要です。
面接・書類の準備を怠らない
転職活動では、面接対策と応募書類の完成度が内定の成否を左右します。
志望動機や自己PRは、トラック運転手という職種にマッチした内容に仕上げることが求められます。
過去の職務経験や人柄が伝わるエピソードを交えると、より好印象を与えることが可能です。
履歴書・職務経歴書も形式にとらわれすぎず、読みやすさや誤字脱字に注意しながら丁寧に仕上げましょう。
希望条件を整理する
転職先に求める条件が不明確なままだと、後悔する選択につながる恐れがあります。
自分にとって譲れない条件を事前に整理しておくことが大切です。
優先順位をつけることで、応募先を絞り込みやすくなり、納得感のある転職が実現しやすくなります。
- 月収・年収の希望額
- 土日休みや日勤のみなど勤務体系
- 通勤距離・社宅の有無
転職エージェントを利用する
初めてトラック運転手に挑戦する人にとって、転職エージェントの活用は心強い選択肢です。
業界事情に詳しい担当者が希望条件や適性に応じた求人を提案してくれるため、自力で探すより効率的です。
また、面接日程の調整や書類添削のサポートも受けられるため、時間のない人にも適しています。
無料で利用できるサービスが多いため、気軽に相談してみるとよいでしょう。
まとめ
トラック運転手の仕事は体力や時間の面で厳しさがある一方で、人間関係のストレスが少なく、自分のペースで働けるといった魅力も存在します。
「やめとけ」と言われる理由を冷静に把握し、適切な対策を講じることで、無理なく続けられる道も見えてくるはずです。
もし続けることが難しいと感じたら転職という選択肢も視野に入れて、自分に合った環境で新たな一歩を踏み出すのも前向きな判断といえるでしょう。
SHARE この記事を友達におしえる!


