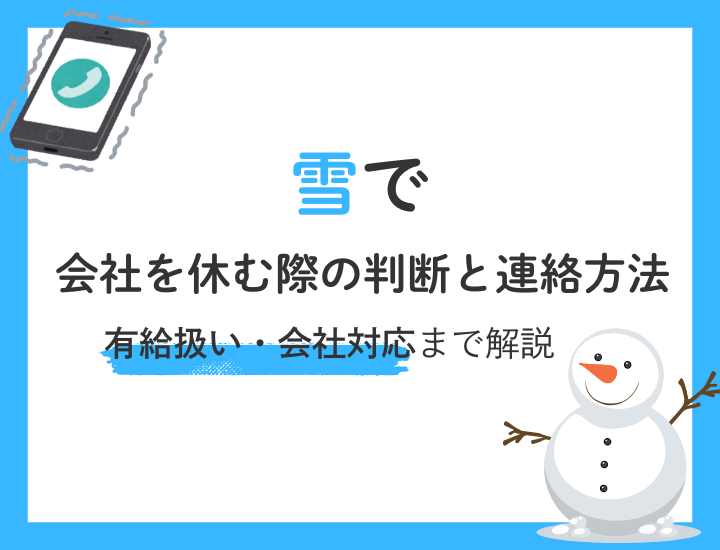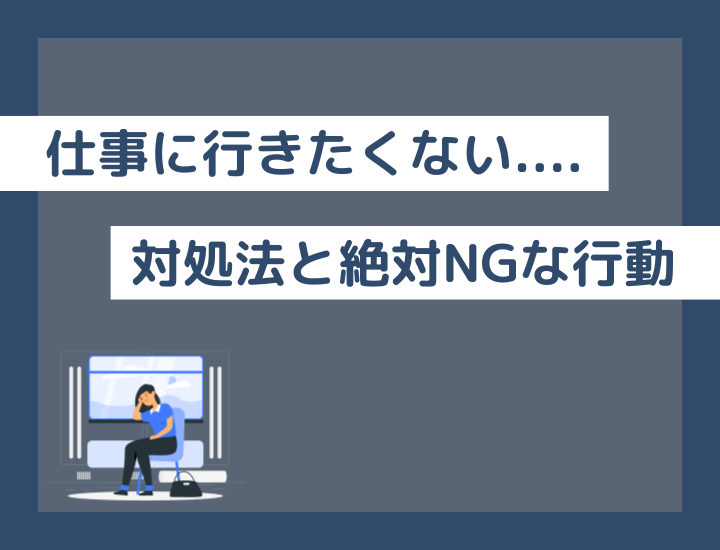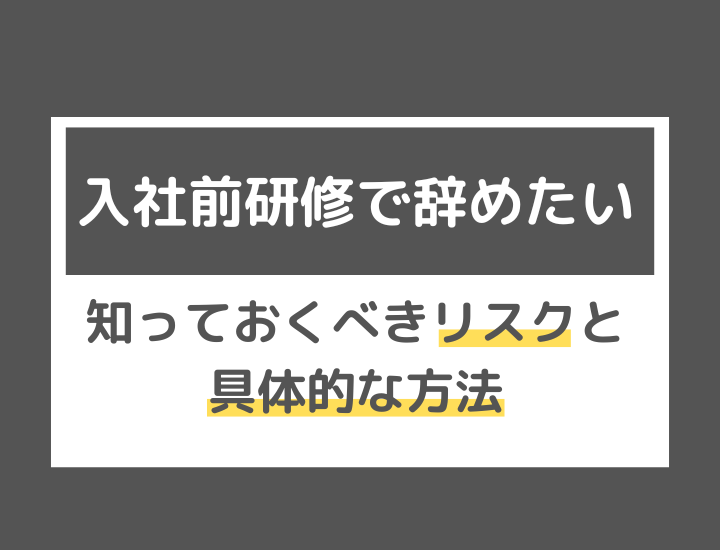
入社前の研修で辞めたい!知っておくべきリスクと具体的な方法について解説
はじめに
「研修についていけない」
「入社前なのに、もう会社を辞めたい」
「辞めたら違約金を請求されるのでは」
入社前の研修で不安や迷いを感じている方は少なくありません。
この記事では、10年以上の採用コンサルティング経験を持つ専門家の知見をもとに、入社前研修での退職に関する法的リスクや対処法を解説します。
この記事を読めば、自分の状況に合わせた判断と、円満な退職への道筋が見えてくるはずです。
一緒に、将来のキャリアにとってベストな選択を考えていきましょう。
入社前研修で辞めることは可能
結論から言えば、研修期間中であっても入社日から2週間以上前に告知すれば辞められます。
入社前研修の多くは内定承諾後に受けることが多い点から、法律上では労働契約が成立している可能性が高いため、即日辞めるのはおすすめできません。
即日辞退は最悪の場合、研修費請求などトラブルが起こるリスクもあります。
「労働契約書に書かれている内容と違っていた」などやむを得ない理由でない限りは、きちんと事前に退職する旨を上司に申し出て、きちんと相談するようにしましょう。
入社前の研修で辞めるときの流れ
研修期間中であっても、入社日から2週間以上前に告知すれば退職は可能です。
1.上司への退職の旨を伝える
2.退職届の作成する
3.退職届の提出をする
なお、メールや電話での退職通知は避け、必ず対面で伝えるようにしましょう。また、研修費用の返還義務が発生する可能性もあるため、契約内容の確認は慎重に行う必要があります。
入社前研修で辞めるときのリスク
ここからは、入社前研修での退職に伴う具体的なリスクと、その対処法について解説します。
入社前研修での退職には、リスクが存在します。可能性として研修費用の返還請求を受けることがあります。特に、研修費用に関する契約書にサインをしている場合は要注意です。
リスクを知って、今辞めることが良いのかどうかの判断をしてみましょう。
注意を受ける可能性がある
入社直前に辞めるとなれば、やはり会社から注意を受ける可能性があります。
「入社してもらうために何日も前から準備していたあなたに期待していたことなどを考えると、冷静にいようとしても感情が揺さぶられることがあるかもしれません。
一度は入る意志を見せたという部分でやはり落ち度があるので、何か厳しい言葉で叱責や注意を受けることがあっても、その時限りだと思って飲み込むようにしましょう。
必要以上に落ち込まないよう、次は良い会社を探すとしっかり気持ちを切り替えて自身のメンタルケアに努めることが大切です。
研修費用を請求される可能性がある
研修費用については原則企業が負担しますが、状況によっては研修費用を請求される可能性があります。
例えば企業に対して「研修費用を出して欲しい」とお願いしたときなどです。
その場合は「〇〇日までに辞退の意志がある場合、研修費用を全額返還する」といった契約書を交わすことがあります。
契約書に記載されている状態であれば、研修費用を返還する義務が発生してしまうこともあるのです。
入社前研修で辞めるときのメリット
入社前研修で辞めるときのメリットは、主に次の2つです。
-
履歴書に書く必要がない
-
キャリアの軌道修正がしやすい
ここからは、研修期間中に退職をするメリットについて解説します。
履歴書に書く必要がない
入社して雇用保険に入ってしまうと、履歴書には在籍していた記録が残りますが、研修前であれば入社扱いにならないことがほとんどです。
履歴書に退職の履歴がなければ、採用担当者から退職理由を聞かれることはありません。
キャリアの軌道修正がしやすい
入社前の段階で辞めておけば、キャリアの軌道修正がしやすくなります。
つまり研修を通して自分の向き・不向きがわかるようになって、改めて就活しなおすことができるということです。
また実務に近い研修という体験を経て、本当に自分がやりたいことや興味のある業界などの選択肢が増えることでしょう。
さらに一般的な社会人マナーについてもある程度習得できるため、転職活動のときに他の学生よりも有利に働くことがあります。
入社前研修で辞めるときのデメリット
入社前研修で辞めるときのデメリットは、主に次の2つです。
-
辞めグセがつく可能性がある
-
辞めた企業や関連企業への応募は難しくなる
ここからは、研修期間中の退職によって生じるデメリットについて解説します。
辞めグセがつく可能性がある
短期間で研修や仕事を辞めてしまうと、辞めグセがついてしまう可能性があります。
一度辞めグセがつき退職を繰り返すと、我慢耐性が低くなる、仕事が決まりにくくなるといったデメリットが生じてしまいます。
何度も辞めてしまうことがないよう、自分はなぜ辞めたいのか、今から解決できないことなのかをじっくり考えるようにしましょう。
辞めた企業や関連企業への応募は難しくなる
入社前の研修で辞めてしまうと、企業からの信用がなくなり、その企業はもちろん、関連会社へ就職・転職することが難しくなってしまいます。
円満退職であれば話は変わりますが、研修前の辞退は内定辞退とほぼ同義と考えて良いでしょう。
そのため辞める決断を下す前にもう一度考えて、「やっぱり研修を頑張れば良かった」と後悔のないようにしておくことが大切です。
内定承諾後は違法になる可能性がある
内定を承諾したあとの辞退は、企業にとって不利益が生じる可能性もあります。
そのため内定承諾後では違法になる可能性もゼロではありません。
ここからは、違法にならないケースと違法となるケースについて解説します。
違法にならないケース
入社日から2週間以上前に辞退の旨を伝えれば、一般的には違法になりません。
入社日が近くなるにつれ、企業は新入社員を迎え入れる準備を進めていくため、直前の辞退は迷惑がかかってしまいます。
突然辞めると伝えられてしまうと、企業は新たに人材を確保する費用的なコストもかかってくるでしょう。
企業への配慮を欠かすことなく、辞める意志が固まったらすぐに担当者へ伝えることが大切です。
違法になるケース
一方、入社まで2週間を切ってしまっている状態で辞める意志を伝えた場合は、違法になることもあるでしょう。
特に内定承諾書にサインをしたあとの辞退は、単に「入社を辞める」ではなく、労働契約の解約になり契約不履行と扱われることがあります。
学生の場合、損害賠償請求が起きる可能性は低いかもしれませんが、企業側にとっては経済的ダメージもあるので、入社直前の辞退は極力控えましょう。
内定承諾後に辞めるときの手段
内定承諾後に辞めるときの手段は、主に次の2つです。
-
辞めると決めた時点で人事に連絡する
-
辞めたい理由を明確に伝える
辞めると決めた時点で人事に連絡する
辞めると決めた時点で、できるだけ早く人事に連絡を入れるようにしましょう。
悩んでいる間も、企業は研修を含め新入社員を迎え入れるための準備を進めているからです。
早く辞める意志を伝えてもらえれば、企業も新たに採用を再開するため動けます。
研修期間中に辞めたいときは、入社日の2週間前までに連絡を入れるようにしましょう。
確実に連絡がつく電話が望ましいですが、営業時間外の場合は、まずメールで一言連絡を入れておくようにするのがポイントです。
電話で伝えるときのポイント
電話では時間を割いてくれていること、研修を進めてくれていることへの感謝を伝えてから、辞退したい旨を伝えましょう。
人事から辞退するに至った理由を聞かれることがあります。
その際は「自分の適性を生かせる仕事を探したい」「別の業界に興味が出てきた」など、ネガティブさが伝わらないよう配慮するのがポイントです。
また電話は、相手の迷惑にならないよう営業時間中にしましょう。
メールで伝えるときのポイント
メールで伝えるときも、電話同様内容自体に大きな違いはありません。
しかし人事は毎日多くのメールが届き、対応に追われています。
そのため読む相手が一目で内容を理解できるように、件名の中に【内定辞退のご連絡】と明記し、自分の名前を記載しましょう。
メールは送信日時が記録されるので、電話とあわせて利用すればトラブル回避に効果的です。
辞めたい理由を明確に伝える
辞めたい理由を明確に伝えましょう。
ただ「辞めたい」と抽象的な理由では、会社側も納得しづらいからです。
辞める事実に変わりはないので、誠実さを見せる意味でも、聞かれた理由については正直に伝えておいた方が良いでしょう。
ただし「研修がつらかった」「苦手な人が多かった」などネガティブな要素のある理由を伝えるのはNGです。
「他者の方が自身の適正に沿っていた」「地元で働くことになった」など相手の気を悪くさせないような理由を伝えましょう。
入社前研修で辞めるときの注意点
研修期間中に辞めるということは、相手に迷惑がかかる可能性も高いため慎重に進める必要があります。
入社前の研修段階で辞めるときの注意点は次の5つです。
-
誠意ある対応を心がける
-
連絡する時間帯に気をつける
-
曖昧な態度を見せない
-
呼び出しされたときは断る
-
後悔しないのかどうか再度考える
入社前研修での退職は、適切な対応が求められます。
ここからは、スムーズな退職のための注意点について解説します。
誠意ある対応を心がける
誠意ある対応を心がけるようにしましょう。
どうせ辞めるからといって連絡をしないのはNGです。
連絡をする際は、感謝の言葉や迷惑をかけたことに対する謝罪を忘れないようにしましょう。
また辞める理由についてもうやむやにせず、正直な気持ちを伝えることが大切です。
きちんと誠意が伝われば、企業側も追及したり叱責したりすることもせず、納得して受け入れてくれるかもしれません。
たとえ相手が感情的になっている場合でも、冷静に感謝や謝罪を伝えるようにしましょう。
連絡する時間帯に気をつける
辞める連絡は、連絡する時間帯に注意しましょう。
始業時間すぐや、昼休憩、終業時間直前は控えておいた方が無難です。
一般的な勤務時間を設ける企業であれば、9:30~11:30、13;30〜18:30ぐらいの時間帯が望ましいでしょう。
曖昧な態度を見せない
辞めるに際して、相手に曖昧な態度を見せないようにしましょう。
辞めるのか辞めないのかはっきりしない様子だと、もう一度考え直すように説得されてしまう可能性があるからです。
そこで辞めないという選択肢もありますが、研修で辞めたいと考えているなら、その会社で長く働き続けるのは難しいと言えます。
しっかり考え抜いた末の決断であることを伝え、毅然とした態度で対応するようにしましょう。
呼び出しされたときは断る
もし呼び出しを受けたときは、丁寧に断るようにしましょう。
企業によっては呼び出しをして、引き止め、あるいは叱責してくるケースがあります。
対面になってしまうと、一度辞めようと思った気持ちが気持ちが揺らいでしまうかもしれません。
しかし辞める意志が固まっておらず、悩んでいる状況であるのなら、一度企業へ訪問して人事に相談してみるのも一つの手段です。
後悔しないのかどうか再度考える
研修を辞退する前に、本当に後悔しないのかどうかをしっかり考えてみましょう。
デメリットでもお伝えしたとおり、一度研修を受けた企業を辞めてしまうと再応募や関連企業への応募が難しくなってしまうからです。
辞めたあとで「もう少し頑張れば良かった」とならないように、今自身が置かれている状況を踏まえながら、辞めるかどうかを慎重に検討しましょう。
入社前研修で辞めるときの伝え方【例文あり】
「研修期間中の退職、どのように伝えれば円満に辞められるだろうか」
「具体的な退職理由の伝え方がわからない」
「上司に失礼のない伝え方を知りたい」
入社前研修での退職は、適切な伝え方で円満な退職につながります。
ここからは、状況別の具体的な退職理由の伝え方と例文を解説します。
体調不良で業務の継続が難しいケース
体調不良による退職は、最も受け入れられやすい退職理由の一つです。
特に持病や長期的な治療が必要な場合、会社側も退職を認めざるを得ません。
退職を伝える際は、以下の3点を説明しましょう。
- 具体的な症状や診断内容
- 治療に必要な期間
- 業務継続が困難な理由
大変申し訳ございませんが、先日の健康診断で◯◯◯◯と診断されました。
現在、動悸や不整脈、疲労感が強く、医師からは週3回の通院治療と、安静が必要との診断を受けております。
症状が安定するまでに6か月程度かかる見込みで、この状態では長時間のデスクワークや集中力を要する業務に支障をきたす可能性が高いとのことです。
社内での時短勤務なども検討いたしましたが、現時点では治療に専念する必要があるため、誠に勝手ながら退職をお願いしたく存じます。
業務内容が自分に合わないケース
業務内容が自分に合わない場合、状況説明と自己分析に基づく理由を示すことが重要です。
退職を伝える際は、会社や業務自体を否定せず、あくまでも自身の適性の観点から説明するようにしましょう・
入社前研修を通じて、営業職の業務内容について真摯に向き合ってまいりましたが、お客様との商談や数値目標の達成において、自身の適性と求められる能力に大きなギャップを感じております。
特に、提案型営業に必要な即時の状況判断や交渉力が自分には不足していると実感しています。
研修期間中ではございますが、このまま継続しても会社の期待に応えることができないと判断し、退職をお願いしたく存じます。
業務のレベルに追いつけないケース
業務レベルの問題による退職は、デリケートな話題ですが、具体的な状況と自己分析を率直に伝えることが重要です。
特に、努力したプロセスと客観的な判断基準を示すことで、相手の理解を得やすくなります。
研修期間中、システム開発の基礎から懸命に学習してまいりましたが、プログラミング言語の習得や論理的思考において、想定される期間内での成長が難しいと判断いたしました。
Java言語の基本文法の習得に予定の倍の時間を要し、また実践的なコーディング演習では、他の研修生と比べて作業速度に大きな差が生じております。
毎日3時間の自主学習も行いましたが、今後も同様の遅れが予想され、チーム開発での足かせになることを懸念し、退職をお願いしたく存じます。
希望していた業務と実際の業務が異なるケース
業務内容の相違は、よくある問題です。
特に、採用時の説明と実際の業務内容に大きな違いがある場合、早期退職をするケースがあります。
業務内容の相違を伝える際は、個人の成長やキャリア形成の観点から説明するようにしましょう。
入社時の説明では、Webマーケティング部門でデジタル広告の運用や分析業務を担当する予定でしたが、実際には一般的な事務作業が大半を占めております。
私自身、デジタルマーケティングのスキルを活かし、データ分析や施策立案に携わることを期待して入社を決意しました。
しかし、現状の業務内容では、キャリア目標の達成が難しいと判断し、誠に申し訳ございませんが、退職をお願いしたく存じます。
人間関係や社風が合わないケース
社風や人間関係が合わないケースは、慎重に伝える必要がある退職理由です。
この場合、個人や組織を批判せず、価値観の違いという観点から説明することが重要です。
「入社前研修を通じて、御社の企業文化や働き方について理解を深めてまいりましたが、私自身が目指すキャリアの方向性と、会社の価値観に違いがあると感じております。
私は個人の裁量で柔軟に業務を進められる環境を望んでいましたが、御社の厳格な管理体制のもとでは、十分なパフォーマンスを発揮できないと判断いたしました。
真摯に適応を試みましたが、このままでは会社の期待に応えることができないため、退職をお願いしたく存じます。
家庭の事情で継続が困難なケース
家庭の事情による退職は、比較的受け入れられやすい退職理由の一つです。
具体的な状況説明と今後の見通しを明確に伝えることが重要です。
ただし、家庭の事情による退職は、虚偽の申告が発覚した場合のリスクが高いため、正直な理由を伝えるようにしましょう。
大変申し訳ございませんが、父の急病により、実家の家業を継ぐ必要が生じました。
父は先月、重度の腰椎ヘルニアと診断され、今後半年以上の安静が必要とのことです。
家族で何度も話し合いを重ねましたが、私が家業を引き継ぐ以外に選択肢がない状況です。
研修期間中の退職となり、会社に多大なご迷惑をおかけすることは重々承知しておりますが、このような事情をご理解いただき、退職をお願いしたく存じます。
入社前研修で辞めるときの伝え方のポイント
「退職を決意したけど、誰にどう伝えればいいのだろう」
「上司への伝え方を間違えて、関係が悪化してしまわないか」
「正直に話すべきか、それとも適当な理由を考えるべきか」
入社前研修での退職は、伝え方一つで円満退職と険悪な関係の分かれ道となります。
ここからは、人事担当者として数多くの退職相談に対応してきた経験から、「直属の上司への伝え方」と「正直な理由の伝え方」について解説します。
これらのポイントを押さえることで、企業との良好な関係を維持しながら、スムーズな退職が可能です。
直属の上司に伝える
退職の意思は必ず直属の上司に口頭で伝えることが重要です。
メールや電話での通知は、トラブルの原因となる可能性が高く、避けましょう。
1.上司の予定を確認し、面談の時間を確保する
2.個室など適切な場所を選択する
3.退職理由と希望退職時期を明確に説明する
4.感謝の意を示しつつ、今後の手続きについて相談する
上司を飛び越えて、より上位の役職者に直接伝えることはマナー違反です。
対面での会話では、退職理由と希望退職時期を説明し、これまでの指導への感謝も忘れずに伝えましょう。
上司から厳しい言葉を受けることもありますが、円満な退職のためには誠実な対応が不可欠です。
嘘はつかずに正直に伝える
退職理由を正直に伝えることは、企業との信頼関係を維持し、場合によっては業務改善のきっかけとなる重要な機会です。
退職理由を正直に伝えることで、企業側が問題点を認識し、改善策を提案する可能性があります。
例えば、業務内容の不一致を伝えることで、配属先の変更や業務内容の調整といった柔軟な対応を引き出せることがあります。
ただし、正直に伝える際も、批判的な表現は避け、建設的な表現を心がけましょう。
例えば「この部署は非効率的だ」ではなく、「より効率的な業務遂行方法を模索したい」といった表現がおすすめです。
入社前研修を受けるのか判断するポイント
内定をもらい入社前研修が始まってしまうと、辞める手続きを進めるのは困難になります。
そのため、内定を承諾する前に慎重に判断して入社を決めることが重要です。
入社を決める際のポイントとしては、以下の3つがあります。
ポン
- 雇用契約書を読み込む
- 気になることは事前に聞いておく
- 迷っているときは研修は受けない
ここからは入社前研修を受けるか否かの判断に必要なポイントを解説します。
雇用契約書を読み込む
内定をもらうことができたら、雇用契約書にしっかり目を通しておきましょう。
雇用契約書とは、企業が労働者から契約の合意をとるための書類です。
労働契約の期間や勤務地、時間外労働の有無など働く上で決められた条件について詳しく記載されています。
自分の希望に沿った条件かどうかを再度確認して、サインするようにしましょう。
雇用契約書に同意して提出した時点で取り消しは難しくなってしまうので、文章量が多くても、一つひとつきちんと読み込んでおくことが大切です。
気になることは事前に聞いておく
気になることは、面接の段階でしっかり聞いておきましょう。
聞いておきたいポイントとしては、以下のようなものがあります。
どのような業務内容なのか
まずどのような業務内容なのかを聞いておきましょう。
事前に理解しているつもりであっても、実際に聞いてみれば求人情報には記載されていなかった話が出てくるかもしれません。
聞いただけではわからないような業務内容であれば、さらに踏み込んで具体的な仕事の流れについても聞いておくと良いでしょう。
待遇はどうなっているか
次に給与やボーナス、福利厚生といった待遇についても聞いておきましょう。
例えば給与であれば、求人情報で「〇円以上」と書かれているだけでは、具体的な金額がわかりません。
また手当の付き方や昇給の仕組みなどは、企業によって若干ルールが異なることがあります。
待遇は仕事をする上で欠かせない要素であるため、聞きづらいと思わず今後長く働くためにも聞いておくことをおすすめします。
どのような社風があるのか
どのような社風があるのかを聞いておくのも大切です。
大切にしている文化や信念など、会社の雰囲気を掴んでおけば自分にとって働きやすい職場であるかどうかの判断ができます。
ただしホームページを見ればわかるような内容については、質問しないようにしましょう。
それでも質問するのであれば「御社の社風は〇〇な環境づくりとありますが、実際どのように皆様は仕事を進められているのでしょうか」と聞き、掘り下げた内容に変えて聞いてみるのがポイントです。
配属先はどのような部署なのか
あとは配属先の部署について聞いておくと良いでしょう。
実際に入社してみると、求人情報に記載されていない部署へ配属されるという可能性もゼロではありません。
所属先の部署の業務内容が、自分のスキルや経験を生かしづらいと、長く働くのが難しい可能性もあるでしょう。
配属先の人数や社員構成などを聞いておけば、働くときのイメージが膨らみやすくなります。
キャリアアップ環境が整っているか
キャリアアップ環境が整っているかどうかも、入社前に聞いておきたいポイントです。
企業が研修や学習セミナーなどを定期的に開催しているのかを知ることで、キャリアアップできる環境であるかどうかの判断ができます。
仕事に不安を感じている人は、新入社員研修の期間がどれくらい設けられているのか聞いてみても良いでしょう。
また昇給や昇進はキャリアアップに関わってくる部分であるため、あわせて確認しておくことが重要です。
迷っているときに研修は受けない
迷っているときは研修を受けないようにしましょう。
一度研修に参加してしまうと、研修費用などが発生している場合、辞退の意志を伝えたあとに費用を請求されるリスクが潜んでいるからです。
特に、複数社の内定をもらっている場合や、業界自体への迷いがある場合は、慎重な判断が必要です。
この段階で正直に人事部門に相談することで、むしろ企業からの信頼を得られる可能性があります。
研修で辞めると決断したらすぐに転職活動を
「研修を辞めることは決めたけど、次の転職はいつ始めればいいのだろう」
「離職期間が長くなると、不利になるのではないか」
「効率的に次の仕事を見つけるにはどうすればいいのか」
ここからは、スムーズな転職をするための方法と、「離職期間の管理」と「転職エージェントの活用」について解説します。
これらを知ることで、効率的な転職活動が可能です。
離職期間を長引かせない
離職期間の長期化は、転職活動において大きなマイナス要因です。
空白期間が長引くほど、転職の機会を逃すリスクが高まり、さらに経済的・精神的な負担も増加します。
早期転職活動のメリット
- 経済的な不安の軽減
- 転職市場での競争力維持
- メンタル面の安定性確保
経済的な備えとして、最低3ヶ月分の生活費を確保した上で転職活動の開始をおすすめします。
余裕を持つことで、焦ることなく転職先を見つけることが可能です。
転職エージェントを利用する
研修期間中の退職後の転職活動では、転職エージェントの活用が効果的です。
転職エージェントは、求職者のスキルや経験に基づいて、最適な企業とのマッチングを実現します。
転職エージェントを利用するメリットは、専門的なサポート体制です。
経験豊富なキャリアアドバイザーが、履歴書や職務経歴書の添削から面接対策まで、きめ細かな支援を提供します。
特に、研修期間中の退職という繊細な状況において、その理由を前向きに伝える方法についても的確なアドバイスを受けられるでしょう。
また、転職エージェントは企業の詳細な情報も把握しているため、社風や業務内容のミスマッチを防ぐことができます。
さらに、公開求人では得られない非公開求人の紹介も受けられ、より多くの選択肢の中から転職先を見つけることが可能です。
特に重要なのは、転職活動の効率化です。
一人で転職活動を行う場合と比べて、より短期間で的確な企業との出会いが期待できます。
これにより、空白期間を最小限に抑えることができ、スムーズな転職が可能です。
まとめ
入社前研修での退職は、慎重な判断と適切な対応が求められる重要な決断です。
入社前研修での退職は、キャリアの中での一つの転機として捉え、次の成長につなげることが大切です。
慎重に判断し、手順で進めることで、円満な退職と新たなキャリアへの良いスタートを切れるでしょう。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!