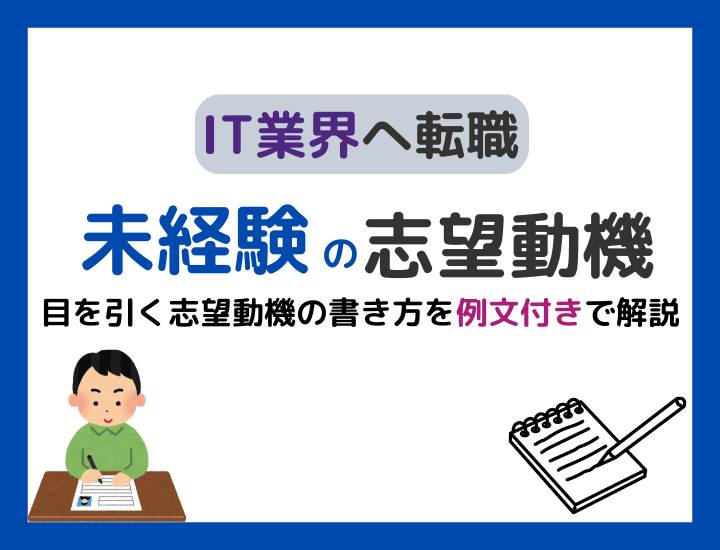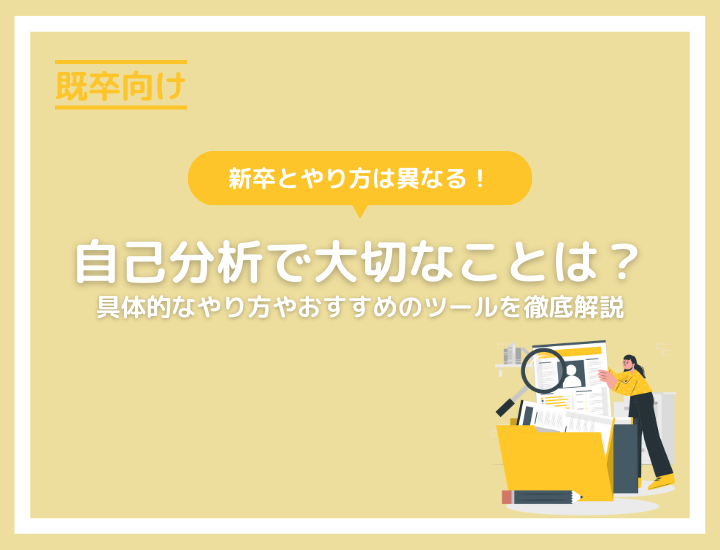
【既卒向け】自己分析で大切なことは?具体的なやり方やおすすめのツールを徹底解説
はじめに
大学を卒業して少し時間が経過し、就活をしようと思っている方の中には、最初にやるべきである自己分析も「何から手をつけたら良いのかわからない」という状態の方も多いのではないでしょうか。
新卒の就活生がやる自己分析とはどう違うのか、就活を一緒に進める仲間も多くない中で、どうやって進めたら良いのかわからないといった不安は、事前に自己分析のやり方や就職活動の進め方について理解しておけば、取り払うことが可能です。
この記事では、既卒ならではの自己分析法から、企業が評価するポイント、よくある質問まで解説します。
【既卒者の自己分析】自己分析をする目的
「自分のことは自分が一番よく知っている」という言葉がありますが、実際は完全に自分のことを理解できている人はいないと言っても過言ではありません。
そんな中、就職活動をするタイミングで、なぜ自己分析をあらためてやる必要があるのかを理解しておくことは、とても大切です。
目的を知っておくことで、より自己分析を的確に効率よく進めていくことができますので、以下ではその目的について詳しく解説していきます。
モチベーションの源泉を知るため
自己分析をすると、自分自身がどういった価値観を持っているかや、どういうときにやりがいを感じるかなどを知ることができます。
それによって、自分が何に対して全力で取り組むことができるのか、努力をするためのモチベーションの源泉を理解することになり、職種の選択にも大きく関わってくるのです。
このモチベーションの源泉と噛み合わない職種を選択すると、入社後も積極的に働くことが難しくなり、早期の離職といった結果にもなりかねません。
そのため、採用担当者は教育コストを無駄にしないために、志望している職種に適正があるかどうかを非常に重視して就活生と向き合います。
就職活動においては、あらゆる採用段階において、この自己分析の結果がもとになりますので、しっかり取り組むことが重要です。
自分の特徴を言語化できるようにするため
面接では、志望動機など自分で用意しておいたことをプレゼンする形で進むものもあります。
ただ、一方的に話して終わるわけではなく、採用担当者から用意してきた答え以上のものを深掘りして、聞いてくることもあります。
そのときに、自分自身についてきちんと理解ができていないと「なぜ」という問いに対して、言語化して答えることが難しくなってしまいます。
逆に、その「なぜ」という問いに対してきちんと答えることができれば、志望動機やキャリアプランなども説得力があるものとして採用者に届くため、良い印象を与えて面接を終えることが可能です。
普段の生活の中で言語化できていない深い層まで自分を深掘りしておくためにも、自己分析は必須と言えます。
企業とのミスマッチを防ぐため
自分の特徴をきちんと理解しないまま就活を行い、条件や待遇などだけで志望し入社してしまうと、本当は自分に向いていない職種や業界に入ってしまうことがあります。
そうなると、仕事でやりがいを見出すことができません。
周囲の同僚とも価値観が合わず、モチベーションが低下してしまうでしょう。
結果として、早期退職につながってしまいかねません。
そうなると、今度は時間をかけて、転職活動をやり直すことにもなってしまいます。
今のうちから自己分析をしっかり行い、自分がモチベーションを高く持ちながら働けて、やりがいを感じられる職種を選択できるようにしましょう。
これは内定を獲得することだけではなく、入社後の環境や生活にも大きく関わることになってきます。
【既卒者の自己分析】そもそも既卒とは
一般に既卒とは、大学や専門学校などを卒業し、就業経験がない人のことを指します。
似たような言葉に新卒や第二新卒という言葉もありますが、それらとの違いを一覧で示すと以下のようになります。
| 大学・専門学校などを卒業しているか | 会社への就業経験があるか | |
| 新卒 | 卒業予定 | なし |
| 第二新卒 | 卒業している | あり
(新卒入社から3年以内に離職) |
| 既卒 | 卒業している | なし |
| フリーター | 卒業している | どちらとも言えない |
それぞれについてより詳しく紹介するので、新卒や第二新卒、フリーターとの違いを理解しておきましょう。
新卒との違い
新卒とは、年度内に通っている学校を卒業する予定の学生で、既卒との違いは教育機関を卒業しているかどうかです。
通っている教育機関は、大学・専門学校・高等専門学校・高校などがあります。
一般的な新卒採用とは、毎年同じ時期に大学卒業予定の学生を所定の人数だけ一度に採用する、新卒一括採用のことです。
人材を効率よく確保することで会社組織を活性化させたり、社風をなじませやすい人材を得られたりするメリットがあることから、多くの企業が取り入れています。
一方で、教育コストの負担や選考でのミスマッチが起きるといったデメリット存在する採用方法です。
また、企業が新卒採用を実施できるかどうかについては、社会情勢や経済状況にも左右されます。
第二新卒との違い
第二新卒とは新卒採用で入社した会社を3年以内で離職した人のことで、既卒との違いは社会人経験の有無です。
厚生労働省の調査によると、新卒で入社した社会人が3年以内に離職する割合は、大卒・高卒ともに3割を超えています。
第二新卒に対しては、社会人としての最低限のマナーは備わっているので、その部分についての研修コストがカットできるというのが一般的な見方です。
その一方で、仕事に対するスキルや実績、経験の面が乏しいので、即戦力としての扱いは難しいと考えられています。
そのため、扱いとしては既卒と第二新卒に大きな差はなく、どちらかが選考で有利になるといったことはありません。
選考ではあくまで個人の人柄や入社への意欲が評価基準です。
フリーターとの違い
フリーターとはパートやアルバイトで生計を立てている人のことで、既卒と明確な差異があるとは言い切れません。
既卒である条件を満たしながらもアルバイトをしていればフリーターと呼べますし、会社を辞めた第二新卒に該当する人が、パートで生活していればその人もフリーターです。
就活の場では、既卒や第二新卒とは別の概念となるため、双方で比較すること自体無意味であるともいえます。
フリーターであったことが就職活動に悪影響を及ぼすとはいい切れません。
既卒や第二新卒と呼べる期間内であれば、それらの枠で求人への応募が可能です。
一方で、フリーターとしての期間が長引けば既卒の枠で応募することができなくなります。
できるだけ早めに就職したい企業を見つけるようにしましょう。
【既卒者の自己分析】既卒就活の状況
既卒者の就活状況ですが、企業としても少子高齢化に伴う若い人材不足に対応するために、既卒者の採用に積極的です。
未経験・経歴不問とする求人が多くなっているので、基本的な就活対策ができていれば就職できる可能性は高くなります。
採用の時期についても、既卒者に向けて通年採用を実施する動きが活発です。
社会情勢で見ると国を挙げて既卒者の就職がもっと容易になるよう後押しする動きがありますし、追い風の兆候が見られています。
その一方で、内定率については劇的に良くなっているとはいい難く、割合だけで見ると厳しいです。
では、既卒者を取り巻く就活の現状や、内定率についてもう少し掘り下げて紹介します。
新卒扱いしてくれる場合がある
厚生労働省の「青少年雇用機会確保指針」改正により、卒業後3年以内の既卒者は新卒枠で応募できるよう企業に呼びかけられています。
若者の就職機会を増やすため、政府は既卒者の新卒扱いを推進しているのです。
令和6年8月の労働経済動向調査によると、新卒採用を行った企業の72%が既卒者の応募を可能としており、そのうち40%が実際に採用に至っています。
2010年の25%から大幅に増加しており、既卒者の就職環境が改善されている結果といえるでしょう。
特に医療・福祉業では85%、情報通信業では85%の企業が既卒者の応募を受け付けています。
少子化による人材不足も背景に、若い既卒者を積極的に採用する傾向が強まっているのです。
内定率は約40%
厚生労働省の労働経済動向調査(令和6年8月)によると、既卒者の内定率は約40%となっています。
これは前年度の39%からわずかにではありますが上昇しています。
業種別に見ると、情報通信業では53%と高い採用率を示し、次いで宿泊業・飲食サービス業(49%)、医療・福祉(46%)と続いています。
新卒と比較すると内定率は低いものの、約4割の既卒者が内定を獲得できている現状は、既卒就活にとっては嬉しいことです。
特に人材不足が深刻な業界では採用率が高く、既卒としても内定獲得のチャンスは十分にあります。
【既卒者の自己分析】既卒に対して企業の印象
既卒者は企業が既卒者に対してどのような印象を持っているのか、実際のことが知りたいのではないでしょうか。
多くの方はネガティブな印象を持っているのではないかと考えるでしょうが、実はポジティブに思われている部分もあります。
過信は禁物で、ポジティブな印象ばかりではなくネガティブな印象もありますから、良い面と悪い面の両方について理解を深め、就職活動ではネガティブなイメージを取り払えるように心がけましょう。
好印象:貴重な若手人材
既卒の枠に入るのは、学校を卒業してから遅くても3年程度です。
そのため、既卒として選考活動を受ける人材は若手の人材となります。
企業としては、教えたことの吸収が早く、長く努めてくれる可能性がある若手人材を欲しているので、既卒に対してもポジティブに迎え入れます。
若手がなかなか新卒で入社しないような中小企業においては、既卒者からの応募は若手人材を獲得するまたとないチャンスですから、歓迎してくれる可能性も高いです。
若手の人材が特に求められるのは、介護やサービス業界、建設系といった肉体労働が中心となっている業界となります。
若いからこそ身体の強さや体力の多さが高く評価されやすいです。
好印象:すぐに入社してもらえる
既卒が新卒や第二新卒と比較してポジティブに捉えられやすいポイントの1つに、入社時期の自由度があります。
新卒一括採用では、新入社員の入社時期は学校卒業後の年度頭と決まっており、第二新卒の場合は前職に努めている場合もあり、そちらの退職を待たなければなりません。
既卒はこれらの事情で入社時期を遅らせなければならない理由がないです。
そのため、人材が欲しい時期に入社してくれる若手の人材として、前向きに捉えられやすいでしょう。
また、通年採用を実施している企業の多くは人手が不足しているので、一刻も早く入社してもらって、人材を確保したいと考えます。
新卒や第二新卒では内定を出した後で期間が空いてしまうので、その間に辞退されるおそれがありますが、既卒であればその心配もありません。
こうした事情から、既卒は若い人材をすぐに求める企業にとってはありがたい存在でもあります。
悪印象:人間性に不安を感じる
既卒が持たれやすいネガティブな面が、人間性への不安です。
既卒は新卒採用時に内定を獲得できなかった人材でもあるわけですから、他の企業が選考の過程で弾いた人材といえます。
そこで企業の採用担当者が考えるのは、なぜ新卒で入社できなかったかです。
社会人になるための基本的なスキルを持っていなかったか、人柄の面で難ありと判断されたかのどちらかだろうと思われてしまい、ネガティブイメージを持たせた段階からの選考となります。
この点については、選考の過程で人柄を見せられるような活動を心がけるようにして、ネガティブイメージを好転させましょう。
たとえ新卒採用の段階で難ありとされていても、就職活動に臨んだ時点で企業が求めている人物像に合致すれば良いのです。
企業がどのような人柄の人材を求めているかが分かれば、人間性への不安というハンデも乗り越えられます。
悪印象:熱意があるか不安
企業は既卒に対して、仕事への熱意が足りないから就職活動も成功しなかったのではないかという印象を持つことも多いです。
そのような印象を逆転させるためには、熱意や意欲の部分で不安にさせないような自己PRを心がける必要があります。
実際、既卒となっている人の全てが就職活動を途中で投げ出したり失敗したりしているわけではありません。
卒業を間近にして内定を辞退したり、会社の都合で内定取り消しになったりするようなケースも存在します。
また、既卒での就職活動は新卒のときよりも業界や業種の幅を広げ、自分の希望よりも適性に合った企業を選ぶようにしているなどの前向きなケースも考えられる理由です。
大事なのは、なぜ既卒としての道を選び、就職活動に臨んでいるかを明確にアピールすることとなります。
その過程で仕事に対する熱意や入社への意欲を示すことも可能です。
【既卒者の自己分析】自己分析のやり方
自己分析にはさまざまなやり方がありますが、まずは基本となるやり方から始めることで、ほかの手法やツールを活用したときによりその理解度が深まりやすくなります。
紹介するやり方は決して難しい作業ではないですが、じっくりと取り組むことも重要ですので、就活を始めたら早めに取り掛かるのがおすすめです。
既卒者が、具体的にどのような形で自己分析をしていくかについて解説していきます。
しっかりと自分の内面と向き合い、深掘りしていきましょう。
目標を明確にする
まず一番に実施するべきなのは、目標を明確にさせることです。
入社してどのようなことを達成させたいのかを言語化して、それを最終選考まで一貫して主張できるほど確固たるものにしましょう。
目標がないまま自己分析に臨んでも、入社後にやりたいことが見つからず、自己PRや志望動機が弱いものになってしまいます。
面接の際に軸とするものがなく、受け答えの内容が途中で変わるようなことにもなりかねません。
そのような仕上がりでは、内定を獲得することはできないです。
書類を作成するときや面接対策をする際に、筆や言葉が詰まることなく志望動機やキャリアプランを述べられるようにすることを、目標としておすすめします。
自信を持って選考に臨めるようなゴールを設定しましょう。
自分の好きなところ、嫌いなところを書く
自己分析を成功させるには、どこまで自分を深掘りしていけるかが大切な要素となります。
そのきっかけ作りとして有効なのが、好きなところと嫌いなところの書き出しです。
自分が好きだと思うこと、嫌いだと感じることを可能な限り多く書き出してみてください。
このときに深く考えこむことはせず、とにかく数を出すことが大切です。
仕事に直接関係なさそうなことでも構いません。
最低でも、それぞれ10個ずつは書き出すようにしましょう。
中には言語化しにくいと感じるものもあるかもしれませんが、そういったものを明確にしておくことも、今後にとって意味のあることです。
この作業は、自分を知っていくための大きな手がかりとなっていきます。
短所ばかりを見ないように
自己分析を進めていく中で注意したいのが、ネガティブな要素ばかりに目を向けないことです。
特に自分で自分を褒めることが苦手な人にありがちな傾向ですが、自己分析をしていくと、どうしても自分の短所ばかり目立ってしまいます。
そのような部分ばかりに目を向けていると、自己肯定感が下がり、積極的な就職活動ができません。
自分の適性を見つけ出すこともできなくなってしまいます。
自分を過信するのも良くないですが、自分の長所は必ず見つけておきましょう。
どのように小さなことでも構いません。
他人より劇的に優れている必要もないです。
自分が能力を発揮したことによって達成したことがあれば、そこから自分の長所が見つかります。
自信を持って主張できることですから、短所ばかり見ないで長所を見つけましょう。
出ないときは人に聞いてみる
自己分析とはいっても、自分1人で行う必要はありません。
行き詰まったときは他人に聞いてみるようにしてください。
第三者からの目線で見てもらえれば、自分1人では見つけ出せなかったポイントに気が付くことができます。
このとき大切なのは、聞く相手を選ばないことです。
友人や先輩・後輩、先鋭など、自分と関わりがある多くの人に聞いてみてください。
そうした人たちからの客観的な視点によって、自分の新しい可能性が見つけられます。
聞く内容ですが、自分では見つけやすい短所にするのではなく、自分では自覚しにくい長所を中心にしましょう。
悪い内容を人から聞かされると良い気分にはなりませんし、相手もいいにくいです。
相手も気持ちよく口に出せる長所を中心に聞いてみてください。
疑問をぶつけて深堀していく
好きなこと、嫌いなことをたくさん書き出すことができたら、今度はその好きな理由や嫌いな理由を「なぜ」という疑問をぶつけていくことで深掘りを進めます。
例えば「ドラマを見るのが好き」なのであれば、その好きな理由は何でしょうか。
役者さんの演技に引き込まれるのか、脚本が優れているからなのか、映像演出の綺麗さなのか、音響効果に惹かれるのか、作品の制作された背景に興味があるのかなど、どの部分に価値を感じているのかでまったく違った要素を拾うことができます。
ただ好き、ただ嫌いといったところから踏み込んで「こういう理由で好き」「こういう理由で嫌い」という解像度にしていくことにより、本質的な価値観に近いところまで理解を深めることができるでしょう。
深堀した内容から共通点を見つける
「なぜ」を繰り返しぶつけていくと、好きなものや嫌いなものの理由となる部分に共通点が見えてきます。
とくに好きなものの源泉を知ると、一見まったく別の職種であっても、本人にとっては同じ部分にやりがいを感じるポイントがあり、職種の選択肢を広げることが可能です。
逆に嫌いな理由を明らかにしていくと、一見すると楽しめそうな職種や恵まれた待遇であっても、どうしても許せないポイントがあったことで、早期退職につながってしまったという結果を招くリスクを減らすことができます。
こういった自分の価値観を炙り出すことにより、自身の「強み」と言える価値観やモチベーションの源泉、特徴と言える部分が浮き彫りになってくるのです。
【既卒者の自己分析】新卒の自己分析との違い
新卒と既卒には、就活をする際にさまざまな違いがあります。
とくに既卒で就活を始めたという方は、その違いが気になる方も多いのではないでしょうか。
しかし、自己分析に関しては、両者にほとんどやり方や目的において違いはありません。
これまでの人生において、経験してきた過去の体験を振り返り、自分自身の特徴を洗い出していくことが大切です。
自分が一生懸命やってきたことや楽しいと感じたこと、心が動いた出来事など、可能な限り思い出していくことから始めてみると良いでしょう。
【既卒者の自己分析】内定を取るために準備しておきたいこと
既卒として内定を勝ち取るには、新卒とは異なる準備が必要です。
「なぜ新卒で就職しなかったのか」「空白期間は何をしていたのか」といった質問への備えが内定獲得には必要です。
ここからは、既卒者が面接官に好印象を与え、内定を獲得するために準備しておくべきポイントを解説します。
これらの対策を実践することで、既卒就活の成功確率を大きく高めることができるでしょう。
新卒で就職しなかった理由を説明できるようにする
既卒就活で必ず問われるのが「なぜ新卒で就職しなかったのか」という質問です。
この回答は採用担当者の判断材料となるため、明確に説明できる必要があります。
採用担当者は既卒になった理由を通して、自社とのマッチ度や正社員として働き続ける意欲を判断しているのです。
理由が曖昧だと「目的なく既卒を選んだ」と誤解され、マイナス印象につながります。
「在学中に方向性が定まらなかった」「研究に集中していた」「就活がうまくいかなかった」など理由はさまざまですが、大切なのは自分の過去を振り返り、その経験から何を学んだかを伝えることです。
既卒の強みは、挫折経験を乗り越えた精神力と強い就業意欲です。
新卒時の経験から得た学びや成長を前向きに伝え、その挫折が自己成長につながったことをアピールしましょう。
他責思考ではなく、自責的に受け止めつつ改善点を示すことで、素直さと成長意欲を示せます。
空白期間に何をしていたのか説明できるようにする
面接官はこの質問を通じて、就業意欲の強さや長期間勤務する意思を確認しています。
空白期間の過ごし方が曖昧だと「目的なく時間を過ごした」と誤解され、マイナス印象につながるかもしれません。
アルバイト経験でも、その経験を通して学んだことや成長した点を伝えることで、ポジティブな印象を与えられるでしょう。
「飲食店でのアルバイトを通じて、チームワークの重要性や顧客対応力を身につけました」といった形で説明できると好印象です。
身だしなみやマナーは既卒だからこそ徹底する
既卒者は新卒よりも厳しい目で見られるため、身だしなみとマナーには気をつけましょう。
基本的なビジネスマナーや身だしなみが当然にできると期待しています。
清潔感のある服装、髪型、自然なお辞儀の角度、丁寧な言葉遣い、スムーズなドアの開け閉めなど、細部まで気を配ることが重要です。
特に「頭髪」「手・爪」「靴・足元」といった先端部分は注目されやすいため入念にチェックしましょう。
これらは一朝一夕では身につかないため、日常から意識して練習し、面接本番でも自然に振る舞えるよう習慣化することが大切です。
適切なマナーと身だしなみは、仕事への真剣さと自己管理能力の高さを示し、「この人を採用したい」と思わせる効果があります。
早めにアクションを起こす
既卒期間が長くなるほど就職難易度は上がるため、思い立ったらすぐに行動することが重要です。
求人情報は常に更新されており、好条件の募集を逃さないためにも日々のチェックが欠かせません。
「今月中に10社応募する」「3ヶ月以内に内定を獲得する」など明確な期限と目標を設定し、計画的に活動することで成功確率が高まります。
早期行動は単なる焦りではなく、自分の市場価値を最大化するためであることを知っておきましょう。
強みとなるスキルや資格を取得する
資格やスキルは「就業意欲の高さ」と「即戦力としての価値」を客観的に証明できるため、既卒に対する企業の懸念の払拭が期待できます。
業界を問わず活用できる「簿記2級」「MOS」などの汎用的資格や、志望業界に直結する専門資格が特に効果的です。
IT業界志望なら「プログラミングスキル」、金融業界なら「ファイナンシャルプランナー」などが評価される傾向にあります。
資格取得は単なるスキルアップではなく、既卒という経験を前向きに活かした証として取得しておきましょう。
【既卒者の自己分析】自己分析がうまくできない時の対処法
やり方を知って取り掛かってはみたものの、なんだか上手くできないというケースも多くあります。
しかし、その原因の多くは実施する際の心構えであったり、前提条件をきちんと確認していなかったりすることがほとんどです。
そのため、以下の対処法を試すことで、多くの場合は解決することができます。
自己分析が上手くいっていないことに気づけている時点で、自分への理解は一歩進んでいるとも言えますので、もう少し踏み込んで取り組んでみましょう。
自己分析の目的を見直す
自己分析は、それ自体に明確なゴールがない作業です。
ここまでやれば大丈夫というような量や時間が設定してあるわけではないため、なんとなくで始めてしまうと進捗を測ることができません。
記事の冒頭で説明したような「目的」を自身できちんと設定しておかないと、際限なく手応えのない取り組みを続けることになってしまいます。
一箇所を深掘りしようと思うと、どこまでもやれてしまうものであるため、俯瞰的な視野も必要です。
自分の内面からどういった情報を浮き彫りにし、分析すれば良いのかということを常に意識することで、初めて自己分析は意味のあるものになります。
そのため、ある程度やったら他の作業へと移り、志望動機や自己PRなどを書く中で、また必要を感じたら戻ってくるというやり方も状況によっては有効です。
マイナスな面としっかり向き合う
自己分析をしている中で、自分の短所と言える側面とも向き合う必要が出てきます。
これは非常にストレスのかかる作業であり、意識的、無意識的どちらにおいても避けたり、見ないふりをしてしまったりすることで、きちんと自己分析が完了しないというケースも多いです。
短所に目を瞑るということは、自己分析において大きな要素が欠けてしまうということでもあります。。
場合によっては、その短所を覆い隠すために「嘘」が紛れてしまい、そこから深掘りが進まないです。
短所こそしっかり深掘りし、自分の理解を深めていくことで、その短所を長所に置き換えたり、短所が影響しない環境を自ら選べたりできるようになります。
まずはその「短所と向き合うことができない」という弱い自分と、向き合うことから始めてみましょう。
他己分析を行う
自己分析が上手くいかない理由として考えられるのは、分析が主観的になり過ぎているというものです。
本来の自分ではなく「なりたい自分」に寄せて分析をしてしまったり、逆に自分を過小評価してしまったりすることから、分析結果が自分自身として、どこかしっくりこないというケースは少なくありません。
とくに取り組みはじめの頃は、自分を客観視するのが難しいため、こういったケースに陥ることが多いです。
そういうときは、一度自分自身で分析することから離れて、他己分析をしてもらうことをおすすめします。
友人や親など、自分のことをよく知る人物にお願いしてみてください。
その際は、きちんと就活に向けて自己分析をしているから、それを手伝って欲しいと伝えることをおすすめします。
お世辞や気遣いから、ネガティブなことは避けるなどのようなことがあると、適切な結果が出ませんので注意しましょう。
【既卒者の自己分析】オススメの自己分析ツール5選
既卒就活では自己分析が重要ですが、どのツールを使えばいいか迷ってしまう方も多いと思います。
自己分析ツールを活用すれば、強みや適性を客観的に把握でき、面接での自己PRや志望動機の作成に役立ちます。
ここからは、既卒者におすすめの自己分析ツール5選を紹介します。
これらのツールを活用して、強みを明確にし、既卒就活を有利に進めましょう。
キャリアチケットスカウト
キャリアチケットスカウトは、レバレジーズ株式会社が運営する価値観マッチングに特化した新卒向けダイレクトリクルーティングサービスです。
従来の学歴や文理といった表面的な情報ではなく、「価値観」を軸にしたマッチングを実現することで、企業と学生の効果的な出会いが期待できます。
学生は自己PRやキャリアに対する価値観を登録すると、マッチング度の高い企業からスカウトメッセージが届きます。
「オファー機能」と「話したい機能」の2種類のアプローチ方法があり、企業側は月に400〜450通のスカウトを送信可能です
企業側は学生のどの価値観に共感したかを伝えることで、知名度や業界に関係なく高いオファー承諾率(平均15〜20%)を実現できます。
また、2023年1月からはイベント掲載機能も追加され、本選考やインターンへの募集も可能になりました。
いろいろな自己分析ツールを使ってみたいと思うのであれば、登録作業なども簡単なので、一度触ってみましょう。
キミスカ適性検査
キミスカ適性検査は、累計400万件を超えるビッグデータから生成された自己分析ツールで、「タイプ別適職検査」と「性格資質検査」の2種類があります。
就活生が自分の強み・弱みや適性を客観的に把握することで、自己PRの作成や企業選びに役立てられるでしょう。
タイプ別適職検査では約80問(所要時間約10分)の質問に答えることで、ゼネラリスト、フリーランサー、パイオニア、スペシャリストの4タイプに分類され、自分に合った職種や働き方がわかります。
性格資質検査では約150問(所要時間約15〜20分)を通じて、革新性、環境順応性、社交性など8つの項目で自分の特性が詳細に分析されます。
検査結果は企業にも公開され、適性に合った企業からスカウトが届く仕組みです。
スコアの高さではなく、企業の求める人材像とのマッチ度で評価されるため、自分らしさを活かした就活が可能になります。
これから自己分析を始める方にはぜひおすすめしたいサービスです。
業界タイプ別就活診断(みん就)
業界タイプ別就活診断は、みん就(旧楽天みん就)が提供する無料の適性診断ツールです。
わずか4つの質問に答えるだけで、自分に合った業界を客観的に把握できるため、業界選びや自己分析に悩む就活生におすすめです。
日常生活に関する簡単な質問に回答するだけで、約30秒という短時間で診断結果が表示されます。
結果では自分の性格タイプと相性の良い業界・職種が具体的に示され、就活の方向性を定める手がかりになります。
みん就への無料会員登録が必要ですが、診断だけでなく29,260社以上の企業別掲示板や内定者による体験記も閲覧可能です。
特に「どの業界が自分に向いているかわからない」「志望業界が自分に合っているか確認したい」という就活生にとって、効率的な業界研究のスタートポイントとなるツールです。
ただ、情報の精度に関しては、あくまで掲示板であるため高いとは言えない点も踏まえておきましょう。
3分間!適職診断(リクナビNEXT)
3分間!適職診断はリクルート社が運営するリクナビNEXTで提供されている、短時間で自分の適職を診断できるツールです。
転職や就職活動において、自分に合った仕事や企業を客観的に知ることは重要です。
この診断では、優先したい条件や幼少期の性格などから適職を導き出します。
診断結果では適性に合った職種や業界がを教えてもらえるため、キャリア選択の参考になるでしょう。
アゲルキャリアのMBTI診断
アゲルキャリアは、株式会社HRteamが運営する中途向けの転職エージェントです。
アゲルキャリアが提供しているMBTI診断は、52個の質問に回答することで、適職がわかる自己分析ツールです。
MBTIだけではなく、自分自身ではわかりづらい短所や長所がわかるので、自己PRを考える時にも役立ちます。
『自宅は整理整頓されていますか?』など日常的な質問が多いので、気軽に回答でき、また質問数が多いので質がよいのも特徴です。
診断もLINEの登録をするだけで無料でできるので、とりあえず自己分析ツールを使ってみたいという方におすすめです
【既卒者の自己分析】既卒の就活でよくある質問
既卒の就職は既卒ならではの悩みがあり、どのように解決すれば良いのか分からなくなるケースも存在します。
一度つまづいてしまうと、悩みから抜け出せなくなって就活にも影響が出てしまいますが、あらかじめ悩みやすいポイントについて知っておけば、自分なりの答えを用意しておくことも可能です。
ありがちな悩みを良くある質問としてまとめてあるので、その回答をチェックして自分の就活に役立ててください。
Q:どう活動していいのかがわからない
既卒は新卒一括採用と違って、決まった時期に決まった形でエントリーするといった流れが存在しません。
そのため、いざ行動する段階になってもどのように活動すれば良いのか分からない人が多いです。
まず必要なのは、スケジュールを立てることです。
これは新卒枠で応募するのか、中途採用での応募となるのかで組み立て方が変わります。
新卒であれば、入社を予定している前の前の年度から行動を開始し、応募先の絞り込みと自己分析、企業研究などを実施しましょう。
中途採用での活動であれば、企業の採用スケジュールから逆算して予定を立ててください。
応募・面接が始まる前々月から自己分析と企業研究を始めるようにすれば、予定が押して間に合わないということにはなりません。
どちらにせよ、できるだけ早く行動に移すことが重要です。
Q:既卒を募集している企業がわからない
既卒が悩みやすいのが、既卒でも応募して良い求人かどうかが分からないときです。
新卒の求人でも既卒が応募できるケースはありますが、明確に既卒でもエントリー可となっているか記載されていないと、応募がしづらいです。
既卒でも応募が可能な企業を探す方法はいくつかあります。
1つが就活サイトです。
就活サイトの検索で、既卒、あるいは未経験可で絞り込んで探せば見つけやすいです。
自分でうまく探せないときは、就職エージェントを利用するのも有効な方法となります。
就職エージェントは自分の適性に合う企業を紹介してくれたり、書類や面接の対策を相談することも可能です。
Q:既卒になっている理由が答えられない
既卒が頭を抱えやすい問題が、企業の採用担当者に既卒として就職活動を行っている理由を話せないことです。
人によっては答えづらい内容になるかもしれませんが、既卒である以上は避けられない質問だと心得ておく必要があります。
どのような事情であれ、下手に嘘をいうのは避けましょう。
既卒として就職活動を実施している理由を、ありのまま話すようにしてください。
そして現在に至るまで、就職活動をどのように実施しているかまでを付け加えて話せば、問題はありません。
新卒での就活の失敗があったとして、それをどのように反省し、既卒での就活に生かせているかを話すことができれば、逆に人間性の良さをアピールすることにもつながります。
Q:誰に相談をしていいのかわからない
新卒では、学校の就職担当者や先輩・先生などに就職活動でうまく行かないことを相談することができました。
しかし既卒では相談する相手が限られてしまいます。
人によっては相談する相手が見つからず、自分1人で進めようとする人も多いです。
そのような状態が続くと、ストレスが溜まってしまい、精神的に参ってしまうおそれもあるので、相談する相手は確保しておきましょう。
身近な人で浮かぶのは友人や両親になるでしょうが、既卒で就職活動をしている立場を理解してくれる保証がないだけでなく、スケジュールも合わない可能性が高くなります。
既卒が就活中に相談する相手としては、就職エージェントのキャリアアドバイザーがおすすめです。
既卒にありがちな悩みが解決するだけでなく、就職に関する幅広い知見で悩みを解決してくれます。
まとめ
既卒者の自己分析は、就活を成功へ導く重要なステップです。
この記事で解説したように、自己分析の目的を理解し、既卒ならではの強みを見つけるこようにしましょう。
また、身だしなみやマナーの徹底、早めの行動開始、スキルや資格の取得も内定獲得の確率を高めます。
自己分析がうまくいかない場合は、キャリアチケットスカウトやキミスカ適性検査などのツールを活用してみてください。
既卒就活は決して不利ではありません。
むしろ、社会経験や自己理解を深める時間があったことをポジティブに捉え、その経験を強みに変えることで、ぴったりの企業との出会いが待っています。
自信を持って行動してみましょう。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!