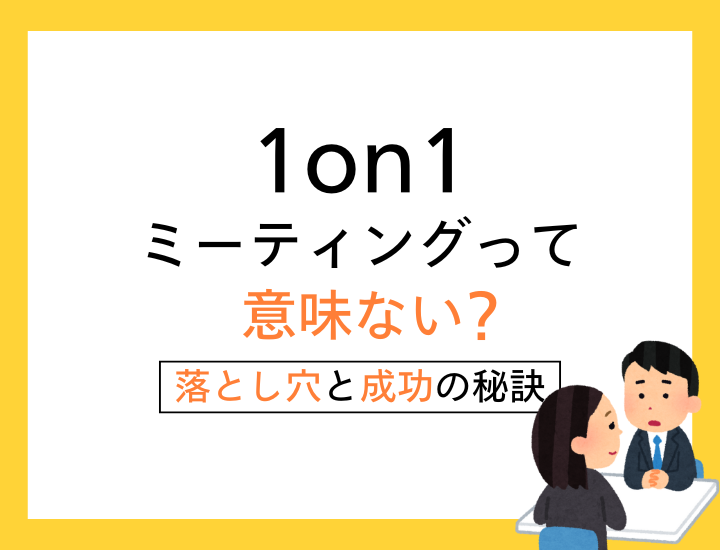営業職が覚えておきたい「顕在ニーズ」と「潜在ニーズ」の捉え方
「潜在ニーズ」「顕在ニーズ」は主にマーケティングでよく聞かれる言葉ですが、実は営業にも活かせる優れものです。
しかし、ニーズをうまく使い分けられなければ十分な効果を得られません。
顧客のニーズを引き出せば顧客満足度の向上だけでなく、営業成績や社員・顧客からの信頼度アップも叶えられます。
ニーズの意味や重要性、メリットを解説したうえでニーズを引き出すポイントや具体例などを紹介しますので、参考としてお役立てください。
顕在ニーズと潜在ニーズ
顕在ニーズと同様に良く聞くワードが「潜在ーズ」ではないでしょうか。
潜在ニーズと顕在ニーズの違いを分かりやすくお伝えすると、「顧客自身が自分のニーズを理解しているかいないかの違い」ということです。
例えば、「xxという課題を解決するものが欲しい」というように顧客が自分でニーズに気づけているのが顕在ニーズです。
一方、潜在ニーズは顧客自身では気づけていないニーズのことで、基本的には顕在ニーズを深掘りすることで出てきます。
「xxという課題を解決するものが欲しい」というニーズに対して、営業側が「なぜ」を突き詰めてヒアリングすることで表面化してきます。
これら2つの違いと引き出し方について、次より詳しく解説します。
顕在ニーズとは
「顕在ニーズ」とは先述した通り、「xxという課題を解決するものが欲しい」というように顧客が自分で気づいているニーズのことです。
顧客自身で今の課題をとらえており、それを解決していくためにどういうサービスが適しているかを自覚しているため、ニーズが表面化している状態です。
ニーズを自覚できていると、相手は「A」という課題に対して何をして解決すべきかが分かっているため、営業側は購買意欲の高い状態で商談にのぞむことができます。
例えば保険商品の場合、「結婚をしたので今まで以上に病気や死亡時に備えたい」というニーズがあったとしましょう。
この時に提案すべき商品は、がん保険や生命保険が該当しているのではないでしょうか。
顧客側の表面的なニーズに対して提案することができるため、顕在ニーズに対する営業活動や販売行為は比較的楽といえます。
また、ニーズが顕在化していればいるほど、顧客は課題解決の手段を積極的に探すので、顧客が購買行動を起こしやすくなります。
顕在ニーズがある顧客の集客は比較的簡単だといえるでしょう。
顕在ニーズの具体例
顕在ニーズは、インターネットの検索にもあらわれます。
たとえば「東京 おすすめ ランチ」と検索する人は、顕在的に「東京でおいしいランチを食べたい」と思っている人です。
このケースでは、ランチを食べる相手、もしくは自分自身で楽しむことは決まっているものの、具体的に「何を」食べるのかは決まっていない場合がほとんどでしょう。
そのため顕在ニーズは「東京でおいしいランチが食べられるお店を知りたい」と予想できます。
顕在ニーズを知ることが自社サイトの売り上げやアクセス向上にもつながりますが、ユーザーを満たすには潜在ニーズも探ることが大切です。
ユーザーが自覚していないような潜在ニーズも満たせれば、満足度はより高くなるでしょう。
潜在ニーズとは
「潜在ニーズ」とは、相手が潜在的に求めている欲求や求めているものに対して、自覚がない状態のことを意味しています。
潜在ニーズは欲しいものを意識できていない状態なので、仕事へ活かすには潜在ニーズの顕在化が欠かせません。
主にマーケティングの分野で使われていますが、潜在ニーズは営業にも応用できます。
営業においては、顧客の潜在ニーズを把握すれば、ヒット商品を生み出すだけでなく、営業成績もアップさせることが可能です。
マーケティングでは新規商品の開発のヒントなどに活かされますが、営業では主に新規顧客を開拓する際に役立ちます。
顧客の潜在ニーズをつかむことによって、強い見込みのある新規顧客を開拓できます。
潜在ニーズを掘り下げた結果、これまで目を向けなかったような分野に対してアプローチでき、それが成功につながったケースもあるのです。
潜在ニーズを把握できれば、顧客の真のニーズがわかるので、商談も有利に進めやすくなるでしょう。
おのずと営業成績が向上するため、企業の業績にも良い影響が出るはずです。
営業に活かせる顧客の潜在ニーズを呼び起こすには、相手に適切な質問を投げかけたり、相手の仕草などからも読み取ったりする必要があります。
潜在ニーズの具体例
潜在ニーズをより理解するために、次は具体例をチェックしていきましょう。
顧客の潜在ニーズを把握すると、課題解決をする手段の幅が広がり、相手により大きな価値を提供できます。
たとえば、「コーヒーが飲みたい」というニーズがあるとします。
このケースでは「なぜコーヒーが飲みたいのか?」と何度も振り返ることが大切です。
1つのニーズに対して答えがもう出ないところまで「なぜ」を追求することで、相手の本当に求めていることがクリアになります。
「なぜ」を繰り返し考えると、さまざまな理由のうち「眠気を飛ばしたいのかもしれない」などのニーズ予想が次第に浮かび上がってきます。
眠気を飛ばすためにコーヒーを求めているのであれば、コーヒー以外にも眠気を飛ばす手段はきっとあるはずです。
より思考を深めていくとコーヒー以外の「ガム」「休憩所」などの代替案が見つかるので、より相手が満足する可能性は高まるのです。
「眠気を飛ばしたい」というニーズであれば、コーヒーを提供するほかにもたくさんの選択肢があることを理解しておきましょう。
「コーヒーが飲みたい」を鵜呑みにしてしまうと、相手の本当に求めていることがわからなくなってしまうため、注意してください。
いかに相手の本来の欲求や目的を掘り下げ、課題解決の幅を広げられるかが肝心です。
【番外編】ニーズとウォンツの違い
潜在ニーズと顕在ニーズをより深く理解するには、「ニーズ」と「ウォンツ」についても確認しておきましょう。
ニーズとは目的、ウォンツとは具体的な手段のことを意味しています。
ウォンツはニーズを理解したうえで、さらに必要な要素なのです。
たとえばニーズは「のどがかわいている」、ウォンツは「水を飲みたい」という状態のことを指します。
人の欲求が満たされていない状態をニーズと呼び、ニーズに対する具体的な要望がウォンツだと考えられるでしょう。
ニーズだけでなくウォンツも理解し使い分けることによって、より顧客のニーズを効果的に把握できる可能性があります。
ニーズとウォンツの関係を正しく理解し、顧客満足度を向上させられるようにしましょう。
顕在ニーズ・潜在ニーズを引き出すにはインサイトも理解しよう
ニーズの説明をするうえで、「インサイト」についても理解しておく必要があります。
インサイトとは、顕在ニーズや潜在ニーズのさらに深くにある最も根本的な欲求のことです。
洞察や直感を意味するインサイトですが、本人も無意識のため見極めは簡単ではありません。
潜在ニーズとの区別も曖昧であり、インサイトを潜在ニーズと表現することもあります。
隠れた購買意欲を見極めることは、潜在ニーズ同様ビジネスやマーケティングでは必須です。
行動や思考を細かく観察し見極められます。
インサイトの具体例
例えば「おしゃれな服」を例に挙げてみましょう。
消費者はその服を着用することで、雰囲気が良くなり周りからの評価が高まることを期待しているとします。
異性にモテたり友達が増えたりすればニーズが満たされますよね。
しかし、実際はその成功体験を通して自分に自信を持ち可能性を信じたいと思っていたかもしれません。
人としての価値が高まり人生を楽しむことが根源的な欲求と考えられます。
これがインサイトにあたります。
ファッションを通して人生を変えたいということを見抜けば、アパレル店は魅力的な服の製作や販売に活かせます。
消費者の未来の姿を想像するとインサイトの見極めに近づけるでしょう。
潜在ニーズと合わせて引き出す方法を探ってみましょう。
【顕在ニーズとは】顧客のニーズを理解するメリットはある?
これまで潜在ニーズと顕在ニーズの違いや具体例をご覧になったことで、ある程度双方の概要や顧客の温度感が把握できたのではないでしょうか。
この2つのニーズを追求して理解を深めることで、より効果的な提案ができるようになります。
実際にこの2つのニーズをうまく理解することで、営業活動においてどのようなメリットが得られるのかをご紹介します。
顧客満足度が高まる
顕在ニーズだけでなく潜在ニーズまで理解して提案をすることで、顧客満足度が格段にアップします。
なぜなら、顧客が本来気づけていなかった課題を、営業側がうまく見つけてくれることでより効果的な解決策が見つかるからです。
ビジネスシーンにおいては良好な関係性を保つことが必須。
そのためには、普遍的な提案をする営業よりも、顧客に寄り添って課題解決に取り組んでくれる人が求められます。
顕在ニーズで聞いた情報をもとに、潜在ニーズまでうまく引き出せるようになれれば、問題の解決策にプラスアルファの提案ができるため、より効果的な解決策を導き出せるようになります。
顧客が想像していた以上の良い提案ができるようになれば、顧客満足度が上がりあなたへの信頼度も高まるでしょう。
顧客から信頼されるパートナーになれる
顕在ニーズと潜在ニーズを理解した上で上手な提案ができる人は顧客から信頼されやすく、BtoBの分野において重宝されます。
法人を相手とする営業職やコンサルティング職は、顧客側の企業が抱える課題に対する解決策としてプロダクトを提案しています。
経営課題に直結する課題なので、効果が見込める提案でないと導入にはいたらないでしょう。
しかし、顕在ニーズから潜在ニーズをうまく引き出した上で課題をとらえれば、相手が求めているもの以外の解決策が見つかり、より効果的な提案ができるようになります。
顧客側が想定していたこと以上に良い提案ができるようになれば、顧客はあなたを信頼してくれて、ただの営業ではなく「パートナー」としてみてくれるでしょう。
売り上げの向上につながる
3つ目のメリットは「売り上げの向上につながること」です。
お客様の信頼を勝ち取り満足度が高まれば、商品やサービスへの投資が期待できます。
口コミやメディアでの拡散がされれば、新規顧客の獲得も難しくはないでしょう。
お客様が増えることで、単純な売り上げが向上します。
利益が出ればより良い商品の開発や社員への還元など良い循環が見込めますよね。
ニーズを理解しなければ売り上げや利益の向上は実現しません。
長期的なビジネスを行うためにもニーズの理解は必須といえます。
顧客に合わせた営業ができる
4つ目のメリットは「顧客に合わせた営業ができること」です。
ニーズの理解は、営業活動でも大いに役立ちます。
営業の基本は、ただ商品を勧めるだけではなく、お客様の課題や悩みを先に聞き出し最適解を提案してお客様に主体的に選択してもらうことです。
最適解を提示するためには、顕在ニーズだけでなく潜在ニーズやインサイトなど根本的なニーズを理解する必要があります。
ニーズが引き出せれば、お客様を満足させられるような営業につながりますよね。
契約が取れればお互いにwin-winです。
ノルマ達成のために数をこなすことも重要ですが、一回一回お客様にきちんと寄り添うことが求められます。
潜在ニーズの引き出し方
どの業界のトップ営業マンでも共通していることが、潜在ニーズの引き出し方が上手であるということです。
先述した通り、顧客満足度を高め信頼を得るには、相手が想定している以上の提案をしなければなりません。
そのためには、顕在的なニーズだけではなく、その先を深掘りした潜在ニーズが鍵となります。
ここからご紹介するのは、潜在ニーズを上手に引き出す3つのコツです。
主に商談のシーンで活用できることなので、ぜひチェックして明日からの商談に備えましょう。
相手の仕草から読み取る
人の欲求や心理は、行動に直接影響します。
したがって「相手の仕草から読み取る」方法は効果的です。
話しているときの様子や普段の行動などをよく観察することで、その人が何を求めて動いているのか判断できます。
自覚していないこともあるため、細かいところにまで目を配ることがポイントです。
例えば話していてそっけない人がいるとします。
表面的には、話したくない・目を合わせたくないと感じているはずです。
ところが深掘りすると、恥ずかしがり屋で自信がないためにあまり発言したくないと感じていると考えられます。
顔を赤らめていたり、声のバランスに違和感を感じるならばその可能性が高いでしょう。
褒めたり肯定したりすることで、相手のニーズを満たしてあげられますよね。
行動の観察はニーズの引き出しには手っ取り早い方法といえます。
相手にとって効果的な質問を投げかける
顕在ニーズに対して相手にとって効果的な質問を投げかけることも、潜在ニーズを引き出すことに役立ちます。
質問を繰り返すことで相手の潜在ニーズを直接引き出すことが可能です。
例えば営業では、お客様に現在の悩みや使用状況などを詳しく質問しますよね。
高圧的な質問や関係のない質問はNGですが、相手の話をうまく引き出すような質問を繰り返すことで本人も気づかないうちに本音を打ち明けるでしょう。
引き出した潜在ニーズに合うサービスや商品が提案できれば、契約が取れる確率も高まります。
また質問を工夫し相手の回答を誘導するという方法もあります。
返ってくる答えを聞き、潜在ニーズを見極めましょう。
商談でNGな質問例
潜在ニーズを引き出すときに注意したいのが、深掘りしようとしすぎて直球で失礼な質問をしてしまうことです。
下記のような聞き方の質問は避けましょう。
- 誘導尋問に近い聞き方(最終的に営業側が提案したい商品の話に持っていくような流れの会話)
- 予算に関する直球すぎる質問(プランと料金の話の前にしてしまうのは失礼)
- オープンクエスチョンが多すぎる(「はい」「いいえ」で回答できるクローズドクエスチョンが多い方が、相手が楽)
商談での質問内容はあらかじめメモをした上でヒアリングする人も多いと思いますが、会話の脈絡を無視して質問攻めしてしまうのもNGです。
あくまで、商談の本筋に沿って「会話のキャッチボール」をすることは前提として進めましょう。
相手の回答に対してさらに深掘りして質問する
商談で上手に会話のキャッチボールをするには、相手の回答に対して深掘りするような質問を投げかけるのが大切です。
例えば求人に関する商談の場だとすると、基本的に「採用したい」というのが顕在ニーズ。
これに対して、「なぜ」を深掘りしながらヒアリングしていくと、潜在ニーズに辿り着きます。
「パートさんを採用したい」という顕在ニーズに対し、まずは何名くらい採用するのが良いのかを聞きます。
その上で、なぜその人数が必要なのかもヒアリングすると、どういう人をターゲットに採用すればうまくいくのかまでわかるようになります。
そうして最終的には「こういう年齢層の人を、何名、いつまでに採用する」というプランを立てた上で効果的な提案ができるようになるのです。
商談で顕在・潜在ニーズを上手に引き出すコツ
抱えている案件の成約確度を上げるためには、商談でキャッチしたニーズの数と質の良さが良いことが大前提です。
そのためには、商談前の事前準備から徹底して顕在ニーズと潜在ニーズを引き出せるようになりましょう。
これからご紹介するのは、商談の質を上げるための事前準備とニーズを上手に引き出すコツです。
基本的なことですが、トップ営業のほとんどはこのプロセスが完璧なので、ぜひチェックしておきましょう。
仮説だてをする
商談前に準備しておきたいことが、「相手が何を求めていそうか?」という仮説です。
顕在的なニーズはある程度わかっているはずなので、そこから具体的エピソードを想定して、何を提案したら良いか?どういうヒアリングをしたら潜在的な回答が得られるかを準備しておきましょう。
仮説だてをせずにいきなり商談にのぞむのはNGです。
ある質の良い会話が飛び交う商談にするために、相手の市場や置かれた状況も確認しながら、そこから想定されるニーズと提案内容をパターン化しておきましょう。
商談でのヒアリング事項を用意する
仮説立てをしたら、次はその仮説にあったヒアリング事項を用意しましょう。
相手の顕在ニーズに対して、まずはなぜそのニーズがあるのかを回答してもらえる内容を用意します。
そして次は、仮説立てをしたことに対してあっているか確認できる質問を用意しておきましょう。
なお、ここで気をつけておきたいのが、質問の方向性が雑多になりすぎるということです。
方向性の違う質問がたくさん飛んでくると、相手は不快になります。
質問したい事項にも優先順位をつけて、慎重にヒアリングを進めましょう。
相手に合わせた資料を準備する
想定された課題に対して適切な情報を提供するためには、相手に合わせた資料を準備しましょう。
仮説だてはいくつかしておく必要があるので、それぞれに合わせた提案ができるよう、プランは複数パターン用意しておくのがベターです。
なお、資料作成に時間を取られてしまうと効率的とはいえませんので、あくまで提案内容についてはシンプルにまとめましょう。
テストクロージングをする
テストクロージングは、最終的な決断を促すクロージングの前に、テスト的にクロージングをすることです。
例えば顧客が検討段階の状況で、「今回ご提案しているxxの内容です、御社としては率直にどうお感じでしょうか」という確認をするのが、テストクロージングです。
クロージング前にこのような会話をすることで、案件の受注確度をある程度把握することができますし、相手が懸念に思っていることを引き出すきっかけにもなります。
自分が提案しているプランに懸念点があればクロージング前に軌道修正ができるため、失注を避けることもできます。
(受注確度が低ければ)再商談の設定
商談時に受注確度が低いと感じた場合、ヒアリングした懸念点を払拭したプランを再提案するために、改めて商談を設定しましょう。
再商談をすることで、前回失敗した提案のどこが悪かったかを理解した上で、より効果的なプランを提案することができるようになります。
なお、再商談を設定する際はできるだけ期間を空けないことがおすすめです。
あまりにも期間を空けすぎてしまうと、その間にライバル企業にリプレイスされてしまう可能性もありますし、そもそも顧客の温度感もどんどん下がってしまいます。
もちろん顧客側のスケジュールに合わせることが前提ですが、可能なら1週間以内の再設定をおすすめします。
まとめ
営業の仕事をしていると、顕在ニーズは簡単に引き出せることがわかるのではないでしょうか。
しかし、トップ営業になるために大切なことは、顕在ニーズから潜在ニーズを引き出すことです。
潜在ニーズが分かれば相手の本質的な課題をとらえた上で効果的な提案ができるようになります。
相手が気づけなかった視点で効果的な提案をすることで信頼度が上がり、商談での受注率も格段に向上するでしょう。
商談での受注率に悩んでいる営業職の皆さんは、ぜひ今回ご紹介したコツを参考に、商談の質を上げる取り組みを検討してみてください。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!