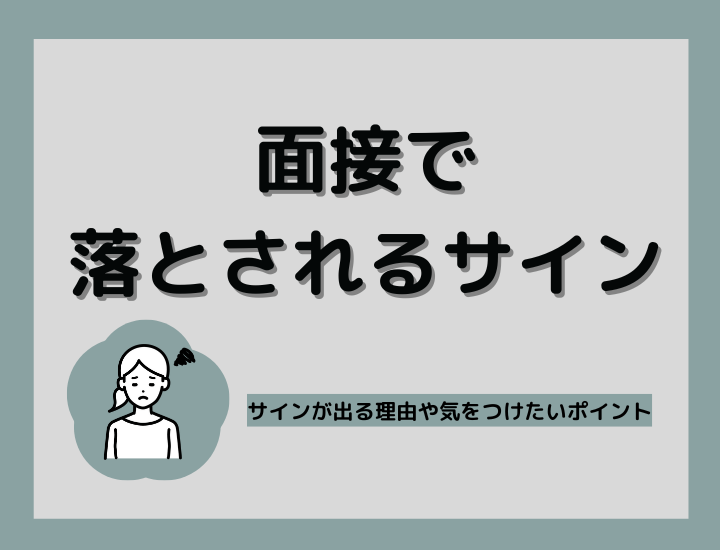第二新卒でもOB訪問は必要?メリットや聞くべき質問を解説
- はじめに
- 【第二新卒がOB訪問するメリット】OB訪問とは
- 【第二新卒がOB訪問するメリット】第二新卒がOB訪問するメリット
- 【第二新卒がOB訪問するメリット】OBOG訪問の前に準備すべきこと
- 【第二新卒がOB訪問するメリット】第二新卒が就職を有利に進めるために必要なこと
- 【第二新卒がOB訪問するメリット】第二新卒として就職するメリット
- 【第二新卒がOB訪問するメリット】第二新卒は企業にとって採用するメリットが大きい
- 【第二新卒がOB訪問するメリット】OGOB訪問でおすすめの質問例
- 【第二新卒がOB訪問するメリット】OBOG訪問の際に気をつける点
- 【第二新卒がOB訪問するメリット】OBOG訪問ってどれくらいするべき?
- まとめ
はじめに
OB訪問は、就職したい会社へ行き、実際に働いている社員の話を聞ける貴重な機会です。
説明会や面接では本当の会社の雰囲気はわかりづらく、入社してからのギャップで早期退職してしまうことも珍しくはありません。
就活の時期には多くの学生が取り組むOB訪問ですが、一度就職して3年以内に退職した第二新卒には必要ないと考えていないでしょうか。
実際には、第二新卒にとってもOB訪問は重要と言えます。
この記事では、第二新卒がOB訪問するメリットや、聞くべき質問を解説します。
第二新卒として就活をしている方は参考にしてみてください。
【第二新卒がOB訪問するメリット】OB訪問とは
OBOG訪問をする目的は、明確にしておきましょう。
近年はインターネットからでもターゲットとする企業の情報は簡単に入手できます。
しかし公式サイトやプレスリリースの発信情報から知り得る情報には限りがあります。
ネットの情報源から自分ではわかっているつもりでも、OBOG訪問でターゲットとする企業で実際に活躍している社会人の話を聞けば新たな発見があるはずです。
就活で差をつけるために目的をしっかりともち、OBOG訪問はなるべくしましょう。
就活の進め方を知るため
OBOG訪問をする目的の1つは就活の進め方を知るために、実際に就労しているOBやをOG訪ねて話を聞くことです。
実際に話を聞いて、志望動機を具体的なものにできるのがOBOG訪問のメリットでもあります。
話を聞いたうえで練られた志望動機は、説得力や具体性が加わることはいうまでもありません。
就活の進め方がわかれば、自己PRの方向性を決められるでしょう。
どんなに優秀は自己PRであったとしても、企業が求める人材とマッチしていなければ採用には至りません。
OBOG訪問で実際に「どんな人材が求められているか」などという話を聞けば、就活の方向性を定められます。
業界や職種について理解を深めるため
業界や職種について理解を深めるためにOBOG訪問をします。
実際にターゲットとする企業で働くOBらから生の話を聞けば、業界や企業を知ることができるのです。
また、先輩の仕事に対しての価値観を知ることができます。
それはターゲットとする業界や職種について理解を深めるルートの1つでもあります。
またOBOG訪問は少人数もしくは1対1で対話ができるので、説明会よりもリラックスした雰囲気で質問できることも魅力です。
たとえば説明会などでも事業内容や企業力などを知ることは可能です。
しかし、仕事内容や1日の流れについては、OBOG訪問のような少人数でリラックスしながら質問できる場所でなければ、なかなか知ることのできない内容でしょう。
企業の実態を確かめるため
OBOG訪問は実際にターゲットとする企業で働く先輩の生きた情報を入手できるので、その企業の実態を確かめることも可能です。
- 企業の文化
- 評価指標
- 働き方
- 就労者の人柄 など
これらの詳細は、インターネットなどではなかなか調べられません。
近年、あこがれて入社した企業であっても、いざ仕事が始まると人間関係のトラブルや、入社前に想像していた働き方との相違で退職していく人もいます。
そのような問題を回避し、実体を確かめるために、すでに就労している先輩に実情を聞けるOBOG訪問がおすすめなのです。
ターゲットとする企業の実態を確かめれば、自分の目指す企業がどの程度自分とマッチしているかを見極めるステップにもなるわけです。
働き方について知るため
働きたい業界や、実際にやってみたい仕事が決まっていない場合は、働き方から志望企業や業界を決めていくと良いでしょう。
「若いうちにたくさん働いて実力をつけたい」「ワークライフバランスを大切にしたい」「産休・育休を取得した後は、職場に復帰して仕事をしたいなど」、人によって理想とする働き方や譲れないポイントがあると思います。
先輩の働き方やライフスタイルを知ることで、自分にとって合っている企業や働き方が見えてくるかもしれません。
【第二新卒がOB訪問するメリット】第二新卒がOB訪問するメリット
第二新卒であっても、基本的にはOB訪問をしたほうがよいと言えます。
一部の企業ではOB訪問が選考に含まれているところもありますが、そうでなかったとしても自主的に行うメリットは多いため、詳しく解説していきます。
新卒のときとは違った見方ができる
第二新卒の強みは、一度就職しているということです。
当然ですが、新卒は初めての就職ということもあり、OB訪問しても視野が狭いことがほとんどです。
例えば、働いている先輩社員との話だけに夢中になってしまい、会社全体を見渡せていないことが多いでしょう。
働いているのはOBの数人だけではなく、他の学校卒業者や中途採用など、さまざまな社員がいます。
一度就職している第二新卒は、こういった別の視点で見ることができるようになっていることがポイントです。
新卒のときと同じようにOB訪問するのではなく、会社の見るべきポイントを理解していることは大きなメリットになるでしょう。
会社の雰囲気がわかりやすい
OB訪問一番のメリットは、会社の雰囲気がわかりやすいということです。
会社の説明会や面接は、実際に働いている場所を見られるわけではありません。
特に大手企業であれば、面接会場すら会社以外の場所ということもあります。
こうなると、会社の雰囲気は面接官からしかわからず、実際には全く違った人が多いという可能性も少なくありません。
OB訪問では実際に会社に訪れて働いている場所を見られることから、雰囲気がわかりやすくなります。
「どういった人が多いのか」「自分が馴染めそうな会社なのか」といった部分が見えやすくなるでしょう。
これは新卒も同じですが、第二新卒は一度就職しているからこそ、退職の原因になった部分に目を向けることも可能です。
就職が有利になる
OB訪問すると必ず選考に通過しやすくなるとは言えません。
しかし、就職が有利になる可能性は十分にあります。
もしOBが人事部でなかったとしても、面接を受ける第二新卒者がどのような人物なのかは、OBに質問します。
このとき、OBの評価が高ければ、人事部にも良い印象を与えられる可能性は高いです。
当然ですが、OBに悪い印象を与えてしまった場合には、就職で不利になると考えてください。
あまりにも的外れな質問ばかりをしたり、仕事とは関係のない話ばかりしていては、良い印象にはならないでしょう。
特に第二新卒は早期退職していることから、退職理由によっては面接官に悪い印象を与えかねません。
OB訪問でこの辺りをクリアにできていれば、選考が有利に進む可能性は高くなります。
自己PRが書きやすくなる
就職活動で多くの方がつまずくのが自己PRです。
基本的には学生時代に取り組んだ部活やサークル、ボランティア、アルバイトの経験を盛り込みます。
しかし、こういった経験と応募先企業の業務内容を繋ぐことは意外と難しいものです。
そこで、OB訪問した際に社員の生の声を聞ければ、自分の経験をどのように活かせるかが明確になってきます。
また、自己PRだけではなく、志望動機もより現実的なものになります。
「なぜこの企業で働きたいのか」が明確になれば、相手にも熱意が伝わりやすくなり、採用の可能性は高まるでしょう。
社員の自然な反応が見れる
OB訪問では、説明会や面接では見られないような、社員の自然な反応が見られる可能性があります。
会社の説明会では人事が近くにいることから、社員は自然な話ができず、余計なことを言わないようにセーブしていることがほとんどです。
つまり、本音では話していないことが多く、自然な姿とは言えません。
一方、OB訪問では自分の部署や休憩室など、人事の目を気にすることなく話せるため、より自然な言葉が出てきます。
デリカシーのない質問はよくありませんが、今回の就職でどうしてもクリアにしておきたい内容は聞きやすいでしょう。
例えば、以前の職場で残業が多く退職してしまったのであれば、それとなく残業時間について聞いてみるのもよいかもしれません。
あくまでストレートに聞くのではなく、「繁忙期などは皆さんが協力して遅くまで努力されているのですか」といったように、「残業したくない」と捉えられないような聞き方をしてみてください。
【第二新卒がOB訪問するメリット】OBOG訪問の前に準備すべきこと
実際にOBOG訪問する場合、そこで何について知りたいのか、何を聞きたいのかを準備しておきましょう。
せっかくターゲットとなる企業で実際に働いているOBやOGから話が聞けるわけです。
そんな貴重な時間を無駄にしないためにも、調べてわかる内容ではない質問を準備しておけば、就活がスムーズになります。
就活全体に関する有益な情報を得られるかもしれないチャンスなので、質問のポイントを押さえて訪問しましょう。
企業や業界のことを自分なりに調べる
OBOG訪問前には、自分で調べられる範囲のターゲットとなる企業や業界のことは自分なりに調べておきましょう。
自分で調べてわかるような質問では訪問した意味がありません。
生の声からしか聴けない内容とは、たとえば以下のことがあげられます。
- 仕事の詳しい内容
- その企業のリアルな実態
- 実際の残業時間や有休などのプライベートな問題や働き方
実際就職した際に知っておきたい内容を質問するために、その下準備では自分で調べられることは調べておいてください。
たとえば先輩が入社した動機を質問してみるのも、企業探しの参考にしたり、企業を理解したりすることにもつながります。
口コミなども事前に調べておくとよいでしょう。
わからない部分を具体化する
OBOG訪問前にはわからない部分について具体的な質問を考えておきましょう。
アバウトな質問だとアバウトな回答しか得られません。
たとえば「御社はどのような社風ですか?」という漠然とした質問は効果的とはいえないでしょう。
「御社の社風として掲げられている「挑戦し続ける精神」は具体的にどのように活かせていますか?」という質問に変えてみると、より具体性のある回答が得られます。
せっかくそこで就労している人の率直な意見が聞ける機会を無駄にはできません。
実際に調べてみても、わからない部分はたくさんあります。
思いついた質問は実際言葉に出してみると、アバウトな内容である場合があります。
質問は紙に書き出し、実際に口に出してみるとよいでしょう。
【第二新卒がOB訪問するメリット】第二新卒が就職を有利に進めるために必要なこと
第二新卒は、「就職が不利になる」と言われることも少なくはありません。
たしかに、人によっては「早期退職した続かない人」というイメージで見ることもあります。
しかし、しっかりとポイントを押さえておけば、第二新卒だから不利ということにはなりません。
第二新卒が就職を有利に進めるために必要なことを解説します。
退職理由を明確にする
まずは、退職理由を明確にすることです。
第二新卒の定義としては、新卒から3年以内に辞めたというのが基本と言われています。
世間一般的に3年以内は早期退職と考えられることが多く、「すぐに辞める人材」と捉えられることも少なくはありません。
そこで重要なのは、退職理由です。
「嫌だったから」「自分には合わなかったから」という理由は身勝手で子供っぽいことから、面接で伝えれば不採用になる可能性が高まります。
重要なのは、退職理由を明確にしてポジティブに変換すること、「辞めるしかなかった」と周りに感じさせることです。
例えば、残業時間が長くて退職した場合には、「自分のスキルを磨くための時間が取れなくなってしまった」といった伝え方をします。
向上心があるのに、以前の会社では物理的に制約されてしまったといった内容であれば、悪い退職とは考えられません。
また、今回応募している企業の業種に興味が向き、早期退職してでも転職したかったといった理由もよいでしょう。
退職理由を明確にすることで、早期退職する可能性を下げることもできます。
自分がなぜ退職したのかを考えなければ、次の会社でも同じことが起きるかもしれません。
自己分析と企業分析をする
続いて、自己分析と企業分析をすることです。
そもそも、自分がどのような仕事をしたいのか、どのような働き方をしたいのかを考えたことはあるでしょうか。
「給与が高い」「休みが多い」「待遇面が良い」「仕事内容が好き」など、仕事を選ぶ基準は人それぞれです。
しかし、こういった自己分析をせずになんとなく就職してしまうと、また退職に繋がる可能性があります。
まずは自分がどのような働き方がしたいのかを明確にすることで、入社してからのギャップを減らすべきです。
また、企業分析もしっかりと行いましょう。
仕事内容や企業理念など、共感できなければ長く続けることは難しいかもしれません。
求人内容をみるだけではなく、会社のホームページや口コミサイトを見るだけでも企業分析は可能です。
自己分析と企業分析をしておけば、ミスマッチを防げるため、長く働ける企業に就職しやすくなります。
自己PRを充実させる
第二新卒は新卒とは違い、社会人スキルを身につけていることが強みです。
多くの会社では、新卒社員に対してビジネスマナーを含めた研修を実施します。
こういった研修を受けていれば、次の会社は新入社員研修を受けさせる必要はありません。
研修は担当の社員を準備しプログラムを作成するなど、会社にとってはマイナスになることの多い内容です。
第二新卒であれば、基本的な研修を終了しているからこそ、会社に余分な労力を発生させません。
こういった部分を自己PRに含めておけば、企業側としては採用しやすくなるでしょう。
ただし、1年以上は働いていなければ、ビジネスマナーを身につけているとは考えにくいかもしれません。
あくまで、社会人として一定期間働いていることが基本とはなりますが、身につけているスキルやビジネスマナーを自己PRに含めれば、採用率を高められます。
【第二新卒がOB訪問するメリット】第二新卒として就職するメリット
自分が第二新卒ということで負い目を感じる人は少なくありません。
しかし、第二新卒として就職することには、実は大きなメリットがいくつかあります。
新卒で就職できなかった企業にチャレンジできる
新卒のとき、就職したくても条件を満たせずに諦めた企業はないでしょうか。
例えば、学歴や学部、業務に関わる経験などです。
同業種で数年働いたのであれば、新卒のときに希望していた企業へ就職できるかもしれません。
例えば、第二新卒枠ではなく中途採用枠を利用する方法もあります。
新卒と中途採用では条件が異なり、学歴や学部がそこまで厳しくないことも珍しくはありません。
代わりに同じ業界の実務経験があれば、入社しやすくなるでしょう。
第二新卒は経験を積んだからこそ挑戦できる企業が増えるのもメリットです。
新卒の経験を活かせる
第二新卒は一度就職活動をしているため、失敗したことや成功したことを活かせるのもメリットです。
例えば、新卒のときにエントリーした数が少なかったのであれば増やしてみる、企業分析をしなかったのであればしてみるとよいでしょう。
反対に、新卒のとき上手くいったことがあれば、今回も同様に利用すべきです。
第二新卒は一度新卒として就職活動をしているからこそ、その経験を最大限活かすべきといえます。
自分の就きたい仕事が明確になっている
一度就職したことで、「やりたい仕事ではなかった」と感じた方も多いのではないでしょうか。
やりたい仕事と違ったことで退職したということは、決して悪いことではありません。
次はその業種を外し、新たに自分のやりたい仕事を考えられます。
特に、やりたい仕事に気づいて退職したのであれば、今度はその業種に絞って就職活動するだけです。
【第二新卒がOB訪問するメリット】第二新卒は企業にとって採用するメリットが大きい
第二新卒は、早期退職していることで就職が難しいと考えている方が多いはずです。
確かに、退職理由が明確ではなかったり、早すぎる退職はデメリットになります。
しかし、企業側から見ると、第二新卒は採用するメリットの多い人材です。
いくつかその理由を解説します。
社会人経験がある
少し前述していますが、第二新卒ということは少なからず社会人経験があるということです。
社内研修やビジネスマナー研修を受けていることが多く、新たに採用する企業としては、これらの研修を省ける可能性があります。
研修も会社にとっては負担があり、会場や資料の準備だけではなく、研修を担当する社員はその間は他の業務ができません。
先を見据えて取り組むことであり、これを不利益と考えるわけではないものの、実施しなくてよいのであれば会社の利益は大きくなると言えるでしょう。
前職に染まっていない
働いていた期間が長いほど、仕事の仕方が固まってしまい、新しい職場では馴染みにくいものです。
第二新卒であれば、まだ前職で凝り固まっていないことから、教えやすいと考える会社は多くあります。
加えて、社会人としての基本が身についていることから、ちょうど良い人材とも考えられます。
同じ会社で10年働いていた人材よりも、若く柔軟性のある第二新卒を採用するメリットは、企業側にとって大きいと言えるでしょう。
人材不足の影響
業界によっては人材不足になっており、求人を出しても応募すらこないということも珍しくはありません。
特に、インターンシップを実施している企業が早期選考で人材を確保していることも多く、新卒を採用できないことがあります。
こういった背景から、新卒にこだわらず第二新卒を含めた採用に取り組んでいる企業が増えてきています。
企業側にとっても採用するメリットが高まっていることから、第二新卒が就職しにくいということはないと考えられます。
【第二新卒がOB訪問するメリット】OGOB訪問でおすすめの質問例
ここからはOBOG訪問で具体的なおすすめの質問例を紹介していきます。
ある程度ターゲットが絞られている就活者に役立つ「業種や職種を理解したいときの質問」
訪問先の企業を志望している就活者に役立つ「企業の実態を確かめたいときの質問」
上記3つのカテゴリーに分けて解説します。
それぞれ3選ずつ質問例をあげました。
OBOG訪問する前の質問選びの参考にしてください。
就活相談をしたいときの質問3選
まず就活初期の就活者がOBOG訪問で質問するとよい例をあげました。
就活初期は、就活の進め方に関した質問を用意するのがおすすめです。
ここで質問した返答が、就活全体の参考となる情報になる場合もあります。
OBやOGたちがどんな就活をしていたかとか、就活時にやるべきことは何かという内容は、これから始める就活の進め方の指針となることでしょう。
同時に志望動機を聞くことは業界選びや企業選びの参考にもなります。
なぜその企業に入社を決めたのか
志望動機を聞けば、その人の仕事の軸や大切にしていることがわかります。
この質問についての返答は業種選びや企業選びの参考になります。
先輩の志望動機を知ることは、その企業の魅力を理解する手がかりの1つです。
数ある企業の中でその企業を選んだ理由は、ほかの企業と比較するときの参考にもなります。
志望動機に共感できるかどうかでその企業と自分の相性を知ることができ、志望先の選択に役立つことでしょう。
ほかにどんな業界を見ていたのか
就活初期であるなら、OBOG訪問で先輩に「就活ではほかにどんな業界を見てきたか」という質問をしてみるとこれからの就活に役立つ情報となります。
ただし何でも教えて欲しいという態度で質問するのはよくありません。
自分で考えず人に頼ってばかりだという印象を与えてしまう場合があるからです。
まず「御社以外にこんな業界も参考にしているが、先輩方は就活ではどんな業界を見てこの仕事を選んだのか」というように質問を具体化しましょう。
就活時にしておくべきだったこと・しておいてよかったことは何か
就活時にしておくべきことやしておいてよかったことを質問してみるのもよいでしょう。
この質問も内容次第ですが、この質問も質問の次第では、自分で調べず何でも教えて欲しいという態度に取られてしまう場合があります。
「ネットや説明会などで事業内容や企業力は知り得るけれど、業種や企業選びをするにあたって何かほかにしておくことはあるか」などとこれも具体的に質問することが重要です。
業種や職種を理解したいときの質問3選
ここからの質問例3選は、ある程度ターゲットの決まっている就活生がOBOG訪問する際におすすめの質問事項です。
業種や職種を理解するための質問は、就活生にとって仕事のやりがいへの回答につながります。
その仕事のやりがいや魅力を聞けば、業種や職種の理解を深めることが可能です。
同時に質問の内容に共感できれば、自分がその仕事に求めるものとの距離感がわかり、就活の方向性を決めるときの参考にできます。
企業や業界のこれからについてどう考えているか
実際の社員が考える企業や業界の将来像は、就活を進めるうえで知りたい内容です。
どんなに理想とする企業であっても、実際に就労している先輩が将来性に乏しいなどといえば志望先の変更も考えなければなりません。
OBやOGの方に向けて失礼な質問にならないように、「こんな事実からこんな風に思っている」と自分の仮説も訴えたうえで質問するとよいでしょう。
このような聞き方であれば、働く人ならではの観点に気づきやすく失礼な質問にもなりません。
仕事のうえで一番困難だった経験は何か
理想ばかりで仕事は続けられません。
仕事の大変な部分を聞けば、あこがれやイメージだけの就活から1歩ステップアップできます。
結果を出すためには努力や苦労はつきものです。
「一番困難だった経験から得られた達成感ややりがいとは何か」などと質問を掘り下げてみるとよいでしょう。
一日の仕事の流れについて
1日の仕事の流れがわかれば、仕事内容をより具体的にイメージできます。
具体的にどう仕事を進めていくかや、働き方(ワークライフバランス)のような部分も確かめられます。
現在の仕事内容だけでなく、新入社員だった頃からどのように仕事が変わっていくかなど具体的な内容を質問してみましょう。
これは入社後のイメージにもつながります。
- 繁忙期はいつか
- 仕事をスムーズに進めるコツ
- 業務に課せられる目標
- 話題に出る仕事の具体的な中身
こんな流れを聞いておくと仕事のイメージがしやすくなり、志望動機や自己PRにも役立ちます。
企業の実態を確かめたいときの質問8選
次の8選は、ある程度ターゲットの絞れている就活者がOBOG訪問する際におすすめしたい質問事項の例です。
訪問先の企業を志望している場合は、その企業をより一層に理解したいものです。
実態を把握できれば、自分がその企業のニーズにマッチしているか自己判断ができます。
企業の実態を確かめる場合は「少し質問しづらい内容でもありますが」などと前置きをして質問しましょう。
面接よりも和やかな雰囲気で質問できるOBOG訪問の場で情報を得ておきましょう。
企業の理念は実際の業務にどう活きているか
企業の実態を確かめたい場合に「企業の理念は実際の業務にどう活きているか」などという質問をするのもおすすめです。
理念の浸透度や社員の働くことに対する意識がわかります。
深い質問ですが、企業の理念はネットからでも探ることはできます。
しかし、その理念が実際に業務でどのように活きているかはOBOG訪問でしか情報が得られません。
ここから得られる回答は、自分がその企業のニーズに合った人材であるかどうか知り得る情報でもあります。
入社後にギャップを感じた部分はあるか
OBOG訪問では、説明会で聞けないネガティブな部分や、それをどう捉えているのかを質問できます。
たとえば大手人材派遣会社マンパワーの調査では、早期離職の理由に「入社してからギャップを感じた」という理由があがっています。
入社前に聞いておけばよかったギャップとは、残業や職場の人間関係などを含めた問題です。
企業にとってはデメリットにもなる質問ですが、入社後に抱くギャップをどう捉えるかという情報は入社前に聞いておきたい情報です。
どんな人が活躍しているのか
その企業でどんな人が活躍しているかわかれば、その企業で自分が活躍できるかどうか判断できます。
これは企業の評価制度や評価の指標がきちんとしているかも確かめられるので、OBOG訪問で聞いておきたい質問です。
回答では「英語力の優れた人」や「コミュニケーションのうまい人」などという回答がくる場合もあります。
そのような回答では、活躍するために必要なスキルや素質を知れるわけです。
仕事のやりがい
企業や職種を選ぶ際に、やりがいを重要視する就活生は多いと思います。
しかし、仕事のやりがいは、実際に業務を行わないとなかなかわからないものです。
OBやOGに質問することで、具体的なやりがいを知り、自分が働く姿をイメージできます。
また、やりがいについて尋ねることは、仕事の解像度が上がることにもつながり、業務への理解度も高まるようになります。
事前に作る質問リストの中に、ぜひ「仕事のやりがいは何ですか?」という質問を入れるようにしてください。
残業はどのくらいあるのか
「社会人になっても勉強の時間を確保したい」「趣味を充実させたい」と考える就活生にとって、残業時間は気になるポイントです。
残業時間について知ることで、社会人になってからの生活スタイルや、時間の使い方のイメージがしやすくなります。
また、先輩方の業務終了後や休日の過ごし方について質問すると、より入社後の生活が想像できるようになるでしょう。
今後の人生を豊かなものにするためにも、ワークライフバランスを重視する会社かどうか確認することは非常に大切です。
この会社に入ってよかったと思った瞬間
仕事や会社の魅力は、就活を進めるうえで非常に重要な情報となります。
たとえば、「仕事のやりがいが大きい」「多くの人に影響を与えることができる」という話を聞いたとします。
この場合、OBやOGに教えてもらったその仕事や会社の魅力を、OB・OG訪問をしたことも含めてESの志望動機に書くと、高評価につながるでしょう。
また、会社や仕事の魅力は就活のモチベーションアップにもつながるので、OB・OG訪問当日は「実際に入ってよかったと思った瞬間はありますか?」と聞いてみてください。
面接の際のアドバイス
面接は、内定を獲得するために避けては通れない重要なフェーズです。
ですので、面接官の特徴や面接時間・内容について質問してみましょう。
たとえば、ほとんどの企業では、基本的に1次面接は現場の社員が面接官となります。
しかし、最終面接ともなると、役員・社長といった方々が面接をします。
面接が進めば進むほど、事前に準備する内容が変わるほか、難易度も上がることがほとんどです。
OBやOGから面接で質問された内容や見られていたポイントなどを聞き、きちんと対策していきましょう。
会社の人間関係について
会社の人間関係は、説明会で配布された資料だけではなかなかわからない点です。
また、インターネット上の情報では、企業の雰囲気はイメージや偏見で語られることが多く、鵜呑みにするのは危険です。
体育会系な雰囲気や、ビジネスライクな関係など、企業や部署によって人間関係は様変わりします。
このようなことを知ることで、入社する前に自分にとって働きやすい職場かどうか確認することができます。
会社の人間関係について聞くことは、早期離職を防ぐことにもつながりますので、可能な範囲で聞いておくようにしてください。
【第二新卒がOB訪問するメリット】OBOG訪問の際に気をつける点
OB訪問やOG訪問で気をつける点は、主に3つあります。
1つ目は、相手に合わせて質問内容を変えることです。
たとえば、入社数年以内の若手社員の場合、ESの書き方や面接で意識した点など、選考に関する質問が良いかもしれません。
一方で、入社20年以上のベテラン社員には、キャリアプランや業界の動向といった、長く勤めないと見えてこない内容について質問してみてください。
2つ目は、企業のホームページや説明会でわかるような質問を極力控えることです。
忙しい中で会ってもらっているのですから、インターネットや四季報ではわからないようなことを聞き、選考に活かしましょう。
3つ目は、時間を守ることです。
相手は、毎日懸命に仕事に励む社会人です。
遅刻をすると印象は悪くなり、場合によっては中止になってしまう可能性もあるので、時間厳守で行動しましょう。
【第二新卒がOB訪問するメリット】OBOG訪問ってどれくらいするべき?
質問の内容も理解したところで、実際にOBOG訪問してみましょう。
一般的な回数は1~5回ほどといわれます。
次に6~10回という訪問回数も多いという就職サイトの調査結果もあります。
就活者の納得度によって違いはあることでしょうが、回数を重ねても無駄な場合もあるのです。
ではどのくらいの回数を基準にすればよいか、また理想の回数はどれくらいなのか調べてみました。
「自分の疑問が解消されたか」を基準にしよう
OBOG訪問をどれくらいするべきか、その決まりはありません。
自分が納得して、就職先が決められるかどうかを目安に回数を決めるとよいでしょう。
疑問や悩みが生じたらまた追加でOBOG訪問をすればよいのです。
回数に決まりはありません。
収集したい情報量が多い場合は、中身の濃い内容の訪問ができるように質問の内容をよく考えて回数を調整しながら訪問すればよいでしょう。
ただ上記で解説したようにOBOG訪問に向けて準備すべきことがあります。
何でも相談するのは印象を悪くしてしまうことも念頭に置き、準備万全な状態で訪問するようにしてください。
就活には労力も必要ですが、人生の転機となる重要ポイントです。
満足いく就活を目指して、準備万全で上手に情報収集してください。
OBOG訪問の理想回数は5回くらい
自分が納得する回数とはいっても、一般的にOBOG訪問の理想回数は1~5回くらいといわれています。
次に6~10回という訪問回数も多いといわれていますが、これらの回数は目安でしかありません。
5回くらい訪問すれば、大方の情報を得られます。
ただあくまでも目安です。
少ない回数でも内容が濃ければそれでよいし、納得がいかなければ回数を増やしても構わないのです。
就活の相談から始めた人は必然的に回数は多くなり、訪問回数は人それぞれといえます。
またOBOG訪問は第一希望の企業だけではなく、志望する業界に勤めている方を訪問することもおすすめです。
同時にすでにその企業を辞めた方に話を聞くのも、企業の実態を知り得る訪問となります。
幅広い属性の人に話を聞けば、その分就活で差をつけられるでしょう。
まとめ
就活で差をつけるためにOBOG訪問をすることはおすすめです。
OBOG訪問は説明会では聞けない話や、インターネットでは調べられない情報を知り得ることができます。
質問の内容は浅いことから深いところまで掘り下げて話を聞けますが、訪問前に準備すべきことをきちんとして具体的な質問ができるようにしましょう。
アバウトな質問からはアバウトな情報しか得られません。
就活の限られた時間を無駄にすることなく、よい就活ができるよう頑張ってください。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!