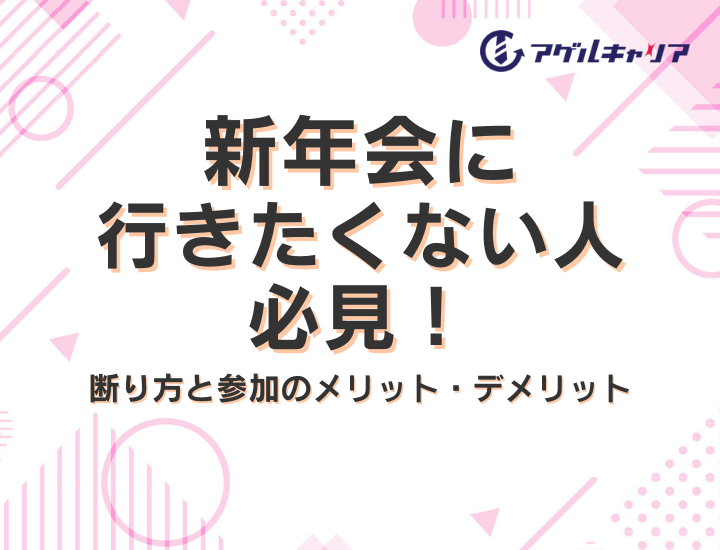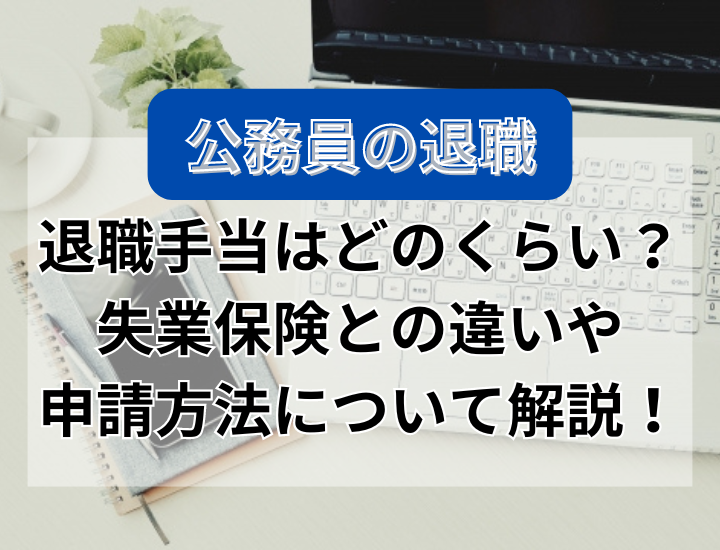
公務員の退職手当はいくらくらい?国家公務員・地方公務員の違いや申請方法を紹介!
はじめに
公務員を退職しようとしている人のほとんどは、退職手当について疑問に思うのではないでしょうか。
「公務員の退職手当ってどれくらいもらえるの?」
「公務員は失業保険を受け取れないって本当?」
「退職手当を受け取るにはどういう手続きを踏めば良いの?」
公務員を辞めてから転職をして新たなキャリアを積み上げようとしていても、退職後の生活も安心できる状態に備えておいた方が安心です。
公務員の退職手当は年数に応じて金額が変わりますから、今の自分がどれくらいの手当をもらえるのかは大きな関心事項と言えるでしょう。
ある程度まとまったお金が手に入るのであれば、転職活動期間中も経済面での心配を減らせます。
そこで今回の記事では、公務員の退職手当について以下の内容を解説します。
- 公務員は失業保険を受け取れないことについて
- 公務員の退職金制度について
- 退職手当の申請方法
公務員の退職を考えている方が疑問に思うポイントに絞って解説したので、ぜひ最後までお読みください!
【公務員の退職手当】公務員の退職金制度とは?
ここでは、公務員の退職金について詳しく説明します。
公務員の退職金は、勤続1年目からでも受け取ることが可能であり、退職手当の仕組みや受け取るタイミングについても明確なルールがあります。
また、退職金は所得税や住民税の課税対象となるため、税金の扱いについても理解しておくことが大切です。
本記事では、特に疑問が生じやすいポイントを中心に解説していくので、公務員の退職金について詳しく学んでいきましょう。
勤続年数1年目からでも受け取れる
結論からお伝えすると、公務員が退職する場合は勤続年数1年目からでも退職手当を受け取れます。
厳密にいうと、6ヵ月以上継続して勤務していれば、退職手当を受け取る権利が発生するのです。
なお、在職期間が6ヵ月未満の場合は切り捨てで、6ヵ月以上は切り上げて1年とカウントされる仕組みです。
例えば、公務員として働いて6ヵ月を過ぎたタイミングで退職する場合、月給が20万円だったとすると20万円×0.5022=100,440円、つまり約10万円の退職金を受け取れます。
0.5022などの退職手当支給率は「国家公務員退職手当支給率早見表」にて確認可能です。
ただし、勤続年数に応じて退職金が計算されるため、当然ながら在職期間が短い場合の退職金は「雀の涙」程度なので注意しましょう。
所得税及び住民税の課税所得対象となる
また、受け取った退職手当にも税金がかかることを押さえておきましょう。
具体的な計算式は、以下の通りです。
(退職手当支給額-退職所得控除額)×0.5
そして退職所得控除額は、以下のように計算します。
勤続年数が20年以下
勤続年数×40万円
勤続年数が20年より長い
(勤続年数-20)×70万円+800万円
なお、退職金が支払われるタイミングで「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、源泉徴収済みの額が支給されるため、別で手続きをする必要はありません。
ただ「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合、税金を納めるために確定申告が必要になることを押さえておきましょう。
退職手当を受け取れるタイミング
退職手当は、退職した翌月中には振り込まれるのが一般的です。
たとえば、3月31日に退職した場合、4月中には入金されることになります。
支払いのタイミングは、「国家公務員退職手当法」や「地方自治法」などの法律で定められており、大幅な遅れが発生することはほとんどありません。
そのため、退職後の生活設計を考える際にも、安心して資金計画を立てることができます。
もし不安な場合は、事前に勤務先へ確認しておくとよいでしょう。
【公務員の退職手当】公務員は失業保険をもらえない
退職時にほとんどの人が疑問に思うのが、失業保険についてでしょう。
公務員は退職手当が給付される仕組みであるため、失業保険を受け取ることはできません。
ここでは失業保険がもらえない理由や代わりとなる退職手当について詳しく解説します。
- 公務員が失業保険を受け取れない理由
- 失業保険の代わりに退職手当を受け取れる
- 退職手当を受給するための条件
- 支給額の決まり方
それぞれ詳しく見ていきましょう。
公務員が失業保険を受け取れない理由
国家公務員・地方公務員の方は、退職時に失業保険を受け取れません。
その理由は「雇用保険法第六条」にて、雇用保険の対象にはならないと定められているからです。
失業保険の本質的な目的は、急な失業に見舞われた方の生活を守り求職活動を支援することです。
そのため一般企業と比較して失業のリスクが低い公務員は、雇用保険の適用外とされている点を押さえておきましょう。
なお例外として、国立大学や郵便局などの適用事業所に勤務していた場合は、退職後に必要な手続きを行うことで退職届を受け取れます。
失業保険の代わりに退職手当を受け取れる
ただ、公務員は失業保険を受け取れない代わりに退職手当を受け取れます。
そのため失業保険を受け取れないからと言って、過剰に不安になることはありません。
また、勤続年数が短い場合は手当の支給額が少なくなります。
失業保険の見込み額と実際に受け取った退職手当の差が大きい場合、その差額を受け取れる可能性があります。
なお差額を受給する手続きは、一定の期間内に行わなければならないので注意しましょう。
退職手当を受給するための条件
公務員が退職手当を受け取るためには、いくつかの条件があります。
以下は、内閣官房が指定している条件です。
- 原則として、勤続期間が12月以上で退職した職員であること。
- 退職手当の額が、雇用保険法の失業等給付相当額に満たないこと。
- 原則として、退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業していること。
- 待期日数を超えて失業していること。
引用:内閣官房
これらの条件を満たしている方は、退職手当を受け取れます。
支給額の決まり方
公務員に支給される退職手当の支給額は、以下のような要素で決定されます。
- 勤続年数
- 退職理由(自己都合または定年退職)
- 退職時の年齢
- 退職前の給与額
一般的には自己都合退職よりも定年退職のほうが、退職手当は多めに支給されるケースがほとんどです。
なお、地方公務員か国家公務員かで基本的な支給条件は同じです。
ただ、地方公務員の場合は各自治体の地方自治法によって退職手当の支給額が決定されます。
そのため、地方公務員の場合は地域によって支給額が異なるケースがある点だけ押さえておきましょう。
【公務員の退職手当】退職手当の申請方法
次に公務員が退職手当を申請するときの手順について解説します。
やり方は基本的にシンプルで、以下の2つのステップのみです。
- 所属先で退職票をもらう
- ハローワークで手続きする
それぞれのステップで必要となる書類についてもご紹介するので、実際に退職を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
所属先で退職票をもらう
まずは所属先で退職票を受け取ります。
国家公務員の方は「国家公務員退職票」で、地方公務員の方は「国家公務員退職票」に準ずる書類を受け取ります。
地域によって形式は異なるため、各自治体が用意している退職票を入手しましょう。
ハローワークで手続きする
次に居住している地域を管轄するハローワークに退職票を提出し、求職の申込をします。
ハローワークで受理証明を受け退職票を所属先に提出すれば「退職手当受給資格証」と「失業者の退職手当請求書」が交付されます。
これらを、指定された日程にハローワークに提出すると失業認定がおります。
また失業認定を受けた期間について、「失業者の退職手当請求書」を福利課に提出すれば、退職手当を受け取る準備は完了です。
なお、退職手当を受け取るのは求職活動をしていることが前提です。
当面の間無職を予定していても、何回かハローワークに通う必要がある点だけ覚えておきましょう。
【公務員の退職手当】計算方法
公務員の退職手当は、退職時の月給によって金額が異なります。
また、退職手当がどのように計算されるかについては、自己都合退職と定年退職によって異なります。
この2パターンを実際に計算しながら解説します。
それぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
自己都合退職の場合
そもそも退職手当は退職理由や、退職時の月給によって決まります。
基本的には以下のルールに基づいて退職手当は計算されます。
退職時の月給×退職手当支給率+調整額=退職手当
※調整額とは、在職中の貢献度によって加算される金額
ちなみに退職手当支給率は「国家公務員退職手当支給率早見表」で確認できるので、自身に当てはまる条件で計算してみてください。
例えば月給30万円の10年間勤務した公務員が自己都合を理由に退職する場合、早見表を参考にすると以下のように計算できます。
300,000×4.5198=1,355,940円
※調整額は簡単のため割愛
なお退職手当支給率は、勤続年数によって大きく変わり長ければ長いほど支給率は高くなることを押さえておきましょう。
定年退職の場合
次に定年退職の場合です。
定年を60歳とし、新卒の22歳から38年間勤続していた公務員が定年退職するときに受け取れる退職手当を計算すると、以下の通りです。
(月給は45万円を想定)
450,000×47.709=21,469,050円
※調整額は簡単のため割愛
また勤続38年でも自己都合退職の場合、退職手当支給率は42.7707となり定年退職の47.709と比較すると定年退職のほうが有利であることがわかるでしょう。
【公務員の退職手当】退職手当の受給期間は延長できる
退職手当の受給期間(退職手当を受け取るための手続きを行なえる期間)は、原則退職した日から起算せいて1年間です。
ただ妊娠や出産、病気などの理由で職業に就けない方は受給期間を延長できます。
手続き方法は「受給期間延長申請書」を離職先の担当部署に提出しましょう。
公務員を退職したあとに、誰でもすぐに働けるというわけではありません。
ただ退職手当を受け取るにはハローワークで求職する必要があります。
すぐに求職活動を始められない方は、受給期間延長の手続きを踏んで退職手当を受け取る権利を確保しておきましょう。
【公務員の退職手当】退職手当の相場
実際、公務員が退職した際にどれくらいの退職金を受け取っているのか見ていきましょう。
ここでは、地方公務員と国家公務員の2つのパターンを比較していきます。
地方公務員
まず地方公務員における退職金の平均値を見ていきましょう。
| 全退職者平均支給額 | 定年退職者平均支給額 |
|---|---|
| 約13,745,000円 | 約22,095,000円 |
この結果から地方公務員の方は定年退職の場合、2000万円以上の退職金を受け取っていることが分かります。
こちらは、大企業に務めている大学卒の退職金とほぼ同程度です。
また、自己都合退職を含めた平均値値は約1400万円ではあるものの、退職者によって大きなばらつきがあることは押えておくべきでしょう。
国家公務員
一方、国家公務員の退職金は以下のとおりです。
| 全退職者平均支給額 | 定年退職者平均支給額 |
|---|---|
| 約11,043,000円 | 約21,122,000円 |
※出典:内閣人事局|給与・退職手当R4
この表から分かるように国家公務員と地方公務員で定年退職者の平均支給額は大差ないことが分かります。
国家公務員の退職手当で目を付けるべきなのは「応募認定退職」で、令和4年の平均支給額は約25,247,000円です。
つまり定年退職で辞めるより、より多くの退職手当を受け取れる可能性があります。
国家公務員からの退職を考えている方は「応募認定退職」を狙うのも、かしこい選択と言えるでしょう。
【公務員の退職手当】追加手当てを受け取れる場合
また退職手当が失業保険の相当額より少ない場合、その差額を受け取れる可能性があります。
差額を受け取るには、退職前半年から1年分の給与明細を準備しておきましょう。
例えば教員の方であれば、勤務地を管轄する教育委員会で手続きを行います。
具体的な手続きの方法については各地域の教育委員会でご確認ください。
教育委員会にて差額の受給申請ができたのであれば、ハローワークで求職の申し込みをして「求職申し込み証明書」や「失業証明書」を受け取りましょう。
これらの書類を教育委員会に提出すれば、手続きは完了です。
【公務員の退職手当】公務員をやめるメリット
これを読んでいる方の中には、まだ退職するべきか迷っている方も多いのではないでしょうか。
たとえ退職手当が受け取れたとしても、その後の転職活動がうまくいく保証はないため、不安に感じるのは当然です。
そこで、まずは退職することのメリットとデメリットをしっかり整理することが大切です。
公務員を退職するメリットとしては、年功序列の制度から解放され、自分の努力次第でキャリアアップできることなどが挙げられます。
さらに、働き方の自由度が高まり、ワークライフバランスを見直せるようにもなるでしょう。
これらも含めて、公務員を退職するメリットについて詳しく解説していきますので、実際に退職を考えている方はぜひ参考にしてみてください。
年功序列制度から解放される
公務員を辞めるメリットの一つに、年功序列制度から解放されることが挙げられます。
公務員は、長く在籍しているだけで給与が上がる仕組みが根付いています。
そのため、実力があっても若手のうちは評価されにくく、モチベーションが下がってしまうことも少なくありません。
一方、民間企業の多くは実力主義を採用しており、成果を上げた人が正当に評価される仕組みになっています。
たとえば、営業職やIT業界などでは、努力次第で若いうちから昇進や高収入を得ることが可能です。
公務員のように、実力を問わず在籍年数が長いだけで高い給与をもらえるケースが少なく、実力が正当に評価される環境を求める人にとっては、民間企業の方が働きやすいでしょう。
このように、公務員の給与体系に納得できない人にとって、実力が評価される環境へ転職することは大きなメリットになります。
自分のスキルや成果を正当に評価されたいと考えているなら、民間企業への転職を前向きに検討する価値は十分にあるでしょう。
働き方が改善される
公務員として働いている中で、職場環境の悪さに悩んでいる場合、退職によって働き方が改善される可能性があります。
職場環境が悪くなる要因には、人間関係のストレスや長時間労働などがありますが、退職することでそうした問題から解放されるきっかけになるでしょう。
もちろん、転職先の職場環境が必ずしも理想的であるとは限りません。
しかし、企業の社風や働き方を事前にリサーチすることで、劣悪な環境を避けることは十分に可能です。
特に民間企業では、在宅勤務制度やフレックスタイム制を導入している企業も多く、公務員と比べて柔軟な働き方がしやすいというメリットがあります。
もし現在の職場環境に不満を感じているのであれば、転職によってより良い環境を手に入れられる可能性は十分にあるでしょう。
自分に合った働き方を実現するためにも、一度退職を検討してみるのも選択肢の一つです。
手に職を付けるチャンスが広がる
公務員として働いている中で「スキルアップが見込めない」と感じている場合、退職して新しい仕事に挑戦することで、手に職をつけるチャンスが広がります。
公務員の事務作業は定型業務が多く、決められた仕事を繰り返すことが一般的です。
そのため、「自分のスキルでお金を稼ぐ力が身についていない」と不安を感じる方は、転職を検討するのも一つの選択肢でしょう。
また、公務員は副業が禁止されているため、本業以外でスキルを磨く機会が限られています。
しかし、民間企業では副業を認めている会社が多く、仕事をしながら新しいスキルを習得し、副収入を得ることも可能です。
たとえば、ITスキルを活かしてフリーランスの仕事をしたり専門知識を活かして講師業を始めるなど、多様な働き方が選べます。
なお、手に職をつけるのであれば昔から興味のあった職種や挑戦したい仕事に就くことをおすすめします。
スキルを磨きながら働くことで、より充実したキャリアを築くことができるでしょう。
【公務員の退職手当】公務員をやめるデメリット
公務員を辞めることはメリットだけではありません。
ここでは、辞めることで生じるデメリットについて解説します。
- 福利厚生が下がる可能性がある
- 転職までの間収入がなくなる
- 新しい職場に慣れる必要がある
メリットとデメリットの両面を把握することで、自分にとって最善の判断を下せるでしょう。
福利厚生が下がる可能性がある
公務員を辞める際に念頭に置いておくべきなのは、福利厚生が下がる可能性があることです。
比較的安定した職業である公務員は、福利厚生の良さも魅力の一つと言われています。
そのため公務員を辞める際は、手厚い福利厚生を手放すことになる点を押さえておきましょう。
ただ大企業の福利厚生は公務員に引けを取らないケースは珍しくありません。
そのため、経営が安定している会社に転職できれば、公務員と同等あるいはそれ以上の複利厚生を手に入れるケースもあるでしょう。
もちろん公務員を辞めることで安定感を失うリスクはありますが、転職先を選んで内定を勝ち取れば公務員として働いていたときより状況は良くなるでしょう。
転職までの間収入がなくなる
公務員をやめてから新しい仕事につくまでの間は、収入がなくなります。
退職手当は受け取れるものの、収入がないという状況は、精神的に不安にさせる大きな要因と言えるでしょう。
転職活動をしている最中にメンタルが安定していないと、上手くいくはずの面接も思うように進まなくなる可能性が高くなります。
転職活動にどれくらいの時間がかかるかは人によりますが、約半年くらいの生活費を蓄えておけばすぐにお金に困ることはありません。
そのためある程度の貯金を準備してから公務員を辞めると良いでしょう。
新しい職場に慣れる必要がある
そして転職に成功したとしても、新しい職場に慣れる必要があります。
仕事の進め方や人間関係などを一から構築していく作業は、なれるまで負担になるでしょう。
とはいえ一度慣れてしまえばそれほど負担は大きくないので、最初の3ヵ月から半年耐えれば楽になるという心づもりで働くと気が楽になります。
働く前に新しい職場に慣れることに対して億劫に思ってしまうと、なかなか転職の一歩を踏みだせません。
給与面やスキル面で不満がある場合は、できる限り早めに決断して行動するのがかしこい選択です。
【公務員の退職手当】転職する際に評価されるポイント
公務員の方が転職する際に評価されるポイントを、国家公務員と地方公務員それぞれの場合に分けて解説します。
公務員として働いていた経験は、転職の際にどのように活かせるのかを考えていきましょう。
国家公務員の場合
国家公務員から一般企業に入社する場合は、思考力や折衝力などのビジネススキル全般を評価してもらえる傾向があります。
ただ企業の面接を受ける際は、公務員と求められている価値が異なることが多いため、会社の理念や価値観をあらかじめリサーチしておかなくてはなりません。
公務員の価値観で評価されることと、一般企業のなかで評価されることにギャップがあるので、その点を意識して面接にも望めると採用確率を高められるでしょう。
地方公務員の場合
地方公務員から民間企業に転職をする場合、責任感の強さや誠実さ等をアピールすると評価される傾向があります。
規則に則った上で、責任感を持って丁寧な仕事ができる人は、民間企業でも重宝されるはずです。
公務員と一般企業とでは、面接官が評価しているポイントが異なるケースが多いため、自分が受ける会社がどのような人材を求めているのかを調べておくと良いでしょう。
そうすれば、自分が志望している会社に入社できる可能性を高められます。
【公務員の退職手当】転職を成功させる人の特徴
最後に、公務員からの転職を成功させる人の特徴について5つ紹介します。
- 転職市場で自分の価値を理解している
- 公務員の悪口を言わない
- チャレンジ精神がある
- スキルがある
- 転職エージェントを活用している
もし当てはまっている特徴が多いのであれば、転職が成功する確率は高いかもしれません。
転職市場で自分の価値を理解している
公務員から民間企業へ転職を成功させるためには、自分自身の市場価値を正しく評価することが重要です。
転職を考える際に、自分のスキルが民間企業では通用しないと思い込んでしまう人もいますが、必要以上に自分を低く見積もるのは避けるべきです。
実際、公務員試験を突破し、行政業務をこなしてきた経験は、採用担当者から見ても十分な評価対象となることがあります。
そのために、転職活動を始める前には、自己分析をしっかり行うことが大切です。
自分の強みや得意なことを整理し、それが民間企業でどのように活かせるのかを考えることで、適した職種や業界を見つけやすくなります。
自己分析を怠ると、適性に合わない仕事を選んでしまい、転職後にミスマッチを感じるリスクも高まります。
自分の価値を正しく理解し、自信を持って転職活動に取り組める人ほど、良い結果を得られる傾向があります。
転職市場を知るとともに自己理解を高めて、自分に合ったキャリアを築いていきましょう。
公務員の悪口を言わない
採用面接時に公務員時代の悪口等は言わないようにしましょう。
なぜなら「不平不満を言う人」という悪い印象を面接官に与えてしまうためです。
「業務量のバランスがおかしかった」「上司が人として尊敬できなかった」といった本音は誰しも抱えています。
ただそれを口に出してしまうと「この人はうちの会社でも不平不満を言うのかも…。」という懸念を採用担当者に与えかねません。
そのため公務員としての働き方に不満があったとしても、プラスの側面にフォーカスして面接官に伝えるようにしましょう。
周囲の人に前向きな印象を与えられる人は、転職においても成功しやすいと言えます。
チャレンジ精神がある
チャレンジ精神がある人は、志望している会社の内定をつかみ取る傾向があります。
公務員と聞くと「安定志向」という印象を持つ方は多く、面接官も例外ではありません。
そんな中、チャレンジ精神をアピールできるエピソードや「入社したらこういう風になりたい」というようなビジョンを熱く伝えられれば、面接官に気持ちを動かせるでしょう。
スキルがある
また、何らかのスキルを持っている人も転職で成功しやすい傾向があります。
公務員の場合、警察官や教師などの専門職に就いていた方は、同じ業界を選ぶだけで有利になる可能性は高めです。
例えば教師として働いていた方が、教育系の一般企業にチャレンジするのは相性が良いと言えるでしょう。
公務員だった方は、公務員試験に合格したという実績が付いてきます。
その実績を活用しつつ自分のスキルを活かせる業種を選べば、成功確率を高められるでしょう。
転職エージェントを活用している
公務員からの転職を目指すのであれば、転職エージェントを活用するのが定石です。
一般企業の採用プロセスは公務員と大きく異なるため、エージェントのサポートを頼るのがかしこい選択です。
また転職エージェントには、有利に就職活動を進めるための情報が豊富にそろっています。
場合によっては、表では公開されていないレアな求人を紹介してもらえるケースも。
なおアゲルキャリアは、求職者にマッチした職場の内定を獲得できるサポートを提供しています。
無料で相談できるので、気になる方はぜひご利用ください。
公務員が転職を成功させるためにやるべきこと3選
公務員が民間企業への転職を行う際は、これまでとは全く異なる異業種への転職となります。
そのため、会社員からの転職に比べると色眼鏡でみられることもあるでしょう。
転職成功率を高めるためには、自己理解を高めて自分に合った環境を把握することが大前提。
その上で、行きたい業界や企業を決めて、自分のアピールポイントを整理しながら面接でアプローチしましょう。
相性の良い転職先を見つけて内定率を上げるためにやっておきたいことは3つです。
順を追って見ていきましょう。
自己分析
公務員から民間企業へ転職を成功させるためには、まず自己分析をしっかり行うことが重要です。
自己分析をすることで、自分の強みや適性を明確にし、どの業界・職種に向いているのかを判断しやすくなるからです。
公務員としての経験は、業務の正確性や責任感、調整力、文書作成能力、法律や制度に関する知識など、多くのスキルにつながっています。
しかし、これらをそのまま民間企業の仕事に当てはめるのではなく、「どのように活かせるか」を考えることが大切です。
たとえば、行政での折衝経験は営業職やコンサルタント職に、資料作成やデータ分析の経験は企画職やマーケティング職に応用できる可能性があります。
自己分析の方法としては、これまでの経験を振り返ることから始まります。
「どんな業務が得意だったか」「どんな場面でやりがいを感じたか」「周囲から評価されたスキルは何か」などを書き出して整理するのがおすすめです。
また、転職エージェントのキャリア相談を活用したり、適性診断ツールを利用して自己分析するのも有効です。
やり方がわからない人は自分だけでやみくもに進めるのではなく、使えるものはとことん使いましょう。
自己分析をしっかり行うことで、自分に合った仕事を見つけやすくなり、転職後のミスマッチを防ぐことができます。
転職を考えている公務員の方は、まず自分の強みを明確にすることから始めてみましょう。
業界研究
行きたい業界が決まったら、事前の業界研究を行いましょう。
公務員と民間企業では働き方や評価基準が大きく異なるため、事前にしっかりリサーチし、自分に合った業界を見極めることが重要です。
業界研究の第一歩としては、まず各業界の特徴や動向を把握することです。
そのためには、企業の公式サイトや業界ニュースをチェックするほか、転職エージェントの情報を活用するのも有効です。
また、実際にその業界で働いている人の話を聞くことで、リアルな業務内容や働き方を知ることができるので、周りに話を聞ける人がいればぜひ質問してみましょう。
なお、転職成功率を上げるためには、これまでの経験をどの業界で活かせるのか洗い出した上で自分のアピールポイントを見つけることが重要です。
業界研究をしっかり行い、自分に合った分野を見つけることで、転職成功の可能性を高めましょう。
企業研究
業界研究と一緒に行っておきたいのが、企業研究です。
行きたい業界だけではなく、応募先の企業について徹底して調べることが成功のカギとなります。
企業研究でキャッチした情報は、具体的な志望動機を作成するためのヒントにもなります。
応募先企業の魅力をとことんアピールできる様になれれば、入社意欲と熱意が伝わって高い評価を得られるでしょう。
企業研究ではまず、企業の経営方針や事業内容、働き方を把握することが大切です。
公式サイトや企業の採用ページをチェックし、「どんな事業を展開しているのか」「今後の成長性はあるか」「自分のスキルが活かせる職種はあるか」などを確認しましょう。
また、企業の口コミサイトやSNSなど外部からの情報も調べておけば、実際の職場環境や社風、給与制度などのリアルな情報を得ることができます。
次に、企業の求める人物像を理解し、自分の経験とどう結びつけるかを考えることも大切です。
公務員として培った調整力や事務処理能力、コミュニケーション力は、多くの企業で活かせるスキルです。
企業の求める人材像と自分の強みがマッチしているかを確認し、志望動機や自己PRに反映させることで、選考通過率を高められます。
しっかり企業研究を行うことで、転職後のミスマッチを防ぎ、長く働ける企業を見つけることができるでしょう。
まとめ
以上、公務員の退職手当は勤続年数が長ければ長いほど高くなる傾向があります。
一番短くても6ヵ月以上公務員として働いていれば、退職手当は受け取れるものの、額は期待できないでしょう。
また公務員は失業保険を受け取れないものの、その分退職手当を受け取れるという仕組みの元でバランスが保たれています。
ただ失業保険の見込み額と比較して実際に受け取った退職手当の額が大幅に低かった場合は、その差額を受け取れるケースがあることを押さえておきましょう。
勤続年数が短いと退職手当の額は少なくなってしまいますが、早めに決断すればより条件の良い職場に転職できる可能性はあります。
公務員として働くことに魅力を感じていないのであれば、早めに行動を始めたほうが良いでしょう。
転職を成功させるには、転職エージェントを使うのがおすすめです。
アゲルキャリアでは、無料で専任エージェントに相談できるので、ぜひ活用してみてください。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!