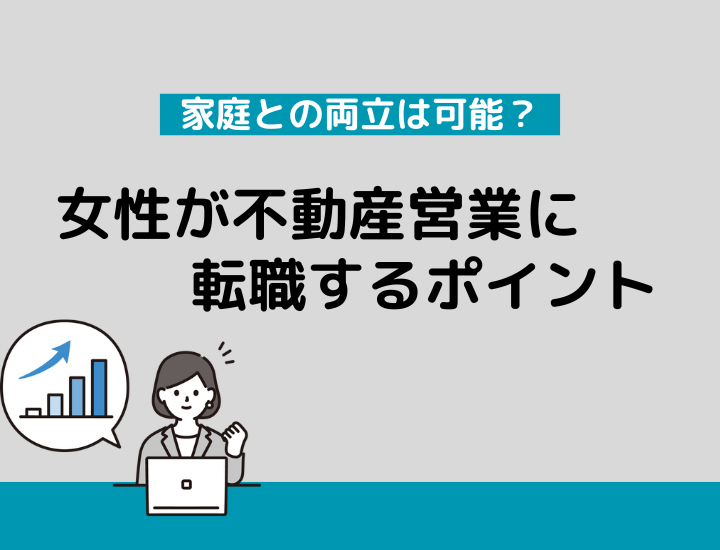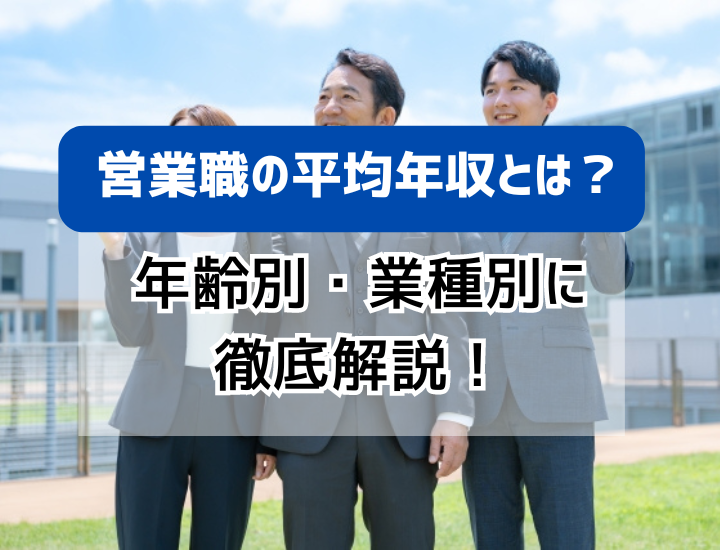営業管理とは?7つの管理方法やおすすめツールを選ぶポイントも解説
はじめに
営業マネージャーなら誰もが直面する「チームの成果がバラつく」「営業プロセスが見えない」という悩み。
これらの問題を解決する方法のひとつに「営業管理」があります。
この記事では、営業チームの生産性を向上させる営業管理の全体像から実践方法までを解説します。
適切な営業管理を導入することで、チーム全体の営業力が底上げされ、安定した成果を生み出せるようになるでしょう。
営業管理はとても忙しい仕事ではありますが、やるべきことの優先順位をつけた上で進めていけばスムーズに仕事が回るはずです。
営業管理とは
営業管理とは、目標売上の達成に向けた行動プロセスを計画し、進捗を管理することです。
具体的には、成約数や売上に関する「目標管理」、抱えている顧客や案件数に対する「顧客管理」「案件管理」、営業メンバー個人の「行動管理」「モチベーション管理」「スケジュール管理」営業テクニックなどの質を上げるための「人材育成管理」などの7つの分類に分けられます。
この7つの管理の質を上げることで、KGIの達成を最短距離で叶えることが可能になるのです。
営業管理が必要な理由
営業管理は、企業の売上目標達成と成長に不可欠です。
結論から言えば、営業管理は営業パーソンのパフォーマンスを最大化し、組織全体の営業活動を効率化するために必要です。
まず営業管理がなければ目標と現実のギャップが生じます。
営業活動の進捗状況や成果が見えないため、問題点の早期発見や対応が困難になるからです。
また、個々の営業担当者の活動が属人化し、ナレッジの共有や標準化が進まず、組織としての成長が妨げられます。
営業管理を適切に行うことで、常に次にとるべき行動を把握できるようになり、営業活動の無駄を省き効率化につながります。
さらに、データに基づいた戦略立案や意思決定が可能となり、より効果的な営業アプローチの実現につながるでしょう。
営業管理は単なる監視ではなく、営業チーム全体の生産性と成果を高めるための重要な基盤なのです。
営業管理のメリット
営業管理を実践することで、得られるメリットを知りたいと考えているマネージャーも多いでしょう。
営業管理は、案件情報の可視化から業務効率化まで、営業チーム全体のパフォーマンス向上に直結します。
ここからは、営業管理を導入することで得られる4つのメリットを解説します。
案件情報・営業進捗状況の可視化ができる
営業管理のメリットは、案件情報と営業進捗状況の可視化を実現できることです。
営業活動の全プロセスを可視化することで、チーム全体の意思決定と問題解決が迅速化します。
営業管理を通じて「どの案件がどのフェーズにあるか」「誰がいつどのように顧客対応したか」といったデータを一元管理することで、営業活動の全体像が把握できます。
これにより、ボトルネックの特定や対応漏れの防止が可能になります。
また、個人では気づけなかった課題もチーム全体で共有でき、解決策を見出せることも期待できます。
目標が明確化・共有できる
目標が明確化・共有されることで、チーム全体が同じ方向を向いて効率的に行動できるようになります。
営業管理によって営業目標が部門全体に共有されると、各担当者が何を目指して活動すべきかが明確になります。
数値目標(KPI)の設定も、営業活動の指針が数値化され、目標達成に向けた行動計画が立てやすくなります。
目標管理は、単なる数字の追求ではなく、チーム全体の一体感が出やすく、個々の営業担当者が目的意識を持って活動するための基盤となるのです。
営業ナレッジを共有して属人化を防止できる
営業管理を実践することで、個人に依存していた営業ノウハウを組織全体の資産として活用できるようになります。
営業管理を通じて各担当者のアプローチ方法や成功事例をデータ化することで、トップセールスのスキルやノウハウを可視化し、チーム全体で共有でき属人化対策になるでしょう。
業務を効率化できる
営業管理を活用すれば、無駄な作業時間を削減し、営業活動に集中できます。
営業管理により情報が一元化されるため、案件の進捗確認のために情報を探し回る必要がなくなるからです。
また、業績会議の資料作成時に複数のExcelやパワポを確認する手間も省けます。
営業管理による業務効率化は、組織全体の生産性向上につながるのです。
営業管理の7つのプロセス
営業管理には、先ほどあげた7つのプロセスが存在します。
・目標管理…成約数や売上
・顧客管理…見込み顧客と既存顧客の管理
・案件・商談管理…見込み案件と商談の質に関する管理
・行動管理…メンバーの行動数(KPI)管理
・モチベーション管理…メンバー一人一人のメンタルケアや向上心のアップ
・スケジュール管理…目標期日まで逆算した利益推移の予定
・人材育成管理…営業の質を上げるための管理
営業目標を達成させるためには、これら7つのプロセスが密接に関わっています。
これらの質を全体的に向上させることで、強い営業チームに育つので、順を追ってご説明します。
1.目標管理
まずは目標管理です。
営業管理における目標管理は、チーム全体と営業個人に課されている売上目標を管理することです。
月ごと(または週ごと)の達成率や進捗率を日々確認することで、目標売上に対するギャップのどこに課題があるのかを常に把握しておく必要があります。
営業マネージャーが確認すべき目標管理の指標は、次の3つです。
・リアルタイムでの合計売上
・目標額に対するギャップ
・本日時点での進捗率
これら3つに常に目を配ることで、目標に対するギャップが生まれた時の課題の洗い出しをしやすくします。
なお、目標管理で重要なことは、リアルタイムでの売上進捗を確認するだけにとどまらないということです。
ギャップが生まれた時にそのままにしていると、その差分はどんどん開いて、目標期日までに到底届かない差分を生み出してしまうことになります。
ギャップの大小にかかわらず、課題は常に眠っているはずです。
それにいち早く気づくべき存在が営業マネージャーです。
常に課題に気づけるような体制を整えるためには、営業管理ツールを導入したり毎日ホワイトボードなどオフィスの見えるところで進捗状況が確認できるようにしたりと、可視化しやすくすると良いでしょう。
2.顧客管理
顧客管理は、既に取引をいただいている「既存顧客」と、まだ既存顧客化していない「見込み客」の2つに分けて管理をします。
既存顧客については、営業活動において基本となってくる情報(決裁者・会社概要・連絡先・提案中の案件・現在の契約状況・フォロー状況・折衝した履歴)がわかっているので、過去のデータも含めて情報を抽出することで提案の質を改善するヒントにします。
見込み顧客は、情報(決裁者・会社概要・連絡先・提案中の案件・現在の契約状況・フォロー状況・折衝した履歴)がわからないことが多いので、わかっている情報をもとにテレアポなどでどのような切り口の営業をすれば良いかを検討することから始まります。
また、これらの顧客の接触頻度や商談などの折衝回数に優先順位付けをするために、顧客ごとにBANTSを握ることが重要です。
BANTSがわかっていない状態だと、いつどのくらいの売り上げが入りそうか、見込みを立てることも難しいためです。
・Budget(予算)…今回の提案に対する予算がどのくらいか
・Authority(決裁権)…誰が決裁者か
・Needs(ニーズ)…どういうニーズがどこにあるか
・Timeframe(導入時期)…導入するとしたら時期はいつになりそうか
これら4つが握れている顧客は、「いつ・どのくらい・どの内容で売れそうか」がわかるので、売上見込みがわかりやすくなります。
また、ニーズが高く導入見込み時期が早い顧客から優先順位をつけてアプローチするなど、営業の行動管理においても重要な指標となります。
3.案件・商談管理
案件管理(または商談管理)は、顧客ではなくリアルタイムで抱えている「案件」に対して優先順位をつけて進捗状況を追っていく管理方法です。
受注確度ごとにカテゴライズして受注確率の高い顧客を優先して接触対象にすることで、どのくらいの金額で目標に到達しそうかどうかの判断基準にもなります。
例えば、次のような形式で案件に確度をつけていきます。
・優先順位高…顧客のBANTSが握れている/もしくは受注になった場合の見込み金額が大きい
・優先順位中…顧客のBANTSは一部握れている/もしくは受注になった場合の見込み金額は平均的
・優先順位低…顧客のBANSTSが握れていない/もしくは受注になった場合の見込み金額が低い
以上のように優先順位に高低をつけたり、会社によってはA〜Eまで5段階で優先順位をつけたりもします。
なお、案件管理は確度やアプローチ状況などを細かく分析した上で優先順位をつける必要があります。
そのため、管理方法が煩雑だと混乱して案件が散らかってしまうことも少なくありません。
Salesforceやkintoneなどの営業の売上管理システムを使ったり、スプレッドシートで管理したりなど、オンラインですぐに見られるシステムを整えておくことをおすすめします。
4.行動管理
行動管理は、目標達成に向けたチーム全体または営業メンバー個人の行動プロセスを管理することです。
目標管理においてはゴールである「売上達成」に向けた管理ですが、行動管理は売上達成のための「行動方法」を管理することです。
行動管理をすることで、1件成約するまでの平均期間や一人一人ができるアプローチ数などを把握できるため、プロセス毎の改善項目を洗い出ししやすくなります。
具体的には以下の項目をすることによって、プロセスの進捗状況を管理します。
ポン
・案件毎のアプローチ状況
・抱えている商談数
・平均成約単価
・成約率
・新規アポイント獲得数
5.モチベーション管理
営業管理は、先ほどまでご紹介した数値的な管理をするだけでは終わりません。
営業チームメンバーや個人個人のモチベーションを維持し続けることも、マネージャーに課される業務の一つです。
一人のモチベーションが低下し、やる気のない態度が出てしまうとチームメンバー全員にも影響があります。
もちろん、そんな状態で商談にのぞんでも受注確率は一向に上がらないでしょう。
モチベーション一つで利益を大きく左右してしまうので、たった一人の営業であってもモチベーションを上げてあげることはとても重要です。
もしメンバーの誰かのモチベーションが低下したと感じた場合、いち早く声をかけて話に耳を傾けましょう。
そして悩みをとことん引き出したら、悩んでいることに対してのアドバイスをすることも忘れずに。
なお、モチベーションの低下のきっかけが仕事以外の場合もあります。
もしかするとプライベートで何か辛いことがあったかもしれません。
その時は、マネージャーではなく、本人と距離が近い直属の上司から声をかけてもらうなど、ワンクッション置いてみると良いでしょう。
6.スケジュール管理
スケジュール管理は、チーム全体の売り上げ目標が達成するまでに逆算して管理することが重要です。
月ごと(または週ごと)に決めた目標アポイント設定数や架電数、訪問数などを含めて全体の予定の進捗を把握し続けることで、行動管理とともに進捗を見ていきます。
さらに、スケジュールに狂いを出さないように営業メンバー個人のスケジュールについても管理をします。
顧客との商談日やクロージング日など、営業メンバー個人個人で設定したスケジュールを管理することによって、業務の優先順位をつけやすくなり、営業活動における効率化が図れるのです。
なお、スケジュール管理は営業メンバー数が増えれば増えるほどやりにくくなるものです。
常に全体に目を配って進捗状況に遅れがないかチェックするには、共有カレンダーアプリなどを使うことをおすすめします。
7.人材育成管理
人材育成管理は、営業メンバー全員の営業テクニックを底上げしてスキルを均一化するための管理です。
まずは個人のスキルや経験を分析し、スキルが足りていない経験の浅いメンバーを中心に育成プロセスを検討します。
経験豊富なメンバーについては、若い営業や数字が足りていないメンバーに対するフォローアップの仕方などについて教えることもあります。
具体的に注力しておこなっておきたい育成方法としては、レベルアップのために一段階難しい案件・顧客を任せてみたり、ベテラン営業と新人営業を同行させてノウハウを共有するなどです。
そのほかには、定期研修的な形で毎週のミーティング内で営業テクニックの共有をするなども良いでしょう。
営業管理を効率的に行うための会議のコツ
営業管理の内容をより濃く効率的に行うためには、営業会議の方法や流れをブラッシュアップすることも重要です。
営業会議は議題の数や発言するメンバーが多ければ多いほど、熱くディスカッションしてしまいがちです。
そうなると予定終了時刻から大幅にオーバーしてしまったり、TODOが決まらずに終わってしまったりと、意味のない会議になってしまいます。
営業会議は、売り上げを上げるための会議ですから、しっかりとした役割分担を決めて進めることも重要です。
ここからご紹介するのは、営業会議を効率的に進めるためのコツです。
順を追ってご説明します。
会議のアジェンダを設定する
会議では必ずアジェンダ(議題)を決めた上でスタートしましょう。
アジェンダが決まっていない状態で会議を始めると、どこをゴールにすれば良いかがわからず、だらだらと話してしまいがちです。
基本的には会議の前日までに決定しておくと良いでしょう。
なお、営業管理を効率的に行うという観点からでお伝えすると、アジェンダは以下の5つの指標をもとに決めておくことをおすすめします。
1.前回の会議で決めたTODO(決定事項)の進捗
2.目標に対する進捗率の共有(全体数値)
3.目標に対する数値共有(個人数値)
4.数値にギャップがあった場合の課題の洗い出しと解決策の決定
5.今回の会議で決めるTODO
この5つのように、営業会議で話すべきことは「数字」についてが中心です。
全体共有事項などは毎日の朝礼やグループチャットで簡潔に済ませられる内容がほとんどなので、営業会議ではできるだけ数値に対する話の濃度を意識して進めましょう。
参加メンバーで役割分担する
営業会議では、ファシリテーター・議事録者など役割分担をして進めるとスムーズです。
ファシリテーターがいることで、一つの議題に対して時間内に終わらせられるように会話を進めることができますし、議事録者がいれば後からグループチャットで議事録を共有する時に漏れが防げます。
可能であればタイムキーパーもいると良いでしょう。
また、ファシリテーターは新人にも任せると人材育成にもつながります。
会議を時間内に終わらせる効率的な進め方を覚えてもらえることができるので、ビジネススキルの底上げになります。
TODOを決定する
TODOは、その週に行うべきタスクです。
個人のタスクは全体共有の場で共有する形で決めることで、タスクの抜け漏れが防げます。
また、次回の会議でタスクの進捗についても振り返ることができることもメリットです。
会議の資料作成時間はツールを使って短縮
会議で資料を使う時は、作成時間をできるだけ短縮できるよう、普段からツールを使うことを心がけましょう。
もちろん、パワーポイントでゼロから作成しても良いですが、一度の会議でしか使わない資料に労力をかけることほど無駄なことはありません。
そこでおすすめなのが、BIツールやSFAツールのダッシュボード、レポート機能を利用することです。
スクリーンショット等を使えば、わざわざエクセルなどに入力し直して作る必要がありませんし、普段から目にしている営業ツールの形式なので会議参加者にも見やすいです。
予定時刻を過ぎたら一旦終了する
営業会議ではディスカッションしてしまうこともしばしばあるでしょう。
しかし、盛り上がっているからといって予定時刻を過ぎても終わらないことはNGです。
会議が長引けばその分セールスタイムが削られて業務効率を下げてしまいます。
営業会議は利益を作るためにするものなので、時間オーバーによりセールスタイムがなくなったことで顧客との接触時間が少なくなってしまっては、もとも子もありません。
もし予定時刻を過ぎそうになったらいったん締めましょう。
終了時刻の5分前くらいには、その時点で決まっている決定事項やTODO、次回の議題について共有をします。
そしてちょうど終了予定時刻になったらすぐに終わりましょう。
もし個別で対話が必要なメンバーがいれば、後日1on1の時間を設けて話し合うと良いでしょう。
営業管理における注意点
営業管理を効果的に実践するには、いくつかの注意点があります。
営業マネジメントは、チームワークを大事にしながらも、時には数字に厳しい姿勢を見せなければなりません。
さらに、業務効率を上げる取り組みをしてメンバーが無駄なく営業に取り組めるような環境整備も必要です。
この後ご説明するのは、全体をまとめる際に徹底しておきたいことと、営業管理ツールを使用して効率良く全体の業務を進める方法です。
営業管理におすすめのクラウドツールなどもご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
情報共有は全体に浸透させるまで徹底
営業マネジメントをする際に重要視したいことの一つとして、チーム全体とのコミュニケーションの取り方があります。
近年ではリモートワーク等で顔を合わせずにチーム間でのコミュニケーションをとる会社が増えましたが、どういう状況であれ、チームセリングの仕事は全体が同じように情報を理解していることが重要です。
情報共有がなされていないと、チーム間で案件を引き継ぐ際に連携が取れず、お互いの認識の誤差によって業務に支障をきたしてしまいます。
また、営業チームはコミュニケーションが少ないとモチベーションが下がることにもつながります。
こうした事態に陥らないためにも、定期的な情報共有とコミュニケーションは営業管理において必須なのです。
週に1回の会議で情報共有をするだけでなく、たとえば毎朝グループチャット内で伝達事項と数字進捗についての情報共有をしあったり定期的な1on1面談の場を設けたりすることも良いでしょう。
営業チームにおいて雑談しすぎることは無駄かもしれませんが、あまりにも会話がなさすぎるというのもNGです。
営業管理ツールを活用する
営業管理にはクラウド型のツールなどを使用することをおすすめします。
なぜなら、クラウド型なら全体と共有できるためです。
全員が閲覧・編集できるようなツールがあれば、会議で数値管理の話をした時も何の話をしているのかがわかりやすいですし、共通認識を持って業務に取り組むことができます。
今からお伝えするのは、営業管理におすすめしたい4つのツールです。
1.エクセルオンライン/Googleスプレッドシート
2.営業支援ツール
3.クラウド型ファイル共有サービス
4.紙/ホワイトボード
これらの具体的なメリットについて、それぞれ詳細をお伝えします。
1.エクセルオンライン/Googleスプレッドシート
エクセルオンラインはGoogleスプレッドシートは、マイクロソフトオフィスやGoogleのアカウントさえあれば誰でも使用できるサービスです。
エクセル型なので、グラフや表での数値管理がしやすいですし、全員が編集権限を持っていればリアルタイムで案件数や受注額を入力することができます。
デメリットとしては、データを入れすぎると読み込みが遅くなってしまうという点です。
営業管理をしていくと、どうしても見るべき指標がたくさん出てきてしまい、ページ数が多くなってしまうものです。
マクロ関数を入れたりすることでさらにデータが重くなるため、外出先のスマートフォンで閲覧する際には見づらくなることは覚悟です。
2.営業支援ツール(SFA/CRM)
SFA/CRMは営業活動における情報を一元管理し、営業プロセスを効率化・最適化するためのシステムです。
SFA/CRMを導入することで、取引先情報、目標、案件、行動に関するデータを自動的に蓄積・分析できます。
Excelとは異なり、入力項目が少なく、データは自動で処理されるため、営業担当者の負担が軽減されるでしょう。
ただし、導入初期はデータ蓄積に時間がかかり、使い方に慣れるまでマネージャーのフォローやベンダーのサポートが必要な点に注意が必要です。
3.クラウド型ファイル共有サービス
クラウド型ファイル共有サービスは、「Dropbox Business」や「OneDrive」「Googleドライブ」などが有名です。
これらのサービスには大きな差はありませんので、月額利用料金や容量で決めると良いでしょう。
4.紙/ホワイトボード
先ほどまでシステム系ツールをご紹介していたので、ここにきて紙とホワイトボードを紹介されることに驚く方も多いことでしょう。
実は、紙やホワイトボードはITが主流の今だからこそおすすめしたいツールなのです。
もちろん、普段使う営業管理ツールとしてはITツールをおすすめします。
しかし、ITツールはWeb上で管理するため、見たいと思うページに遷移しないとたどり着くことができません。
そのため、意識的に見る癖がつけられていないと売り上げに対する焦りや競争心が薄れてしまうことが盲点です。
一方、紙やホワイトボードで社内の見えるところに掲示すれば、嫌でも目につきます。
グラフにしたりランキングにしたりすることで、負けず嫌いなメンバーの闘争心に火をつけることもできるでしょう。
管理項目は最小限にする
管理項目が多すぎると営業担当者の負担が増大し、本来の営業活動に支障をきたすため、必要最小限の項目に絞るべきです。
また、情報過多になると重要なデータが埋もれ、分析が困難になります。
最小限の管理項目としては、以下が挙げられます。
- 目標管理:総売上高、新規受注件数
- 顧客管理:取引先情報、担当者情報
- 案件管理:商談日、進捗状況、受注確度、予定金額
- 行動管理:アプローチ数、商談数、受注数
これらの基本項目に絞ることで、営業担当者の入力負担を軽減しながら、必要な情報を確実に収集できます。
管理項目は定期的に見直し、不要なものは削除する習慣をつけましょう。
他部署と連携する
営業部門が他部署と積極的に連携することで、顧客対応の質が向上し、受注率の大幅な改善も期待できます。
営業組織で蓄積したデータは、マーケティング部門やサポート部門と共有することで、その価値が何倍にも高まるからです。
マーケティング部門は営業から得た詳細な顧客情報をもとに、より精度の高いターゲット設定が可能になります。
サポート部門は過去の案件情報から顧客の潜在的な課題を予測し、先回りした対応ができるようになるでしょう。
他部署連携は、組織全体の営業力を高める戦略的アプローチなのです。
営業管理ツールを選ぶポイント
営業管理の重要性を理解したものの、「どのツールを選べばいいのか」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
ツール選びは営業管理を左右する重要な要素です。
ここからは、数多くある営業管理ツールの中から最適なものを選ぶための3つのポイントを解説します。
導入する目的を明確にする
導入目的が不明確なままツールを選ぶと、機能過多で使いこなせなかったり、必要な機能が不足したりする失敗につながります。
営業管理ツールは導入自体が目的ではなく、特定の経営課題を解決するための手段だからです。
「営業ノウハウの蓄積・共有」「営業担当者の業務効率化」「顧客情報の一元管理」など、自社が解決したい課題を特定することで、必要な機能が見えてきます。
導入コスト・ランニングコストを考慮する
初期費用だけでなく長期的なランニングコストまで含めた総コストで判断することも重要です。
初期費用が0円でも月額料金が高額な場合や、その逆のケースもあります。
また、長期利用を前提とすると、初期費用の安さだけで選ぶと結果的に総コストが高くなる可能性もあります。
自社の予算と必要機能のバランスを見極め、長期的に無理なく利用できるツールを選ぶことが、持続的な営業管理の実現につながります。
ツールの特徴を理解する
ツールの機能や特性を十分に把握せずに導入すると、業務に適合せず、投資対効果が得られない可能性が高まります。
営業管理ツールには案件管理、顧客管理、活動管理、予実管理、日報管理など様々な機能があり、ツールによって強みとする機能が異なります。
自社の課題解決に必要な機能が充実しているツールを選ばなければ、導入効果を最大化できません。
まとめ
この記事では、営業管理の重要性とその実践方法について解説してきました。
営業管理は組織の営業力を最大化し、安定した業績向上を実現するための必須要素です。
営業管理によって案件情報や進捗状況が可視化され、目標が明確化・共有されます。
また、営業ナレッジの共有により属人化を防止でき、業務効率化も実現します。
営業管理は単なる監視や数値追求ではなく、営業チーム全体の成長と成果最大化を支援するための仕組みです。
この記事を参考に、自社の営業管理の仕組みを構築してみましょう。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!