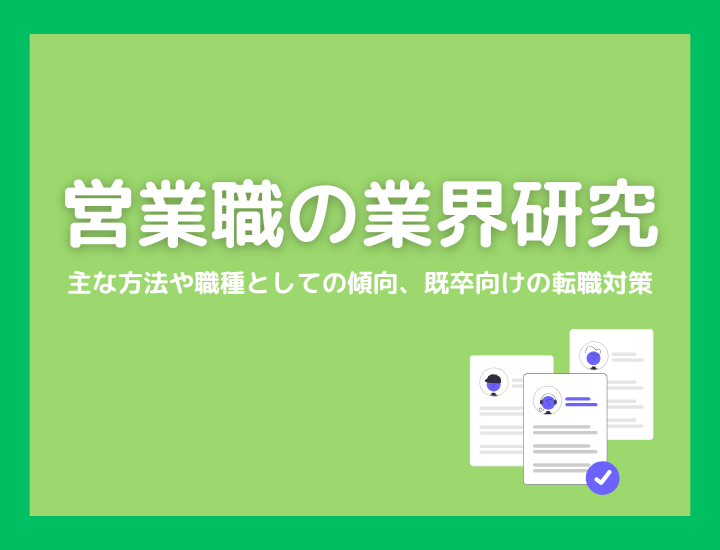
営業職の業界研究|主な方法や職種としての傾向、既卒向けの転職対策
はじめに
営業職への転職を考える中で「コンサルと営業の違いって何だろう?」「営業職の種類や業界の違いについて詳しく知りたい」といった疑問を感じることもあるでしょう。
既卒での転職を考える際、業界研究は重要なステップとなります。
しかし、営業職は業界や職種によって求められるスキルや働き方が大きく異なるため、漠然とした理解では適切な判断が難しいでしょう。
この記事では、営業職の業界研究に必要な基礎知識から、具体的な研究方法、業界別の特徴まで詳しく解説します。
既卒者の方が押さえておくべきポイントも含めて、転職活動に役立つ情報を掲載しているので、ぜひ最後までご覧ください。
【営業職の業界研究】そもそも「業界研究」とは
業界研究を正しく理解しないと、効果的な分析はできません。
業界研究の目的は、さまざまな業界の情報を集め、それぞれの特徴や違いを理解することです。
漠然とした認識ではなく「〇〇業界には△△の特徴がある」と自分の言葉で説明できるレベルが理想です。
多くの業界を調査することで、自分の営業スタイルに合った手法や興味のある分野を発見できる可能性があります。
最初は幅広く調べ、そこから特に興味を引かれた業界について深掘りすることで、質の高い業界研究につながります。
さらに、業界の動向や将来性、競合状況も知っておくと、営業職としての視野が広がります。
次章では、業界研究を効率的に進めるための具体的な手順やポイントについて詳しく解説します。
【営業職の業界研究】6つの方法
実際に業界研究を進めるには以下6つの方法を実践するのがおすすめです。
- 業界最大手の企業HPを見る
- 転職サイトなどの業界特集やコラムを読む
- 新聞やニュースサイトをなどからトレンドを追う
- 業界研究に特化した本を読んでみる
- セミナーに参加する
- OB・OG訪問を行う
それぞれの方法について詳しく解説していくので、実際に営業職の業界研究を進めるうえでの参考にしてください。
業界最大手の企業HPを見る
業界研究の出発点として、最大手企業のHPを確認するのは効果的です。
まず、業界全体のシェア率や市場規模をインターネットや「会社四季報」で調べ、主要企業を把握しましょう。
最大手の企業HPには、事業内容・企業理念・強み・ビジョンなどが掲載されており、業界のトレンドや方向性を読み取れます。
シェア2位・3位の企業HPも確認し、どのような違いがあるかを比較することで、業界内での位置づけや特色が明確になります。
また、異業種トップ企業との比較も有効です。
例えば、興味のある業界と自動車業界トップのTOYOTAを比べることで、業界リーダーの共通点や特異性が見えてきます。
複数の業界を調べると、営業活動に取り入れるべきポイントも見つかるでしょう。
転職サイトなどの業界特集やコラムを読む
転職サイトは業界研究に役立つ情報が豊富です。
求人情報に加え、業界特集や企業コラム、業界分析記事が掲載されていることが多く、短時間で業界の現状を把握できます。
特に「業界地図」では、業界内の企業の関連性や勢力図を視覚的に理解することが可能です。
ビジネス環境が激変する今、最新情報を押さえることは重要です。
転職サイトでは業界のトレンドや動向をリアルタイムで把握できるため、日々のチェックがおすすめです。
また、サイトによっては業界選びのヒントやキャリアの方向性を考えるコラムもあります。
求人を見るだけでなく、コラムや特集に目を通せば、業界への理解が深まり、興味のある分野を見つけやすくなります。
新聞やニュースサイトなどからトレンドを追う
新聞やニュースサイトは、業界研究のための最新情報を提供してくれる重要なリソースです。
特に日経電子版などの経済メディアは、ビジネス関連のニュースが網羅されているため、毎日目を通すことで業界トレンドを素早くキャッチできます。
興味のある業界が定まったら、その業界専門の月刊誌や週刊誌も購読すると良いでしょう。
専門誌は業界の詳細な分析や未来予測を扱うため、知識の幅が広がります。
また、スマホを活用すれば、通勤時間や隙間時間を有効に使い、手軽に情報収集ができます。
気になる記事はブックマークやメモで整理し、後から読み返せるようにしておきましょう。
効率よく情報を取り入れる習慣をつけることで、業界研究の質が向上します。
業界研究に特化した本を読んでみる
書店には業界研究に特化した書籍が数多く並んでいます。
「会社四季報」は特に有名で、業界全体の構造や主要企業、業界の将来展望まで網羅されています。
業界ごとの詳細な情報や企業の強み・弱みを把握できるため、業界全体を俯瞰するのに最適です。
興味のある業界だけでなく、幅広い分野の本を読むことで、新たな視点や意外な発見があるかもしれません。
情報量が多い場合は、気になる部分から読み進めると効率的です。
業界のトレンドや未来予測が掲載されたコラムも参考になります。
通読することで、興味を持てる業界が見つかる可能性が高まり、営業活動に活かせる知識の幅も広がるでしょう。
セミナーに参加する
業界研究セミナーは、大学・自治体・業界団体などが主催しており、オンライン形式も増えています。
セミナーでは業界の最新情報や実際の働き方について、専門家や業界関係者から直接学ぶことが可能です。
特に自治体主催のセミナーでは、地元企業が参加することが多く、地域密着型の業界事情も把握できるでしょう。
オンラインセミナーなら、場所や時間の制約を気にせず参加できます。
業界についての理解を深めるためには、疑問点を整理し、質問する姿勢が重要です。
セミナーで得た知識やネットワークは、今後の業界研究やキャリア選択に大いに役立ちます。
興味のある業界があれば積極的に参加してみましょう。
OB・OG訪問を行う
OB・OG訪問は、興味のある業界や企業について生の情報を得る絶好の機会です。
実際に働いている先輩から、業界のリアルな状況や職場の雰囲気、業務内容を聞くことが可能です。
ネットや本では分からない具体的な話や経験談は、業界への理解を深める大きな手助けになります。
訪問する際は、アポイントを取り、事前に質問内容を準備しておくことが大切です。
礼儀正しく、社会人としてのマナーを守りましょう。
訪問後にはお礼の連絡を忘れずにすることも重要です。
リアルな現場の声を知ることで、業界への適性や自分が働くイメージが明確になり、就職活動において大きな武器となります。
【営業職の業界研究】業務内容
営業職と一口に言っても、業務内容は非常に幅広くなっています。
営業職の主な業務内容は、以下のとおりです。
【オーソドックスな赤いボックス】
- 個人営業
- 法人営業
- 新規開拓営業
- ルート営業
- インサイドセールス
- 有形商材
- 無形商材
ここでは、営業職の業務内容についてそれぞれ解説していきます。
個人営業
個人営業は、一般消費者など個人を対象とする営業です。
代表例として、生命保険の営業が挙げられます。
見込み顧客に商品を提案し、購入の意思決定を促すのが特徴です。
1対1の対話が基本となるため、顧客のライフスタイルに合わせた柔軟な対応が求められます。
例えば、就業時間後や土日といった顧客の都合に合わせた商談が必要です。
業務の性質上、シフト制を採用する企業も多く、不規則な働き方になることもあります。
個人営業では比較的小規模な商品を扱うため、成約までの時間は短めです。
顧客との距離が近いため、営業担当者自身の人間性や信頼関係の構築が重要視されます。
顧客の要望に寄り添い、細やかな対応が求められる職種です。
法人営業
法人営業は、企業を相手に営業活動を行う業務です。
B to B(Business to Business)とも呼ばれ、取引額が大きく、長期にわたる交渉が一般的です。
例えば、億単位の契約が発生することもあり、成約までに1年以上かかるケースもあります。
取引相手は担当者ですが、最終的な決裁権は管理職や経営層が持つことが多く、複数人を対象に提案するスキルが必要です。
法人営業は、個人営業よりも課題の分析力や提案力が求められます。
業務は平日が中心で、カレンダー通りの休日が多いものの、繁忙期には仕事が集中することがあります。
企業のニーズを把握し、最適な解決策を提案するため、業界知識や高いコミュニケーション力が欠かせません。
新規開拓営業
新規開拓営業は、取引実績のない企業と新たな契約を結ぶ営業活動です。
事業や売上を拡大するためには欠かせない手法です。
ゼロから関係を築く必要があるため、コミュニケーションスキルや忍耐力が問われます。
新規開拓では、見込み顧客リストを元に営業活動を行いますが、契約に至る確率は低く、100件アプローチして1件成約すれば良い方です。
主な手法には、電話でアポイントを取る「テレアポ」や、直接訪問する「飛び込み営業」などがあります。
多くの断りを受けるため、精神的なタフさも必要です。
新規開拓営業は企業規模に関係なく実施されており、多くの営業担当者が経験する業務です。
成功体験が得られれば、大きな自信につながります。
ルート営業
ルート営業は、既存顧客との関係を維持・強化しながら、新たな提案やフォローを行う営業です。
定期的な訪問で信頼関係を築き、トラブルがあれば迅速に対応することが求められます。
現在導入している商品やサービスの改善提案や、新製品の紹介を通じて、取引の継続や拡大を図ります。
既存顧客との取引が長期にわたることが多いため、関係維持を怠ると、競合他社に乗り換えられるリスクもあるでしょう。
顧客との関係性を保ちつつ、常に有益な情報を提供することが重要です。
顧客との良好な関係を築ければ、安定した成果が期待できます。
ルート営業は信頼の積み重ねが大切で、丁寧なコミュニケーションと迅速な対応力が求められます。
有形商材
有形商材は、形がある商品のことを指します。
例えば、家電メーカーの営業が新しい洗濯機や冷蔵庫を販売する場合、製品を持参し、機能や特徴を直接説明できます。
有形商材は目に見えるため、顧客も製品のイメージが湧きやすく、具体的な質問が出やすいのが特徴です。
そのため、製品に関する深い知識や、柔軟な対応力が求められます。
顧客からの質問に的確に答えられないと、製品や担当者への信頼が失われ、商談が失敗することもあります。
有形商材は、実際に製品を触ったり、デモンストレーションを行ったりすることで、製品の魅力を伝えることが可能です。
わかりやすい説明と自信を持ったプレゼンテーションが成功のポイントです。
無形商材
無形商材は、形のない商品やサービスのことです。
例えば、IT業界で提供されるクラウドサービスやセキュリティソフト、人材紹介サービス、広告枠の販売などが該当します。
無形商材は実物が存在しないため、顧客にサービス内容をイメージさせるスキルが求められます。
提案時には、具体的な資料や事例を用いて、顧客に価値やメリットを伝えることが重要です。
知識レベルが顧客ごとに異なるため、相手に合わせたわかりやすい説明が欠かせません。
顧客の課題を理解し、どのように解決できるかを明確に伝えることが必要です。
信頼関係の構築が難しい反面、一度導入されれば継続的な取引が期待できるため、高い提案力と説得力が求められます。
【営業職の業界研究】業界一覧
ここでは、以下の業界ごとに営業職の特徴について解説します。
- メーカー系
- 人材系
- 広告・メディア系
- インフラ系
- IT系
- 保険
- 銀行・金融系
- 医療系
- 不動産系
- 商社
ここで紹介する業界を、自身の進むキャリアを決めるうえでの参考にしてください。
メーカー系
日本のメーカー業界には、自動車・機械・食品・素材などさまざまな分野があります。
営業職は主に法人営業が多く、例えば自動車部品メーカーの営業は、自動車メーカーに製品を提案・販売します。
メーカーと顧客の関係が長期的に築かれているため、ルート営業が中心となる場合が多いでしょう。
営業には商品に関する深い知識が求められ、製品の特徴やメリットを的確に伝えるスキルが重要です。
また、自社製品の強みを理解し、競合製品との差別化ポイントを明確に示す必要があります。
技術的な説明や製品デモンストレーションが必要な場面もあるため、技術者と連携しながら提案を行うケースもあるでしょう。
製品に形があるため、取引先もイメージしやすく、具体的な商談が可能です。
人材系
人材系の営業には、求人広告営業・人材紹介営業・人材派遣営業などがあります。
求人広告営業は、企業の求人情報を効果的に広告として掲載する提案を行う手法です。
どの広告枠を使うか、どんな内容で掲載するかを企業と打ち合わせし、採用活動を支援します。
人材紹介営業は、企業が求める人材をヒアリングし、適切な候補者をマッチングさせる役割です。
一方、人材派遣営業は、企業に対して派遣スタッフを提案し、派遣後のフォローも担当します。
人材系の営業は、幅広い業界の知識が必要で、企業と求職者双方のニーズを理解し、信頼関係を築くことが求められます。
採用トレンドや労働市場の動向に敏感であることも重要です。
柔軟な対応力と、高いコミュニケーション能力も求められるでしょう。
広告・メディア系
広告・メディア系の営業では、広告代理店やメディア企業に所属し、法人向けに提案を行います。
扱う商材は無形の広告枠やマーケティングサービスが多く、クライアントの課題に応じた広告戦略を提案します。
例えば、企業の認知度向上や売上拡大を目的とした広告キャンペーンの企画・実施です。
近年はデジタル広告やSNSマーケティングの需要が増加しており、最新のトレンドやテクノロジーを活用するスキルが求められます。
クライアントの要望をもとに、オーダーメイドで広告プランを作成し、クリエイティブな提案を行うことが特徴です。
提案力や企画力に加え、効果を分析する力も必要です。
柔軟な発想と迅速な対応が、広告・メディア営業に欠かせない要素です。
インフラ系
インフラ系営業は、電気・ガス・水道など、生活に欠かせないサービスを提供する仕事です。
商材は無形であることが多く、個人と法人の両方を対象に営業活動を行います。
インフラ業界は競合が少なく、国や地方自治体のサポートを背景に、業績が安定している企業が多いでしょう。
電力自由化の影響で競争が激しくなっている分野もありますが、信頼性や安定感が重要視されるため、比較的落ち着いた営業活動が可能です。
生活に直結するサービスのため、需要がなくなることはほとんどありません。
労働条件が良い企業も多く、営業ノルマも他業界に比べて緩やかな傾向にあります。
顧客との長期的な信頼関係を築き、安定したサービス提供を行うことが求められます。
IT系
IT系の営業は、ハードウェアのような有形商材から、ソフトウェアやクラウドサービスなどの無形商材まで幅広い商品を扱います。
主な顧客は法人で、企業の業務効率化や課題解決をITで支援する提案を行います。
例えば、勤怠管理システムの導入提案や、セキュリティソフトの販売などです。
提案時には、課題解決の効果を数値化し、導入メリットを明確に示すことが求められます。
導入後のフォローやトラブル対応も重要な業務で、迅速かつ的確なサポートが必要です。
業界の変化が激しいため、最新技術やトレンドに関する知識を常にアップデートしなければなりません。
時には休日対応も発生するため、柔軟な働き方が求められます。
保険
保険営業は、個人と法人の両方を対象に、生命保険や損害保険などの商品を提案する仕事です。
契約件数に応じたインセンティブが設定されており、高い成果を出せば高収入が期待できます。
しかし、目標達成が難しい場合、精神的・肉体的にハードな業務になることもあります。
営業活動では、顧客一人ひとりに寄り添い、ニーズを正確に把握することが重要です。
保険商品は複雑なため、深い商品知識や分かりやすい説明スキルが求められます。
顧客のライフプランに合った提案を行い、信頼関係を築くことで、継続的な契約につながります。
人間性や誠実さがポイントであり、顧客との関係構築が非常に重要な営業です。
銀行・金融系
銀行・金融系の営業は、法人営業と個人営業に分かれます。
法人営業では、企業の業績を調査し、融資の提案や資金調達支援を行います。
事業継承や経営改善の提案をすることもあり、金融知識をわかりやすく伝えるスキルが必要です。
融資先が倒産すると銀行にも影響があるため、企業と二人三脚で経営支援を行うことが求められます。
中小企業診断士などの資格があれば、提案に説得力が増します。
個人営業は、株式や債券、投資信託などの金融商品を提案し、顧客のライフプランに合った商品を紹介するのが特徴です。
信頼関係を築くことで、大口の取引や長期的な契約につながることもあります。
金融知識や提案力、信頼構築が求められる職種です。
医療系
医療系の営業は、医薬品や医療機器を病院やクリニックに提案・販売するMR(医薬情報担当者)が代表的です。
営業の相手は医師や薬剤師など専門職のため、高度な医療知識が求められます。
薬の効能や副作用、使用法について正確に説明し、医師からの質問にも即座に答えられる知識が必要です。
さらに、医療業界の最新トレンドや新薬情報にも精通していることが求められます。
専門的な知識が必要な分、高い営業スキルも要求されます。
日々情報をアップデートし、医師との信頼関係を築くことで、医薬品や医療機器の導入が進むでしょう。
業務の専門性が高いため、給与水準は他業界よりも高めです。
医療業界への貢献度が高い、やりがいのある営業職です。
不動産系
不動産系の営業は、自社が保有する土地や建物、または委託された物件の売買を仲介するのが主な業務です。
個人向けの住宅販売や賃貸仲介、法人向けのオフィスビルや商業施設の売買仲介があります。
取引の規模が大きいため、インセンティブが高額になることも特徴です。
しかし、目標達成には激務が伴うことが多く、ハードな環境で働くことになります。
不動産取引では、物件に関する知識はもちろん、法律や税金、ローンに関する知識も必要です。
宅地建物取引士(宅建)の資格があれば、信頼性が増し、業務に有利になります。
顧客の要望に合った物件を提案し、契約までサポートするため、高い提案力や交渉力、信頼構築が求められる職種です。
商社
商社の営業は、商品やサービスを扱う企業同士を結びつける仲介役です。
需要のある商品を求める企業と、その商品を提供する企業をマッチングし、仲介手数料を得ます。
商材は食品・機械・エネルギー・化学製品など多岐にわたり、総合商社では幅広い分野を扱います。
一方、専門商社は特定の業界に特化しているため、深い専門知識が必要です。
新たな販路の開拓やビジネスマッチングが求められ、柔軟な対応力や交渉力が不可欠です。
商社はグローバル展開している場合が多く、海外取引や駐在の機会もあります。
語学力や異文化理解力があると有利です。
取引先との信頼関係を築き、ビジネスチャンスを広げることが商社営業の使命です。
【営業職の業界研究】特徴別の傾向
営業職の業界研究を進めるうえでは、以下の視点から理解度を深めることも重要です。
- 楽な業界
- きつい業界
- 収入が高い業界
- 将来性のある業界
ここで紹介する内容も、営業職の業界研究にお役立てください。
楽な業界
営業職はノルマや飛び込み営業のイメージが強く、大変と思われがちですが、業界によって負担が軽い仕事もあります。
ワークライフバランスが整い、残業が少なく、給与が安定している業界は「楽な営業」と言えるでしょう。
例えば、競合他社が少なく、独占的にシェアを持つインフラ系や公共事業関連の営業は比較的穏やかです。
顧客が固定されているルート営業も、定期的な訪問やフォローが中心となるため、新規開拓のストレスが少なく、安定しています。
また、メーカー系の法人営業では、長年の取引関係がある場合が多く、信頼関係をベースに業務が進みます。
これらの業界では、過度なプレッシャーが少ないため、働きやすい環境が整っていると言えるでしょう。
きつい業界
営業職の中でも「きつい」とされる業界は、新規開拓が中心であることが多いでしょう。
具体的には、飛び込み営業やテレアポが主な手法となる保険・不動産・人材系の業界が挙げられます。
断られることが日常茶飯事であり、精神的にも体力的にもタフさが求められます。
また、高い目標設定や厳しいノルマが課されることも多く、未達成の場合はインセンティブが得られない厳しい環境です。
しかし、その分達成時の報酬ややりがいが大きく、高収入や昇進のチャンスも豊富です。
成果を出すことで自己成長が感じられるため、挑戦意欲のある人には向いているでしょう。
努力が報われやすい業界とも言えますが、ストレス耐性や忍耐力が必須です。
収入が高い業界
営業職の魅力の一つは、自分の成果次第で高収入が得られる点です。
特に収入が高い業界は、単価の高い商材を扱う場合が多く、不動産・保険・金融・IT系が代表例です。
例えば、不動産の売買仲介や保険商品では、1件の成約で大きなインセンティブが発生することがあります。
金融業界では、法人向けに資産運用や融資の提案を行い、高額な取引が可能です。
また、IT業界のシステム導入やソフトウェア販売では、企業規模によっては数千万円、数億円規模の契約もあります。
これらの業界では、自分の努力や営業スキル次第で収入が大幅に変わるため、成果を出せば大きな報酬が期待できます。
実力主義の環境を好む人には特に魅力的です。
将来性のある業界
営業職として長く働くには、業界の将来性も重要なポイントです。
近年、AIやテクノロジーの進化により、営業職の一部は自動化される可能性があります。
定型業務や単純な商材の販売は、AIに置き換えられるかもしれません。
しかし、専門知識や高度な提案力が求められる営業は、今後も需要が続くでしょう。
特に、IT・医療・インフラ・環境関連の業界は成長が見込まれます。
例えば、IT系はクラウドやセキュリティ分野の需要が拡大し、医療業界では高齢化に伴う医薬品や医療機器の需要が増加しています。
AIの発展により、新たな商材やサービスが生まれるため、テクノロジーと連携した営業が重要になるでしょう。
【営業職の業界研究】既卒での転職について
営業職は、多くの企業で募集をしており、未経験者でも歓迎される求人が多くあります。
そのため、既卒で転職を考えている方にとって、選択肢の一つとして魅力的なのではないでしょうか。
これから既卒で営業職に転職をしたいと考えている方に向けて「既卒」とは何か、営業職に向いている理由、転職を成功させるための方法を紹介します。
そもそも「既卒」とは
「既卒」とは、学校を卒業した後に一度も就職経験のない人のことを指します。
一般的には、卒業後1〜3年以内の人が既卒とされています。
新卒と既卒の違いは、学校を卒業しているかどうかという点です。
また、第二新卒とは異なり、既卒は社会人経験がありません。
フリーターはアルバイトで生計を立てている人を指しますが、既卒の人がアルバイトをしている場合、既卒でありフリーターでもあるということになります。
営業職への転職に既卒が重宝される理由
既卒者が転職活動をする際、新卒や中途採用枠のどちらにも応募できますが、どちらにも強力なライバルが存在します。
新卒採用枠では年齢が若い学生、中途採用枠では社会人経験のある第二新卒層と競合することになるでしょう。
しかし、企業の採用活動において、近年では新卒採用だけでは人員を確保できない企業が増えていることから、既卒者を採用する企業が増えています。
また、組織の年齢構成を適正に保つため、企業は定期的に若手を採用する必要があり、既卒者は若手人材として重宝されています。
特に営業職は、企業の業績に直結する重要な職種であり、常に人材が求められているのです。
また、営業職は経験やスキルがなくても、努力次第で結果を出すことができ、人材育成の観点からも既卒者は魅力的な存在です。
既卒で営業職の転職を成功させるには
既卒で営業職に転職を成功させるには、事前の準備と積極的な行動が重要です。
転職活動を開始する前に自己分析を行い、自分の強みや弱みを理解しましょう。
また、営業職にはどのような種類があり、どのようなスキルが求められるのかを理解しておくことも大切です。
求人サイトや転職エージェントなどを活用し、自分に合った企業を探しましょう。
応募書類の作成や面接対策も入念に行いましょう。
特に面接では、既卒になった理由や空白期間について聞かれることが予想されます。
質問に対して、前向きな回答を準備しておくことが大切です。
まとめ
今回は営業職の業界研究について、基本的な方法から業界別の特徴、既卒での転職のポイントまで詳しく解説してきました。
営業職は業界によって働き方や求められるスキルが大きく異なりますが、既卒者の経験や人間力は多くの企業で重宝されます。
業界研究を通じて自身の適性や希望する働き方と照らし合わせることで、より的確な転職先の選択が可能となるでしょう。
これから転職活動を始める既卒者は、まずは今回の記事で紹介した業界研究の方法を実践してみてください。
具体的な企業選びや面接対策にも、本記事から得た知識が必ず活きてくるはずです。
話題沸騰中の人気診断ツール
今の仕事、本当にあなたに合っていますか?
転職活動で最も避けたい「ミスマッチ」。 失敗しないキャリア選びの第一歩は、自分自身の特性を客観的に把握することから始まります。「64タイプ性格診断」X 「適職診断」。後悔のない転職のために。まずは自分の適性を確かめてみませんか?

SHARE この記事を友達におしえる!



